目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
監督:Yorgos Lanthimos, プロデュース:Ed Guiney, プロデュース:Andrew Lowe, プロデュース:Yorgos Lanthimos, プロデュース:Kasia Malipan, Writer:Yorgos Lanthimos, Writer:Efthimis Filippou, 出演:Emma Stone, 出演:Jesse Plemons, 出演:Willem Dafoe, 出演:Margaret Qualley, 出演:Hong Chau, 出演:Mamoudou Athie, 出演:Emma Stone, 出演:Emma Stone, 出演:Jesse Plemons, 出演:Jesse Plemons, 出演:Willem Dafoe, 出演:Willem Dafoe, 出演:Margaret Qualley, 出演:Margaret Qualley, 出演:Margaret Qualley, 出演:Hong Chau, 出演:Hong Chau, 出演:Joe Alwyn, 出演:Joe Alwyn, 出演:Joe Alwyn, 出演:Mamoudou Athie, 出演:Mamoudou Athie, 出演:Hunter Schafer, 出演:Yorgos Stefanakos, 出演:Fadeke Adeola, 出演:Tessa Bourgeois, 出演:Kencil Mejia, 出演:Thaddeus Burbank, 出演:Suzanna Stone, 出演:Jerskin Fendrix, 出演:Nikki Chamberlin, 出演:Christian M. Letellier, 出演:Lawrence Johnson, 出演:Lindsey G. Smith, 出演:Kevin Guillot
¥2,500 (2025/04/02 23:09時点 | Amazon調べ)
ポチップ
VIDEO
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
「同じ役者を使った3つの異なる物語」はどれも、「ルールの分からないスポーツを観させられている」みたいな意味不明さを感じさせる どの話も「飛び抜けた奇妙さ」を有しているにも拘らず、全体のトーンが似た感じだったことに驚かされた 原題の『KINDS OF KINDNESS』の直訳は「親切の種類」であり意味不明だが、邦題の『憐れみの3章』も無情報すぎて凄い ヨルゴス・ランティモス監督のファンというわけではなく、前作『哀れなるものたち』は苦手だったが、本作『憐れみの3章』はとにかく面白くてビックリした
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
まったく意味は分からないのにメチャクチャ面白かった映画『憐れみの3章』。私は映画『哀れなるものたち』は苦手だったが、本作には圧倒させられたし、とにかく凄く良かった
凄まじく意味不明だった のだが、もの凄く面白い作品 だった。実に不思議 である。結局のところ、「何が面白かったのか」は今もよく分からない 。ただ、すこぶる変な表現ではあるのだが、「映画を観てるなぁ」という感覚を強く抱かされる作品 だった。映画を観ているのだから当然と言えば当然なのだが、そういうことではなく、「これぞ映画って感じがする」みたいな感覚 とでも言えばいいだろうか。いや、やはり上手くは説明できない な。いずれにせよ、印象的な作品だったことは確か である。
あわせて読みたい
【衝撃】「仕事の意味」とは?天才・野崎まどが『タイタン』で描く「仕事をしなくていい世界」の危機
「仕事が存在しない世界」は果たして人間にとって楽園なのか?万能のAIが人間の仕事をすべて肩代わりしてくれる世界を野崎まどが描く『タイタン』。その壮大な世界観を通じて、現代を照射する「仕事に関する思索」が多数登場する、エンタメ作品としてもド級に面白い傑作SF小説
さて、一応先に書いておくと、私は同監督の前作『哀れなるものたち』は好きになれなかった 。面白いとはまったく感じられなかったのだ。そんなわけで私は、どうやら人気があるらしいヨルゴス・ランティモス監督のファンというわけではない 。そういうこととは関係なく、純粋に本作単体での評価 である。なので、私と同じように『哀れなるものたち』がダメだったという人も、本作『憐れみの3章』はチャレンジしてみてもいいかもしれない 。
実に奇妙な構成の、実に奇妙な物語なのだが、とにかく面白かった
それではまず、本作の最も特徴的な点 から触れていくことにしよう。
本作はタイトルで示唆されている通り、「3つの異なる物語」で構成されている 。人物設定も世界観もすべて違う というわけだ。しかし、主要な登場人物を演じる役者は同じ である。変な喩えだが、「桃太郎・浦島太郎・金太郎を演じるのはすべて菅田将暉」みたいな感じ である。本作の3つの物語に関連があるのかは正直私にはよく分からなかったのだが、いずれにせよ、本作全体においては「1人が3役をこなしている」 というわけだ。本作はとにかく、まずはこの点が実に特異的 だと言えるだろう。少なくとも私は、同じような構成の映像作品に触れたことはない と思う。
あわせて読みたい
【記憶】映画『退屈な日々にさようならを』は「今泉力哉っぽさ」とは異なる魅力に溢れた初期作品だ(主…
今泉力哉作品のオールナイト上映に初めて参加し、『退屈な日々にさようならを』『街の上で』『サッドティー』を観ました。本作『退屈な日々にさようならを』は、時系列が複雑に入れ替わった群像劇で、私が思う「今泉力哉っぽさ」は薄い作品でしたが、構成も展開も会話も絶妙で、さすが今泉力哉という感じです
さて、3つの物語には共通している点が1つある 。それは「どの物語も奇妙である 」ということだ。まあ、共通点と言えるようなものではないかもしれないが、もう少しこの辺りの話を深めたい と思う。
「奇妙」にも色んなタイプがある だろうが、本作で描かれる物語の奇妙さは、「ルールの分からないスポーツを観させられている」みたいな感じに近い かもしれない。どの物語も、「その世界を貫く基本原則が掴めない」みたいな印象が強い のだ。
例えば「カバディ」というスポーツでは「攻撃中は『カバディ』と言い続けなければならない」というルールがある 。今の私はそれを知っているので、仮にカバディの試合を観に行っても驚かないはずだが、ルールも何も知らない人が観たら「えっ? 何してるの?」となるだろう 。そして本作に対する印象も、そんな感じ なのである。「えっ? 何してるの?」みたいに感じる場面がとても多く 、さらに、「作中世界に存在するどんなルールからそれらが生み出されているのか」が分からなかった のである。
あわせて読みたい
【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…
映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった
そんな訳の分からなさを孕んでいて、しかもなんと164分もあるかなり長い映画 なのだが、これが実に面白かった 。最後までまったく飽きずに観ることができた のだ。とても不思議 である。普通に考えれば、「ルールの分からないスポーツ」を観させられることはかなり苦痛なはず なのだが、本作では全然そんな感覚にならなかった 。繰り返しになるが、私は別にヨルゴス・ランティモス監督のファンというわけでもない し、主演のエマ・ストーンが好きなわけでもない し、そもそも映画を観る際は常に「ストーリー」を追うタイプ だ。だから、ストーリーが好きになれないとなかなか「観て良かった!」とはならない のだが、本作は、その肝心のストーリーが意味不明なのにとても面白かった のである。本当に、こんな訳の分からない物語を「面白い」と感じさせる監督は凄い なと感じた。
というわけで、その「奇妙さ」を何となくでも理解してもらうために、まずは内容の紹介から始めよう と思う。
映画『憐れみの3章』の内容紹介
R.M.F.の死
車に乗ったロバートは、深夜の路上でしばし待機していた 。しなければならないことがあるからだ。目の前を走り抜ける予定の車に、全力でぶつかりにいかなければならない のである。彼はターゲットとなる車を確認すると、アクセルを踏み込んだ。車は確かに相手の車体にぶつかった 。しかしそれは、”依頼人”の望むような成果にはならなかった のである。怖気付いてしまい、アクセルを踏み切れなかったことが敗因だ 。
あわせて読みたい
【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…
映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う
翌日、ロバートはレイモンドに呼び出された 。すぐに前日の不手際を謝罪した のだが、レイモンドは改めて「同じことをやり遂げろ」と命ずる 。ロバートは逡巡しながらも、「他のことなら何でもやるが、これだけは出来ない」と言って断った 。10年間の付き合いの中で、初めての”反抗” である。しかしその返答を聞いたレイモンドは、「バーで2時間考え直してから、改めて結論を伝えに来なさい 」と言って去ってしまう。
ロバートはこれまで、レイモンドが指示した通りに生きてきた 。それは尋常ではないレベル であり、まさに「人生丸ごとレイモンドに預けていた」といった感じ である。住んでいる家 も、後に妻となるサラと交際をスタートさせたこと も、セックスはするが子どもは作らなかったこと さえも、すべてレイモンドの指示 によるものなのだ。ロバートは、レイモンドの言いなりになることであらゆるものを手にすることが出来、何不自由ない生活を送れていた のである。
そんな”恩人”であるレイモンドからの頼み ではあるが、やはりこればかりは出来ない 。ロバートは2時間考え、改めてレイモンドの依頼を断ろうと決めた 、のだが……。
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
R.M.F.は飛ぶ
警察官のダニエルは、落ち着かないまま仕事を続けていた 。というのも、海洋研究者である妻リズが、他の研究者と共に船に乗ったまま行方不明になってしまった からだ。同僚のニールとその妻も、ダニエルを心配してくれていた 。リズを含めた4人は、乱交を楽しむ仲 である。
そんなある日、妻が無事に発見されたとの知らせが届く 。彼女は実に幸運だった 。というのも、船に乗った5人の内3人は死亡、1人は片脚の切断を余儀なくされた からだ。そんな中リズは、酷く衰弱していたものの、外傷もなく救助された のである。まさに奇跡的な生還 だった。
しかし、妻の帰りを待ちわびていたダニエルは、彼女に対する違和感を日々募らせていく ことになる。失踪前は履けていたはずの靴が足に合わなかったり 、試す気持ちで「僕の一番好きな曲を掛けて」と車内で頼んだ時も、リズなら間違えるはずのない曲をセレクトした のだ。
あわせて読みたい
【生と死】不老不死をリアルに描く映画。「若い肉体のまま死なずに生き続けること」は本当に幸せか?:…
あなたは「不老不死」を望むだろうか?私には、「不老不死」が魅力的には感じられない。科学技術によって「不老不死」が実現するとしても、私はそこに足を踏み入れないだろう。「不老不死」が実現する世界をリアルに描く映画『Arc アーク』から、「生と死」を考える
リズに対する疑念が膨らみ続けたダニエルは考える 。妻の姿形をしたこの女は、一体誰なのだろう 、と。
R.M.F.はサンドイッチを食べる
アンドリューとエミリーの2人はある女性を探している のだが、肝心の情報がほとんどない 。分かっているのは、「双子で、一方は既に亡くなっている 」ぐらいである。そんな状態で人探しなど出来るはずもない が、しかしエミリーには「見れば分かる」という確信 があった。彼女には思い当たる節 がある。プールの底の排水口に髪が挟まった自分を助けてくれたシンクロナイズドスイミングの双子こそ探している女性に違いない 、と。とはいえそれは、夢で見た光景にすぎない のだが。
2人はいつも水を持ち歩いており、他の水は口にしない 。彼らが持っているのは、”教祖”的な存在である夫妻の涙が混ざった水 であり、彼らはその夫妻を中心とした数十人のメンバーと共同生活している 。エミリーには実は夫と娘がいる のだが、その夫妻のコミュニティで生活するために、自らの意思で失踪した のだった。
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
しかしエミリーは、夫と娘が住む自宅にこっそり戻っては、娘へのプレゼントをベッドに置く などしている。コミュニティは「穢れ」を大層嫌っており、「『涙入りの水』を飲まない人」とは距離を置かなければならないのが鉄則 だ。当然、エミリーの行動は許されるものではない 。しかし、彼女が何をしているのか何となく察しているアンドリューは、彼女の振る舞いを黙認している 。
そんなある日のこと。ダイナーで食事していた彼らは1人の女性から声を掛けられた 。そして彼女はなんと、「あなたたちが探しているのは、私の双子の姉よ」と口にした のである……。
映画『憐れみの3章』の感想
映画全体に対する感想
自分で書いていても意味の分からない内容紹介 なのだから、恐らく読んでも全然理解できなかったんじゃないかと思う 。「観たら分かる」なんてことも、たぶんない だろう。それぞれの物語は「分かりやすい結末」に辿り着いたりしないし、ホントによく分からないまま終わる 。しかしそれにも拘らず、どの物語にも惹きつける何かがあるし、最後まで観させられてしまう のだ。凄いものだなと思う。
あわせて読みたい
【解説】映画『スターフィッシュ』をネタバレ全開で考察。主人公が直面する”奇妙な世界”の正体は?
映画『スターフィッシュ』は、「親友の葬儀」とそれに続く「不法侵入」の後、唐突に「意味不明な世界観」に突入していき、その状態のまま物語が終わってしまう。解釈が非常に難しい物語だが、しかし私なりの仮説には辿り着いた。そこでこの記事では、ネタバレを一切気にせずに「私が捉えた物語」について解説していくことにする
さらに感心させられたのが、3つの物語がどれも「同じようなトーン」でまとまっていた ことである。つまり、「電車、パンダ、梅干し」ではなく「リンゴ、みかん、パイナップル」ぐらいのまとまりが感じられた というわけだ。「訳の分からない物語」を作ろうと思えばいくらでも作れるかもしれないが、無秩序に作ると「電車、パンダ、梅干し」ぐらい統一感が無くなってもおかしくない だろう。しかし本作では、それぞれ全然違う物語にも拘らず、全体のトーンだけはかなり共通していて、「よくもまあこんな似たテイストの『奇妙な物語』を3つも揃えたものだ」と感じさせられた のだ。本当に凄いものである。
さて、その「トーン」は色んな要素によって生み出されている と思うのだが、物語の大枠に絡んだ話で言えば、「『人知を超えた何か』に対する畏怖の気持ち」みたいな部分が共通している ように感じられた。まあこの印象に関しては、「一神教の国で作られた映画である」という先入観があることは認めざるを得ない が。
『R.M.F.の死』では「すべての選択肢を与える男」 、『R.M.F.は飛ぶ』では「リズに姿形を似せた謎の存在」 、そして『R.M.F.はサンドイッチを食べる』では「『水』を介して支配する教祖」が「人知を超えた何か」に相当する と言えるだろう。そしてそれらに対しての様々な感情、つまり「恐怖」「諦念」「信頼」「無力感」「畏敬」……みたいな心の動きがどの物語にも通底している ような気がしたのである。それが「同じようなトーン」でまとまっている1つの理由 ではないかと思う。
あわせて読みたい
【無謀】園子温が役者のワークショップと同時並行で撮影した映画『エッシャー通りの赤いポスト』の”狂気”
「園子温の最新作」としか知らずに観に行った映画『エッシャー通りの赤いポスト』は、「ワークショップ参加者」を「役者」に仕立て、ワークショップと同時並行で撮影されたという異次元の作品だった。なかなか経験できないだろう、「0が1になる瞬間」を味わえる“狂気”の映画
3つの物語はどれも狂気じみた雰囲気のまま終わる のだが、中でも、2番目の『R.M.F.は飛ぶ』のラストが凄かった 。後半に入ってから「まさかな」と思いながら物語を追っていた のだが、そのまさかが実際に起こった のだ。普通なら「予想した通り」みたいな受け取り方になるのかもしれないが、本作の場合は、その「まさか」があまりにもあり得なかったので、「さすがにそんな風にはならないだろう」と思っていた のである。だからこそ驚きが強かった 。「凄いことするな 」とも感じさせられたというわけだ。
このラストの展開は、普通の物語ならまず成立しない だろうと思う。「ンな無茶な」と思われておしまい である。しかし本作の場合は、ラストに至るまでの展開で様々な”不穏さ”を撒き散らされているので、むしろ「これ以外のラストはあり得ない」みたいな感覚にさえさせられる のだ(「まさかな」と思っていたことと矛盾するかもしれないが、どちらも本心である)。この展開、脚本を読んだ役者たちがどう感じたのかは気になるところ である。このラストシーンは、映像や音響のインパクトもすべて含めた上で成り立っている 感じがするので、文字だけで提示された場合には「さすがにそれは無理があるでしょ」みたいになりそうな気がする のだ。まあ恐らく、「監督を信頼している」みたいな感覚が役者側にあったからこそ成立している のだとは思うが、それにしても凄い展開だった なと思う。
その他感想
さて、「監督を信頼している」と言えば、邦題も凄いなと感じた 。「憐れみの3章」というタイトルは、「物語が3つある」という情報以外ほぼ何も伝えていない からである。しかも原題は『KINDS OF KINDNESS』 だそうで、邦題の「3章」に該当するようなフレーズは存在しない のだ。普通ならこんな邦題にGOサインが出るとは思えない のだが、それでもOKが出たのはきっと、「この監督・役者なら、タイトルの良し悪しなどもはや関係ない」みたいな共通理解があるからこそ だと思う。そうじゃなければ、こんな「無情報」の邦題などなかなか付けられない だろう。
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
ちなみに翻訳サイトによると、「KINDS OF KINDNESS」は「親切の種類」という意味になる そうだ。とはいえ、そんな原題の意味を知ったところで内容に対する理解が深まるわけでもない 。本作では別に「親切」に該当するような要素が描かれているようには思えない し、むしろ「親切」からは距離のあるものばかりが登場する ようにも思う。何なら、邦題の「憐れみ」の方が作品のテイストに合っている とさえ言えるだろう。いや、もっと言うなら、前作の『哀れなるものたち』こそ、本作のタイトルとして最も相応しいのではないか という気にさえなってくる。
さて、映画『哀れなるものたち』も本作同様エマ・ストーンが主演だった のだが、『哀れなるものたち』では「人造人間」みたいなキャラクターだったこともあり、彼女の表情にはあまり意識が向かなかった ように思う。そして本作で私は、エマ・ストーンを見て「良い顔するなぁ」と感じた 。もちろん「綺麗な顔」であることは確か なのだが、そういうことではなく、「良い顔するなぁ」という感じだった のだ。なんとなく伝わるだろうか?
というわけで、最後にどうでも良い話を1つ 。本作では、メインの登場人物としてホン・チャウというアジア人女優が登場する 。どこかで見たことがある気がするなぁと思ったら、以前観た映画『ザ・ホエール』に出ていた人 だった。で、これは決して人種差別などではないと自分では考えている のだが、本作の物語には「アジア人」はいらなかったんじゃないか と思う。私も同じアジア人なのでこういうことを書いてもギリギリセーフかなと思っているのだが、なんだかそんな感じがしてしまったのだ。もしかしたらそれは、「本作が3つの異なる物語で構成されている」という特殊さから来ているのかもしれない 。3つの内1つだけなら違和感を覚えることはなかった気もするが、3つすべてにアジア人が出てきたので、「それはちょっと違う気がするなぁ」となった ようにも思う。いずれにせよ、アジア人の登場は、本作においては少し「ノイズ」みたいに思えてしまった 。
あわせて読みたい
【映画】『キャスティング・ディレクター』の歴史を作り、ハリウッド映画俳優の運命を変えた女性の奮闘
映画『キャスティング・ディレクター』は、ハリウッドで伝説とされるマリオン・ドハティを描き出すドキュメンタリー。「神業」「芸術」とも評される配役を行ってきたにも拘わらず、長く評価されずにいた彼女の不遇の歴史や、再び「キャスティングの暗黒期」に入ってしまった現在のハリウッドなどを切り取っていく
ただ、これは以前何かで見知った記憶がある話 なのだが、ダイバーシティが重視されるようになった世の中においては、「役者の人種の多様性も踏まえないと賞レースにそもそもノミネートされない」みたいなことが起こっている そうだ。本作にそういう意識があったのかどうか分からないものの、そういう理由で”非白人”を意識的に登場させる映画も増えてきているんじゃないか と思う。そのような流れは正直あまり好きになれない のだが、制作側もきっと「そうせざるを得ない」みたいに感じているような気がする 。これもまた難しい問題 だなと思う。
監督:Yorgos Lanthimos, プロデュース:Ed Guiney, プロデュース:Andrew Lowe, プロデュース:Yorgos Lanthimos, プロデュース:Kasia Malipan, Writer:Yorgos Lanthimos, Writer:Efthimis Filippou, 出演:Emma Stone, 出演:Jesse Plemons, 出演:Willem Dafoe, 出演:Margaret Qualley, 出演:Hong Chau, 出演:Mamoudou Athie, 出演:Emma Stone, 出演:Emma Stone, 出演:Jesse Plemons, 出演:Jesse Plemons, 出演:Willem Dafoe, 出演:Willem Dafoe, 出演:Margaret Qualley, 出演:Margaret Qualley, 出演:Margaret Qualley, 出演:Hong Chau, 出演:Hong Chau, 出演:Joe Alwyn, 出演:Joe Alwyn, 出演:Joe Alwyn, 出演:Mamoudou Athie, 出演:Mamoudou Athie, 出演:Hunter Schafer, 出演:Yorgos Stefanakos, 出演:Fadeke Adeola, 出演:Tessa Bourgeois, 出演:Kencil Mejia, 出演:Thaddeus Burbank, 出演:Suzanna Stone, 出演:Jerskin Fendrix, 出演:Nikki Chamberlin, 出演:Christian M. Letellier, 出演:Lawrence Johnson, 出演:Lindsey G. Smith, 出演:Kevin Guillot
¥2,500 (2025/04/02 23:11時点 | Amazon調べ)
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
そんなわけで、本当に最後の最後までまったく意味が分からなかった のだが、最後までずっと面白かった 。正直、もう1回観てもいいとさえ思っているし、「良い映画を観たなぁ」という感覚が強く残っている ことも印象的だ。実に不思議 である。「面白さ」を言語化出来ないのは少し癪 ではあるが、オススメなので機会があれば観てみてほしい 。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『国宝』は圧巻だった!吉沢亮の女形のリアル、圧倒的な映像美、歌舞伎の芸道の狂気(…
映画『国宝』は、ちょっと圧倒的すぎる作品だった。原作・監督・役者すべての布陣が最強で、「そりゃ良い作品になるよね」という感じではあったが、そんな期待をあっさりと超えていくえげつない完成度は圧巻だ。あらゆる意味で「血」に翻弄される主人公・喜久雄の「狂気の生涯」を、常軌を逸したレベルで描き出す快作である
あわせて読みたい
【丁寧】筒井康隆『敵』を吉田大八が映画化!死を見定めた老紳士が囚われた狂気的日常を描く(主演:長…
映画『敵』(吉田大八監督)は、原作が筒井康隆だけのことはあり、物語はとにかく意味不明だった。しかしそれでも「面白い」と感じさせるのだから凄いものだと思う。前半では「イケオジのスローライフ」が丁寧に描かれ、そこから次第に、「元大学教授が狂気に飲み込まれていく様」が淡々と、しかし濃密に描かれていく
あわせて読みたい
【ネタバレ】フィンランド映画『ハッチング』が描くのは、抑え込んだ悪が「私の怪物」として生誕する狂気
映画『ハッチング―孵化―』は、「卵から孵った怪物を少女が育てる」という狂気的な物語なのだが、本作全体を『ジキルとハイド』的に捉えると筋の通った解釈をしやすくなる。自分の内側に溜まり続ける「悪」を表に出せずにいる主人公ティンヤの葛藤を起点に始まる物語であり、理想を追い求める母親の執念が打ち砕かれる物語でもある
あわせて読みたい
【洗脳】激しく挑発的だった映画『クラブゼロ』が描く、「食べないこと」を「健康」と言い張る狂気(主…
映画『クラブゼロ』は、「健康的な食事」として「まったく食べないこと」を推奨する女性教師と、彼女に賛同し実践する高校生を描き出す物語。実に狂気的な設定ではあるが、しかし同時に、本作で描かれているのは「日々SNS上で繰り広げられていること」でもある。そんな「現代性」をSNSを登場させずに描き出す、挑発的な作品だ
あわせて読みたい
【狂気】瀧内公美の一人語りのみで展開される映画『奇麗な、悪』の衝撃。凄まじいものを見た(監督:奥…
映画『奇麗な、悪』は、女優・瀧内公美が78分間一人語りするだけの作品で、彼女が放つ雰囲気・存在感に圧倒させられてしまった。誰もいない廃院で、目の前に医師がいるかのように話し続ける主人公の「狂気」が凄まじい。スクリーンの向こう側の出来事なのに、客席で何故か息苦しさを感じたほどの圧巻の演技に打ちのめされた
あわせて読みたい
【恐怖】「1970年代の生放送の怪しげなテレビ番組」を見事に再現したフェイクドキュメンタリー:映画『…
映画『悪魔と夜ふかし』は、「1970年代に放送されていた生放送番組のマスターテープが発見された」というテイで、ハロウィンの夜の放送回をそのまま流すという設定のモキュメンタリーである。番組の細部までリアルに作り込まれており、それ故に、「悪魔の召喚」という非現実的な状況もするっと受け入れられる感じがした
あわせて読みたい
【異次元】リアリティ皆無の怪作映画『Cloud クラウド』は、役者の演技でギリ成立している(監督:黒沢…
映画『Cloud クラウド』(黒沢清監督)は、リアリティなどまったく感じさせないかなり異様な作品だった。登場人物のほとんどが「人間っぽくない」のだが、錚々たる役者陣による見事な演技によって、「リアリティ」も「っぽさ」も欠いたまま作品としては成立している。「共感は一切出来ない」と理解した上で観るなら面白いと思う
あわせて読みたい
【天才】映画『箱男』はやはり、安部公房がSNSの無い時代に見通した「匿名性」への洞察が驚異的(監督:…
映画『箱男』は、安部公房本人から映画化権を託されるも一度は企画が頓挫、しかしその後27年の月日を経て完成させた石井岳龍の執念が宿る作品だ。SNSなど無かった時代に生み出された「匿名性」に関する洞察と、「本物とは何か?」という深淵な問いが折り重なるようにして進む物語で、その魅惑的な雰囲気に観客は幻惑される
あわせて読みたい
【狂気】「こんな作品を作ろうと考えて実際世に出した川上さわ、ヤベェな」って感じた映画『地獄のSE』…
私が観た時はポレポレ東中野のみで公開されていた映画『地獄のSE』は、最初から最後までイカれ狂ったゲロヤバな作品だった。久しぶりに出会ったな、こんな狂気的な映画。面白かったけど!「こんなヤバい作品を、多くの人の協力を得て作り公開した監督」に対する興味を強く抱かされた作品で、とにかく「凄いモノを観たな」という感じだった
あわせて読みたい
【変態】映画『コンセント/同意』が描く50歳と14歳少女の”恋”は「キモっ!」では終われない
映画『コンセント/同意』は、50歳の著名小説家に恋をした14歳の少女が大人になってから出版した「告発本」をベースに作られた作品だ。もちろん実話を元にしており、その焦点はタイトルの通り「同意」にある。自ら望んで36歳年上の男性との恋に踏み出した少女は、いかにして「同意させられた」という状況に追い込まれたのか?
あわせて読みたい
【あらすじ】老夫婦の”穏やかな日常”から核戦争の恐怖を描くアニメ映画『風が吹くとき』の衝撃
一軒家の中だけで展開される老夫婦の日常から「核戦争」の危機をリアルに描き出す映画『風が吹くとき』は、日本では1987年に公開された作品なのだが、今まさに観るべき作品ではないかと。世界的に「核戦争」の可能性が高まっているし、また「いつ起こるか分からない巨大地震」と読み替えても成立する作品で、実に興味深かった
あわせて読みたい
【感想】B級サメ映画の傑作『温泉シャーク』は、『シン・ゴジラ』的壮大さをバカバカしく描き出す
「温泉に入っているとサメに襲われる」という荒唐無稽すぎる設定のサメ映画『温泉シャーク』は、確かにふざけ倒した作品ではあるものの、観てみる価値のある映画だと思います。サメの生態を上手く利用した設定や、「伏線回収」と表現していいだろう展開などが巧みで、細かなことを気にしなければ、そのバカバカしさを楽しめるはずです
あわせて読みたい
【解説】映画『スターフィッシュ』をネタバレ全開で考察。主人公が直面する”奇妙な世界”の正体は?
映画『スターフィッシュ』は、「親友の葬儀」とそれに続く「不法侵入」の後、唐突に「意味不明な世界観」に突入していき、その状態のまま物語が終わってしまう。解釈が非常に難しい物語だが、しかし私なりの仮説には辿り着いた。そこでこの記事では、ネタバレを一切気にせずに「私が捉えた物語」について解説していくことにする
あわせて読みたい
【狂気】押見修造デザインの「ちーちゃん」(映画『毒娘』)は「『正しさ』によって歪む何か」の象徴だ…
映画『毒娘』は、押見修造デザインの「ちーちゃん」の存在感が圧倒的であることは確かなのだが、しかし観ていくと、「決して『ちーちゃん』がメインなわけではない」ということに気づくだろう。本作は、全体として「『正しさ』によって歪む何か」を描き出そうとする物語であり、私たちが生きる社会のリアルを抉り出す作品である
あわせて読みたい
【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…
映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった
あわせて読みたい
【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ
映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています
あわせて読みたい
【衝撃】広末涼子映画デビュー作『20世紀ノスタルジア』は、「広末が異常にカワイイ」だけじゃない作品
広末涼子の映画デビュー・初主演作として知られる『20世紀ノスタルジア』は、まず何よりも「広末涼子の可愛さ」に圧倒される作品だ。しかし、決してそれだけではない。初めは「奇妙な設定」ぐらいにしか思っていなかった「宇宙人に憑依されている」という要素が、物語全体を実に上手くまとめている映画だと感じた
あわせて読みたい
【天才】映画『ツィゴイネルワイゼン』(鈴木清順)は意味不明だが、大楠道代のトークが面白かった
鈴木清順監督作『ツィゴイネルワイゼン』は、最初から最後まで何を描いているのかさっぱり分からない映画だった。しかし、出演者の1人で、上映後のトークイベントにも登壇した大楠道代でさえ「よく分からない」と言っていたのだから、それでいいのだろう。意味不明なのに、どこか惹きつけられてしまう、実に変な映画だった
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『悪は存在しない』(濱口竜介)の衝撃のラストの解釈と、タイトルが示唆する現実(主…
映画『悪は存在しない』(濱口竜介監督)は、観る者すべてを困惑に叩き落とす衝撃のラストに、鑑賞直後は迷子のような状態になってしまうだろう。しかし、作中で提示される様々な要素を紐解き、私なりの解釈に辿り着いた。全編に渡り『悪は存在しない』というタイトルを強く意識させられる、脚本・映像も見事な作品だ
あわせて読みたい
【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた
『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる
あわせて読みたい
【狂気】異質なホラー映画『みなに幸あれ』(古川琴音主演)は古い因習に似せた「社会の異様さ」を描く
古川琴音主演映画『みなに幸あれ』は、”シュールさ”さえ感じさせる「異質なホラー映画」だ。「村の因習」というよくあるパターンをベースに据えつつ、そこで展開される異様な状況が、実は「私たちが生きる世界」に対応しているという構成になっている。「お前の物語だからな」と終始突きつけられ続ける作品だ
あわせて読みたい
【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する
映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である
あわせて読みたい
【衝撃】映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想外すぎる着地を見せる普通じゃないドキュメンタリー
国連事務総長だったハマーショルドが乗ったチャーター機が不審な墜落を遂げた事件を、ドキュメンタリー映画監督マッツ・ブリュガーが追う映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想もつかない衝撃の展開を見せる作品だ。全世界を揺るがしかねない驚きの”真実”とは?
あわせて読みたい
【狂気】映画『ニューオーダー』の衝撃。法という秩序を混沌で駆逐する”悪”に圧倒されっ放しの86分
映画『ニューオーダー』は、理解不能でノンストップな展開に誘われる問題作だ。「貧富の差」や「法の支配」など「現実に存在する秩序」がひっくり返され、対極に振り切った「新秩序」に乗っ取られた世界をリアルに描き出すことで、私たちが今進んでいる道筋に警鐘を鳴らす作品になっている
あわせて読みたい
【狂気】入管の収容所を隠し撮りした映画『牛久』は、日本の難民受け入れ問題を抉るドキュメンタリー
映画『牛久』は、記録装置の持ち込みが一切禁じられている入管の収容施設に無許可でカメラを持ち込み、そこに収容されている難民申請者の声を隠し撮りした映像で構成された作品だ。日本という国家が、国際標準と照らしていかに酷い振る舞いをしているのかが理解できる衝撃作である
あわせて読みたい
【狂気】ホロコーストはなぜ起きた?映画『ヒトラーのための虐殺会議』が描くヴァンゼー会議の真実
映画『ヒトラーのための虐殺会議』は、ホロコーストの計画について話し合われた「ヴァンゼー会議」を描き出す作品だ。唯一1部だけ残った議事録を基に作られた本作は、「ユダヤ人虐殺」をイベントの準備でもしているかのように「理性的」に計画する様を映し出す。その「狂気」に驚かされてしまった。
あわせて読みたい
【映画】『別れる決心』(パク・チャヌク)は、「倫理的な葛藤」が描かれない、不穏で魅惑的な物語
巨匠パク・チャヌク監督が狂気的な関係性を描き出す映画『別れる決心』には、「倫理的な葛藤が描かれない」という特異さがあると感じた。「様々な要素が描かれるものの、それらが『主人公2人の関係性』に影響しないこと」や、「『理解は出来ないが、成立はしている』という不思議な感覚」について触れる
あわせて読みたい
【不穏】大友克洋の漫画『童夢』をモデルにした映画『イノセンツ』は、「無邪気な残酷さ」が恐ろしい
映画『イノセンツ』は、何がどう展開するのかまるで分からないまま進んでいく実に奇妙な物語だった。非現実的な設定で描かれるのだが、そのことによって子どもたちの「無邪気な残酷さ」が一層リアルに浮き彫りにされる物語であり、「意図的に大人が排除された構成」もその一助となっている
あわせて読みたい
【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…
「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ
あわせて読みたい
【驚嘆】映画『TAR/ター』のリディア・ターと、彼女を演じたケイト・ブランシェットの凄まじさ
天才女性指揮者リディア・ターを強烈に描き出す映画『TAR/ター』は、とんでもない作品だ。「縦軸」としてのターの存在感があまりにも強すぎるため「横軸」を上手く捉えきれず、結果「よく分からなかった」という感想で終わったが、それでも「観て良かった」と感じるほど、揺さぶられる作品だった
あわせて読みたい
【感想】これはドキュメンタリー(実話)なのか?映画『女神の継承』が突きつける土着的恐怖
ナ・ホンジンがプロデューサーを務めた映画『女神の継承』は、フィクションなのかドキュメンタリーなのか混乱させる異様な作品だった。タイ東北部で強く信じられている「精霊(ピー)」の信仰をベースに、圧倒的なリアリティで土着的恐怖を描き出す、強烈な作品
あわせて読みたい
【あらすじ】アリ・アスター監督映画『ミッドサマー』は、気持ち悪さと怖さが詰まった超狂ホラーだった
「夏至の日に映画館で上映する」という企画でようやく観ることが叶った映画『ミッドサマー』は、「私がなんとなく想像していたのとはまるで異なる『ヤバさ』」に溢れる作品だった。いい知れぬ「狂気」が随所で描かれるが、同時に、「ある意味で合理的と言えなくもない」と感じさせられる怖さもある
あわせて読みたい
【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理
オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く
「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品
あわせて読みたい
【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画
映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい
あわせて読みたい
【未知】「占い」が占い以外の効果を有するように、UFOなど「信じたいものを信じる」行為の機能を知れる…
「占い」に「見透かされたから仕方なく話す」という効用があるように、「『未知のもの』を信じる行為」には「『否定されたという状態』に絶対に達しない」という利点が存在する。映画『虚空門GATE』は、UFOを入り口に「『未知のもの』を信じる行為」そのものを切り取る
あわせて読みたい
【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ
江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品
あわせて読みたい
【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い
サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画
あわせて読みたい
【純愛】映画『ぼくのエリ』の衝撃。「生き延びるために必要なもの」を貪欲に求める狂気と悲哀、そして恋
名作と名高い映画『ぼくのエリ』は、「生き延びるために必要なもの」が「他者を滅ぼしてしまうこと」であるという絶望を抱えながら、それでも生きることを選ぶ者たちの葛藤が描かれる。「純愛」と呼んでいいのか悩んでしまう2人の関係性と、予想もつかない展開に、感動させられる
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
あわせて読みたい
【無謀】園子温が役者のワークショップと同時並行で撮影した映画『エッシャー通りの赤いポスト』の”狂気”
「園子温の最新作」としか知らずに観に行った映画『エッシャー通りの赤いポスト』は、「ワークショップ参加者」を「役者」に仕立て、ワークショップと同時並行で撮影されたという異次元の作品だった。なかなか経験できないだろう、「0が1になる瞬間」を味わえる“狂気”の映画
あわせて読みたい
【衝撃】映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』凄い。ラストの衝撃、ビョークの演技、”愛”とは呼びたくな…
言わずとしれた名作映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』を、ほぼ予備知識ゼロのまま劇場で観た。とんでもない映画だった。苦手なミュージカルシーンが効果的だと感じられたこと、「最低最悪のラストは回避できたはずだ」という想い、そして「セルマのような人こそ報われてほしい」という祈り
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
あわせて読みたい
【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…
映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた
あわせて読みたい
【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?
タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う
あわせて読みたい
【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…
ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ
あわせて読みたい
【実話】映画『アウシュビッツ・レポート』が描き出す驚愕の史実。世界はいかにホロコーストを知ったのか?
映画『アウシュヴィッツ・レポート』は、アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした実話を基にした作品。2人が持ち出した「アウシュビッツ・レポート」こそが、ホロコーストについて世界が知るきっかけだったのであり、そんな史実をまったく知らなかったことにも驚かされた
あわせて読みたい
【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…
在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。
あわせて読みたい
【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…
実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品
あわせて読みたい
【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ
「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ
あわせて読みたい
【驚愕】あるジャーナリストの衝撃の実話を描く映画『凶悪』。「死刑囚の告発」から「正義」を考える物語
獄中の死刑囚が警察に明かしていない事件を雑誌記者に告発し、「先生」と呼ばれる人物を追い詰めた実際の出来事を描くノンフィクションを原作にして、「ジャーナリズムとは?」「家族とは?」を問う映画『凶悪』は、原作とセットでとにかく凄まじい作品だ
あわせて読みたい
【狂気】バケモン・鶴瓶を映し出す映画。「おもしろいオッチャン」に潜む「異常さ」と「芸への情熱」:…
「俺が死ぬまで公開するな」という条件で撮影が許可された映画『バケモン』。コロナ禍で映画館が苦境に立たされなければ、公開はずっと先だっただろう。テレビで見るのとは違う「芸人・笑福亭鶴瓶」の凄みを、古典落語の名作と名高い「らくだ」の変遷と共に切り取る
あわせて読みたい
【考察】アニメ映画『虐殺器官』は、「便利さが無関心を生む現実」をリアルに描く”無関心ではいられない…
便利すぎる世の中に生きていると、「この便利さはどのように生み出されているのか」を想像しなくなる。そしてその「無関心」は、世界を確実に悪化させてしまう。伊藤計劃の小説を原作とするアニメ映画『虐殺器官』から、「無関心という残虐さ」と「想像することの大事さ」を知る
あわせて読みたい
【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える
どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える
あわせて読みたい
【驚愕】正義は、人間の尊厳を奪わずに貫かれるべきだ。独裁政権を打倒した韓国の民衆の奮闘を描く映画…
たった30年前の韓国で、これほど恐ろしい出来事が起こっていたとは。「正義の実現」のために苛烈な「スパイ狩り」を行う秘密警察の横暴をきっかけに民主化運動が激化し、独裁政権が打倒された史実を描く『1987、ある闘いの真実』から、「正義」について考える
あわせて読みたい
【葛藤】子どもが抱く「家族を捨てたい気持ち」は、母親の「家族を守りたい気持ち」の終着点かもしれな…
家族のややこしさは、家族の数だけ存在する。そのややこしさを、「子どもを守るために母親が父親を殺す」という極限状況を設定することで包括的に描き出そうとする映画『ひとよ』。「暴力」と「殺人犯の子どもというレッテル」のどちらの方が耐え難いと感じるだろうか?
あわせて読みたい
【漫画原作】映画『殺さない彼と死なない彼女』は「ステレオタイプな人物像」の化学反応が最高に面白い
パッと見の印象は「よくある学園モノ」でしかなかったので、『殺さない彼と死なない彼女』を観て驚かされた。ステレオタイプで記号的なキャラクターが、感情が無いとしか思えないロボット的な言動をする物語なのに、メチャクチャ面白かった。設定も展開も斬新で面白い
あわせて読みたい
【壮絶】本当に「美人は得」か?「美しさ」という土俵を意識せざるを得ない少女・女性たちの現実:『自…
美醜で判断されがちな”ルッキズム”の世の中に刃を突きつける小説『自画像』。私自身は、「キレイな人もキレイな人なりの大変さを抱えている」と感じながら生きているつもりだが、やはりその辛さは理解されにくい。私も男性であり、ルッキズムに加担してないとはとても言えない
あわせて読みたい
【逃避】つまらない世の中で生きる毎日を押し流す”何か”を求める気持ちに強烈に共感する:映画『サクリ…
子どもの頃「台風」にワクワクしたように、未だに、「自分のつまらない日常を押し流してくれる『何か』」の存在を待ちわびてしまう。立教大学の学生が撮った映画『サクリファイス』は、そんな「何か」として「東日本大震災」を描き出す、チャレンジングな作品だ
あわせて読みたい
【称賛】生き様がかっこいい。ムンバイのホテルのテロ事件で宿泊客を守り抜いたスタッフたち:映画『ホ…
インドの高級ホテルで実際に起こったテロ事件を元にした映画『ホテル・ムンバイ』。恐ろしいほどの臨場感で、当時の恐怖を観客に体感させる映画であり、だからこそ余計に、「逃げる選択」もできたホテルスタッフたちが自らの意思で残り、宿泊を助けた事実に感銘を受ける
あわせて読みたい
【リアル】社会の分断の仕組みを”ゾンビ”で学ぶ。「社会派ゾンビ映画」が対立の根源を抉り出す:映画『C…
まさか「ゾンビ映画」が、私たちが生きている現実をここまで活写するとは驚きだった。映画『CURED キュアード』をベースに、「見えない事実」がもたらす恐怖と、立場ごとに正しい主張をしながらも否応なしに「分断」が生まれてしまう状況について知る
あわせて読みたい
【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…
「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える
あわせて読みたい
【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…
金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
あわせて読みたい
【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…
世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ
あわせて読みたい
【実話】人質はなぜ犯人に好意を抱くか?「ストックホルム症候群」の由来である銀行強盗を描く映画:『…
「強盗や立てこもり事件などにおいて、人質が犯人に好意・共感を抱いてしまう状態」を「ストックホルム症候群」と呼ぶのだが、実はそう名付けられる由来となった実際の事件が存在する。実話を基にした映画『ストックホルムケース』から、犯人に協力してしまう人間の不可思議な心理について知る
あわせて読みたい
【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…
「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える
あわせて読みたい
【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…
2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る
あわせて読みたい
【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…
小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る
あわせて読みたい
【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…
30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。
あわせて読みたい
【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」
オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く
あわせて読みたい
【考察】世の中は理不尽だ。平凡な奴らがのさばる中で、”特別な私の美しい世界”を守る生き方:『オーダ…
自分以外は凡人、と考える主人公の少女はとてもイタい。しかし、世間の価値観と折り合わないなら、自分の美しい世界を守るために闘うしかない。中二病の少女が奮闘する『オーダーメイド殺人クラブ』をベースに、理解されない世界をどう生きるかについて考察する
あわせて読みたい
【覚悟】人生しんどい。その場の”空気”から敢えて外れる3人の中学生の処世術から生き方を学ぶ:『私を知…
空気を読んで摩擦を減らす方が、集団の中では大体穏やかにいられます。この記事では、様々な理由からそんな選択をしない/できない、『私を知らないで』に登場する中学生の生き方から、厳しい現実といかにして向き合うかというスタンスを学びます
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
どう生きるべきか・どうしたらいい【本・映画の感想】 | ルシルナ
どんな人生を歩みたいか、多くの人が考えながら生きていると思います。私は自分自身も穏やかに、そして周囲の人や社会にとっても何か貢献できたらいいなと、思っています。…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…






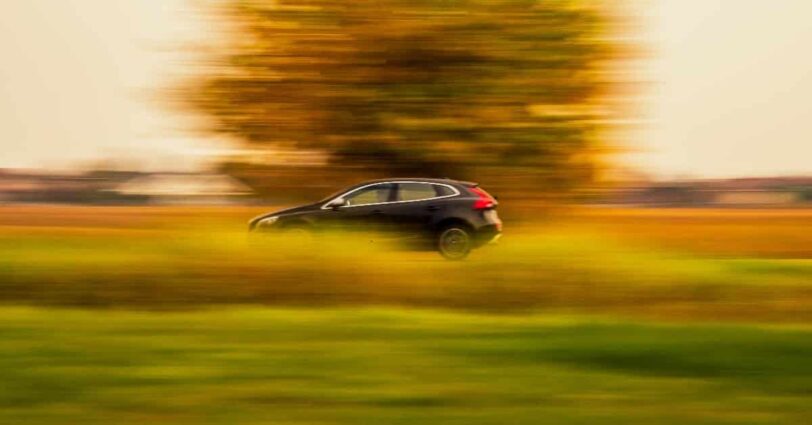











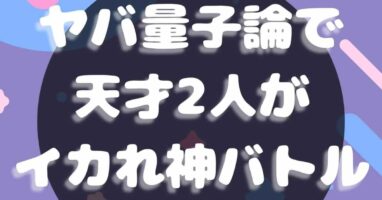
































































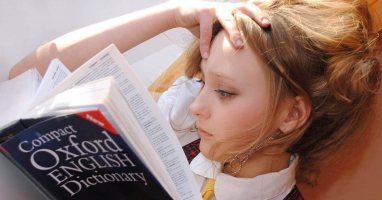

















コメント