目次
はじめに
この記事で取り上げる映画

「片思い世界」公式HP
この映画をガイドにしながら記事を書いていくようだよ
この記事で伝えたいこと
この記事ではネタバレになるような言及を避けて感想を書きました
そのため、舞台挨拶で出演者・監督・脚本家が語った内容に多く触れています
この記事の3つの要点
- 脚本を担当した坂元裕二が別名義で作詞した劇中歌『声は風』こそが、本作全体を絶妙にまとめあげていると思う
- 冒頭の「見せ方」がとにかく絶妙で、また、「予告編」も実に上手く作ってある
- 「そうであってほしい」と感じてしまうような世界観を坂元裕二はどのように作り上げたのか?
私の文章を読んでもさっぱり理解できないと思うので、読まずにすぐに本作を観ましょう
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
映画『片思い世界』は、思いがけない設定で思いがけない世界を描き出す、ちょっと驚きの物語だった
脚本を担当した坂元裕二が作詞した劇中歌『声は風』の歌詞の内容が、作品全体をまとめ上げているように思う
あわせて読みたい
【絶妙】映画『水深ゼロメートルから』(山下敦弘)は、何気ない会話から「女性性の葛藤」を描く(主演…
高校演劇を舞台化する企画第2弾に選ばれた映画『水深ゼロメートルから』は、「水のないプール」にほぼ舞台が固定された状態で、非常に秀逸な会話劇として展開される作品だ。退屈な時間を埋めるようにして始まった「ダルい会話」から思いがけない展開が生まれ、「女として生きること」についての様々な葛藤が描き出される点が面白い
これは実に素敵な作品でした。ただ、ネタバレを避けたまま内容に詳しく触れるのは不可能で、でも、やはり本作は「どんな設定なのか」を知らずに観た方がいいと思うので、この記事では「ネタバレをせず、書けそうな範囲内のことだけ書く」ことにしたいと思います。
まあネタバレの状態で観ても全然面白いとは思うけど、やっぱり何も知らない方が驚きが大きくなるからね
それが明かされるまでの描き方も、明かされてからの展開も、よく出来てるんだよなぁ

私は、特に狙っていたわけではないのですが、、本作を「ライブビューイングでの舞台挨拶付きの上映回」で観ました。それで今回は、内容についてのネタバレを避けるために、この舞台挨拶で言及された話に多く触れることになると思います。
あわせて読みたい
【解説】映画『スターフィッシュ』をネタバレ全開で考察。主人公が直面する”奇妙な世界”の正体は?
映画『スターフィッシュ』は、「親友の葬儀」とそれに続く「不法侵入」の後、唐突に「意味不明な世界観」に突入していき、その状態のまま物語が終わってしまう。解釈が非常に難しい物語だが、しかし私なりの仮説には辿り着いた。そこでこの記事では、ネタバレを一切気にせずに「私が捉えた物語」について解説していくことにする
さて、出演者の1人である杉咲花がその舞台挨拶の中で、劇中歌『声は風』の歌詞のある箇所が好きだという話をしていました。それが、
花が忘れても 種はおぼえてる
生きるよろこびを
という部分です。そして本作『片思い世界』は、まさに「生きるよろこび」みたいなものを強く実感させてくれる作品じゃないかと思います。私が言っている「生きる」には悲しい意味も含まれているのですが、本作では、そういう「悲しさ」もすべてひっくるめた上で「生きるよろこび」が描かれている感じがあって、凄く素敵だなと感じました。
「生きる」って言葉に色んな可能性を見出したくなるような感じだよね
「そうだったらいいなぁ」って思う人は多いんじゃないかな
さて、この『声は風』の歌詞は、本作の脚本を担当した坂元裕二が別名義で作詞したそうなのですが、「脚本を書き終える前に作詞しなければならなくなり、つまり同時並行だった」のだそうです。だとすればもしかしたら、「作詞が終わってから登場人物の名前を考えた」なんて可能性もあるかもしれません。というのも、相楽美咲・片石優花・阿澄さくらという主人公3人は「花」を連想させる名前になっているからです(あるいは、「花」というモチーフが先にあって、そこから登場人物の名前も『声は風』の作詞も連想していった、と考える方が自然でしょうか)。
あわせて読みたい
【助けて】映画『生きててごめんなさい』は、「共依存カップル」視点で生きづらい世の中を抉る物語(主…
映画『生きててごめんなさい』は、「ちょっと歪な共依存関係」を描きながら、ある種現代的な「生きづらさ」を抉り出す作品。出版社の編集部で働きながら小説の新人賞を目指す園田修一は何故、バイトを9度もクビになり、一日中ベッドの上で何もせずに過ごす同棲相手・清川莉奈を”必要とする”のか?
というわけでもう少し『声は風』の話を続けると、サビのフレーズである「声は風 風は夢 飛んでけ」にはもちろん「種」のイメージが含まれているでしょう。つまり、「種から芽吹いた花は厳密には元の花とは違うけれど、枯れては咲いてを繰り返すことで生命は続いていく」みたいなことが、劇中歌『声は風』に、そしてひいては本作『片思い世界』にも貫かれているというわけです。監督の土井裕泰が言っていた通り、本作は『片思い世界』というタイトル以外はあり得ない作品であり、そして、タイトルやテーマ性など作品を形作る様々な要素が「全体としてまとまっている」みたいな印象だったのが凄く良かったなと思います。
予告編を観ているだけじゃ全然想像も出来ない作品だからね
映画『片思い世界』の内容紹介
年齢も苗字もバラバラの3人の女性が、1つ屋根の下で暮らしている。今日は、一番年下のさくらの誕生日だ。美咲と優花は部屋中を飾り付けて”サプライズ”のお祝いを用意しているのだが、サプライズが全然好きじゃない我が道タイプのさくらは、「毎回驚いたフリをしなきゃいけないこっちの身にもなって」と苛立ちを隠さない。しかしそれはただの照れ隠しで、なんとこの後、美咲と優花が感動するような展開が待っているのだ。
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
というわけで彼女たちは3人で仲良く暮らしている。朝はバタバタと起き出し、一番年長の美咲が3人分のお弁当を作り、「柱に背の高さを刻む」という恒例の日課をやってから、それぞれの場所へと向かう。美咲はオフィスへ、優花は大学へ、そしてさくらは水族館である。日中はそんな風にそれぞれで過ごしつつ、何だかんだ3人はいつも一緒にいて、食べたり映画を観たり寝たりして楽しそうに暮らしていた。

さて、美咲とさくらが乗るバスには、さくらが「アホ毛」と呼んでいる男性がいつも乗っている。どうも、美咲は彼のことが気になっているようだ。そんなわけである日、さくらが凄まじいお節介を焼き(そういう性格なのだろう)、その「アホ毛」がラフマニノフのピアノコンサートで女性とデート予定だと突き止める。でなんと、彼女たちはそのまま、2人のデートについていくようにしてコンサート会場まで押しかけてしまうのだ。
一方、優花は大学の近くに停まっている花屋のバンを見ている。いや、そのバンに乗っている女性を見ているみたいだ。ちょっと驚いたような表情をしている。そう、彼女は実は思いも寄らない人を見つけてしまったのだ……。
あわせて読みたい
【煌めき】映画『HAPPYEND』が描く、”監視への嫌悪”と”地震への恐怖”の中で躍動する若者の刹那(監督:…
映画『HAPPYEND』は、「監視システム」と「地震」という「外的な制約条件」を設定し、その窮屈な世界の中で屈せずに躍動しようとする若者たちをリアルに描き出す物語である。特に、幼稚園からの仲であるコウとユウタの関係性が絶妙で、演技未経験だという2人の存在感と映像の雰囲気が相まって、実に素敵に感じられた
冒頭の見せ方も予告編の作り方も絶妙で、とにかく「よくこんな物語にまとめ上げたものだ」と感心させられた
本作ではまず、冒頭の「見せ方」が凄く上手かったなと思います。本作の冒頭は内容紹介で書いた通りさくらの誕生会のシーンなので、まずはさくらの「見せ方」がとても上手いという感じです。誕生会のシーンだけでも「さくらのぶっ飛んだ雰囲気」が伝わってくるし、そしてそれ故に、冒頭の「あるシーン」の違和感が目立ちません。物語が後半に入ってからこの冒頭の場面を思い返せば、誰もが「見せ方が上手いなぁ」と感じることでしょう。
映画について話す友人が1人いるんだけど、「このシーンは上手かった」って言ってたわ
最初は絶対に気づかないし、けど、後から確実に「そうだったのか」ってなるのが上手いよね
そして本作では、他にも同じような感じで、「気になると言えば気になるけど、気にならないと言えば気にならない程度の違和感」が少しずつ積み上がっていきます。そして、それらの「違和感」が一気に解消された瞬間から物語が本格的に始まると言っていいでしょう。で、そうなる前の段階ではまず、「さくらの変わりっぷり」や「3人の関係性」なんかが結構魅力的でした。本作では、「違和感が解消された後」の展開も役者に高い演技力が求められると思うのですが、「違和感が解消される前」もまた違った繊細さが必要とされる感じがあって、とにかく主人公3人を演じた広瀬すず、杉咲花、清原果耶はかなり苦労したんじゃないかなと思います。
あわせて読みたい
【秘密】映画『ドライブ・イン・マンハッタン』は、「タクシー内の会話のみ」だが絶妙に良かった(主演…
映画『ドライブ・イン・マンハッタン』は、「タクシー内」というワンシチュエーションで「会話のみ」によって展開されるミニマムな要素しかない物語なのに、とにかく面白くて驚かされてしまった。運転手による「ゲスい会話」や女性客が抱えているのだろう「謎の秘密」などについて、色々と考えたくなるような深みのある物語である
また本作は、「予告編が絶妙な形で機能している映画」と言えるでしょう。予告編だけを観ても別に違和感らしい違和感はないのですが、「違和感が解消された後」でこの予告編を思い出してみると、「予告編のあのシーンは、本作においてどんな形で登場・成立するんだろう?」みたいに感じるんじゃないかと思います。これもまたよく出来ているなと感じました。別に「予告編を観ておくのは必須」なんてことは全然ありませんが、予告編を先に観ておくことで、「何がどうなったら予告編のあのシーンのような展開になるんだ?」みたいな方向からも本作を楽しめるようになるかもしれません。それはそれでまた面白い見方ではないかと思います。
しかし、予告編を作る人も頭を抱えたんじゃないかなぁ
「物語の本質的な要素は出しちゃいけない」っていう制約の中で、よくああいう予告編を完成させたなって感じだよね
さて、先程から書いている通り、本作ではある時点で「違和感が解消される」わけで、そこから物語のトーンが一気に変わりました。で、「違和感が解消された後」は皆、「この後、何がどうなるわけ?」みたいに感じるんじゃないかと思います。「なるほど、設定は理解した。で、ここからどう展開するの?」というわけです。
あわせて読みたい
【天才】映画『リバー、流れないでよ』は、ヨーロッパ企画・上田誠によるタイムループの新発明だ
ヨーロッパ企画の上田誠が生み出した、タイムループものの新機軸映画『リバー、流れないでよ』は、「同じ2分間が繰り返される」という斬新すぎる物語。その設定だけ聞くと、「どう物語を展開させるんだ?」と感じるかもしれないが、あらゆる「制約」を押しのけて、とんでもない傑作に仕上がっている
そしてこの点に関しては監督自身も言及しています。監督もまた「面白いけど、じゃあここからどうなっていくんだろう?」と感じたと言っていました。というのも本作は、「紙1枚に20行程度の文章(プロットと呼べるほどのものでもない)」からスタートしているからです。坂元裕二から提出されたその文章を読んで、監督は前述のような感想を抱いたそうで、そりゃそうだろうなと思います。その時点ではもちろん、脚本は全然仕上がっていなかったわけですが、そこからよくもまあ、この「かなり複雑な制約のある物語」を面白い作品に仕上げたものだなと感じました。
しかしまさか、「スーパーカミオカンデ」の話が出てくるとは思わなかったよね
理解できなくても全然問題ない要素だけど、物理が好きな私としてはちょっとテンションが上がった
「そうであってほしい」と思わせるような物語はどのように生まれたのか?
舞台挨拶の仲で坂元裕二は、本作の脚本を思いついた時のエピソードについて聞かれていて、次のように答えていたように思います。

設定などをすべて思いついて書き始めた後で、「そう言えばこの物語は、子どもの頃の自分が布団の中でずっと考えていたものだった」と気付いた。
本作を観終えた人なら、彼のこの感覚は何となく理解できるんじゃないでしょうか。具体的なことに触れずに書くのはなかなか無理があるのですが、本作の設定に対しては、割と多くの人が「そうであってほしい」みたいに感じるんじゃないかと思います。同じような発想を頭に思い浮かべたことがある人は結構いるでしょう。そしてだからこそ本作は、多くの人に届いているんじゃないかと思います。
あわせて読みたい
【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…
映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ
あるいは、本作を観たことで「そうであってほしい」と思うようになったみたいな人もいるだろうしね
そして本作では、そんな「『そうであってほしい』と願ってしまうような世界観」が、最後までちゃんと“リアル”に展開されていたことも良かったです。ネタバレをせず、観ていない人にこの「リアルさ」を伝えるのは無理なのですが、「『やっぱりそうだよね』というある種の残酷さ」がきちんと内包されていて、そしてその上で、「その残酷さをちょっとした偶然で和らげる展開」になるのが凄く良かったなと思います。
個人的には特に、「車にぶつかるシーン」にそこはかとなく救いを感じました。「映し出される状況」だけを客観的に捉えたら、とても「救い」なんて表現を使える場面ではないのですが、それでも、「どうしようもない無力感」で満たされてしまった作品世界において「観客が望む展開を用意する」という点でこのシーンは絶妙だったと思うし、そういう意味で「救い」という言葉を使ったつもりでいます。
なんていうか、「それぐらいのことが起こらないと釣り合わないよね」みたいな感じかな
しかしホント、ふわっとさせたまま伝えるのは難しいよね
ちなみに本作では、先述した「紙1枚に20行程度の文章」を提出した時点で既に、広瀬すず・杉咲花・清原果耶の出演が決定していたそうです。そしてその話を受けて司会者が坂元裕二に、「この3人が演じるという事実は、脚本の執筆に何か影響しましたか?」と質問をします。それに対して坂元裕二は、「普段は演者に寄せることも考えるのですが、今回は主人公3人に何かキャラクターを与えるような書き方をしてはいけないんじゃないかと思っていた」みたいな返答をしていました。
あわせて読みたい
【考察】映画『街の上で』(今泉力哉)が描く「男女の友情は成立する」的会話が超絶妙で素晴らしい(出…
映画『街の上で』(今泉力哉監督)は、「映画・ドラマ的会話」ではない「自然な会話」を可能な限り目指すスタンスが見事だった。「会話の無駄」がとにかく随所に散りばめられていて、そのことが作品のリアリティを圧倒的に押し上げていると言える。ある男女の”恋愛未満”の会話もとても素晴らしかった
さらに彼は、「これは監督とも一致している部分なのですが、今回は3人のキャラクターを1人の人物であるかのようにして描くイメージを持っていた」のだそうです。舞台挨拶では監督もこの点について言及していたのですが、監督の発言に触れるとかなりネタバレに絡んでくるのでここでは避けます。ただやはり、監督自身も「1人の人間を3つのキャラクターに分けて描く」ような意識で本作を撮っていったそうで、そういう見方をしてみるのもまた面白いかもしれません。
舞台挨拶の話であと印象的だったのは、「完成しないかもしれないと思った」って話
後で調べて分かったけど、本作の撮影中に監督らスタッフが交通事故に遭ってかなりの重症だったみたいね

さて最後に、本作の「残酷さ」についてもう少し触れておきましょう。本作では、先述した「車がぶつかるシーン」とそこに至るまでの一連の流れを除けば、「視覚的に残酷なシーン」はほぼ存在しません。ただ本作にはずっと、「拭いきれない『残酷さ』」みたいなものが付きまとっていた印象もあります。
あわせて読みたい
【不穏】大友克洋の漫画『童夢』をモデルにした映画『イノセンツ』は、「無邪気な残酷さ」が恐ろしい
映画『イノセンツ』は、何がどう展開するのかまるで分からないまま進んでいく実に奇妙な物語だった。非現実的な設定で描かれるのだが、そのことによって子どもたちの「無邪気な残酷さ」が一層リアルに浮き彫りにされる物語であり、「意図的に大人が排除された構成」もその一助となっている
そういう「残酷さ」は大体の場合、広瀬すず・杉咲花・清原果耶の3人が織りなす「楽しげな雰囲気」にかき消されて可視化されません。しかし、彼女たちが笑顔を保てない状況においては、「楽しげな雰囲気」で蓋をされて表に出てこなかった「残酷さ」が一気に噴出して、思いがけず「悲しさ」に支配される瞬間がやってきたりもします。もちろん、彼女たちは「ずっとそういう環境にいた」わけで、思いのほかダメージは大きくないのかもしれません。しかし、観ている側は「こういう世界で生きざるを得ないからこそ抱いてしまう苦しみ」を勝手に増幅して感じ取ってしまうというわけです。
そんな風に感じさせる絶妙な設定も、設定を上手く活かす展開・演出も素晴らしく、とても満足できる鑑賞でした。
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
私の文章を読んだだけではきっと、本作『片思い世界』がどんな物語なのかまるで想像できないでしょう。でも、それで正解だと思います。是非、何も知らないまま観て下さい。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ
私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。
ただ私は以前、「犬や猫が死んじゃうシーンがある映画は絶対に観れないから、そういうのは先に調べないと無理」みたいな意見を目にしたことがあります。なるほど、「何も知らずに映画を観る」という行為にそんなハードルがあるのかと感じたのですが、そういう方のために一応、「犬も猫もカメも死にません」と書いておくことにしましょう(予告編でカメが出てくるので一応言及しておきました)。
というわけで、とても素敵な作品でした。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…
私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。
次におすすめの記事
あわせて読みたい
【感想】映画『ファーストキス 1ST KISS』は、「過去に戻り未来を変える物語」として脚本が秀逸(監督…
映画『ファーストキス 1ST KISS』は、稀代の脚本家である坂元裕二の手腕が存分に発揮された作品。「過去にタイムスリップして未来を変える」というありがちな設定をベースにしながら、様々な「特異さ」を潜ませた物語は、とにかく絶妙に上手かったし面白かった。設定も展開も役者の演技もすべて秀逸な、実に面白いエンタメ作品
あわせて読みたい
【感想】実写映画『からかい上手の高木さん』(今泉力哉)は「あり得ない関係」を絶妙に描く(主演:永…
私は実写映画『からかい上手の高木さん』を「今泉力哉の最新作」として観に行った。常に「普通には成立しないだろう関係性」を描き出す今泉力哉作品らしく、本作でもそんな「絶妙にややこしい関係」が映し出されている。「正解がない」からこそ「すべてが正解になる」はずの「恋愛」をベースに、魅力的な関わりを描き出す物語
あわせて読みたい
【秀逸】映画『ゴーストキラー』は、アクションを活かす見事な配役・設定が魅力を生んでいる(監督:園…
映画『ゴーストキラー』はまず何よりも、主演を務めた髙石あかりの演技とアクションが素晴らしい。映画冒頭では正直、「大丈夫か、この映画……」と感じてしまったのだが、髙石あかりの演技の上手さで冒頭を乗り切った後は圧倒的なアクションで惹き付ける展開になり、普段はストーリーにしか興味がない私も圧倒された
あわせて読みたい
【レビュー】実写映画『秒速5センチメートル』が描く「魂が震える人と出会うこと」の煌めきと残酷さ(監…
実写映画『秒速5センチメートル』は、何よりもまず「雰囲気」が最高に素晴らしい作品でした。「人生の早い段階で『魂が震える人』と出会ってしまったこと」の煌めきと残酷さが深く描かれていて、観ている間じゅう色んなことを考えさせられたし、会話も役者の演技も主題歌もすべてが完璧で、とにかく観て良かったなと思います
あわせて読みたい
【相違】友人の友人が作ったZINE『our house』には様々な「恋愛に惑う気持ち」が詰まっている
ひょんなことから知り合った女性が制作したZINE『our house』は、「恋愛」や「友情」に対して私が以前から抱いていた感覚にかなり近い内容で、実に興味深い。特に「恋愛においても、自分のことを性別で捉えられたくない」という感覚は新鮮で、そこから「男性は『恋愛的に惹かれている』という感覚を持たないかも」とも考えた
あわせて読みたい
【あらすじ】のん(能年玲奈)が実に素敵な映画『私にふさわしいホテル』が描く文壇の変な世界(監督:…
「こんな奴いないだろ」というような人物を絶妙な雰囲気で演じるのん(能年玲奈)の存在感がとにかく素敵な映画『私にふさわしいホテル』では、小説家・編集者がワチャワチャする「文壇」の世界が描かれる。無名の新人と大御所がハチャメチャなバトルを繰り広げるストーリーに、様々な「皮肉」が散りばめられた、なかなか痛快な物語
あわせて読みたい
【実話】特殊詐欺被害者が警察より先に犯人を追い詰める映画『市民捜査官ドッキ』は他人事じゃない
映画『市民捜査官ドッキ』は、実際に起こった詐欺事件を基にした映画なのですが、とても実話とは思えない驚きの状況が描かれます。なにせ、「警察に見放された詐欺被害者が、自ら詐欺グループの拠点を探し当てる」のです。テーマはシリアスですが、全体的にはコメディタッチで展開される作品で、とにかく楽しく見られるでしょう
あわせて読みたい
【人生】映画『雪子 a.k.a.』は、言葉は出ないが嘘もないラップ好きの小学校教師の悩みや葛藤を描き出す
「小学校教師」と「ラップ」というなかなか異色の組み合わせの映画『雪子 a.k.a.』は、「ここが凄く良かった」と言えるようなはっきりしたポイントはないのに、ちょっと泣いてしまうぐらい良い映画だった。「口下手だけど嘘はない」という主人公・雪子の日常的な葛藤には、多くの人が共感させられるのではないかと思う
あわせて読みたい
【包容】映画『違国日記』を観て思う。「他者との接し方」が皆こうだったらもっと平和なはずだって(主…
映画『違国日記』は、人見知りの小説家・高代槙生が両親を亡くした姪・朝を引き取り一緒に暮らすところから始まる物語で、槙生と朝を中心とした様々な人間関係が絶妙に描かれている作品でした。人付き合いが苦手ながら、15歳という繊細な存在を壊さないように、でも腫れ物みたいには扱わないように慎重になる槙生のスタンスが素敵です
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『夏目アラタの結婚』は黒島結菜が演じた品川真珠の歯並びが凄い(でもかわいい)(監…
映画『夏目アラタの結婚』は、まずとにかく、黒島結菜が演じた主人公・品川真珠のビジュアルが凄まじかった。原作者が「譲れない」と言ったという「ガタガタの汚い歯」の再現が凄まじく、これだけで制作陣の本気度が伝わるくらい。ストーリー展開も見事で、もう1人の主人公が最終的に思いがけない実感に行き着く流れも興味深い
あわせて読みたい
【秘密】映画『ドライブ・イン・マンハッタン』は、「タクシー内の会話のみ」だが絶妙に良かった(主演…
映画『ドライブ・イン・マンハッタン』は、「タクシー内」というワンシチュエーションで「会話のみ」によって展開されるミニマムな要素しかない物語なのに、とにかく面白くて驚かされてしまった。運転手による「ゲスい会話」や女性客が抱えているのだろう「謎の秘密」などについて、色々と考えたくなるような深みのある物語である
あわせて読みたい
【失恋】ひたすらカオスに展開する映画『エターナル・サンシャイン』は、最後まで観ると面白い!(主演…
映画『エターナル・サンシャイン』は、冒頭からしばらくの間、とにかくまったく意味不明で、「何がどうなっているのか全然分からない!」と思いながら観ていました。しかし、映像がカオスになるにつれて状況の理解は進み始め、最終的には「よくもまあこんな素っ頓狂なストーリーを理解できる物語に落とし込んだな」と感心させられました
あわせて読みたい
【天才】映画『アット・ザ・ベンチ』面白すぎる!蓮見翔の脚本に爆笑、生方美久の会話劇にうっとり(監…
役者も脚本家も監督も何も知らないまま、「有名な役者が出てこないマイナーな映画」だと思い込んで観に行った映画『アット・ザ・ベンチ』は、衝撃的に面白い作品だった。各話ごと脚本家が異なるのだが、何よりも、第2話「回らない」を担当したダウ90000・蓮見翔の脚本が超絶面白い。あまりの衝撃にぶっ飛ばされてしまった
あわせて読みたい
【感想】高倍率のやばい藝大入試に挑む映画『ブルーピリオド』は「生きてる実感の無さ」をぶち壊す(監…
映画『ブルーピリオド』は、大学入試で最高倍率とも言われる200倍の試験に挑む高校生たちの物語。東京藝術大学絵画科という果てしない最難関に、高校2年生から突然挑戦すると決めた矢口八虎を中心に、「『好き』に囚われた者たち」の果てしない情熱と葛藤を描き出す。絵を描くシーンを吹き替えなしで行った役者の演技にも注目だ
あわせて読みたい
【葛藤】映画『きみの色』(山田尚子)は、感受性が強すぎる若者のリアルをバンドを通じて描き出す(主…
山田尚子監督作『きみの色』は、これといった起伏のないストーリー展開でありながら、「若い世代の繊細さに満ちた人間関係」をとてもリアルに描き出す雰囲気が素敵な作品。「悩み・葛藤を抱えている状態が日常である」という雰囲気をベースにしつつ、「音楽」を起点に偶然繋がった3人の緩やかな日々を描き出す物語に惹きつけられた
あわせて読みたい
【異例】東映京都撮影所が全面協力!自主制作の時代劇映画『侍タイムスリッパー』は第2の『カメ止め』だ…
映画『侍タイムスリッパー』は、「自主制作映画なのに時代劇」「撮影スタッフ10人なのに東映京都撮影所全面協力」「助監督役が実際の助監督も務めている」など、中身以外でも話題に事欠かない作品ですが、何もよりも物語が実に面白い!「幕末の侍が現代にタイムスリップ」というよくある設定からこれほど面白い物語が生まれるとは
あわせて読みたい
【面白い】映画『ラストマイル』は、物流問題をベースに「起こり得るリアル」をポップに突きつける(監…
映画『ラストマイル』は、「物流」という「ネット社会では誰にでも関係し得る社会問題」に斬り込みながら、実に軽妙でポップな雰囲気で展開されるエンタメ作品である。『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界で展開される「シェアード・ユニバース」も話題で、様々な人の関心を広く喚起する作品と言えるだろう
あわせて読みたい
【宣伝】アポロ計画での月面着陸映像は本当か?映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』のリアル
「月面着陸映像はニセモノだ」という陰謀論を逆手にとってリアリティのある物語を生み出した映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』は、「ベトナム戦争で疲弊し、事故続きのNASAが不人気だった」という現実を背景に「歴史のif」を描き出す。「確かにそれぐらいのことはするかもしれない」というリアリティをコメディタッチで展開させる
あわせて読みたい
【評価】高山一実の小説かつアニメ映画である『トラペジウム』は、アイドル作とは思えない傑作(声優:…
原作小説、そしてアニメ映画共に非常に面白かった『トラペジウム』は、高山一実が乃木坂46に在籍中、つまり「現役アイドル」として出版した作品であり、そのクオリティに驚かされました。「現役アイドル」が「アイドル」をテーマにするというド直球さを武器にしつつ、「アイドルらしからぬ感覚」をぶち込んでくる非常に面白い作品である
あわせて読みたい
【感想】B級サメ映画の傑作『温泉シャーク』は、『シン・ゴジラ』的壮大さをバカバカしく描き出す
「温泉に入っているとサメに襲われる」という荒唐無稽すぎる設定のサメ映画『温泉シャーク』は、確かにふざけ倒した作品ではあるものの、観てみる価値のある映画だと思います。サメの生態を上手く利用した設定や、「伏線回収」と表現していいだろう展開などが巧みで、細かなことを気にしなければ、そのバカバカしさを楽しめるはずです
あわせて読みたい
【恋心】映画『サッドティー』は、「『好き』を巡ってウロウロする人々」を描く今泉力哉節全開の作品だった
映画『サッドティー』は、今泉力哉らしい「恋愛の周辺でグルグルする人たち」を描き出す物語。関係性が微妙に重なる複数の人間を映し出す群像劇の中で、「『好き』のややこしさ」に焦点を当てていく構成はさすがです。実に奇妙な展開で終わる物語ですが、それでもなお「リアルだ」と感じさせる雰囲気は、まるで魔法のようでした
あわせて読みたい
【記憶】映画『退屈な日々にさようならを』は「今泉力哉っぽさ」とは異なる魅力に溢れた初期作品だ(主…
今泉力哉作品のオールナイト上映に初めて参加し、『退屈な日々にさようならを』『街の上で』『サッドティー』を観ました。本作『退屈な日々にさようならを』は、時系列が複雑に入れ替わった群像劇で、私が思う「今泉力哉っぽさ」は薄い作品でしたが、構成も展開も会話も絶妙で、さすが今泉力哉という感じです
あわせて読みたい
【感想】映画『ルックバック』の衝撃。創作における衝動・葛藤・苦悩が鮮やかに詰め込まれた傑作(原作…
アニメ映画『ルックバック』は、たった58分の、しかもセリフも動きも相当に抑制された「静」の映画とは思えない深い感動をもたらす作品だった。漫画を描くことに情熱を燃やす2人の小学生が出会ったことで駆動する物語は、「『創作』に限らず、何かに全力で立ち向かったことがあるすべての人」の心を突き刺していくはずだ
あわせて読みたい
【絶妙】映画『水深ゼロメートルから』(山下敦弘)は、何気ない会話から「女性性の葛藤」を描く(主演…
高校演劇を舞台化する企画第2弾に選ばれた映画『水深ゼロメートルから』は、「水のないプール」にほぼ舞台が固定された状態で、非常に秀逸な会話劇として展開される作品だ。退屈な時間を埋めるようにして始まった「ダルい会話」から思いがけない展開が生まれ、「女として生きること」についての様々な葛藤が描き出される点が面白い
あわせて読みたい
【狂気】押見修造デザインの「ちーちゃん」(映画『毒娘』)は「『正しさ』によって歪む何か」の象徴だ…
映画『毒娘』は、押見修造デザインの「ちーちゃん」の存在感が圧倒的であることは確かなのだが、しかし観ていくと、「決して『ちーちゃん』がメインなわけではない」ということに気づくだろう。本作は、全体として「『正しさ』によって歪む何か」を描き出そうとする物語であり、私たちが生きる社会のリアルを抉り出す作品である
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『52ヘルツのクジラたち』の「無音で叫ぶ人」と「耳を澄ます人」の絶妙な響鳴(原作:…
映画『52ヘルツのクジラたち』は、「現代的な問題のごった煮」と感じられてしまうような”過剰さ”に溢れてはいますが、タイトルが作品全体を絶妙に上手くまとめていて良かったなと思います。主演の杉咲花がやはり見事で、身体の内側から「不幸」が滲み出ているような演技には圧倒されてしまいました
あわせて読みたい
【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…
映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です
あわせて読みたい
【衝撃】広末涼子映画デビュー作『20世紀ノスタルジア』は、「広末が異常にカワイイ」だけじゃない作品
広末涼子の映画デビュー・初主演作として知られる『20世紀ノスタルジア』は、まず何よりも「広末涼子の可愛さ」に圧倒される作品だ。しかし、決してそれだけではない。初めは「奇妙な設定」ぐらいにしか思っていなかった「宇宙人に憑依されている」という要素が、物語全体を実に上手くまとめている映画だと感じた
あわせて読みたい
【映画】ウォン・カーウァイ4Kレストア版の衝撃!『恋する惑星』『天使の涙』は特にオススメ!
『恋する惑星』『天使の涙』で一躍その名を世界に知らしめた巨匠ウォン・カーウァイ作品の4Kレストア版5作品を劇場で一気見した。そして、監督の存在さえまったく知らずに観た『恋する惑星』に圧倒され、『天使の涙』に惹きつけられ、その世界観に驚かされたのである。1990年代の映画だが、現在でも通用する凄まじい魅力を放つ作品だ
あわせて読みたい
【奇妙】映画『鯨の骨』は、主演のあのちゃんが絶妙な存在感を醸し出す、斬新な設定の「推し活」物語
映画『鯨の骨』は、主演を務めたあのちゃんの存在感がとても魅力的な作品でした。「AR動画のカリスマ的存在」である主人公を演じたあのちゃんは、役の設定が絶妙だったこともありますが、演技がとても上手く見え、また作品全体の、「『推し活』をある意味で振り切って描き出す感じ」もとても皮肉的で良かったです
あわせて読みたい
【怖い?】映画『アメリ』(オドレイ・トトゥ主演)はとても奇妙だが、なぜ人気かは分かる気がする
名作として知られているものの観る機会の無かった映画『アメリ』は、とても素敵な作品でした。「オシャレ映画」という印象を持っていて、それは確かにその通りなのですが、それ以上に私は「主人公・アメリの奇妙さ」に惹かれたのです。普通には成立しないだろう展開を「アメリだから」という謎の説得力でぶち抜く展開が素敵でした
あわせて読みたい
【あらすじ】声優の幾田りらとあのちゃんが超絶良い!アニメ映画『デデデデ』はビビるほど面白い!:『…
幾田りらとあのちゃんが声優を務めた映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』は、とにかく最高の物語だった。浅野いにおらしいポップさと残酷さを兼ね備えつつ、「終わってしまった世界でそれでも生きていく」という王道的展開を背景に、門出・おんたんという女子高生のぶっ飛んだ関係性が描かれる物語が見事すぎる
あわせて読みたい
【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…
映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった
あわせて読みたい
【評価】映画『ゴジラ-1.0』(山崎貴監督)は面白い!迫力満点の映像と絶妙な人間ドラマ(米アカデミー…
米アカデミー賞で視覚効果賞を受賞した映画『ゴジラ-1.0』(山崎貴監督)は、もちろんそのVFXに圧倒される物語なのだが、「人間ドラマ」をきちんと描いていることも印象的だった。「終戦直後を舞台にする」という、ゴジラを描くには様々な意味でハードルのある設定を見事に活かした、とても見事な作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『レザボア・ドッグス』(タランティーノ監督)はとにかく驚異的に脚本が面白い!
クエンティン・タランティーノ初の長編監督作『レザボア・ドッグス』は、のけぞるほど面白い映画だった。低予算という制約を逆手に取った「会話劇」の構成・展開があまりにも絶妙で、舞台がほぼ固定されているにも拘らずストーリーが面白すぎる。天才はやはり、デビュー作から天才だったのだなと実感させられた
あわせて読みたい
【感想】映画『ローマの休日』はアン王女を演じるオードリー・ヘプバーンの美しさが際立つ名作
オードリー・ヘプバーン主演映画『ローマの休日』には驚かされた。現代の視点で観ても十分に通用する作品だからだ。まさに「不朽の名作」と言っていいだろう。シンプルな設定と王道の展開、そしてオードリー・ヘプバーンの時代を超える美しさが相まって、普通ならまずあり得ない見事なコラボレーションが見事に実現している
あわせて読みたい
【おすすめ】カンヌ映画『PERFECT DAYS』は、ほぼ喋らない役所広司の沈黙が心地よい(ヴィム・ヴェンダ…
役所広司主演映画『PERFECT DAYS』(ヴィム・ヴェンダース監督)は、主人公・平山の「沈黙」がとにかく雄弁な物語である。渋谷区のトイレの清掃員である無口な平山の、世間とほとんど繋がりを持たない隔絶した日常が、色んなものを抱えた者たちを引き寄せ、穏やかさで満たしていく様が素晴らしい
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『千年女優』(今敏)はシンプルな物語を驚愕の演出で味付けした天才的アニメ作品
今敏監督の映画『千年女優』は、ちょっとびっくりするほど凄まじく面白い作品だった。観ればスッと理解できるのに言葉で説明すると難解になってしまう「テクニカルな構成」に感心させられつつ、そんな構成に下支えされた「物語の感性的な部分」がストレートに胸を打つ、シンプルながら力強い作品だ
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
あわせて読みたい
【家族】映画『女優は泣かない』は、蓮佛美沙子が「再起を賭ける女優」を演じる笑い泣き満載の作品(出…
蓮佛美沙子が、スキャンダルで落ちぶれ再起を賭ける女優を演じる映画『女優は泣かない』は、ミニマムかつシンプルな構成ながら、笑いあり涙ありのハートフルコメディだった。「やりたくはないが、やらねばならぬ」とお互いが感じているドキュメンタリー撮影を軸に、家族の物語を織り込む展開が素敵
あわせて読みたい
【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…
映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ
あわせて読みたい
【考察】映画『街の上で』(今泉力哉)が描く「男女の友情は成立する」的会話が超絶妙で素晴らしい(出…
映画『街の上で』(今泉力哉監督)は、「映画・ドラマ的会話」ではない「自然な会話」を可能な限り目指すスタンスが見事だった。「会話の無駄」がとにかく随所に散りばめられていて、そのことが作品のリアリティを圧倒的に押し上げていると言える。ある男女の”恋愛未満”の会話もとても素晴らしかった
あわせて読みたい
【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…
映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う
あわせて読みたい
【理解】「多様性を受け入れる」とか言ってるヤツ、映画『炎上する君』でも観て「何も見てない」って知…
西加奈子の同名小説を原作とした映画『炎上する君』(ふくだももこ監督)は、「多様性」という言葉を安易に使いがちな世の中を挑発するような作品だ。「見えない存在」を「過剰に装飾」しなければならない現実と、マジョリティが無意識的にマイノリティを「削る」リアルを描き出していく
あわせて読みたい
【映画】ストップモーションアニメ『マルセル 靴をはいた小さな貝』はシンプルでコミカルで面白い!
靴を履いた体長2.5センチの貝をコマ撮りで撮影したストップモーション映画『マルセル 靴をはいた小さな貝』は、フェイクドキュメンタリーの手法で描き出すリアリティ満載の作品だ。謎の生き物が人間用の住居で工夫を凝らしながら生活する日常を舞台にした、感情揺さぶる展開が素晴らしい
あわせて読みたい
【歴史】NIKEのエアジョーダン誕生秘話!映画『AIR/エア』が描くソニー・ヴァッカロの凄さ
ナイキがマイケル・ジョーダンと契約した時、ナイキは「バッシュ業界3位」であり、マイケル・ジョーダンも「ドラフト3位選手」だった。今からは信じられないだろう。映画『AIR/エア』は、「劣勢だったナイキが、いかにエアジョーダンを生み出したか」を描く、実話を基にした凄まじい物語だ
あわせて読みたい
【魅力】モンゴル映画『セールス・ガールの考現学』は、人生どうでもいい無気力女子の激変が面白い!
なかなか馴染みのないモンゴル映画ですが、『セールス・ガールの考現学』はメチャクチャ面白かったです!設定もキャラクターも物語の展開もとても変わっていて、日常を描き出す物語にも拘らず、「先の展開がまったく読めない」とも思わされました。主人公の「成長に至る過程」が見応えのある映画です
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』を観てくれ!現代の人間関係の教科書的作品を考…
映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』は、私にグサグサ突き刺さるとても素晴らしい映画だった。「ぬいぐるみに話しかける」という活動内容の大学サークルを舞台にした物語であり、「マイノリティ的マインド」を持つ人たちの辛さや葛藤を、「マジョリティ視点」を絶妙に織り交ぜて描き出す傑作について考察する
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『四畳半タイムマシンブルース』超面白い!森見登美彦も上田誠も超天才だな!
ヨーロッパ企画の演劇『サマータイムマシン・ブルース』の物語を、森見登美彦の『四畳半神話大系』の世界観で描いたアニメ映画『四畳半タイムマシンブルース』は、控えめに言って最高だった。ミニマム過ぎる設定・物語を突き詰め、さらにキャラクターが魅力的だと、これほど面白くなるのかというお手本のような傑作
あわせて読みたい
【感想】どんな話かわからない?難しい?ジブリ映画『君たちはどう生きるか』の考察・解説は必要?(監…
宮崎駿最新作であるジブリ映画『君たちはどう生きるか』は、宮崎アニメらしいファンタジックな要素を全開に詰め込みつつ、「生と死」「創造」についても考えさせる作品だ。さらに、「自分の頭の中から生み出されたものこそ『正解』」という、創造物と向き合う際の姿勢についても問うているように思う
あわせて読みたい
【感想】映画『すずめの戸締まり』(新海誠)は、東日本大震災後を生きる私達に「逃げ道」をくれる(松…
新海誠監督の『すずめの戸締まり』は、古代神話的な設定を現代のラブコメに組み込みながら、あまりに辛い現実を生きる人々に微かな「逃げ道」を指し示してくれる作品だと思う。テーマ自体は重いが、恋愛やコメディ要素とのバランスがとても良く、ロードムービー的な展開もとても魅力的
あわせて読みたい
【映画】今泉力哉監督『ちひろさん』(有村架純)が描く、「濃い寂しさ」が溶け合う素敵な関係性
今泉力哉監督、有村架純主演の映画『ちひろさん』は、その圧倒的な「寂しさの共有」がとても心地よい作品です。色んな「寂しさ」を抱えた様々な人と関わる、「元風俗嬢」であることを公言し海辺の町の弁当屋で働く「ちひろさん」からは、同じような「寂しさ」を抱える人を惹き付ける力強さが感じられるでしょう
あわせて読みたい
【あらすじ】アリ・アスター監督映画『ミッドサマー』は、気持ち悪さと怖さが詰まった超狂ホラーだった
「夏至の日に映画館で上映する」という企画でようやく観ることが叶った映画『ミッドサマー』は、「私がなんとなく想像していたのとはまるで異なる『ヤバさ』」に溢れる作品だった。いい知れぬ「狂気」が随所で描かれるが、同時に、「ある意味で合理的と言えなくもない」と感じさせられる怖さもある
あわせて読みたい
【実話】映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』(杏花主演)が描く、もの作りの絶望(と楽しさ)
実在したエロ雑誌編集部を舞台に、タブーも忖度もなく業界の内実を描き切る映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』は、「エロ雑誌」をテーマにしながら、「もの作りに懸ける想い」や「仕事への向き合い方」などがリアルに描かれる素敵な映画だった。とにかく、主役を演じた杏花が良い
あわせて読みたい
【天才】映画『リバー、流れないでよ』は、ヨーロッパ企画・上田誠によるタイムループの新発明だ
ヨーロッパ企画の上田誠が生み出した、タイムループものの新機軸映画『リバー、流れないでよ』は、「同じ2分間が繰り返される」という斬新すぎる物語。その設定だけ聞くと、「どう物語を展開させるんだ?」と感じるかもしれないが、あらゆる「制約」を押しのけて、とんでもない傑作に仕上がっている
あわせて読みたい
【感動】円井わん主演映画『MONDAYS』は、タイムループものの物語を革新する衝撃的に面白い作品だった
タイムループという古びた設定と、ほぼオフィスのみという舞台設定を駆使した、想像を遥かに超えて面白かった映画『MONDAYS』は、テンポよく進むドタバタコメディでありながら、同時に、思いがけず「感動」をも呼び起こす、竹林亮のフィクション初監督作品
あわせて読みたい
【あらすじ】大泉洋主演映画『月の満ち欠け』は「生まれ変わり」の可能性をリアルに描く超面白い作品
あなたは「生まれ変わり」を信じるだろうか? 私はまったく信じないが、その可能性を魅力的な要素を様々に散りばめて仄めかす映画『月の満ち欠け』を観れば、「生まれ変わり」の存在を信じていようがいまいが、「相手を想う気持ち」を強く抱く者たちの人間模様が素敵だと感じるだろう
あわせて読みたい
【驚異】映画『RRR』『バーフバリ』は「観るエナジードリンク」だ!これ程の作品にはなかなか出会えないぞ
2022年に劇場公開されるや、そのあまりの面白さから爆発的人気を博し、現在に至るまでロングラン上映が続いている『RRR』と、同監督作の『バーフバリ』は、大げさではなく「全人類にオススメ」と言える超絶的な傑作だ。まだ観ていない人がいるなら、是非観てほしい!
あわせて読みたい
【感想】映画『君が世界のはじまり』は、「伝わらない」「分かったフリをしたくない」の感情が濃密
「キラキラした青春学園モノ」かと思っていた映画『君が世界のはじまり』は、「そこはかとない鬱屈」に覆われた、とても私好みの映画だった。自分の決断だけではどうにもならない「現実」を前に、様々な葛藤渦巻く若者たちの「諦念」を丁寧に描き出す素晴らしい物語
あわせて読みたい
【感想】映画『朝が来る』が描く、「我が子を返して欲しい気持ち」を消せない特別養子縁組のリアル
「特別養子縁組」を軸に人々の葛藤を描く映画『朝が来る』は、決して「特別養子縁組」の話ではない。「『起こるだろうが、起こるはずがない』と思っていた状況」に直面せざるを得ない人々が、「すべての選択肢が不正解」という中でどんな決断を下すのかが問われる、非常に示唆に富む作品だ
あわせて読みたい
【感想】のん主演映画『私をくいとめて』から考える、「誰かと一緒にいられれば孤独じゃないのか」問題
のん(能年玲奈)が「おひとり様ライフ」を満喫する主人公を演じる映画『私をくいとめて』を観て、「孤独」について考えさせられた。「誰かと関わっていられれば孤独じゃない」という考えに私は賛同できないし、むしろ誰かと一緒にいる時の方がより強く孤独を感じることさえある
あわせて読みたい
【考察】映画『哀愁しんでれら』から、「正しい」より「間違ってはいない」を選んでしまう人生を考える
「シンデレラストーリー」の「その後」を残酷に描き出す映画『哀愁しんでれら』は、「幸せになりたい」という気持ちが結果として「幸せ」を遠ざけてしまう現実を描き出す。「正しい/間違ってはいない」「幸せ/不幸せではない」を区別せずに行動した結果としての悲惨な結末
あわせて読みたい
【感想】映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)の稲垣吾郎の役に超共感。「好きとは何か」が分からない人へ
映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)は、稲垣吾郎演じる主人公・市川茂巳が素晴らしかった。一般的には、彼の葛藤はまったく共感されないし、私もそのことは理解している。ただ私は、とにかく市川茂巳にもの凄く共感してしまった。「誰かを好きになること」に迷うすべての人に観てほしい
あわせて読みたい
【純愛】映画『ぼくのエリ』の衝撃。「生き延びるために必要なもの」を貪欲に求める狂気と悲哀、そして恋
名作と名高い映画『ぼくのエリ』は、「生き延びるために必要なもの」が「他者を滅ぼしてしまうこと」であるという絶望を抱えながら、それでも生きることを選ぶ者たちの葛藤が描かれる。「純愛」と呼んでいいのか悩んでしまう2人の関係性と、予想もつかない展開に、感動させられる
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
あわせて読みたい
【感想】殺人事件が決定打となった「GUCCI家の崩壊」の実話を描く映画『ハウス・オブ・グッチ』の衝撃
GUCCI創業家一族の1人が射殺された衝撃の実話を基にした映画『ハウス・オブ・グッチ』。既に創業家一族は誰一人関わっていないという世界的ブランドGUCCIに一体何が起こったのか? アダム・ドライバー、レディー・ガガの演技も見事なリドリー・スコット監督作
あわせて読みたい
【感想】綿矢りさ原作の映画『ひらいて』は、溢れる”狂気”を山田杏奈の”見た目”が絶妙に中和する
「片想いの相手には近づけないから、その恋人を”奪おう”」と考える主人公・木村愛の「狂気」を描く、綿矢りさ原作の映画『ひらいて』。木村愛を演じる山田杏奈の「顔」が、木村愛の狂気を絶妙に中和する見事な配役により、「狂気の境界線」をあっさり飛び越える木村愛がリアルに立ち上がる
あわせて読みたい
【感想】映画『先生、私の隣に座っていただけませんか?』は、「リアル」と「漫画」の境界の消失が絶妙
映画『先生、私の隣に座っていただけませんか?』は、「マンガ家夫婦の不倫」という設定を非常に上手く活かしながら、「何がホントで何かウソなのかはっきりしないドキドキ感」を味わわせてくれる作品だ。黒木華・柄本佑の演技も絶妙で、良い映画を観たなぁと感じました
あわせて読みたい
【喪失】家族とうまくいかない人、そして、家族に幻想を抱いてしまう人。家族ってなんてめんどくさいの…
「福島中央テレビ開局50周年記念作品」である映画『浜の朝日の嘘つきどもと』は、福島県に実在した映画館「朝日座」を舞台に、住民が抱く「希望(幻想)」が描かれる。震災・コロナによってありとあらゆるものが失われていく世の中で、私たちはどう生きるべきか
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ
私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。
あわせて読みたい
【矛盾】法律の”抜け穴”を衝く驚愕の小説。「ルールを通り抜けたものは善」という発想に潜む罠:『法廷…
完璧なルールは存在し得ない。だからこそ私たちは、矛盾を内包していると理解しながらルールを遵守する必要がある。「ルールを通り抜けたものは善」という”とりあえずの最善解”で社会を回している私たちに、『法廷遊戯』は「世界を支える土台の脆さ」を突きつける
あわせて読みたい
【考察】『うみべの女の子』が伝えたいことを全力で解説。「関係性の名前」を手放し、”裸”で対峙する勇敢さ
ともすれば「エロ本」としか思えない浅野いにおの原作マンガを、その空気感も含めて忠実に映像化した映画『うみべの女の子』。本作が一体何を伝えたかったのかを、必死に考察し全力で解説する。中学生がセックスから関係性をスタートさせることで、友達でも恋人でもない「名前の付かない関係性」となり、行き止まってしまう感じがリアル
あわせて読みたい
【日常】「何もかも虚しい」という心のスキマを「異性」や「お金」で安易に埋めてしまうのは危険だ:映…
「どこにでもいる普通の女性」が「横領」に手を染める映画『紙の月』は、「日常の積み重ねが非日常に接続している」ことを否応なしに実感させる。「主人公の女性は自分とは違う」と考えたい観客の「祈り」は通じない。「梅澤梨花の物語」は「私たちの物語」でもあるのだ
あわせて読みたい
【生きる】しんどい人生を宿命付けられた子どもはどう生きるべき?格差社会・いじめ・恋愛を詰め込んだ…
厳しい受験戦争、壮絶な格差社会、残忍ないじめ……中国の社会問題をこれでもかと詰め込み、重苦しさもありながら「ボーイ・ミーツ・ガール」の爽やかさも融合されている映画『少年の君』。辛い境遇の中で、「すべてが最悪な選択肢」と向き合う少年少女の姿に心打たれる
あわせて読みたい
【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事
「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である
あわせて読みたい
【世界観】映画『夜は短し歩けよ乙女』の”黒髪の乙女”は素敵だなぁ。ニヤニヤが止まらない素晴らしいアニメ
森見登美彦の原作も大好きな映画『夜は短し歩けよ乙女』は、「リアル」と「ファンタジー」の境界を絶妙に漂う世界観がとても好き。「黒髪の乙女」は、こんな人がいたら好きになっちゃうよなぁ、と感じる存在です。ずっとニヤニヤしながら観ていた、とても大好きな映画
あわせて読みたい
【考察】生きづらい性格は変わらないから仮面を被るしかないし、仮面を被るとリア充だと思われる:『勝…
「リア充感」が滲み出ているのに「生きづらさ」を感じてしまう人に、私はこれまでたくさん会ってきた。見た目では「生きづらさ」は伝わらない。24年間「リアル彼氏」なし、「脳内彼氏」との妄想の中に生き続ける主人公を描く映画『勝手にふるえてろ』から「こじらせ」を知る
あわせて読みたい
【あらすじ】濱口竜介監督『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」のみで成り立つ凄まじい映画。天才だと思う
「映画」というメディアを構成する要素は多々あるはずだが、濱口竜介監督作『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」だけで狂気・感動・爆笑を生み出してしまう驚異の作品だ。まったく異なる3話オムニバス作品で、どの話も「ずっと観ていられる」と感じるほど素敵だった
あわせて読みたい
【秘密】映画『ドライブ・イン・マンハッタン』は、「タクシー内の会話のみ」だが絶妙に良かった(主演…
映画『ドライブ・イン・マンハッタン』は、「タクシー内」というワンシチュエーションで「会話のみ」によって展開されるミニマムな要素しかない物語なのに、とにかく面白くて驚かされてしまった。運転手による「ゲスい会話」や女性客が抱えているのだろう「謎の秘密」などについて、色々と考えたくなるような深みのある物語である
あわせて読みたい
【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える
どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える
あわせて読みたい
【考察】映画『ジョーカー』で知る。孤立無援の環境にこそ”悪”は偏在すると。個人の問題ではない
「バットマン」シリーズを観たことがない人間が、予備知識ゼロで映画『ジョーカー』を鑑賞。「悪」は「環境」に偏在し、誰もが「悪」に足を踏み入れ得ると改めて実感させられた。「個人」を断罪するだけでは社会から「悪」を減らせない現実について改めて考える
あわせて読みたい
【漫画原作】映画『殺さない彼と死なない彼女』は「ステレオタイプな人物像」の化学反応が最高に面白い
パッと見の印象は「よくある学園モノ」でしかなかったので、『殺さない彼と死なない彼女』を観て驚かされた。ステレオタイプで記号的なキャラクターが、感情が無いとしか思えないロボット的な言動をする物語なのに、メチャクチャ面白かった。設定も展開も斬新で面白い
あわせて読みたい
【無知】映画『生理ちゃん』で理解した気になってはいけないが、男(私)にも苦労が伝わるコメディだ
男である私にはどうしても理解が及ばない領域ではあるが、女友達から「生理」の話を聞く機会があったり、映画『生理ちゃん』で視覚的に「生理」の辛さが示されることで、ちょっとは分かったつもりになっている。しかし男が「生理」を理解するのはやっぱり難しい
あわせて読みたい
【狂気】「当たり前の日常」は全然当たり前じゃない。記憶が喪われる中で”日常”を生きることのリアル:…
私たちは普段、「記憶が当たり前に継続していること」に疑問も驚きも感じないが、「短期記憶を継続できない」という記憶障害を抱える登場人物の日常を描き出す『静かな雨』は、「記憶こそが日常を生み出している」と突きつけ、「当たり前の日常は当たり前じゃない」と示唆する
あわせて読みたい
【あらすじ】天才とは「分かりやすい才能」ではない。前進するのに躊躇する暗闇で直進できる勇気のこと…
ピアノのコンクールを舞台に描く『蜜蜂と遠雷』は、「天才とは何か?」と問いかける。既存の「枠組み」をいとも簡単に越えていく者こそが「天才」だと私は思うが、「枠組み」を安易に設定することの是非についても刃を突きつける作品だ。小説と映画の感想を一緒に書く
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
あわせて読みたい
【難しい】映画『鳩の撃退法』をネタバレ全開で考察。よくわからない物語を超詳細に徹底解説していく
とても難しくわかりにくい映画『鳩の撃退法』についての考察をまとめていたら、1万7000字を超えてしまった。「東京編で起こったことはすべて事実」「富山編はすべてフィクションかもしれない」という前提に立ち、「津田伸一がこの小説を書いた動機」まで掘り下げて、実際に何が起こっていたのかを解説する(ちなみに、「実話」ではないよ)
あわせて読みたい
【解説】「小説のお約束」を悉く無視する『鳩の撃退法』を読む者は、「読者の椅子」を下りるしかない
佐藤正午『鳩の撃退法』は、小説家である主人公・津田が、”事実”をベースに、起こったかどうか分からない事柄を作家的想像力で埋める物語であり、「小説のお約束を逸脱しています」というアナウンスが作品内部から発せられるが故に、読者は「読者の椅子」を下りざるを得ない
あわせて読みたい
【再生】ヤクザの現実を切り取る映画『ヤクザと家族』から、我々が生きる社会の”今”を知る
「ヤクザ」を排除するだけでは「アンダーグラウンドの世界」は無くならないし、恐らく状況はより悪化しただけのはずだ。映画『ヤクザと家族』から、「悪は徹底的に叩きのめす」「悪じゃなければ何をしてもいい」という社会の風潮について考える。
あわせて読みたい
【感想】映画『窮鼠はチーズの夢を見る』を異性愛者の男性(私)はこう観た。原作も読んだ上での考察
私は「腐男子」というわけでは決してないのですが、周りにいる腐女子の方に教えを請いながら、多少BL作品に触れたことがあります。その中でもダントツに素晴らしかったのが、水城せとな『窮鼠はチーズの夢を見る』です。その映画と原作の感想、そして私なりの考察について書いていきます
あわせて読みたい
【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…
好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性
あわせて読みたい
【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…
誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【感想】努力では才能に勝てないのか?どうしても辿り着きたい地点まで迷いながらも突き進むために:『…
どうしても辿り着きたい場所があっても、そのあまりの遠さに目が眩んでしまうこともあるでしょう。そんな人に向けて、「才能がない」という言葉に逃げずに前進する勇気と、「仕事をする上で大事なスタンス」について『羊と鋼の森』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…
メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方
あわせて読みたい
【前進】誰とも価値観が合わない…。「普通」「当たり前」の中で生きることの難しさと踏み出し方:『出会…
生きていると、「常識的な考え方」に囚われたり、「普通」「当たり前」を無自覚で強要してくる人に出会ったりします。そういう価値観に合わせられない時、自分が間違っている、劣っていると感じがちですが、そういう中で一歩踏み出す勇気を得るための考え方です
ルシルナ
苦しい・しんどい【本・映画の感想】 | ルシルナ
生きていると、しんどい・悲しいと感じることも多いでしょう。私も、世の中の「当たり前」に馴染めなかったり、みんなが普通にできることが上手くやれずに苦しい思いをする…
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…















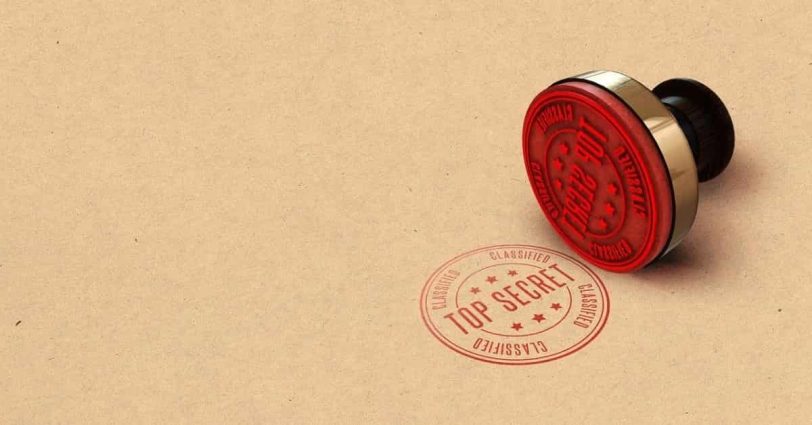
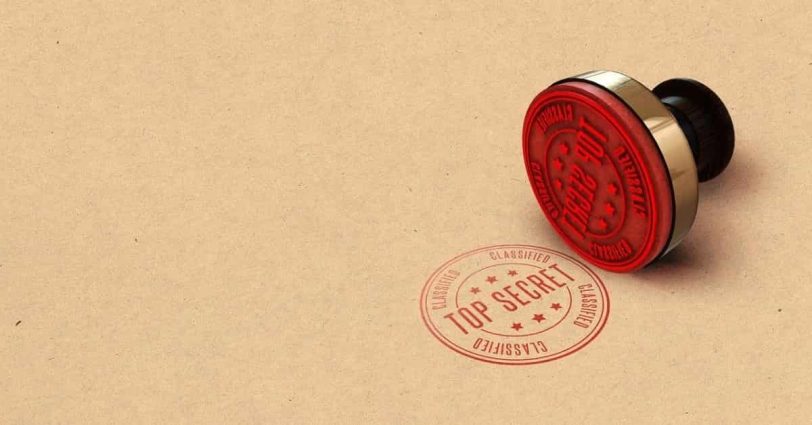














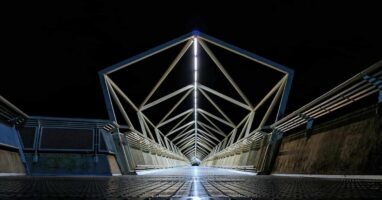
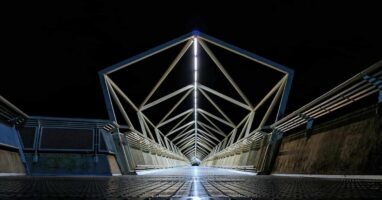












































































































































































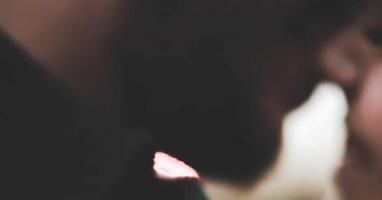
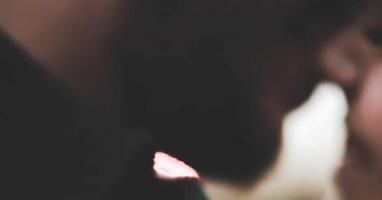




































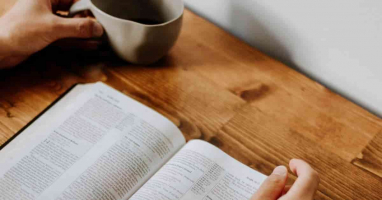
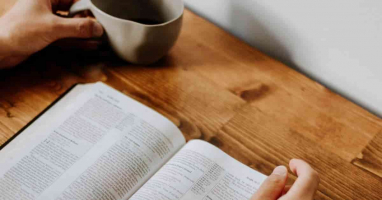






























コメント