目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
監督:クリストファー・ザラ, クリエイター:3Pas Studios, プロデュース:ジョシュア・デイヴィス, Writer:クリストファー・ザラ, 出演:エウヘニオ・デルベス, 出演:ダニエル・ハダッド, 出演:ジェニファー・トレホ, 出演:ミア・フェルナンダ・ソリス, 出演:ダニーロ・グアルディオラ
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
今どこで観れるのか?
公式HPの劇場情報をご覧ください
この記事の3つの要点
- 「6年生の半数が卒業出来ないかもしれない学校」に主人公が赴任してすぐ、全国テストで驚異の成績を叩き出し、全国1位も輩出したという信じがたい物語
- しかし主人公は最後まで「試験対策などしない」と言い張り、「考えさせる授業」を行い続けた
- 他の教師の賛同が得られない中でも孤軍奮闘を続ける主人公の努力や葛藤に心打たれる
教師だけではなく、親や今まさに教育を受けている子どもたち自身も観るべき良作だと思う
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
メキシコ最底辺の小学校で”あり得ない”成果を挙げた教師の孤軍奮闘を描く映画『型破りな教室』は、「実話を基にしている」という事実にとにかく驚かされる
実に素晴らしい映画だった。正直、ちょっと泣いてしまうぐらいに感動させられたし、何よりも、これが実話だというのが本当に凄まじい。「教育って何だっけ?」と改めて考える良いきっかけにも素敵な参考にもなる作品であり、是非多くの人に観てほしいなと思う。
あわせて読みたい
【衝撃】「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』は、「義務教育」の概念を破壊する…
驚きの教育方針を有する私立小学校「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』と、「日本の教育にはほとんどルールが無い」ことを示す特徴的な公立校を取り上げる映画『夢見る公立校長先生』を観ると、教育に対する印象が変わる。「改革を妨げる保護者」にならないためにも観るべき作品だ
本作ではラストで、アインシュタインによるよく知られた名言が表示される。
私の学習を妨げた唯一のものは、私が受けた教育である。

本作の主人公であるフアレスは、まさにそうならないための「教育」を実践しようとした。そして、見事それをやり遂げたのである。教育を与える側も受ける側も共に知っておくべき知見に溢れた作品だと言っていいし、アインシュタインの名言と共にフアレスの奮闘も記憶されるべきだと思う。
主人公である小学校教師フアレスが叩き出したとんでもない成果
それではまず、本作の主人公である小学校教師フアレスが一体どんな成果を成し遂げたのかについて、数字を踏まえつつ確認していくことにしよう。
あわせて読みたい
【発見】映画『小学校~それは小さな社会~』(山崎エマ)が映し出すのは、我々には日常すぎる日常だ
映画『小学校~それは小さな社会~』は、ごく一般的な公立小学校に密着し、日本で生まれ育った人間には「当たり前」にしか思えない日常を切り取った作品なのだが、そんな映画が諸外国で大いに評価されているという。「TOKKATSU」という「日本式教育」が注目されているらしく、私たちの「当たり前」が違和感だらけに見えているのだそうだ
彼が教師として赴任したのは、アメリカとの国境付近の町マタモロスにあるホセ・ウルビナ・ロペス小学校である。メキシコには「ENLACE」と呼ばれる全国共通テストが存在するのだが、この小学校の平均点は毎年最低レベルだった。しかしそれも仕方ないだろう。なにせ町の治安は著しく悪く、銃撃戦が日常茶飯事なのだ。もちろん貧しい者も多く、児童の1人は父親と2人でゴミ山に暮らし、ゴミを拾って生計を立てているほどである。なんと、「6年生の半数以上が卒業できないかもしれない」というレベルなのだ。
そんな学校だから、もちろん教師も赴任したがらない。恐らく公立校であり、だから公立校の教師であれば誰もがこの学校に送られる可能性があるのだが、なんと教師たちの間でこの小学校は「罰の学校」と呼ばれている。もし赴任が決まったら「罰」みたいなものというわけだ。さらにこの小学校の教師たちは、「生きてりゃ採用(つまり「誰でも採用される」ということ)」なんて冗談とも言い切れない冗談を言うほどである。
さて、本作では実際の試験の結果が表示されるのだが、フアレスが赴任する前年の「ENLACE」の成績は、「数学:55%合格 国語69%合格」だった。細かな仕組みは分からないものの、恐らく「設定された『合格点』を超えた児童が何%いるか」という数字なのだと思う。そしてフアレスが赴任した年はなんと、「数学:93%合格 国語:97.5%合格」(恐らくこれは学校全体ではなく、フアレスのクラスの成績だと思われる)という、尋常ではない伸びを示したのである。さらに、数学の成績で全国順位0.1%以内に入った児童がなんと10人もいたというのだ。
あわせて読みたい
【思考】「”考える”とはどういうことか」を”考える”のは難しい。だからこの1冊をガイドに”考えて”みよう…
私たちは普段、当たり前のように「考える」ことをしている。しかし、それがどんな行為で、どのように行っているのかを、きちんと捉えて説明することは難しい。「はじめて考えるときのように」は、横書き・イラスト付きの平易な文章で、「考えるという行為」の本質に迫り、上達のために必要な要素を伝える
しかし驚くのはまだ早い。なんと、この試験で全国1位を獲得したのがフアレスのクラスの生徒だったのだ。映画の最後に表示された字幕によれば、この快挙は国中で大きな話題となり、家が贈られた(恐らく国から)という。そりゃあみんなたまげただろう。なにせ、前年まで最底辺だった学校の平均点が一気に上がり、さらに全国1位の生徒まで出したのだから。
これが、「フアレスが叩き出した成果」である。
しかしあくまでもこれは結果論でしかない。というのも、フアレスは試験直前まで「ENLACE対策のために勉強するなんて馬鹿げている」という姿勢を崩さなかったのだ。フアレスの学校では(あるいはメキシコの学校はどこもそうかもしれないが)、「ENLACEで良い点数を取るための試験対策」に多くの時間を費やす。恐らく、補助金やら何やらに関係しているからだろう。しかしフアレスは「ENLACEのための勉強」など一切行わなかった。あくまでも「子どもたちの未来のために必要」だと信じる教育をやり続けただけなのだ。
それはざっくり言えば「『自分の頭で考える力』を養うための教育」であり、だからフアレスの教育が結果としてENLACEにも良い影響を与えたことは間違いないと思う。ただ、「全国1位」はフアレスにとって超が付くほどのラッキーだっただろう。ムチャクチャ頭の良い児童がたまたまクラスにいただけだからだ。ただし、その児童には色々あって、昔なら「ENLACE」を受けていなかったはずなので、だから「フアレスのお陰」であることは間違いない。というか実際には、フアレスはその児童に対してより深く関わっているわけで、その辺りのことは是非映画を観てほしいなと思う。
あわせて読みたい
【変人】学校教育が担うべき役割は?子供の才能を伸ばすために「異質な人」とどう出会うべきか?:『飛…
高校の美術教師からアーティストとして活動するようになった著者は、教育の現場に「余白(スキマ)」が減っていると指摘する。『飛び立つスキマの設計学』をベースに、子どもたちが置かれている現状と、教育が成すべき役割について確認する。
何にせよ、結果が出れば注目されるし信頼もされる。個人的にはフアレスの教育方針には大賛成なので、ラッキーだろうが何だろうが、世間をざわつかせるほどの結果を出したことによってフアレスの教育がやりやすくなったのであれば、それは素晴らしいことだと思う。
主人公フアレスは一体どんな授業をしていたのか?

フアレスは試験の直前、自分のクラスの児童たちに次のような言葉をかけていた。
私は君たちに十分教えることが出来ていないかもしれない。しかし、君たちなら大丈夫だ。これまでずっと「初めて知る問題」に取り組み続けてきた君たちなら、初見の問題であっても、考えれば絶対に解けるはずだ。
先述した通り、彼が徹底して行っていたのは「児童に自ら考えさせること」である。というわけで、例として映画冒頭で提示される「授業」の説明をしようと思う。
あわせて読みたい
【肯定】社会不適合者こそ非凡。学校・世の中に馴染めなかった異才たちの過去から”才能”の本質を知る:…
「みんなと同じ」に馴染めないと「社会不適合」と判断され、排除されてしまうことが多いでしょう。しかし『非属の才能』では、「どこにも属せない感覚」にこそ才能の源泉があると主張します。常識に違和感を覚えてしまう人を救う本から、同調圧力に屈しない生き方を学ぶ
フアレスはまず、児童が来る前の教室から机と椅子を外に出し、広い空間を作った。そして、やってきた児童たちにこんな風に問うのである。
ここは海で、船が転覆した。救命ボートは5つ、乗組員は23人、さぁどうやって分かれて乗る?
さて、映画冒頭のこのシーンはフアレスが赴任してきて初めての授業であり、だから児童たちの反応は薄かった。というか、何をすればいいのか分からなかったのだと思う。そして、そうなってしまうのも仕方ないだろう。そもそもこの学校の教師は、児童を「管理すべき存在」としか見ておらず、フアレスは同僚の教師から「弱みを見せたらダメだ。誰がボスか分からせろ」みたいな”アドバイス”をもらったほどだ。また教頭に当たるような人なのだろう、ある教師から「教室に机が無いと誰が偉いか分からない」みたいにして暗に「机と椅子を外に出すなよ」と言われてしまったのである。そんな学校にいれば「自主性」など育つはずもないし、フアレスの「授業」に戸惑うのも当然だろう。
あわせて読みたい
【抽象】「思考力がない」と嘆く人に。研究者で小説家の森博嗣が語る「客観的に考える」ために大事なこ…
世の中にはあまりに「具体的な情報」が溢れているために、「客観的、抽象的な思考」をする機会が少ない。そんな時代に、いかに思考力を育てていくべきか。森博嗣が『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』を通じて伝える「情報との接し方」「頭の使い方」
しかし、そんな「授業」を何度か続けていると、児童たちも次第に慣れてくる。そしてある日、同じようにして船の転覆の実演をしているところに校長が通りかかった。見慣れない光景を目にした校長が教室に入ってくると、フアレスは「新たな遭難者だ!」と声を掛け、児童たちを焚きつける。彼らはどうにか校長をボートに載せようとするのだが、ある児童が咄嗟に「ダメダメ!ボートが沈んじゃう!」と口にした。校長はかなり太っているのだ。
そのタイミングでフアレスは、「お、今良い疑問が出てきたぞ。『校長が乗るとボートが沈む』と誰か言ったな。じゃあそもそも、どうして船は浮かんでいられるんだ?」と問うのである。
そこからは「船が浮かぶ問題」について、フアレスが先導する形であれこれ議論を重ねるのだが、しばらくして児童たちが活発に意見を出し合う様子を見たフアレスは、「俺は必要ないようだな」と言って教室を出てしまう。「ちょっと飲み物を買ってくるから、30分後ぐらいに戻るよ」なんて言いながら。しかし内心はとても不安だった。やはりフアレスは、「子どもたちだけでちゃんと議論になっているか」が心配だったのだ。彼は教室に戻るべきか何度も逡巡しながら、しかし結局、子どもたちを信じて戻らなかった。
あわせて読みたい
【発想力】「集中力が続かない」と悩むことはない。「集中しない思考」こそAI時代に必要だ:『集中力は…
『「集中力がない」と悩んでいる人は多いかもしれません。しかし本書では、「集中力は、思ってるほど素晴らしいものじゃない」と主張します。『集中力はいらない』をベースに、「分散思考」の重要性と、「発想」を得るための「情報の加工」を学ぶ
そして、その間にフアレスは、校長室へと向かう。恐らくだが、フアレス自身も「船が浮かぶ問題」についてちゃんと答えられなかったのだと思う。そこで、学校で唯一のパソコンがある校長室へと行き、ネットで答えを調べようとしたのである。しかし結局、校長はパソコンを使わせてくれなかった。そんな30分を過ごした後で教室に戻ってみると、素晴らしいことに班ごとに議論が白熱し、お互いにプレゼンまでするほどになっていたのである。子どもたちを信じてすべて任せたのが正解だったというわけだ。

とはいえ、「自分で考えさせる」という教育方針には「そうせざるを得なかった」みたいな側面もあったと思う。教育環境があまりにも酷かったのだ。学校内に図書館はあるものの、蔵書はスカスカで百科事典は巻抜けしている。さらに、「哲学書が読みたい」と口にする児童に対し、「あなたの年齢ではまだ読む必要なんかないでしょう」と司書が言ったりもするのだ。最悪すぎるだろう。さらに、「パソコン教室」は存在するものの、設置してから僅か2ヶ月ですべてのパソコンが盗まれてしまい、そのまま4年間放置されている。また、本作の舞台は2011年であり、メキシコではまだそこまでスマホは普及していなかったようだ。校長はスマホを持っていたが、フアレスも児童の多くも持っていなかったと思う。このように、とにかく「情報を得るのが難しい環境」だったのである。そのため、「思考のみによって『正しさ』を導き出そう」という教育方針にせざるを得なかったという側面もあるんじゃないかという気がした。
そしてそのお陰で、子どもたちは飛躍的に成長していったのだ。
あわせて読みたい
【思考】『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、中学生と猫の対話から「自分の頭で考える」を学べる良書
「中学生の翔太」と「猫のインサイト」が「答えの出ない問い」について対話する『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、「哲学」の違う側面を見せてくれる。過去の哲学者・思想家の考えを知ることが「哲学」なのではなく、「自分の頭で考えること」こそ「哲学」の本質だと理解する
「教育」は本当に大事だと思うし、もっと社会全体で考えるべき課題だとも感じた
こういう「『考える力』を養う」的な話で真っ先に思い浮かぶのが、以前読んだ『女子高生アイドルは、なぜ東大生に知力で勝てたのか?』(村松秀/講談社)である。かつてNHKで『すイエんサー』という番組が放送されており(私は見たことがない)、そのプロデューサーが書いた本だ。
著:村松秀, イラスト:五月女ケイ子
¥434 (2025/07/11 06:57時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
『すイエんサー』というのは、決して知力に秀でているわけではない女子高生アイドルを集め、彼女たちにある「お題」を提示し、そして「考え続けること」によって「答え」に辿り着くまでの過程を映し出す番組である。そして番組では、そんな女子高生アイドルたちが大学生と対決するという展開にまで発展し、なんと「与えられたお題でより優れた知見を導き出す」という知力勝負で有名大学の学生に勝利を収めるほど成長していくのである。
このエピソードだけを以って「知識より思考力の方が大事だ」と主張するのは乱暴だが、ただやはり、多くの人が「知識を覚えるだけじゃダメ」みたいな感覚を持っているんじゃないかとも思う。個人的には、「知識も大事だ」と言っておきたいところなのだが(「思考力」を正しく駆使するには「知識」が必要になるはずだ)、いずれにせよ、より重要なのは「思考力」の方だと考えている。メキシコに今も「ENLACE」が存在するのかは知らないが、「知識を持っているかどうかを測るテスト」など、本当に無意味だと私は思う。
とはいえ私は、「試験一発勝負で大学の合否が決まる」という日本みたいな仕組みは良いと思っている(出自や家庭環境などに“あまり”左右されずに、努力で差が付きやすいから)。そして、社会もそれを求めているのなら、まだまだ「知識を詰め込む教育」が続くのだろうが、しかし少しずつ変わってはいくだろう。例えば私は、ここ10年ぐらい新聞に掲載されているセンター試験(共通テスト)を解いているのだが、2~3年前ぐらいから、英語がすべて長文読解になったことに驚かされた。私がセンター試験を受けた頃は、「発音問題」や「単語を並び替えて長文を組み立てる問題」などがあったのだが、今はそういうものは一切なく、最初から最後まで長文読解のみなのである。これははっきりと、「知識を問うことを止めた」と受け取れる事例だと思う。そしてそういう方向性は、これからますます鮮明になっていくんじゃないだろうか。
あわせて読みたい
【能力】激変する未来で「必要とされる人」になるためのスキルや考え方を落合陽一に学ぶ:『働き方5.0』
AIが台頭する未来で生き残るのは難しい……。落合陽一『働き方5.0~これからの世界をつくる仲間たちへ~』はそう思わされる一冊で、本書は正直、未来を前向きに諦めるために読んでもいい。未来を担う若者に何を教え、どう教育すべきかの参考にもなる一冊。
だからこそ、本作で示されているような教育は非常に重要になっていくはずだと思っている。
さて、本作には印象的なシーンが色々あったのだが、個人的に一番好きだったのは、フアレスが同僚の教師と話している場面でのやり取りだ。2人はお互いの教育方針がまったく違うことを会話から理解するのだが、その後でフアレスがその同僚教師に、「教師が子どもに言える最強の言葉って何か知ってるか?」と問う。これはとても面白い問いなので、皆さんも少し考えてみてほしい。あなたがもし教師だとしたら、何と答えるだろうか?
こう問われた同僚教師は、「知らない」と答えた。この「知らない」は「考える気もない」みたいなニュアンスを含むものであり、「お前の相手なんかしてられるか」という雰囲気すら感じさせるものだったのだが、面白いことにフアレスはこの同僚教師の返答に「正解」と返したのだ。意味が分かるだろうか? つまり、「『知らない』こそ、教師が子どもに言える最強の言葉である」というわけだ。「教える側が『知らない』と口にする勇気を持つこと」こそがこれからの「教育」に必要だと説いているわけで、これはとても印象的なやり取りだった。
あわせて読みたい
【異端】子育ては「期待しない」「普通から外れさせる」が大事。”劇薬”のような父親の教育論:『オーマ…
どんな親でも、子どもを幸せにしてあげたい、と考えるでしょう。しかしそのために、過保護になりすぎてしまっている、ということもあるかもしれません。『オーマイ・ゴッドファーザー』をベースに、子どもを豊かに、力強く生きさせるための”劇薬”を学ぶ
フアレスが本当にそう思っていることは、「ENLACE」の直前に児童たちに声がけしたシーンからも理解できるだろう。彼は「僕は君たちからたくさんのことを学んだ」と言っていたのだ。また彼は児童たちに、様々な機会を捉えては「君が学んだことを他の人にも共有してくれ。それこそが学びになるから」とも話していた。「教師は『知っている人』、児童は『知らない人』」みたいに分けるのではなく、「『知っている人』が『知らない人』に教えればいいよね」というスタンスなのであり、その上でフアレス自身も積極的に「知らない人」になれるというわけだ。これは教師だけではなく、子育て中の親の振る舞いとしても重要ではないかと感じさせられた。

しかし、本作を観て改めて思ったのは、「良い教師に出会えるかどうかで人生は結構大きく変わるよな」ということだ。大人になれば「誰から学ぶか」を自ら選べる機会も多いだろうが、子どもの頃はなかなかそうはいかない。特に、「お受験」と無縁であれば、小中学校は住んでいる地域でほぼ決まってしまうはずだ。なので、良い教師(というか「自分と合う教師」)と出会えるかは、本当に運でしかない。
ただ、「教師・教育全体の質を高める」ことが出来れば、良い教師に出会える確率は高まると言えるだろう。そして、「教師・教育全体の質を高める」ことは社会全体の課題であると私は思う。「親ガチャ」は本当に運以外の何物でもないが、「教師ガチャ」に関しては、社会全体で頑張れば「ハズレの可能性」を低くすることは可能なはずだ。私は別に結婚していないし子どももいないが、それでも、「国のお金」はもっと子どもに注ぎ込むべきだと思っている。フアレスみたいな教師がそこかしこにいれば、それだけで「教育」は豊かになるだろうし、教育環境全体の底上げにも寄与するだろう。
あわせて読みたい
【社会】学生が勉強しないのは、若者が働かないのは何故か?教育現場からの悲鳴と知見を内田樹が解説:…
教育現場では、「子どもたちが学びから逃走する」「学ばないことを誇らしく思う」という、それまでには考えられなかった振る舞いが目立っている。内田樹は『下流志向』の中で、その原因を「等価交換」だと指摘。「学ばないための努力をする」という発想の根幹にある理屈を解き明かす
そういう社会を我々が作っていかなければならないのだと、改めて実感させられる作品でもあった。
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
監督:クリストファー・ザラ, クリエイター:3Pas Studios, プロデュース:ジョシュア・デイヴィス, Writer:クリストファー・ザラ, 出演:エウヘニオ・デルベス, 出演:ダニエル・ハダッド, 出演:ジェニファー・トレホ, 出演:ミア・フェルナンダ・ソリス, 出演:ダニーロ・グアルディオラ
 ポチップ
ポチップ
最後に
この記事では「教育」についてあーだこーだ書いただけで、映画の内容にはあまり触れなかったが、エンタメ的な意味でも楽しく観られる作品ではないかと思う。実話を基にしているとはちょっと信じられないようなストーリーと、最底辺の学校で孤軍奮闘するフアレスの闘いぶりを、是非体感してほしい。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【壮絶】映画『フロントライン』は「コロナパンデミックの発端」におけるDMATの奮闘をリアルに描く(監…
映画『フロントライン』は、ド級の役者が集ったド級のエンタメ作品でありながら、「フィクションっぽさ」が非常に薄い映画でもあり、「起こった出来事をリアルに描く」という制作陣の覚悟が感じられた。マスコミ報道を通じて知ったつもりになっている「事実」が覆される内容で、あの時の混乱を知るすべての人が観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【虚構】映画『シアトリカル』が追う唐十郎と劇団唐組の狂気。芝居に生きる者たちの”リアル”とは?
映画『シアトリカル』は、異端児・唐十郎と、彼が主宰する「劇団唐組」に密着するドキュメンタリー映画である。「普段から唐十郎を演じている」らしい唐十郎は、「ややこしさ」と「分かりやすさ」をないまぜにした実に奇妙な存在だった。「演劇」や「演じること」に己を捧げた「狂気を孕む者たち」の生き様が切り取られた作品だ
あわせて読みたい
【実話】特殊詐欺被害者が警察より先に犯人を追い詰める映画『市民捜査官ドッキ』は他人事じゃない
映画『市民捜査官ドッキ』は、実際に起こった詐欺事件を基にした映画なのですが、とても実話とは思えない驚きの状況が描かれます。なにせ、「警察に見放された詐欺被害者が、自ら詐欺グループの拠点を探し当てる」のです。テーマはシリアスですが、全体的にはコメディタッチで展開される作品で、とにかく楽しく見られるでしょう
あわせて読みたい
【信念】アフガニスタンに中村哲あり。映画『荒野に希望の灯をともす』が描く規格外の功績、生き方
映画『荒野に希望の灯をともす』は、アフガニスタンの支援に生涯を捧げ、個人で実現するなど不可能だと思われた用水路建設によって砂漠を緑地化してしまった中村哲を追うドキュメンタリー映画だ。2019年に凶弾に倒れるまで最前線で人々を先導し続けてきたその圧倒的な存在感に、「彼なき世界で何をすべきか」と考えさせられる
あわせて読みたい
【日々】映画『なみのおと』は、東日本大震災を語る人々の対話を”あり得ない”アングルから撮る(監督:…
映画『なみのおと』は、「東日本大震災の被災者が当時を振り返って対話をする」という内容そのものももちろん興味深いのだが、カメラをどう配置しているのかが分からない、ドキュメンタリー映画としては”あり得ない”映像であることにも驚かされた。また、悲惨な経験を軽妙に語る者たちの雰囲気も印象的な作品である
あわせて読みたい
【包容】映画『違国日記』を観て思う。「他者との接し方」が皆こうだったらもっと平和なはずだって(主…
映画『違国日記』は、人見知りの小説家・高代槙生が両親を亡くした姪・朝を引き取り一緒に暮らすところから始まる物語で、槙生と朝を中心とした様々な人間関係が絶妙に描かれている作品でした。人付き合いが苦手ながら、15歳という繊細な存在を壊さないように、でも腫れ物みたいには扱わないように慎重になる槙生のスタンスが素敵です
あわせて読みたい
【実話】不可能を成し遂げた男を描く映画『愛を耕すひと』は、愛を知るための長い旅路の物語でもある(…
映画『愛を耕すひと』は、18世紀のデンマークを舞台に、「不可能」とまで言われた「ユトランド半島の開拓」を成し遂げたルドヴィ・ケーレンを描き出す物語だ。とはいえ「偉人の伝記」のような内容ではない。嫌がらせをしてくる貴族や、迷信を信じる者たちからの不信感などと闘いながら「愛」を知っていく、実に印象的な物語である
あわせて読みたい
【発見】映画『小学校~それは小さな社会~』(山崎エマ)が映し出すのは、我々には日常すぎる日常だ
映画『小学校~それは小さな社会~』は、ごく一般的な公立小学校に密着し、日本で生まれ育った人間には「当たり前」にしか思えない日常を切り取った作品なのだが、そんな映画が諸外国で大いに評価されているという。「TOKKATSU」という「日本式教育」が注目されているらしく、私たちの「当たり前」が違和感だらけに見えているのだそうだ
あわせて読みたい
【感動】映画『ぼくとパパ、約束の週末』は「自閉症への理解が深まる」という点で実に興味深かった
映画『ぼくとパパ、約束の週末』は「心温まる物語」であり、一般的にはそういう作品として評価されているはずだが、個人的には「『自閉症』への解像度が高まる」という意味でも興味深かった。「ルールは厳密に守るが、ルール同士が矛盾していて袋小路に陥ってしまう」という困難さが実に分かりやすく描かれている
あわせて読みたい
【日常】映画『大きな家』(竹林亮)は、児童養護施設で「家族」と「血縁」の違いや難しさに直面する
児童養護施設に長期密着した映画『大きな家』は、映画『14歳の栞』で中学2年生をフラットに撮り切った竹林亮が監督を務めたドキュメンタリーである。子どもたちの過去に焦点を当てるのではなく、「児童養護施設の日常風景」として彼らを捉えるスタンスで、その上でさらに「家族のあり方」に対する子どもたちの認識が掘り下げられる
あわせて読みたい
【映画】ディオールのデザイナーだった天才ジョン・ガリアーノが差別発言で破滅した人生を語る:映画『…
何者なのかまったく知らない状態で観たドキュメンタリー映画『ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナー』は、差別発言によって失墜しすべてを失った天才デザイナーの凄まじい来歴が描かれる作品だ。実に複雑で興味深い存在だったし、その波乱の人生は、私のようなファッションに疎い人間でも面白く感じられると思う
あわせて読みたい
【実話】株仲買人が「イギリスのシンドラー」に。映画『ONE LIFE』が描くユダヤ難民救出(主演:アンソ…
実話を基にした映画『ONE LIFE 奇跡が繋いだ6000の命』は、「イギリスに住むニコラス・ウィントンがチェコのユダヤ人難民を救う」という話であり、仲間と共に669名も救助した知られざる偉業が扱われている。多くの人に知られるべき歴史だと思うし、また、主演を務めたアンソニー・ホプキンスの演技にも圧倒されてしまった
あわせて読みたい
【現在】ウーマンラッシュアワー村本大輔がテレビから消えた理由と彼の”優しさ”を描く映画:『アイアム…
「テレビから消えた」と言われるウーマンラッシュアワー・村本大輔に密着する映画『アイアム・ア・コメディアン』は、彼に対してさほど関心を抱いていない人でも面白く観られるドキュメンタリー映画だと思う。自身の存在意義を「拡声器」のように捉え、様々な社会問題を「お笑い」で発信し続ける姿には、静かな感動さえ抱かされるだろう
あわせて読みたい
【あらすじ】有村架純が保護司を演じた映画『前科者』が抉る、罪を犯した者を待つ「更生」という現実
映画『前科者』は、仮釈放中の元受刑者の更生を手助けするボランティアである「保護司」を中心に据えることで、「元犯罪者をどう受け入れるべきか」「保護司としての葛藤」などを絶妙に描き出す作品。個別の事件への処罰感情はともかく、「社会全体としていかに犯罪を減らしていくか」という観点を忘れるべきではないと私は思っている
あわせて読みたい
【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…
映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
あわせて読みたい
【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…
映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である
あわせて読みたい
【魅惑】マツコも絶賛の“日本人初のパリコレトップモデル”山口小夜子のメイクの凄さや素顔を描く映画:…
日本人初のパリコレトップモデルである山口小夜子と親交があった監督が紡ぐ映画『氷の花火 山口小夜子』は、未だ謎に包まれているその人生の一端を垣間見せてくれる作品だ。彼女を知る様々な人の記憶と、彼女を敬愛する多くの人の想いがより合って、一時代を築いた凄まじい女性の姿が浮かび上がってくる
あわせて読みたい
【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた
『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる
あわせて読みたい
【現実】我々が食べてる魚は奴隷船が獲ったもの?映画『ゴースト・フリート』が描く驚くべき漁業の問題
私たちは、「奴隷」が獲った魚を食べているのかもしれない。映画『ゴースト・フリート』が描くのは、「拉致され、数十年も遠洋船上に隔離されながら漁をさせられている奴隷」の存在だ。本作は、その信じがたい現実に挑む女性活動家を追うドキュメンタリー映画であり、まさに世界が関心を持つべき問題だと思う
あわせて読みたい
【未知】コーダに密着した映画『私だけ聴こえる』は、ろう者と聴者の狭間で居場所がない苦悩を映し出す
あなたは「コーダ」と呼ばれる存在を知っているだろうか?「耳の聴こえない親を持つ、耳が聴こえる子ども」のことであり、映画『私だけ聴こえる』は、まさにそんなコーダが置かれた状況を描くドキュメンタリー映画だ。自身は障害者ではないのに大変な苦労を強いられている現状が理解できる作品
あわせて読みたい
【衝撃】「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』は、「義務教育」の概念を破壊する…
驚きの教育方針を有する私立小学校「きのくに子どもの村学園」に密着する映画『夢見る小学校』と、「日本の教育にはほとんどルールが無い」ことを示す特徴的な公立校を取り上げる映画『夢見る公立校長先生』を観ると、教育に対する印象が変わる。「改革を妨げる保護者」にならないためにも観るべき作品だ
あわせて読みたい
【天才】タランティーノ作品ほぼ未見で観た面白ドキュメンタリー。映画に愛された映画オタクのリアル
『パルプ・フィクション』しか監督作品を観たことがないまま、本作『クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男』を観たが、とても面白いドキュメンタリー映画だった。とにかく「撮影現場に笑いが絶えない」ようで、そんな魅力的なモノづくりに関わる者たちの証言から、天才の姿が浮かび上がる
あわせて読みたい
【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘
重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
あわせて読みたい
【実話】福島智とその家族を描く映画『桜色の風が咲く』から、指点字誕生秘話と全盲ろうの絶望を知る
「目が見えず、耳も聞こえないのに大学に進学し、後に東京大学の教授になった」という、世界レベルの偉業を成し遂げた福島智。そんな彼の試練に満ちた生い立ちを描く映画『桜色の風が咲く』は、本人の葛藤や努力もさることながら、母親の凄まじい献身の物語でもある
あわせて読みたい
【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…
「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか
あわせて読みたい
【感想】実業之日本社『少女の友』をモデルに伊吹有喜『彼方の友へ』が描く、出版に懸ける戦時下の人々
実業之日本社の伝説の少女雑誌「少女の友」をモデルに、戦時下で出版に懸ける人々を描く『彼方の友へ』(伊吹有喜)。「戦争そのもの」を描くのではなく、「『日常』を喪失させるもの」として「戦争」を描く小説であり、どうしても遠い存在に感じてしまう「戦争」の捉え方が変わる1冊
あわせて読みたい
【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…
「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る
あわせて読みたい
【挑戦】手足の指を失いながら、今なお挑戦し続ける世界的クライマー山野井泰史の”現在”を描く映画:『…
世界的クライマーとして知られる山野井泰史。手足の指を10本も失いながら、未だに世界のトップをひた走る男の「伝説的偉業」と「現在」を映し出すドキュメンタリー映画『人生クライマー』には、小学生の頃から山のことしか考えてこなかった男のヤバい人生が凝縮されている
あわせて読みたい
【苦しい】「恋愛したくないし、興味ない」と気づいた女性が抉る、想像力が足りない社会の「暴力性」:…
「実は私は、恋愛的な関係を求めているわけじゃないかもしれない」と気づいた著者ムラタエリコが、自身の日常や専門学校でも学んだ写真との関わりを基に、「自分に相応しい関係性」や「社会の暴力性」について思考するエッセイ。久々に心にズバズバ刺さった、私にはとても刺激的な1冊だった。
あわせて読みたい
【伝説】やり投げ選手・溝口和洋は「思考力」が凄まじかった!「幻の世界記録」など数々の逸話を残した…
世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的なトレーニングと、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界記録」を叩き出した天才の伝説と実像
あわせて読みたい
【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…
数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊
あわせて読みたい
【価値】どうせ世の中つまらない。「レンタルなんもしない人」の本でお金・仕事・人間関係でも考えよう…
「0円で何もしない」をコンセプトに始まった「レンタルなんもしない人」という活動は、それまで見えにくかった様々な価値観を炙り出した見事な社会実験だと思う。『<レンタルなんもしない人>というサービスをはじめます。』で本人が語る、お金・仕事・人間関係の新たな捉え方
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
あわせて読みたい
【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』
世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す
あわせて読みたい
【芸術】実話を下敷きに描く映画『皮膚を売った男』は、「アートによる鮮やかな社会問題風刺」が見事
「シリア難民の背中にタトゥーを彫り芸術作品として展示する」と聞くと非常に不謹慎に感じられるだろうが、彫ったのが国家間の移動を自由にする「シェンゲンビザ」だという点が絶妙な皮肉。実話をベースにした映画『皮膚を売った男』の、アートによる社会問題提起の見事な鮮やかさ
あわせて読みたい
【貢献】社会問題を解決する2人の「社会起業家」の生き方。「豊かさ」「生きがい」に必要なものは?:『…
「ヤクの毛」を使ったファッションブランド「SHOKAY」を立ち上げ、チベットの遊牧民と中国・崇明島に住む女性の貧困問題を解決した2人の若き社会起業家の奮闘を描く『世界を変えるオシゴト』は、「仕事の意義」や「『お金』だけではない人生の豊かさ」について考えさせてくれる
あわせて読みたい
【奇人】天才数学者で、自宅を持たずに世界中を放浪した変人エルデシュは、迷惑な存在でも愛され続けた…
数学史上ガウスに次いで生涯発表論文数が多い天才エルデシュをご存知だろうか?数学者としてずば抜けた才能を発揮したが、それ以上に「奇人変人」としても知られる人物だ。『放浪の天才数学者エルデシュ』で、世界中の数学者の家を泊まり歩いた異端数学者の生涯を描き出す
あわせて読みたい
【天才】『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、科学者のイメージが変わる逸話満載の非・科学エッセイ
「天才科学者」と言えばアインシュタインやニュートン、ホーキングが思い浮かぶだろうが、「科学者らしくないエピソード満載の天才科学者」という意味ではファインマンがずば抜けている。世界的大ベストセラー『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、「科学」をほぼ扱わないエッセイです
あわせて読みたい
【人生】日本人有名プロゲーマー・梅原大吾の名言満載の本。「努力そのものを楽しむ」ための生き方とは…
「eスポーツ」という呼び名が世の中に定着する遥か以前から活躍する日本人初のプロゲーマー・梅原大吾。17歳で世界一となり、今も一線を走り続けているが、そんな彼が『勝ち続ける意志力』で語る、「『努力している状態』こそを楽しむ」という考え方は、誰の人生にも参考になるはずだ
あわせて読みたい
【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…
環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る
あわせて読みたい
【妄執】チェス史上における天才ボビー・フィッシャーを描く映画。冷戦下の米ソ対立が盤上でも:映画『…
「500年に一度の天才」などと評され、一介のチェスプレーヤーでありながら世界的な名声を獲得するに至ったアメリカ人のボビー・フィッシャー。彼の生涯を描く映画『完全なるチェックメイト』から、今でも「伝説」と語り継がれる対局と、冷戦下ゆえの激動を知る
あわせて読みたい
【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…
Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた
あわせて読みたい
【幻想】日本での子育ては無理ゲーだ。現実解としての「夜間保育園」の実状と親の想いを描く映画:『夜…
映画『夜間もやってる保育園』によると、夜間保育も行う無認可の「ベビーホテル」は全国に1749ヶ所あるのに対し、「認可夜間保育園」は全国にたった80ヶ所しかないそうだ。また「保育園に預けるなんて可哀想」という「家族幻想」も、子育てする親を苦しめている現実を描く
あわせて読みたい
【感想】映画『若おかみは小学生!』は「子どもの感情」を「大人の世界」で素直に出す構成に号泣させられる
ネット記事を読まなければ絶対に観なかっただろう映画『若おかみは小学生!』は、基本的に子ども向け作品だと思うが、大人が観てもハマる。「大人の世界」でストレートに感情を表に出す主人公の小学生の振る舞いと成長に、否応なしに感動させられる
あわせて読みたい
【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る
「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える
あわせて読みたい
【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….
つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る
あわせて読みたい
【奇跡】鈴木敏夫が2人の天才、高畑勲と宮崎駿を語る。ジブリの誕生から驚きの創作秘話まで:『天才の思…
徳間書店から成り行きでジブリ入りすることになったプロデューサー・鈴木敏夫が、宮崎駿・高畑勲という2人の天才と共に作り上げたジブリ作品とその背景を語り尽くす『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』。日本のアニメ界のトップランナーたちの軌跡の奇跡を知る
あわせて読みたい
【危機】教員のセクハラは何故無くならない?資質だけではない、学校の構造的な問題も指摘する:『スク…
『スクールセクハラ なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるのか』では、自分が生徒に対して「権力」を持っているとは想像していなかったという教師が登場する。そしてこの「無自覚」は、学校以外の場でも起こりうる。特に男性は、読んで自分の振る舞いを見直すべきだ
あわせて読みたい
【社会】学生が勉強しないのは、若者が働かないのは何故か?教育現場からの悲鳴と知見を内田樹が解説:…
教育現場では、「子どもたちが学びから逃走する」「学ばないことを誇らしく思う」という、それまでには考えられなかった振る舞いが目立っている。内田樹は『下流志向』の中で、その原因を「等価交換」だと指摘。「学ばないための努力をする」という発想の根幹にある理屈を解き明かす
あわせて読みたい
【貢献】働く上で大切にしたいことは結局「人」。海士町(離島)で持続可能な社会を目指す若者の挑戦:…
過疎地域を「日本の未来の課題の最前線」と捉え、島根県の離島である「海士町」に移住した2人の若者の『僕たちは島で、未来を見ることにした』から、「これからの未来をどう生きたいか」で仕事を捉える思考と、「持続可能な社会」の実現のためのチャレンジを知る
あわせて読みたい
【逸脱】「仕事を辞めたい」という気持ちは抑えちゃダメ。アウェイな土俵で闘っても負けるだけだ:『ニ…
京都大学卒「日本一有名なニート」であるpha氏の『ニートの歩き方 お金がなくても楽しくクラスためのインターネット活用法』は、常識や当たり前に囚われず、「無理なものは無理」という自分の肌感覚に沿って生きていくことの重要性と、そのための考え方が満載の1冊
あわせて読みたい
【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…
世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ
あわせて読みたい
【葛藤】「多様性を受け入れること」は難しい。映画『アイヌモシリ』で知る、アイデンティティの実際
「アイヌの町」として知られるアイヌコタンの住人は、「アイヌ語を勉強している」という。観光客のイメージに合わせるためだ。映画『アイヌモシリ』から、「伝統」や「文化」の継承者として生きるべきか、自らのアイデンティティを意識せず生きるべきかの葛藤を知る
あわせて読みたい
【素顔】「ヨコハマメリー史」から「伊勢佐木町史」を知れる映画。謎の女性が町の歴史に刻んだものとは…
横浜で長らく目撃されていた白塗りの女性は、ある時から姿を消した。彼女の存在を欠いた伊勢佐木町という街は、大きく変わってしまったと語る者もいる。映画『ヨコハマメリー』から、ある種のアイコンとして存在した女性の生き様や彼女と関わった者たちの歴史、そして彼女の”素顔”を知る
あわせて読みたい
【変人】学校教育が担うべき役割は?子供の才能を伸ばすために「異質な人」とどう出会うべきか?:『飛…
高校の美術教師からアーティストとして活動するようになった著者は、教育の現場に「余白(スキマ)」が減っていると指摘する。『飛び立つスキマの設計学』をベースに、子どもたちが置かれている現状と、教育が成すべき役割について確認する。
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
あわせて読みたい
【挑戦】自閉症のイメージを変えるおすすめ本。知的障害と”思い込む”専門家に挑む母子の闘い:『自閉症…
専門家の思い込みを覆し、自閉症のイメージを激変させた少年・イド。知的障害だと思われていた少年は、母親を通じコミュニケーションが取れるようになり、その知性を証明した。『自閉症の僕が「ありがとう」を言えるまで』が突きつける驚きの真実
あわせて読みたい
【能力】激変する未来で「必要とされる人」になるためのスキルや考え方を落合陽一に学ぶ:『働き方5.0』
AIが台頭する未来で生き残るのは難しい……。落合陽一『働き方5.0~これからの世界をつくる仲間たちへ~』はそう思わされる一冊で、本書は正直、未来を前向きに諦めるために読んでもいい。未来を担う若者に何を教え、どう教育すべきかの参考にもなる一冊。
あわせて読みたい
【異端】子育てがうまくいかないと悩む方へ。9歳で大学入学の天才児に学ぶ「すべきでないこと」:『ぼく…
12歳で数学の未解決問題を解いた天才児は、3歳の時に「16歳で靴紐が結べるようになったらラッキー」と宣告されていた。専門家の意見に逆らって、重度の自閉症児の才能をどう開花させたのかを、『ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい』から学ぶ
あわせて読みたい
【自由】幸せは比較してたら分からない。他人ではなく自分の中に「幸せの基準」を持つ生き方:『神さま…
「世間的な幸せ」を追うのではなく、自分がどうだったら「幸せ」だと感じられるのかを考えなければいけない。『神さまたちの遊ぶ庭』をベースに、他人と比較せずに「幸せ」の基準を自分の内側に持ち、その背中で子どもに「自由」を伝える生き方を学ぶ
あわせて読みたい
【異端】子育ては「期待しない」「普通から外れさせる」が大事。”劇薬”のような父親の教育論:『オーマ…
どんな親でも、子どもを幸せにしてあげたい、と考えるでしょう。しかしそのために、過保護になりすぎてしまっている、ということもあるかもしれません。『オーマイ・ゴッドファーザー』をベースに、子どもを豊かに、力強く生きさせるための”劇薬”を学ぶ
あわせて読みたい
【天職】頑張っても報われない方へ。「自分で選び取る」のとは違う、正しい未来の進み方:『そのうちな…
一般的に自己啓発本は、「今、そしてこれからどうしたらいいか」が具体的に語られるでしょう。しかし『そのうちなんとかなるだろう』では、決断・選択をするべきではないと主張されます。「選ばない」ことで相応しい未来を進む生き方について学ぶ
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
あわせて読みたい
【考察】世の中は理不尽だ。平凡な奴らがのさばる中で、”特別な私の美しい世界”を守る生き方:『オーダ…
自分以外は凡人、と考える主人公の少女はとてもイタい。しかし、世間の価値観と折り合わないなら、自分の美しい世界を守るために闘うしかない。中二病の少女が奮闘する『オーダーメイド殺人クラブ』をベースに、理解されない世界をどう生きるかについて考察する
あわせて読みたい
【覚悟】人生しんどい。その場の”空気”から敢えて外れる3人の中学生の処世術から生き方を学ぶ:『私を知…
空気を読んで摩擦を減らす方が、集団の中では大体穏やかにいられます。この記事では、様々な理由からそんな選択をしない/できない、『私を知らないで』に登場する中学生の生き方から、厳しい現実といかにして向き合うかというスタンスを学びます
あわせて読みたい
【葛藤】部活で後悔しないために。今やりたいことをやりきって、過去を振り返らないための全力:『風に…
勉強の方が、部活動より重要な理由なんて無い。どれだけ止められても「全力で打ち込みたい」という気持ちを抑えきれないものに出会える人生の方が、これからの激動の未来を生き延びられるはずと信じて突き進んでほしい。部活小説『風に恋う』をベースに書いていく
あわせて読みたい
【肯定】価値観の違いは受け入れられなくていい。「普通」に馴染めないからこそ見える世界:『君はレフ…
子どもの頃、周りと馴染めない感覚がとても強くて苦労しました。ただし、「普通」から意識的に外れる決断をしたことで、自分が持っている価値観を言葉で下支えすることができたとも感じています。「普通」に馴染めず、自分がダメだと感じてしまう人へ。
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
教育・学校【本・映画の感想】 | ルシルナ
大人になって様々な本を読んだことで、「子どもの頃にこういう考えを知れたらよかった」「学校でこういうことを教えてほしかった」とよく感じるようになりました。子どもの…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…



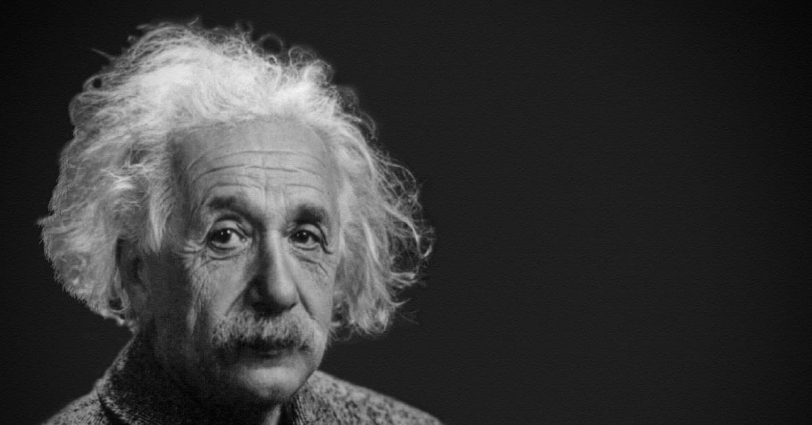

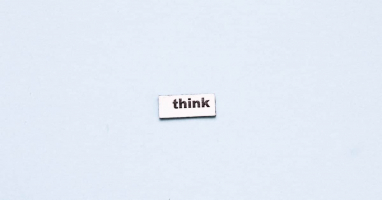
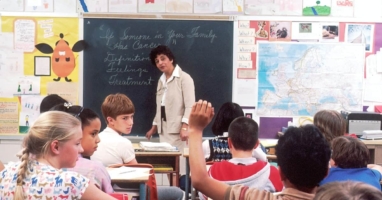
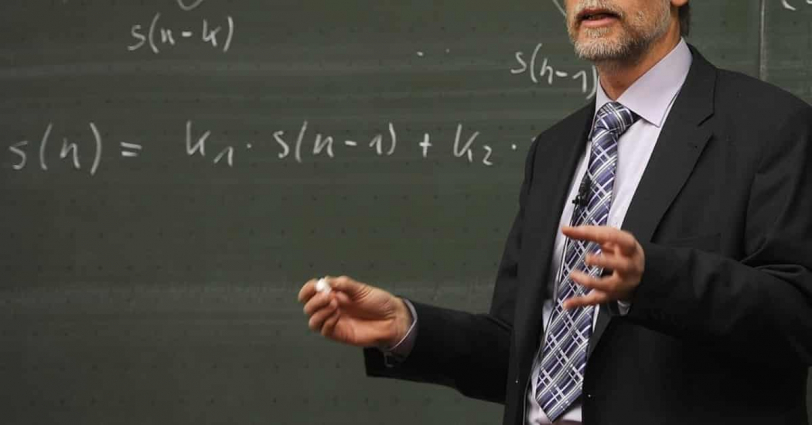


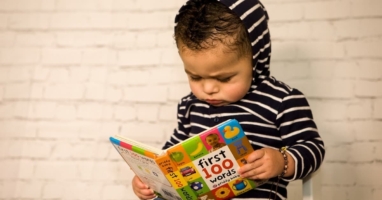
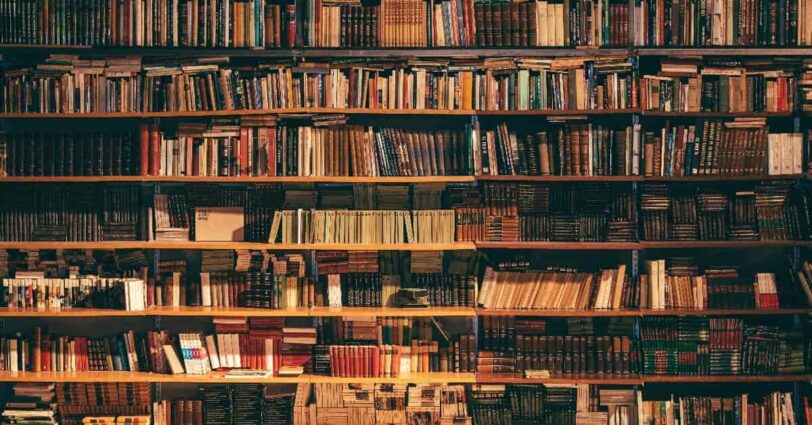




























































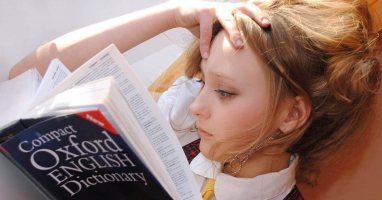


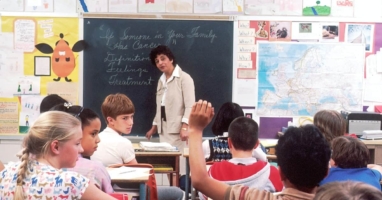



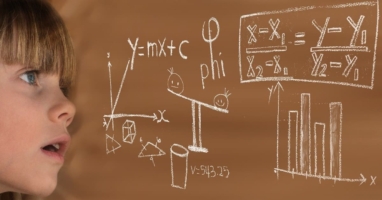











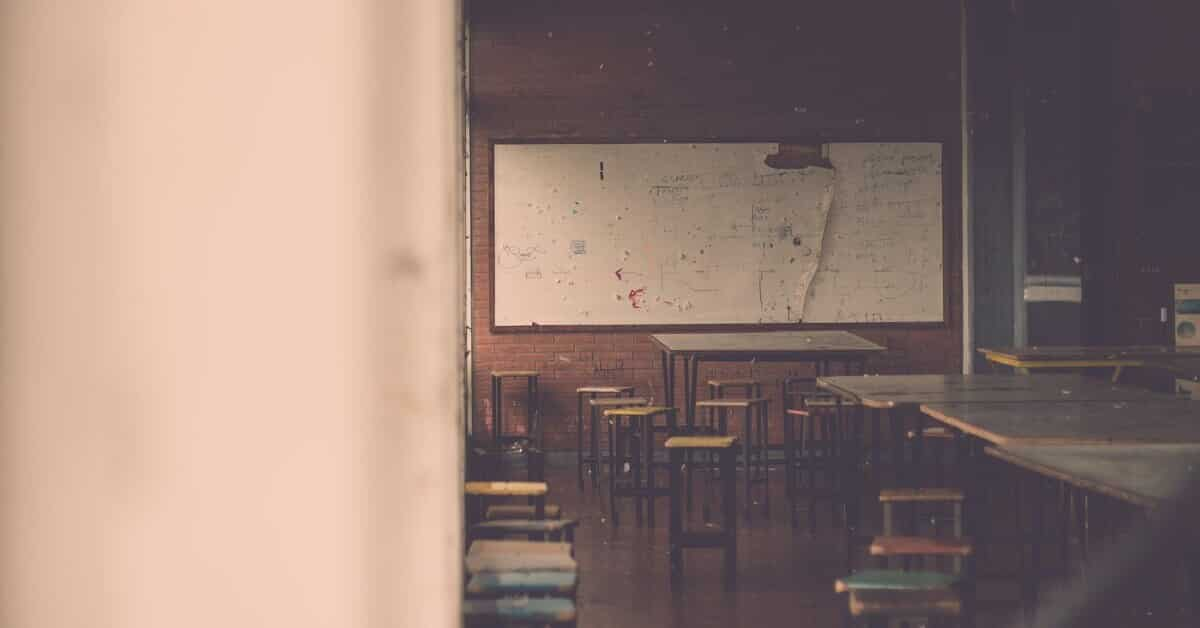






コメント