目次
はじめに
この記事で取り上げる映画

「ウォン・カーワァイ 4K」公式HP
出演:トニー・レオン, 出演:フェイ・ウォン, 出演:ブリジット・リン, 出演:金城武, 出演:ヴァレリー・チョウ, 監督:ウォン・カーウァイ, プロデュース:ジェフ・ラウ, Writer:ウォン・カーウァイ
¥330 (2024/08/10 23:01時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
出演:レオン・ライ, 出演:ミシェール・リー, 出演:金城武, 出演:チャーリー・ヤン, 出演:カレン・モク, 監督:ウォン・カーウァイ, プロデュース:ジェフ・ラウ, Writer:ウォン・カーウァイ
¥330 (2024/08/10 23:02時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
今どこで観れるのか?
公式HPの劇場情報をご覧ください
この記事の3つの要点
- この記事では、『恋する惑星』『天使の涙』『花様年華』『2046』『ブエノスアイレス』の5作品の感想を書いていく
- 『恋する惑星』の鑑賞時、観ようと思っていた日のチケットが取れず、さらに若いお客さんが多かったことに驚かされた
- ウォン・カーウァイ作品に対しては全体的に、「魅力的な女性が多数登場する」という点が素敵だと思う
ストーリーなど無いようにさえ感じられる作品なのに、全体の雰囲気がとても魅力的で惹きつけられてしまう
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
ウォン・カーウァイ監督作品5作を紹介!『恋する惑星』『天使の涙』など必見の話題作を含む、20世紀末を鮮やかに彩ったスタイリッシュな作品群
2022年8月、ウォン・カーウァイ監督作品5作が、監督自身の手による4Kレストアを経て劇場公開された。
『WKW4K ウォン・カーウァイ4K 5作…
『WKW4K ウォン・カーウァイ4K 5作品』オフィシャルサイト
8.19(金)全国順次公開|監督自らの手により4Kレストア! 新しい作品として生まれ変わった『恋する惑星』、『天使の涙』、
『ブエノスアイレス』、『花様年華』、『2046』が…
さて、私はそれまで、「ウォン・カーウァイ」という映画監督のことを正直知らなかったし、もちろん作品についても同様である。だから、「あの監督の4Kレストア版が観れる!」みたいな動機で映画館に足を運んだのではない。

一方私は、「基本的に映画館でしか映画を観ない」と決めている。なので、「過去の名作を観る機会」はほとんどない。ただ最近は「4Kレストア版」「4Kリマスター版」などが劇場公開されることが多くなってきた。そしてやはり、そういう映画は「名作と呼ばれる作品」であることが多いだろう。なので私は、「なるべくレストア版・リマスター版は積極的に観るようにしている」のである。
そんな理由で私は、ウォン・カーウァイ4Kレストア版5作品をすべて観た。
さて、先に私の好き嫌いについて触れておこう。今回観た5作品の中で、私が一番好きなのが『天使の涙』である。そしてその次が『恋する惑星』。それから『花様年華』と『2046』がほぼ同列、『ブエノスアイレス』はちょっと好きになれなかったという感じだ。
ただ、この評価は「観た順番」にも依るかもしれないとも考えている。
調べてみると、ウォン・カーウァイ作品は「様々な形で歴史に翻弄された『香港』という土地を舞台にしている」という点にとても大きな意味があるのだそうだ。「様々な政治・国際情勢を背景にしながら、『そんな香港で生きる人々』を切り取っている」という要素も、作品の評価の一因になっているのである。
あわせて読みたい
【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』
2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない
しかし私は、そういう背景的なことはほとんど知らず、作品からも読み取れない状態で映画を鑑賞していた。そのため、ウォン・カーウァイ作品の分かりやすい特徴である「スタイリッシュさ」に惹かれたと言っていいだろう。そしてその「スタイリッシュさ」は、この5作品で割と共通している。私はこの5作品を、『恋する惑星』『天使の涙』『花様年華』『ブエノスアイレス』『2046』の順に観たのだが、もし『花様年華』や『2046』を先に観ていたら、そっちを好きになっていたかもしれない。
またこの印象は、「5作品を短期間で一気見したからこそのもの」とも言えるだろう。
たとえ「スタイリッシュさ」が似通っていたとしても、作品鑑賞のタイミングがズレていれば印象もまた変わったかもしれない。しかし私は今回、1ヶ月間で5作品観た。つまり、「似た印象の『スタイリッシュさ』を続けざまに取り込んだ」ことになる。それで「先に観た作品の方がより良い印象になっている」という可能性もあるだろう。
いずれにせよ、私はウォン・カーウァイ作品の「スタイリッシュさ」にかなり惹かれたし、この記事ではそういう「表面的な見方」ばかりに触れるつもりだ。深い考察をしているわけではないので、そのような内容を期待している方はここで読むのを止めていただくのがいいだろう。
それでは、それぞれの作品を紹介していくことにする。
あわせて読みたい
【感想】映画『ローマの休日』はアン王女を演じるオードリー・ヘプバーンの美しさが際立つ名作
オードリー・ヘプバーン主演映画『ローマの休日』には驚かされた。現代の視点で観ても十分に通用する作品だからだ。まさに「不朽の名作」と言っていいだろう。シンプルな設定と王道の展開、そしてオードリー・ヘプバーンの時代を超える美しさが相まって、普通ならまずあり得ない見事なコラボレーションが見事に実現している
『恋する惑星』
劇場が満員だったことに、とにかく驚かされてしまった
さて、最初に観た『恋する惑星』の話から始めていくが、内容の前にまず、「映画館が満員だった驚き」に触れておきたいと思う。
あわせて読みたい
【傑作】濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』(原作:村上春樹)は「自然な不自然さ」が見事な作品
村上春樹の短編小説を原作にした映画『ドライブ・マイ・カー』(濱口竜介監督)は、村上春樹の小説の雰囲気に似た「自然な不自然さ」を醸し出す。「不自然」でしかない世界をいかにして「自然」に見せているのか、そして「自然な不自然さ」は作品全体にどんな影響を与えているのか
私は元々本作を土曜に観るつもりだったので、その前日金曜の夜にチケットを取ろうと思っていたのだが、その時点で既に、シネマート新宿の335席もあるかなり広い劇場が満員で埋まっていたのである。シネマート新宿はよく行くのだが、あの広い劇場が満員になったところなどそれまで見たことがなかったのでとても驚かされてしまった。
そんなわけで、慌てて日曜のチケットを取ったのだが、結局私が観た回も満員だったようである。とにかく客席が埋まっていたのだ。さらに、ざっくり見た限りの印象だが、若い人が多かったことにも驚かされた。映画『恋する惑星』は1994年公開の映画であり、2022年に私が観た時点で約30年前の作品だ。「当時観ていた映画が懐かしくて劇場に足を運んだ」ということであれば、40~50代の人が多いはずだろう。

もちろん、昔の作品でもレンタルや配信で観れるわけで、そのようにしてウォン・カーウァイ作品に触れていた若者が、「4Kレストア版が上映される」と知って映画館に足を運んだ可能性もあるとは思う。しかし、鑑賞後に近くの席から、明らかに本作を人生で初めて観たのだろう若者の会話が聞こえてきたのである。
さらに、この4Kレストア版はなんと、私が映画館で鑑賞した時点で既に、配信でも観ることが可能だったのだ。つまり若者は、「今まで観たことがなく、かつ配信でも観られる映画を、わざわざ映画館まで観に来ている」ことになる。まず私は、この点に驚かされてしまったというわけだ。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『レザボア・ドッグス』(タランティーノ監督)はとにかく驚異的に脚本が面白い!
クエンティン・タランティーノ初の長編監督作『レザボア・ドッグス』は、のけぞるほど面白い映画だった。低予算という制約を逆手に取った「会話劇」の構成・展開があまりにも絶妙で、舞台がほぼ固定されているにも拘らずストーリーが面白すぎる。天才はやはり、デビュー作から天才だったのだなと実感させられた
若い人の間で「レトロ」「昭和」がブームになっているみたいなので、そういう流れでウォン・カーウァイ作品も話題になっているのかもしれないが、いずれにせよ、「30年近く前に公開された映画に、初日から若い人がじゃんじゃん押し寄せている」という状況が私にはちょっと不思議に感じられた。何にせよ、そのような強い引力を持つ作品と言えるだろう。公開館の規模が違うとはいえ、大ヒットアニメ映画ぐらいお客さんが押し寄せていたので、「アニメ映画以外でもこれほど劇場にお客さんを惹きつける作品がある」ということに少し感動を覚えさえした。
前後半でまったく異なる展開の物語であることに驚愕させられた
映画を観て一番強く感じたのは、「前後半で物語が繋がってないじゃん」ということだ。個人的な感覚では、「2つの短編映画が1作として提示されている」みたいな印象さえ受けたのである。
映画館で観たので時間経過はなんとなくの体感でしか判断できないが、私の感触では「前半の物語が全体の1/3」「後半の物語が全体の2/3」であるように感じられた。そしてその前後半で、主人公が変わる。前後半の物語の共通項は、「同じ屋台を舞台にしている」ぐらいだろう。それ以外には、前後の物語を繋ぐ要素は無かったと思う。実に変な構成だと感じられたし、正直「1つの物語としては成立していない」という印象の方が強かった。
あわせて読みたい
【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…
映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ
ただ、非常に不思議なのだが、作品としてはすごく素敵に感じられたのである。正直、何が良かったのか上手くは説明できない。私は普段、割と「頭(思考)」で映画を観ているのだが、ウォン・カーウァイ作品は全般的に「心(感情)」が持っていかれる感じがした。その差が大きかったのかもしれない。
また、前後半で物語が繋がっていないだけではなく、「全体的にストーリーが破綻している」とさえ感じられた。前半の物語はまだ成り立っているようにも思えるのだが、後半の物語は「ストーリーとして成立してます?」と言いたくなったほどである。物語的な観点から捉えれば正直、「まったく意味不明」と言わざるを得ないだろう。
ただ、これもまた私にとっては不思議な感覚だったのだが、どちらかと言えば後半の物語の方が面白く感じられた。それは圧倒的に、屋台で働く短髪の女性フェイの存在感に依っていると言えるだろう。後半の物語がハチャメチャに見えるのは「フェイが無茶苦茶やってるから」なのだが、しかし同時に、フェイの圧倒的な存在感によって、後半の物語は「観れるもの」として成立できているのだ。フェイの行動は「狂気」と表現することもできるものなのだが、しかし観客は恐らく、その「狂気」をずっと観ていられると感じるだろう。私も正直、彼女のことをもっと観ていたいと思っていた。実に魅力的な女性なのである。
これは「恋」と呼んでいいのだろうか?
あわせて読みたい
【痛快】精神病院の隔離室から脱した、善悪の判断基準を持たない狂気の超能力者が大暴れする映画:『モ…
モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』は、「10年以上拘束され続けた精神病院から脱走したアジア系女性が、特殊能力を使って大暴れする」というムチャクチャな設定の物語なのだが、全編に通底する「『善悪の判断基準』が歪んでいる」という要素がとても見事で、意味不明なのに最後まで惹きつけられてしまった
前半の物語は、分かりやすく「恋」と呼べるものだった。まあ、正確には「失恋」なのだが。しかし、後半の物語を「恋」と呼んでいいのかはちょっとなんとも言えない。フェイの振る舞いに対して最も適切な表現を探すとしたら、やはり「ストーカー」になってしまうだろう。そして、仮にその「ストーカー行為」の動機が「恋」なのだとしても、彼女の行動一つ一つはやはりちょっと謎過ぎる。
前半から後半へと物語が切り替わるタイミングで、「6時間後、彼女は別の男に恋をする」と表示されるので、「フェイが恋に落ちた」という理解で間違いない。というか、そのように説明されるからこそ、観客も「彼女の振る舞いは『恋』が起点になっている」と受け取れると言えるだろう。
そしてもしそのような説明がなかったら、彼女の行動だけを見てそれを「恋」と判断することはほぼ不可能ではないかと思う。いや、もちろん断片的には、「恋をしているんだろうなぁ」と感じさせる場面はある。しかしそれ以上に、「目的の分からない狂気的な振る舞い」が多すぎるため、全体として見た場合に、そこに「恋」を見出すことは難しいように思うのだ。

このように、後から振り返って冷静に分析してみると、フェイの振る舞いの「狂気さ」に改めて気付かされる。だから普通なら、「彼女の振る舞いをもっと観ていたかった」みたいな感想になるはずがないのだ。しかし実際には、フェイがメインで描かれる後半の物語の方が圧倒的に面白かったし、物凄く惹きつけられてしまった。本当に、自分でもよく分からないぐらい不思議な感覚だったなと思う。
音楽や映像もとても素敵
後半の物語では、音楽もとても印象的だった。頻繁に流れる曲に聞き覚えはあったのだが、曲名が分からなかったので鑑賞後に調べたところ、『California Dreamin’』という曲だそうだ。正直、何故聞き覚えがあるのか思い出せないのだが、子どもの頃観ていたテレビ(何かのドラマ?)でも流れていたような気がする。というか恐らく、映画『恋する惑星』がヒットしたことで、この曲が様々な場面で使われるようになったということではないだろうか。しかし、この曲のタイトルを調べてやっと、作中で「カリフォルニア」に言及していた理由が分かった。
あわせて読みたい
【天才】映画音楽の発明家『モリコーネ』の生涯。「映画が恋した音楽家」はいかに名曲を生んだか
「映画音楽のフォーマットを生み出した」とも評される天才作曲家エンリオ・モリコーネを扱った映画『モリコーネ 映画が恋した音楽家』では、生涯で500曲以上も生み出し、「映画音楽」というジャンルを比べ物にならないほどの高みにまで押し上げた人物の知られざる生涯が描かれる
さて、私は基本的に音楽が記憶と結びつかない人間だ。好んで音楽を聴く習慣が元々ないし、テレビなどでよく流れていた音楽についても、曲自体は覚えていても、それがいつの時代のどこで流れていた曲なのかという記憶が喚起されたりはしない。だから私は、本作で流れる『California Dreamin’』を聞いて、どことなく「懐かしさ」を覚えた理由が謎だった。聞くと何故か懐かしく感じられるのだ。そんなわけで、どうしてか「懐かしい」気分になるこの曲の存在も、作品の印象に影響を与えていると言えるだろう。
また私は普段、視覚的な情報にもあまり反応しない人間で、映画を観ても「このシーンは構図が素晴らしい」「役者の衣装が素敵」みたいな感想を抱くことはない。しかし本作の場合、「1990年代の香港の街並み」や「夜のネオンの色彩」みたいなものがとても素敵に感じられたのだ。
前半の物語の舞台はほぼ完全に夜で、だから香港の夜が織りなす色彩がとても印象的だった。「暗い背景の中でネオンが輝く」といった映像が素敵に感じられたのだ。また後半の物語は昼間のシーンもあるのだが、それでも明るい屋外にいることは少ない。外から日があまり差さない暗い室内で展開されることが多いため、映像の背景としては「暗さ」が強調されていると言える。一方で、フェイの服装はキャッチーで彩りが鮮やかなので、後半の物語でも「暗い背景をバックにフェイの衣装が際立つ」という印象が強かった。さらにフェイの服だけではなく、室内の小物なども色鮮やかで、そのような対比が映像的にとても綺麗だったのだ。
また、「背景が暗い」ことによって作品全体の「異様さ」が際立ち、その一方で「ネオンや服・小物の色鮮やかさ」によって作品全体が放つ「異様さ」が緩められているみたいな印象もあった。だから、特に後半の物語では「フェイの狂気」がに焦点が当たっているにも拘らず、「魅力的な物語」になっていたのかもしれない。
あわせて読みたい
【感想】のん主演映画『私をくいとめて』から考える、「誰かと一緒にいられれば孤独じゃないのか」問題
のん(能年玲奈)が「おひとり様ライフ」を満喫する主人公を演じる映画『私をくいとめて』を観て、「孤独」について考えさせられた。「誰かと関わっていられれば孤独じゃない」という考えに私は賛同できないし、むしろ誰かと一緒にいる時の方がより強く孤独を感じることさえある
このように、普段私があまり気にならない「音楽」や「映像美」みたいなものも含めとても素敵な作品だった。しかしそういう要素を考慮しても結局、映画『恋する惑星』の一体何に惹かれたのかは上手く捉えられずにいる。とても不思議な物語だなと思う。あと、前半の物語に出ていたのが金城武だと、エンドロールを見て知った。そうだったのか。
『天使の涙』
映画『恋する惑星』よりも好きな作品
あわせて読みたい
【考察】生きづらい性格は変わらないから仮面を被るしかないし、仮面を被るとリア充だと思われる:『勝…
「リア充感」が滲み出ているのに「生きづらさ」を感じてしまう人に、私はこれまでたくさん会ってきた。見た目では「生きづらさ」は伝わらない。24年間「リアル彼氏」なし、「脳内彼氏」との妄想の中に生き続ける主人公を描く映画『勝手にふるえてろ』から「こじらせ」を知る
さて、『恋する惑星』に続いて観たのが『天使の涙』である。そして私は、本作『天使の涙』の方が好きだなと思った。というわけで、この比較をする理由を1つ挙げておくと、観ながら「『恋する惑星』と『天使の涙』は近い世界観を舞台にした作品だ」と感じたからである。実際、この捉え方は正しかったようだ。というのも『天使の涙』は、元々『恋する惑星』の一部として含まれるはずだった物語を独立させたものなのである。
先程書いた通り、私にとって『恋する惑星』の素敵さはほぼ「短髪の屋台店員フェイの存在感」に依っていたのだが、『天使の涙』は全体的に面白いと感じられた。物語は『恋する惑星』と同様、「ほぼ無関係と言っていい2つのストーリーが展開される」という感じなのだが、『恋する惑星』とは大分印象が異なる。『恋する惑星』では、前後半の物語にまったく繋がりが感じられなかったのだが、『天使の涙』では、無関係な2つの物語の要素が作品全体に散りばめられているような感じがしたのだ。つまり、『天使の涙』の方が、2つの物語に仄かな関係性を感じられたというわけだ。そのような構成が、『恋する惑星』よりも私の好みだったのである。
「色彩の美しさ」や「『夜の香港』の妖しさ」、あるいは「カメラの手ブレを抑えることなくそのまま使うスタイル」など、『恋する惑星』と共通する部分は多く、この2作については「誰が作ったのか」を知らなくても、同じ監督の作品だと誰もが認識できるのではないかと思う。そのような「作家性」が強烈に溢れ出る作品というわけだ。
あわせて読みたい
【感動】円井わん主演映画『MONDAYS』は、タイムループものの物語を革新する衝撃的に面白い作品だった
タイムループという古びた設定と、ほぼオフィスのみという舞台設定を駆使した、想像を遥かに超えて面白かった映画『MONDAYS』は、テンポよく進むドタバタコメディでありながら、同時に、思いがけず「感動」をも呼び起こす、竹林亮のフィクション初監督作品

『恋する惑星』では、「暗い背景」に映える「鮮やかな色彩の衣装や小物」などが印象的に使われていたが、一方、『天使の涙』ではそのようなものには目がいかなかったので、「色彩の鮮やかさ」に関してはほぼ「『夜の香港』のネオンの色」のみと言っていいと思う。物語は基本的に、「殺し屋」か「他人の店を勝手に営業させてしまう迷惑男」のどちらかによって展開されるのだが、この2つは普通1つの作品の中で馴染むものではないだろう。ただ、その「ネオンの妖しさ」が全体の雰囲気を統一しており、そのような部分もまた良かったなと思う。
物語の設定・展開の説明
『天使の涙』にも物語らしい物語は存在しないのだが、『恋する惑星』と比べればストーリー性はあると思うので、少し説明しておくことにしよう。
あわせて読みたい
【驚異】映画『RRR』『バーフバリ』は「観るエナジードリンク」だ!これ程の作品にはなかなか出会えないぞ
2022年に劇場公開されるや、そのあまりの面白さから爆発的人気を博し、現在に至るまでロングラン上映が続いている『RRR』と、同監督作の『バーフバリ』は、大げさではなく「全人類にオススメ」と言える超絶的な傑作だ。まだ観ていない人がいるなら、是非観てほしい!
「綾野剛みたいな殺し屋の男」は、香港の街で「人殺し」を生業に生きてきた。ものぐさを自認している彼は、「誰をどのように殺すのか」をすべて指示してくれる今の仕事を気に入っている。頭ではなく、身体だけ動かしていたいタイプなのだ。
そんな殺し屋に指示を出す「あいみょんみたいなパートナーの女」は、男に仄かな恋心を抱いている。といっても男とは仕事だけの関わりであり、「155週間ぶりに隣に座った」というくらいそもそも会う機会がない。というか彼女は、「わざと距離を置いている。知ると興味を失うから」とさえ考えているのだ。ただ、殺し屋の男への関心は消せないため、彼の家に勝手に忍び込んでは、ゴミを持ち帰って生活ぶりを想像したり、家主不在の部屋でひとりオナニーをしたりするのである。
2人の関係はそのような形で長く継続してきたのだが、殺し屋の心情が少し変わってきた。怪我を負う機会が増えてきたこともあり、殺し屋稼業から足を洗いたいと考えるようになったのである。そんなある日、彼はマクドナルドで「金髪の竹内結子みたいなハイテンション女」と出会う。そして土砂降りの雨に打たれながら、男は知り合ったばかりの女の家に向かうのだ。
一方、金城武が演じているのは、5歳の時に賞味期限切れのパイナップルを食べたことで喋れなくなってしまった「勝手に商売男」である。彼は、シャッターが閉まった店に忍び込んでは、店を勝手に営業し金を稼いでいた。しかもやり方が荒っぽい。コインランドリーに忍び込んでいたホームレスの服を破ってでも脱がせて洗おうとしたり、通行人を捕まえて理髪店の椅子に座らせそのまま髪を洗ったり、アイスクリーム店にやってきた客に有無を言わさず延々にアイスを食べさせるなど、やりたい放題なのだ。そして、その「勝手に商売男」の父親が経営している「重慶ホテル」という安宿に寝泊まりしているのが「あいみょんみたいなパートナーの女」である。
あわせて読みたい
【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…
好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性
「勝手に商売男」は日々、夜の香港でムチャクチャな商売を行っているのだが、ある日、公衆電話で誰かに電話をし続ける「ビビアン・スーみたいな女」に出会う。話を聞くとどうやら、親友に恋人を盗られたようだ。そのため、復讐心に燃えたぎっていた。「ビビアン・スーみたいな女」は「勝手に商売男」から金を借りては電話をし、さらに彼を連れ回して「金髪アレン」と呼ぶ女を探し出そうとするのである。
そんな彼女に、「勝手に商売男」は人生初の恋に落ちた。しかし「ビビアン・スーみたいな女」は、親友に盗られた恋人のことが忘れられないようで、そのことを知った「勝手に商売男」は落ち込んでしまう。ただ、「すべてのものには賞味期限が存在する」と理解している彼は、彼女の恋人への想いが「賞味期限切れ」になるのを待とうと考えるのだが……。
「歪んでいるが歪んでいるようには見えない」という不思議さが素敵な物語
内容的にはやはり、「これは物語と言えるのか?」と感じるくらい意味不明な話だった。しかし、『恋する惑星』よりはちゃんと展開すると言えるだろう。また、個々の登場人物が物語の各所で微妙に接点を持っていくため、「次にどういう展開になっていくのかさっぱり分からない」みたいな感覚がかなり強くなる。そんなわけで、物語の展開そのものがまずシンプルに興味深く感じられたた。
殺し屋とパートナー女の物語は割とシリアスに展開していくのだが、商売男と失恋女の物語は思わず笑ってしまうシーンが満載で、とても陽気に展開していく。このギャップもまた良かったなと思う。映画の冒頭は、「商売男が色んな店を勝手に開けて商売する」というシーンで始まるのだが、このハチャメチャさはすごく面白かったし、また、「金髪アレン」を探そうとする失恋女の「謎のテンションの高さ」も異様で惹きつけられた。
あわせて読みたい
【あらすじ】濱口竜介監督『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」のみで成り立つ凄まじい映画。天才だと思う
「映画」というメディアを構成する要素は多々あるはずだが、濱口竜介監督作『偶然と想像』は、「脚本」と「役者」だけで狂気・感動・爆笑を生み出してしまう驚異の作品だ。まったく異なる3話オムニバス作品で、どの話も「ずっと観ていられる」と感じるほど素敵だった
さて、「異様」と言えば、本作に登場する女性たちは皆どこかしら「歪んでいる」と言っていいだろう。パートナー女は、本人でさえ「恋」と認識しているのか分からないような歪んだ恋心を抱いているし、ハイテンション女は、その常軌を逸したハイテンションっぷりが凄まじいのだ。さらに失恋女も、「まともな思考回路がショートしているのだろうか?」と感じさせるようなぶっ飛んだ行動を繰り返すのである。

しかし、このような「歪み」は、「誰かに説明しよう」と思って言語化する際には意識されるのだが、正直、観ている時にはあまり気にならなかった。『恋する惑星』も同様だったが、この点が本作の凄まじい点だと思う。『恋する惑星』も『天使の涙』も、主に女性たちが「イカれた雰囲気」をこれでもかと醸し出しているのに、観客としてはそれがさほど強く意識されないのである。
恐らくそれは、「映像のかっこよさ」「作品の雰囲気にマッチした女優の美しさ」「作品全体が放つスタイリッシュさ」みたいなものに覆われているからだと思う。これほど強烈な「歪み」が随所に散りばめられているのに、観ている時にはそれが強くは意識されないという作品全体が持つ雰囲気には、ちょっと驚かされてしまった。何をどうしたらそうなるのかさっぱり分からないものの、どこか「錯視映像」を見せられているような感覚であり、やはりとても不思議な作品と言えるだろう。
あわせて読みたい
【逃避】つまらない世の中で生きる毎日を押し流す”何か”を求める気持ちに強烈に共感する:映画『サクリ…
子どもの頃「台風」にワクワクしたように、未だに、「自分のつまらない日常を押し流してくれる『何か』」の存在を待ちわびてしまう。立教大学の学生が撮った映画『サクリファイス』は、そんな「何か」として「東日本大震災」を描き出す、チャレンジングな作品だ
結局のところ誰の物語も進展しないし、本作をシンプルに要約したら「特に何も起こらなかった」となるのではないかと思う。しかしそれでも、物凄く惹きつけられてしまったのである。断片的な描写が延々に続いていくような雰囲気が何故か心地よい作品であり、その形容しがたい雰囲気に圧倒されてしまった。
『花様年華』
「ストーリー的な断片」ではなく「映像的な断片」で構成された物語
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』を観てくれ!現代の人間関係の教科書的作品を考…
映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』は、私にグサグサ突き刺さるとても素晴らしい映画だった。「ぬいぐるみに話しかける」という活動内容の大学サークルを舞台にした物語であり、「マイノリティ的マインド」を持つ人たちの辛さや葛藤を、「マジョリティ視点」を絶妙に織り交ぜて描き出す傑作について考察する
ウォン・カーウァイ作品を見慣れてきたこともあり、そのスタイルには馴染み深ささえ感じるようになってきた。本作『花様年華』でも、「覗き見のようなショット」「印象深い音楽」「断片が積み重ねられる構成の展開」などはとてもウォン・カーウァイ的であり、全体としてはとても好きな感じの作品である。
本作『花様年華』で特徴的だと感じられたのは、「『映像的な断片』で物語が構成されていた」という点だ。それまで観たウォン・カーウァイ作品では、「『ストーリー的な断片』が積み上げられて全体が構成されている」という感じだった。しかし『花様年華』では、それがさらに「映像単位」にまで分割されていたように思えたのだ。「『それ単体では何を描いているのか分からない短い映像』をこれでもかと繋いでいくことで、『意味を持ちそうな物語』を構築していく」というようなやり方で作られているのではないだろうか。
そしてそのような構成だったからだろう、ストーリーを捉えるのがとても難しかった。私は普段、これから観る予定の映画について設定さえも知らないまま劇場に行くことにしており、そのこともあって本作の場合、「そもそも何が描かれているのか」を把握するのにかなり時間が掛かってしまったのだ。
例えばかなり冒頭の方で、「隣人に買ってもらった日本製炊飯器の代金の支払い」に関する場面があった。主人公の1人であるチャウは頻繁に海外出張に出かける隣人に「炊飯器のお礼」を伝え、その上で代金の支払いについて相談しようとする。しかし相手から、「お金はもう、あなたの奥さんからもらった」みたいに言われてしまうのだ。
あわせて読みたい
【正義】復讐なんかに意味はない。それでも「この復讐は正しいかもしれない」と思わされる映画:『プロ…
私は基本的に「復讐」を許容できないが、『プロミシング・ヤング・ウーマン』の主人公キャシーの行動は正当化したい。法を犯す明らかにイカれた言動なのだが、その動機は一考の余地がある。何も考えずキャシーを非難していると、矢が自分の方に飛んでくる、恐ろしい作品
このシーンを観た時には、このやり取りの意味が理解できなかった。分かったのは、だいぶ後になってからである。そしてその後、「バッグ」と「ネクタイ」の話からある事実が判明するのだが、しかしその点についても、「バッグとネクタイが出てくる場面」ですぐに理解できたわけではない。その意味が分かったのは、「日本の切手が貼られた封筒が届くシーン」でのことだ。そしてようやくここで、「なるほど、そういう設定の物語なのか」と理解できたのである。
さて、今私は、本作における「重要な設定」を伏せた上で内容を説明したが、この点に関しては公式HPの内容紹介欄でも触れられているので書いてもネタバレには当たらないだろうと思っている。そのため、これ以降はその点に触れるつもりだ。知らずに鑑賞したいという方は、ここから先を読まないようにしてほしい。
物語の設定・展開について
舞台となるのは、1962年の香港。新聞編集者であるチャウと商社で秘書として働くチャンは、同じ日に同じアパートの隣同士に引っ越してきた。引っ越しのタイミングが重なったこともあり、お互いの荷物が混ざったりとトラブルも起こる。そんなこともあって、2人は初日から話をする機会を得ることになった。
その後2人は、付かず離れずといった距離感の関係を続けていく。共に既婚者だが、お互いの配偶者は出張だったり夜勤だったりで、ほとんど家にはいない。屋台へと向かう階段ですれ違ったり、アパートの中で少し顔を合わせたりする程度で、お互いの配偶者の存在はほとんど感知されないというわけだ。
あわせて読みたい
【感想】映画『先生、私の隣に座っていただけませんか?』は、「リアル」と「漫画」の境界の消失が絶妙
映画『先生、私の隣に座っていただけませんか?』は、「マンガ家夫婦の不倫」という設定を非常に上手く活かしながら、「何がホントで何かウソなのかはっきりしないドキドキ感」を味わわせてくれる作品だ。黒木華・柄本佑の演技も絶妙で、良い映画を観たなぁと感じました
状況に変化が訪れたのは、チャンを呼び出したチャウがある相談を持ちかけた時のことである。チャウは妻にバッグを買ってあげたいと考えており、チャンに「君が持っているバッグはどこで買ったのか」と尋ねたのだ。そしてその話の流れの中で、チャンがチャウのネクタイに話を移し、その結果、「チャウの妻とチャンの夫は不倫しているに違いない」という事実に思い至ったのである。どちらも伴侶に裏切られていたというわけだ。そんな痛みを抱えていることが分かったこともあり、2人の距離はそれまでよりも縮まることになる。

しかし2人は恐らく、「配偶者と同じことはするまい」と考えていたのだと思う。確かに距離は縮まるが、それ以上深い関係になることもなかった。もし2人がまったく違う形で出会っていたら、何の障害を感じることもなく恋をしていたことだろう。しかし、お互いが同じ不幸を背負っていることを同時に知ってしまった2人の恋は結局、始まりもしなければ終わりもしないのである。
「互いの伴侶が不倫をしている」という状況を、一方の側からのみ描き出す物語
先程書いた通り、「ネクタイとバッグの話をしている場面」では、私はまだ「お互いの伴侶が不倫している」という状況に気づいていなかった。そのため、その際に交わされた「私だけかと思った」「どっちが誘ったにしろ、もう始まってる」というやり取りの意味はまったく理解できていなかったのである。そしてその後、「日本の切手が貼られた封筒が出てくるシーン」でようやく状況が掴めたというわけだ。
なので私には、「どう見ても惹かれ合っているだろう2人が恋愛に発展しない理由」がしばらく理解できなかった。もちろん共に既婚者なのだから「恋愛に発展しない」のは自然と言えば自然なのだが、物語的には不自然なのである。そのため、「互いの伴侶が不倫をしている」という設定を理解して、ようやく状況が把握できたというわけだ。
あわせて読みたい
【希望】誰も傷つけたくない。でも辛い。逃げたい。絶望しかない。それでも生きていく勇気がほしい時に…
2006年発売、2021年文庫化の『私を見て、ぎゅっと愛して』は、ブログ本のクオリティとは思えない凄まじい言語化力で、1人の女性の内面の葛藤を抉り、読者をグサグサと突き刺す。信じがたい展開が連続する苦しい状況の中で、著者は大事なものを見失わず手放さずに、勇敢に前へ進んでいく
本作の場合凄いのは、「不倫している側の状況を一切描かないこと」だと思う。何なら、「状況」が描かれないだけではなく、「不倫している側の存在」さえほぼ映し出されないのである。先述した通り、「僅かに気配を感じる」程度にしか描かれないのだ。
そのような構成になっているのは恐らく、「チャウにしてもチャンにしても、『伴侶の不倫』が確定的な事実にはなっていないから」だと思う。いや、2人はもちろん「伴侶の不倫」を確信しているだろう。しかし、「2人が一緒にいるところを目撃した」などの明確な“証拠”を掴んでいるわけではない。つまり「確実な妄想」みたいな認識なのであり、観客に対してもそのようなものとして提示しようと意図しているのだと私は感じた。
つまり、「チャウ、チャン」にとっても「観客」にとっても、「恐らく間違いないが、確証はないこと」として「お互いの伴侶の不倫」が描かれているというわけだ。そして、そのような状況の中で「チャウとチャンの関係性」が描かれていくのである。個人的には、「よくもまあこんな設定の物語を成立させたものだ」と感じさせられた。思っているより難しい設定なんじゃないだろうか。
あわせて読みたい
【魅惑】バーバラ・ローデン監督・脚本・主演の映画『WANDA』の、70年代の作品とは思えない今感
映画館で観た予告が気になって、それ以外の情報を知らずに観に行った映画『WANDA』なんと70年代の映画だと知って驚かされた。まったく「古さ」を感じなかったからだ。主演だけでなく、監督・脚本も務めたバーバラ・ローデンが遺した、死後評価が高まった歴史的一作
私の場合は、「互いの伴侶が不倫している」という設定に気づくのにとにかく相当時間が掛かったため、前半から中盤の描写に関しては「よく分からない」と感じるものが多かった。恐らく、その設定を知った上で観ていたら、もっと細かな描写に気づけたはずだと思う。そういう視点で改めて観直してみたい気もする。
さて本作では、ラスト付近で「カンボジアの実際のニュース映像」が挿入されたり、あるいは「チャウがアンコールワットと思しき場所で佇むシーン」が映し出されたりするのだが、これらの意味が私にはよく分からなかった。恐らく、何か時代背景を踏まえた上での描写なのだろう。こういう部分も含めて理解できると、ウォン・カーウァイ作品をより楽しめるのだろうと思う。
『2046』
『2046』には、『恋する惑星』で短髪の女性を演じた役者が再び出てきたが、やはり彼女の存在感がとても素敵に感じられた。彼女は「日本人と付き合っていることを父親から反対されている役」であり、特に後半で中心的に描かれていく。また彼女は、作中で「アンドロイド」としても登場するのである。この後内容に触れるが、本作は文字で説明しようとするとちょっとややこしくなってしまう作品だ。いずれにせよ、アンドロイド役も担うというトリッキーさも含め、とても興味深かった。
物語の設定・展開の紹介
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
映画冒頭は、とてもSF的な感じでスタートする。木村拓哉演じるタクが、延々に止まらない高速列車の中にいるという状況が映し出されるのだ。彼は「『2046』から初めて戻ってきた男」である。
「2046」というのは、小説『2046』で描かれるある場所のことだ。そしてその小説の作者が、様々な女性と関わりを持つ、トニー・レオン演じる主人公チャウである。小説中では、多くの人が「何かを探すため」に「2046」を目指している。「『2046』では何も変化が起こらない」とされているため、多くの人が「そんな不変的な場所であれば、探しているものが見つかるかもしれない」と考えて「2046」を目指しているのだ。しかし基本的に、「2046」を訪れた者はそこから出ることが出来ない。そして、そんな「2046」から初めて戻ってきた人物こそタクなのだ。チャウとタクは現実世界で知り合いであり、そんなタクと付き合っている女性が、小説『2046』の世界では「wjw1967」というアンドロイド(フェイ・ウォン)として登場する。チャウは、身近な人間を小説に登場させるのだ。
現実の物語は、1966年に始まる。シンガポールにいたチャウは、夫のいる女性と恋仲になってしまったのだ。彼は香港へと戻るタイミンで、彼女に「一緒に行こう」と提案するも、断られてしまう。その後香港に戻った彼は新聞にコラムを書くようになったが、それだけでは暮らせなかったため官能小説を執筆し始める。
あわせて読みたい
【感想】世の中と足並みがそろわないのは「正常が異常」だから?自分の「正常」を守るために:『コンビ…
30代になっても未婚でコンビニアルバイトの古倉さんは、普通から外れたおかしな人、と見られてしまいます。しかし、本当でしょうか?『コンビニ人間』をベースに、多数派の人たちの方が人生を自ら選択していないのではないかと指摘する。
チャウはある日、クラブで古い友人ルルと再会したのだが、彼女は自分のことを覚えていなかった。その後ルルが酔い潰れてしまったため、チャウが彼女をホテルの部屋まで連れて行くと、その部屋番号が2046だったのだ。こうして「ルルと再会したこと」「2046という部屋番号を目にしたこと」がきっかけとなり、彼は後に『2046』という小説を書くことになるのである。

その後しばらくしてから2046号室を訪ねたが、既にルルはいなくなっていた。そこでチャウはホテルに、「2046号室を借りたい」と申し出る。しかし「改装する必要があるため、一旦2047号室に入ってもらえないか」と言われたチャウはそのまま2047号室を借りることにした。すると隣から、チャウには聞き馴染みのない言葉(実は日本語である)の独り言が聞こえてくることに気づく。その独り言は、日本人と付き合っているホテルオーナーの長女のものだった……。
あわせて読みたい
【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…
誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます
映画の感想
時代背景や舞台設定などは『花様年華』とのリンクを感じさせる。実際、『花様年華』には「2046号室の部屋番号が映し出される場面」が出てきた。『2046』を見てようやく、そのシーンの意味が理解できるというわけだ。また、このようなことをちゃんと思い出せるのも、短期間で一気見した良さと言えるだろう。時間を空けて見ていたらたぶん忘れていたと思う。さらに、『恋する惑星』や『天使の涙』ともどことなく繋がりを感じさせる物語であり、ウォン・カーウァイ作品の魅力はそんな部分にも現れているのだろうと感じた。
さて、本作を観た時点では知らなかったことなのだが、「2046」という数字は香港人にとって大きな意味があるのだという。よく知られているように、香港はイギリスから中国に返還された後も、「一国二制度」という形で、中国とは異なるルールで運用されてきた。ただし、返還に際して定められた法律によって、「2046年までは現行ルールのままの体制をを保証する」と決まっているのだ。
実際には、ニュースでもよく取り上げられていたように、香港に対する中国からの介入が強くなり、それに反発した若者らがデモを起こすようになっていった。「2046年まで現行ルールを保証する」というのは空手形だったと言う他ないだろう。しかし、少なくとも本作『2046』が制作された時点では、「香港はまだ大丈夫」という感覚が強かったはずだ。そしてそのような時代においては、「2046」という数字はとても大きなものだったのだろうと思う。
あわせて読みたい
【革命】電子音楽誕生の陰に女性あり。楽器ではなく機械での作曲に挑んだ者たちを描く映画:『ショック…
現代では当たり前の「電子音楽」。その黎明期には、既存の音楽界から排除されていた女性が多く活躍した。1978年、パリに住む1人の女性が「電子音楽」の革命の扉をまさに開こうとしている、その1日を追う映画『ショック・ド・フューチャー』が描き出す「創作の熱狂」
ウォン・カーウァイ作品はこのように、もちろん知らずに観ても十分楽しめるのだが、知っていればより深く作品を理解できるような仕掛けに溢れており、「スタイリッシュさ」だけではない魅力も満載なのである。ちなみに本作にも、魅力的な女性がたくさん出てきた。ウォン・カーウァイ作品を女性がどのように鑑賞するのか分からないが、男としてはやはり、「登場する女性が魅力的」という点は、ウォン・カーウァイ作品において最も強くアピールする部分だなと思う。
『ブエノスアイレス』
さて、本記事は基本的に「観た順番に感想を書く」という形をとってきたが、4番目に観た『ブエノスアイレス』の感想を最後に持ってきたのは、冒頭でも書いた通り、私にはちょっと受け入れられない作品だったからである。
まあその理由はとにかくシンプルだ。ついさっき書いた通り、私にとって「ウォン・カーウァイ作品」の最もキャッチーな魅力は「登場する女性が魅力的」という部分にあるわけで、そのため「男性同士の恋愛」を描く本作には上手く嵌まらなかったのだろうなぁ、と思っている。
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
ここまで散々書いてきたことだが、私が観た「ウォン・カーウァイ作品」は、「ストーリーがよく分からない」と感じるものが多かった。しかしそれでも魅力的に感じられたのは、やはり「作品全体が放つ雰囲気」に惹かれたからだろう。そして、そのような雰囲気をもたらしている一番の要因が、「『よく分かんないけど魅力的に見える女性』がたくさん出てきたこと」だと思う。
そういう部分に強く惹かれていた人間としてはやはり、『ブエノスアイレス』はあまり面白いとは感じられなかった。まあこれは完全に私の好みの問題だ。それに正直、ずっと「うーん」と思いながら観ていたので、作品を的確に捉えられているとも思えない。私の評価をあまり参考にしない方がいいだろう。

ただ、さすがだなと感じたのは「映像の美しさ」である。私は、何で目にしたのか覚えていないのだが、「ウォン・カーウァイ作品は、どこを切り取ってもポストカードになる」みたいな指摘を見かけたことがあり、なるほど確かにその通りだと感じた。また本作は、セックスシーンなんかをかなりリアルに映し出す作品なので、そういう意味でも一層「映像の美しさ」は重要になると言えるだろう。その辺りの手腕はさすがだなと思う。
あわせて読みたい
【感想】殺人事件が決定打となった「GUCCI家の崩壊」の実話を描く映画『ハウス・オブ・グッチ』の衝撃
GUCCI創業家一族の1人が射殺された衝撃の実話を基にした映画『ハウス・オブ・グッチ』。既に創業家一族は誰一人関わっていないという世界的ブランドGUCCIに一体何が起こったのか? アダム・ドライバー、レディー・ガガの演技も見事なリドリー・スコット監督作
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
個人的にはやはり、『恋する惑星』『天使の涙』の印象がとても強かった。そして、普段は映画を「頭で鑑賞する」ことが多い私には珍しく、「身体が弾んでいく」ような感覚をもたらしてくれる作品で、とにかく魅力的に感じられたのである。また、デモが常態化してしまった香港ばかり目にしていた我々には、ウォン・カーウァイ作品に閉じ込められた「まばゆい香港」の姿にもどことなく郷愁的な感覚を抱かされるのではないかと思う。
とにかく、出会えて良かったと思える作品だった。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…
私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『国宝』は圧巻だった!吉沢亮の女形のリアル、圧倒的な映像美、歌舞伎の芸道の狂気(…
映画『国宝』は、ちょっと圧倒的すぎる作品だった。原作・監督・役者すべての布陣が最強で、「そりゃ良い作品になるよね」という感じではあったが、そんな期待をあっさりと超えていくえげつない完成度は圧巻だ。あらゆる意味で「血」に翻弄される主人公・喜久雄の「狂気の生涯」を、常軌を逸したレベルで描き出す快作である
あわせて読みたい
【感想】映画『ファーストキス 1ST KISS』は、「過去に戻り未来を変える物語」として脚本が秀逸(監督…
映画『ファーストキス 1ST KISS』は、稀代の脚本家である坂元裕二の手腕が存分に発揮された作品。「過去にタイムスリップして未来を変える」というありがちな設定をベースにしながら、様々な「特異さ」を潜ませた物語は、とにかく絶妙に上手かったし面白かった。設定も展開も役者の演技もすべて秀逸な、実に面白いエンタメ作品
あわせて読みたい
【感想】実写映画『からかい上手の高木さん』(今泉力哉)は「あり得ない関係」を絶妙に描く(主演:永…
私は実写映画『からかい上手の高木さん』を「今泉力哉の最新作」として観に行った。常に「普通には成立しないだろう関係性」を描き出す今泉力哉作品らしく、本作でもそんな「絶妙にややこしい関係」が映し出されている。「正解がない」からこそ「すべてが正解になる」はずの「恋愛」をベースに、魅力的な関わりを描き出す物語
あわせて読みたい
【相違】友人の友人が作ったZINE『our house』には様々な「恋愛に惑う気持ち」が詰まっている
ひょんなことから知り合った女性が制作したZINE『our house』は、「恋愛」や「友情」に対して私が以前から抱いていた感覚にかなり近い内容で、実に興味深い。特に「恋愛においても、自分のことを性別で捉えられたくない」という感覚は新鮮で、そこから「男性は『恋愛的に惹かれている』という感覚を持たないかも」とも考えた
あわせて読みたい
【あらすじ】驚きの設定で「死と生」、そして「未練」を描く映画『片思い世界』は実に素敵だった(監督…
広瀬すず・杉咲花・清原果耶という超豪華俳優が主演を務める映画『片思い世界』は、是非、何も知らないまま観て下さい。この記事ではネタバレをせずに作品について語っていますが、それすらも読まずにまっさらな状態で鑑賞することをオススメします。「そうであってほしい」と感じてしまうような世界が“リアル”に描かれていました
あわせて読みたい
【あらすじ】「夢を追い求めた先」を辛辣に描く映画『ネムルバカ』は「ダルっとした会話」が超良い(監…
映画『ネムルバカ』は、まず何よりも「ダルっとした会話・日常」が素晴らしい作品です。そしてその上で、「夢を追い求めること」についてのかなり現代的な感覚を描き出していて、非常に印象的でした。「コスパが悪い」という言い方で「努力」を否定したくなる気持ちも全然理解できるし、若い人たちは特に大変だろうなと思います
あわせて読みたい
【死】映画『ミッキー17』は、「何度でも生まれ変われる」ってありがち設定を魅力的な物語に変えた(監…
映画『ミッキー17』は、「ありきたりな設定」がベースにあるのに、エンタメとしても考えさせる物語としても非常に興味深く面白い作品だった。「1人の人間が複数の肉体を持つこと」を禁じた法律の存在により絶妙な面白さとなっていると言えるだろう。さらにイカれた夫婦の言動もぶっ飛んでいて、そういう意味でも興味深い作品だ
あわせて読みたい
【切実】映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』は河合優実目当てだったが伊東蒼が超最高!(…
映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』は、伊東蒼演じるさっちゃんがひたすらに独白し続けるシーンがとにかく圧巻で、恋しさとせつなさと心強さが無限に伝わる最高すぎるシーンだった!「想いを伝えたい気持ち」と「伝えることの暴力性」の間で葛藤しながら、それでも喋らずにはいられない想いの強さが素敵すぎる
あわせて読みたい
【丁寧】筒井康隆『敵』を吉田大八が映画化!死を見定めた老紳士が囚われた狂気的日常を描く(主演:長…
映画『敵』(吉田大八監督)は、原作が筒井康隆だけのことはあり、物語はとにかく意味不明だった。しかしそれでも「面白い」と感じさせるのだから凄いものだと思う。前半では「イケオジのスローライフ」が丁寧に描かれ、そこから次第に、「元大学教授が狂気に飲み込まれていく様」が淡々と、しかし濃密に描かれていく
あわせて読みたい
【あらすじ】のん(能年玲奈)が実に素敵な映画『私にふさわしいホテル』が描く文壇の変な世界(監督:…
「こんな奴いないだろ」というような人物を絶妙な雰囲気で演じるのん(能年玲奈)の存在感がとにかく素敵な映画『私にふさわしいホテル』では、小説家・編集者がワチャワチャする「文壇」の世界が描かれる。無名の新人と大御所がハチャメチャなバトルを繰り広げるストーリーに、様々な「皮肉」が散りばめられた、なかなか痛快な物語
あわせて読みたい
【人生】映画『雪子 a.k.a.』は、言葉は出ないが嘘もないラップ好きの小学校教師の悩みや葛藤を描き出す
「小学校教師」と「ラップ」というなかなか異色の組み合わせの映画『雪子 a.k.a.』は、「ここが凄く良かった」と言えるようなはっきりしたポイントはないのに、ちょっと泣いてしまうぐらい良い映画だった。「口下手だけど嘘はない」という主人公・雪子の日常的な葛藤には、多くの人が共感させられるのではないかと思う
あわせて読みたい
【包容】映画『違国日記』を観て思う。「他者との接し方」が皆こうだったらもっと平和なはずだって(主…
映画『違国日記』は、人見知りの小説家・高代槙生が両親を亡くした姪・朝を引き取り一緒に暮らすところから始まる物語で、槙生と朝を中心とした様々な人間関係が絶妙に描かれている作品でした。人付き合いが苦手ながら、15歳という繊細な存在を壊さないように、でも腫れ物みたいには扱わないように慎重になる槙生のスタンスが素敵です
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『夏目アラタの結婚』は黒島結菜が演じた品川真珠の歯並びが凄い(でもかわいい)(監…
映画『夏目アラタの結婚』は、まずとにかく、黒島結菜が演じた主人公・品川真珠のビジュアルが凄まじかった。原作者が「譲れない」と言ったという「ガタガタの汚い歯」の再現が凄まじく、これだけで制作陣の本気度が伝わるくらい。ストーリー展開も見事で、もう1人の主人公が最終的に思いがけない実感に行き着く流れも興味深い
あわせて読みたい
【全力】圧巻の演奏シーンに驚愕させられた映画『BLUE GIANT』。ライブ中の宮本はとにかく凄い(主演:…
映画『BLUE GIANT』は、「演奏シーン」がとにかく圧倒的すぎる作品でした。ストーリーは、これ以上シンプルには出来ないだろうというぐらいシンプルなのですが、「王道的物語」だからこその感動もあります。また、全体の1/4がライブシーンらしく、その視覚的な演出も含めて、まさに「音楽を体感する映画」だと言えるでしょう
あわせて読みたい
【迷路】映画『国境ナイトクルージング』は、青春と呼ぶにはちょっと大人な3人の関係を丁寧に描く
映画『国境ナイトクルージング』は、男2人女1人の3人による、「青春」と呼ぶには少し年を取りすぎてしまったビターな関係を描き出す物語。説明が少なく、また、様々な示唆的な描写の意味するところを捉えきれなかったためり、「分からないこと」が多かったのだが、全体的な雰囲気が素敵で好きなタイプの作品だった
あわせて読みたい
【失恋】ひたすらカオスに展開する映画『エターナル・サンシャイン』は、最後まで観ると面白い!(主演…
映画『エターナル・サンシャイン』は、冒頭からしばらくの間、とにかくまったく意味不明で、「何がどうなっているのか全然分からない!」と思いながら観ていました。しかし、映像がカオスになるにつれて状況の理解は進み始め、最終的には「よくもまあこんな素っ頓狂なストーリーを理解できる物語に落とし込んだな」と感心させられました
あわせて読みたい
【友情】セリフの無い映画『ロボット・ドリームズ』は、そのシンプルさ故に深い感動へと連れて行く
映画『ロボット・ドリームズ』は、普通に考えれば「映画としては成立しない」と思えるほどシンプルすぎる「幼児向けの絵本」のような内容なのだが、「セリフが一切無い」という特殊な構成によって感動的な作品に仕上がっている。お互いを想い合う「ドッグ」と「ロボット」の関係性が胸に染み入る、とても素敵な作品だ
あわせて読みたい
【奇妙】映画『画家と泥棒』は、非日常的なきっかけで始まったあり得ないほど奇跡的な関係を描く
映画『画家と泥棒』は、「自身の絵を盗まれた画家が、盗んだ泥棒と親しくなる」という奇妙奇天烈なきっかけから関係性が始まる物語であり、現実に起きたこととは思えないほど不可思議なドキュメンタリーである。アートを通じて奇妙に通じ合う2人の関係性は、ある種の美しささえ感じさせる、とても素晴らしいものに見えた
あわせて読みたい
【恐怖】「1970年代の生放送の怪しげなテレビ番組」を見事に再現したフェイクドキュメンタリー:映画『…
映画『悪魔と夜ふかし』は、「1970年代に放送されていた生放送番組のマスターテープが発見された」というテイで、ハロウィンの夜の放送回をそのまま流すという設定のモキュメンタリーである。番組の細部までリアルに作り込まれており、それ故に、「悪魔の召喚」という非現実的な状況もするっと受け入れられる感じがした
あわせて読みたい
【煌めき】映画『HAPPYEND』が描く、”監視への嫌悪”と”地震への恐怖”の中で躍動する若者の刹那(監督:…
映画『HAPPYEND』は、「監視システム」と「地震」という「外的な制約条件」を設定し、その窮屈な世界の中で屈せずに躍動しようとする若者たちをリアルに描き出す物語である。特に、幼稚園からの仲であるコウとユウタの関係性が絶妙で、演技未経験だという2人の存在感と映像の雰囲気が相まって、実に素敵に感じられた
あわせて読みたい
【天才】映画『アット・ザ・ベンチ』面白すぎる!蓮見翔の脚本に爆笑、生方美久の会話劇にうっとり(監…
役者も脚本家も監督も何も知らないまま、「有名な役者が出てこないマイナーな映画」だと思い込んで観に行った映画『アット・ザ・ベンチ』は、衝撃的に面白い作品だった。各話ごと脚本家が異なるのだが、何よりも、第2話「回らない」を担当したダウ90000・蓮見翔の脚本が超絶面白い。あまりの衝撃にぶっ飛ばされてしまった
あわせて読みたい
【豪快】これまで観た中でもトップクラスに衝撃的だった映画『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』(…
私は、シリーズ最新作『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』と、そのメイキングが中心のドキュメンタリー映画しか観ていませんが、あらゆる要素に圧倒される素晴らしい鑑賞体験でした。アクションシーンの凄まじさはもちろん、個人的には、杉本ちさとと深川まひろのダルダルな会話がとても好きで、混ざりたいなとさえ思います
あわせて読みたい
【葛藤】映画『きみの色』(山田尚子)は、感受性が強すぎる若者のリアルをバンドを通じて描き出す(主…
山田尚子監督作『きみの色』は、これといった起伏のないストーリー展開でありながら、「若い世代の繊細さに満ちた人間関係」をとてもリアルに描き出す雰囲気が素敵な作品。「悩み・葛藤を抱えている状態が日常である」という雰囲気をベースにしつつ、「音楽」を起点に偶然繋がった3人の緩やかな日々を描き出す物語に惹きつけられた
あわせて読みたい
【繊細】映画『ぼくのお日さま』(奥山大史)は、小さな世界での小さな恋を美しい映像で描く(主演:越…
映画『ぼくのお日さま』は、舞台設定も人間関係も実にミニマムでありながら、とても奥行きのある物語が展開される作品。予告編で「3つの恋」と言及されなければ、描かれるすべての「恋」には気付けなかっただろうと思うくらいの繊細な関係性と、映像・音楽を含めてすべてが美しい旋律として奏でられる物語がとても素敵でした
あわせて読みたい
【異例】東映京都撮影所が全面協力!自主制作の時代劇映画『侍タイムスリッパー』は第2の『カメ止め』だ…
映画『侍タイムスリッパー』は、「自主制作映画なのに時代劇」「撮影スタッフ10人なのに東映京都撮影所全面協力」「助監督役が実際の助監督も務めている」など、中身以外でも話題に事欠かない作品ですが、何もよりも物語が実に面白い!「幕末の侍が現代にタイムスリップ」というよくある設定からこれほど面白い物語が生まれるとは
あわせて読みたい
【面白い】映画『ラストマイル』は、物流問題をベースに「起こり得るリアル」をポップに突きつける(監…
映画『ラストマイル』は、「物流」という「ネット社会では誰にでも関係し得る社会問題」に斬り込みながら、実に軽妙でポップな雰囲気で展開されるエンタメ作品である。『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界で展開される「シェアード・ユニバース」も話題で、様々な人の関心を広く喚起する作品と言えるだろう
あわせて読みたい
【宣伝】アポロ計画での月面着陸映像は本当か?映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』のリアル
「月面着陸映像はニセモノだ」という陰謀論を逆手にとってリアリティのある物語を生み出した映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』は、「ベトナム戦争で疲弊し、事故続きのNASAが不人気だった」という現実を背景に「歴史のif」を描き出す。「確かにそれぐらいのことはするかもしれない」というリアリティをコメディタッチで展開させる
あわせて読みたい
【感想】B級サメ映画の傑作『温泉シャーク』は、『シン・ゴジラ』的壮大さをバカバカしく描き出す
「温泉に入っているとサメに襲われる」という荒唐無稽すぎる設定のサメ映画『温泉シャーク』は、確かにふざけ倒した作品ではあるものの、観てみる価値のある映画だと思います。サメの生態を上手く利用した設定や、「伏線回収」と表現していいだろう展開などが巧みで、細かなことを気にしなければ、そのバカバカしさを楽しめるはずです
あわせて読みたい
【恋心】映画『サッドティー』は、「『好き』を巡ってウロウロする人々」を描く今泉力哉節全開の作品だった
映画『サッドティー』は、今泉力哉らしい「恋愛の周辺でグルグルする人たち」を描き出す物語。関係性が微妙に重なる複数の人間を映し出す群像劇の中で、「『好き』のややこしさ」に焦点を当てていく構成はさすがです。実に奇妙な展開で終わる物語ですが、それでもなお「リアルだ」と感じさせる雰囲気は、まるで魔法のようでした
あわせて読みたい
【興奮】超弩級の韓国映画『THE MOON』は、月面着陸挑戦からの遭難・救出劇が凄まじい(出演:ソル・ギ…
韓国映画『THE MOON』は「月に取り残された宇宙飛行士を救助する」という不可能すぎる展開をリアルに描き出す物語だ。CGを駆使した圧倒的な映像体験だけではなく、「5年前の甚大な事故を契機にわだかまりを抱える者たち」を絶妙に配することで人間関係的にも魅せる展開を作り出す、弩級のエンタメ作品
あわせて読みたい
【絶妙】映画『水深ゼロメートルから』(山下敦弘)は、何気ない会話から「女性性の葛藤」を描く(主演…
高校演劇を舞台化する企画第2弾に選ばれた映画『水深ゼロメートルから』は、「水のないプール」にほぼ舞台が固定された状態で、非常に秀逸な会話劇として展開される作品だ。退屈な時間を埋めるようにして始まった「ダルい会話」から思いがけない展開が生まれ、「女として生きること」についての様々な葛藤が描き出される点が面白い
あわせて読みたい
【狂気】押見修造デザインの「ちーちゃん」(映画『毒娘』)は「『正しさ』によって歪む何か」の象徴だ…
映画『毒娘』は、押見修造デザインの「ちーちゃん」の存在感が圧倒的であることは確かなのだが、しかし観ていくと、「決して『ちーちゃん』がメインなわけではない」ということに気づくだろう。本作は、全体として「『正しさ』によって歪む何か」を描き出そうとする物語であり、私たちが生きる社会のリアルを抉り出す作品である
あわせて読みたい
【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…
映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった
あわせて読みたい
【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ
映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています
あわせて読みたい
【幻惑】映画『フォロウィング』の衝撃。初監督作から天才だよ、クリストファー・ノーラン
クリストファー・ノーランのデビュー作であり、多数の賞を受賞し世界に衝撃を与えた映画『フォロウィング』には、私も驚かされてしまった。冒頭からしばらくの間「何が描かれているのかさっぱり理解できない」という状態だったのに、ある瞬間一気に視界が晴れたように状況が理解できたのだ。脚本の力がとにかく圧倒的だった
あわせて読みたい
【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…
映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です
あわせて読みたい
【衝撃】広末涼子映画デビュー作『20世紀ノスタルジア』は、「広末が異常にカワイイ」だけじゃない作品
広末涼子の映画デビュー・初主演作として知られる『20世紀ノスタルジア』は、まず何よりも「広末涼子の可愛さ」に圧倒される作品だ。しかし、決してそれだけではない。初めは「奇妙な設定」ぐらいにしか思っていなかった「宇宙人に憑依されている」という要素が、物語全体を実に上手くまとめている映画だと感じた
あわせて読みたい
【感想】アニメ映画『パーフェクトブルー』(今敏監督)は、現実と妄想が混在する構成が少し怖い
本作で監督デビューを果たした今敏のアニメ映画『パーフェクトブルー』は、とにかくメチャクチャ面白かった。現実と虚構の境界を絶妙に壊しつつ、最終的にはリアリティのある着地を見せる展開で、25年以上も前の作品だなんて信じられない。今でも十分通用するだろうし、81分とは思えない濃密さに溢れた見事な作品である
あわせて読みたい
【怖い?】映画『アメリ』(オドレイ・トトゥ主演)はとても奇妙だが、なぜ人気かは分かる気がする
名作として知られているものの観る機会の無かった映画『アメリ』は、とても素敵な作品でした。「オシャレ映画」という印象を持っていて、それは確かにその通りなのですが、それ以上に私は「主人公・アメリの奇妙さ」に惹かれたのです。普通には成立しないだろう展開を「アメリだから」という謎の説得力でぶち抜く展開が素敵でした
あわせて読みたい
【あらすじ】声優の幾田りらとあのちゃんが超絶良い!アニメ映画『デデデデ』はビビるほど面白い!:『…
幾田りらとあのちゃんが声優を務めた映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』は、とにかく最高の物語だった。浅野いにおらしいポップさと残酷さを兼ね備えつつ、「終わってしまった世界でそれでも生きていく」という王道的展開を背景に、門出・おんたんという女子高生のぶっ飛んだ関係性が描かれる物語が見事すぎる
あわせて読みたい
【感想】映画『レオン』は、殺し屋マチルダを演じたナタリー・ポートマンがとにかく素晴らしい(監督:…
映画『レオン』は、その性質ゆえに物議を醸す作品であることも理解できるが、私はやはりナタリー・ポートマンに圧倒されてしまった。絶望的な事態に巻き込まれたマチルダの葛藤と、そんな少女と共に生きることになった中年男性レオンとの関係性がとても見事に映し出されている。実に素敵な作品だった
あわせて読みたい
【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…
映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった
あわせて読みたい
【評価】映画『ゴジラ-1.0』(山崎貴監督)は面白い!迫力満点の映像と絶妙な人間ドラマ(米アカデミー…
米アカデミー賞で視覚効果賞を受賞した映画『ゴジラ-1.0』(山崎貴監督)は、もちろんそのVFXに圧倒される物語なのだが、「人間ドラマ」をきちんと描いていることも印象的だった。「終戦直後を舞台にする」という、ゴジラを描くには様々な意味でハードルのある設定を見事に活かした、とても見事な作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『レザボア・ドッグス』(タランティーノ監督)はとにかく驚異的に脚本が面白い!
クエンティン・タランティーノ初の長編監督作『レザボア・ドッグス』は、のけぞるほど面白い映画だった。低予算という制約を逆手に取った「会話劇」の構成・展開があまりにも絶妙で、舞台がほぼ固定されているにも拘らずストーリーが面白すぎる。天才はやはり、デビュー作から天才だったのだなと実感させられた
あわせて読みたい
【感想】映画『ローマの休日』はアン王女を演じるオードリー・ヘプバーンの美しさが際立つ名作
オードリー・ヘプバーン主演映画『ローマの休日』には驚かされた。現代の視点で観ても十分に通用する作品だからだ。まさに「不朽の名作」と言っていいだろう。シンプルな設定と王道の展開、そしてオードリー・ヘプバーンの時代を超える美しさが相まって、普通ならまずあり得ない見事なコラボレーションが見事に実現している
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『千年女優』(今敏)はシンプルな物語を驚愕の演出で味付けした天才的アニメ作品
今敏監督の映画『千年女優』は、ちょっとびっくりするほど凄まじく面白い作品だった。観ればスッと理解できるのに言葉で説明すると難解になってしまう「テクニカルな構成」に感心させられつつ、そんな構成に下支えされた「物語の感性的な部分」がストレートに胸を打つ、シンプルながら力強い作品だ
あわせて読みたい
【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…
映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ
あわせて読みたい
【考察】映画『街の上で』(今泉力哉)が描く「男女の友情は成立する」的会話が超絶妙で素晴らしい(出…
映画『街の上で』(今泉力哉監督)は、「映画・ドラマ的会話」ではない「自然な会話」を可能な限り目指すスタンスが見事だった。「会話の無駄」がとにかく随所に散りばめられていて、そのことが作品のリアリティを圧倒的に押し上げていると言える。ある男女の”恋愛未満”の会話もとても素晴らしかった
あわせて読みたい
【助けて】映画『生きててごめんなさい』は、「共依存カップル」視点で生きづらい世の中を抉る物語(主…
映画『生きててごめんなさい』は、「ちょっと歪な共依存関係」を描きながら、ある種現代的な「生きづらさ」を抉り出す作品。出版社の編集部で働きながら小説の新人賞を目指す園田修一は何故、バイトを9度もクビになり、一日中ベッドの上で何もせずに過ごす同棲相手・清川莉奈を”必要とする”のか?
あわせて読みたい
【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!
かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ
あわせて読みたい
【希望】誰も傷つけたくない。でも辛い。逃げたい。絶望しかない。それでも生きていく勇気がほしい時に…
2006年発売、2021年文庫化の『私を見て、ぎゅっと愛して』は、ブログ本のクオリティとは思えない凄まじい言語化力で、1人の女性の内面の葛藤を抉り、読者をグサグサと突き刺す。信じがたい展開が連続する苦しい状況の中で、著者は大事なものを見失わず手放さずに、勇敢に前へ進んでいく
あわせて読みたい
【理解】「多様性を受け入れる」とか言ってるヤツ、映画『炎上する君』でも観て「何も見てない」って知…
西加奈子の同名小説を原作とした映画『炎上する君』(ふくだももこ監督)は、「多様性」という言葉を安易に使いがちな世の中を挑発するような作品だ。「見えない存在」を「過剰に装飾」しなければならない現実と、マジョリティが無意識的にマイノリティを「削る」リアルを描き出していく
あわせて読みたい
【映画】ストップモーションアニメ『マルセル 靴をはいた小さな貝』はシンプルでコミカルで面白い!
靴を履いた体長2.5センチの貝をコマ撮りで撮影したストップモーション映画『マルセル 靴をはいた小さな貝』は、フェイクドキュメンタリーの手法で描き出すリアリティ満載の作品だ。謎の生き物が人間用の住居で工夫を凝らしながら生活する日常を舞台にした、感情揺さぶる展開が素晴らしい
あわせて読みたい
【歴史】NIKEのエアジョーダン誕生秘話!映画『AIR/エア』が描くソニー・ヴァッカロの凄さ
ナイキがマイケル・ジョーダンと契約した時、ナイキは「バッシュ業界3位」であり、マイケル・ジョーダンも「ドラフト3位選手」だった。今からは信じられないだろう。映画『AIR/エア』は、「劣勢だったナイキが、いかにエアジョーダンを生み出したか」を描く、実話を基にした凄まじい物語だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『四畳半タイムマシンブルース』超面白い!森見登美彦も上田誠も超天才だな!
ヨーロッパ企画の演劇『サマータイムマシン・ブルース』の物語を、森見登美彦の『四畳半神話大系』の世界観で描いたアニメ映画『四畳半タイムマシンブルース』は、控えめに言って最高だった。ミニマム過ぎる設定・物語を突き詰め、さらにキャラクターが魅力的だと、これほど面白くなるのかというお手本のような傑作
あわせて読みたい
【天才】映画『リバー、流れないでよ』は、ヨーロッパ企画・上田誠によるタイムループの新発明だ
ヨーロッパ企画の上田誠が生み出した、タイムループものの新機軸映画『リバー、流れないでよ』は、「同じ2分間が繰り返される」という斬新すぎる物語。その設定だけ聞くと、「どう物語を展開させるんだ?」と感じるかもしれないが、あらゆる「制約」を押しのけて、とんでもない傑作に仕上がっている
あわせて読みたい
【感動】円井わん主演映画『MONDAYS』は、タイムループものの物語を革新する衝撃的に面白い作品だった
タイムループという古びた設定と、ほぼオフィスのみという舞台設定を駆使した、想像を遥かに超えて面白かった映画『MONDAYS』は、テンポよく進むドタバタコメディでありながら、同時に、思いがけず「感動」をも呼び起こす、竹林亮のフィクション初監督作品
あわせて読みたい
【感想】のん主演映画『私をくいとめて』から考える、「誰かと一緒にいられれば孤独じゃないのか」問題
のん(能年玲奈)が「おひとり様ライフ」を満喫する主人公を演じる映画『私をくいとめて』を観て、「孤独」について考えさせられた。「誰かと関わっていられれば孤独じゃない」という考えに私は賛同できないし、むしろ誰かと一緒にいる時の方がより強く孤独を感じることさえある
あわせて読みたい
【感想】映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)の稲垣吾郎の役に超共感。「好きとは何か」が分からない人へ
映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)は、稲垣吾郎演じる主人公・市川茂巳が素晴らしかった。一般的には、彼の葛藤はまったく共感されないし、私もそのことは理解している。ただ私は、とにかく市川茂巳にもの凄く共感してしまった。「誰かを好きになること」に迷うすべての人に観てほしい
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
あわせて読みたい
【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい
「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる
あわせて読みたい
【感想】映画『竜とそばかすの姫』が描く「あまりに批判が容易な世界」と「誰かを助けることの難しさ」
SNSの登場によって「批判が容易な社会」になったことで、批判を恐れてポジティブな言葉を口にしにくくなってしまった。そんな世の中で私は、「理想論だ」と言われても「誰かを助けたい」と発信する側の人間でいたいと、『竜とそばかすの姫』を観て改めて感じさせられた
あわせて読みたい
【評価】映画『シン・ゴジラ』は、「もしゴジラが実際に現れたら」という”現実”を徹底的にリアルに描く
ゴジラ作品にも特撮映画にもほとんど触れてこなかったが、庵野秀明作品というだけで観に行った『シン・ゴジラ』はとんでもなく面白かった。「ゴジラ」の存在以外のありとあらゆるものを圧倒的なリアリティで描き出す。「本当にゴジラがいたらどうなるのか?」という”現実”の描写がとにかく素晴らしかった
あわせて読みたい
【世界観】映画『夜は短し歩けよ乙女』の”黒髪の乙女”は素敵だなぁ。ニヤニヤが止まらない素晴らしいアニメ
森見登美彦の原作も大好きな映画『夜は短し歩けよ乙女』は、「リアル」と「ファンタジー」の境界を絶妙に漂う世界観がとても好き。「黒髪の乙女」は、こんな人がいたら好きになっちゃうよなぁ、と感じる存在です。ずっとニヤニヤしながら観ていた、とても大好きな映画
あわせて読みたい
【考察】生きづらい性格は変わらないから仮面を被るしかないし、仮面を被るとリア充だと思われる:『勝…
「リア充感」が滲み出ているのに「生きづらさ」を感じてしまう人に、私はこれまでたくさん会ってきた。見た目では「生きづらさ」は伝わらない。24年間「リアル彼氏」なし、「脳内彼氏」との妄想の中に生き続ける主人公を描く映画『勝手にふるえてろ』から「こじらせ」を知る
あわせて読みたい
【感想】映画『若おかみは小学生!』は「子どもの感情」を「大人の世界」で素直に出す構成に号泣させられる
ネット記事を読まなければ絶対に観なかっただろう映画『若おかみは小学生!』は、基本的に子ども向け作品だと思うが、大人が観てもハマる。「大人の世界」でストレートに感情を表に出す主人公の小学生の振る舞いと成長に、否応なしに感動させられる
あわせて読みたい
【漫画原作】映画『殺さない彼と死なない彼女』は「ステレオタイプな人物像」の化学反応が最高に面白い
パッと見の印象は「よくある学園モノ」でしかなかったので、『殺さない彼と死なない彼女』を観て驚かされた。ステレオタイプで記号的なキャラクターが、感情が無いとしか思えないロボット的な言動をする物語なのに、メチャクチャ面白かった。設定も展開も斬新で面白い
あわせて読みたい
【無知】映画『生理ちゃん』で理解した気になってはいけないが、男(私)にも苦労が伝わるコメディだ
男である私にはどうしても理解が及ばない領域ではあるが、女友達から「生理」の話を聞く機会があったり、映画『生理ちゃん』で視覚的に「生理」の辛さが示されることで、ちょっとは分かったつもりになっている。しかし男が「生理」を理解するのはやっぱり難しい
あわせて読みたい
【驚嘆】この物語は「AIの危険性」を指摘しているのか?「完璧な予知能力」を手にした人類の過ち:『預…
完璧な未来予知を行えるロボットを開発し、地震予知のため”だけ”に使おうとしている科学者の自制を無視して、その能力が解放されてしまう世界を描くコミック『預言者ピッピ』から、「未来が分からないからこそ今を生きる価値が生まれるのではないか」などについて考える
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
あわせて読みたい
【感想】映画『窮鼠はチーズの夢を見る』を異性愛者の男性(私)はこう観た。原作も読んだ上での考察
私は「腐男子」というわけでは決してないのですが、周りにいる腐女子の方に教えを請いながら、多少BL作品に触れたことがあります。その中でもダントツに素晴らしかったのが、水城せとな『窮鼠はチーズの夢を見る』です。その映画と原作の感想、そして私なりの考察について書いていきます
あわせて読みたい
【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…
クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます
あわせて読みたい
【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…
好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性
あわせて読みたい
【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…
誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…
メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
苦しい・しんどい【本・映画の感想】 | ルシルナ
生きていると、しんどい・悲しいと感じることも多いでしょう。私も、世の中の「当たり前」に馴染めなかったり、みんなが普通にできることが上手くやれずに苦しい思いをする…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…






















































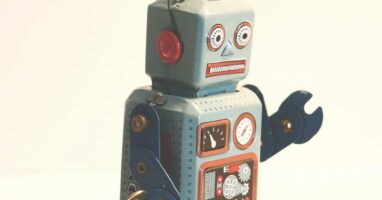


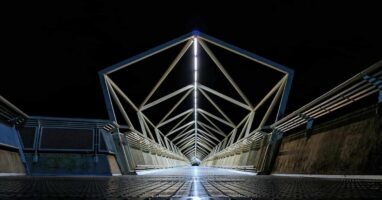











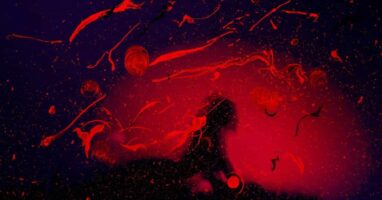



































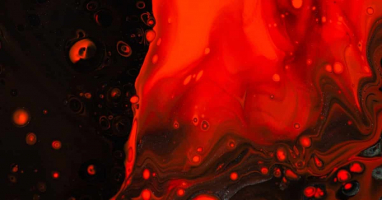
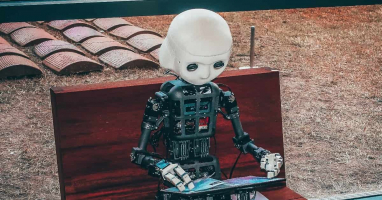














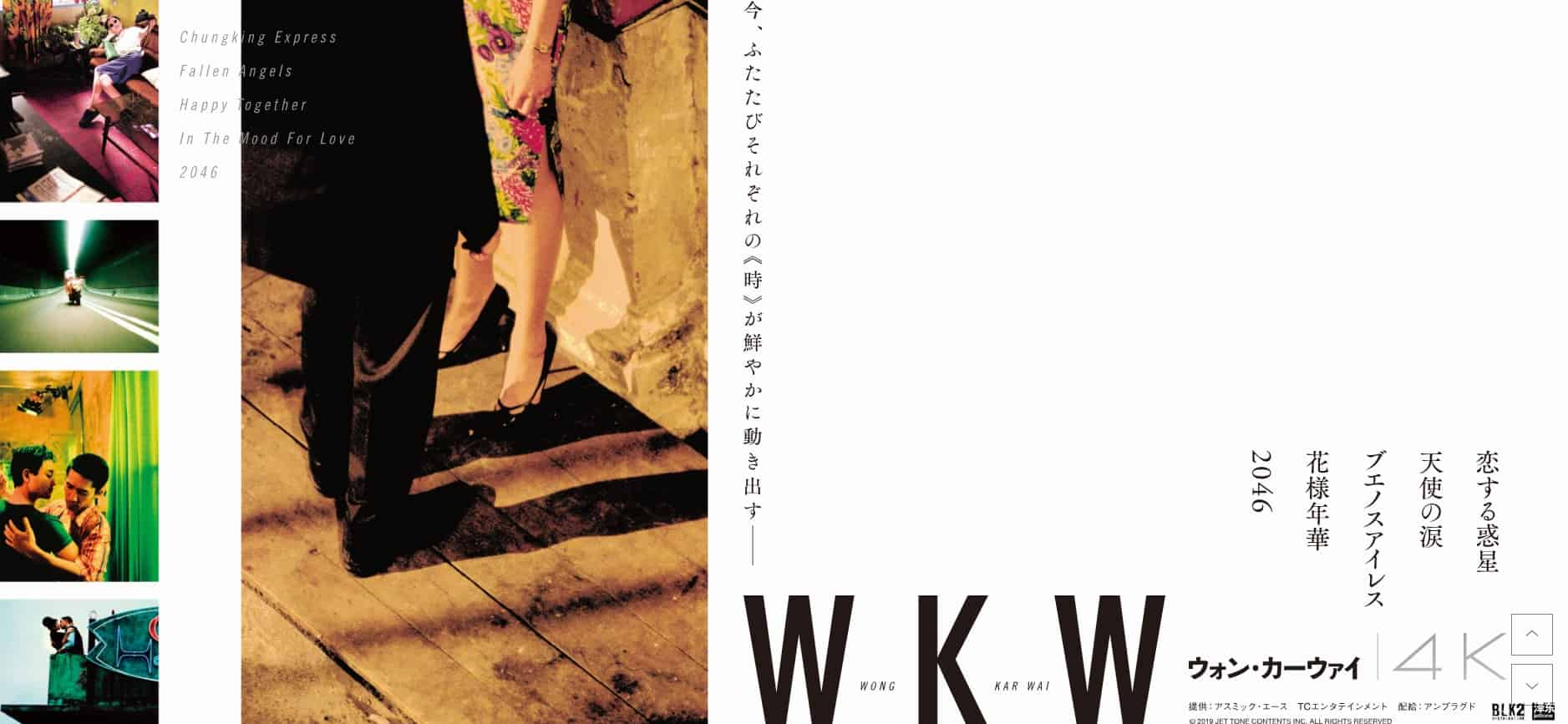


コメント