目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
「それでも私は Though I’m His Daughter」公式HP
VIDEO
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
今どこで観れるのか?
公式HPの劇場情報 をご覧ください
この記事の3つの要点
「加害者家族は別に悪いことなどしていないのだから、堂々と生きていてほしい」と私には思えてしまう 銀行口座の開設すら拒絶され、試験に合格した大学からは入学を断られ、外国からも入国が禁じられている、そのあまりにも酷い現状 「父親が死刑ではなく終身刑だったとしたら、私は結婚だってしていたかもしれない」という発言の真意とは? 麻原彰晃に動機を喋らせることなく死刑を執行させてしまった社会(我々)は反省すべきだし、罪のない個人が批判されずに穏やかに生きていける社会を構築すべきだとも思う
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
オウム真理教・麻原彰晃の三女・松本麗華を追う映画『それでも私は Though I’m His Daughter』は、「加害者家族」のあまりにも辛い現状と彼女の不屈の生き様を描き出す
凄まじい人生 である。ちょっと信じがたい ぐらいだし、よくもまあここまで生きてこられたものだ と思う。松本麗華は作中で何度も「死にたい」と口にしていた のだが、そう感じるのも当然 だろう。ホントに、どうにか少しでも穏やかに生きてほしい ものだなと思う。
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
本作『それでも私は Though I’m His Daughter』はドキュメンタリー映画 で、焦点が当てられるのは、オウム真理教の教祖・麻原彰晃こと松本智津夫の三女・松本麗華 である。2018年2月から取材を始め、そこから6年間もカメラを回し続けた という。そしてその間には、麻原彰晃や幹部らの死刑執行 や、麻原彰晃の遺骨返還裁判 などが行われた。彼女の人生は常に激動だった だろうが、「父親の死刑執行」を含むこの期間はかなり濃密 と言っていいのではないかと思う。
「加害者家族」に対する私自身の考え方について
本作についてあれこれ書く前にまず、「加害者家族」に対して私がどのように考えているのか について触れておくことにしよう。世間一般的に「加害者家族」がどのように認識されているか正確には捉えられてはいないものの、私のイメージでは「加害者家族」はあまりにも酷い扱いがなされている ように感じられている。
状況によって色々と違いがあるとは思うが、私は基本的に、「『加害者がしたこと』と『加害者家族』には何の関係もない」と考えていて、だから「自由に穏やかに生きてくれ」としか思えない 。「加害者」に怒りや批判が向くのは当然だが、しかし同じような視線がその家族にまで向けられるのはちょっと意味が分からなすぎる 。
あわせて読みたい
【誠実】地下鉄サリン事件の被害者が荒木浩に密着。「贖罪」とは何かを考えさせる衝撃の映画:『AGANAI…
私には、「謝罪すること」が「誠実」だという感覚がない。むしろ映画『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』では、「謝罪しない誠実さ」が描かれる。被害者側と加害者側の対話から、「謝罪」「贖罪」の意味と、信じているものを諦めさせることの難しさについて書く
もちろん、家族も犯行に加担していたとか、知っていて黙認していたみたいなことであれば、責められても仕方ない だろう。ただ、そういう場合は普通、その家族も何らかの刑法に引っかかる だろうし、だから「加害者家族」ではなく「加害者」という扱いになる はずだ。つまり、「『加害者家族』には、刑法上の罪は存在しない」というのが私の前提 であり、だから「家族は別に関係ないだろ」としか思えない というわけだ。
あるいは、「『加害者』が未成年」の場合には、ある程度は親が責めを追う必要も出てくる かもしれない。しかしだからと言って、「加害者」に対するのと同等の批判が向けられるのは間違っている と思う。虐待などよほどのことがない限り「親の責任」は限定的 であり、個人的には、「未成年だろうがなんだろうが、『加害者』がそのほとんどの責任を負うべき」だと考えている というわけだ。
それで、本作には原田正治という人物 が登場する。というか、彼の存在が本作のきっかけになった と言っていいだろう。彼は、弟を殺された被害者家族 である。「弟の勤務先の従業員が結託して保険金殺人を企てた 」というなかなか凄まじい事件だ。そしてこの原田氏が松本麗華との対面を望んだことから本作の撮影が始まった ようである。
あわせて読みたい
【真相?】映画『マミー』が描く和歌山毒物カレー事件・林眞須美の冤罪の可能性。超面白い!
世間を大騒ぎさせた「和歌山毒物カレー事件」の犯人とされた林眞須美死刑囚は無実かもしれない。映画『マミー』は、そんな可能性を示唆する作品だ。「目撃証言」と「ヒ素の鑑定」が詳細に検証し直され、さらに「保険金詐欺をやっていた」という夫の証言も相まって、証拠的にも感情的にも支持したくなるような驚きの仮説である
原田氏は当初、加害者らに死刑を望んでいた という。しかし後に加害者から謝罪を受けたことで「生きて償ってほしい」と考えを変え、既に下されていた死刑判決の撤廃を求める運動を始めた のである。しかし結局、死刑はそのまま執行されてしまった そうだ。
そんな原田氏は松本麗華に、「加害者の奥さんと子どもが謝罪に来てくれたことがあり、それで救われた部分も確かにある 」みたいなことを口にしていた。その流れで松本麗華が、「加害者家族からの謝罪は必要だと思いますか?」と聞く と、原田氏は、「救われたことは確かだけど、ただ、『加害者家族が謝罪すべき』だとは思わない。被害者家族も加害者家族も、どっちも被害者ですよ 」と言っていたのである。
一応書いておくと、原田氏は別に、松本麗華に配慮してそんな言い方をしたのではない と思う。というのも、原田氏も松本麗華も書籍を出版しており、お互い相手の著作を読んだ状態でこの対談に臨んでいる からだ。恐らくだが、原田氏は書籍の中で「『加害者家族が謝罪すべき』だとは思わない」みたいなことを書いていて、それを知っていた松本麗華が改めてその展について確認するための質問をした 、みたいな流れだったのではないかと想像している。じゃなければ同じ事件の「加害者」「被害者」ではないとはいえ、「加害者家族が被害者家族に『加害者からの謝罪は必要ですか?』と質問する」なんてことは出来ない だろう。
あわせて読みたい
【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…
「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟
さてもちろんだが、すべての被害者家族が原田氏のように考えているはずがない し、私としても別に、「被害者家族は加害者家族に怒りを向けてはならない」なんて思っているわけではない 。やりきれない思いを抱えているだろう被害者家族が、自分の気持ちを落ち着かせるために、そしてどうにか前を向いて進んでいくために、その怒りの矛先を誰かに向けてしまうのは仕方ない ことだし、その「誰か」が加害者家族になってしまうことだってある だろうと思う。私は別に、そういう状況に対して何か言及したいわけではない。
私が指摘したいのは、「SNSなどでウダウダ言っている連中」に対して である。そして私は、「お前らに加害者家族を批判する資格などない」と言っている だけなのだ。加害者本人を責めるならまだ理解は出来る (それでも、「外野がとやかく言ってんじゃねぇ」と感じてしまうのだが)。ただ、事件と直接的には関係ない加害者家族に対して、そもそも何の関係もないネット民があーだこーだ言っている状況は、私にはちょっと許容できない 。どんな言い訳をしようが、彼らの行動に「正義」などどこにもない はずだ。
というわけで、ここまでで書いたようなことが私の基本的な考え方 である。一応まとめるなら、「『加害者』と『加害者家族』は無関係であり、だから『加害者家族』が批判される必然性などどこにもない。謝罪などしなくていいし、堂々と胸を張って生きてほしい 」となるだろうか。「加害者」の責任なんて、負う必要はない のである。
あわせて読みたい
【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…
『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか
「『加害者家族』への批判」はある種の「抑止力」として機能しているのかもしれないが、そうだとしても「『加害者家族』を責めていい」ということにはならない
さて、「加害者家族」に対するここまでの文章は間違いなく私の本心 だが、それとは少し異なる話 もしておきたいと思う。それは、「『加害者家族』への批判がある種の『抑止力』として機能している現実 」についてだ。
私たちは今、「何か罪を犯せば、自分だけではなくその家族までも批判にさらされる」という社会 に生きている。そしてそれ故に、「自分はともかく、家族を路頭に迷わせるわけにはいかない」と考えて踏みとどまる人もいるんじゃないか と思う。ただ、そういう効果があるとしても、それは測定不能 である。結果として犯罪は起こっていないわけで、「起こっていてもおかしくはなかったが実際には起こらなかったこと」についてカウントしなければならない からだ。さすがにそれは無理がある だろう。ただ測定出来ないとはいえ、「その効果は一定程度存在する」と考えるのが自然 ではないかと思う。
逆に言えば、私が主張するような「加害者家族が責められない世界」が実現したら、「罪を犯したとしても家族に迷惑が掛かることはない」と考えて、結果として犯罪が増えるなんて可能性もあるかもしれない 。こちらも実際のところは検証不可能な仮説 ではあるが、やはり「そうであってもおかしくない 」ぐらいに考えておくのが良いんじゃないかと思う。
あわせて読みたい
【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…
映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う
そして私は、「仮にそうだとしても、加害者家族が責められない社会を実現すべきだ 」と考えている。それがどれだけ「公共の利益」に帰するとしても、そのために「特定の個人に対する不利益」が生まれてしまうのであれば、そんなのフェアだとは思えない からだ。「犯罪の抑止力」について考えるのはもちろん大事 なことである。しかしそれは、「加害者家族が批判される」というのではない形で実現されるべき だろう。「個人に不利益を被らせて社会全体の秩序を守る」なんて、人柱や姥捨て、魔女狩りなどと大差はない 。そんな前時代的な仕組みでしか秩序を維持できないとすれば、そんなの現代社会の敗北でしかない だろう。
そしてこの「加害者家族は責められるべきではない」という私の感覚は、松本麗華に対しても当てはまる と考えている。もちろん彼女の場合、かなり特殊な状況 であることは間違いない。例えば、父親が逮捕された当時彼女は12歳 だったのだが(私は恐らく彼女と同い年で、1ヶ月ほどしか誕生日が違わないと思う)、その時点で彼女は教団内で「アーチャリー」という名前が付けられ、「指導的な立場」をやらされていた という。また、彼女は早い段階でオウム真理教やその後継団体とも一切関わりを絶った のだが、「教祖の娘である」という事実によって神格化され、本人の意思に反して教祖的な扱いがなされてしまう可能性もある だろう。実際にこの記事を書く少し前に、「本人の意思に反しているか」は不明だが、「松本智津夫の次男が後継団体の『グル』を自称している」というニュース が出たりもしていた。松本麗華がそうなっていた可能性もある だろうし、後で触れるが、公安調査庁は今もそのような警戒を続けている ようだ。
だから松本麗華の場合、「ごく一般的な加害者家族」 (という表現も実に変ではあるが)とはちょっと言えない だろうと思う。
あわせて読みたい
【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?
タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う
しかしそうだとしても、「父親が松本智津夫なんだから、その娘はどんな風に扱ったって別に問題ない」みたいになるのはおかしい だろう。というか、イカれている と思う。オウム真理教に関しては、国家が総動員してあらゆることを調べ尽くしているはずなので、「にも拘らず松本麗華が逮捕されていない」ということは、少なくとも彼女は刑法に引っかかるようなことは何もしていない ということだろう。だとすればやはり、彼女が責められるべき謂れはない 。
というかそもそも、松本麗華はオウム真理教の「虫も殺してはいけない」という教えを信じて育った ため、「父親が逮捕されるまでは菜食主義者だった 」と言っていた。その後変わったのかはよく分からない。ただ、冒頭で映し出される原田正治との対談の中で彼女は「生け簀が置かれている店は苦手です 」と口にしていた(そういう話の流れがあったのだ)。完全な菜食主義者ではないかもしれないが、現在でも「生き物を食べること」に多少なりとも抵抗を持っている のかもしれない。
まあそんなことはどうでもいいのだが、何にせよ、松本麗華は「罪のない加害者家族」 でしかなく、松本智津夫の娘だろうがなんだろうが、酷い扱いをしていいはずがない というわけだ。
あわせて読みたい
【絶望】子供を犯罪者にしないために。「異常者」で片付けられない、希望を見いだせない若者の現実:『…
2人を殺し、7人に重傷を負わせた金川真大に同情の余地はない。しかし、この事件を取材した記者も、私も、彼が殺人に至った背景・動機については理解できてしまう部分がある。『死刑のための殺人』をベースに、「どうしようもないつまらなさ」と共に生きる現代を知る
松本麗華が置かれている、あまりにもしんどい日常
さて、何となく想像出来るとは思うが、松本麗華はやはり相当しんどい状況に置かれている 。そのしんどさは、ちょっと想像を絶する んじゃないかと思う。
というわけで、いきなり松本麗華ではない人物の話 から始めるが、私が驚かされたのは「学校の先生からもいじめられた」というエピソード だ。松本麗華が妹・聡香 (映画を観ている時は本名だと思っていたのだが、調べたらペンネームらしい)について話している時に出てきたエピソード である。
聡香は学校(小学校だったと思う)でのクラスメートらからのいじめが苦しくて自傷行為をする ようになったという。そしてそれを知った学校側の誰か(担任なのか校長なのかは覚えていない)が、「あなたの命は1つです。でも、あなたの教団は多くの人の命を奪いました」みたいなことを言った というのだ。この話が事実だとすれば(松本麗華の証言しかないので、念の為こういう表現をしている)、マジで気が狂ってる んだなという感じがする。クラスメートからのいじめももちろん辛かっただろうが、教師からそんな風に言われたのなら絶望でしかなかった だろう。確かに、あの当時は「オウム真理教憎し」という社会全体の雰囲気が凄かった が(私は中学1年ぐらいだったが、やはりかなりのインパクトと共に記憶している)、それにしたって、教師がしていい言動ではない (というか、教師以外ももちろんダメだ)。
あわせて読みたい
【危機】教員のセクハラは何故無くならない?資質だけではない、学校の構造的な問題も指摘する:『スク…
『スクールセクハラ なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるのか』では、自分が生徒に対して「権力」を持っているとは想像していなかったという教師が登場する。そしてこの「無自覚」は、学校以外の場でも起こりうる。特に男性は、読んで自分の振る舞いを見直すべきだ
また本作では、松本麗華が銀行口座の開設を依頼する場面 が映し出される(何らかの方法で隠し撮りされた映像のようだった)。そして銀行側は、彼女の口座開設依頼を拒否する のだ。もちろん松本麗華は「どうして作れないんですか?」と質問する のだが、銀行側は「総合的に判断した」という返答 を繰り返すばかり。しかしそのやり取りからは、明らかに「松本智津夫の娘だから」だということが伝わってくる 。そう、彼女はなんと銀行口座すら作れない のだ。それはあまりにもハードすぎる だろうと思う。
とはいえ、この件で銀行を責めるのは少し酷かもしれない 。というのも、松本麗華はどうやら、公安調査庁から「後継団体(たぶん「アレフ」)の事実上の幹部である」と見なされている ようなのだ。後継団体も恐らく「テロ集団」と認定されているはずで、だから松本麗華は公式の書類において「テロリスト」として扱われているのだと思う 。そしてこの事実が、彼女の社会生活を著しく妨げる要素となっている というわけだ。
松本麗華は、この事実を不服として裁判を起こした 。しかし結果は覆らない 。その後判決を精査してみたところ、やはりその決定には奇妙な点があった という。というのも、公安調査庁はある時点ではっきりと、「11歳当時の松本麗華は教団幹部ではなかった」という報告書をあげていた からである。「松本麗華が後継団体の幹部である」という認定には、「かつて幹部だったこと」と「現在幹部であること」の2つを示す必要がある ようなのだが、前者は公安調査庁自身の報告書によって否定されている のだ(この報告書はもちろん裁判で提出されている)。にも拘らず裁判所は、「松本麗華は後継団体の幹部である」という認定を許容し、取り消しに応じなかった のである。
あわせて読みたい
【生還】内戦下のシリアでISISに拘束された男の実話を基にした映画『ある人質』が描く壮絶すぎる現実
実話を基にした映画『ある人質 生還までの398日』は、内戦下のシリアでISISに拘束された男の壮絶な日々が描かれる。「テロリストとは交渉しない」という方針を徹底して貫くデンマーク政府のスタンスに翻弄されつつも、救出のために家族が懸命に奮闘する物語に圧倒される
このような現状を松本麗華は、「国からいじめを受けている 」と表現していた。確かに、そんな風に言いたくもなる だろう。
また、彼女はある場面で、「個人からのいじめだったら、引っ越したりして私のことを誰も知らない場所に行けばどうにかなる 」みたいなことを言っていた。それも普通なら容易ではない はずだが、しかし彼女には簡単なことに感じられて当然 だとも思う。というのも松本麗華は、なんと「外国からも入国を拒否される 」という状況にあるからだ。恐らくこれも、公式の書類で「後継団体の幹部」と認定されてしまっているため だろう。こんな風にして国は、「松本智津夫の娘」というだけの理由で一個人を徹底的に弾圧している のである。個人的には、ちょっと信じがたい なと感じられてしまった。
さらに、このような「理屈を曲げてでもオウム真理教関係者をねじ伏せる」みたいなやり方は、「麻原彰晃の遺骨の返却」に関しても見られる 。
麻原彰晃ら幹部の死刑が一斉に執行された後、「麻原彰晃の遺骨を誰に渡すか」が問題となった 。というのも、麻原彰晃の逮捕後、彼の家族(母親と6人の子ども)は実質的に一家離散の状態にある からだ。また先述した通り、次男は後継団体アレフの「グル」を自称している 。もし彼の手に遺骨が渡れば教団の新たなシンボルとして扱われる だろうし、そしてそれは、国目線からすれば「家族の誰に渡してもその危険は残る」という判断になる だろう。そのため、裁判所が「遺骨は次女の宇未に引き渡す」ように命じたにも拘らず、国は遺骨の引き渡し自体を拒んだ のである。
あわせて読みたい
【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」
オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く
もちろん、そんな状態はあまりにも理不尽 なので、宇未は裁判を起こすことに決めた 。そして本作には、その裁判で弁護を担当した弁護士が少し登場する のだが、彼は「遺骨を返却しないことに法的根拠など一切ない 」と説明していた。まあ、そりゃあそうだろう 。そしてにも拘らず、国は「遺族が遺骨を引き取ること」を「権利濫用」だと主張し、引き渡しを拒んでいる らしいのだ。マジで意味が分からない し、その弁護士も理解不能だと言っていた 。ここでも国は、ルールを無理やり捻じ曲げてでも「オウム真理教関係者」を排除しようとしている のである。
こんな状態で生きていくのはあまりにもしんどかっただろう 。よく生き延びられたものだなと思う。松本麗華は、試験を突破し合格したはずの大学から入学を拒否されたり (ただ最終的には、弁護士の尽力もあり通えることになった)、働き口を見つけてもすぐに解雇されてしまったり と、とにかくまともな生活が送れずにいる 。そして、誰も明言こそしないだろうが、その理由は間違いなく「松本智津夫の娘だから」 なのだ。
作中では何度か、本作監督と松本麗華がオンラインでやり取りする場面が挿入される のだが、その中で監督が、「『挑戦する』という権利さえ奪われてしまっている 」という表現を使っていた。彼女の現状を表すのにピッタリ という感じがするし、そして、国家がその強大な権力を行使してそのような状況に追い込んでいる事実は、やはりちょっと酷すぎる のではないかと思う。
あわせて読みたい
【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う
「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた
「麻原彰晃が何一つ語らないまま死刑に処された」という現実について
そんな松本麗華の口から語られる話はどれも興味深かった のだが、やはり中でも「死刑」に関する言及はかなり重かった と言っていいだろう。
ただその話をする前に、「麻原彰晃の裁判の様子、そして死刑に至るまでの過程」について少し触れておこう 。一般的にどの程度知られているのかよく分からないが、麻原彰晃の裁判はかなり異例の形で進行した のである。私は、以前読んだ『A3』(森達也)というノンフィクション でその一端を知った。恐らくニュース等でも報じられていたとは思うが、私はリアルタイムではこの事実を認識していなかった 気がするし、私と同じように詳しく知らないという人がいてもおかしくはない だろう。
あわせて読みたい
【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた
「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。
どうやら麻原彰晃は、1審の途中から意味不明なことを口にするようになった ようである。それが演技だったかどうかは、死刑が執行されてしまった今となっては判断できない 。しかし、森達也には「明らかに精神異常が疑われる」という状態に見えた のだそうだ。にも拘らず国は、「裁判を一度中断して治療に専念させるべきだ」という声を無視して裁判を続行、そのまま判決を下し、死刑を執行した のである。つまり、「すべての指示を行った」とされる麻原彰晃の証言は一切取れないまま、オウム真理教に関する事件は終結してしまった というわけだ。
本作の取材が始まったのは、たまたま麻原彰晃らの死刑が執行される少し前 のことであり(死刑がいつ行われるかは事前に公表されないので、本当にたまたまである)、そしてその取材期間中に、宮台真司や森達也ら知識人が集まって、「死刑囚・麻原彰晃を治療すべきだ」という主旨の記者会見が行われた 。ちゃんとは理解できなかったが、恐らく「この会の発起人は松本麗華だが、彼女自身は記者会見に同席しなかった 」みたいな感じだと思う。松本麗華だけではなく、多くの人が「動機や真相の解明をすべきだ」と主張 しており、そしてそのためには「麻原彰晃の治療」が欠かせない 。もちろん、治療したところで治る保証はない が、そうしなければ動機を語らせることも出来ないのだから、「仮に可能性が低くても治療を施すべきだ」と訴えていた のだ。私も、絶対にそうすべき だと思う。特に「オウム真理教が関わった事件」は、あらゆる意味で前代未聞 だったわけだから、実態を解明しなければならない はずだ。
この点に関しては、監督が松本麗華に、「奇跡的に治療が回復して喋れるようになったとして、その場合、お父さんの口から、あなたが望んでいない事実が語られるかもしれないけど、それでも治療を望むの?」と質問する場面 がある。そして彼女は、「その点に関しては繰り返し考えてきたけど、仮に自分が望まない話が出てくるとしても、やっぱり私は治療をしてほしい 」と断言していた。
あわせて読みたい
【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…
三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ
ちなみに、記者会見の中で森達也が話していたのだが、オウム真理教が地下鉄サリン事件を起こしたのは、教団にとっての「絶頂期」だった そうで、麻原彰晃も教団内に愛人を囲うなど申し分ない状況 にあったという。にも拘らず、地下鉄サリン事件は実行された 。それが麻原彰晃の指示なのだとすれば、そんな絶頂期に教団の破滅に繋がるような計画を立てるものだろうか? このような点さえも未だに明らかにされていない ようなのだ。死刑が執行されてしまった今となっては言っても仕方ないことだが、やはり治療を行うべきだった ように思う。
このままだと結果的に「国はオウム真理教に屈した」という印象になる し、「同じような事態に直面した際に対応できないのではないか 」という感じもしてしまう。「麻原彰晃ら幹部を一斉に死刑にした」という事実によって、ある意味で「国民の溜飲を下げる」みたいな効果を狙ったのかもしれない が、そんな一瞬で消えてしまう効果と引き換えにして失ったものは大きい ような気がした。
学生に語っていた「死刑」と「マスコミ」についての話が印象的だった
さて、彼女は「死刑」に関して様々な場面で断片的に話をしていた のだが、個人的に一番興味深いと感じたのは、「マスコミ志望の学生向けのセミナー(みたいなものだと思う)」で彼女が語っていた内容 である。どうしてそのセミナーに松本麗華が登壇することになったのかはよく分からないが、非常に印象的な話が多かった なと思う。
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
このセミナーには質疑応答の時間 があり、講演の中で「死刑には反対だ」と話していた(らしい)松本麗華に対してある学生が、「ではどういう刑罰が必要だと思うか?」と質問していた 。彼女の返答は「終身刑」 であり、恐らくこれは、仮釈放が想定される「無期懲役」ではなく、「仮釈放がない終身刑」という意味 なのだと思う。そしてそれに続けて、「もし父が死刑ではなく終身刑だったら、私の人生は全然違っていたと思う。もしかしたら、結婚だってしていたかもしれない 」みたいなことを言っていたのだ。
私は正直、彼女がそう口にした時にはその意味がまったく理解できていなかった のだが、その後の説明を聞いて、「なるほど、そういうことか」と納得できた 。
先程も少し触れたが、「いつ死刑が執行されるのか」は事前に分からない 。マスコミや家族に伝えられないのは当然、本人にも確か、「その日の朝突然伝えられる」みたいな感じ だったと思う。そしてだからこそ、松本麗華は「会える時に会っておかないと後悔する」と考えていた そうだ。自分が置かれた状況を想像しやすいようにと「介護」を例に挙げていた が、「例えば親の介護をしていて、いつ亡くなってもおかしくないとしたら、会える時に会いたいって思いますよね? 」と話していた。確かに、この方が状況を想像しやすい だろう。そして「そのせいでプライベートがかなり犠牲にされた 」というのだ。
あわせて読みたい
【矛盾】死刑囚を「教誨師」視点で描く映画。理解が及ばない”死刑という現実”が突きつけられる
先進国では数少なくなった「死刑存置国」である日本。社会が人間の命を奪うことを許容する制度は、果たして矛盾なく存在し得るのだろうか?死刑確定囚と対話する教誨師を主人公に、死刑制度の実状をあぶり出す映画『教誨師』から、死刑という現実を理解する
これが終身刑だったとしたら、「父親が突然いなくなる」みたいな可能性は低くなる (突然病死する、みたいな可能性はあるが)。そして「もしそうだったら、今とは全然違う人生を歩んでいたはずだ 」というのだ。「親族に死刑囚がいる」というのはあまりにも状況が特殊 すぎて今まで想像したこともなかったのだが、彼女の話を聞いて「なるほど、確かにそうかもしれない」と感じさせられた 。
さて、そのセミナーではもう1つ、「マスコミ」について興味深い話 がなされた。セミナーの中で松本麗華が「マスコミに対する不信感」みたいな話 をしたのだろう、それに関する学生の質問から展開された話 である。その質問は、「マスコミを一括りに考えているようですが、マスコミも個人の集まりなわけで、そういう個人に対してプラスの印象を抱くことはないんですか? 」というもの。そしてそれに対する返答にも「なるほど」と感じさせられた 。
松本麗華にはマスコミの知り合いがたくさんいる らしく、個人的に会ったり食事をしたりすることもある そうだ。そしてそうなれば、確かにその人は「個人」として認識される ようになる。ただ、そうなればその人のことを信頼できるのかと言えば、そんなことはほとんどない という。彼女にとって「信頼できるマスコミの人」はごく僅か らしい。
あわせて読みたい
【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…
一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う
その理由ははっきりしている。仮に目の前にいる個人のことが信頼できたとしても、その背後に多くの人が関わっているからだ 。要するに、「組織の理屈に個人は勝てない 」という話である。彼女は、「私の映像の編集に副社長が立ち会ったことがある」みたいな話を聞いたことがある そうだ。個人としてはどれだけ信頼できる人だとしても、組織の1人になってしまえば個人の想いなど消し飛んでしまう 。「だから私は、マスコミのことは信頼しない 」と話していた。こちらも、彼女自身の経験を反映した、実に説得力のある話 だなと思う。
映画『それでも私は Though I’m His Daughter』のその他感想
それでは最後に、いくつか気になった話 に触れてこの記事を終えようと思う。
まず、これは松本麗華だけではなく、「父親(松本智津夫)との記憶がちゃんとある家族」は全員同じ感覚を持っている ようなのだが、「父を憎んでいる人はいない 」と話していた。妹の聡香だけは、父親の逮捕当時6歳であり、父親とのまともな記憶がない 。だから彼女は父親を憎んでいるし、父親と対立する道を選んだ そうなのだが、父親との記憶がちゃんとある他の家族は恨んでいない という。松本麗華をこのような酷い状況に追い込んでいるのは明らかに父親 なのだが、そうだとしても「家族の情」みたいなものを感じてしまう ということなのだろう。
あわせて読みたい
【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理
たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける
そしてだからこそ、先述した通り、彼女は「父親を治療して動機を喋らせてほしかった」と考えている のである。父親としての記憶がちゃんとある松本麗華には、「世間で語られる麻原彰晃の姿」とあまりにも乖離が大きすぎると感じ、未だに理解できない のだそうだ。彼女は、「仮に自分たちには意味不明な話だったとしても、父親の口から直接聞きたかった 」みたいに言っていた。結局何も分からないまま死刑に処されてしまったため、その「隔たり」は永遠に埋められない 。そのこともまた、彼女を苦しめる要素になっている ようだ。
また本作には、「松本麗華と次女の宇未が父親の生まれ故郷を訪ね、親族に会う」という場面 も映し出される。一度も会ったことがない親族 だそうで、最初こそ拒絶されたものの、最終的には3時間半にも及ぶ長い話をしていた 。そして、その会話を振り返った松本麗華が次のように言っていた のである。
私たちは、父親が逮捕された時はまだ教団にいたから、教団に守られていたんだろうなと思う。そういうものがなかった親族の人たちはきっと、私たちより遥かにしんどかったと思う。
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
まあ確かにその通り だろう。そしてその上で松本麗華は、「憎めなかったからこその大変さ」みたいな話 もしていた。親族はもちろん松本智津夫のことを憎んでいる のだろうし、であれば「彼に怒りを向けることで発散する」みたいなことも出来た はずだ。一方、松本麗華も宇未も、父親に対して憎しみを抱けない でいる。そして「だからこそ、気持ちの持って行き場が難しい 」みたいな話をしていた。これもまた、リアルな実感 だろうなと思う。
あと、これは既に触れたことではあるが、作中で松本麗華は何度も「死にたい」みたいなことを口にしていた 。そう感じるのも当然 だろう。あらゆる意味で「まともな生活」など望めないし、ただ日常生活を送るだけでもかなりしんどい はずだ。また、妹と同じように彼女も父親の逮捕後にいじめに遭っており、その時のトラウマがフラッシュバックして鬱のような状態になってしまう こともあるという。
そんな「死にたい」と口にする場面の中でも特に印象的だったのが、2ヶ月前にコロナに罹り寝込んでいた松本麗華が久々にカメラの前で話す時のこと である。この時は彼女の方から「会いたい」と連絡があった ようで、監督がその理由を尋ねてみると、彼女は目を潤ませながら次のようなことを言っていた 。
私が死んだ時、「父たちのせいで死んだ」みたいに思われるのはやっぱり違う。「私に攻撃してきた人たち」のせいで死ぬんだ。
あわせて読みたい
【救い】自殺を否定しない「笑える自殺本」。「自殺したい」ってもっと気軽に言える社会がいい:『自殺…
生きることがしんどくて、自殺してしまいたくなる気持ちを、私はとても理解できます。しかし世の中的には、「死にたい」と口にすることはなかなか憚られるでしょう。「自殺を決して悪いと思わない」という著者が、「死」をもっと気楽に話せるようにと贈る、「笑える自殺本」
なかなか穏やかではない雰囲気 である。監督も、いつもと違う雰囲気を感じ取った ようだ。彼女に、「もしかしてカメラの前で遺言を話してるってこと? 」「このまま取材を続けると、『死にたい』って思ってるあなたの背中を押す感じになっちゃう? 」みたいに聞きながら、その真意を確かめようとしていた のである。それに私にも、「遺言のつもりなのかもしれない 」という風に見えていた。「本当に死んじゃうかは分からないけど、衝動的に死にたい気分に襲われて命を落とすことだってあるかもしれないし、そういう場合に備えて、自分の口で『死んだ理由』を説明しておきたい」みたいな動機 があるように思えたのだ。時期や状況などによっても変わるのだろうが、やはりかなり追い詰められていた のだと思う。本当に、どうかそんな風に感じずに穏やかに生きてほしい ものだと願わずにはいられなかった。
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
配慮を一切しない表現をするなら、松本麗華は「ドキュメンタリー映画の被写体」としてかなり最強の部類 に入るんじゃないかと思う。匹敵する存在として思いつくのは、「袴田事件」の袴田巌ぐらい だろうか。本作『それでも私は Though I’m His Daughter』は正直、松本麗華以外の人物が撮影対象だったらちょっと物足りなさを感じたかもしれないが、被写体が松本麗華だったことで、実に興味深い作品に仕上がっている ように感じられた。
あわせて読みたい
【捏造】袴田事件はついに再審での無罪が決定!冤罪の元死刑囚・袴田巌の現在と姉・秀子の奮闘:映画『…
映画『拳と祈り』は、2024年に再審無罪が確定した「袴田事件」の元死刑囚・袴田巌と、そんな弟を献身的にサポートする姉・秀子の日常を中心に、事件や裁判の凄まじい遍歴を追うドキュメンタリーである。日本の司法史上恐らく初めてだろう「前代未聞の状況」にマスコミで唯一関わることになった監督が使命感を持って追い続けた姉弟の記録
「これほど酷いレッテルを貼られた人物もそうそういないだろう」という特異な存在感 や「国家から虐げられている」というあまりにも酷すぎる状況 、さらに「そういう中でも顔と名前を晒しながら社会と対峙する」という姿勢 など、そのすべてにちょっと圧倒させられた し、やはり「被写体として最強だな 」と思う。
何にしても、彼女にはどうにか穏やかに生きていてほしい ものである。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【狂気】映画『ミッシング』(吉田恵輔監督)は「我が子の失踪」を起点に様々な「嫌な世界」を描く(主…
映画『ミッシング』は、「娘の失踪を機に壊れてしまった母親」を石原さとみが熱演する絶望的な物語である。事件を取材する地元局の記者の葛藤を通じて「『事実』とは何か」「『事実を報じる』ことの難しさ」が突きつけられ、さらに、マスコミを頼るしかない母親の苦悩と相まって状況が混沌とする。ホントに「嫌な世界」だなと思う
あわせて読みたい
【実話】特殊詐欺被害者が警察より先に犯人を追い詰める映画『市民捜査官ドッキ』は他人事じゃない
映画『市民捜査官ドッキ』は、実際に起こった詐欺事件を基にした映画なのですが、とても実話とは思えない驚きの状況が描かれます。なにせ、「警察に見放された詐欺被害者が、自ら詐欺グループの拠点を探し当てる」のです。テーマはシリアスですが、全体的にはコメディタッチで展開される作品で、とにかく楽しく見られるでしょう
あわせて読みたい
【人権】チリ女性の怒り爆発!家父長制と腐敗政治への大規模な市民デモを映し出すドキュメンタリー:映…
「第2のチリ革命」とも呼ばれる2019年の市民デモを映し出すドキュメンタリー映画『私の想う国』は、家父長制と腐敗政治を背景にかなり厳しい状況に置かれている女性たちの怒りに焦点が当てられる。そのデモがきっかけとなったチリの変化も興味深いが、やはり「楽しそうにデモをやるなぁ」という部分にも惹きつけられた
あわせて読みたい
【実話】映画『あんのこと』(入江悠)は、最低の母親に人生を壊された少女の更生と絶望を描く(主演:…
映画『あんのこと』では、クソみたいな母親の元でクソみたいな人生を歩まされた主人公・杏の絶望を河合優実が絶妙に演じている。色んな意味で実に胸糞悪い作品で、こんな社会の歪さがどうしてずっとずっと放置され続けるのか理解できないなと思う。また、河合優実だけではなく、佐藤二朗の演技にも圧倒させられてしまった
あわせて読みたい
【正義】名張毒ぶどう酒事件の真相解明の鍵を握る、唯一の再審請求人である妹・岡美代子を追う映画:『…
冤罪と目されている「名張毒ぶどう酒事件」を扱ったドキュメンタリー映画『いもうとの時間』は、逮捕され死刑囚として病死した奥西勝の妹・岡美代子に焦点を当てている。というのも彼女は、「再審請求権」を持つ唯一の人物なのだ。このままでは、事件の真相は闇の中だろう。まずは再審の扉が開かれるべきだと私は思う
あわせて読みたい
【父親】パキスタン本国では上映禁止の映画『ジョイランド』は、古い価値観に翻弄される家族を描く
映画『ジョイランド』は、本国パキスタンで一時上映禁止とされた作品だが、私たち日本人からすれば「どうして?」と感じるような内容だと思う。「(旧弊な)家族観を否定している」と受け取られたからだろうが、それにしたってやはり理不尽だ。そしてそんな「家族のややこしさ」には、現代日本を生きる我々も共感できるに違いない
あわせて読みたい
【絶望】映画『若き見知らぬ者たち』が描くのは”不正解”だが、「じゃあ”正解”って何?」ってなる(監督…
映画『若き見知らぬ者たち』は、「まともな生活が送れなくなった母親の介護」を筆頭に、かなり絶望的な状況に置かれている若者たちを描き出す作品だ。あまりにも不毛で、あまりにも救いがなく、あまりにも辛すぎるその日々は、ついに限界を迎える。そしてその絶望を、磯村勇斗がその凄まじい存在感によって体現していく
あわせて読みたい
【捏造】袴田事件はついに再審での無罪が決定!冤罪の元死刑囚・袴田巌の現在と姉・秀子の奮闘:映画『…
映画『拳と祈り』は、2024年に再審無罪が確定した「袴田事件」の元死刑囚・袴田巌と、そんな弟を献身的にサポートする姉・秀子の日常を中心に、事件や裁判の凄まじい遍歴を追うドキュメンタリーである。日本の司法史上恐らく初めてだろう「前代未聞の状況」にマスコミで唯一関わることになった監督が使命感を持って追い続けた姉弟の記録
あわせて読みたい
【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理
たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける
あわせて読みたい
【映画】ディオールのデザイナーだった天才ジョン・ガリアーノが差別発言で破滅した人生を語る:映画『…
何者なのかまったく知らない状態で観たドキュメンタリー映画『ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナー』は、差別発言によって失墜しすべてを失った天才デザイナーの凄まじい来歴が描かれる作品だ。実に複雑で興味深い存在だったし、その波乱の人生は、私のようなファッションに疎い人間でも面白く感じられると思う
あわせて読みたい
【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実
映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた
あわせて読みたい
【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…
上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした
あわせて読みたい
【赦し】映画『過去負う者』が描く「元犯罪者の更生」から、社会による排除が再犯を生む現実を知る
映画『過去負う者』は、冒頭で「フィクション」だと明示されるにも拘らず、観ながら何度も「ドキュメンタリーだっけ?」と感じさせられるという、実に特異な体験をさせられた作品である。実在する「元犯罪者の更生を支援する団体」を舞台にした物語で、当然それは、私たち一般市民にも無関係ではない話なのだ
あわせて読みたい
【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件
映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった
あわせて読みたい
【狂気】ISISから孫を取り戻せ!映画『”敵”の子どもたち』が描くシリアの凄絶な現実
映画『”敵”の子どもたち』では、私がまったく知らなかった凄まじい現実が描かれる。イスラム過激派「ISIS」に望んで参加した女性の子ども7人を、シリアから救出するために奮闘する祖父パトリシオの物語であり、その最大の障壁がなんと自国のスウェーデン政府なのだる。目眩がするような、イカれた現実がここにある
あわせて読みたい
【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー
北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった
あわせて読みたい
【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…
森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である
あわせて読みたい
【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…
実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
あわせて読みたい
【現実】我々が食べてる魚は奴隷船が獲ったもの?映画『ゴースト・フリート』が描く驚くべき漁業の問題
私たちは、「奴隷」が獲った魚を食べているのかもしれない。映画『ゴースト・フリート』が描くのは、「拉致され、数十年も遠洋船上に隔離されながら漁をさせられている奴隷」の存在だ。本作は、その信じがたい現実に挑む女性活動家を追うドキュメンタリー映画であり、まさに世界が関心を持つべき問題だと思う
あわせて読みたい
【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実
弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている
あわせて読みたい
【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…
稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
あわせて読みたい
【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断
映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく
あわせて読みたい
【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…
「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている
あわせて読みたい
【生還】内戦下のシリアでISISに拘束された男の実話を基にした映画『ある人質』が描く壮絶すぎる現実
実話を基にした映画『ある人質 生還までの398日』は、内戦下のシリアでISISに拘束された男の壮絶な日々が描かれる。「テロリストとは交渉しない」という方針を徹底して貫くデンマーク政府のスタンスに翻弄されつつも、救出のために家族が懸命に奮闘する物語に圧倒される
あわせて読みたい
【実話】ポートアーサー銃乱射事件を扱う映画『ニトラム』が示す、犯罪への傾倒に抗えない人生の不条理
オーストラリアで実際に起こった銃乱射事件の犯人の生い立ちを描く映画『ニトラム/NITRAM』は、「頼むから何も起こらないでくれ」と願ってしまうほどの異様な不穏さに満ちている。「社会に順応できない人間」を社会がどう受け入れるべきかについて改めて考えさせる作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見
ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す
あわせて読みたい
【感想】阿部サダヲが狂気を怪演。映画『死刑にいたる病』が突きつける「生きるのに必要なもの」の違い
サイコパスの連続殺人鬼・榛村大和を阿部サダヲが演じる映画『死刑にいたる病』は、「生きていくのに必要なもの」について考えさせる映画でもある。目に光を感じさせない阿部サダヲの演技が、リアリティを感じにくい「榛村大和」という人物を見事に屹立させる素晴らしい映画
あわせて読みたい
【あらすじ】嵐莉菜主演映画『マイスモールランド』は、日本の難民問題とクルド人の現状、入管の酷さを描く
映画『マイスモールランド』はフィクションではあるが、「日本に住む難民の厳しい現実」をリアルに描き出す作品だ。『東京クルド』『牛久』などのドキュメンタリー映画を観て「知識」としては知っていた「現実」が、当事者にどれほどの苦しみを与えるのか想像させられた
あわせて読みたい
【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り
プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
あわせて読みたい
【衝撃】卯月妙子『人間仮免中』、とんでもないコミックエッセイだわ。統合失調症との壮絶な闘いの日々
小学5年生から統合失調症を患い、社会の中でもがき苦しみながら生きる卯月妙子のコミックエッセイ『人間仮免中』はとんでもない衝撃作。周りにいる人とのぶっ飛んだ人間関係や、歩道橋から飛び降り自殺未遂を図り顔面がぐちゃぐちゃになって以降の壮絶な日々も赤裸々に描く
あわせて読みたい
【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…
環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る
あわせて読みたい
【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…
映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた
あわせて読みたい
【驚愕】キューバ危機の裏側を描くスパイ映画『クーリエ』。核戦争を回避させた民間人の衝撃の実話:『…
核戦争ギリギリまで進んだ「キューバ危機」。その陰で、世界を救った民間人がいたことをご存知だろうか?実話を元にした映画『クーリエ:最高機密の運び屋』は、ごく普通のセールスマンでありながら、ソ連の膨大な機密情報を盗み出した男の信じがたい奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【日常】難民問題の現状をスマホで撮る映画。タリバンから死刑宣告を受けた監督が家族と逃避行:『ミッ…
アフガニスタンを追われた家族4人が、ヨーロッパまで5600kmの逃避行を3台のスマホで撮影した映画『ミッドナイト・トラベラー』は、「『難民の厳しい現実』を切り取った作品」ではない。「家族アルバム」のような「笑顔溢れる日々」が難民にもあるのだと想像させてくれる
あわせて読みたい
【実話】映画『アウシュビッツ・レポート』が描き出す驚愕の史実。世界はいかにホロコーストを知ったのか?
映画『アウシュヴィッツ・レポート』は、アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした実話を基にした作品。2人が持ち出した「アウシュビッツ・レポート」こそが、ホロコーストについて世界が知るきっかけだったのであり、そんな史実をまったく知らなかったことにも驚かされた
あわせて読みたい
【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…
在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。
あわせて読みたい
【勇敢】ユダヤ人を救った杉原千畝を描く映画。日本政府の方針に反しながら信念を貫いた男の生き様
日本政府の方針に逆らってまでユダヤ人のためにビザを発給し続けた外交官を描く映画『杉原千畝』。日本を良くしたいと考えてモスクワを夢見た青年は、何故キャリアを捨てる覚悟で「命のビザ」を発給したのか。困難な状況を前に、いかに決断するかを考えさせられる
あわせて読みたい
【妄執】チェス史上における天才ボビー・フィッシャーを描く映画。冷戦下の米ソ対立が盤上でも:映画『…
「500年に一度の天才」などと評され、一介のチェスプレーヤーでありながら世界的な名声を獲得するに至ったアメリカ人のボビー・フィッシャー。彼の生涯を描く映画『完全なるチェックメイト』から、今でも「伝説」と語り継がれる対局と、冷戦下ゆえの激動を知る
あわせて読みたい
【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ
「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ
あわせて読みたい
【実話】映画『ハドソン川の奇跡』の”糾弾された英雄”から、「正しさ」をどう「信じる」かを考える
制御不能の飛行機をハドソン川に不時着させ、乗員乗客155名全員の命を救った英雄はその後、「わざと機体を沈め損害を与えたのではないか」と疑われてしまう。映画『ハドソン川の奇跡』から、「正しさ」の難しさと、「『正しさ』の枠組み」の重要性を知る
あわせて読みたい
【残念】日本の「難民受け入れ」の現実に衝撃。こんな「恥ずべき国」に生きているのだと絶望させられる…
日本の「難民認定率」が他の先進国と比べて異常に低いことは知っていた。しかし、日本の「難民」を取り巻く実状がこれほど酷いものだとはまったく知らなかった。日本で育った2人のクルド人難民に焦点を当てる映画『東京クルド』から、日本に住む「難民」の現実を知る
あわせて読みたい
【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死
映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る
あわせて読みたい
【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える
どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える
あわせて読みたい
【驚愕】正義は、人間の尊厳を奪わずに貫かれるべきだ。独裁政権を打倒した韓国の民衆の奮闘を描く映画…
たった30年前の韓国で、これほど恐ろしい出来事が起こっていたとは。「正義の実現」のために苛烈な「スパイ狩り」を行う秘密警察の横暴をきっかけに民主化運動が激化し、独裁政権が打倒された史実を描く『1987、ある闘いの真実』から、「正義」について考える
あわせて読みたい
【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る
「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生
あわせて読みたい
【考察】映画『ジョーカー』で知る。孤立無援の環境にこそ”悪”は偏在すると。個人の問題ではない
「バットマン」シリーズを観たことがない人間が、予備知識ゼロで映画『ジョーカー』を鑑賞。「悪」は「環境」に偏在し、誰もが「悪」に足を踏み入れ得ると改めて実感させられた。「個人」を断罪するだけでは社会から「悪」を減らせない現実について改めて考える
あわせて読みたい
【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う
「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
あわせて読みたい
【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…
「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟
あわせて読みたい
【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…
「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する
あわせて読みたい
【勇敢】後悔しない生き方のために”間違い”を犯せるか?法に背いてでも正義を貫いた女性の生き様:映画…
国の諜報機関の職員でありながら、「イラク戦争を正当化する」という巨大な策略を知り、守秘義務違反をおかしてまで真実を明らかにしようとした実在の女性を描く映画『オフィシャル・シークレット』から、「法を守る」こと以上に重要な生き方の指針を学ぶ
あわせて読みたい
【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…
金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る
あわせて読みたい
【素顔】「ヨコハマメリー史」から「伊勢佐木町史」を知れる映画。謎の女性が町の歴史に刻んだものとは…
横浜で長らく目撃されていた白塗りの女性は、ある時から姿を消した。彼女の存在を欠いた伊勢佐木町という街は、大きく変わってしまったと語る者もいる。映画『ヨコハマメリー』から、ある種のアイコンとして存在した女性の生き様や彼女と関わった者たちの歴史、そして彼女の”素顔”を知る
あわせて読みたい
【対話】刑務所内を撮影した衝撃の映画。「罰則」ではなく「更生」を目指す環境から罪と罰を学ぶ:映画…
2008年に開設された新たな刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」で行われる「TC」というプログラム。「罰則」ではなく「対話」によって「加害者であることを受け入れる」過程を、刑務所内にカメラを入れて撮影した『プリズン・サークル』で知る。
あわせて読みたい
【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた
「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。
あわせて読みたい
【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」
オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
あわせて読みたい
【議論】安楽死のできない日本は「死ぬ権利」を奪っていると思う(合法化を希望している):『安楽死を…
私は、安楽死が合法化されてほしいと思っている。そのためには、人間には「死ぬ権利」があると合意されなければならないだろう。安楽死は時折話題になるが、なかなか議論が深まらない。『安楽死を遂げた日本人』をベースに、安楽死の現状を理解する
あわせて読みたい
【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…
三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
理不尽・ストレス・イライラする【本・映画の感想】 | ルシルナ
「理不尽だなー」と感じてしまうことはよくあります。クレームや怒りなど、悪意や無理解から責められることもあるでしょうし、多数派や常識的な考え方に合わせられないとい…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…














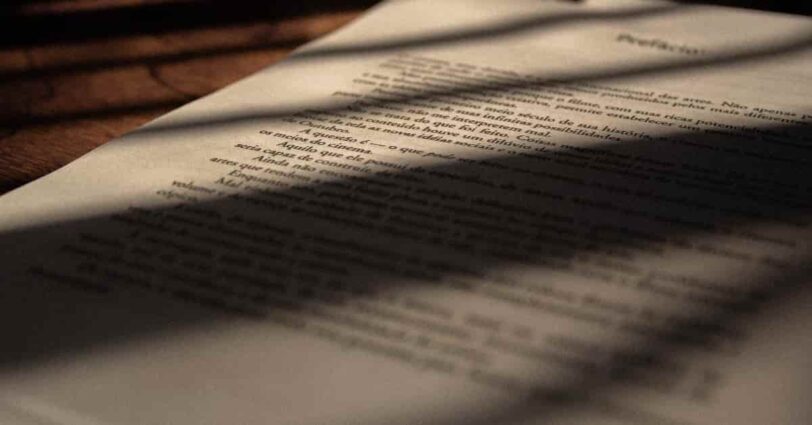



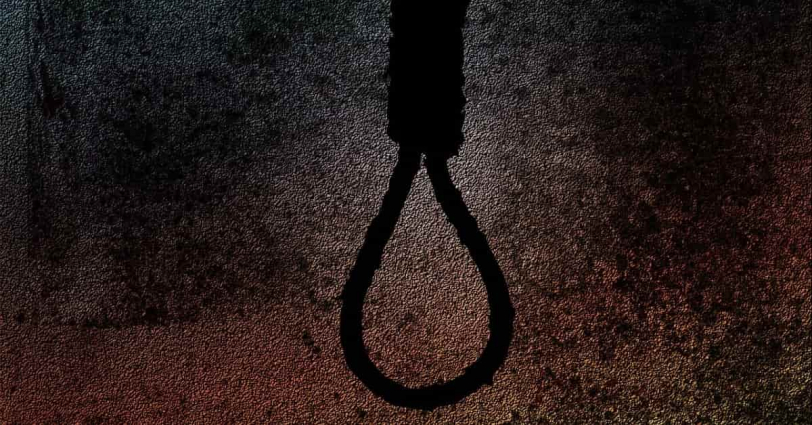







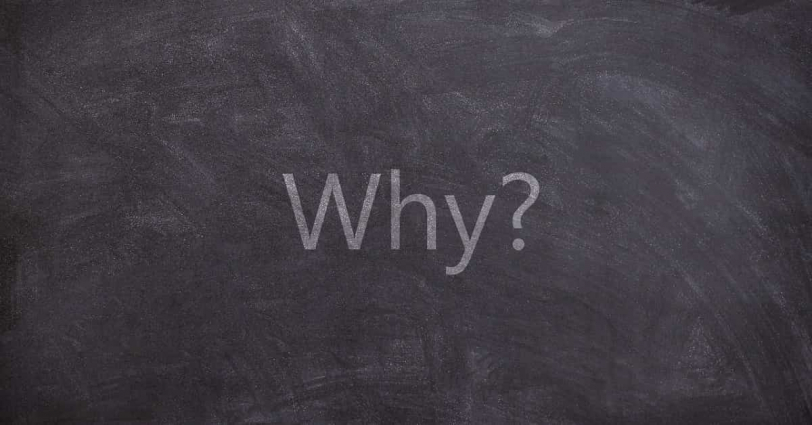





























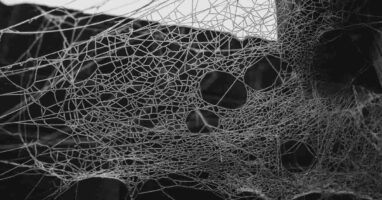















































コメント