目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
監督:村田吉廣, プロデュース:中谷直哉, プロデュース:杉田浩光, プロデュース:八幡麻衣子, 出演:田原総一朗, 出演:小西洋之
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 2015年に変更された「『政治的公平』に関する解釈」は、現在、安倍政権以前の状況に戻っている
- 「放送法」は何故生まれ、安倍政権は何故それに手を入れようとしたのか
- 政権の決定を受けて下されたテレビ局側の素早い「忖度」が、「撤回」後の現在も恐らく引き継がれたままである
「世界報道自由度ランキング63位」に甘んじる日本のジャーナリズムの現状が一発で理解できる作品
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
国会でゴチャゴチャやっていた「放送法の解釈変更」はこう決着していた!映画『テレビ、沈黙。 放送不可能。Ⅱ』で田原総一朗が小西洋之を問い詰める

あわせて読みたい
【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…
「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか
非常に興味深い内容の映画だった。覚えている人もいると思うが、少し前、元総務大臣の高市早苗議員が議員辞職をするとかしないとか国会でゴチャゴチャやっていたことがある。この映画で描かれているのは、この騒動に関係するものだ。いわゆる「放送法の解釈」の話であり、「政権からの圧力があったのではないか」みたいな疑惑がその中心にある。「ニュース番組を見てもよく分からなかった」という人もいるだろうし、問題の本質からズレて高市早苗の進退問題ばかりが取り上げられていたことも余計その状況に拍車をかけていたと言っていいだろう。
その辺りの事情について、問題の発端から、そして恐らく国民のほとんどが知らないだろう「意外な決着」までを、この騒動に火をつけた小西洋之参議院議員に田原総一朗が様々な質問をすることで明らかにしていくのが本作である。
本作における最も重要なポイントについてまずは触れておく
さて、この「放送法」に関するゴタゴタは問題が錯綜しており、非常に分かりづらいので、なかなか上手く捉えられないだろうと思う。しかし、本作『テレビ、沈黙。 放送不可能。Ⅱ』に関して言えば、「絶対に知っておくべき知識」は1つだけだ。それは、後で触れる事情によってテレビ等では一切報じられていないため、国民のほとんどがその事実を知らないはずである。私も、この映画を観て初めて知った。
というわけで、まずはその「最も重要なポイント」について触れておこう。まとめると、以下のようになる。
あわせて読みたい
【権威】心理学の衝撃実験をテレビ番組の収録で実践。「自分は残虐ではない」と思う人ほど知るべき:『…
フランスのテレビ局が行った「現代版ミルグラム実験」の詳細が語られる『死のテレビ実験 人はそこまで服従するのか』は、「権威」を感じる対象から命じられれば誰もが残虐な行為をしてしまい得ることを示す。全人類必読の「過ちを事前に回避する」ための知見を学ぶ
安倍政権時代に高市早苗が発表した、「1つの番組だけから政治的公平性を判断し、電波を停止することも可能である」とする「放送法の解釈変更」は、2023年3月17日に行われた「テレビ放送されない委員会」の場で正式に「撤回」された。
もう少し分かりやすく書くとこうなる。
「放送法の解釈」は、安倍政権以前のもの、つまり「政治的公平性は、放送局全体の番組から総合的に判断される」という解釈に戻った。
あわせて読みたい
【評価】元総理大臣・菅義偉の来歴・政治手腕・疑惑を炙り出す映画。権力を得た「令和おじさん」の素顔…
「地盤・看板・カバン」を持たずに、総理大臣にまで上り詰めた菅義偉を追うドキュメンタリー映画『パンケーキを毒見する』では、その来歴や政治手腕、疑惑などが描かれる。学生団体「ivote」に所属する現役大学生による「若者から政治はどう見えるか」も興味深い
今この記事を読んでくれている方で、「放送法に関しては一定の知識を持っている」という方は、上述した事実を理解していただければ、もうこれ以降の文章を読む必要はない。後は、「その『撤回』を実現させたのが小西洋之議員であること」「総務省の極秘の内部文書を小西洋之に渡した官僚がいたこと」を知っておけば十分だろう。

さて、私自身は映画鑑賞時点で、「放送法の解釈変更」に関してはそれなりに理解していたと思う。ニュース番組等を見て、「何が問題なのか」はある程度分かっていたし、映画を観ながら改めてそう実感することもできた。もちろん、様々な細部について「こんなことが起こっていたんだ」と知れたし、そういう意味でも映画を観て良かったと思う。ただやはり、「『撤回』されていた」という事実には何よりも驚かされた。小西洋之議員がその「撤回」を認めさせた時の映像も映画で流れるのだが、「恐らく、初めて世間に公開されるだろう」と語るぐらい、世間的には知られていない話なのだ。テレビで報じられなかった背景についてはまた後で触れるが、とにかく、「そんな展開になっていたのか」という点に驚かされた。
「放送法の解釈変更」に関する問題の基本情報の整理
さてまずは、「放送法って何?」「解釈の変更?」みたいに感じている人向けに、基本的な情報を整理しておこうと思う。ただ、私の理解不足や認識違いがあるかもしれないので、その点はご容赦願いたい。以下の文章に何か誤りがあったとしても、それは映画の不備を指摘するものではなく、単に私のミスだと理解していただければ幸いである。
あわせて読みたい
【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画
1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品
発端となったのは、2023年3月3日の予算委員会で、小西洋之議員がある質問をしたことだった。それ以前に彼は、総務省の官僚から極秘に内部文書を受け取っており、それに関する質問をしたのである。上映後にトークイベントが行われたのだが、その中で小西洋之は、その内部文書の「性質」について、「『総務省が政権からこのように突っつかれている』という事実を総務省内で共有するために作られたもの」だと語っていた。
そして、自身もかつて総務省の官僚だった小西洋之議員は、その資料をひと目見て「完璧な行政文書だ」と感じたという。見て明らかなぐらい、行政文書としての体裁が整っていたというわけだ。また、「放送法の解釈変更」に関しては、政権が総務省に「明らかに違法だと感じられる要求」を突きつけていたとされている。となれば総務省としては、自分たちの身を守るという意味でも、「このような経緯があってこういう決定をしたのだ」という記録を残しておかなければ後で怖いだろう。そのような様々な背景を踏まえれば、これは間違いなく「総務省で作られた正式な文書」だと判断できるというわけだ。
しかし、何故このような念入りな主張をしているのか。それは、当時の総務大臣だった高市早苗が後に、「この文書は捏造だ」と発言するからである。小西洋之からすれば「そんなことはあり得ない」となるし、先述の経緯を信じるなら、多くの人がそう感じるだろう。「国民に対する裏切りを見て見ぬふり出来ない」と感じた勇気ある内部告発者によって、このような資料が表に出てきたのである。それを「捏造」と言い切って問題の焦点をズラそうとしたというわけだ。
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
では、その極秘文書には一体何が書かれていたのだろうか。その中心的なテーマこそが「放送法の解釈変更」である。「放送法」そのものについては後で詳しく触れるが、その「解釈」について、政権はある変更を行いたかった。そしてそれを実現するために、当時安倍首相の総理補佐官だった礒崎陽輔が総務省に対して、「このような解釈変更をどうにか押し通せ」と、まさに「恫喝」と言うしかない、横車を押すようなやり方を続けていたのだ。その「恫喝」の様子が、文書には記録されているのである。
その文書に記載されている情報を仔細に検討することで、「礒崎陽輔総理補佐官が主導し、安倍首相が追認し、高市早苗総務大臣がそのような事情を理解した上で世間に公表した」という構図が浮かび上がってくるというわけだ。そのような生々しいやり取りを知ることとなった小西洋之が、内部告発をしてくれた官僚の想いに報いるように国会で質問をし、それによって、連日テレビで報じられるような大騒動に発展したのである。
この「解釈変更」は、日本のジャーナリストたちに大きな衝撃を与えることになった。詳しくは「放送法」の説明の中で触れるが、この「解釈変更」を受け入れるのであれば、「日本のジャーナリズムは死んだ」と言うしかない状況になってしまうからである。戦時中のような、「国が報道に直接的に介入する」という状況を許容せざるを得なくなるというわけだ。想像以上に由々しき事態が進行していたのである。
あわせて読みたい
【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ
火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ
「放送法」が誕生したきっかけと、政権がその「解釈」を変更したいと考えた理由
それでは次に、「放送法」そのものの説明に移ることにしよう。まずは、「放送法」が作られた理由から。

この点については非常にシンプルだ。多くの人が知っていると思うが、戦時中の日本では、政権が放送局を支配し、自分たちに都合の良い報道だけをさせていた。いわゆる「大本営発表」である。そして、この時の反省を踏まえた上で作られたのが「放送法」というわけだ。だからこそ「放送法」には、以下のようなスタンスが明確に記載されている。
あわせて読みたい
【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…
三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ
さて、「放送法」そのものの話からは少し脱線するが、作中で田原総一朗が「ジャーナリストを目指すきっかけになった」と語るあるエピソードに触れられる。彼は11歳の時に終戦を迎えたのだが、そのちょっと前までは教師から、「この戦争は、悪の英米からアジア諸国を解放するための素晴らしい戦争である」と教わっていた。しかし終戦を迎えると教師たちは180度意見を変え、「戦争はしてはいけないことなのだ」と言い出すようになったのだ。その後朝鮮戦争が勃発し、田原少年は「戦争反対」と主張したのだが、教師はまた手のひらを返し、「戦争反対」と主張した彼の方が怒られてしまったという。この経験から彼は、「偉い人やマスコミの言うことは信用できない」「国は国民を簡単に騙す」と感じるようになり、ジャーナリストを目指すと決めたのだそうだ。
では話を戻そう。このように高尚な理想の下に誕生した「放送法」だったが、それに手を加えたいと考える人物が現れた。もちろんそれは、安倍元首相である。きっかけとなったのは、「安保法制」に関する審議だった。いわゆる「集団的自衛権」の話である。マスコミも大きく報じたし、また、この「安保法制」に関しては、専門家も「憲法違反だ」と主張するなど、かなり強く反対の声が上がっていた。最終的には強硬的に採決されてしまい、私はこの時以降、「日本は戦争に突き進んでいくつもりなんだな」と感じるようになったわけだが、まあそれはともかく、この時のマスコミ挙げての「大反対」が、安倍元首相には「鬱陶しかった」ようだ。
あわせて読みたい
【絶望】権力の濫用を止めるのは我々だ。映画『新聞記者』から「ソフトな独裁国家・日本」の今を知る
私個人は、「ビジョンの達成」のためなら「ソフトな独裁」を許容する。しかし今の日本は、そもそも「ビジョン」などなく、「ソフトな独裁状態」だけが続いていると感じた。映画『新聞記者』をベースに、私たちがどれだけ絶望的な国に生きているのかを理解する
先に紹介した内部文書には、そのことを示唆するやり取りも記録されていた。ざっくり書けば、「安保法制審議の際の、国民の反対がウザかった。だからちょっと、テレビの報道を押さえつけようぜ」みたいな感覚があったというわけだ。そこで安倍政権が目をつけたのが「放送法 第2章 第4条の第2項」である。第4条は「編集」について規定しているのだが、その第2項で「政治的公平を保つこと」と記載されているのである。
つまり、「この『解釈』を変更すれば、マスコミの頭を押さえつけられるはず」と考えたというわけだ。それでは次で、その辺りの事情についてもう少し詳しく見ていこう。
「解釈変更」に至るまでの流れと、その後の変化
ではそもそも、この「政治的公平を保つこと」という第2項は、これまでどのように「解釈」されていたのだろうか。それは、「あるテレビ局が放送したすべての番組から総合的に判断する」である。例えばQテレビがA・B・Cという3つの報道番組(理屈では報道番組に限る話ではないのだが、実質的にはそう考えていいだろう)を放送しているとしよう。この内、番組Aがかなり政治的公平を欠く内容だったとしても、番組B・Cを含めて総合的に見て、「Qテレビ全体が偏向しているわけではない」と見做されるのであれば、「『放送法』には抵触していない」と判断されていたというわけだ。まあ、普通に考えて、真っ当な判断と言っていいだろう。
あわせて読みたい
【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…
一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う
しかし安倍政権はこれを、「ある1つの番組からだけでも、その放送局全体の政治的公平性を判断可能」という解釈に変えようと考えた。つまり先の例で言えば、「番組Aの政治的公平が保たれていない時点で、Qテレビが『放送法』の基準を満たしていないと判断される」ということである。

しかしそうだとして、一体その何が問題なのか。それは「免許停止の可能性がある」という点にある。テレビ放送というのは、総務省管轄の「免許事業」であり、総務省の許可がなければ事業を行うことが出来ない。つまりこのような「解釈変更」を実現すれば、「おたくは『放送法』に抵触しているので、免許停止になる可能性がありますねぇ」と「脅す」ことが可能になるのである。これで政権にとって都合の悪い報道番組を「潰す」ことが出来るというわけだ。
さて当然だが、総務省としてもこんな解釈変更など到底許容できるものではなかった。だから、必死に抵抗したそうだ。しかし、先の文書から読み取れるのは、その度に礒崎総理補佐官からボロクソに罵倒されるというやり取りだった。こうして総務省も、軟化せざるを得なくなっていくのである。
あわせて読みたい
【感涙】衆議院議員・小川淳也の選挙戦に密着する映画から、「誠実さ」と「民主主義のあり方」を考える…
『衆議院議員・小川淳也が小選挙区で平井卓也と争う選挙戦を捉えた映画『香川1区』は、政治家とは思えない「誠実さ」を放つ”異端の議員”が、理想とする民主主義の実現のために徒手空拳で闘う様を描く。選挙のドキュメンタリー映画でこれほど号泣するとは自分でも信じられない
その背景には、官僚人事に関するある変化も関係していると言えるだろう。確か安倍政権下で変更されたはずだが、新たに「内閣人事局」という組織が作られ、「内閣が官僚の人事を一手に掌握する」という形に変わったのだ。それまでの人事の形態を知っているわけではないが、恐らく省庁ごとに独立で行われていたのだろう。だから、官僚が政権に反対するような立場を取っても、省庁内でその行動が承認されていれば、人事に影響はなかった。しかし今は、人事の主導権が内閣にあるため、「政権に歯向かうと左遷させられるかもしれない」という可能性を拭いきれないのである。この仕組みのせいで、官僚は大いに萎縮しているのだ。
こうして、横紙破りとでも言うべき横暴が通ってしまい、礒崎総理補佐官が主導した「放送法の解釈変更」が現実のものとなってしまった。そしてその後、当時の総務大臣である高市早苗が委員会で公に発表し、世間の知るところとなったのである。
テレビ局の動きは早かった。高市早苗の発表と呼応するように、「物言うキャスター」の交代が相次いだのだ。『サンデーモーニング』の岸井成格、『報道ステーション』の古舘伊知郎、『クローズアップ現代』の国谷裕子らの降板が次々に発表された。各テレビ局は、「高市早苗の発表とは関係なく、自主的な判断である」との声明を発表したそうだが、そんな風に受け取った人はほとんどいないだろう。「放送法の解釈変更」を受けて、「いち番組のキャスターの発言で免許停止にさせられたらたまらん」と考え、各社が降板を決めたとしか考えられない。
あわせて読みたい
【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…
「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う
映画に登場した小西洋之議員も実際に、テレビ局の「忖度」「萎縮」を肌で感じ取っていた。彼が、3月3日の委員会で質問したことは既に触れたが、それ以前に、内部文書を受け取った時点で、マスコミにもあらかじめ情報提供を行っていたのだ。
経緯はこうである。内部文書を受け取ってすぐ、小西洋之議員は総務省に掛け合った。しかしその時の対応は、まったく暖簾に腕押しだったという。そこで「公表しますよ」と伝え、2023年3月2日に記者会見を行った。しかし、60名ほどの記者が会場に集ったにも拘わらず、この件はほとんどと言っていいほど報道されなかったのである。
さらに言えば、翌3月3日の予算委員会での質問も大して取り上げられなかった。そしてその後、「この文書は捏造だ」と繰り返し主張していた高市早苗が、「もし捏造でないなら議員を辞める」と発言してからようやく報道が加熱したのである。しかしその報道も、「放送法」に関する話はほとんど取り上げず、「高市早苗が議員辞職するか否か」ばかりが議論されていたというわけだ。
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
「撤回」を勝ち取った小西洋之議員の奮闘と、テレビ制作現場における「忖度」の継続
さて、それ以降の流れはテレビで報じられていた通り、高市早苗にばかり焦点が当たったものの、結局議員辞職することはなく、なし崩し的に問題が収束してしまう。しかしそんな中でも、小西洋之議員は独自の奮闘を行っていた。総務省から「撤回」を引き出したのである。

それは3月17日のことだった。小西洋之議員は、当初からテレビ中継の予定がない委員会の場において、総務省から正式に「安倍政権時代の解釈は撤回する」という回答を引き出したのだ。これは総務省の公式な決定であり、つまり現在は、「いち番組だけでも政治的公平が判断可能」という、2015年から2023年3月16日まで存在していた「解釈」は無くなり、安倍政権以前の解釈、つまり「放送局全体で政治的公平を判断する」という従来のやり方に戻ったのである。
あわせて読みたい
【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…
映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた
しかし、何故小西洋之議員は「テレビ中継の予定がない委員会」でこのようなやり取りを行うことにしたのだろうか。その裏話が興味深かった。小西洋之議員は水面下で事前に総務省とやり取りをしていたわけだが、その際、「テレビ中継される委員会では撤回出来ない」と申し入れがあったというのだ。ここからは私の勝手な推測だが、安倍元首相が亡くなり、政権が変わった今も、総務省は「『放送法の解釈変更』を撤回すること」が「政権に対する批判」と受け取られる可能性を恐れているのではないかと思う。しかし総務省としては当然、こんな「改悪」は撤回したい。だから、「世間では広く取り上げられず、しかし総務省としてはきちんと正しい対応をしたと見做される形」での対応しか出来ないと考えたのだろうと思う。そんなわけで、冒頭でも触れたが、小西洋之議員が「撤回」を引き出した委員会の映像は、恐らく本作が初出だろうとのことだった。
ただ当然だが、この委員会の様子は別に「秘匿」されていたわけでもなんでもない。映像素材は、手に入れようと思えばマスコミだって入手出来たはずだ。またそもそも、この委員会の様子については記者クラブを通じて情報は流れているわけで、少なくとも記者はその事実を知っていたはずである。だから、「撤回を引き出した」という事実を「報じない」と決めたのは、「テレビ局側の意思」と考えていいと思う。マスコミでこの「撤回」を取り上げたのは、朝日新聞と東京新聞だけだったというが、それも「社説」で言及があっただけだったそうだ。
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
この事実だけ捉えてみても、マスコミによる「忖度」「萎縮」が継続していると判断できる思う。
一応、少しだけ擁護しておこう。私は新聞を読まず、基本的にニュースはテレビから仕入れている。そして、高市早苗が議員辞職するかどうかばかり報じていた時期にも、番組によっては「放送法の解釈変更」についてかなり詳しく説明していた。だからこそ、本作鑑賞前の時点で私は、それなりの知識を持っていたのだ。確かに、「解釈変更が『撤回』されたこと」はテレビで報じていなかったのだと思うが、「放送法」に関する説明はされていたので、「事実」はそれなりに報じていると言えるだろう。
ただ映画の中で小西洋之議員と田原総一朗は、「テレビは『政策論評』をしなくなった」と指摘しており、確かにそれはその通りかもしれないと思う。私が知る限りでは、朝の番組で橋下徹が政策の良し悪しに言及しているのを見る機会はあるが、他の番組ではあまりない。「事実としてこうなっています」ということは報じるが、それが良いのか悪いのかという個人的な見解を話す人は、私が見ている範囲ではかなり減ったと感じる。
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
それは、2015年に高市早苗が「放送法の解釈変更」を発表してからずっと続いてきた「忖度」「萎縮」の賜物なのだと思うが、その一方で小西洋之議員は映画の中で、「安倍政権時代の解釈が『撤回』されたという事実を、テレビ制作の現場にいる人たちがそもそもどの程度正しく理解しているのが疑問だ」と語っていた。法解釈が変更されたところで、その事実をテレビ制作側が認識していなければ、それまでの「忖度」「萎縮」が無くなるはずがない。恐らくこのような状況を見越して、総務省は「テレビ中継のない委員会」を指定したのだろうし、まさにその狙いは上手く行ったと言っていいだろうと思う。小西洋之議員も田原総一朗も、彼らの肌感覚として、「放送に関わる人でも知らない人の方が多いんじゃないか」と言っていた。

はっきりと「撤回」という回答が引き出されたのだし、それを明確に証明する映像も残っているのだから、テレビ局が「免許停止」を恐れる理由はまったくない。これまで通り、放送局全体で公平性を保っていれば、「ギリギリを攻める」ような番組を作ってもいいはずだ。しかし残念ながら、そうはなっていない。まあ恐らく、「今後同じようなことが起こらないとも限らない」と警戒しているのだろうし、確かにそのような危惧は常に持ち続けるべきだと私も思う。しかしそうだとしても、現状のスタンスで良いはずがないだろう。
テレビ局は、高市早苗発言を受けて「降板」という形でインパクトのある反応を素早く見せたのだから、今回の「撤回」についても、「テレビ局は変革した」と伝わるようなインパクトのある反応を示してもいいように感じる。そのような変化を期待したいものだ。
あわせて読みたい
【誠実】映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』で長期密着した政治家・小川淳也の情熱と信念が凄まじい
政治家・小川淳也に17年間も長期密着した映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』は、誠実であるが故に大成できない1人の悩める政治家のありのままが描かれる。サラリーマン家庭から政治家を目指し、未来の日本を健全にするために奮闘する男の信念と情熱が詰まった1本
日本のジャーナリズムはどうあるべきか
さて、以前から認識していたことではあるが、「国境なき記者団」というNGOが発表している「世界報道自由度ランキング」において、日本は非常に評価が低い。
Sustainable Japan | 世界のサステ…
【国際】世界報道自由度ランキング2023年版、首位ノルウェー。日本は68位で3位アップ | Sustainable Japan …
国際ジャーナリストNGOの国境なき記者団(RSF)は5月3日、「世界報道自由度ランキング」の2023年版を発表した。首位はノルウェー。日本は68位だった。RSFは2002年から毎…
2023年度は180ヶ国を対象に調査が行われ、日本は63位。「レソト」「リベリア」「モーリシャス」「ガイアナ」「ブルキナファソ」「ベリーズ」などの聞き馴染みのない国にも負けているし、アジア圏で比べても「韓国」「台湾」に大きく水をあけられているのだ。私の個人的な感覚としても「日本の報道はかなりヤバい」と思うし、それはもちろん、「日本の政治」に対する絶望感から来るものでもある。
「世界報道自由度ランキング」の下位要因は色々考えられると思うが、映画に絡めた話をすれば、「許認可制」の仕組みが挙げられるだろう。映画の中では、ヨーロッパや韓国の仕組みが紹介されていた。それらの国では「独立した第三者機関」が公平性などを判断して放送事業の免許を与えるという制度になっているのだそうだ。つまり、そもそもの仕組みからして、「時の政権の関与する余地は無い」ということである。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見
ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す
日本の場合、「放送法の解釈変更」が撤回されたとはいえ、テレビ放送が「総務省の免許事業」であることに変わりはない。そのため、「放送法の解釈変更」なんてまだるっこしいことをせずとも、「国の圧力によって放送が歪められる」可能性は全然残されているのだ。実際、過去にそのような出来事が起こっている。
1968年、TBSの報道番組『ニュースコープ』のエースキャスターだった田英夫の降板が決まった。この背景には、自民党の圧力があったと言われている。そのため、この解任劇をきっかけとして、一部のTBS社員が「報道の自由は死んだ」という喪章をつけてストライキに入ったそうだ。
結局、ストライキによって状況が変わることはなかったため、志を同じくするTBS社員が一斉に退社し、その後「テレビマンユニオン」を立ち上げた。そしてこの「テレビマンユニオン」こそ、田原総一朗と共に「放送不可能。」シリーズを作っている制作会社なのだ。それを知るとより一層、彼らがこの映画に込めた想いが理解できるのではないかと思う。

あわせて読みたい
【絶望】安倍首相へのヤジが”排除”された衝撃の事件から、日本の民主主義の危機を考える:映画『ヤジと…
映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』が映し出すのは、「政治家にヤジを飛ばしただけで国家権力に制止させられた個人」を巡る凄まじい現実だ。「表現の自由」を威圧的に抑えつけようとする国家の横暴は、まさに「民主主義」の危機を象徴していると言えるだろう。全国民が知るべき、とんでもない事件である
ジャーナリズムにとって最も重要なことは、「現内閣、現首相を批判すること」であり、そのことは本作でも指摘されていた。しかし、「放送法の解釈変更」に関するゴタゴタによって、日本では一層、その重要な役割が軽視されるようになったようにも思う。ヌルい報道ばかりに接してきたことで、国民の側が「報道ってそういうものなんだろう」と感じるようになっているのかもしれない。あるいは逆に、「ジャーナリズムが成すべき真っ当な批判」が「単に悪口を言っている」みたいに受け取られ、「批判する側が悪い」みたいな風潮が生まれてしまう可能性さえ考えられるだろう。
「ジャーナリズムの役割」について、マスコミだけではなく私たち国民も改めて認識し直すべきだと感じさせられた。
映画を観てもイマイチ理解できなかったこと
上映後にトークイベントが行われたのだが、質疑応答の時間はなかった。もしあれば聞きたいと考えていたことがあるので、その点について触れてこの記事を終えようと思う。
あわせて読みたい
【扇動】人生うまくいかないと感じる時に読みたい瀧本哲史の本。「未来をどう生きる?」と問われる1冊:…
瀧本哲史は非常に優れたアジテーターであり、『2020年6月30日にまたここで会おう』もまさにそんな1冊。「少数のカリスマ」ではなく「多数の『小さなリーダー』」によって社会が変革されるべきだ、誰にだってやれることはある、と若者を焚きつける、熱量満載の作品
さて、以下に書く話は、もしかしたら「政治の世界では当たり前のこと」なのかもしれないし、単に私の「知識不足」を晒すだけになるかもしれないとも思う。しかし私は、「政治に詳しくない人間」の1人として、「恐らく世間の人もこういうことは理解していないだろう」と感じている。永田町界隈では「当たり前」かもしれないが、世間的には恐らくそうではないはずなので、詳しい方がいたら教えてほしい。
疑問は2つあるのだが、1つ目は「政権、あるいは省庁による『法律の解釈変更』は、そもそも法律的に認められているのかどうか」である。
私は、「最高裁判所が『法律の解釈変更』を行えること」については理解している。正しい捉え方かどうか分からないが、「立法府ではない裁判所が解釈変更を行う」という仕組みは真っ当に感じられるので、特に問題はないように思う。しかし今回の「放送法の解釈変更」は、立法に関わる政権によって行われているのだ。それは、三権分立的な意味においてそもそも許容されていることなのだろうか?
作中で繰り返し言及される内部文書でも、この「放送法の解釈変更」については、「専門家を呼んで議論すべきだ」と指摘されている。それほどの大掛かりな「解釈変更」が政権から強制されていたのである。もちろん、専門家と議論するような手続きは踏んでもらいたいところだが、しかしそれ以前の話として、「そもそも『法律の解釈変更』は法的に認められた行為なのか?」という点が気になったというわけだ。
あわせて読みたい
【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す
香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す
さらに、1点目と関係する話ではあるが、「法律の解釈変更」が認められているのだとして、「それは『省庁』の判断で行うことなのか?」という点も疑問である。映画ではとにかく、「政権側が総務省に無理やり解釈変更を迫った」という描かれ方になっているのだが、そもそも「政権の判断で解釈変更できるなら、総務省を動かそうとしなくてもいい」はずだろう。そして、政権の独断では出来ない仕組みになっているのなら、「じゃあ、省庁にはその権限があるのか」という疑問が出てくるというわけだ。

要するに、「『法律の解釈変更』が許されているのだとして、その『主体』は一体どこにあると定められているのか」という話なのである。
「解釈変更の是非」についても「解釈変更の主体」についても、作中では詳しく触れられなかったので、「そもそも前提が上手く理解できないまま話が展開されていた」という印象になってしまった。「『法律の解釈変更』は認められており、その『主体』は各省庁である」みたいな説明がなされていれば、状況をより捉えやすかっただろうが、「前提として何が許容されているのか」が判然としなかったため、「どの行為が『横紙破り』だったのか」についても上手く捉えきれなかったというわけだ。この辺りは、もう少し説明があっても良かったかなと思う。
あわせて読みたい
【評価】映画『シン・ゴジラ』は、「もしゴジラが実際に現れたら」という”現実”を徹底的にリアルに描く
ゴジラ作品にも特撮映画にもほとんど触れてこなかったが、庵野秀明作品というだけで観に行った『シン・ゴジラ』はとんでもなく面白かった。「ゴジラ」の存在以外のありとあらゆるものを圧倒的なリアリティで描き出す。「本当にゴジラがいたらどうなるのか?」という”現実”の描写がとにかく素晴らしかった
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【問題】映画『国葬の日』が切り取る、安倍元首相の”独裁”が生んだ「政治への関心の無さ」(監督:大島新)
安倍元首相の国葬の1日を追ったドキュメンタリー映画『国葬の日』は、「国葬」をテーマにしながら、実は我々「国民」の方が深堀りされる作品だ。「安倍元首相の国葬」に対する、全国各地の様々な人たちの反応・価値観から、「『ソフトな独裁』を維持する”共犯者”なのではないか」という、我々自身の政治との向き合い方が問われているのである
さて、大事なことなので何度でも繰り返すが、「『放送法の解釈変更』は『撤回』された」のであり、テレビ局は「免許停止」を危惧することなく番組作りが可能な状況に戻ったというわけだ。しかしその事実は広く知られていないし、そして、このことがテレビ制作の現場で共有されなければ、テレビ番組が変わるはずもない。「ジャーナリズム」の根幹に関わるため、マスコミに大いに関係すると言える話なのだが、もちろん、私たちには無関係なんてはずもない。「世界報道自由度ランキング63位」の国に住まざるを得ない状況は、ある意味で私たち自身が生み出しているとも言えるからだ。
「放送法の解釈変更」という単語だけ聞くとなかなか関心を持ちにくいかもしれないが、「私たちが普段接している情報が、どのように作られ届けられているのか」に直結する話だと理解できれば、関心度はかなり高まるはずだと思う。私たちにも大いに関わる世界の話が描かれる作品であり、多くの人が知るべき事実だと私は感じた。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【権力】コンクラーベをリアルに描く映画『教皇選挙』は、ミステリ的にも秀逸で面白い超社会派物語(監…
映画『教皇選挙』は、「カトリックの教皇を選ぶコンクラーベ」という、一般的な日本人にはまず馴染みのないテーマながら劇場が満員になるほどで、まずそのことに驚かされた。本質的には「権力争い」なのだが、そこに「神に仕える者」という宗教ならではの要素が組み込まれることによって特異で狂気的な状況が生み出されている
あわせて読みたい
【面白い】映画『ラストマイル』は、物流問題をベースに「起こり得るリアル」をポップに突きつける(監…
映画『ラストマイル』は、「物流」という「ネット社会では誰にでも関係し得る社会問題」に斬り込みながら、実に軽妙でポップな雰囲気で展開されるエンタメ作品である。『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界で展開される「シェアード・ユニバース」も話題で、様々な人の関心を広く喚起する作品と言えるだろう
あわせて読みたい
【あらすじ】老夫婦の”穏やかな日常”から核戦争の恐怖を描くアニメ映画『風が吹くとき』の衝撃
一軒家の中だけで展開される老夫婦の日常から「核戦争」の危機をリアルに描き出す映画『風が吹くとき』は、日本では1987年に公開された作品なのだが、今まさに観るべき作品ではないかと。世界的に「核戦争」の可能性が高まっているし、また「いつ起こるか分からない巨大地震」と読み替えても成立する作品で、実に興味深かった
あわせて読みたい
【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…
映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた
あわせて読みたい
【幻惑】映画『落下の解剖学』は、「真実は誰かが”決める”しかない」という現実の不安定さを抉る
「ある死」を巡って混沌とする状況をリアルに描き出す映画『落下の解剖学』は、「客観的な真実にはたどり着けない」という困難さを炙り出す作品に感じられた。事故なのか殺人なのか自殺なのか、明確な証拠が存在しない状況下で、憶測を繋ぎ合わせるようにして進行する「裁判」の様子から、「『真実性』の捉えがたさ」がよく理解できる
あわせて読みたい
【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…
上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした
あわせて読みたい
【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件
映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった
あわせて読みたい
【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…
映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である
あわせて読みたい
【問題】映画『国葬の日』が切り取る、安倍元首相の”独裁”が生んだ「政治への関心の無さ」(監督:大島新)
安倍元首相の国葬の1日を追ったドキュメンタリー映画『国葬の日』は、「国葬」をテーマにしながら、実は我々「国民」の方が深堀りされる作品だ。「安倍元首相の国葬」に対する、全国各地の様々な人たちの反応・価値観から、「『ソフトな独裁』を維持する”共犯者”なのではないか」という、我々自身の政治との向き合い方が問われているのである
あわせて読みたい
【絶望】安倍首相へのヤジが”排除”された衝撃の事件から、日本の民主主義の危機を考える:映画『ヤジと…
映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』が映し出すのは、「政治家にヤジを飛ばしただけで国家権力に制止させられた個人」を巡る凄まじい現実だ。「表現の自由」を威圧的に抑えつけようとする国家の横暴は、まさに「民主主義」の危機を象徴していると言えるだろう。全国民が知るべき、とんでもない事件である
あわせて読みたい
【衝撃】映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想外すぎる着地を見せる普通じゃないドキュメンタリー
国連事務総長だったハマーショルドが乗ったチャーター機が不審な墜落を遂げた事件を、ドキュメンタリー映画監督マッツ・ブリュガーが追う映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想もつかない衝撃の展開を見せる作品だ。全世界を揺るがしかねない驚きの”真実”とは?
あわせて読みたい
【映画】『街は誰のもの?』という問いは奥深い。「公共」の意味を考えさせる問題提起に満ちた作品
映画『街は誰のもの?』は、タイトルの通り「街(公共)は誰のものなのか?」を問う作品だ。そしてそのテーマの1つが、無許可で街中に絵を描く「グラフィティ」であることもまた面白い。想像もしなかった問いや価値観に直面させられる、とても興味深い作品である
あわせて読みたい
【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実
弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている
あわせて読みたい
【抵抗】若者よ、映画『これは君の闘争だ』を見ろ!学校閉鎖に反対する学生運動がブラジルの闇を照らす
映画『これは君の闘争だ』で描かれるのは、厳しい状況に置かれた貧困層の学生たちによる公権力との闘いだ。「貧困層ばかりが通う」とされる公立校が大幅に再編されることを知った学生が高校を占拠して立て籠もる決断に至った背景を、ドキュメンタリー映画とは思えないナレーションで描く異色作
あわせて読みたい
【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…
ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?
あわせて読みたい
【真実】田原総一朗✕小泉純一郎!福島原発事故後を生きる我々が知るべき自然エネルギーの可能性:映画『…
田原総一朗が元総理・小泉純一郎にタブー無しで斬り込む映画『放送不可能。「原発、全部ウソだった」』は、「原発推進派だった自分は間違っていたし、騙されていた」と語る小泉純一郎の姿勢が印象的だった。脱原発に舵を切った小泉純一郎が、原発政策のウソに斬り込み、再生可能エネルギーの未来を語る
あわせて読みたい
【信念】映画『ハマのドン』の主人公、横浜港の顔役・藤木幸夫は、91歳ながら「伝わる言葉」を操る
横浜港を取り仕切る藤木幸夫を追うドキュメンタリー映画『ハマのドン』は、盟友・菅義偉と対立してでもIR進出を防ごうとする91歳の決意が映し出される作品だ。高齢かつほとんど政治家のような立ち位置でありながら、「伝わる言葉」を発する非常に稀有な人物であり、とても興味深かった
あわせて読みたい
【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る
TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す
あわせて読みたい
【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…
稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる
あわせて読みたい
【爆笑】ダースレイダー✕プチ鹿島が大暴れ!映画『センキョナンデス』流、選挙の楽しみ方と選び方
東大中退ラッパー・ダースレイダーと新聞14紙購読の時事芸人・プチ鹿島が、選挙戦を縦横無尽に駆け回る様を映し出す映画『劇場版 センキョナンデス』は、なかなか関わろうとは思えない「選挙」の捉え方が変わる作品だ。「フェスのように選挙を楽しめばいい」というスタンスが明快な爆笑作
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
あわせて読みたい
【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…
「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…
「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか
あわせて読みたい
【誠実】映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』で長期密着した政治家・小川淳也の情熱と信念が凄まじい
政治家・小川淳也に17年間も長期密着した映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』は、誠実であるが故に大成できない1人の悩める政治家のありのままが描かれる。サラリーマン家庭から政治家を目指し、未来の日本を健全にするために奮闘する男の信念と情熱が詰まった1本
あわせて読みたい
【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画
1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品
あわせて読みたい
【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す
香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す
あわせて読みたい
【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ
ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見
ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す
あわせて読みたい
【狂気】アメリカの衝撃の実態。民営刑務所に刑務官として潜入した著者のレポートは国をも動かした:『…
アメリカには「民営刑務所」が存在する。取材のためにその1つに刑務官として潜入した著者が記した『アメリカン・プリズン』は信じがたい描写に溢れた1冊だ。あまりに非人道的な行いがまかり通る狂気の世界と、「民営刑務所」が誕生した歴史的背景を描き出すノンフィクション
あわせて読みたい
【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画
映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい
あわせて読みたい
【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り
プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品
あわせて読みたい
【不謹慎】コンプライアンス無視の『テレビで会えない芸人』松元ヒロを追う映画から芸と憲法を考える
かつてテレビの世界で大ブレイクを果たしながら、現在はテレビから完全に離れ、年間120もの公演を行う芸人・松元ヒロ。そんな知る人ぞ知る芸人を追った映画『テレビで会えない芸人』は、コンプライアンスに厳しく、少数派が蔑ろにされる社会へ一石を投じる、爆笑社会風刺である
あわせて読みたい
【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』
2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない
あわせて読みたい
【誇り】福島民友新聞の記者は、東日本大震災直後海に向かった。門田隆将が「新聞人の使命」を描く本:…
自身も東日本大震災の被災者でありながら、「紙齢をつなぐ」ために取材に奔走した福島民友新聞の記者の面々。『記者たちは海に向かった』では、取材中に命を落とした若手記者を中心に据え、葛藤・後悔・使命感などを描き出す。「新聞」という”モノ”に乗っかっている重みを実感できる1冊
あわせて読みたい
【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…
原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す
あわせて読みたい
【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ
火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ
あわせて読みたい
【衝撃】『ゆきゆきて、神軍』はとんでもないドキュメンタリー映画だ。虚実が果てしなく入り混じる傑作
奥崎謙三という元兵士のアナーキストに密着する『ゆきゆきて、神軍』。ドキュメンタリー映画の名作として名前だけは知っていたが、まさかこんなとんでもない映画だったとはと驚かされた。トークショーで監督が「自分の意向を無視した編集だった」と語っていたのも印象的
あわせて読みたい
【悲哀】2度の東京オリンピックに翻弄された都営アパートから「公共の利益」と「個人の権利」を考える:…
1964年の東京オリンピックを機に建設された「都営霞ケ丘アパート」は、東京オリンピック2020を理由に解体が決まり、長年住み続けた高齢の住民に退去が告げられた。「公共の利益」と「個人の権利」の狭間で翻弄される人々の姿を淡々と映し出し、静かに「社会の在り方」を問う映画
あわせて読みたい
【評価】元総理大臣・菅義偉の来歴・政治手腕・疑惑を炙り出す映画。権力を得た「令和おじさん」の素顔…
「地盤・看板・カバン」を持たずに、総理大臣にまで上り詰めた菅義偉を追うドキュメンタリー映画『パンケーキを毒見する』では、その来歴や政治手腕、疑惑などが描かれる。学生団体「ivote」に所属する現役大学生による「若者から政治はどう見えるか」も興味深い
あわせて読みたい
【民主主義】占領下の沖縄での衝撃の実話「サンマ裁判」で、魚売りのおばぁの訴えがアメリカをひっかき…
戦後の沖縄で、魚売りのおばぁが起こした「サンマ裁判」は、様々な人が絡む大きな流れを生み出し、最終的に沖縄返還のきっかけともなった。そんな「サンマ裁判」を描く映画『サンマデモクラシー』から、民主主義のあり方と、今も沖縄に残り続ける問題について考える
あわせて読みたい
【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る
地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する
あわせて読みたい
【想像力】「知らなかったから仕方ない」で済ませていいのか?第二の「光州事件」は今もどこかで起きて…
「心地いい情報」だけに浸り、「知るべきことを知らなくても恥ずかしくない世の中」を生きてしまっている私たちは、世界で何が起こっているのかあまりに知らない。「光州事件」を描く映画『タクシー運転手 約束は海を越えて』から、世界の見方を考える
あわせて読みたい
【驚愕】正義は、人間の尊厳を奪わずに貫かれるべきだ。独裁政権を打倒した韓国の民衆の奮闘を描く映画…
たった30年前の韓国で、これほど恐ろしい出来事が起こっていたとは。「正義の実現」のために苛烈な「スパイ狩り」を行う秘密警察の横暴をきっかけに民主化運動が激化し、独裁政権が打倒された史実を描く『1987、ある闘いの真実』から、「正義」について考える
あわせて読みたい
【感涙】衆議院議員・小川淳也の選挙戦に密着する映画から、「誠実さ」と「民主主義のあり方」を考える…
『衆議院議員・小川淳也が小選挙区で平井卓也と争う選挙戦を捉えた映画『香川1区』は、政治家とは思えない「誠実さ」を放つ”異端の議員”が、理想とする民主主義の実現のために徒手空拳で闘う様を描く。選挙のドキュメンタリー映画でこれほど号泣するとは自分でも信じられない
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
あわせて読みたい
【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…
「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える
あわせて読みたい
【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?
一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
あわせて読みたい
【逸脱】「人生良いことない」と感じるのは、「どう生きたら幸せか」を考えていないからでは?:『独立…
「常識的な捉え方」から逸脱し、世の中をまったく異なる視点から見る坂口恭平は、「より生きやすい社会にしたい」という強い思いから走り続ける。「どう生きたいか」から人生を考え直すスタンスと、「やりたいことをやるべきじゃない理由」を『独立国家のつくりかた』から学ぶ
あわせて読みたい
【絶望】権力の濫用を止めるのは我々だ。映画『新聞記者』から「ソフトな独裁国家・日本」の今を知る
私個人は、「ビジョンの達成」のためなら「ソフトな独裁」を許容する。しかし今の日本は、そもそも「ビジョン」などなく、「ソフトな独裁状態」だけが続いていると感じた。映画『新聞記者』をベースに、私たちがどれだけ絶望的な国に生きているのかを理解する
あわせて読みたい
【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…
歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る
あわせて読みたい
【権利】「難民だから支援すべき」じゃない。誰でも最低限の安全が確保できる世界であるべきだ:映画『…
難民申請中の少年が、国籍だけを理由にチェスの大会への出場でが危ぶまれる。そんな実際に起こった出来事を基にした『ファヒム パリが見た奇跡』は実に素晴らしい映画だが、賞賛すべきではない。「才能が無くても安全は担保されるべき」と考えるきっかけになる映画
あわせて読みたい
【勇敢】後悔しない生き方のために”間違い”を犯せるか?法に背いてでも正義を貫いた女性の生き様:映画…
国の諜報機関の職員でありながら、「イラク戦争を正当化する」という巨大な策略を知り、守秘義務違反をおかしてまで真実を明らかにしようとした実在の女性を描く映画『オフィシャル・シークレット』から、「法を守る」こと以上に重要な生き方の指針を学ぶ
あわせて読みたい
【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…
「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える
あわせて読みたい
【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…
金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る
あわせて読みたい
【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像
1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ
あわせて読みたい
【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…
一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う
あわせて読みたい
【衝撃】森達也『A3』が指摘。地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教は社会を激変させた
「オウム真理教は特別だ、という理由で作られた”例外”が、いつの間にか社会の”前提”になっている」これが、森達也『A3』の主張の要点だ。異常な状態で続けられた麻原彰晃の裁判を傍聴したことをきっかけに、社会の”異様な”変質の正体を理解する。
あわせて読みたい
【加虐】メディアの役割とは?森達也『A』が提示した「事実を報じる限界」と「思考停止社会」
オウム真理教の内部に潜入した、森達也のドキュメンタリー映画『A』は衝撃を与えた。しかしそれは、宗教団体ではなく、社会の方を切り取った作品だった。思考することを止めた社会の加虐性と、客観的な事実など切り取れないという現実について書く
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
あわせて読みたい
【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…
日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書
あわせて読みたい
【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…
三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
メディア・マスコミ・表現の自由【本・映画の感想】 | ルシルナ
様々な現実を理解する上で、マスコミや出版などメディアの役割は非常に大きいでしょう。情報を受け取る我々が正しいリテラシーを持っていなければ、誤った情報を発信する側…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…






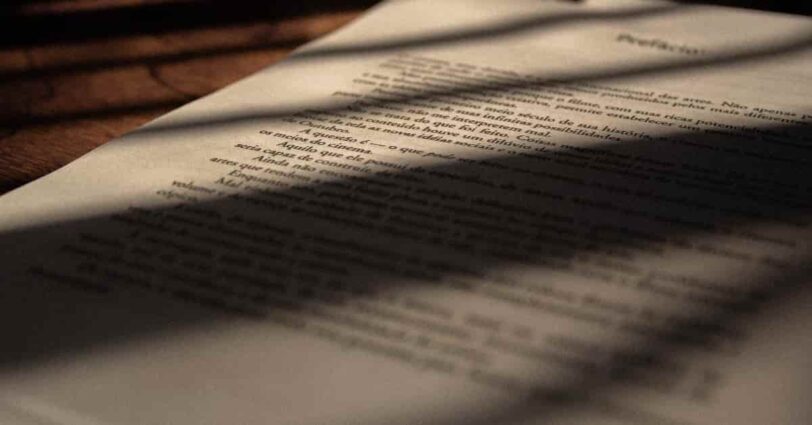



































































































コメント