目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
「太陽(ティダ)の運命」公式HP
VIDEO
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
今どこで観れるのか?
公式HPの劇場情報 をご覧ください
この記事の3つの要点
「基地問題」という難問と向き合わざるを得ない沖縄県知事として数奇な”運命”を辿った大田昌秀と翁長雄志について 大田昌秀がどうしても許容できなかった「不健全な民主主義」とは? 大田昌秀に対して大批判を展開した翁長雄志が知事となり、大田昌秀の苦悩を知るに至るまでの奮闘 私たちに出来る第一歩としては、「基地問題は沖縄の問題ではなく、日本全体の問題だ」と認識することだろうと思う
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
沖縄の基地問題の遍歴を追う映画『太陽(ティダ)の運命』は、大田昌秀・翁長雄志の2人の知事に焦点を当てつつ、その苦悩の歴史を炙り出す
実に興味深い作品 だった。一般的に、ドキュメンタリー映画はフィクションの映画と比べると注目度が低い し、さらに本作の場合は、「沖縄の基地問題」という内容的にも「観たい!」という気分になる人は決して多くない だろうが、それでも、何か機会があれば是非観てほしい なと思う。
あわせて読みたい
【友情】映画『ノー・アザー・ランド』が映し出す酷すぎる現実。イスラエル軍が住居を壊す様は衝撃だ
イスラエルのヨルダン川西岸地区内の集落マサーフェル・ヤッタを舞台にしたドキュメンタリー映画『ノー・アザー・ランド』では、「昔からその場所に住み続けているパレスチナ人の住居をイスラエル軍が強制的に破壊する」という信じがたい暴挙が映し出される。そんな酷い現状に、立場を越えた友情で立ち向かう様を捉えた作品だ
映画『太陽(ティダ)の運命』内で2度言及される、大田昌秀による印象的な言葉
『太陽(ティダ)の運命』というタイトルからはちょっと内容を想像しにくい とは思うが、本作は先述した通り「沖縄の基地問題 」を扱っており、そしてその問題を、「歴代の沖縄県知事」に焦点を当てながら描き出す作品 である。ちなみに「ティダ」というのは沖縄の方言で、「太陽」だけではなく「リーダー」を意味する言葉 でもあるらしい。太陽が象徴する「沖縄」と、そんな沖縄の未来を握る「リーダー」の”運命”を追った作品 というわけだ。
さて私はこれまで、映画『サンマデモクラシー』『シン・ちむどんどん』などの「沖縄の近現代史を扱ったドキュメンタリー」を観てきた し(ただ、本作監督の『米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー』などは観ていない)、それらの作品で沖縄の「基地問題」や「歴史」に触れる機会は結構あった 。しかし当然ではあるが、まだまだ知らないことはたくさんある 。本作は「基地問題」に絞ってその歴史を丁寧に追っていく作品 であり、「なるほど、こういう流れで今このようになっているのか」ということが凄く良く理解できた 気になれた。
あわせて読みたい
【民主主義】占領下の沖縄での衝撃の実話「サンマ裁判」で、魚売りのおばぁの訴えがアメリカをひっかき…
戦後の沖縄で、魚売りのおばぁが起こした「サンマ裁判」は、様々な人が絡む大きな流れを生み出し、最終的に沖縄返還のきっかけともなった。そんな「サンマ裁判」を描く映画『サンマデモクラシー』から、民主主義のあり方と、今も沖縄に残り続ける問題について考える
あわせて読みたい
【歴史】映画『シン・ちむどんどん』は、普天間基地移設問題に絡む辺野古埋め立てを”陽気に”追及する(…
映画『シン・ちむどんどん』は、映画『センキョナンデス』に続く「ダースレイダー・プチ鹿島による選挙戦リポート」第2弾である。今回のターゲットは沖縄知事選。そして本作においては、選挙戦の模様以上に、後半で取り上げられる「普天間基地の辺野古移設問題の掘り下げ」の方がより興味深かった
そんな本作では2度に渡り、ある印象的なフレーズが紹介される 。後に第4代沖縄県知事を務めた、当時は大学教授だった大田昌秀が、沖縄返還の1年前に書いた文章 だ。
日本人は醜い。
正確ではないが、概ねこんな感じの文章 である。そして本作では、作中とラストの2度に渡り、このフレーズが画面に表示された 。
さて、私が本作を観たのは公開初日 で、上映後には監督による舞台挨拶 が行われた。そしてその中で監督が、「沖縄での先行上映の際に観客から、『大田さんのあの言葉を2回も入れて、本土の人がどう受け取るのか心配』と言われた 」と言っていたのである。確かに普通に考えて、先の大田昌秀の言葉は「内地の人間を批判する言葉」 なわけで、そういう反応が出てくるのも当然 だろう。しかし一方で、やはりこの言葉は「沖縄県民の総意」と受け取るべき だろうなとも感じる。私たちは、意識しているかどうかに拘らず、はっきりと「沖縄に難問を押し付けている」 のであり、だから、沖縄の人からそういう視線を向けられることは甘んじて受け入れなければならない と思う。そう、これはあまりにも解決が難しい難問 なのだ。
あわせて読みたい
【信念】映画『ハマのドン』の主人公、横浜港の顔役・藤木幸夫は、91歳ながら「伝わる言葉」を操る
横浜港を取り仕切る藤木幸夫を追うドキュメンタリー映画『ハマのドン』は、盟友・菅義偉と対立してでもIR進出を防ごうとする91歳の決意が映し出される作品だ。高齢かつほとんど政治家のような立ち位置でありながら、「伝わる言葉」を発する非常に稀有な人物であり、とても興味深かった
そして沖縄県知事は、そんな難問とずっと向き合わされ続けている のである。本作では大田昌秀がインタビューを受ける映像が多く使われている が、その中で「沖縄県知事とはどういう存在ですか? 」と聞かれた彼が、「日本一難しい問題を背負わされている」と答えていたのが印象的 だった。本当にその通り だなと思う。
その「難しさ」は一言で表現できるようなものではもちろんない のだが、それでも無理やりまとめるならば、「基地問題では国に拳を振り下ろしつつ、県の振興策では国に頭を下げなければならない 」となるだろう。作中に確か、このような表現が出てきたと思う。
本作『太陽(ティダ)の運命』では、大田昌秀と、第7代沖縄県知事の翁長雄志の2人に特に焦点が当てられる のだが、彼らは共に、基地問題に関して国から訴訟を起こされている 。まさに「拳を振り下ろす」ようにしてバチバチに闘っていた というわけだ。しかしその一方で、経済振興策については国の援助を願い出なければならない 。東京や大阪などとは経済規模がまるで違うため、政府の支援なしには経済的な政策を実現出来ない のだ。このように、一方では相手を非難しながら、一方では相手に頭を下げなければならないという立場に置かれている わけで、その舵取りが相当困難であることは容易に想像できるのではないか と思う。
あわせて読みたい
【実話】株仲買人が「イギリスのシンドラー」に。映画『ONE LIFE』が描くユダヤ難民救出(主演:アンソ…
実話を基にした映画『ONE LIFE 奇跡が繋いだ6000の命』は、「イギリスに住むニコラス・ウィントンがチェコのユダヤ人難民を救う」という話であり、仲間と共に669名も救助した知られざる偉業が扱われている。多くの人に知られるべき歴史だと思うし、また、主演を務めたアンソニー・ホプキンスの演技にも圧倒されてしまった
そして、歴代の沖縄県知事の中でも基地問題に関してかなり厳しい態度を示した2人は、実は「保守」と「革新」というまったく異なるところから知事になった 。しかもこの2人は当初、激しく対立する関係だった のだ。しかし”運命”のいたずらか、結果として2人はほぼ同じ道を歩む ことになった。そんな、「基地問題」を背景にした数奇な人生を追いかけていく物語 である。
大学教授から沖縄県知事になった大田昌秀が抱え続けた葛藤
大田昌秀は大学教授時代から基地問題に対して厳しい主張を続けていた 。そしてそれ故に、周囲から次第に「是非知事になってほしい」という声が上がる ようになる。とはいえ、大田昌秀は知事になるつもりなどなかった そうだ。しかし、作中に登場した「大田昌秀を説得した1人」として紹介された人物は、「言うだけ言って実行しないなんて無責任だ。逃げるんですか?」と煽るかのような物言いをした という。そして最終的に、その言葉をきっかけの1つとして出馬を決意した のだそうだ。
知事に就任した大田昌秀は、当然、沖縄県民の悲願である「無条件での基地返還」を実現すべく奮闘した 。しかしそんな出鼻をくじくかのように、就任早々難しい判断を迫られる ことになってしまう。それが「広告縦覧代行 」である。これはざっくり言えば、「土地の使用期限の再延長」みたいな手続き のことだ。米軍が基地として使っている土地は沖縄県の所有(のはず) であり、契約の際に毎回使用期限が設定される 。そしてその期限が切れる前に行う再延長の手続きが「広告縦覧代行」 なのだ。大田昌秀は就任してすぐのタイミングで、その書面にサインするかどうかという問題に直面する ことになったのである。
あわせて読みたい
【問題】映画『国葬の日』が切り取る、安倍元首相の”独裁”が生んだ「政治への関心の無さ」(監督:大島新)
安倍元首相の国葬の1日を追ったドキュメンタリー映画『国葬の日』は、「国葬」をテーマにしながら、実は我々「国民」の方が深堀りされる作品だ。「安倍元首相の国葬」に対する、全国各地の様々な人たちの反応・価値観から、「『ソフトな独裁』を維持する”共犯者”なのではないか」という、我々自身の政治との向き合い方が問われているのである
大田昌秀の従来の主張・信念からすれば、ここは「署名拒否」しかない 。「米軍に土地を使わせない」という意思を示すことは、自身の主張・信念の一貫性という観点からも非常に重要 なのだ。しかし結局、彼は悩みに悩んだ末に署名することに決めた 。この時、大田昌秀はかなり批判を浴びた そうだ。
さてその後、大田昌秀にとって転機となる出来事 が起こる。米兵による少女暴行事件が発生した のだ。現在においても繰り返されているこの問題は、日米地位協定により、日本側は「被疑者の素性さえ分からない」という状況に置かれる 。そしてこの現状に、大田昌秀は怒り狂った のだ。作中である人物が、「この出来事が彼にとって転換点となったはずだ 」と語っていた。
そして1995年10月21日、大田昌秀は総決起大会を開催する 。なんと8万5000人もの県民が集まった そうだ。この時参加した者たちは、所属する団体等から動員を掛けられたみたいなことではなく、皆自主的に集まった のだという。そしてこの総決起大会で「オール沖縄」として一体となり、基地問題に徹底的に対峙する決意を固めた のである。ある人物は、「『オール沖縄』として立ち上がったこの時に、恐らく政府は初めて危機感を持ったのではないか 」と話していた。
あわせて読みたい
【解説】映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、凄まじい臨場感で内戦を描き、我々を警告する(…
映画『シビル・ウォー』は、「アメリカで勃発した内戦が長期化し、既に日常になってしまっている」という現実を圧倒的な臨場感で描き出す作品だ。戦争を伝える報道カメラマンを主人公に据え、「戦争そのもの」よりも「誰にどう戦争を伝えるか」に焦点を当てる本作は、様々な葛藤を抱きながら最前線を目指す者たちを切り取っていく
さて、大田昌秀が知事に就任した際の総理大臣は村山富市だった のだが、その後橋本龍太郎に変わる 。そして橋本龍太郎は、沖縄の基地問題をどうにか前進させようとかなり奮闘した のだそうだ。本作では、橋本龍太郎が「普天間基地の返還」を発表する記者会見の映像 が使われている。そしてそういう対外的な発信だけではなく、橋本龍太郎と直接関わった経験からも、大田昌秀は「政府の本気」を感じるようになっていった そうだ。
しかし、橋本龍太郎が発表した「普天間基地の返還」には条件がついていた 。「代替施設の提供 」である。つまり、「普天間基地は返還するから、沖縄のどこかに日本が費用を出して新しい基地施設を作ってくれ 」というわけだ。これはアメリカの要求 であり、そしてその過程で出てきたのが、今も続く「辺野古移設」 なのである。
大田昌秀は大いに悩んだ 。彼の主張も沖縄県民の望みも「無条件での基地返還」 なのだが、橋本龍太郎がまとめてきた条件は、それとは相当大きな隔たり がある。結局代替施設を沖縄に作らなければならないのであれば、状況に変わりはないんじゃないか 。果たしてこれは、受け入れるべき選択肢なのだろうか 。大田昌秀はそんな風に悩んでいた のだ。さらに2度目の「広告縦覧代行」のタイミングも重なり、彼は国との交渉も横目に睨みながら難しい決断を迫られる のである。
あわせて読みたい
【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…
ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ
大田昌秀が許容できなかった「少数が我慢を強いられる不健全な民主主義」について
本作では、「筑紫哲也NEWS23」の映像 が多く使われていた。本作の監督が元々「NEWS23」でもキャスターを務めていたアナウンサー なのだそうで(今もTBS所属らしいが、現在はアナウンサー職ではないそうだ)、そのことも関係しているのだろう。そしてその映像の中に、知事を引退した大田昌秀と、彼が知事時代に総理補佐官(正確には覚えていないが、そのような役職の人)だった人物が対談している ものがあり、その中で「大田昌秀と国がどのような点で対立していたのか」が明らかにされていた 。
まずは総理補佐官の、つまり国側の主張 から見ていこう。私が理解出来た範囲の話 に触れるので、認識の間違いがあるかもしれない が、国は要するに「現実的な手段として、辺野古移設は『基地縮小へ向かう第1歩』として適切な判断だった 」みたいな主張をしていたように思う。「基地を返還する」というのはかなり大事であり、実際的な手続きを踏んで進んでいくしかない 。国は基地縮小の方向を目指すつもり でいたが、そうだとしても物事は1歩ずつ進めていくしかないし、いきなり最終目的地には辿り着けない 。だから、「まずは危険な普天間基地を閉鎖し、規模を縮小した上で辺野古へ移設、そしてそれから少しずつ基地縮小を目指していく」というのが最善策だと今でも思っている 、みたいなことを言っていたはずである。
さて、沖縄出身でも在住でもない私の個人的な感覚で言えば、この総理補佐官の主張にはそれなりの妥当性があるように感じられた 。もちろん、「ん?」と感じた部分もある 。例えば、総理補佐官は「辺野古へは一時的に移すだけだ」と言っていたと思う が、それに対して大田昌秀は確か、「アメリカの資料には、『使用40年、耐用年数200年』と書いてある」みたいに矛盾を指摘していた 。もしも彼の言っている通りであれば、総理補佐官の「一時的」という主張はちょっと整合性が取れなくなる だろう。とはいえ、総理補佐官(国)の主張の大枠は「市街地にある危険な普天間基地を閉鎖して、海上に代替施設を作る(しかもその代替施設は普天間基地よりも縮小される)」 であり、この点に関して言えば、「なるほど、それが現実的な落とし所なのかもしれないなぁ」みたいに感じられた のだ。
あわせて読みたい
【衝撃】ミキ・デザキが映画『主戦場』で示す「慰安婦問題」の実相。歴史修正主義者の発言がヤバすぎ
「慰安婦問題」に真正面から取り組んだ映画『主戦場』は、「『慰安婦問題』の根幹はどこにあるのか?」というその複雑さに焦点を当てていく。この記事では、本作で映し出された様々な情報を元に「慰安婦問題」について整理したものの、結局のところ「解決不可能な問題である」という結論に行き着いてしまった
しかし総理補佐官のこの主張に対して大田昌秀が口にした話もまた実に印象的だった なと思う。
さて、先の発言を踏まえた上で、総理補佐官は「例えば、100人亡くなっていたものが1人に減るのであれば、確かに危険性はゼロにはなっていないけれども、よりベターな選択だとは言えるのではないか?」と口にしていた (この死者数の話はあくまで譬え話で、普天間基地の実際の死者数とは関係ないはず)。そしてこれに対して大田昌秀はまず「100人でも1人でも命の重さは変わらない」と反論する 。私はこれを聞いて、「まあ確かにその通りだけど、実に政治家っぽい発言であまりしっくり来ないな 」みたいに思っていた。しかしそれに続けて口にしたことに「なるほど」と感じさせられた のである。
常に多数が少数に我慢を強いる状況は、健全な民主主義ではない。
あわせて読みたい
【称賛?】日本社会は終わっているのか?日本在住20年以上のフランス人が本国との比較で日本を評価:『…
日本に住んでいると、日本の社会や政治に不満を抱くことも多い。しかし、日本在住20年以上の『理不尽な国ニッポン』のフランス人著者は、フランスと比べて日本は上手くやっていると語る。宗教や個人ではなく、唯一「社会」だけが善悪を決められる日本の特異性について書く
実際にはもう少し長かったような気もするが、概ねこのような主旨の発言 をしていた。これにはもう少し説明が必要だろう 。先程、総理補佐官の「100人の犠牲が1人になるなら、それはベターだろう」という発言 を紹介したが、大田昌秀はこれをそのまま「1億人の国民と100万人の沖縄県民」に対応させた のである。つまり、「100万人の沖縄県民が犠牲になってくれたら1億人が助かるんだからその方がベターだよね」と読み替えた のだ。そしてまさにこれは、沖縄と日本の現状そのもの である。大田昌秀はそのような状況に対して異議を唱えていた 、ということなのだろう。
大田昌秀のこの発言を聞いて、私は「確かにその通りだ」と感じた 。「辺野古移設によって死者が100人から1人に減るならベターじゃないか」という意見に賛同するということは、「100万人の沖縄県民に負担を押し付ける日本国民の発想」そのもの と言っていいだろう。私は、「死者が100人から1人に減る」のは良いことだと考えているのに、「1億人のために100万人が犠牲になる」のは良いことだとは思えないと言っている わけで、これは明らかにダブルスタンダード である。そのことに気付かされて、ハッとさせられてしまった というわけだ。
さて、これに関連した話として、後半の翁長雄志に焦点が当たるパートでちょっと驚くようなシーン があった。ある国会議員が翁長雄志との会談の場で、「『基地を引き受けてもいい』なんて思ってる日本国民は1人もいない」「本土が嫌だと言ってるんだから沖縄が引き受けるのが当然だろ」みたいなことを平然と言い放った という話が紹介されるのだ。翁長雄志は、「そんな価値観を持っている国会議員とどうやって対話しろと言うんだ」と怒りを滲ませていた が、本当にその通りだなと思う。
あわせて読みたい
【課題】原子力発電の廃棄物はどこに捨てる?世界各国、全人類が直面する「核のゴミ」の現状:映画『地…
我々の日常生活は、原発が生み出す電気によって成り立っているが、核廃棄物の最終処分場は世界中で未だにどの国も決められていないのが現状だ。映画『地球で最も安全な場所を探して』をベースに、「核のゴミ」の問題の歴史と、それに立ち向かう人々の奮闘を知る
また、「『基地を引き受けてもいい』なんて思ってる日本国民は1人もいない」という発言に絡めて言えば、翁長雄志がある場面で口にしていたことだが、「沖縄はこれまで1度だって自ら土地を提供したことなどない」というは発言も印象的 だった。本作では、沖縄に米軍基地が作られた経緯についてもざっくり説明される のだが、どの瞬間においてもそこに沖縄の意思はなく、沖縄以外の誰かの決定によって事が進んでいった ようである。
もしも1度でも「沖縄が自らの意思で米軍基地を誘致した」みたいな事実があるのなら、「俺たちは嫌なんだからお前らが引き受けろよ」という暴論が成り立つ余地も出てくるかもしれない 。しかしそんな事実はまったくなく、沖縄はずっと蚊帳の外に置かれたまま、米軍基地を受け入れざるを得なくなっただけ なのだ。それなのに「お前らが引き受けろよ」みたいな発言をするなんて、ちょっとあまりにも異常としか言いようがない だろう。
しかしそれはそれとして、「『基地を引き受けてもいい』なんて思ってる日本国民は1人もいない」という発言 に関しては、決して口には出さないものの、私を含む多くの国民がうっすらと感じていることだとやはり認めざるを得ない だろうし、だからこそ余計に難しい問題 だなと思っている。
あわせて読みたい
【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘
重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー
そんなわけで、このような理由もあって大田昌秀は、「代替施設を用意した上で普天間基地を返還してもらう」という橋本龍太郎の案に悩んでいた のだろう。そしてそうやって大田昌秀が悩んでいる間に国(橋本龍太郎)は痺れを切らした ようで、当初はかなり協力的な姿勢だった にも拘らず、次第に「大田は決断が出来ない」みたいな評価 になっていったそうだ。双方に様々な主張・思惑があったとはいえ、このような状況の変化はやはりちょっと残念 と言えるのではないかと思う。
ちなみに、第5代沖縄県知事の稲嶺惠一の発言 だったと思うが、彼は、「大田昌秀に関する橋本龍太郎の言葉で覚えていることが3つある 」という話をしていた。1つ目が「騙された俺が悪かったのか 」、2つ目が「私はあなたに貸しがある 」、そして3つ目が「最初からNOと言ってくれていれば 」である。橋本龍太郎のこんな発言からも、「彼がかなり状況改善に積極的であり、『大田が決断しさえすれば変わったのに』と考えていた」ことが窺える のではないかと思う。
大田昌秀を批判し続けた翁長雄志が県知事になるまで
さて、本作『太陽(ティダ)の運命』では、この辺りから少しずつ翁長雄志に焦点が当てられていく 。大田昌秀が県知事だった頃には、翁長雄志はまだ当選1回のぺーぺーだった のだが、彼は議会で「大田県政」を猛烈に批判する 。その発言は議事録にも残っており、本作でも多く引用されていた のだが、かなり手厳しいもの に感じられた。
あわせて読みたい
【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…
「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか
正直なところ私には、本作の描写だけからは「翁長雄志が大田昌秀をあれほど手厳しく攻撃し続けた理由」がよくわからなかった (恐らくこれは、私が「保守」やら「革新」やらをちゃんとは理解していないから だと思う)。しかしいずれにせよ、大田昌秀は翁長雄志の様々な戦略によって県知事の座から引きずり降ろされた のである。ただ、翁長雄志は別に、自身が県知事になろうと考えていたのではない 。目指していたのは那覇市長だった そうだ。
そもそも、彼の父親が政治家だった そうで、確か「市長選で負けた 」みたいな話だったと思う(彼が出馬したのは、現・那覇市である真和志市の市長選 )。そしてその際に、小学6年生だった翁長雄志は母親から「お前は政治家にならないでおくれ」と言われた のだが、彼はまさにこの瞬間に「自分は政治家になる」と決断した のだそうだ。何とも天邪鬼な子ども である。ちなみに、父親は後に真和志市長に選ばれた そうで、恐らくそういうこともあって、翁長雄志は那覇市長を目指そうと考えていた のだと思う。
しかしここで、翁長雄志の“運命”を変える出来事 が起こった。いわゆる「教科書問題 」である。安倍元首相の主導により行われた教科書の改定によって、「軍命による集団自決は無かった」と教科書の記述が書き換えられてしまった のだ。この「教科書問題」を機に、沖縄県民は再び立ち上がった 。沖縄県民としては看過できない問題 であり、翁長雄志も奮起したのである。そしてこの時に、大田昌秀による総決起大会以来の「オール沖縄」が実現した 。そんなこともあり、元々県知事になるつもりなどなかった翁長雄志は、かつて盟友だった人物と知事選を争い、実に10万票もの大差をつけた圧勝で沖縄県知事への就任が決まった のである。
あわせて読みたい
【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…
映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である
さて、そんな彼のエピソードの中では「『どうしても会いたい』と人づてに頼んである人物との接触を試みた」という話が印象的 だった。いつの出来事なのかはっきりとは覚えていない(あるいは「描かれていない」)が、知事選への出馬を決めた後だったと思う 。翁長雄志はなんと、かつて敵対していた大田昌秀に会おうとしていた のだ。沖縄に四半世紀通い詰めているという監督は舞台挨拶で、「これは本作の取材中に初めて出てきた話だ」とその驚きを語っていた 。
2人の再会を仲介した人物は、大田昌秀を半ば騙すようにして自宅に翁長雄志を連れて行った そうなのだが、結局大田昌秀は目を合わせることも話しかけることもなかった そうだ。やはり知事時代の禍根が残っていたのだろう 。議事録に記録されていた翁長雄志の言い草は相当にキツいものだったので、大田昌秀のその判断もまあ当然だろう なと思う。
しかしその後、知事になった翁長雄志の働きぶりを見て考えが変わったのだろう 。それ以降も結局、2人が直接会ったり話したりすることはなかった そうだが、「夫は様々な機会に翁長雄志を評価する言葉を口にしていた」と彼の妻が語っていた 。何かがほんの少し違っていれば、まったく違う関係性だったんじゃないか と思う。
あわせて読みたい
【レッテル】コミュニケーションで大事なのは、肩書や立場を外して、相手を”その人”として見ることだ:…
私は、それがポジティブなものであれ、「レッテル」で見られることは嫌いです。主人公の1人、障害を持つ大富豪もまたそんなタイプ。傍若無人な元犯罪者デルとの出会いでフィリップが変わっていく『THE UPSIDE 最強のふたり』からコミュニケーションを学ぶ
さて、翁長雄志は知事として、やはり大田昌秀と同じように基地問題に関する厳しい現状に直面する ことになる。しかし、知事就任以前からかなり覚悟していた ようだ。翁長雄志は就任前に、稲嶺惠一(確かその当時沖縄県知事だったんじゃないかな)に頼んで、基地問題に関する交渉に同席するためアメリカまで一緒に行った のだという。そしてその当時のことを振り返った稲嶺惠一が、「一言も喋らなかったが、翁長雄志はあの時に『この問題に落とし所など無い』と理解したんじゃないか」と語っていたのが印象的 だった。
また、確か翁長雄志の妻の発言 だったと思うのだが、「知事になってからどんな風に闘っていくか」について次のように語っていたことがある そうだ。
国は沖縄の主張に耳を貸さないだろう。恐らく、裁判所も味方にはなってくれない。
あわせて読みたい
【悲劇】大川小学校はなぜ津波被害に遭ったのか?映画『生きる』が抉る現実と国家賠償請求の虚しさ
東日本大震災において、児童74人、教職員10人死亡という甚大な津波被害を生んだ大川小学校。その被害者遺族が真相究明のために奮闘する姿を追うドキュメンタリー映画『生きる』では、学校の酷い対応、出来れば避けたかった訴訟、下された画期的判決などが描かれ、様々な問題が提起される
これは「闘い方」ではなく「負け方」 だと言っていいと思うが、「そうでもしない限り、この巨大な問題とそもそも対峙することすら出来ない」と理解していたのだろう 。このように、相当悲壮な覚悟を持って「日本一難しい知事」に就任した のである。
大田昌秀と同じ葛藤を抱くようになった翁長雄志、そして、基地問題に対する私の考え方
翁長雄志は、リーダーとして実に気持ちの良い人間だ 。「主義主張がはっきりしていて力強い」という点も好印象 だったが、それ以上に「敵対する陣営からも幹部を登用した」というエピソードが個人的にはとても印象的 だった。
翁長雄志は那覇市長時代に、「自身を支持していないことが明白な労働組合トップ(正確な役職は覚えていないが、そんな感じの人)」を幹部に起用した という。本作には当の本人が出演 しており、「その人事を聞いて耳を疑った 」みたいに話していた。翁長雄志が一般的にどう評価されているのか、私は詳しく知らない。ただ、少なくとも本作を観ている限りにおいては、「こんなリーダーだったらついて行きたいってみんな思うんじゃないか 」という感じだった。
あわせて読みたい
【驚異】プロジェクトマネジメントの奇跡。ハリウッドの制作費以下で火星に到達したインドの偉業:映画…
実は、「一発で火星に探査機を送り込んだ国」はインドだけだ。アメリカもロシアも何度も失敗している。しかもインドの宇宙開発予算は大国と比べて圧倒的に低い。なぜインドは偉業を成し遂げられたのか?映画『ミッション・マンガル』からプロジェクトマネジメントを学ぶ
そして翁長雄志は、沖縄県知事になったことで、かつて大批判を繰り広げていた大田昌秀の苦悩が理解できるようになる 。作中で誰かが「沖縄は矛盾の塊だ 」みたいな表現を使っていたが、まさにその通り という感じで、翁長雄志もまた様々な場面で難しい決断を迫られていた 。そして結果的に、色んな状況で大田昌秀の後に続くような言動を繰り返すことになる のである。
さて先述した通り、大田昌秀も翁長雄志も国から提訴されている のだが、この点に関して作中で誰かが(もしかしたら大田昌秀だったかもしれない)次のような発言をしていた 。
日本の司法と立法は行政に従属している。
あわせて読みたい
【驚愕】日本の司法は終わってる。「中世レベル」で「無罪判決が多いと出世に不利」な腐った現実:『裁…
三権分立の一翼を担う裁判所のことを、私たちはよく知らない。元エリート裁判官・瀬木比呂志と事件記者・清水潔の対談本『裁判所の正体』をベースに、「裁判所による統制」と「権力との癒着」について書く。「中世レベル」とさえ言われる日本の司法制度の現実は、「裁判になんか関わることない」という人も無視できないはずだ
最高裁判所は、日米安全保障条約は憲法より上位に位置しており、日米安全保障条約には関知できないとはっきり言っている。
この発言の真実性みたいなものは私には判断できないが、もし正しいのであれば、独立国家としてはかなり大きな問題ではないか と思う。さらにこの話は、翁長雄志が当時官房長官だった菅義偉との会談の中で口にした「自治は神話」というフレーズにも関係してくる だろう。アメリカ統治時代の高等弁務官であるキャラウェイの発言からの引用 であり、このような「自治」の話になればやはり、「沖縄だけの問題ではない」と感じられるはず だ(もちろん基地問題も沖縄だけの問題ではないのだが)。これは、我々皆が考えなければならない問題 なのである(ちなみに、キャラウェイの「自治は神話」発言に関しては、映画『サンマデモクラシー』の記事に色々と書いた のでそちらも併せて読んでみてほしい)。
あわせて読みたい
【民主主義】占領下の沖縄での衝撃の実話「サンマ裁判」で、魚売りのおばぁの訴えがアメリカをひっかき…
戦後の沖縄で、魚売りのおばぁが起こした「サンマ裁判」は、様々な人が絡む大きな流れを生み出し、最終的に沖縄返還のきっかけともなった。そんな「サンマ裁判」を描く映画『サンマデモクラシー』から、民主主義のあり方と、今も沖縄に残り続ける問題について考える
さらに、かつてジャーナリストだったという大学教授が作中で、「沖縄はこの国の民主主義のカナリアだ」と発言していたのも印象的 だった。もちろん、「炭鉱のカナリア」になぞらえた表現 であり、「最も弱く脆い沖縄に、民主主義の最初の亀裂が入る」という意味 である。沖縄の基地問題を「自分ごと」と捉えることが難しいとしても、「沖縄の基地問題の行く末は、日本全体の民主主義の未来に繋がっている」という認識を持てばまた少し捉え方は変わってくる のではないかと思う。「安全保障」という観点から「基地問題」が重要なのは当たり前 の話だが、それだけではなく、「民主主義」の観点からも決して「他人ごと」には出来ない問題 なのである。
とまあ、あーだこーだと好き勝手書いてはいるが、こと「沖縄の基地問題」に関しては、「どう決着するのが最もベターなのか」について考えるのは本当に難しい なと思う。というわけで最後に少し、「沖縄の基地問題」について私なりの考えを書いて終わりにする ことにしよう。
さて、まずは「ありとあらゆる条件を無視した場合の理想状態」について考える ことにする。この場合、沖縄にとってベストな未来は「安全保障上の問題をクリアした上で、日本(あるいは沖縄)から米軍基地がなくなる」だろう し、その次の選択肢としては「沖縄にある米軍基地(の一部)を県外移設する」ではないか と思う。いずれかが実現すれば、沖縄としてはかなり「悲願達成」 と言えるのではないだろうか。
あわせて読みたい
【信念】9.11後、「命の値段」を計算した男がいた。映画『WORTH』が描く、その凄絶な2年間(主演:マイ…
9.11テロの後、「被害者の『命の値段』を算出した男」がいたことをご存知だろうか?映画『WORTH』では、「被害者遺族のために貢献したい」と無償で難題と向き合うも、その信念が正しく理解されずに反発や対立を招いてしまった現実が描かれる。実話を基にしているとは思えない、凄まじい物語だ
しかし、ベストな選択肢は「地政学的な観点」からまずあり得ない ように思うし(中国や北朝鮮の脅威がほぼ0になる、みたいな状況にでもならない限り)、次善の選択肢はやはり「引き受ける自治体が存在するはずがない」という点が最大のネックとなる だろう。
ただ、「引き受ける自治体」に関しては、「将来的に状況が変わるかもしれない」 とも考えている。というのも、日本は今後明らかに人口が激減していく からだ。出生率を踏まえれば、これは明白な未来予測 である。恐らく、東京・大阪・福岡などの都市圏への人口流入は止まることがない だろうし、であれば、地方にはどんどんと「人が住まない土地」が増えていく ことになるだろう。そうなった時、運営の厳しくなった地方自治体が、米軍基地(や、核廃棄物の最終処分場)などの誘致に名乗りを上げる可能性はゼロではない と思っている。人口の減少具合によっては、「県1つ丸ごと消滅させる」みたいな判断さえ出てきてもおかしくはない だろうし、そうなればまた違った選択肢が生まれ得る とは思う。
とはいえ、そんな未来はすぐにはやってこないし、今まさに成すべき対策を考える上では何の関係もない 。そして、「まさに今どんな対策を打てるのか」について考えようとすると、やはり私は思考停止に陥ってしまう 。「安全保障のことなんかどうでもいい!」と腹を括ればいくらだって選択肢はあるだろうが、やはりそういうわけにもいかないだろう。しかしだとすれば、結局「沖縄に負担を押し付けたままの現状」を許容することになってしまう 。本当に難しい問題 だ。
あわせて読みたい
【評価】元総理大臣・菅義偉の来歴・政治手腕・疑惑を炙り出す映画。権力を得た「令和おじさん」の素顔…
「地盤・看板・カバン」を持たずに、総理大臣にまで上り詰めた菅義偉を追うドキュメンタリー映画『パンケーキを毒見する』では、その来歴や政治手腕、疑惑などが描かれる。学生団体「ivote」に所属する現役大学生による「若者から政治はどう見えるか」も興味深い
「難しい問題だ」と言って立ち止まっていては何も始まりはしない のだが、どの方向に進んでみたらいいかもよく分からないような難問 であり、「どうすればいいんだろうな 」と思っている。沖縄に住んでいない人間は「どうすればいいんだろうな」と思っていればそのまま時間は過ぎ去っていくが、沖縄に住んでいる人にはそうもいかない 。いずれにせよ、みんなで考え続けるしかない のだろうなと思う。
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
私は本当に、学生時代に「歴史」の勉強をすっ飛ばしてきた こともあり、特に近現代史については基本的な知識すら持たないまま大人になってしまった 。社会人になってから、ノンフィクションを読んだりドキュメンタリーを観たりして様々な知識を吸収するようにはなった が、その中でも、複雑な歴史を持つ「沖縄」の様々な問題は本当に難しい なと感じさせられる。
あわせて読みたい
【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画
1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品
私は別に好んで旅行をするタイプではないので、沖縄にももう長いこと行っていない が、多くの人にとって「沖縄」というのは「旅行先」 だろうし、そういう「プラスの面」しか見ていない のだと思う(私も大体そうだ)。もちろん、沖縄の人だって、観光客には来県してほしいだろうし、「沖縄のプラスの面」に注目してもらえることはありがたいはず だ。しかし、それだけに留まっていると、やはり何も進まない 。
結局のところ大方針としては、「基地問題は100万人の沖縄県民の問題ではなく、1億人の日本国民の問題だ」と認識するところから始めなければならない だろう。国は100万人を無視することは出来ても(無視してはいけないが)、1億人を無視することは出来ないはずだ 。そうなって初めて、この問題が正しく動き出す ように思う。
そんなわけで私には、「そういう意識を1人1人が持つところから始めていくしかない」という結論 しか導くことが出来ずにいる。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【壮絶】映画『フロントライン』は「コロナパンデミックの発端」におけるDMATの奮闘をリアルに描く(監…
映画『フロントライン』は、ド級の役者が集ったド級のエンタメ作品でありながら、「フィクションっぽさ」が非常に薄い映画でもあり、「起こった出来事をリアルに描く」という制作陣の覚悟が感じられた。マスコミ報道を通じて知ったつもりになっている「事実」が覆される内容で、あの時の混乱を知るすべての人が観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【煽動】プロパガンダの天才ゲッベルスがいかにヒトラーやナチスを”演出”したのかを描く映画:『ゲッベ…
映画『ゲッベルス ヒトラーをプロデュースした男』では、ナチスドイツで宣伝大臣を担当したヨーゼフ・ゲッベルスに焦点が当てられる。「プロパガンダの天才」と呼ばれた彼は、いかにして国民の感情を操作したのか。「現代の扇動家」に騙されないためにも、そんな彼の数奇な人生や実像を理解しておいた方がいいのではないかと思う
あわせて読みたい
【評価】都知事選出馬、安芸高田市長時代の「恥を知れ」などで知られる石丸伸二を描く映画『掟』
石丸伸二をモデルに描くフィクション映画『掟』は、「地方政治に無関心な人」に現状の酷さを伝え、「自分ごと」として捉えてもらうきっかけとして機能し得る作品ではないかと感じた。首長がどれだけ変革しようと試みても、旧弊な理屈が邪魔をして何も決まらない。そんな「地方政治の絶望」が本作には詰め込まれているように思う
あわせて読みたい
【悲劇】東京大空襲経験者の体験談。壊滅した浅草、隅田川の遺体、その後の人々の暮らし等の証言集:映…
映画『東京大空襲 CARPET BOMBING of Tokyo』は、2時間半で10万人の命が奪われたという「東京大空襲」を始め、「山手空襲」「八王子空襲」などを実際に経験した者たちの証言が収録された作品だ。そのあまりに悲惨な実態と、その記憶を具体的にはっきりと語る証言者の姿、そのどちらにも驚かされてしまった
あわせて読みたい
【信念】アフガニスタンに中村哲あり。映画『荒野に希望の灯をともす』が描く規格外の功績、生き方
映画『荒野に希望の灯をともす』は、アフガニスタンの支援に生涯を捧げ、個人で実現するなど不可能だと思われた用水路建設によって砂漠を緑地化してしまった中村哲を追うドキュメンタリー映画だ。2019年に凶弾に倒れるまで最前線で人々を先導し続けてきたその圧倒的な存在感に、「彼なき世界で何をすべきか」と考えさせられる
あわせて読みたい
【人権】チリ女性の怒り爆発!家父長制と腐敗政治への大規模な市民デモを映し出すドキュメンタリー:映…
「第2のチリ革命」とも呼ばれる2019年の市民デモを映し出すドキュメンタリー映画『私の想う国』は、家父長制と腐敗政治を背景にかなり厳しい状況に置かれている女性たちの怒りに焦点が当てられる。そのデモがきっかけとなったチリの変化も興味深いが、やはり「楽しそうにデモをやるなぁ」という部分にも惹きつけられた
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『ソウルの春』は、軍部が反乱を起こした衝撃の実話「粛清クーデター」の真相を描く(…
映画『ソウルの春』は、「これが実話!?」と感じるほど信じがたい史実が描かれる作品だ。韓国が軍事政権下にあったことは当然知っていたが、まさかこんな感じだったとは。「絶対的な正義 VS 絶対的な悪」みたいな展開で、「絶対にこうなるはず!」と思い込んでいたラストにならなかったことも、個人的には衝撃的すぎた
あわせて読みたい
【正義】名張毒ぶどう酒事件の真相解明の鍵を握る、唯一の再審請求人である妹・岡美代子を追う映画:『…
冤罪と目されている「名張毒ぶどう酒事件」を扱ったドキュメンタリー映画『いもうとの時間』は、逮捕され死刑囚として病死した奥西勝の妹・岡美代子に焦点を当てている。というのも彼女は、「再審請求権」を持つ唯一の人物なのだ。このままでは、事件の真相は闇の中だろう。まずは再審の扉が開かれるべきだと私は思う
あわせて読みたい
【友情】映画『ノー・アザー・ランド』が映し出す酷すぎる現実。イスラエル軍が住居を壊す様は衝撃だ
イスラエルのヨルダン川西岸地区内の集落マサーフェル・ヤッタを舞台にしたドキュメンタリー映画『ノー・アザー・ランド』では、「昔からその場所に住み続けているパレスチナ人の住居をイスラエル軍が強制的に破壊する」という信じがたい暴挙が映し出される。そんな酷い現状に、立場を越えた友情で立ち向かう様を捉えた作品だ
あわせて読みたい
【異様】映画『聖なるイチジクの種』は、イランで起こった実際の市民デモを背景にした驚愕の物語である
「家庭内で銃を紛失した」という設定しか知らずに観に行った映画『聖なるイチジクの種』は、「実際に起こった市民デモをベースに、イランという国家の狂気をあぶり出す作品」であり、思いがけず惹きつけられてしまった。「反政府的な作品」に関わった本作監督・役者・スタッフらが処罰されるなど、人生を賭けて生み出された映画でもある
あわせて読みたい
【捏造】袴田事件はついに再審での無罪が決定!冤罪の元死刑囚・袴田巌の現在と姉・秀子の奮闘:映画『…
映画『拳と祈り』は、2024年に再審無罪が確定した「袴田事件」の元死刑囚・袴田巌と、そんな弟を献身的にサポートする姉・秀子の日常を中心に、事件や裁判の凄まじい遍歴を追うドキュメンタリーである。日本の司法史上恐らく初めてだろう「前代未聞の状況」にマスコミで唯一関わることになった監督が使命感を持って追い続けた姉弟の記録
あわせて読みたい
【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実
映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた
あわせて読みたい
【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞
映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である
あわせて読みたい
【正義?】FBIが警告した映画『HOW TO BLOW UP』は環境活動家の実力行使をリアルに描き出す
映画『HOW TO BLOW UP』は、「テロを助長する」としてFBIが警告を発したことでも話題になったが、最後まで観てみると、エンタメ作品として実に見事で、とにかく脚本が優れた作品だった。「環境アクティビストが、石油パイプラインを爆破する」というシンプルな物語が、見事な脚本・演出によって魅力的に仕上がっている
あわせて読みたい
【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件
映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品
あわせて読みたい
【衝撃】EUの難民問題の狂気的縮図!ポーランド・ベラルーシ国境での、国による非人道的対応:映画『人…
上映に際し政府から妨害を受けたという映画『人間の境界』は、ポーランド・ベラルーシ国境で起こっていた凄まじい現実が描かれている。「両国間で中東からの難民を押し付け合う」という醜悪さは見るに絶えないが、そのような状況下でも「可能な範囲でどうにか人助けをしたい」と考える者たちの奮闘には救われる思いがした
あわせて読みたい
【真相】飯塚事件は冤罪で死刑執行されたのか?西日本新聞・警察・弁護士が語る葛藤と贖罪:映画『正義…
映画『正義の行方』では、冤罪のまま死刑が執行されたかもしれない「飯塚事件」が扱われる。「久間三千年が犯行を行ったのか」という議論とは別に、「当時の捜査・司法手続きは正しかったのか?」という観点からも捉え直されるべきだし、それを自発的に行った西日本新聞の「再検証連載」はとても素晴らしかったと思う
あわせて読みたい
【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件
映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
あわせて読みたい
【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…
映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である
あわせて読みたい
【衝撃】ミキ・デザキが映画『主戦場』で示す「慰安婦問題」の実相。歴史修正主義者の発言がヤバすぎ
「慰安婦問題」に真正面から取り組んだ映画『主戦場』は、「『慰安婦問題』の根幹はどこにあるのか?」というその複雑さに焦点を当てていく。この記事では、本作で映し出された様々な情報を元に「慰安婦問題」について整理したものの、結局のところ「解決不可能な問題である」という結論に行き着いてしまった
あわせて読みたい
【歴史】映画『シン・ちむどんどん』は、普天間基地移設問題に絡む辺野古埋め立てを”陽気に”追及する(…
映画『シン・ちむどんどん』は、映画『センキョナンデス』に続く「ダースレイダー・プチ鹿島による選挙戦リポート」第2弾である。今回のターゲットは沖縄知事選。そして本作においては、選挙戦の模様以上に、後半で取り上げられる「普天間基地の辺野古移設問題の掘り下げ」の方がより興味深かった
あわせて読みたい
【狂気】ISISから孫を取り戻せ!映画『”敵”の子どもたち』が描くシリアの凄絶な現実
映画『”敵”の子どもたち』では、私がまったく知らなかった凄まじい現実が描かれる。イスラム過激派「ISIS」に望んで参加した女性の子ども7人を、シリアから救出するために奮闘する祖父パトリシオの物語であり、その最大の障壁がなんと自国のスウェーデン政府なのだる。目眩がするような、イカれた現実がここにある
あわせて読みたい
【問題】映画『国葬の日』が切り取る、安倍元首相の”独裁”が生んだ「政治への関心の無さ」(監督:大島新)
安倍元首相の国葬の1日を追ったドキュメンタリー映画『国葬の日』は、「国葬」をテーマにしながら、実は我々「国民」の方が深堀りされる作品だ。「安倍元首相の国葬」に対する、全国各地の様々な人たちの反応・価値観から、「『ソフトな独裁』を維持する”共犯者”なのではないか」という、我々自身の政治との向き合い方が問われているのである
あわせて読みたい
【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…
クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい
あわせて読みたい
【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー
北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった
あわせて読みたい
【衝撃】映画『JFK/新証言』(オリヴァー・ストーン)が描く、ケネディ暗殺の”知られざる陰謀”
映画『JFK/新証言』は、「非公開とされてきた『ケネディ暗殺に関する資料』が公開されたことで明らかになった様々な事実を基に、ケネディ暗殺事件の違和感を積み上げていく作品だ。「明確な証拠によって仮説を検証していく」というスタイルが明快であり、信頼度の高い調査と言えるのではないかと思う
あわせて読みたい
【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…
森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である
あわせて読みたい
【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ
映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ
あわせて読みたい
【絶望】安倍首相へのヤジが”排除”された衝撃の事件から、日本の民主主義の危機を考える:映画『ヤジと…
映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』が映し出すのは、「政治家にヤジを飛ばしただけで国家権力に制止させられた個人」を巡る凄まじい現実だ。「表現の自由」を威圧的に抑えつけようとする国家の横暴は、まさに「民主主義」の危機を象徴していると言えるだろう。全国民が知るべき、とんでもない事件である
あわせて読みたい
【現実】我々が食べてる魚は奴隷船が獲ったもの?映画『ゴースト・フリート』が描く驚くべき漁業の問題
私たちは、「奴隷」が獲った魚を食べているのかもしれない。映画『ゴースト・フリート』が描くのは、「拉致され、数十年も遠洋船上に隔離されながら漁をさせられている奴隷」の存在だ。本作は、その信じがたい現実に挑む女性活動家を追うドキュメンタリー映画であり、まさに世界が関心を持つべき問題だと思う
あわせて読みたい
【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる
ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?
あわせて読みたい
【衝撃】映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想外すぎる着地を見せる普通じゃないドキュメンタリー
国連事務総長だったハマーショルドが乗ったチャーター機が不審な墜落を遂げた事件を、ドキュメンタリー映画監督マッツ・ブリュガーが追う映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想もつかない衝撃の展開を見せる作品だ。全世界を揺るがしかねない驚きの”真実”とは?
あわせて読みたい
【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実
弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている
あわせて読みたい
【抵抗】若者よ、映画『これは君の闘争だ』を見ろ!学校閉鎖に反対する学生運動がブラジルの闇を照らす
映画『これは君の闘争だ』で描かれるのは、厳しい状況に置かれた貧困層の学生たちによる公権力との闘いだ。「貧困層ばかりが通う」とされる公立校が大幅に再編されることを知った学生が高校を占拠して立て籠もる決断に至った背景を、ドキュメンタリー映画とは思えないナレーションで描く異色作
あわせて読みたい
【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…
ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?
あわせて読みたい
【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る
TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す
あわせて読みたい
【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と
黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作
あわせて読みたい
【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…
「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか
あわせて読みたい
【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画
1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品
あわせて読みたい
【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態
ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない
あわせて読みたい
【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す
香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見
ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す
あわせて読みたい
【あらすじ】嵐莉菜主演映画『マイスモールランド』は、日本の難民問題とクルド人の現状、入管の酷さを描く
映画『マイスモールランド』はフィクションではあるが、「日本に住む難民の厳しい現実」をリアルに描き出す作品だ。『東京クルド』『牛久』などのドキュメンタリー映画を観て「知識」としては知っていた「現実」が、当事者にどれほどの苦しみを与えるのか想像させられた
あわせて読みたい
【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り
プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
あわせて読みたい
【対立】パレスチナとイスラエルの「音楽の架け橋」は実在する。映画『クレッシェンド』が描く奇跡の楽団
イスラエルとパレスチナの対立を背景に描く映画『クレッシェンド』は、ストーリーそのものは実話ではないものの、映画の中心となる「パレスチナ人・イスラエル人混合の管弦楽団」は実在する。私たちが生きる世界に残る様々な対立について、その「改善」の可能性を示唆する作品
あわせて読みたい
【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』
2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない
あわせて読みたい
【歴史】『大地の子』を凌駕する中国残留孤児の現実。中国から奇跡的に”帰国”した父を城戸久枝が描く:…
文化大革命の最中、国交が成立していなかった中国から自力で帰国した中国残留孤児がいた。その娘である城戸久枝が著した『あの戦争から遠く離れて』は、父の特異な体験を起点に「中国残留孤児」の問題に分け入り、歴史の大きなうねりを個人史として体感させてくれる作品だ
あわせて読みたい
【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…
原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す
あわせて読みたい
【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ
火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…
ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ
あわせて読みたい
【実話】映画『アウシュビッツ・レポート』が描き出す驚愕の史実。世界はいかにホロコーストを知ったのか?
映画『アウシュヴィッツ・レポート』は、アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした実話を基にした作品。2人が持ち出した「アウシュビッツ・レポート」こそが、ホロコーストについて世界が知るきっかけだったのであり、そんな史実をまったく知らなかったことにも驚かされた
あわせて読みたい
【悲哀】2度の東京オリンピックに翻弄された都営アパートから「公共の利益」と「個人の権利」を考える:…
1964年の東京オリンピックを機に建設された「都営霞ケ丘アパート」は、東京オリンピック2020を理由に解体が決まり、長年住み続けた高齢の住民に退去が告げられた。「公共の利益」と「個人の権利」の狭間で翻弄される人々の姿を淡々と映し出し、静かに「社会の在り方」を問う映画
あわせて読みたい
【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…
在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。
あわせて読みたい
【弾圧】香港デモの象徴的存在デニス・ホーの奮闘の歴史。注目の女性活動家は周庭だけじゃない:映画『…
日本で香港民主化運動が報じられる際は周庭さんが取り上げられることが多いが、香港には彼女よりも前に民主化運動の象徴的存在として認められた人物がいる。映画『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』の主人公であるスター歌手の激動の人生を知る
あわせて読みたい
【勇敢】ユダヤ人を救った杉原千畝を描く映画。日本政府の方針に反しながら信念を貫いた男の生き様
日本政府の方針に逆らってまでユダヤ人のためにビザを発給し続けた外交官を描く映画『杉原千畝』。日本を良くしたいと考えてモスクワを夢見た青年は、何故キャリアを捨てる覚悟で「命のビザ」を発給したのか。困難な状況を前に、いかに決断するかを考えさせられる
あわせて読みたい
【民主主義】占領下の沖縄での衝撃の実話「サンマ裁判」で、魚売りのおばぁの訴えがアメリカをひっかき…
戦後の沖縄で、魚売りのおばぁが起こした「サンマ裁判」は、様々な人が絡む大きな流れを生み出し、最終的に沖縄返還のきっかけともなった。そんな「サンマ裁判」を描く映画『サンマデモクラシー』から、民主主義のあり方と、今も沖縄に残り続ける問題について考える
あわせて読みたい
【残念】日本の「難民受け入れ」の現実に衝撃。こんな「恥ずべき国」に生きているのだと絶望させられる…
日本の「難民認定率」が他の先進国と比べて異常に低いことは知っていた。しかし、日本の「難民」を取り巻く実状がこれほど酷いものだとはまったく知らなかった。日本で育った2人のクルド人難民に焦点を当てる映画『東京クルド』から、日本に住む「難民」の現実を知る
あわせて読みたい
【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:…
グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る
あわせて読みたい
【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る
地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する
あわせて読みたい
【書評】奇跡の”国家”「ソマリランド」に高野秀行が潜入。崩壊国家・ソマリア内で唯一平和を保つ衝撃の”…
日本の「戦国時代」さながらの内戦状態にあるソマリア共和国内部に、十数年に渡り奇跡のように平和を維持している”未承認国家”が存在する。辺境作家・高野秀行の『謎の独立国家ソマリランド』から、「ソマリランド」の理解が難しい理由と、「奇跡のような民主主義」を知る
あわせて読みたい
【権利】衝撃のドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』は、「異質さを排除する社会」と「生きる権利」を問う
「ヤクザ」が排除された現在でも、「ヤクザが担ってきた機能」が不要になるわけじゃない。ではそれを、公権力が代替するのだろうか?実際の組事務所(東組清勇会)にカメラを持ち込むドキュメンタリー映画『ヤクザと憲法』が映し出す川口和秀・松山尚人・河野裕之の姿から、「基本的人権」のあり方について考えさせられた
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
あわせて読みたい
【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…
『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る
あわせて読みたい
【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…
歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る
あわせて読みたい
【課題】原子力発電の廃棄物はどこに捨てる?世界各国、全人類が直面する「核のゴミ」の現状:映画『地…
我々の日常生活は、原発が生み出す電気によって成り立っているが、核廃棄物の最終処分場は世界中で未だにどの国も決められていないのが現状だ。映画『地球で最も安全な場所を探して』をベースに、「核のゴミ」の問題の歴史と、それに立ち向かう人々の奮闘を知る
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
理不尽・ストレス・イライラする【本・映画の感想】 | ルシルナ
「理不尽だなー」と感じてしまうことはよくあります。クレームや怒りなど、悪意や無理解から責められることもあるでしょうし、多数派や常識的な考え方に合わせられないとい…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…







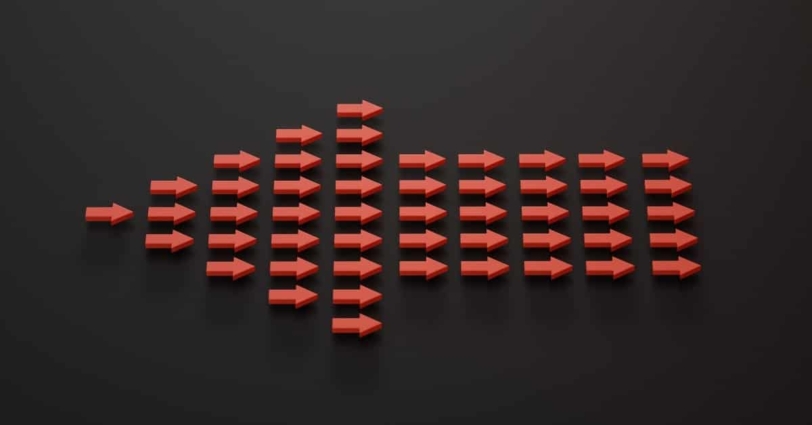






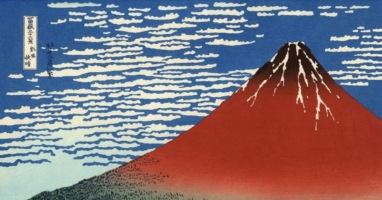








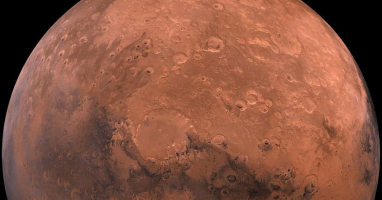
























































































コメント