目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
監督:ニコライ・アーセル, 出演:マッツ・ミケルセン, 出演:アマンダ・コリン, 出演:シモン・ベンネビヤーグ, 出演:メリナ・ハグバーグ
¥400 (2025/09/17 06:22時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- ユトランド半島の「ヒース」は何故「開拓不可能」と言われ、そしてケーレンは何故そんな土地の開拓に挑もうとしたのか?
- 「そこは俺の土地だ」と言いがかりをつける貴族シンケルからのムチャクチャな嫌がらせにケーレンは抵抗し続けた
- 「鶏を盗む少女」との関わりを起点とする、ケーレンのある驚くべき決断とは?
原題とも英題とも異なる邦題『愛を耕すひと』が実に絶妙だと感じさせる内容で、実話を元にしていることにも驚かされた
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
広大な土地を個人で開拓した史実を元にした映画『愛を耕すひと』は、思いがけず「愛」を描き出す物語だった
これはなかなか素敵な映画だった。ただ、どこまで事実なのかは気になるところだ。本作で描かれているのは1755年から始まる18世紀の話であり、かなり昔の出来事である。また、主人公は確かに偉業を成した人物ではあるのだが、本作での描かれ方を踏まえると、「主人公が何か記録を書き残していない限り、事実の詳細は分からない」というのが実際のところではないかと思う。公式HPによると「実話を元にした歴史小説」をベースにしているそうなので、「ある程度創作が含まれているのだろう」という理解をしている。
あわせて読みたい
【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作
大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい
また、実話かどうかの話で言えば、ラストシーンが本当にあった出来事なのかはとても気になるところだ。最後の最後、私は劇場でリアルに「嘘でしょ」と小さく呟いてしまった。「基本的には実話なのだろう」と思いながら物語を追っていたからこその反応なわけだが、さすがにその展開はあり得ないような気がする。実際のところ、どうなのだろうか。
映画『愛を耕すひと』の内容紹介

それでは、本作の主人公であるルドヴィ・ケーレンがどんな偉業を成し遂げたのかを中心に、本作の設定について書いていこうと思う。
舞台となるのは18世紀のデンマーク。当時ユトランド半島には「ヒース」と呼ばれる不毛な土地があった。それまでにも多くの人が開拓に挑戦し入植を目指してきたものの、どの試みもすべて跳ね除けてきた荒れ地である。デンマークでは既に、「ヒースは開拓不可能」とさえ考えられていたぐらいだ。
あわせて読みたい
【実話】英国王室衝撃!映画『ロスト・キング』が描く、一般人がリチャード3世の遺骨を発見した話(主演…
500年前に亡くなった王・リチャード3世の遺骨を、一介の会社員女性が発見した。映画『ロスト・キング』は、そんな実話を基にした凄まじい物語である。「リチャード3世の悪評を覆したい!」という動機だけで遺骨探しに邁進する「最強の推し活」は、最終的に英国王室までをも動かした!
そんな土地の開拓に名乗りを挙げたのがケーレンである。彼は、父親は不明、母親は使用人、本人は元庭師という経歴ながら、25年かけて大尉にまで上り詰めたにも拘らず、退役後の1755年には救貧院にいたほど困窮していた。そこでこの現状を打破すべく財務省へと出向き、「ヒースの開拓をやらせてほしい」と訴えたのである。
もちろん彼の提案は鼻であしらわれた。「これまで何人も挑戦してダメだったものに、金なんか出せるか」というわけだ。しかしケーレンは驚きの提案をする。「金は自分で工面する」というのだ。困窮はしているが、軍の年金が支給されるから、それでどうにか生活するという。そしてケーレンがそう言ってから風向きが変わっていく。
というのも実は、ヒースの開拓は国王の悲願だったからだ。そのため財務省としてもただ手をこまねいているわけにもいかず、「だったらこの男を送り出せば我々の顔も立つのではないか。まあどうせ無理だろうが」みたいに考えるようになったのだ。ケーレンは、「開拓が成功した暁には貴族の称号、そして相応の土地と使用人がほしい」と条件を提示し、財務省から許可を得る。こうしてケーレンは無謀な挑戦に踏み出すことになったのである。
あわせて読みたい
【誠実】映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』で長期密着した政治家・小川淳也の情熱と信念が凄まじい
政治家・小川淳也に17年間も長期密着した映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』は、誠実であるが故に大成できない1人の悩める政治家のありのままが描かれる。サラリーマン家庭から政治家を目指し、未来の日本を健全にするために奮闘する男の信念と情熱が詰まった1本
たった1人でヒースにやってきたケーレンは、しばらくの間ずっと、ただ黙々と土と掘り返してはその状態を見ることを繰り返していた。少しでも良い土壌を探し、そこを拠点に開拓を進めようというのだろう。さて、デンマークの国土は九州とほぼ同じぐらいらしい。さらに作中でケーレンは財務省の面々に、「国土の1/3が未開拓なのは不名誉では?」と話していた。となると、「ヒース」の広さは九州の1/3程度、つまり「九州地方から2つの県を選んだその合計」ぐらいの広さになるんじゃないだろうか。「そんな広大な土地の土壌を手作業でチェックし最適な場所を探す」なんて作業から始まるほど途方もないプロジェクトなのである。
そしてケーレンは、ついに最適な場所を見つけた。そこからは拠点作りである。当面住む家を建てるための材料を手配し、さらに、領主の元から逃げ出した小作人夫妻を雇った。雇ったと言っても寝食を与えるだけで賃金は払わない。そしてそんな彼らとたった3人で、「不可能」と言われた開拓をスタートさせていくのだが……。
ケーレンの挑戦を邪魔しようとするクソみたいな貴族の存在
さて、こんな映画が作られるぐらいだから、「ケーレンが実際に開拓を成し遂げたこと」は明らかだと言っていいはずだし、この点に触れてもさすがにネタバレにはならないだろう。かなりの偉業と言っていいはずだし、国内で教科書に載るぐらいの知名度があるのかは分からないが(個人的には、伊能忠敬レベルの凄い人に思える)、いずれにせよ、称賛されて当然の人物であることは間違いないと思う。
あわせて読みたい
【信念】9.11後、「命の値段」を計算した男がいた。映画『WORTH』が描く、その凄絶な2年間(主演:マイ…
9.11テロの後、「被害者の『命の値段』を算出した男」がいたことをご存知だろうか?映画『WORTH』では、「被害者遺族のために貢献したい」と無償で難題と向き合うも、その信念が正しく理解されずに反発や対立を招いてしまった現実が描かれる。実話を基にしているとは思えない、凄まじい物語だ
しかし本作は、「ルドヴィ・ケーレンって凄いことを成し遂げた人だよね!」みたいな内容では全然ない。さて、私は少し前に「伊能忠敬はかなりの偉人なのにあまり映像化されないのは、ただ歩いているだけで物語にならないからでは?」みたいなネットのまとめを目にしたのだが、「ヒースの開拓」にも似たところがあるかもしれない。「単に開拓物語を描く」というだけではたぶん、映画にはならなかったんじゃないかと思う。
であれば、本作では一体何がメインになるのか。それは「貴族との争い」である。ケーレンは、「お前が開拓している土地は俺のものだ」と難癖をつけてくる「貴族ゴロ」からの陰湿な嫌がらせと闘い続けなければならなかったのだ。そしてその争いこそが、本作の核となる物語なのである。

さて、本作で描かれるの争いは、大小2つに大別出来るだろう。大きい方が「貴族ゴロ」とのバトルで、まずはこちらから説明しよう。
ケーレンが「ここが最適だ」と見定めた土地の近くに、シンケルという裁判官が居を構えていた。彼は、「貴族になったことが分かりやすいように」という理由で、自分で勝手に「デ」を付け足して「デ・シンケル」と名乗っていたほど自己顕示欲が強いタイプである。親から譲り受けた広大な土地と屋敷を有する領主であり、気に入らない者がいればメイドでも誰でも殺してしまうようなムチャクチャな性格だった。それでいて、有力者であることは間違いないわけで、ノルウェーの貴族が「是非婚約者に」と自身の娘を送り込むほどだ(当のエレルにはシンケルと結婚するつもりなどまったくないのだが)。
あわせて読みたい
【感想】リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』から、社会が”幻想”を共有する背景とその悲劇…
例えば、「1万円札」というただの紙切れに「価値を感じる」のは、社会の構成員が同じ「共同幻想」の中に生きているからだ。リドリー・スコット監督の映画『最後の決闘裁判』は、「強姦では妊娠しない」「裁判の勝者を決闘で決する」という社会通念と、現代にも通じる「共同幻想」の強さを描き出す
そしてこのシンケルが「そこは俺の土地だから勝手なことはするな」と難癖つけてくるのである。ケーレンが「あそこは王領地だ」「国王から付託を受けている」と主張しても耳を貸さず、また「お前の土地だという証拠はあるのか?」とシンケルを問い詰めても「測量図を無くしてしまった」とのらりくらりかわすばかり。そんな人物が裁判官だという事実にも絶望させられるが、さらに彼はその権力を不当に行使し、「◯◯しなければ捕まえるぞ」「◯◯すれば罪を見逃してやる」みたいな交渉をケーレンに持ちかけてくるのだ。
とにかく死ぬほど嫌なヤツである。とはいえ恐らくだが、当時の貴族としてはデフォルトというか「あるある」だったのではないかとも思う。「ここが最適」と見定めた場所の近くにたまたまそんなクソみたいな人間がいたという不運に、ケーレンは対処しなければならなかったのだ。
ケーレンはとにかく、シンケルに対して毅然とした態度を取り続け、どんな懐柔にもなびかなかった。実はケーレンのところには元々もっと働き手がいたのだが(しばらくしてから増えたのである)、シンケルが「今の2倍の賃金を出す」と言ってどんどんと奪っていくので(もちろんケーレンへの嫌がらせだ)、結局残ったのは小作人夫妻だけという状況になってしまう。それでも彼は闘い続けたのである。ちなみに、この小作人夫妻がケーレンの元を離れなかった理由はシンプルだ。彼らは、まさにシンケルの元から逃げ出したのである。シンケルに見つかれば何をされるか分からない彼らは、無給でもここにいるしかないのだ。
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
しかし、ケーレンに雇われているヨハネスとアン・バーバラ夫妻も、ケーレンの元から離れたいと思っている。確かに「領主の元から逃げ出した小作人は違法」であり、そんな立場では多くを望めないと分かってはいるのだが、それにしたってケーレンの待遇は酷いと感じているのだ。詳しく触れはしないが、ケーレンは「貴族の称号を得るため」だけに開拓を目指しているので、手伝ってくれる者たちのことを大事にしようなどとは考えていないのだと思う。そんなわけで2人は、「しばらくしたらここを出よう」と相談しているのだ。そうなれば、ケーレンにとってはさらに打撃となることは間違いない。
シンケルが提示する条件を呑みさえすれば資金も人手も潤沢に手に入ることはもちろんケーレンには分かっていた。しかしそれは、「ケーレンがシンケルの小作人になること」を意味している。開拓が終わった後、そこからの収穫をシンケルと分け合わなければならないのだ。貴族を目指しているケーレンには、とても呑める条件ではなかった。
そこでケーレンは、”奇策”と言っていいだろう大胆な方法でこの窮地を乗り越えようとするのである。
貴族からの嫌がらせにも負けずに、ケーレンは粛々と開拓を続けていく
あわせて読みたい
【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….
つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る
開拓を始めた当初から、住処の作った鶏小屋から鶏がよく盗まれていた。少女が忍び込んで盗んでいるようだ。ケーレンには実は、その少女の存在に心当たりがあったため、ある夜、待ち伏せして捕まえた少女に無理やり案内させる形で、目的の場所へと辿り着いた。

そこは南方に住むタタール人の棲み処である。デンマークではどうやらタタール人は嫌われているようで、彼らは山の中で集団生活をしていた。少女が鶏を好き放題盗めたのも、タタール人だったからだ。ケーレンが雇った者たちに「鶏を盗む者をどうして捕まえないのか?」と聞くと、「南方の子は不吉だから」と返していた。盗みを咎めることさえ避けたいぐらい関わりたくないということなのだろう。
そしてケーレンは、そんな彼らを開拓民として働かせようと考えていた。とはいえ、当時の法律ではどうも、「タタール人を雇うこと」は違法だったようである。しかしケーレンは、そんなことは承知の上で、開拓を成功させるために彼らに手伝わせようと決めたのだ。
あわせて読みたい
【衝撃】NHKがアマゾン奥地の先住民ヤノマミ族に長期密着。剥き出しの生と死、文明との共存の難しさ
NHKのディレクターでありノンフィクション作家でもある国分拓が、アマゾン奥地に住む先住民ヤノマミ族の集落で150日間の長期密着を行った。1万年の歴史を持つ彼らの生活を描き出す『ヤノマミ』は、「生と死の価値観の差異」や「先住民と文明との関係の難しさ」を突きつける
こんな風にしてケーレンは、シンケルからの嫌がらせにも屈することなく、「開拓を成功させて貴族になる」という自身の目標のために突き進むのである。とはいえ、やはり貴族も強い。特に先述した通り、シンケル自身が裁判官なのだから、「シンケルは何をしても罰されない」と言える。だから狂気的な振る舞いも含め、あの手この手でケーレンを追い詰めるのだ。徒手空拳の退役軍人に出来ることは決して多くはないし、結局彼はじわじわと押し込まれ、かなりの窮地に追い込まれてしまうのだ。
それでもケーレンは、このような大変な状況の中で実際に開拓を成し遂げ、見事貴族の称号を獲得する。しかし、この話にはさらに別の要素が組み込まれており、それが小さい方の争いに関係しているのだ。
父娘のような関係になるケーレンとアンマイ・ムス、そして彼の信じがたい決断
鶏を盗んだことでタタール人の棲み処を案内させられることになった少女アンマイ・ムスは、色々あってタタール人とは離れ、ケーレンたちと一緒に暮らすことになる。なんとなく「疑似家族」のようになっていくというわけだ。しかし、ケーレンの不屈の努力によって開拓が進み、その成果が認められて実際に入植者が送られてくるようになると、彼女の存在が問題として浮上することになる。やはり、「不吉な南方の子どもがいる」という事実に対して、入植者が不信感を抱くようになるのだ。
あわせて読みたい
【LGBT】映画『リトル・ガール』で映し出される、性別違和を抱える8歳の”女の子”のリアルと苦悩
映画撮影時8歳だった、身体は男の子、心は女の子のサシャは、スカートを履いての登校が許されず、好きなバッグもペンケースも使わせてもらえない。映画『リトル・ガール』が描く、「性別違和」に対する社会の不寛容と、自分を責め続けてしまう母親の苦悩
さて、この問題が物語の中で具体的にどう関わってくるのかについては、後半の展開に関わる話なので詳しくは触れないことにしよう。本作では、表向きはとにかく「ケーレンによる開拓」と「ケーレンとシンケルの争い」がずっと描かれている。ただその背後では、はっきりとは見えないものの明らかに「ケーレンの内的変化」が起こっていて、後半は特にその「内的変化」に焦点が当てられるというわけだ。
この変化は凄く素敵なものなので、少し抽象的な形で触れておきたいのだが、要するに「ケーレンの目的が変わってしまった」ということなのだと思う。本作ではケーレンはとにかく無口な存在なので、はっきり断言できることは少ない。ただ、恐らくケーレン自身でさえ想定していなかった変化が自身の中で起こり、そのことがケーレンの意識を決定的に変えてしまったのだと思う。そのことは、本作のラスト付近で字幕表記されるある事実によっても理解できるだろう。ケーレンのその判断・行動には、ちょっと驚かされてしまった。
そしてそういう本作後半の展開を踏まえると、『愛を耕すひと』という邦題は作品にもの凄く合っているなと思う。
あわせて読みたい
【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事
「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である
デンマーク語の原題は『Bastarden』で、これは「私生児」「ロクデナシ」というような意味だそうだ。また、英題の『The Promised Land』は「約束の地」というような意味だろう。どちらも確かに、作品の内容に合っていると言えば合っている。しかし私の感触では、何よりも作品の雰囲気に合っているのは邦題の『愛を耕すひと』だと思う。まさに「耕す」という行為によって「愛」が成長していくような物語だからだ。

特に、先程も触れたが「字幕表記されるある事実」はちょっと衝撃的だった。いやもちろん、この記事の冒頭で言及した「ラストの結末」がもし事実なら驚きはそちらの方が上だが、さすがにこれはフィクションではないかという気がする。そして、「今の私の認識の中で事実だと確定していること」の中では、ケーレンのこの決断が最も驚きというわけだ。ただ、それまで物語を追ってきた観客目線で言えば、「そうであってくれて良かった」みたいな安堵感さえ抱かされるのではないかと思う。本作は様々な意味で「救いが少ない物語」なのだが、字幕で表記されたこの事実は、本作における大きな救いと言っていいはずだ。
しかしそうなると逆に、「開拓に着手する前、つまり軍人時代には『そういう経験』はなかったのだろうか」みたいにも感じるだろう。そして、ケーレンの過去についてはほとんど詳しく描かれないので詳細は分からないものの、彼がした決断を踏まえれば、やはり何もなかったと考えるのが自然なのだと思う。このように、後半で示唆されるケーレンのある行動は、ケーレンその人についても想像させるものだと言えるだろう。
そんな、実に興味深い物語だった。
あわせて読みたい
【感想】映画『夜明けのすべて』は、「ままならなさ」を抱えて生きるすべての人に優しく寄り添う(監督…
映画『夜明けのすべて』は、「PMS」や「パニック障害」を通じて、「自分のものなのに、心・身体が思い通りにならない」という「ままならなさ」を描き出していく。決して他人事ではないし、「私たちもいつそのような状況に置かれるか分からない」という気持ちで観るのがいいでしょう。物語の起伏がないのに惹きつけられる素敵な作品です
監督:ニコライ・アーセル, 出演:マッツ・ミケルセン, 出演:アマンダ・コリン, 出演:シモン・ベンネビヤーグ, 出演:メリナ・ハグバーグ
¥400 (2025/09/17 06:23時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
本作は、邦題やメインビジュアルなどからはちょっと想像できないハードさを含む作品で、思いがけない内容に驚かされる人も多いかもしれない。「そういう時代だったから仕方ない」と言えばそれまでではあるのだが、胸糞悪いシーンもかなり多く、不快感を覚える人も多いのではないかと思う。
とはいえ、何だかんだ良い話ではある。セリフがほとんどないのであくまでも観る側の想像に委ねられてはいるものの、「ケーレンの内的変化」の描写はなかなか良くて、ラストの展開はかなり素敵に感じられるだろう。また、この記事ではあまり触れなかったが、小作人の妻であるアン・バーバラもとても良い雰囲気を醸し出していて、特に、彼女にとって最大の”見せ場”(と言っていいかは悩ましいが)のインパクトは凄まじいものがあったなと思う。
人物の存在感にも物語の展開にもどちらも惹きつけられた、非常に印象的な作品である。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…
私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【壮絶】映画『フロントライン』は「コロナパンデミックの発端」におけるDMATの奮闘をリアルに描く(監…
映画『フロントライン』は、ド級の役者が集ったド級のエンタメ作品でありながら、「フィクションっぽさ」が非常に薄い映画でもあり、「起こった出来事をリアルに描く」という制作陣の覚悟が感じられた。マスコミ報道を通じて知ったつもりになっている「事実」が覆される内容で、あの時の混乱を知るすべての人が観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【リアル】多様性を受け入れる気がない差別主義者のヘイトクライムを描く映画『ソフト/クワイエット』
映画『ソフト/クワイエット』は、「白人至上主義者の女性たちがムチャクチャする」という内容なのだが、実は「多様性」について再考を迫るようなストーリーでもあり、実に興味深かった。さらに「全編ワンカット」というスタイルで撮られており、緊張感や没入感も圧倒的なのだ。凄い映画を観たなと感じさせられた
あわせて読みたい
【実話】特殊詐欺被害者が警察より先に犯人を追い詰める映画『市民捜査官ドッキ』は他人事じゃない
映画『市民捜査官ドッキ』は、実際に起こった詐欺事件を基にした映画なのですが、とても実話とは思えない驚きの状況が描かれます。なにせ、「警察に見放された詐欺被害者が、自ら詐欺グループの拠点を探し当てる」のです。テーマはシリアスですが、全体的にはコメディタッチで展開される作品で、とにかく楽しく見られるでしょう
あわせて読みたい
【信念】アフガニスタンに中村哲あり。映画『荒野に希望の灯をともす』が描く規格外の功績、生き方
映画『荒野に希望の灯をともす』は、アフガニスタンの支援に生涯を捧げ、個人で実現するなど不可能だと思われた用水路建設によって砂漠を緑地化してしまった中村哲を追うドキュメンタリー映画だ。2019年に凶弾に倒れるまで最前線で人々を先導し続けてきたその圧倒的な存在感に、「彼なき世界で何をすべきか」と考えさせられる
あわせて読みたい
【権力】コンクラーベをリアルに描く映画『教皇選挙』は、ミステリ的にも秀逸で面白い超社会派物語(監…
映画『教皇選挙』は、「カトリックの教皇を選ぶコンクラーベ」という、一般的な日本人にはまず馴染みのないテーマながら劇場が満員になるほどで、まずそのことに驚かされた。本質的には「権力争い」なのだが、そこに「神に仕える者」という宗教ならではの要素が組み込まれることによって特異で狂気的な状況が生み出されている
あわせて読みたい
【ネタバレ】フィンランド映画『ハッチング』が描くのは、抑え込んだ悪が「私の怪物」として生誕する狂気
映画『ハッチング―孵化―』は、「卵から孵った怪物を少女が育てる」という狂気的な物語なのだが、本作全体を『ジキルとハイド』的に捉えると筋の通った解釈をしやすくなる。自分の内側に溜まり続ける「悪」を表に出せずにいる主人公ティンヤの葛藤を起点に始まる物語であり、理想を追い求める母親の執念が打ち砕かれる物語でもある
あわせて読みたい
【人権】チリ女性の怒り爆発!家父長制と腐敗政治への大規模な市民デモを映し出すドキュメンタリー:映…
「第2のチリ革命」とも呼ばれる2019年の市民デモを映し出すドキュメンタリー映画『私の想う国』は、家父長制と腐敗政治を背景にかなり厳しい状況に置かれている女性たちの怒りに焦点が当てられる。そのデモがきっかけとなったチリの変化も興味深いが、やはり「楽しそうにデモをやるなぁ」という部分にも惹きつけられた
あわせて読みたい
【秘密】映画『ドライブ・イン・マンハッタン』は、「タクシー内の会話のみ」だが絶妙に良かった(主演…
映画『ドライブ・イン・マンハッタン』は、「タクシー内」というワンシチュエーションで「会話のみ」によって展開されるミニマムな要素しかない物語なのに、とにかく面白くて驚かされてしまった。運転手による「ゲスい会話」や女性客が抱えているのだろう「謎の秘密」などについて、色々と考えたくなるような深みのある物語である
あわせて読みたい
【実話】最低の環境で異次元の結果を出した最高の教師を描く映画『型破りな教室』は超クールだ
映画『型破りな教室』は、メキシコでの実話を基にした信じがたい物語だ。治安最悪な町にある最底辺の小学校に赴任した教師が、他の教師の反対を押し切って独自の授業を行い、結果として、全国テストで1位を取る児童を出すまでになったのである。「考える力」を徹底的に養おうとした主人公の孤軍奮闘がとにかく素晴らしい
あわせて読みたい
【失恋】ひたすらカオスに展開する映画『エターナル・サンシャイン』は、最後まで観ると面白い!(主演…
映画『エターナル・サンシャイン』は、冒頭からしばらくの間、とにかくまったく意味不明で、「何がどうなっているのか全然分からない!」と思いながら観ていました。しかし、映像がカオスになるにつれて状況の理解は進み始め、最終的には「よくもまあこんな素っ頓狂なストーリーを理解できる物語に落とし込んだな」と感心させられました
あわせて読みたい
【感動】映画『ぼくとパパ、約束の週末』は「自閉症への理解が深まる」という点で実に興味深かった
映画『ぼくとパパ、約束の週末』は「心温まる物語」であり、一般的にはそういう作品として評価されているはずだが、個人的には「『自閉症』への解像度が高まる」という意味でも興味深かった。「ルールは厳密に守るが、ルール同士が矛盾していて袋小路に陥ってしまう」という困難さが実に分かりやすく描かれている
あわせて読みたい
【感動】映画『ボストン1947』は、アメリカ駐留時代の朝鮮がマラソンで奇跡を起こした実話を描く
映画『ボストン1947』は、アメリカ軍駐留時代の朝鮮を舞台に、様々な困難を乗り越えながらボストンマラソン出場を目指す者たちの奮闘を描き出す物語。日本統治下で日本人としてメダルを授与された”国民の英雄”ソン・ギジョンを中心に、「東洋の小国の奇跡」と評された驚くべき成果を実現させた者たちの努力と葛藤の実話である
あわせて読みたい
【宣伝】アポロ計画での月面着陸映像は本当か?映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』のリアル
「月面着陸映像はニセモノだ」という陰謀論を逆手にとってリアリティのある物語を生み出した映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』は、「ベトナム戦争で疲弊し、事故続きのNASAが不人気だった」という現実を背景に「歴史のif」を描き出す。「確かにそれぐらいのことはするかもしれない」というリアリティをコメディタッチで展開させる
あわせて読みたい
【実話】株仲買人が「イギリスのシンドラー」に。映画『ONE LIFE』が描くユダヤ難民救出(主演:アンソ…
実話を基にした映画『ONE LIFE 奇跡が繋いだ6000の命』は、「イギリスに住むニコラス・ウィントンがチェコのユダヤ人難民を救う」という話であり、仲間と共に669名も救助した知られざる偉業が扱われている。多くの人に知られるべき歴史だと思うし、また、主演を務めたアンソニー・ホプキンスの演技にも圧倒されてしまった
あわせて読みたい
【実話】映画『ディア・ファミリー』は超良い話だし、大泉洋が演じた人物のモデル・筒井宣政は凄すぎる…
実話を基にした映画『ディア・ファミリー』では、個人が成したとは信じがたい偉業が描き出される。大泉洋が演じたのは、娘の病を治そうと全力で突き進んだ人物であり、そのモデルとなった筒井宣政は、17万人以上を救ったとされるIABPバルーンカテーテルの開発者なのだ。まったくホントに、凄まじい人物がいたものだと思う
あわせて読みたい
【実話】映画『ダム・マネー ウォール街を狙え!』は「株で大儲けした」だけじゃない痛快さが面白い
ダム・マネー ウォール街を狙え!』では、株取引で莫大な利益を得た実在の人物が取り上げられる。しかし驚くべきは「大金を得たこと」ではない。というのも彼はなんと、資産5万ドルの身にも拘らず、ウォール街の超巨大資本ファンドを脅かす存在になったのである! 実話とは思えない、あまりにも痛快な物語だった
あわせて読みたい
【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…
映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた
あわせて読みたい
【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件
映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
あわせて読みたい
【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…
映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である
あわせて読みたい
【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…
映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった
あわせて読みたい
【実話】英国王室衝撃!映画『ロスト・キング』が描く、一般人がリチャード3世の遺骨を発見した話(主演…
500年前に亡くなった王・リチャード3世の遺骨を、一介の会社員女性が発見した。映画『ロスト・キング』は、そんな実話を基にした凄まじい物語である。「リチャード3世の悪評を覆したい!」という動機だけで遺骨探しに邁進する「最強の推し活」は、最終的に英国王室までをも動かした!
あわせて読みたい
【絶望】映画『少年たちの時代革命』が描く、香港デモの最中に自殺者を救おうとした若者たちの奮闘
香港の民主化運動の陰で、自殺者を救出しようと立ち上がったボランティア捜索隊が人知れず存在していた。映画『少年たちの時代革命』はそんな実話を基にしており、若者の自殺が急増した香港に様々な葛藤を抱えながら暮らし続ける若者たちのリアルが切り取られる作品だ
あわせて読みたい
【信念】映画『ハマのドン』の主人公、横浜港の顔役・藤木幸夫は、91歳ながら「伝わる言葉」を操る
横浜港を取り仕切る藤木幸夫を追うドキュメンタリー映画『ハマのドン』は、盟友・菅義偉と対立してでもIR進出を防ごうとする91歳の決意が映し出される作品だ。高齢かつほとんど政治家のような立ち位置でありながら、「伝わる言葉」を発する非常に稀有な人物であり、とても興味深かった
あわせて読みたい
【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘
重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー
あわせて読みたい
【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と
黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作
あわせて読みたい
【異常】韓国衝撃の実話を映画化。『空気殺人』が描く、加湿器の恐怖と解決に至るまでの超ウルトラC
2011年に韓国で実際に起こった「加湿器殺菌剤による殺人事件」をモデルにした映画『空気殺人』は、金儲け主義の醜悪さが詰まった作品だ。国がその安全を保証し、17年間も販売され続けた国民的ブランドは、「水俣病」にも匹敵する凄まじい健康被害をもたらした
あわせて読みたい
【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…
「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【驚異】映画『RRR』『バーフバリ』は「観るエナジードリンク」だ!これ程の作品にはなかなか出会えないぞ
2022年に劇場公開されるや、そのあまりの面白さから爆発的人気を博し、現在に至るまでロングラン上映が続いている『RRR』と、同監督作の『バーフバリ』は、大げさではなく「全人類にオススメ」と言える超絶的な傑作だ。まだ観ていない人がいるなら、是非観てほしい!
あわせて読みたい
【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ
ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見
ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す
あわせて読みたい
【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…
『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか
あわせて読みたい
【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作
大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい
あわせて読みたい
【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画
映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい
あわせて読みたい
【圧巻】150年前に気球で科学と天気予報の歴史を変えた挑戦者を描く映画『イントゥ・ザ・スカイ』
「天気予報」が「占い」と同等に扱われていた1860年代に、気球を使って気象の歴史を切り開いた者たちがいた。映画『イントゥ・ザ・スカイ』は、酸素ボンベ無しで高度1万1000m以上まで辿り着いた科学者と気球操縦士の物語であり、「常識を乗り越える冒険」の素晴らしさを教えてくれる
あわせて読みたい
【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…
遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
あわせて読みたい
【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』
世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す
あわせて読みたい
【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…
環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る
あわせて読みたい
【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ
火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【日常】難民問題の現状をスマホで撮る映画。タリバンから死刑宣告を受けた監督が家族と逃避行:『ミッ…
アフガニスタンを追われた家族4人が、ヨーロッパまで5600kmの逃避行を3台のスマホで撮影した映画『ミッドナイト・トラベラー』は、「『難民の厳しい現実』を切り取った作品」ではない。「家族アルバム」のような「笑顔溢れる日々」が難民にもあるのだと想像させてくれる
あわせて読みたい
【差別】才ある者の能力を正しく引き出す者こそ最も有能であり、偏見から能力を評価できない者は無能だ…
「偏見・差別ゆえに、他人の能力を活かせない人間」を、私は無能だと感じる。そういう人は、現代社会の中にも結構いるでしょう。ソ連との有人宇宙飛行競争中のNASAで働く黒人女性を描く映画『ドリーム』から、偏見・差別のない社会への道筋を考える
あわせて読みたい
【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る
地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する
あわせて読みたい
【真実】ホロコーストが裁判で争われた衝撃の実話が映画化。”明らかな虚偽”にどう立ち向かうべきか:『…
「ホロコーストが起こったか否か」が、なんとイギリスの裁判で争われたことがある。その衝撃の実話を元にした『否定と肯定』では、「真実とは何か?」「情報をどう信じるべきか?」が問われる。「フェイクニュース」という言葉が当たり前に使われる世界に生きているからこそ知っておくべき事実
あわせて読みたい
【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る
「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生
あわせて読みたい
【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る
「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える
あわせて読みたい
【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….
つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る
あわせて読みたい
【レッテル】コミュニケーションで大事なのは、肩書や立場を外して、相手を”その人”として見ることだ:…
私は、それがポジティブなものであれ、「レッテル」で見られることは嫌いです。主人公の1人、障害を持つ大富豪もまたそんなタイプ。傍若無人な元犯罪者デルとの出会いでフィリップが変わっていく『THE UPSIDE 最強のふたり』からコミュニケーションを学ぶ
あわせて読みたい
【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…
「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える
あわせて読みたい
【理解】東田直樹の本は「自閉症の見方」を一変させた。自身も自閉症児を育てるプロデューサーが映画化…
東田直樹の著作を英訳し世界に広めた人物(自閉症児を育てている)も登場する映画『僕が跳びはねる理由』には、「東田直樹が語る自閉症の世界」を知ることで接し方や考え方が変わったという家族が登場する。「自閉症は知恵遅れではない」と示した東田直樹の多大な功績を実感できる
あわせて読みたい
【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…
「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する
あわせて読みたい
【改心】人生のリセットは困難だが不可能ではない。過去をやり直す強い意思をいかにして持つか:映画『S…
私は、「自分の正しさを疑わない人」が嫌いだ。そして、「正しさを他人に押し付ける人」が嫌いだ。「変わりたいと望む者の足を引っ張る人」が嫌いだ。全身刺青だらけのレイシストが人生をやり直す、実話を元にした映画『SKIN/スキン』から、再生について考える
あわせて読みたい
【天才】諦めない人は何が違う?「努力を努力だと思わない」という才能こそが、未来への道を開く:映画…
どれだけ「天賦の才能」に恵まれていても「努力できる才能」が無ければどこにも辿り着けない。そして「努力できる才能」さえあれば、仮に絶望の淵に立たされることになっても、立ち上がる勇気に変えられる。映画『マイ・バッハ』で知る衝撃の実話
あわせて読みたい
【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…
世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ
あわせて読みたい
【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…
「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える
あわせて読みたい
【挑戦】自閉症のイメージを変えるおすすめ本。知的障害と”思い込む”専門家に挑む母子の闘い:『自閉症…
専門家の思い込みを覆し、自閉症のイメージを激変させた少年・イド。知的障害だと思われていた少年は、母親を通じコミュニケーションが取れるようになり、その知性を証明した。『自閉症の僕が「ありがとう」を言えるまで』が突きつける驚きの真実
あわせて読みたい
【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…
誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…
メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
孤独・寂しい・友達【本・映画の感想】 | ルシルナ
孤独と向き合うのは難しいものです。友達がいないから学校に行きたくない、社会人になって出会いがない、世の中的に他人と会いにくい。そんな風に居場所がないと思わされて…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…








































































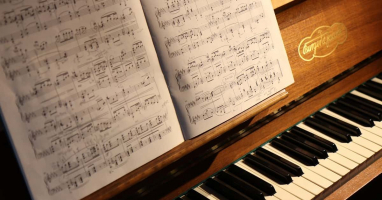
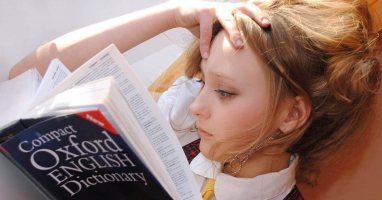













コメント