目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
VIDEO
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
国は恐らく、大嘘をついてでも「兵士は自らの意思で中国に残った」と主張し続けるつもりだろう 「訓練のために人を殺した場所」を戦後初めて再訪した奥村和一が抱いていた葛藤 全体的には非常に誠実に見える奥村和一が、「日本兵」としての一面を露わにした印象的なシーン 18年前に公開された映画だが、監督が言うように、本作で示唆される”狂気”は現代の方がより緊迫度が高いと思う
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
映画『蟻の兵隊』は、奥村和一が抱く様々な葛藤と共に、「終戦後、日本軍が中国に残り内戦を闘った」という知られざる歴史を炙り出す
あわせて読みたい
【驚異】信念を貫く勇敢さを、「銃を持たずに戦場に立つ」という形で示した実在の兵士の凄まじさ:映画…
第二次世界大戦で最も過酷な戦場の1つと言われた「前田高地(ハクソー・リッジ)」を、銃を持たずに駆け回り信じがたい功績を残した衛生兵がいた。実在の人物をモデルにした映画『ハクソー・リッジ』から、「戦争の悲惨さ」だけでなく、「信念を貫くことの大事さ」を学ぶ
私は本作『蟻の兵隊』についてほとんど何も知らないまま観に行った こともあり、監督による上映後のトークイベントで語られたエピソードにそもそも驚かされてしまった 。
私が本作を見たのはシアター・イメージフォーラムという映画館で、そして本作は18年前に同館で公開された のだそうだ。シアター・イメージフォーラムには、1階と地下1階に1つずつ劇場がある のだが、公開時はその両方を使い、1日8回も上映した らしい。しかし、それでも立ち見が出るほどお客さんが押し寄せた という。『ゆきゆきて、神軍』や『カメラを止めるな!』など、単館映画館から大ヒットに至った映画は色々ある だろうが、本作もその1 つというわけだ。
そんな本作で描かれるのは、「終戦後に、日本軍が上官の命令で中国に残り、4年に渡り中国の内戦を闘っていた」という驚くべき事実 である。信じがたいことに、命令に従って残った彼らは「自らの意思で帰国しなかった」と見なされ、戦後補償を受けられていない 。あまりにも異様な歴史 ではないだろうか。
あわせて読みたい
【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画
1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品
本作で描かれる、ちょっと信じがたい歴史
本作はドキュメンタリー映画であり、スポットライトが当たるのは奥村和一 である。彼は第二次世界大戦時に中国の山西省へと送られ、そこで戦闘に従事していた 。その後1945年8月15日の終戦を迎えたのだが、彼らは上官の指示で中国に残らざるを得なくなってしまう 。こうして奥村和一のいた部隊は、中国国民党軍の一員として中国共産党軍と闘うことになった 。実に4年間も、彼らは中国の内戦を闘っていた のである。
結局、2600名もの日本軍が残留し、その内550名が戦死した 。その後5年間の捕虜生活 を経て、奥村和一らは昭和29年(1954年)にようやく日本に帰還できた のである。
しかし、彼ら「残留日本軍部隊」の面々は、国からの戦後補償を受けられていない 。その理由は驚くべきものだった。国が彼らを、「お前たちは”自由意志”で中国に残り、日本軍としてではなく傭兵として中国の内戦を闘ったにすぎない」と見なしている からなのだ。
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
中国にいた兵士たちも当然、ポツダム宣言が受諾されたことを知っていた 。「これで戦争が終わった 」「帰れる 」と思ったに違いない。しかし、上官からの命令で仕方なく中国に残ることになった 。彼らはその時点でも「日本軍人」という認識でいたため、「上官の命令には従うしかない」と考えていた のである。そしてそのせいで彼らは、終戦からさらに9年間もの時間を”無駄に”過ごすことになった のだ。
それなのに、国はその事実を認めていない 。作中では、奥村和一らが裁判で自身の主張を訴える姿も映し出される のだが、その判決は、彼らの主張を一顧だにしないもの に私には感じられた。トークイベントでは監督が、「この裁判に対する国民の関心が薄かったからあんな判決が出たんだろうと私は思っています 」と話していたが、それはその通りかもしれない。当時マスコミが報じていたかどうかは定かではないが、少なくとも私は、このような裁判が行われていることをまったく知らなかった 。
しかし、奇妙ではないだろうか? どうして国は頑なに、「彼らは自由意志で残った」などという、どう考えてもそんなはずがない主張を通そうとしているのか 、と。実はそこにはちゃんと理由がある。そしてその理由のために国は、「彼らが日本軍として中国に残った」とは絶対に認められない のだ。
あわせて読みたい
【倫理】報道の自由度に関わる「放送法の解釈変更」問題をわかりやすく説明(撤回の真相についても):…
安倍政権下で突然発表された「放送法の解釈変更」が、2023年3月17日に正式に”撤回された”という事実をご存知だろうか?映画『テレビ、沈黙。 放送不可能。Ⅱ』は、その「撤回」に尽力した小西洋之議員に田原総一朗がインタビューする作品だ。多くの人が知るべき事実である
というのも日本は、「侵略を継続させるために兵を中国に残した」 からである。ただこれは、「私がそう解釈しただけ 」だという点に注意してほしい。作中ではもう少し違う表現をしていた のだが、鑑賞時にはパッと意味が取れず、ちゃんとメモ出来なかったのだ(私は映画館でメモを取り、それを元に感想を書いている)。作中では「侵略を継続させるために兵を中国に残した」みたいな分かりやすい表現を使っていなかった ので、場合によっては私の捉え間違いの可能性もあるが、ともあれも私はこのように解釈した 。
つまり、「『中国の内戦への協力』という名目で兵を残し、敗戦を受け入れる”フリ”をしながら戦争の継続を目論んでいた」という事実を隠蔽するには、「彼らは自由意志で残った」と主張するしかない というわけだ。
また、ポツダム宣言の問題 もある。こちらについても映画を観ているだけでは詳しく分からなかったが、奥村和一が作中で言及していたことを踏まえると、ポツダム宣言には恐らく「敗戦国に武装解除を求める文言」が含まれているのだと思う 。まあ、そりゃあそうだろう。しかし「残留日本軍部隊」の存在は、「ポツダム宣言を受諾したはずなのに、武装した日本軍が存在していた」ことを意味する 。つまり、その存在を認めてしまえば、ポツダム宣言に違反していたと認めることにもなる わけで、それを回避したいという思惑もあるのだと思う。
あわせて読みたい
【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…
歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る
このような理由から、恐らく国は「残留日本軍部隊」の存在を決して認めはしないだろう 。
しかし一方で、作中では「上からの指示があった」ことを示す証言・証拠が映し出される 。最も重要な証言をしたのは宮崎舜市 だろう。彼は終戦後、中国からの引き揚げを担当していた そうだ。しかし、実務が遅々として進まなかった 。埒が明かないと感じた彼は自ら山西省へと向かい、現地にいた旧知の人物に事情を聞いた そうだ。そして、そこで彼は初めて「中国に一部の日本兵を残す」という計画の存在を知った という。実際に、残留を命じる軍の命令書も目にした そうだ。映画撮影時には、彼は意識がないまま入院していたのだが、そうなる以前にテレビ局のインタビューに答えており、そこではっきりと先のように証言していた のである。
また、奥村和一は証拠探しのために自ら中国へと足を運ぶ のだが、その際にある文書を見つけた 。それは、「残留日本軍部隊設立の意図や総則」について記されたもの である。その中には、「いつが休日になるのか」といった、かなり細かな記述もあった 。この総則等を作成したのは残留日本軍部隊のトップになった人物 なのだが、当然、こんなものを勝手に作れるわけがない 。奥村和一は、「もっと上の階級の承認が無ければ、こんな文書が存在するがはずがない 」と断言していた。つまり、「総則について書かれた文章が存在する」という事実こそが、「日本軍が残留を命じたこと」を明確に示している というわけだ。
あわせて読みたい
【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ
「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ
しかし、この文書も裁判で提出したそうなのだが、国も裁判所もまったく無視を決め込んだ という。もちろん、国際問題に発展する話であり、国としては嘘を押し通してでも隠蔽するした という。だから、「真っ当な形での保証」は難しい のかもしれない。しかしそうだとしても、奥村和一ら残留日本軍部隊の面々が何らかの形できちんと報われるような、そんな展開になってほしかった ものだなと思う。
自身の過去の悪事を受け止め、贖罪のために行動する奥村和一
トークイベントの中で、監督が本作『蟻の兵隊』を何が何でも完成させようと決意した際の出来事 について話していた。
さてそもそもだが、当時の日本軍では初年兵訓練として「刺突訓練」が行われていた そうだ。監督によると、この「刺突訓練」は中国に送られた新兵のほぼ全員が経験している のだそうだ。これは読んで字のごとく「突き刺す訓練 」であり、「銃剣で人を殺す」ことを訓練としてやらせていた というわけだ。日本軍はこれを「肝試し」と呼んでいた という。
あわせて読みたい
【歴史】『大地の子』を凌駕する中国残留孤児の現実。中国から奇跡的に”帰国”した父を城戸久枝が描く:…
文化大革命の最中、国交が成立していなかった中国から自力で帰国した中国残留孤児がいた。その娘である城戸久枝が著した『あの戦争から遠く離れて』は、父の特異な体験を起点に「中国残留孤児」の問題に分け入り、歴史の大きなうねりを個人史として体感させてくれる作品だ
この事実を知っていた監督は、既に密着を始めていた奥村和一に「『肝試し』をしたことはあるか?」と聞いた そうだ。そしてやはり奥村和一は、「銃剣で人を殺す訓練をさせられた」と話した という。それを聞いた監督はすぐに、「じゃあその現場に行きましょう」と奥村和一に提案した 。かつて自身が人殺しをした場所を再訪し、何を感じるのか確かめよう というわけだ。
奥村和一は本作の撮影が始まる以前から中国へと自ら足を運び資料の確認などしていた ため、監督は「もしかしたら人を殺した現場にも行っているかもしれない」と考えた そうだが、確認してみると終戦後は1度も訪れていない という。そして、そんな現場に行こうと提案された奥村和一は、「行かなければならない場所だと思っています」と答えた そうだ。監督は、「まさにこの時『この映画は絶対に完成させなければならない』と決意を新たにした 」と語っていた。
では、「行かなければならない場所だと思っています」という奥村和一の返答には、どんな想いが込められていたのだろうか? この点については、監督が推測を語っていた 。
あわせて読みたい
【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー
北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった
奥村和一が「戦争の被害者」として国を訴えていた という話は既にした通りである。一方で彼は、自身の加害についてはこれまで沈黙を続けてきた 。ただ私の個人的な感覚では、「沈黙していたこと」を悪いとは思えない 。戦時中のことだし、望んでしたことではないからだ。もちろん、自ら語り反省出来ればより望ましいかもしれないが、それが出来なかったとしても責められる謂れはない と思う。
しかし奥村和一は恐らく、「『被害者だ』と訴えているのに、自身が行った加害について語らないのはフェアではない」と考えたのだろう 。そしてそんな彼の想いが、「人を殺した場所を訪れ、自らの口で何をしたのか語り、『加害者』としての立場を明確にする」という行動に繋がった のだと思う。さらに、そんな覚悟が伝わってきたからこそ、監督も「絶対に映画を完成させる」と決意した というわけだ。
私は、奥村和一のこの誠実さにとにかく驚かされてしまった 。繰り返しになるが、「戦時中の出来事」について元日本兵たちが何も語らないとしても、責めるべきではない と私は思っている。もちろん、「かなり上の立場の人間で、全体像を把握した上で指揮出来る立場にいた」とかなら話は別 だが、奥村和一のような「末端」の人間には「言われた通りにやる」以外の選択肢はなかった はずだ。そのため、「どんな『加害行為』があったとしても、それが『命令』によるものであるならば、その人個人の責任ではない 」と私は思う。そしてだからこそ、奥村和一の「自身の責任としてきちんと向き合う」という覚悟がとても誠実に感じられた し、さらに、明確な行動に移しているという事実に圧倒されてしまった のである。そういう人は他にもいるかもしれないが、決して多くはないはずだ。
あわせて読みたい
【誠実】地下鉄サリン事件の被害者が荒木浩に密着。「贖罪」とは何かを考えさせる衝撃の映画:『AGANAI…
私には、「謝罪すること」が「誠実」だという感覚がない。むしろ映画『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』では、「謝罪しない誠実さ」が描かれる。被害者側と加害者側の対話から、「謝罪」「贖罪」の意味と、信じているものを諦めさせることの難しさについて書く
「日本兵だった頃の感覚に戻ってしまう」というややこしさ
さて、奥村和一はそんな「誠実さ」に溢れた人物だと私には感じられた のだが、本作はそんな奥村和一のまた違った一面も映し出している 。「人間はやはり複雑だ」と感じさせられたシーン であり、「『過去の罪を振り返り贖罪した奥村和一』が『一介の日本兵』に戻ってしまった」という、非常に印象的な場面 だ。
ただその説明をするためには、もう少し「肝試し」について詳しく触れておく必要がある 。日本兵の犠牲になっていたのは中国人 で、縛られて動けなくさせられた中国人を前に初年兵は銃剣を構え、無抵抗の彼らに銃剣を突き刺さなければならなかった 。そんな彼らは、自分が銃剣を刺している相手について、「何の罪もない農民」と聞かされていた という。これが重要なポイント である。
さて、中国を訪れた奥村和一はある人物と面会する ことになった。それは、「結果的に日本兵の犠牲にならなかった中国人」の息子と孫 である。本人は既に亡くなっている のだが、子孫の話によると、彼は事前に「日本兵が襲ってくる」という情報を耳にし逃げていたため、「肝試し」の犠牲にならずに済んだ という。そして彼らが、本人から聞いた話として当時の状況を奥村和一に語っていた のだ。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『1917』は、ワンカット風の凄まじい撮影手法が「戦場の壮絶な重圧」を見事に体感させる
映画『1917 命をかけた伝令』は、「全編ワンカット風」という凄まじい撮影手法で注目されたが、私は、その撮影手法が「戦場における緊迫感」を見事に増幅させているという点に驚かされた。「物語の中身」と「撮影手法」が素晴らしく合致したとんでもない作品だ
そのやり取りの中で、「逃げ出して難を逃れたのは『鉱山の警備兵』であり、共産党軍の襲撃を受けた際に『武器を置けば助けてやる』と言われて武器を置いた者」だということが判明した 。そして何故かこの点について、奥村和一は子孫に厳しく問いただしていた のである。「何故戦わなかったのか 」「戦わずに武器を置くなど、ただの敵前逃亡でしかない 」と、かなり厳しい口調で詰め寄っていた のだ。
私には正直、このシーンを観ている時点では、奥村和一が何故そんなことを言っているのか分からなかった のだが、監督の話を聞いてようやく理解できた 。つまり奥村和一は、「自分が刺し殺したのは『何の罪もない農民』などではなく、『戦わずに武器を置いた警備兵』だった」という事実に反応していた のである。
「戦わずに武器を置いた」のであれば、それは単なる「敵前逃亡兵」だ 。少なくとも奥村和一の価値観ではそうなる。そしてそうだとしたら、自分の「罪」は思ったほど重くはないのではないか 。奥村和一は恐らくそんな風に考えた に違いないというわけだ。
あわせて読みたい
【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…
ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない
このやり取りの後、ホテルに戻った奥村和一は監督から、「殺したのが農民ではないと知って、少しは気が楽になりましたか?」と聞かれている 。なかなか突っ込んだ質問をするものだと思った。そしてこの質問に対して奥村和一は、最初こそ否定していたものの、しばらくして「気が楽にならなかったと言えば嘘になる」と、正直な感情を口にする のである。これは本作の中でも特に複雑な感情を抱かせる場面 であり、人間が抱える「ままならなさ」みたいなものを強烈に放つシーン だと感じられた。
監督によると、この後奥村和一は、「自分はまだ戦争のことを知らない」と口にするようになった という。そしてだからだろう、奥村和一とどのような関係にある人物なのか分からなかったが、元軍人の自宅を訪ねては、無理やり話を聞き出そうとする場面も映し出される 。「押しかけて無理やり話を聞こうとする」という行動の是非はともかく、彼の想いやスタンスはとても素晴らしい ものに感じられた。
このようなことを書くと、「奥村和一のように行動しなかった者はダメだ」みたいに主張していると誤解されそうだが、そんなつもりはまったくない 。繰り返しになるが、戦時中のことについて口を閉ざしたり何か行動に移せなかったりしても、それは仕方ない ことだと思う。私はただ、過去の振る舞いを反省し、さらに「あの時一体何があったのか?」を知ろうと奮闘する奥村和一の姿はとにかく素晴らしい と言っているだけなのだ。
あわせて読みたい
【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態
ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない
「戦争」があまりにも遠いものに感じられるため、我々の想像力が失われている
さて、本作『蟻の兵隊』は第二次世界大戦(後)をテーマにした映画 であり、「過去の歴史を扱った作品 」と言っていいのだが、しかし同時に、本作で描かれていることはすべて現代にも当てはまるはず である。監督も、「本作が示唆することは、公開した18年前よりもむしろ今の方が緊迫度が高い」という言い方 をしていた。私もそう思う。特に私は、安倍晋三が総理大臣だった時代に、「あぁ、日本はこのまま戦争に突入していくんだな」という雰囲気を強く感じていた 。私には、それぐらい「戦争」がリアルに感じられていた し、それは今も大きくは変わっていない。日本の社会は全体として、どうも間違った方向に進もうとしているように思えてならない のだ。
また監督は、森友問題にも言及していた 。この件では近畿財務局の職員が自殺している が、その妻・雅子さんが数年前に本作『蟻の兵隊』を観て「同じだ」という感想を口にした のだそうだ。起こった出来事をまるで何もなかったかのように扱い、「体裁を取り繕う」ためだけに無理筋の嘘をつき続けるという体質 は、今も昔も大差ないのである。
奥村和一が随所で、「自分だってそうしていたかもしれない」という類の言葉を口にしていた のが印象的だった。彼は新兵になった後、比較的早く終戦を迎えた が(その後9年間帰国できなかったわけだが)、「もし戦争が長引いていれば、今度は自分が新兵に『肝試し』をやらせていたはず」という意味 だ。また、本作には「日本兵に輪姦された」という女性が登場する のだが、彼女とのやり取りにおいても、彼は「その場にいたら自分もやっていたかもしれない」と口にしていた 。
あわせて読みたい
【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る
地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する
そして私は、このような認識はとても大事 だと思っている。
恐らく多くの人が、「自分は、戦争が始まっても人を殺さないし、酷い振る舞いだってしない」と考えているのではないか と思う。私も、意識してはいるつもりだが、そういう感覚が根底にあることを否定するのはやはり難しい 。そしてそんな風に思っていれば当然、「そんな下劣なことがやれてしまうなんて、人としてどうかしてるんじゃないか」みたいな感覚にもなってしまう だろうと思う。
しかし、そのような認識はやはり「想像力不足」 と言わざるを得ない。平時を生きたことしかない人間には、有事の際に自分がどうなるか分かるはずがない からだ。そして、「過去の戦争では、多くの『普通の人』が残虐な行為をしていた」という事実を踏まえれば、「我々も有事になればどんな振る舞いをするか分からない」と認識しておくべき だと思う。有事を経験した奥村和一はその自覚を持てている わけだが、平和な日本を生きてきた私たちには、なかなかそのような想像が及ばない のである。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話
映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ
だからこそ、本作のような作品に触れ、少しは想像してみる必要がある と私は思う。もちろん、「絶対に想像が及ばない世界」ではある のだが、本作を足がかりにするなどして努力してみるべき だろう。そういう「想像力」を多くの人が持とうと考えなければ、「戦争はしてはならない」という感覚がどんどんと薄れてしまう はずだ。
そしてそれとは別に、本作は「国家は大嘘をつくことがある」とも教えてくれる作品 である。国家は確かに国民を守るが、決して「全員」ではない 。だから、「自分がいつ切り捨てられる側になるか分からない」と肝に銘じておくべき だと思う。国家はあっさりと手のひらを返し裏切ってくる 。そのことははっきりと理解しておく必要があるというわけだ。
そんな教訓に満ちた作品 である。
あわせて読みたい
【勇敢】ユダヤ人を救った杉原千畝を描く映画。日本政府の方針に反しながら信念を貫いた男の生き様
日本政府の方針に逆らってまでユダヤ人のためにビザを発給し続けた外交官を描く映画『杉原千畝』。日本を良くしたいと考えてモスクワを夢見た青年は、何故キャリアを捨てる覚悟で「命のビザ」を発給したのか。困難な状況を前に、いかに決断するかを考えさせられる
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
シアター・イメージフォーラムでは期間限定での上映だった のだが、どうやら連日満員 のようだった。この記事をUPした時点では配信では観れなそう なので、劇場公開される機会があったら是非お見逃しなく 。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【煽動】プロパガンダの天才ゲッベルスがいかにヒトラーやナチスを”演出”したのかを描く映画:『ゲッベ…
映画『ゲッベルス ヒトラーをプロデュースした男』では、ナチスドイツで宣伝大臣を担当したヨーゼフ・ゲッベルスに焦点が当てられる。「プロパガンダの天才」と呼ばれた彼は、いかにして国民の感情を操作したのか。「現代の扇動家」に騙されないためにも、そんな彼の数奇な人生や実像を理解しておいた方がいいのではないかと思う
あわせて読みたい
【評価】都知事選出馬、安芸高田市長時代の「恥を知れ」などで知られる石丸伸二を描く映画『掟』
石丸伸二をモデルに描くフィクション映画『掟』は、「地方政治に無関心な人」に現状の酷さを伝え、「自分ごと」として捉えてもらうきっかけとして機能し得る作品ではないかと感じた。首長がどれだけ変革しようと試みても、旧弊な理屈が邪魔をして何も決まらない。そんな「地方政治の絶望」が本作には詰め込まれているように思う
あわせて読みたい
【平和】巣鴨プリズン収監のBC級戦犯だった冬至堅太郎の貴重な記録から知られざる歴史を紐解く映画:『…
映画『巣鴨日記 あるBC級戦犯の生涯』は、一般的にはまったく詳しいことが知られていないという「BC級戦犯」に関するドキュメンタリー映画である。巣鴨プリズンに収監された冬至堅太郎がつけていた日記、そして横浜軍事法廷で行われた彼の裁判の記録。これらを基に知られざる戦後史が明らかにされていく
あわせて読みたい
【信念】映画『太陽の運命』は、2人の知事、大田昌秀・翁長雄志から沖縄の基地問題の歴史を追う(監督:…
映画『太陽(ティダ)の運命』は、米軍基地問題に翻弄され続けた沖縄の歴史を、大田昌秀・翁長雄志という2人の知事に焦点を当てることで浮き彫りにしていくドキュメンタリー映画である。「日本一難しい問題を背負わされている」という沖縄県知事の苦悩と、「2人の間にあった様々な因縁」がないまぜになった数奇な“運命”の物語
あわせて読みたい
【権力】コンクラーベをリアルに描く映画『教皇選挙』は、ミステリ的にも秀逸で面白い超社会派物語(監…
映画『教皇選挙』は、「カトリックの教皇を選ぶコンクラーベ」という、一般的な日本人にはまず馴染みのないテーマながら劇場が満員になるほどで、まずそのことに驚かされた。本質的には「権力争い」なのだが、そこに「神に仕える者」という宗教ならではの要素が組み込まれることによって特異で狂気的な状況が生み出されている
あわせて読みたい
【人権】チリ女性の怒り爆発!家父長制と腐敗政治への大規模な市民デモを映し出すドキュメンタリー:映…
「第2のチリ革命」とも呼ばれる2019年の市民デモを映し出すドキュメンタリー映画『私の想う国』は、家父長制と腐敗政治を背景にかなり厳しい状況に置かれている女性たちの怒りに焦点が当てられる。そのデモがきっかけとなったチリの変化も興味深いが、やはり「楽しそうにデモをやるなぁ」という部分にも惹きつけられた
あわせて読みたい
【冷戦】”アメリカのビートルズ”と評された、「鉄のカーテンを超えた初のロックバンド」を襲った悲劇:…
映画『ブラッド・スウェット&ティアーズに何が起こったのか?』では、米ソ冷戦の最中に人気を博したロックバンド・BS&Tが辿った数奇な運命を描き出すドキュメンタリー映画である。当時は公表できなかった理由により「鉄のカーテン」の向こう側に行かざるを得なかった彼らは、何を見て、どんな不遇に直面させられたのか?
あわせて読みたい
【洗脳】激しく挑発的だった映画『クラブゼロ』が描く、「食べないこと」を「健康」と言い張る狂気(主…
映画『クラブゼロ』は、「健康的な食事」として「まったく食べないこと」を推奨する女性教師と、彼女に賛同し実践する高校生を描き出す物語。実に狂気的な設定ではあるが、しかし同時に、本作で描かれているのは「日々SNS上で繰り広げられていること」でもある。そんな「現代性」をSNSを登場させずに描き出す、挑発的な作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『ソウルの春』は、軍部が反乱を起こした衝撃の実話「粛清クーデター」の真相を描く(…
映画『ソウルの春』は、「これが実話!?」と感じるほど信じがたい史実が描かれる作品だ。韓国が軍事政権下にあったことは当然知っていたが、まさかこんな感じだったとは。「絶対的な正義 VS 絶対的な悪」みたいな展開で、「絶対にこうなるはず!」と思い込んでいたラストにならなかったことも、個人的には衝撃的すぎた
あわせて読みたい
【友情】映画『ノー・アザー・ランド』が映し出す酷すぎる現実。イスラエル軍が住居を壊す様は衝撃だ
イスラエルのヨルダン川西岸地区内の集落マサーフェル・ヤッタを舞台にしたドキュメンタリー映画『ノー・アザー・ランド』では、「昔からその場所に住み続けているパレスチナ人の住居をイスラエル軍が強制的に破壊する」という信じがたい暴挙が映し出される。そんな酷い現状に、立場を越えた友情で立ち向かう様を捉えた作品だ
あわせて読みたい
【尊厳】映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、安楽死をテーマに興味深い問いを突きつける(監督:ペ…
全然期待せずに観た映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、思いがけず面白い作品だった。「安楽死」をテーマにした、ティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーアのほぼ2人芝居といったシンプルな作品だが、そこに通底する「死生観」や、「死生観」の違いによるすれ違いなどが実に見事に描かれていて、強く惹きつけられた
あわせて読みたい
【異常】オンラインゲーム『DayZ』内でドキュメンタリー映画を撮るという狂気的な実験が映す人間模様:…
映画『ニッツ・アイランド』は、「『DayZ(デイジー)』というサバイバル・ゲーム内で撮られたドキュメンタリー映画」という斬新すぎる作品だ。「生き物を殺さない集団」「人殺しを楽しんで行う集団」など、ゲーム内の様々なプレイヤーから話を聞きつつ、「ゲーム内の世界は『リアル』なのか?」という問いにも焦点が当てられる
あわせて読みたい
【異様】映画『聖なるイチジクの種』は、イランで起こった実際の市民デモを背景にした驚愕の物語である
「家庭内で銃を紛失した」という設定しか知らずに観に行った映画『聖なるイチジクの種』は、「実際に起こった市民デモをベースに、イランという国家の狂気をあぶり出す作品」であり、思いがけず惹きつけられてしまった。「反政府的な作品」に関わった本作監督・役者・スタッフらが処罰されるなど、人生を賭けて生み出された映画でもある
あわせて読みたい
【忌避】小児性愛者から子どもを救え!映画『サウンド・オブ・フリーダム』が描く衝撃の実話(主演:ジ…
映画『サウンド・オブ・フリーダム』は、世界的に大問題となっている「子どもの人身売買」を扱った、実話を基にした物語である。「フィクションとしか思えないようなおとり捜査」を実行に移した主人公の凄まじい奮闘と、「小児性愛者の変態的欲望」の餌食になる悲惨な子どもたちの現実をリアルに描き出していく
あわせて読みたい
【解説】映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、凄まじい臨場感で内戦を描き、我々を警告する(…
映画『シビル・ウォー』は、「アメリカで勃発した内戦が長期化し、既に日常になってしまっている」という現実を圧倒的な臨場感で描き出す作品だ。戦争を伝える報道カメラマンを主人公に据え、「戦争そのもの」よりも「誰にどう戦争を伝えるか」に焦点を当てる本作は、様々な葛藤を抱きながら最前線を目指す者たちを切り取っていく
あわせて読みたい
【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…
「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている
あわせて読みたい
【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実
映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた
あわせて読みたい
【あらすじ】老夫婦の”穏やかな日常”から核戦争の恐怖を描くアニメ映画『風が吹くとき』の衝撃
一軒家の中だけで展開される老夫婦の日常から「核戦争」の危機をリアルに描き出す映画『風が吹くとき』は、日本では1987年に公開された作品なのだが、今まさに観るべき作品ではないかと。世界的に「核戦争」の可能性が高まっているし、また「いつ起こるか分からない巨大地震」と読み替えても成立する作品で、実に興味深かった
あわせて読みたい
【現在】ウーマンラッシュアワー村本大輔がテレビから消えた理由と彼の”優しさ”を描く映画:『アイアム…
「テレビから消えた」と言われるウーマンラッシュアワー・村本大輔に密着する映画『アイアム・ア・コメディアン』は、彼に対してさほど関心を抱いていない人でも面白く観られるドキュメンタリー映画だと思う。自身の存在意義を「拡声器」のように捉え、様々な社会問題を「お笑い」で発信し続ける姿には、静かな感動さえ抱かされるだろう
あわせて読みたい
【あらすじ】有村架純が保護司を演じた映画『前科者』が抉る、罪を犯した者を待つ「更生」という現実
映画『前科者』は、仮釈放中の元受刑者の更生を手助けするボランティアである「保護司」を中心に据えることで、「元犯罪者をどう受け入れるべきか」「保護司としての葛藤」などを絶妙に描き出す作品。個別の事件への処罰感情はともかく、「社会全体としていかに犯罪を減らしていくか」という観点を忘れるべきではないと私は思っている
あわせて読みたい
【現在】猟師になった東出昌大を追う映画『WILL』は予想外に良かった。山小屋での生活は衝撃だ(監督:…
猟師・東出昌大に密着した映画『WILL』は、思いがけず面白い作品だった。正直、東出昌大にはまったく興味がなく、本作も期待せず観たのだが、異常なほどフラットなスタンス故に周囲にいる人間を否応なく惹きつける「人間力」や、狩猟の世界が突きつける「生と死」というテーマなど実に興味深い。本当に観て良かったなと思う
あわせて読みたい
【赦し】映画『過去負う者』が描く「元犯罪者の更生」から、社会による排除が再犯を生む現実を知る
映画『過去負う者』は、冒頭で「フィクション」だと明示されるにも拘らず、観ながら何度も「ドキュメンタリーだっけ?」と感じさせられるという、実に特異な体験をさせられた作品である。実在する「元犯罪者の更生を支援する団体」を舞台にした物語で、当然それは、私たち一般市民にも無関係ではない話なのだ
あわせて読みたい
【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…
映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話
映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ
あわせて読みたい
【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…
映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う
あわせて読みたい
【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…
実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる
あわせて読みたい
【狂気】ホロコーストはなぜ起きた?映画『ヒトラーのための虐殺会議』が描くヴァンゼー会議の真実
映画『ヒトラーのための虐殺会議』は、ホロコーストの計画について話し合われた「ヴァンゼー会議」を描き出す作品だ。唯一1部だけ残った議事録を基に作られた本作は、「ユダヤ人虐殺」をイベントの準備でもしているかのように「理性的」に計画する様を映し出す。その「狂気」に驚かされてしまった。
あわせて読みたい
【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実
弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている
あわせて読みたい
【驚愕】本屋大賞受賞作『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は凄まじい。戦場は人間を”怪物”にする
デビュー作で本屋大賞を受賞した『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は、デビュー作であることを抜きにしても凄まじすぎる、規格外の小説だった。ソ連に実在した「女性狙撃兵」の視点から「独ソ戦」を描く物語は、生死の境でギリギリの葛藤や決断に直面する女性たちのとんでもない生き様を活写する
あわせて読みたい
【信念】映画『ハマのドン』の主人公、横浜港の顔役・藤木幸夫は、91歳ながら「伝わる言葉」を操る
横浜港を取り仕切る藤木幸夫を追うドキュメンタリー映画『ハマのドン』は、盟友・菅義偉と対立してでもIR進出を防ごうとする91歳の決意が映し出される作品だ。高齢かつほとんど政治家のような立ち位置でありながら、「伝わる言葉」を発する非常に稀有な人物であり、とても興味深かった
あわせて読みたい
【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る
TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す
あわせて読みたい
【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…
稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる
あわせて読みたい
【驚異】映画『RRR』『バーフバリ』は「観るエナジードリンク」だ!これ程の作品にはなかなか出会えないぞ
2022年に劇場公開されるや、そのあまりの面白さから爆発的人気を博し、現在に至るまでロングラン上映が続いている『RRR』と、同監督作の『バーフバリ』は、大げさではなく「全人類にオススメ」と言える超絶的な傑作だ。まだ観ていない人がいるなら、是非観てほしい!
あわせて読みたい
【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態
ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない
あわせて読みたい
【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す
香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『1917』は、ワンカット風の凄まじい撮影手法が「戦場の壮絶な重圧」を見事に体感させる
映画『1917 命をかけた伝令』は、「全編ワンカット風」という凄まじい撮影手法で注目されたが、私は、その撮影手法が「戦場における緊迫感」を見事に増幅させているという点に驚かされた。「物語の中身」と「撮影手法」が素晴らしく合致したとんでもない作品だ
あわせて読みたい
【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作
大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい
あわせて読みたい
【異次元】『ハイパーハードボイルドグルメリポート』は本も読め。衝撃すぎるドキュメンタリーだぞ
テレビ東京の上出遼平が作る、“異次元のグルメ番組”である「ハイパーハードボイルドグルメリポート」の書籍化。映像からも異様さが伝わる「激ヤバ地」に赴き、そこに住む者と同じモノを食べるという狂気が凄まじい。私がテレビで見た「ケニアのゴミ山の少年」の話は衝撃的だった
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
あわせて読みたい
【選択】特異な疑似家族を描く韓国映画『声もなく』の、「家族とは?」の本質を考えさせる深淵さ
喋れない男が、誘拐した女の子をしばらく匿い、疑似家族のような関係を築く韓国映画『声もなく』は、「映画の中で描かれていない部分」が最も印象に残る作品だ。「誘拐犯」と「被害者」のあり得ない関係性に、不自然さをまったく抱かせない設定・展開の妙が見事な映画
あわせて読みたい
【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…
ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない
あわせて読みたい
【誇り】福島民友新聞の記者は、東日本大震災直後海に向かった。門田隆将が「新聞人の使命」を描く本:…
自身も東日本大震災の被災者でありながら、「紙齢をつなぐ」ために取材に奔走した福島民友新聞の記者の面々。『記者たちは海に向かった』では、取材中に命を落とした若手記者を中心に据え、葛藤・後悔・使命感などを描き出す。「新聞」という”モノ”に乗っかっている重みを実感できる1冊
あわせて読みたい
【歴史】『大地の子』を凌駕する中国残留孤児の現実。中国から奇跡的に”帰国”した父を城戸久枝が描く:…
文化大革命の最中、国交が成立していなかった中国から自力で帰国した中国残留孤児がいた。その娘である城戸久枝が著した『あの戦争から遠く離れて』は、父の特異な体験を起点に「中国残留孤児」の問題に分け入り、歴史の大きなうねりを個人史として体感させてくれる作品だ
あわせて読みたい
【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…
原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
あわせて読みたい
【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…
環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る
あわせて読みたい
【驚愕】キューバ危機の裏側を描くスパイ映画『クーリエ』。核戦争を回避させた民間人の衝撃の実話:『…
核戦争ギリギリまで進んだ「キューバ危機」。その陰で、世界を救った民間人がいたことをご存知だろうか?実話を元にした映画『クーリエ:最高機密の運び屋』は、ごく普通のセールスマンでありながら、ソ連の膨大な機密情報を盗み出した男の信じがたい奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…
ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ
あわせて読みたい
【実話】映画『アウシュビッツ・レポート』が描き出す驚愕の史実。世界はいかにホロコーストを知ったのか?
映画『アウシュヴィッツ・レポート』は、アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした実話を基にした作品。2人が持ち出した「アウシュビッツ・レポート」こそが、ホロコーストについて世界が知るきっかけだったのであり、そんな史実をまったく知らなかったことにも驚かされた
あわせて読みたい
【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ
「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ
あわせて読みたい
【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:…
グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る
あわせて読みたい
【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死
映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る
あわせて読みたい
【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る
「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生
あわせて読みたい
【情熱】映画『パッドマン』から、女性への偏見が色濃く残る現実と、それを打ち破ったパワーを知る
「生理は語ることすらタブー」という、21世紀とは思えない偏見が残るインドで、灰や汚れた布を使って経血を処理する妻のために「安価な生理用ナプキン」の開発に挑んだ実在の人物をモデルにした映画『パッドマン 5億人の女性を救った男』から、「どう生きたいか」を考える
あわせて読みたい
【レッテル】コミュニケーションで大事なのは、肩書や立場を外して、相手を”その人”として見ることだ:…
私は、それがポジティブなものであれ、「レッテル」で見られることは嫌いです。主人公の1人、障害を持つ大富豪もまたそんなタイプ。傍若無人な元犯罪者デルとの出会いでフィリップが変わっていく『THE UPSIDE 最強のふたり』からコミュニケーションを学ぶ
あわせて読みたい
【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…
「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
あわせて読みたい
【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…
「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟
あわせて読みたい
【驚愕】ロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」はどう解釈すべきか?沢木耕太郎が真相に迫る:『キャパ…
戦争写真として最も有名なロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」には、「本当に銃撃された瞬間を撮影したものか?」という真贋問題が長く議論されてきた。『キャパの十字架』は、そんな有名な謎に沢木耕太郎が挑み、予想だにしなかった結論を導き出すノンフィクション。「思いがけない解釈」に驚かされるだろう
あわせて読みたい
【称賛】生き様がかっこいい。ムンバイのホテルのテロ事件で宿泊客を守り抜いたスタッフたち:映画『ホ…
インドの高級ホテルで実際に起こったテロ事件を元にした映画『ホテル・ムンバイ』。恐ろしいほどの臨場感で、当時の恐怖を観客に体感させる映画であり、だからこそ余計に、「逃げる選択」もできたホテルスタッフたちが自らの意思で残り、宿泊を助けた事実に感銘を受ける
あわせて読みたい
【リアル】社会の分断の仕組みを”ゾンビ”で学ぶ。「社会派ゾンビ映画」が対立の根源を抉り出す:映画『C…
まさか「ゾンビ映画」が、私たちが生きている現実をここまで活写するとは驚きだった。映画『CURED キュアード』をベースに、「見えない事実」がもたらす恐怖と、立場ごとに正しい主張をしながらも否応なしに「分断」が生まれてしまう状況について知る
あわせて読みたい
【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…
歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る
あわせて読みたい
【勇敢】後悔しない生き方のために”間違い”を犯せるか?法に背いてでも正義を貫いた女性の生き様:映画…
国の諜報機関の職員でありながら、「イラク戦争を正当化する」という巨大な策略を知り、守秘義務違反をおかしてまで真実を明らかにしようとした実在の女性を描く映画『オフィシャル・シークレット』から、「法を守る」こと以上に重要な生き方の指針を学ぶ
あわせて読みたい
【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…
「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える
あわせて読みたい
【驚異】プロジェクトマネジメントの奇跡。ハリウッドの制作費以下で火星に到達したインドの偉業:映画…
実は、「一発で火星に探査機を送り込んだ国」はインドだけだ。アメリカもロシアも何度も失敗している。しかもインドの宇宙開発予算は大国と比べて圧倒的に低い。なぜインドは偉業を成し遂げられたのか?映画『ミッション・マンガル』からプロジェクトマネジメントを学ぶ
あわせて読みたい
【誠実】地下鉄サリン事件の被害者が荒木浩に密着。「贖罪」とは何かを考えさせる衝撃の映画:『AGANAI…
私には、「謝罪すること」が「誠実」だという感覚がない。むしろ映画『AGANAI 地下鉄サリン事件と私』では、「謝罪しない誠実さ」が描かれる。被害者側と加害者側の対話から、「謝罪」「贖罪」の意味と、信じているものを諦めさせることの難しさについて書く
あわせて読みたい
【現実】戦争のリアルを”閉じ込めた”映画。第一次世界大戦の英軍を収めたフィルムが描く衝撃:映画『彼…
第一次世界大戦でのイギリス兵を映した膨大な白黒フィルムをカラー化して編集した『彼らは生きていた』は、白黒の映像では実感しにくい「リアルさ」を強く感じられる。そして、「戦争は思ったよりも安易に起こる」「戦争はやはりどこまでも虚しい」と実感できる
あわせて読みたい
【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像
1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ
あわせて読みたい
【無知】メディアの問題の本質は?「報道の限界」と「情報の受け取り方」を独裁政治の現実から知る:『…
メディアは確かに「事実」を報じている。しかし、報道に乗らない情報まで含めなければ、本当の意味で世の中を理解することは難しいと、『こうして世界は誤解する』は教えてくれる。アラブ諸国での取材の現実から、報道の「限界」と「受け取り方」を学ぶ
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
あわせて読みたい
【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…
日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書
あわせて読みたい
【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…
メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
理不尽・ストレス・イライラする【本・映画の感想】 | ルシルナ
「理不尽だなー」と感じてしまうことはよくあります。クレームや怒りなど、悪意や無理解から責められることもあるでしょうし、多数派や常識的な考え方に合わせられないとい…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…























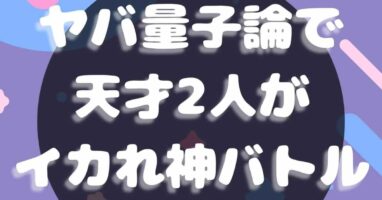
































































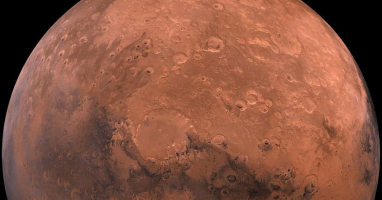















コメント