目次
はじめに
この記事で取り上げる本
青土社
¥1,760 (2024/12/13 22:11時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 「『友達』は『残余カテゴリー』」だからこそ、私は「恋愛」よりも「友情」の方が良いと思える
- 「『好意に基づく関係性』の方が上位である」という感覚がもたらす息苦しさ
- 「関係性が不安定」だから「名前を付けて安定させたい」のではないかという考察
仲の良い友人が本書の存在を教えてくれたお陰で、とても興味深い思考を展開することが出来ました
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
「現代思想 <友情>の現在」は、私が昔から抱いていた「男女間のモヤモヤ」について、情報の整理と深い指摘をしてくれる特集である
「現代思想」の本特集を読もうと思った理由と、私の友人の話
私には、6年ぐらい前に知り合った「人生で一番仲良くなった」と感じている友人がいる。そしてその友人から、『現代思想 <友情>の現在』の写真と共に「めっちゃおもしろい……刺さりまくり」というLINEが届いたのが、本書を読もうと思った直接的な理由だ。
あわせて読みたい
【苦しい】「恋愛したくないし、興味ない」と気づいた女性が抉る、想像力が足りない社会の「暴力性」:…
「実は私は、恋愛的な関係を求めているわけじゃないかもしれない」と気づいた著者ムラタエリコが、自身の日常や専門学校でも学んだ写真との関わりを基に、「自分に相応しい関係性」や「社会の暴力性」について思考するエッセイ。久々に心にズバズバ刺さった、私にはとても刺激的な1冊だった。
さて、友人からのこのLINEには、「自分が読んで良いと感じた」というだけではなく、明らかに「犀川さんにも絶対に刺さるはず」という意味も含まれている。というのも、本書に書かれているようなことを普段からよく話しているからだ。我々にとっての「日常会話」とも言える内容なのである。そんなわけで、先程のLINEには「犀川さんも読んでみたら?」という意味が込められていると判断できるというわけだ。

「何を当たり前のことを書いているんだ」と感じるかもしれないが、そんな話をしているのには理由がある。その友人は「12歳年下の女性」なのだ。この記事を書いている時点で私が41歳、彼女が29歳である。一般的に、「そんな年齢差のある異性間には『友人関係』は成立しない」と判断されるだろう。まあ、それは当然だと思う。そもそも人によっては「男女の友情は成立しない」と考えているだろうし、また、92歳と80歳みたいな関係なら12歳差など大した問題ではないだろうが、41歳と29歳の場合には普通、まともな関係性が成り立たないと思われて当然だと自分でも理解している。
では、ここで想起されているだろう「困難さ」とは、一体どのようなものなのだろうか? つまり、「何故『41歳と29歳の異性間には友人関係が成り立たない』と思われるのか」ということだ。この点については、少し意味合いは異なるのだが、本作中のこんな文章によっても説明出来るのではないかと思う。
あわせて読みたい
【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…
誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます
第一に、アセクシュアルにとっての友情が恋愛と地続きの性的関係として誤読されてしまうケースである。例えば、アセクシュアルの男性が女性と恋愛的でも性的でもない友人関係を築こうとする際、女性への性的欲望を当然のこととする男性のセクシュアリティに対するステレオタイプによって、女性たちに警戒されたり、そうした意向を疑われたりすることがある(Cupta 2019:1206)。他方でアセクシュアル女性の場合、男性に性的魅力を与えるという伝統的な女らしさの期待のもとで、特定の服装やふるまいが一方的に性的な文脈に回収されて理解されてしまう(Cuthbert 2019:855; Cupta 2019:1206-1207)。
佐川魅恵「親密さの境界を問い直す」
唐突に「アセクシュアル」という単語が出てくるが(ちなみに私は「アセクシャル」という言い方に馴染んでいるので、以下、私が書く文章中では「アセクシャル」と表記する)、馴染みがないという方も多いだろう。これは「異性愛」「同性愛」などの「セクシャリティ」の一種であり、「他者に対して性的欲求を抱かない」というタイプを指している。この概念を初めて知ったという方には信じがたい話に思えるかもしれない。ただ、割と昔から知られていた概念のようで、私は15年ぐらい前に、当時働いていた職場の同僚から「私はアセクシャルなんです」と打ち明けられた経験がある。
さて、先の引用は「アセクシャルが異性の友人を作る際の困難さ」についてのものであるが、これは広く「異性の友人を作る際の困難さ」と読み替えることもできるだろう。そして私はここ10年ぐらい、こういう「困難さ」を日々実感しながらどうにか「異性の友人」を作ろうと頑張ってきたし、それなりには上手くいっていると自分では思っている。
あわせて読みたい
【レッテル】コミュニケーションで大事なのは、肩書や立場を外して、相手を”その人”として見ることだ:…
私は、それがポジティブなものであれ、「レッテル」で見られることは嫌いです。主人公の1人、障害を持つ大富豪もまたそんなタイプ。傍若無人な元犯罪者デルとの出会いでフィリップが変わっていく『THE UPSIDE 最強のふたり』からコミュニケーションを学ぶ
ちなみにだが、私は別に「アセクシャル」ではないし、また「恋愛感情を抱かない」という「アロマンティック」でもない。少なくとも、私はそう自覚している。つまり、「異性のことが恋愛的に好きだと感じるし、性的欲求もある」というわけだ。ただ私はあるタイミングで、「異性との恋愛はやめて友人を目指そう」と決めた。「恋愛という関係性」が圧倒的に向いていないと気付いたからである。世の中には「猫好きなのに猫アレルギー」みたいな人がいるが、私もそういう感じなのだと思う。恋愛に対しての感情や欲はゼロではないが、あまりにも向いていないと自覚したため、「恋愛関係にしない方が自分にとってはプラスなんじゃないか」と考えるようになったというわけだ。
そして先述した友人は、そんなマインドに切り替えてから出会った人であり、個人的には一番と言っていいぐらい仲良くなれたと思っている。そんな彼女もまた、「『恋愛したい』と思いつつ、生理的に無理」という、私とはタイプは異なるものの「恋愛」に対して困難さを抱えている人で、そんなこともあり、本書で書かれているようなテーマについてよく話しているというわけだ。
ちなみに、この記事(正確には「この記事の元になった文章」)はその友人にも読んでもらっている。「この記事の元になった文章」も、内容的にはこの記事とほぼ同じなので、冒頭の記述もほとんど変わらない。普通なら、「一番仲良くなったと思っている」みたいに言及しているその本人にそんな文章を読まれるのは恥ずかしいし、「ちょっと変な感じになるかも」みたいな懸念が生まれたりもするだろう。私も、普段ならそんな風に考えるはずだが、「彼女ならまあ大丈夫だろう」とも思っている。そういう意味でもなかなか特殊な形で仲良くなれた人だと言えるだろう。それぐらい感覚の合う人と出会えて良かったなと思う。
あわせて読みたい
【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に
「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた
「友達」が「残余カテゴリー」であることの良さ
それでは内容に言及していくことにしよう。
本作は様々な人物による「友情」をテーマにした文章が収録された作品だ。主な執筆者は「学者・研究者」である。そのため、すべての文章が面白かったなんてことはない。特に後半に行けば行くほど、内容的に高度だったり、テーマ的に興味が持てなかったりするものが多くなっていった。ただそれはそれとして、本書に目を通すことで、「世の中には色んな研究テーマが存在するんだなぁ」と実感出来ることは興味深いポイントだと思う。「建設業に従事する沖縄のヤンキー的人間関係」「バンドマンの友人関係」「ママ友のLINE分析」「合唱曲と卒業ソングを用いた友情分析」「ホストクラブの人間関係」などなど様々な研究が紹介されるのだ。中には「オッペンハイマーと湯川秀樹の初邂逅」についての文章もあり、その幅の広さに驚かされた。

そしてその中でも個人的に最も共感できたのが、本書冒頭に収録されている中村香住と西井開の対談「すべてを『友情』と呼ぶ前に」である。中村香住は「レズビアン」、そして西井開は「『非モテ研究会』の発足人」という立ち位置で対談に臨んでおり、2人ともジェンダー的な観点から社会学の研究を行っているそうだ。先述した友人も、やはりこの冒頭の対談が一番良かったと言っていた。
あわせて読みたい
【感涙】映画『彼女が好きなものは』の衝撃。偏見・無関心・他人事の世界から”脱する勇気”をどう持つか
涙腺がぶっ壊れたのかと思ったほど泣かされた映画『彼女が好きなものは』について、作品の核となる「ある事実」に一切触れずに書いた「ネタバレなし」の感想です。「ただし摩擦はゼロとする」の世界で息苦しさを感じているすべての人に届く「普遍性」を体感してください
さて、この対談の中だけでも様々なことに言及されているのだが、まずは対談冒頭のこんな文章から引用してみたい。
(前略)恋人・家族・仕事上の関係、地縁、血縁のいずれにも当てはまらない人間関係が、すべて「友情」や「友達」という言葉に押し込められていることに、小さい頃から違和感を覚えてきました。私はグループで仲良くすることもたまにはありますが、基本的には一対一で人との関係性を取り結ぶタイプなので、それぞれ異なるはずの関係がすべて同じ「友達」という言葉で説明されなくてはならないこと、いわば「残余カテゴリー」としてこの言葉が使われることに疑問を抱いてきました。(中村香住)
中村香住+西井開 すべてを「友情」と呼ぶ前に
これは「人間関係に違和感を覚えるようになったきっかけ」として語られているもので、その主張には私も概ね賛同できる。私も「基本的には一対一で人との関係性を取り結ぶタイプ」であり、大人数の集まりなどにはあまり適性がない。また、「『じゃない関係性』がすべて『友達』でまとめられている」みたいに思う感覚も同じである。
しかし1点だけ違うところがあった。中村香住は「『友達が残余カテゴリーであること』に不満を抱いている」わけだが、私はむしろ「『友達が残余カテゴリーであること』に良さを感じている」のである。
あわせて読みたい
【考察】『うみべの女の子』が伝えたいことを全力で解説。「関係性の名前」を手放し、”裸”で対峙する勇敢さ
ともすれば「エロ本」としか思えない浅野いにおの原作マンガを、その空気感も含めて忠実に映像化した映画『うみべの女の子』。本作が一体何を伝えたかったのかを、必死に考察し全力で解説する。中学生がセックスから関係性をスタートさせることで、友達でも恋人でもない「名前の付かない関係性」となり、行き止まってしまう感じがリアル
さて、私のその感覚を説明するために、本書中の別の文章からこんな引用をしてみよう。
恋って再生産に次ぐ再生産で、もはや恋をしたことがなくても型みたいなのがあって、とりあえず作り手も受け手もそれをどれだけ上手にその型のまま演舞できるかという、武道めいたものを感じる。恋愛武道が悪いわけじゃないけど、歌を聴いて「これは詞ではなく、型だよなぁ」と思ってしまうことも、正直ないわけじゃない。その模倣しやすい友情歌詞の「型」がまだ少ないから、まだまだ足りないのかなぁと思ったり。これは鶏が先か卵が先かみたいなもんだけど。(児玉雨子)
児玉雨子+ゆっきゅん「ラブソングのその先へ」
この文章は、作詞家であるらしい2人がやり取りした往復書簡からの抜粋である。児玉雨子は「恋愛ソング」が多い理由について、「『恋愛』には『型』が存在するから供給が多いのではないか」と分析しており、それと比較する形で、「『友情』には『型』があまりないから『友情ソング』の供給が少ないのではないか」と指摘しているというわけだ。
そして、この作詞家2人がそう言及しているわけではないのだが、「『友情』に『型』が少ない理由」はやはり、「『友達』が『残余カテゴリー』だから」だと私は思っている。「じゃない関係性」をすべて「友達」と呼んでいるが故に、「友達」には分かりやすい「型」が存在しないのだろう。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ
私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。
そしてその上で、私には「型が存在しないこと」が「友達」の最大の良さに感じられている。だから私は、「友達が残余カテゴリーであること」をポジティブに捉えているのだ。
「残余カテゴリー」ではないからこそ、「恋愛」には向いていなかった
さらに、私が「恋愛に向いていない」と考えるようになった理由も、この「残余カテゴリー」という発想で説明できるだろう。「恋愛」は「残余カテゴリー」ではないので「型」がたくさん存在する。そしてそれ故に、私は「恋愛」に向いていないのだと思う。

「恋愛」になるとどうしても、「こういう時にはこういうことを『した方がいい』『しなければならない』『すべきである』」みたいな話が多くなる。誕生日や記念日がどうこうとか、連絡を取り合う頻度がどうだとか、そういう話は色々とあるだろう。そして面倒だなと思うのは、「そうしなければ、『相手のことが好きではない』というメッセージとして受け取られてしまい得る」ということだ。私にはどうにもこの辺りの感覚が馴染めなかった。
あわせて読みたい
【美麗】映画『CLOSE/クロース』はあまりにも切ない。「誰かの当たり前」に飲み込まれてしまう悲劇
子どもの頃から兄弟のように育った幼馴染のレオとレミの関係の変化を丁寧に描き出す映画『CLOSE/クロース』は、「自分自身で『美しい世界』を毀損しているのかもしれない」という話でもある。”些細な”言動によって、確かに存在したあまりに「美しい世界」があっさりと壊されてしまう悲哀が描かれる
例えば、「プレゼントをあげる」という行為について考えてみよう。私としては、「『あげたい』と思った時にあげる」のが一番良いんじゃないかと思っている。むしろ、「誕生日や記念日じゃない日に、『似合うと思ったから』みたいな理由であげる方がいいんじゃないか」とさえ考えているのだ。しかし「恋愛」においてはどうしても、「誕生日や記念日にプレゼントをあげる”べき”」みたいな雰囲気が感じられてしまう。そして私は、そういう「強制されているような状況」がどうにも好きになれないのだ。「したいからしている」のではなく、「しなければならないからしている」みたいな感覚に囚われてしまうので、いつも嫌だなと思っていた。どうしても、「『型』を演じている」みたいな意識が強くなってしまうのである。
一方「友達」の場合、そういう「型」は少ないように思う。あるとしても、「困った時には助ける」ぐらいじゃないだろうか。もちろん中には、「友達なんだから◯◯してよ」みたいな考えを持っている人もいるだろうが、そういう風潮はさほど強くない気がしている。つまり、「『友達』という関係性を継続させるためにしなければならないこと」はかなり少ないと考えているのだ。そしてだからこそ私には、「友達が残余カテゴリーであること」が心地よく感じられるのである。
しかし「友達」も、状況次第では「『型』の多い関係性」になってしまう。この点については対談中で次のように指摘されていた。
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
(前略)境界画定の力学が働く集団では構成員の近密度は上がるけれど、誰もがそこからはじき出されないように互いに承認を求め続けなければならない。なので承認をめぐるしんどさを抱える人が安心して過ごすには、境界を曖昧にしたような集まりや関係性のあり方が模索されるべきだと思います。しかし、欠乏感を埋めるために、さらなる承認を求め、強く結びつきたいと思えば思うほど、境界線が太く濃く引かれてしまう悪循環があります。(西井開)
中村香住+西井開 すべてを「友情」と呼ぶ前に
先述した通り、私は「基本的には一対一で人との関係性を取り結ぶタイプ」なので、上述の「友達グループ」のような集団に取り込まれることは今は無い。ただ、学生時代はやはりそのような関係性の中にいざるを得なかったし、だから「『その集団の構成員として相応しい』という承認を常に得続けなければその集団にはいられない」みたいな感覚も理解できる。そして、まさにこれは「型」の存在を示唆していると言えるだろう。「友達」の場合も、集団になると「型」が形成され、「残余カテゴリー」ではなくなってしまうというわけだ。
「非モテ男性」が抱える困難さ
さて、この対談の中で西井開は、「男性が抱えている困難さ」についての言語化を試みている。それは主に、「恋愛関係を結べない非モテ男性」に関する言及であり、先程の「友達グループ」についての指摘もそのような流れの中で出てきていた。対談の中では、先述の「友達グループ」のことを「同質性が高い集団」と呼んでおり、彼がこれまで話を聞いてきた「恋愛関係を結べない非モテ男性」たちは、「『同質性の高い集団』に留まらざるを得なかった」みたいな感覚を抱いているのだという。その理由についてはいくつか理由が挙げられていた。
あわせて読みたい
【考察】世の中は理不尽だ。平凡な奴らがのさばる中で、”特別な私の美しい世界”を守る生き方:『オーダ…
自分以外は凡人、と考える主人公の少女はとてもイタい。しかし、世間の価値観と折り合わないなら、自分の美しい世界を守るために闘うしかない。中二病の少女が奮闘する『オーダーメイド殺人クラブ』をベースに、理解されない世界をどう生きるかについて考察する
まず異性愛主義の問題があります。小学校低学年ぐらいまでは「男女の友情」という関係が成り立っているのに、高学年くらいになると周囲から「お前何あいつとイチャイチャしてるん」とからかわれたり、制裁を受けることで、異性との友人関係が切断されていく。(西井開)
中村香住+西井開 すべてを「友情」と呼ぶ前に
加えて男性同士の一対一という関係も切断されていきます。男子が二人で仲良くしていると、ホモフィビア的制裁を受けてしまうのです。(西井開)
中村香住+西井開 すべてを「友情」と呼ぶ前に
クラスメイト、そして教師からも「お前らできているのか」とからかわれた経験があると語る男性は少なくありません。そうして一対一での関係も作りづらくなると、自分が所属するのは男性集団しかないと思い込む/思い込まされていく。(西井開)
中村香住+西井開 すべてを「友情」と呼ぶ前に
あわせて読みたい
【漫画原作】映画『殺さない彼と死なない彼女』は「ステレオタイプな人物像」の化学反応が最高に面白い
パッと見の印象は「よくある学園モノ」でしかなかったので、『殺さない彼と死なない彼女』を観て驚かされた。ステレオタイプで記号的なキャラクターが、感情が無いとしか思えないロボット的な言動をする物語なのに、メチャクチャ面白かった。設定も展開も斬新で面白い
このような文章を読んで私も、「確かに学生時代はそういう状況に置かれていたような気がする」と思い出した。もちろん私は、そんな風潮に違和感を覚えていた側の人間である。

私は子どもの頃から、どうも同性との相性がとても悪かった。高校生ぐらいまで、「人間が苦手なんだ」と思っていたぐらいである。しかしその後異性との関わりが増えてきたことで、「人間」ではなく「同性」が苦手なだけだと気付けるようになった。そしてそんなこともあって私は、「『異性と友人になる』という方向に進もう」と考えるようになったのだ。
そんなわけで私は、何となく上手いことするっと「同質性の高い同性の集団」から抜けられていた。というか、それは単に「はみ出していただけ」とも言えるわけだが、まあ結果オーライという感じである。もしも「同質性の高い同性の集団」に囚われたままだったら、今も「人間が苦手」という感覚のままだったのではないかと思う。
あわせて読みたい
【助けて】映画『生きててごめんなさい』は、「共依存カップル」視点で生きづらい世の中を抉る物語(主…
映画『生きててごめんなさい』は、「ちょっと歪な共依存関係」を描きながら、ある種現代的な「生きづらさ」を抉り出す作品。出版社の編集部で働きながら小説の新人賞を目指す園田修一は何故、バイトを9度もクビになり、一日中ベッドの上で何もせずに過ごす同棲相手・清川莉奈を”必要とする”のか?
さて、別の項でも似たような言及がなされていたので紹介しておこう。
「非モテ」をテーマに、当事者グループでの実践のフィールドワークを通した男性学研究を行う西井開は、「非モテ」男性の困難の根源が女性にモテないこと自体ではなく、男性コミュニティの中でからかいなどの緩やかな排除を受けていることにあると論じる。(中略)親密な関係を築くことへの価値づけ・期待の高さゆえに、周囲から尊重・敬意を得られず孤立しているという問題が、恋人ができるという、特定の誰かとの親密な関係の獲得によって解決するという風に、誤って考えられてしまうというのだ。
社会の中で尊重を受けていないという問題を、恋人を得ることで解決できてしまうと考えることは、確かに問題の所在を取り違えている。
筒井晴香 「友達問題」と「推すこと」
ここで指摘されているのは、「『異性の恋人がいること』の価値」である。さて、私は今「異性愛者の男性」を取り上げているので「異性の」と書いたが、この点は集団の性質によって異なるだろう。まあいずれにせよ、「『恋人がいる』という事実にとても高い価値が認められている」せいで、「恋人が出来れば状況が変わるはず」みたいな思考になってしまうというわけだ。本質的には、「不遇をかこつ現状」と「恋人の不在」は何の関係もない。しかし、「同質性の高い集団」において「『恋人がいること』の価値」が高く設定されているために、「恋人が出来れば、今の悪い状況もすべて一掃されるはずだ」という思考になってしまうようなのだ。この話は「恋人」に限らず、「配偶者」でも同じだろう。
あわせて読みたい
【思考】戸田真琴、経験も文章もとんでもない。「人生どうしたらいい?」と悩む時に読みたい救いの1冊:…
「AV女優のエッセイ」と聞くと、なかなか手が伸びにくいかもしれないが、戸田真琴『あなたの孤独は美しい』の、あらゆる先入観を吹っ飛ばすほどの文章力には圧倒されるだろう。凄まじい経験と、普通ではない思考を経てAV女優に至った彼女の「生きる指針」は、多くの人の支えになるはずだ
そしてそんな感覚が共通理解として存在するため、「非モテ男性」は自身のことを「異常独身男性」と評したりもするのだそうだ。この点に関して西井開は、「『モテを重視していない人』が仲間内での連帯のためにこの言葉を使うケースもあるだろう」と断りを入れつつも、次のように話している。
(前略)その裏には家父長制に下支えされた異性愛規範・恋愛伴侶規範に縛られて「恋愛できなさ」について真剣に思い悩む男性が実在すること、その悩みを「異常独身男性」という自虐めいたテイストでしか表に出せない状況があることも忘れてはならないと思います。(西井開)
中村香住+西井開 すべてを「友情」と呼ぶ前に
「真剣に悩んでいるのだが、その真剣さを悟られたくない」という気持ちが「異常独身男性」という言葉に込められているのではないか、という分析である。そういう意味で、この「悩み」はなかなか深く複雑だと言えるのではないかと思う。
あわせて読みたい
【恋愛】モテない男は何がダメ?AV監督が男女共に贈る「コミュニケーション」と「居場所」の話:『すべ…
二村ヒトシ『すべてはモテるためである』は、タイトルも装丁も、どう見ても「モテ本」にしか感じられないだろうが、よくある「モテるためのマニュアル」が書かれた本ではまったくない。「行動」を促すのではなく「思考」が刺激される、「コミュニケーション」と「居場所」について語る1冊
「好意に基づく関係」が過大視され過ぎている
さて、ここまで書いてきた通り、私は「異性とは恋愛ではなく友人を目指そう」と考えていたり、「異性の方が楽に関われる」と気付けるタイミングがあったりしたため、運良く「モテないこと=異常」みたいな感覚に囚われずに生きてこられた。また、人によっては「恋人・配偶者がいる」という事実が自己肯定感や自信に繋がったりするのだろうが、私の場合、そのような感覚はまったくない。むしろ、「『恋愛関係になること』より『異性と友人になること』の方が遥かに難しい」と考えているので、「異性の友人がいる」という事実の方が私にとってはより価値が高いのである。

そんな風に考えているからこそ、次のような指摘は非常に重要なものに感じられた。
生きていくうえで友達の存在が極めて重要なもののように思われるのは、自発的な好意に基づく関係の価値が過大視されているせいも多分にある。むしろ、好意を伴う関係はなくとも、互いの嫌な点を受け入れ合って付き合いを続ける関係や、互いに尊重・敬意を保つ関係を得ることが重要である。それらが得られれば、互いの自発的な好意に基づく関係は、実はなくてもよいものなのではないか。
筒井晴香 「友達問題」と「推すこと」
あわせて読みたい
【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…
好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性
筒井晴香はこの文章に続けて、「でも好意を気にせず生きるのは難しいよね」みたいなことを書いているので、上述の引用はあくまでも「そんな風に考えられるようになりたい」という願望のようなものと捉えるべきだとは思う。ただ、私はかなり共感できた。そしてこの指摘は、冒頭で触れた「友達が残余カテゴリーであること」の話に繋がっていくと私は考えている。
さて実は、冒頭で私は、中村香住の主張を彼女の意図するのとは異なる形で用いた。私は彼女の主張を「『友達が残余カテゴリーであること』に不満を抱いている」とまとめたわけだが、この要約は本質的には正しくない。彼女は「『残余カテゴリー』だから残念だ」と言っているのではなく、「『友達』と呼ばれる関係性の中には、『恋人や家族よりも上位だと認識可能なもの』もあるのではないか?」と主張しているのである。つまり、「『好意に基づいている』から『関係が上位』というのはおかしくないか?」というわけだ。
彼女は対談の中で「私には『重要な他者』が数人いるのですが」と発言していたのだが、私にもこの「重要な他者」という表現はとてもしっくりくる感じがある。この「重要な他者」という表現には、「『恋人』や『家族』ではないが、『友達』と呼ぶには収まりが悪い」という感覚が含まれていると考えていいだろう。つまり、「『恋人』や『家族』と同列かそれ以上に感じられる『友達』が存在する」と言っているのだ。私も同感である。
あわせて読みたい
【あらすじ】声優の幾田りらとあのちゃんが超絶良い!アニメ映画『デデデデ』はビビるほど面白い!:『…
幾田りらとあのちゃんが声優を務めた映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』は、とにかく最高の物語だった。浅野いにおらしいポップさと残酷さを兼ね備えつつ、「終わってしまった世界でそれでも生きていく」という王道的展開を背景に、門出・おんたんという女子高生のぶっ飛んだ関係性が描かれる物語が見事すぎる
ちなみに少し脱線するが、中村香住は「『重要な他者』だと思っている相手と突然連絡が取れなくなることがある」という。そしてその際は、「数年後にまた縁があることを願って一旦身を引き、何もしない」そうで、私もまったく同じなのでとても共感できてしまった。私も同じような状況に陥ることが度々あるが、「しばらく何もしない」というやり方によってやり取りが復活した人もいる(まだそうなっていない人もいるが)。思いがけず「同じ感覚の人」の存在を知れてとても嬉しかった。
さて話を戻そう。一般的にはどうしたって「『好意に基づく関係性』の方が上位である」という感覚の方が強いはずだし、それはある意味で”圧力”のようにも機能するのではないかと思う。そしてそれ故に、「恋人や配偶者がいる」という事実が「人間として優位」であるかのように思えてしまい、そうでない人には辛く感じられたりもするというわけだ。
しかし私は、「『好意に基づく関係性』の方が上位である」という感覚は幻想でしかないと思っている。その理由の一端は、次のような文章からも感じ取れるかもしれない。
あわせて読みたい
【衝撃】広末涼子映画デビュー作『20世紀ノスタルジア』は、「広末が異常にカワイイ」だけじゃない作品
広末涼子の映画デビュー・初主演作として知られる『20世紀ノスタルジア』は、まず何よりも「広末涼子の可愛さ」に圧倒される作品だ。しかし、決してそれだけではない。初めは「奇妙な設定」ぐらいにしか思っていなかった「宇宙人に憑依されている」という要素が、物語全体を実に上手くまとめている映画だと感じた
ただ、どのような関係性にも常に不安定性がつきものですよね。そうした不安定性を、例えば恋人なら「恋人」というラベルを貼ることによって覆い隠している側面もあるのだと思います。(中村香住)
中村香住+西井開 すべてを「友情」と呼ぶ前に
つまり、「『関係性の不安定さ』に耐えられない」から「『強いラベル』を貼って安定しているように思い込みたい」みたいな感覚になるんじゃないかというわけだ。もっと平たく言えば、「『好意に基づく関係の方が上位だ』と”虚勢”を張っていないと怖くてやってられない」みたいな感じになるだろうか。このような捉え方をすると、少しは見え方が変わってくるんじゃないかと思う。

「不安だから関係に名前を付ける」という解釈、そして「結婚観の変遷」について
あわせて読みたい
【選択】特異な疑似家族を描く韓国映画『声もなく』の、「家族とは?」の本質を考えさせる深淵さ
喋れない男が、誘拐した女の子をしばらく匿い、疑似家族のような関係を築く韓国映画『声もなく』は、「映画の中で描かれていない部分」が最も印象に残る作品だ。「誘拐犯」と「被害者」のあり得ない関係性に、不自然さをまったく抱かせない設定・展開の妙が見事な映画
さて私はというと、「『名前が付かない関係性』の方がむしろ良い」と考えている。もっと正確に言えば、「他に呼びようがないから『友達』ということになっている関係性」が一番好きなのだ。先程「重要な他者」という表現を紹介したが、これもまた「一般的には存在しない概念をどうにか扱うための呼び名」であって、私の中では同じように「名前が付かない関係性」に含まれる。
そして当然のことながら、「恋人」や「配偶者」などと比べると「名前が付かない関係性」は不安定になりがちだ。「恋愛」や「結婚」の場合には、「こういう振る舞いをしていれば、その関係性の内側に留まれる」みたいな要素(何度か言及している「型」と同じようなもの)が存在するわけだが、そういう要素が無いからこそ「名前が付かない」のだし、不安定にもなってしまう。ただ私には、「『名前を付けること』によって不安定さを覆い隠せはしない関係性」の方が「関係性の強度」が高いように感じられるのだ。
さて、もしも私のこの思考が妥当だとすれば、こんな風にも考えられるだろう。つまり、多くの人が「『名前が付くこと』に安心感を抱く」という”呪縛”から逃れられれば、「人間関係がもたらすややこしさ」の多くが解消するのではないか、と。私の考えでは、「恋愛」や「結婚」がもてはやされるのは、単に「それらに『名前』が付いているから」でしかない。だから、「『名前が付くと安心』という感覚は”幻想”に過ぎない」と理解できれば、みんなもっと人間関係に気楽でいられる気がするのだ。
あわせて読みたい
【世界観】映画『夜は短し歩けよ乙女』の”黒髪の乙女”は素敵だなぁ。ニヤニヤが止まらない素晴らしいアニメ
森見登美彦の原作も大好きな映画『夜は短し歩けよ乙女』は、「リアル」と「ファンタジー」の境界を絶妙に漂う世界観がとても好き。「黒髪の乙女」は、こんな人がいたら好きになっちゃうよなぁ、と感じる存在です。ずっとニヤニヤしながら観ていた、とても大好きな映画
もちろん、こんな考えこそ”幻想”かもしれないと自分でも思うが、しかし、まったく可能性が無いとも言えないだろう。何せ本作中にも、そんな風に思わせてくれる文章が存在するのだ。
このことは、恋愛がロマン主義の中で制度的結婚の外部に生まれ、結婚と対立し結婚を脅かしてきたにもかかわらず、恋愛結婚の誕生によって結婚の条件となった歴史を思えば、驚くべきことである(加藤 2004:1章)
久保田裕之 友人関係と共同的親密性
すなわち、地域共同体や親族共同体を通じた階級的地位・品性・資産を交換する家同士の政治・経済的打算であった結婚は、近代の配偶者選択における「愛の大転換」(Illouz 2012:41)によって全く別ものへと変容した。すなわち、階層構造から結婚が切り離されることで配偶者選択が性化・心理学化し、社会的規制(人種・国籍・宗教・階層)から自由な「結婚市場」と、感情的特質や性的魅力によって膨大な潜在的パートナーが競合しあう象徴闘争としての「性的界」(Illouz 2012:55)を誕生させた。
久保田裕之 友人関係と共同的親密性
あわせて読みたい
【母娘】よしながふみ『愛すべき娘たち』で描かれる「女であることの呪い」に男の私には圧倒されるばかりだ
「女であること」は、「男であること」と比べて遥かに「窮屈さ」に満ちている。母として、娘として、妻として、働く者として、彼女たちは社会の中で常に闘いを強いられてきた。よしながふみ『愛すべき娘たち』は、そんな女性の「ややこしさ」を繊細に描き出すコミック
意味が分かるだろうか? 要するに、「今と昔とでは『結婚』の捉えられ方が様変わりしている」という話である。

かつて「結婚」には、「個人の意思」が入り込む余地などまったくなかった。「家」単位で行われるべきものであり、「誰と結婚したい」みたいな個人の希望など、端から無視されていたのだ。そのような中、「『制度的結婚』の外部」に「恋愛」という仕組みが生まれた。そしてそんな「恋愛」が「制度的結婚」を脅かし、「家」単位で行われるべきものだった「結婚」を、「恋愛を通じて相手を選ぶ」という「個人」単位の競争に変えたのである。我々は「恋愛結婚」を当たり前のものだと思っているが、その歴史は思いのほか浅いのだ。
であれば、「同じような大転換がまた起こる」という考えもあながちおかしなものとは言えないはずである。
あわせて読みたい
【共感】「恋愛したくない」という社会をリアルに描く売野機子の漫画『ルポルタージュ』が示す未来像
売野機子のマンガ『ルポルタージュ』は、「恋愛を飛ばして結婚すること」が当たり前の世界が描かれる。私はこの感覚に凄く共感できてしまった。「恋愛」「結婚」に対して、「世間の『当たり前』に馴染めない感覚」を持つ私が考える、「恋愛」「結婚」が有する可能性
「友人関係」にも「配慮」が必要になったことで、「恋愛」の価値が下がるのではないか
もちろん、そんな大転換がすぐに起こることはないだろうし、そもそも起こらないかもしれない。ただ、「変化の兆しなのでは?」と感じさせる記述が本書の中にあったので紹介しておこう。
若者の友人関係はかつて理想とされた互いにぶつかり合い腹を割って話し合って築いていく人間関係から、高度に繊細な気配りを伴った「優しい関係」へと変化してきたと論じられた。この原因についても、制度的な地縁や血縁、学校や会社といった共同体に埋め込まれた友人関係は、その拘束力によって離脱や選択が困難であったのに対して、個人化により拘束力が弱まることで、友人関係が選択可能になる反面、一方的に解消されるリスクや、だれからも選択されないリスクにさらされることになったとされる。友人への頼み、悩みの相談、コンプレックスの吐露、相手のためを思っての忠告はもはや友情の絆を紡ぐ試練でも支援でもなく、明日自分が友人から切り捨てられるかもしれない悪手となる。こうした友人関係のリスク化は、恋愛関係同様、資源の多寡に基づく友人関係の階層化と孤立を生むとされる。
久保田裕之 友人関係と共同的親密性
この文章を読んでどう思っただろうか? 「そんな気を遣ってばかりの相手は『友達』なんかじゃない」みたいに感じる人ももしかしたら多いのかもしれない。ただ私は、サンプルこそ多くはないものの、若い世代と喋っている中で、「友人への頼み、悩みの相談、コンプレックスの吐露、相手のためを思っての忠告はもはや友情の絆を紡ぐ試練でも支援でもなく、明日自分が友人から切り捨てられるかもしれない悪手となる」みたいに感じている人が多いなという印象を抱いている。また私自身も、そのような感覚を若干は有していると言っていいだろう。かなり共感できる指摘だなと思う。
あわせて読みたい
【誠実】戸田真琴は「言葉の人」だ。コンプレックスだらけの人生を「思考」と「行動」で突き進んだ記録…
戸田真琴のエッセイ第2弾『人を心から愛したことがないのだと気づいてしまっても』は、デビュー作以上に「誰かのために言葉を紡ぐ」という決意が溢れた1冊だ。AV女優という自身のあり方を客観的に踏まえた上で、「届くべき言葉がきちんと届く」ために、彼女は身を削ってでも生きる
さらに、「位置情報共有アプリ『Zenly』を介した人間関係」に関する考察の中にも同じような主張があった。
そしてここでより興味深いのは、友だちとの合理的な接し方に、多重の配慮がなされている点ではないだろうか。
鈴木亜矢子 位置情報を交換する若者たち
こう考えると、先に述べたBさんのアプリの使い方にも、空気を読んで「察する」配慮が見てとれる。まず相手がどこに何時間滞在しているかをアプリで確認し、相手の状況を推測する。そしてゲームや遊びに誘える状況にあると判断したら、そこで初めてLINEを使って相手にアプローチする。相手に直接打診する前に位置情報共有アプリで相手の現状を読み取り、誘うタイミングをうかがっているのだ。このように、位置情報共有アプリでは情報の受け手が能動的に働き、配慮に基づく簡略化したコミュニケーションが行われている。
鈴木亜矢子 位置情報を交換する若者たち
あわせて読みたい
【考察】生きづらい性格は変わらないから仮面を被るしかないし、仮面を被るとリア充だと思われる:『勝…
「リア充感」が滲み出ているのに「生きづらさ」を感じてしまう人に、私はこれまでたくさん会ってきた。見た目では「生きづらさ」は伝わらない。24年間「リアル彼氏」なし、「脳内彼氏」との妄想の中に生き続ける主人公を描く映画『勝手にふるえてろ』から「こじらせ」を知る
また、ここ数年「マルハラ」という言葉を耳にするようになった。LINEなどで送られてくる「文末に『。』が付いた文章」を「怖い」と感じる感覚のことだ。この「マルハラ」の是非についてはどうでもいいのだが、若い世代のこのような感覚からも、「些細な要素から相手の感情などの情報を読み取り、相手に最大限配慮しようとする姿勢」が窺えるのではないかと思う。
そしてこれらの話をまとめる、「『友人関係』が『恋愛関係』と同じかそれ以上に難しくなっている」という現状が浮かび上がってくると言えるだろう。

このように、「『友人関係』にも多くの配慮が必要」という考えが若い世代で当たり前となり、「『恋愛』と同じくらいややこしい」みたいになっていくとしたら、「『恋愛』なんかとてもしていられない」と感じる人が増えていく可能性は十分あるはずだ。そしてそれによって少しずつ、「『好意に基づく関係性』の方が上位である」という価値観が薄れていってもおかしくはないと思う。もしかしたら、「お見合い結婚」がまた主流になるなんて未来がやってくるかもしれない。「結婚観の変遷」を踏まえれば、それぐらいの変化は十分あり得るはずだ。
あわせて読みたい
【感涙】映画『彼女が好きなものは』の衝撃。偏見・無関心・他人事の世界から”脱する勇気”をどう持つか
涙腺がぶっ壊れたのかと思ったほど泣かされた映画『彼女が好きなものは』について、作品の核となる「ある事実」に一切触れずに書いた「ネタバレなし」の感想です。「ただし摩擦はゼロとする」の世界で息苦しさを感じているすべての人に届く「普遍性」を体感してください
そんな可能性さえ感じさせる内容だった。
青土社
¥1,760 (2024/12/13 22:13時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
『現代思想 <友情>の現在』の記述と私の個人的な感覚をベースに様々な話題に触手を伸ばしてみたが、いかがだっただろうか? もしかしたら、多くの人にとって「意味がわからない」と感じられる内容だったかもしれない。
実際、こういう話を周りの人にしてみても通じないことの方が多いし、そもそも私の価値観が一般的な感覚からズレていることも理解してはいる。ただ、冒頭で紹介した友人のように、メチャクチャ話が通じる人と出会えたりすることもあるのだ。決して多くはないだろうけど、「分かる!」と感じてくれる人もそれなりにはいるんじゃないだろうか。
あわせて読みたい
【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…
映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う
本書で扱われている話やこの記事で書いたような内容が「当たり前」だと受け取られる世の中になってくれたらいいなと思っているし、何となくだが少しずつそんな変化の兆しも感じてはいる。もちろん、時代がどんな風に変わろうが社会から「マイノリティ」が消えることはないし、そういう人はマジョリティに馴染めずにこれからも苦労するだろう。社会がどう変化しようが、そういう現実がゼロになることはない。それでも、色んな状況が「フラット」になっているように思えるのは、とても喜ばしいことだ。
そして個人的にも、こういうことについて久々にガッツリ言語化出来てとても楽しかった。教えてくれた友人に感謝である。
さて、ここからは追記だが、私は2025年9月6日に、劇団「いいへんじ」による演劇『われわれなりのロマンティック』を観に行った。こちらも、本書『現代思想 <友情>の現在』の存在を教えてくれた友人からのオススメである。何故ここでそんな話をしているのかと言えば、この演劇で「ジェンダー・セクシュアリティ監修」を務めたのが巻頭の対談に登場した中村香住だからだ。
この演劇の感想については別途noteに書いたので、機会があれば以下のリンクから読んでみてほしい。演劇自体は既に終幕を迎えており、再演でもない限り観られる機会はないと思うが、扱っているテーマも役者の演技もとにかく素敵な演劇だった。
note(ノート)
【感想・レビュー】「クワロマンティック」をリアルに描き出す舞台演劇『われわれなりのロマンティック』(…
超久々に観た演劇『われわれなりのロマンティック』(いいへんじ)は、私の個人的な問題意識にも突き刺さる、超絶面白い物語だった
ルシルナ | 生きる知る悩む~「生き…
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…
私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【包容】映画『違国日記』を観て思う。「他者との接し方」が皆こうだったらもっと平和なはずだって(主…
映画『違国日記』は、人見知りの小説家・高代槙生が両親を亡くした姪・朝を引き取り一緒に暮らすところから始まる物語で、槙生と朝を中心とした様々な人間関係が絶妙に描かれている作品でした。人付き合いが苦手ながら、15歳という繊細な存在を壊さないように、でも腫れ物みたいには扱わないように慎重になる槙生のスタンスが素敵です
あわせて読みたい
【天才】映画『アット・ザ・ベンチ』面白すぎる!蓮見翔の脚本に爆笑、生方美久の会話劇にうっとり(監…
役者も脚本家も監督も何も知らないまま、「有名な役者が出てこないマイナーな映画」だと思い込んで観に行った映画『アット・ザ・ベンチ』は、衝撃的に面白い作品だった。各話ごと脚本家が異なるのだが、何よりも、第2話「回らない」を担当したダウ90000・蓮見翔の脚本が超絶面白い。あまりの衝撃にぶっ飛ばされてしまった
あわせて読みたい
【葛藤】映画『きみの色』(山田尚子)は、感受性が強すぎる若者のリアルをバンドを通じて描き出す(主…
山田尚子監督作『きみの色』は、これといった起伏のないストーリー展開でありながら、「若い世代の繊細さに満ちた人間関係」をとてもリアルに描き出す雰囲気が素敵な作品。「悩み・葛藤を抱えている状態が日常である」という雰囲気をベースにしつつ、「音楽」を起点に偶然繋がった3人の緩やかな日々を描き出す物語に惹きつけられた
あわせて読みたい
【繊細】映画『ぼくのお日さま』(奥山大史)は、小さな世界での小さな恋を美しい映像で描く(主演:越…
映画『ぼくのお日さま』は、舞台設定も人間関係も実にミニマムでありながら、とても奥行きのある物語が展開される作品。予告編で「3つの恋」と言及されなければ、描かれるすべての「恋」には気付けなかっただろうと思うくらいの繊細な関係性と、映像・音楽を含めてすべてが美しい旋律として奏でられる物語がとても素敵でした
あわせて読みたい
【孤独】映画『ナミビアの砂漠』は、自由だが居場所がない主人公を演じる河合優実の存在感が圧倒的(監…
映画『ナミビアの砂漠』は、とにかく「河合優実が凄まじい」のひと言に尽きる作品だ。彼女が演じたカナという主人公の「捉えどころの無さ」は絶妙で、一見すると凄まじく「自由」に羽ばたいている感じなのに、実際には全然「自由」には見えないというバランスが見事だった。特段の物語はないのに、137分間惹きつけられてしまうだろう
あわせて読みたい
【変態】映画『コンセント/同意』が描く50歳と14歳少女の”恋”は「キモっ!」では終われない
映画『コンセント/同意』は、50歳の著名小説家に恋をした14歳の少女が大人になってから出版した「告発本」をベースに作られた作品だ。もちろん実話を元にしており、その焦点はタイトルの通り「同意」にある。自ら望んで36歳年上の男性との恋に踏み出した少女は、いかにして「同意させられた」という状況に追い込まれたのか?
あわせて読みたい
【評価】高山一実の小説かつアニメ映画である『トラペジウム』は、アイドル作とは思えない傑作(声優:…
原作小説、そしてアニメ映画共に非常に面白かった『トラペジウム』は、高山一実が乃木坂46に在籍中、つまり「現役アイドル」として出版した作品であり、そのクオリティに驚かされました。「現役アイドル」が「アイドル」をテーマにするというド直球さを武器にしつつ、「アイドルらしからぬ感覚」をぶち込んでくる非常に面白い作品である
あわせて読みたい
【絶妙】映画『水深ゼロメートルから』(山下敦弘)は、何気ない会話から「女性性の葛藤」を描く(主演…
高校演劇を舞台化する企画第2弾に選ばれた映画『水深ゼロメートルから』は、「水のないプール」にほぼ舞台が固定された状態で、非常に秀逸な会話劇として展開される作品だ。退屈な時間を埋めるようにして始まった「ダルい会話」から思いがけない展開が生まれ、「女として生きること」についての様々な葛藤が描き出される点が面白い
あわせて読みたい
【感想】映画『夜明けのすべて』は、「ままならなさ」を抱えて生きるすべての人に優しく寄り添う(監督…
映画『夜明けのすべて』は、「PMS」や「パニック障害」を通じて、「自分のものなのに、心・身体が思い通りにならない」という「ままならなさ」を描き出していく。決して他人事ではないし、「私たちもいつそのような状況に置かれるか分からない」という気持ちで観るのがいいでしょう。物語の起伏がないのに惹きつけられる素敵な作品です
あわせて読みたい
【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…
映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった
あわせて読みたい
【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ
映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『52ヘルツのクジラたち』の「無音で叫ぶ人」と「耳を澄ます人」の絶妙な響鳴(原作:…
映画『52ヘルツのクジラたち』は、「現代的な問題のごった煮」と感じられてしまうような”過剰さ”に溢れてはいますが、タイトルが作品全体を絶妙に上手くまとめていて良かったなと思います。主演の杉咲花がやはり見事で、身体の内側から「不幸」が滲み出ているような演技には圧倒されてしまいました
あわせて読みたい
【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件
映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品
あわせて読みたい
【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…
映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です
あわせて読みたい
【怖い?】映画『アメリ』(オドレイ・トトゥ主演)はとても奇妙だが、なぜ人気かは分かる気がする
名作として知られているものの観る機会の無かった映画『アメリ』は、とても素敵な作品でした。「オシャレ映画」という印象を持っていて、それは確かにその通りなのですが、それ以上に私は「主人公・アメリの奇妙さ」に惹かれたのです。普通には成立しないだろう展開を「アメリだから」という謎の説得力でぶち抜く展開が素敵でした
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『悪は存在しない』(濱口竜介)の衝撃のラストの解釈と、タイトルが示唆する現実(主…
映画『悪は存在しない』(濱口竜介監督)は、観る者すべてを困惑に叩き落とす衝撃のラストに、鑑賞直後は迷子のような状態になってしまうだろう。しかし、作中で提示される様々な要素を紐解き、私なりの解釈に辿り着いた。全編に渡り『悪は存在しない』というタイトルを強く意識させられる、脚本・映像も見事な作品だ
あわせて読みたい
【おすすめ】カンヌ映画『PERFECT DAYS』は、ほぼ喋らない役所広司の沈黙が心地よい(ヴィム・ヴェンダ…
役所広司主演映画『PERFECT DAYS』(ヴィム・ヴェンダース監督)は、主人公・平山の「沈黙」がとにかく雄弁な物語である。渋谷区のトイレの清掃員である無口な平山の、世間とほとんど繋がりを持たない隔絶した日常が、色んなものを抱えた者たちを引き寄せ、穏やかさで満たしていく様が素晴らしい
あわせて読みたい
【考察】A24のホラー映画『TALK TO ME』が描くのは、「薄く広がった人間関係」に悩む若者のリアルだ
「A24のホラー映画史上、北米最高興収」と謳われる『TALK TO ME トーク・トゥ・ミー』は、一見「とても分かりやすいホラー映画」である。しかし真のテーマは「SNS過剰社会における人間関係の困難さ」なのだと思う。結果としてSNSが人と人との距離を遠ざけてしまっている現実を、ホラー映画のスタイルに落とし込んだ怪作
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『アンダーカレント』(今泉力哉)は、失踪をテーマに「分かり合えなさ」を描く
映画『アンダーカレント』において私は、恐らく多くの人が「受け入れがたい」と感じるだろう人物に共感させられてしまった。また本作は、「他者を理解すること」についての葛藤が深掘りされる作品でもある。そのため、私が普段から抱いている「『他者のホントウ』を知りたい」という感覚も強く刺激された
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
あわせて読みたい
【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…
映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ
あわせて読みたい
【考察】映画『街の上で』(今泉力哉)が描く「男女の友情は成立する」的会話が超絶妙で素晴らしい(出…
映画『街の上で』(今泉力哉監督)は、「映画・ドラマ的会話」ではない「自然な会話」を可能な限り目指すスタンスが見事だった。「会話の無駄」がとにかく随所に散りばめられていて、そのことが作品のリアリティを圧倒的に押し上げていると言える。ある男女の”恋愛未満”の会話もとても素晴らしかった
あわせて読みたい
【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…
映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う
あわせて読みたい
【未知】コーダに密着した映画『私だけ聴こえる』は、ろう者と聴者の狭間で居場所がない苦悩を映し出す
あなたは「コーダ」と呼ばれる存在を知っているだろうか?「耳の聴こえない親を持つ、耳が聴こえる子ども」のことであり、映画『私だけ聴こえる』は、まさにそんなコーダが置かれた状況を描くドキュメンタリー映画だ。自身は障害者ではないのに大変な苦労を強いられている現状が理解できる作品
あわせて読みたい
【闘争】映画『あのこと』が描く、中絶が禁止だった時代と、望まぬ妊娠における圧倒的な「男の不在」
中絶が禁止されていた1960年代のフランスを舞台にした映画『あのこと』は、「望まぬ妊娠」をしてしまった秀才の大学生が、「未来を諦めない」ために中絶を目指す姿が描かれる。さらに、誰にも言えずに孤独に奮闘する彼女の姿が「男の不在」を強調する物語でもあり、まさに男が観るべき作品だ
あわせて読みたい
【助けて】映画『生きててごめんなさい』は、「共依存カップル」視点で生きづらい世の中を抉る物語(主…
映画『生きててごめんなさい』は、「ちょっと歪な共依存関係」を描きながら、ある種現代的な「生きづらさ」を抉り出す作品。出版社の編集部で働きながら小説の新人賞を目指す園田修一は何故、バイトを9度もクビになり、一日中ベッドの上で何もせずに過ごす同棲相手・清川莉奈を”必要とする”のか?
あわせて読みたい
【希望】誰も傷つけたくない。でも辛い。逃げたい。絶望しかない。それでも生きていく勇気がほしい時に…
2006年発売、2021年文庫化の『私を見て、ぎゅっと愛して』は、ブログ本のクオリティとは思えない凄まじい言語化力で、1人の女性の内面の葛藤を抉り、読者をグサグサと突き刺す。信じがたい展開が連続する苦しい状況の中で、著者は大事なものを見失わず手放さずに、勇敢に前へ進んでいく
あわせて読みたい
【理解】「多様性を受け入れる」とか言ってるヤツ、映画『炎上する君』でも観て「何も見てない」って知…
西加奈子の同名小説を原作とした映画『炎上する君』(ふくだももこ監督)は、「多様性」という言葉を安易に使いがちな世の中を挑発するような作品だ。「見えない存在」を「過剰に装飾」しなければならない現実と、マジョリティが無意識的にマイノリティを「削る」リアルを描き出していく
あわせて読みたい
【信念】凄いな久遠チョコレート!映画『チョコレートな人々』が映す、障害者雇用に挑む社長の奮闘
重度の人たちも含め、障害者を最低賃金保証で雇用するというかなり無謀な挑戦を続ける夏目浩次を追う映画『チョコレートな人々』には衝撃を受けた。キレイゴトではなく、「障害者を真っ当に雇用したい」と考えて「久遠チョコレート」を軌道に乗せたとんでもない改革者の軌跡を追うドキュメンタリー
あわせて読みたい
【家族】ゲイの男性が、拘置所を出所した20歳の男性と養子縁組し親子関係になるドキュメンタリー:映画…
「ゲイの男性が、拘置所から出所した20歳の男性と養子縁組し、親子関係になる」という現実を起点にしたドキュメンタリー映画『二十歳の息子』は、奇妙だが実に興味深い作品だ。しばらく何が描かれているのか分からない展開や、「ゲイであること」に焦点が当たらない構成など、随所で「不協和音」が鳴り響く1作
あわせて読みたい
【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に
「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた
あわせて読みたい
【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断
映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
あわせて読みたい
【美麗】映画『CLOSE/クロース』はあまりにも切ない。「誰かの当たり前」に飲み込まれてしまう悲劇
子どもの頃から兄弟のように育った幼馴染のレオとレミの関係の変化を丁寧に描き出す映画『CLOSE/クロース』は、「自分自身で『美しい世界』を毀損しているのかもしれない」という話でもある。”些細な”言動によって、確かに存在したあまりに「美しい世界」があっさりと壊されてしまう悲哀が描かれる
あわせて読みたい
【苦悩】「やりがいのある仕事」だから見て見ぬふり?映画『アシスタント』が抉る搾取のリアル
とある映画会社で働く女性の「とある1日」を描く映画『アシスタント』は、「働くことの理不尽さ」が前面に描かれる作品だ。「雑用」に甘んじるしかない彼女の葛藤がリアルに描かれている。しかしそれだけではない。映画の「背景」にあるのは、あまりに悪逆な行為と、大勢による「見て見ぬふり」である
あわせて読みたい
【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…
「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』を観てくれ!現代の人間関係の教科書的作品を考…
映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』は、私にグサグサ突き刺さるとても素晴らしい映画だった。「ぬいぐるみに話しかける」という活動内容の大学サークルを舞台にした物語であり、「マイノリティ的マインド」を持つ人たちの辛さや葛藤を、「マジョリティ視点」を絶妙に織り交ぜて描き出す傑作について考察する
あわせて読みたい
【映画】今泉力哉監督『ちひろさん』(有村架純)が描く、「濃い寂しさ」が溶け合う素敵な関係性
今泉力哉監督、有村架純主演の映画『ちひろさん』は、その圧倒的な「寂しさの共有」がとても心地よい作品です。色んな「寂しさ」を抱えた様々な人と関わる、「元風俗嬢」であることを公言し海辺の町の弁当屋で働く「ちひろさん」からは、同じような「寂しさ」を抱える人を惹き付ける力強さが感じられるでしょう
あわせて読みたい
【共感】「恋愛したくない」という社会をリアルに描く売野機子の漫画『ルポルタージュ』が示す未来像
売野機子のマンガ『ルポルタージュ』は、「恋愛を飛ばして結婚すること」が当たり前の世界が描かれる。私はこの感覚に凄く共感できてしまった。「恋愛」「結婚」に対して、「世間の『当たり前』に馴染めない感覚」を持つ私が考える、「恋愛」「結婚」が有する可能性
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く
「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品
あわせて読みたい
【誠実】戸田真琴は「言葉の人」だ。コンプレックスだらけの人生を「思考」と「行動」で突き進んだ記録…
戸田真琴のエッセイ第2弾『人を心から愛したことがないのだと気づいてしまっても』は、デビュー作以上に「誰かのために言葉を紡ぐ」という決意が溢れた1冊だ。AV女優という自身のあり方を客観的に踏まえた上で、「届くべき言葉がきちんと届く」ために、彼女は身を削ってでも生きる
あわせて読みたい
【苦しい】「恋愛したくないし、興味ない」と気づいた女性が抉る、想像力が足りない社会の「暴力性」:…
「実は私は、恋愛的な関係を求めているわけじゃないかもしれない」と気づいた著者ムラタエリコが、自身の日常や専門学校でも学んだ写真との関わりを基に、「自分に相応しい関係性」や「社会の暴力性」について思考するエッセイ。久々に心にズバズバ刺さった、私にはとても刺激的な1冊だった。
あわせて読みたい
【感想】のん主演映画『私をくいとめて』から考える、「誰かと一緒にいられれば孤独じゃないのか」問題
のん(能年玲奈)が「おひとり様ライフ」を満喫する主人公を演じる映画『私をくいとめて』を観て、「孤独」について考えさせられた。「誰かと関わっていられれば孤独じゃない」という考えに私は賛同できないし、むしろ誰かと一緒にいる時の方がより強く孤独を感じることさえある
あわせて読みたい
【感想】おげれつたなか『エスケープジャーニー』は、BLでしか描けない”行き止まりの関係”が絶妙
おげれつたなか『エスケープジャーニー』のあらすじ紹介とレビュー。とにかく、「BLでしか描けない関係性」が素晴らしかった。友達なら完璧だったのに、「恋人」ではまったく上手く行かなくなってしまった直人と太一の葛藤を通じて、「進んでも行き止まり」である関係にどう向き合うか考えさせられる
あわせて読みたい
【違和感】平田オリザ『わかりあえないことから』は「コミュニケーション苦手」問題を新たな視点で捉え…
「コミュニケーションが苦手」なのは、テクニックの問題ではない!?『わかりあえないことから』は、学校でのコミュニケーション教育に携わる演劇人・平田オリザが抱いた違和感を起点に、「コミュニケーション教育」が抱える問題と、私たち日本人が進むべき道を示す1冊
あわせて読みたい
【感想】映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)の稲垣吾郎の役に超共感。「好きとは何か」が分からない人へ
映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)は、稲垣吾郎演じる主人公・市川茂巳が素晴らしかった。一般的には、彼の葛藤はまったく共感されないし、私もそのことは理解している。ただ私は、とにかく市川茂巳にもの凄く共感してしまった。「誰かを好きになること」に迷うすべての人に観てほしい
あわせて読みたい
【思考】戸田真琴、経験も文章もとんでもない。「人生どうしたらいい?」と悩む時に読みたい救いの1冊:…
「AV女優のエッセイ」と聞くと、なかなか手が伸びにくいかもしれないが、戸田真琴『あなたの孤独は美しい』の、あらゆる先入観を吹っ飛ばすほどの文章力には圧倒されるだろう。凄まじい経験と、普通ではない思考を経てAV女優に至った彼女の「生きる指針」は、多くの人の支えになるはずだ
あわせて読みたい
【欠落】映画『オードリー・ヘプバーン』が映し出す大スターの生き方。晩年に至るまで生涯抱いた悲しみ…
映画『オードリー・ヘプバーン』は、世界的大スターの知られざる素顔を切り取るドキュメンタリーだ。戦争による壮絶な飢え、父親の失踪、消えぬ孤独感、偶然がもたらした映画『ローマの休日』のオーディション、ユニセフでの活動など、様々な証言を元に稀代の天才を描き出す
あわせて読みたい
【価値】どうせ世の中つまらない。「レンタルなんもしない人」の本でお金・仕事・人間関係でも考えよう…
「0円で何もしない」をコンセプトに始まった「レンタルなんもしない人」という活動は、それまで見えにくかった様々な価値観を炙り出した見事な社会実験だと思う。『<レンタルなんもしない人>というサービスをはじめます。』で本人が語る、お金・仕事・人間関係の新たな捉え方
あわせて読みたい
【恋愛】モテない男は何がダメ?AV監督が男女共に贈る「コミュニケーション」と「居場所」の話:『すべ…
二村ヒトシ『すべてはモテるためである』は、タイトルも装丁も、どう見ても「モテ本」にしか感じられないだろうが、よくある「モテるためのマニュアル」が書かれた本ではまったくない。「行動」を促すのではなく「思考」が刺激される、「コミュニケーション」と「居場所」について語る1冊
あわせて読みたい
【感涙】映画『彼女が好きなものは』の衝撃。偏見・無関心・他人事の世界から”脱する勇気”をどう持つか
涙腺がぶっ壊れたのかと思ったほど泣かされた映画『彼女が好きなものは』について、作品の核となる「ある事実」に一切触れずに書いた「ネタバレなし」の感想です。「ただし摩擦はゼロとする」の世界で息苦しさを感じているすべての人に届く「普遍性」を体感してください
あわせて読みたい
【母娘】よしながふみ『愛すべき娘たち』で描かれる「女であることの呪い」に男の私には圧倒されるばかりだ
「女であること」は、「男であること」と比べて遥かに「窮屈さ」に満ちている。母として、娘として、妻として、働く者として、彼女たちは社会の中で常に闘いを強いられてきた。よしながふみ『愛すべき娘たち』は、そんな女性の「ややこしさ」を繊細に描き出すコミック
あわせて読みたい
【苦しい】恋愛で寂しさは埋まらない。恋に悩む女性に「心の穴」を自覚させ、自己肯定感を高めるための…
「どうして恋愛が上手くいかないのか?」を起点にして、「女性として生きることの苦しさ」の正体を「心の穴」という言葉で説明する『なぜあなたは「愛してくれない人」を好きになるのか』はオススメ。「著者がAV監督」という情報に臆せず是非手を伸ばしてほしい
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ
私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。
あわせて読みたい
【中絶】望まない妊娠をした若い女性が直面する現実をリアルに描く映画。誰もが現状を知るべきだ:『17…
他の様々な要素を一切排し、「望まぬ妊娠をした少女が中絶をする」というただ1点のみに全振りした映画『17歳の瞳に映る世界』は、説明もセリフも極端に削ぎ落としたチャレンジングな作品だ。主人公2人の沈黙が、彼女たちの置かれた現実を雄弁に物語っていく。
あわせて読みたい
【考察】『うみべの女の子』が伝えたいことを全力で解説。「関係性の名前」を手放し、”裸”で対峙する勇敢さ
ともすれば「エロ本」としか思えない浅野いにおの原作マンガを、その空気感も含めて忠実に映像化した映画『うみべの女の子』。本作が一体何を伝えたかったのかを、必死に考察し全力で解説する。中学生がセックスから関係性をスタートさせることで、友達でも恋人でもない「名前の付かない関係性」となり、行き止まってしまう感じがリアル
あわせて読みたい
【考察】生きづらい性格は変わらないから仮面を被るしかないし、仮面を被るとリア充だと思われる:『勝…
「リア充感」が滲み出ているのに「生きづらさ」を感じてしまう人に、私はこれまでたくさん会ってきた。見た目では「生きづらさ」は伝わらない。24年間「リアル彼氏」なし、「脳内彼氏」との妄想の中に生き続ける主人公を描く映画『勝手にふるえてろ』から「こじらせ」を知る
あわせて読みたい
【無知】映画『生理ちゃん』で理解した気になってはいけないが、男(私)にも苦労が伝わるコメディだ
男である私にはどうしても理解が及ばない領域ではあるが、女友達から「生理」の話を聞く機会があったり、映画『生理ちゃん』で視覚的に「生理」の辛さが示されることで、ちょっとは分かったつもりになっている。しかし男が「生理」を理解するのはやっぱり難しい
あわせて読みたい
【爆発】どうしても人目が気になる自意識過剰者2人、せきしろと又吉直樹のエッセイに爆笑&共感:『蕎麦…
「コンビニのコピー機で並べない」せきしろ氏と、「フラッシュモブでの告白に恐怖する」又吉直樹氏が、おのれの「自意識過剰さ」を「可笑しさ」に変えるエッセイ『蕎麦湯が来ない』は、同じように「考えすぎてしまう人」には共感の嵐だと思います
あわせて読みたい
【逃避】つまらない世の中で生きる毎日を押し流す”何か”を求める気持ちに強烈に共感する:映画『サクリ…
子どもの頃「台風」にワクワクしたように、未だに、「自分のつまらない日常を押し流してくれる『何か』」の存在を待ちわびてしまう。立教大学の学生が撮った映画『サクリファイス』は、そんな「何か」として「東日本大震災」を描き出す、チャレンジングな作品だ
あわせて読みたい
【感想】映画『窮鼠はチーズの夢を見る』を異性愛者の男性(私)はこう観た。原作も読んだ上での考察
私は「腐男子」というわけでは決してないのですが、周りにいる腐女子の方に教えを請いながら、多少BL作品に触れたことがあります。その中でもダントツに素晴らしかったのが、水城せとな『窮鼠はチーズの夢を見る』です。その映画と原作の感想、そして私なりの考察について書いていきます
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
あわせて読みたい
【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…
好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性
あわせて読みたい
【辛い】こじらせ女子必読!ややこしさと共に生きるしかない、自分のことで精一杯なすべての人に:『女…
「こじらせ」って感覚は、伝わらない人には全然伝わりません。だからこそ余計に、自分が感じている「生きづらさ」が理解されないことにもどかしさを覚えます。AVライターに行き着いた著者の『女子をこじらせて』をベースに、ややこしさを抱えた仲間の生き方を知る
あわせて読みたい
【考察】世の中は理不尽だ。平凡な奴らがのさばる中で、”特別な私の美しい世界”を守る生き方:『オーダ…
自分以外は凡人、と考える主人公の少女はとてもイタい。しかし、世間の価値観と折り合わないなら、自分の美しい世界を守るために闘うしかない。中二病の少女が奮闘する『オーダーメイド殺人クラブ』をベースに、理解されない世界をどう生きるかについて考察する
あわせて読みたい
【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…
誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【肯定】価値観の違いは受け入れられなくていい。「普通」に馴染めないからこそ見える世界:『君はレフ…
子どもの頃、周りと馴染めない感覚がとても強くて苦労しました。ただし、「普通」から意識的に外れる決断をしたことで、自分が持っている価値観を言葉で下支えすることができたとも感じています。「普通」に馴染めず、自分がダメだと感じてしまう人へ。
あわせて読みたい
【前進】誰とも価値観が合わない…。「普通」「当たり前」の中で生きることの難しさと踏み出し方:『出会…
生きていると、「常識的な考え方」に囚われたり、「普通」「当たり前」を無自覚で強要してくる人に出会ったりします。そういう価値観に合わせられない時、自分が間違っている、劣っていると感じがちですが、そういう中で一歩踏み出す勇気を得るための考え方です
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
普通って何?【本・映画の感想】 | ルシルナ
人生のほとんどの場面で、「普通」「常識」「当たり前」に対して違和感を覚え、生きづらさを感じてきました。周りから浮いてしまったり、みんなが当然のようにやっているこ…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…































































































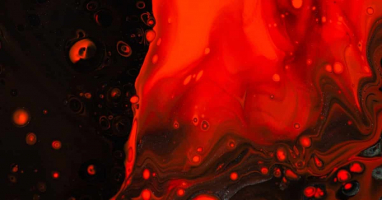



















コメント