目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
監督:サーイム・サーディク, クリエイター:オールキャップス, クリエイター:クーサットフィルムズ, プロデュース:アポールヴァ・チャラン, プロデュース:サルマド・クーサット, プロデュース:ローレン・マン, Writer:サーイム・サーディク, 出演:アリ・ジュネージョー, 出演:ラスティ・ファルーク, 出演:アリーナ・ハーン, 出演:サルワット・ギラーニ, 出演:ソハイル・サミール, 出演:サルマーン・ピアザダ, 出演:サニア・サイード
ポチップ
VIDEO
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
「家父長制」と「宗教」が絡まりあった、「諸悪の根源」としか言いようがない父親の価値観 「『古い価値観』のせいで個人の人生が制約される」という状況には、共感させられる人も多いはずだ 「男性でも女性でもない性」を意味する「ヒジュラー」という単語が大昔から存在し、今も使われていることに対して驚かされた 私は「宗教的なもの」を全般的に毛嫌いしているので、そういう意味でも許容しがたい状況が多数描かれる作品だった
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
本国パキスタンでは上映が禁止された映画『ジョイランド』は、今も残る古い家族観に翻弄される若者たちを描き出す作品だ
なかなか興味深い映画 だった。
本作はパキスタンの映画 なのだが、本国ではなんと、一度「上映禁止」が決まった そうだ。正直なところ、ごく一般的な日本人には、どうして本作を上映禁止にしなければならないのか理解できない だろう。それぐらい、私たちには「ごく普通のテーマ」にしか見えない はずだ。恐らくだが、パキスタンでは今も「昔ながらの家族観(家父長制)」が強い のだろうし、さらに「LGBTQへの理解」も乏しい と思われるので、そういう理由で拒絶反応が生まれてしまった ということなのだと思う。
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
ちなみに本作は、ノーベル平和賞を受賞したマララ・ユサフザイらの支援のお陰で、パキスタンでも上映されることになった のだが、しかしそれでも、監督の出身であり本作の舞台となっている地域では、今も上映禁止措置が続いている という。宗教とも関係する話だと思うのでややこしいのだが、しかし個人的には、こんな風に「国家が『個人の日常生活』を検閲する」みたいな感じはやはり好きになれないし、そんな国には本当に住みたくない なと思う。
本作はひたすらに「家族の物語」 でしかなく、舞台設定も人間関係もとてもミニマムで日常的なもの である。ただ特殊なのは、かつての日本のような「家父長制」が今も根強く、さらに「男は働いて家族を養うべき」「女は家で家事をするのが当然」みたいな古い価値観が当然のように蔓延っている という点だろう。そんなすこぶる窮屈な世界の中で、どうにか自分らしく生きていこうとする者たちの奮闘を描き出す作品 である。
映画『ジョイランド』の内容紹介
物語の舞台となるのは、3世代9人が暮らすある一家 。主人公は次男のハイダル である。彼は、実に2年間も働いていない 。ただ、「お金を稼ぐ仕事をしていない」というだけで、兄サリームの娘たち(ハイダルにとっては姪)の面倒を見たり、兄嫁のヌチと分担で家中の家事を担ったりしている 。ハイダルの妻ムムターズが美容部員として働き家計を支えている のだが、彼女にとっては仕事が生きがい で、「ハイダルが家事、ムムターズが仕事」という役割分担はとてもうまくいっていた。
あわせて読みたい
【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか
私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう
本作の物語は、ヌチが4人目の子どもを出産するところから始まる 。検査では男の子だという話だったので喜んでいたのだが、結局生まれてきたのはまたしても女の子 。ムムターズがハイダルに「5人目に挑むのかな? 」と口にするほど、兄夫婦はとにかく男児の誕生を待ち望んでいる 。
一方ハイダル夫妻は、子どもを持つつもりは特にない ようだ。恐らくどちらともが「今のままでいい」と考えている のだと思う。ハイダルが「自分の子どもを持つこと」に対してどう考えているのかはっきりとは分からない。ただ、ムムターズは間違いなく「ずっと仕事を続けていたい」のだろうし、だから子どもを望んでいない のだと思う。
そんなわけで、この一家のバランスは絶妙な感じで保たれていた のである。父親を除いては 。
年を取って足が弱っている のだろう、車椅子での生活を余儀なくされている父親は、ハイダル夫妻にも子どもが生まれることを望んでいる 。恐らくその背景には、兄夫婦の子どもが女児ばかり であることも関係しているのだろう。「跡継ぎ」となる男児の誕生は、やはり父親にとっても大きな関心事 なのである。
あわせて読みたい
【実話】田舎暮らし失敗。映画『理想郷』が描く、めんどくさい人間関係が嫌がらせに発展した事件
実話を基にした映画『理想郷』は、「理想の田舎暮らし」が粉微塵に粉砕されていく過程を描く物語である。第一義的には当然、夫妻に嫌がらせを続ける兄弟が悪いのだが、しかしそのように捉えるだけでは何も変わらないだろう。双方の譲れない「価値観」が否応なしに正面衝突する状況で、一体何が「正解」となり得るだろうか?
そんな父親の希望はあったものの、とはいえ平穏に暮らしていた一家に変化が訪れたきっかけは、なんとハイダルに仕事が決まったこと だった。別に探していたわけではない 。友人に無理やり「劇場のダンサー」のオーディション に連れて行かれ、そのまま受かってしまった のだ。騙し討ちのようにステージに上げた友人にハイダルは怒り心頭だった のだが、しかし、ビバの登場によって気持ちが一気に変わる 。今回のオーディションは「ビバのバックダンサー」を探すものであり、ハイダルはビバに一目惚れした のだ。ビバはどうやらトランスジェンダーで、「身体は男、心は女性」のよう なのだが、見た目も女性以上に女性らしく、その容姿で周囲を圧倒する存在 である。
こうして、ビバに会いたいハイダルはダンサーとして働くことに決めた のだが、当然問題は山積み だ。そもそもだが、「劇場で働いている」というだけで外聞が悪い (らしい)。ハイダルは父親に「劇場の支配人」と嘘をついた のだが、それでも父親は家族に「近所には言うな」と厳命していた ぐらいだ。
しかしより問題だったのは、家事の負担がすべてヌチに降りかかってしまうこと である。4人の子育てと9人分の食事の用意を1人でこなすのはさすがに不可能だ 。
あわせて読みたい
【差別】才ある者の能力を正しく引き出す者こそ最も有能であり、偏見から能力を評価できない者は無能だ…
「偏見・差別ゆえに、他人の能力を活かせない人間」を、私は無能だと感じる。そういう人は、現代社会の中にも結構いるでしょう。ソ連との有人宇宙飛行競争中のNASAで働く黒人女性を描く映画『ドリーム』から、偏見・差別のない社会への道筋を考える
ではどうするか。ここで父親が「ムムターズが仕事を辞めるべき」だと決めてしまう 。仕事が生きがいのムムターズとしては非常に厳しい決断 だし、もちろんハイダルとしても妻をそんな辛い状況に追いやりたくはない 。しかしハイダルの中では、ビバに対する恋心がどうしても勝ってしまい ……。
「家父長制」と「宗教」が絡まり合った結果としての「家族のややこしさ」
本作の物語は、「ハイダルとビバの恋」を除けば、ほぼすべて家族内で展開される 。「ハイダルが働きに出る」という、父親にとっては非常に喜ばしい出来事がきっかけとなって、まるで玉突き事故のように状況が変転していく展開が実に面白かった 。
本作で浮き彫りにされる様々な「問題」は正直、父親がいなければ生まれなかった と言っていいだろう。そもそも、ハイダルの友人がどうして彼を無理やりオーディションに連れて行ったかといえば、「ハイダルの父親の希望(息子に仕事をしてほしい)を叶えようと思っている」から なのだ。ハイダルについて友人は、仲間内で「こいつは親父の許可がないと小便も出来ない」と口にするぐらいこの親子のことを知っており 、彼なりに「どうにかしてあげたい」という気持ちを持っていたのである。
あわせて読みたい
【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…
「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている
この友人がハイダルの父親のためを思って行動しなければ彼がビバに恋をすることもなかった し、当然、ムムターズが仕事を辞める必要もなかった のだ。言い方はキツいが、私としては「父親が諸悪の根源 」と言うほかない。そして、はっきりそういう主張が描かれるわけではないものの、本作は明らかに「こんな状況おかしいよね?」と訴えかける内容 になっていて、恐らくそのことが「上映禁止」の理由なのだと思う 。
私は世の中の様々な事柄に対して、普段から「『法を犯していない』限り、個人が何らかの形で制約されるべきではない」 と考えている。ただ、実際のところなかなかそうはいかない だろう。「日本の場合は『世間』だけが善悪の基準となる 」みたいな主張をする『理不尽な国ニッポン』という本を昔読んだことがあって凄く面白かったのだが、日本以外の多くの国でその基準は「宗教」であるはずだ 。そして恐らく、「家族のあり方」や「性自認」なども「宗教による制約」を受けるのだろうし、そのことが問題をより複雑にしている のだと思う。
あわせて読みたい
【称賛?】日本社会は終わっているのか?日本在住20年以上のフランス人が本国との比較で日本を評価:『…
日本に住んでいると、日本の社会や政治に不満を抱くことも多い。しかし、日本在住20年以上の『理不尽な国ニッポン』のフランス人著者は、フランスと比べて日本は上手くやっていると語る。宗教や個人ではなく、唯一「社会」だけが善悪を決められる日本の特異性について書く
さて、パキスタンはイスラム教の国 だそうである。この点に関しては、本作を観る少し前に「パキスタンは元々インドだった」という話を知って驚かされた 。確かNHKの番組を観たんだったと思う。元々はイギリスが「インド帝国」を支配していた のだが、「独立運動を弱体化させるため」みたいな名目で、「ヒンドゥー教のインド」と「イスラム教のパキスタン」に分離された のだそうだ。「インド・パキスタン国境では、毎夕『国境閉鎖の儀式』が行われている」という話題が番組で取り上げられていて、その中でそんな歴史がざっくりと紹介されていた のである。全然知らなかったので驚かされてしまった 。
そんなわけでパキスタンはイスラム教の国である。そしてイスラム教というと、国にもよるのだろうが、「女性の権利を軽視している」という印象がどうしても強い ので、それで、本作で描かれているような「家父長制」「女性に対する扱いの酷さ」に繋がっていく のだろう。個人的には本当に不愉快な世界 だなと思う。
「古い価値観」に根ざした問題には、我々日本人も共感できるはず
さて、タイトルの「ジョイランド」は「遊園地」を指す ようで、作中には遊園地のシーンもある 。ヌチと、家事に専念することになったムムターズが2人で遊園地に行こうと考える のだ。そしてそのためには義父の許可を得なければならない 。ただ本作においては、この状況が「家父長制」から来るものだと断言するのは若干の難しさがある 。というのも、義父は先述した通り車椅子での生活 であり、ヌチやムムターズじゃなくても、誰かが家にいて彼の世話をする必要がある からだ。
あわせて読みたい
【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断
映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく
この場面では、近所のオバサン(だと思う。関係性はよく分からなかった)に父親の世話など家のことを任せられたため、2人は遊園地に行くことが許された 。しかし、まさかここからあんな展開が待っているとは 誰も想像できなかったんじゃないかと思う。この展開もまた「『古い価値観』が残っているが故のややこしさ」という印象 で、本当に難しいなと感じた。
ただ、本作で描かれるような「家族・地域社会のややこしさ」は、現代の日本にも残っている はずだ。「はずだ」と書いたのは、私が東京で一人暮らしをしているため実感する機会がない からである。恐らく地方の方が、「古い家族観」や「地域社会の謎の習慣」などが支配的だったりする のではないかと思う。私は子どもの頃から「家族」とか「地域社会」みたいなものに対する苦手意識が強かったのでなるべく距離を置いていた し、だから今もあまり関わらずに済んでいる 。ただ、本作を観て「全然他人事じゃない」みたいに感じる人も結構いるんじゃないか と思う。
もちろん、個人の希望をすべて押し通していたら何も成立しなくなる し、だからある程度の「制約」は仕方ない と私も理解している。しかしそういう話は、本作で描かれる父親のスタンスとは関係な いだろう。「父親が最も偉い」なんて価値観に合理性などない からだ。ただ、それが「宗教」と結びついているが故にとてもややこしい 。恐らく、パキスタンの若者もそんな風に感じているのだろうし、「やってらんねー」みたいな気分でいるんじゃないか と思う。
あわせて読みたい
【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と
黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作
そして恐らく、そんな風に感じる若い世代が全世界的に多くなっている のだろう。だから本作は世界中で絶賛され、パキスタン映画として初めてカンヌ国際映画祭で上映されて受賞 を果たし、さらにパキスタン映画として初めて米アカデミー賞の長編映画賞の候補にもなった のだと思う。決して派手な物語ではない ものの、多くの人が持っている「個人的な悩み」に突き刺さったのだろう し、それは、現代日本を生きる私たちも大差ない はずである。
「第3の性」を表す「ヒジュラー」に対する驚き
さて、ビバがトランスジェンダーだという話には既に触れたが、パキスタンにはそもそも「ヒジュラー」という単語が存在する そうだ。これは、ビバについて話すヌチとムムターズの会話中に出てきたもの で、字幕上は「第3の性」という単語の上に小さく「ヒジュラー」と記されていた 。調べてみると「男性でも女性でもない性」を指す単語で、「両性具有者」みたいな意味になる らしい。
私は、この「ヒジュラー」という単語にとても驚かされてしまった 。というのも、「『男性でも女性でもない性』を表す単語が元々存在し、それが当たり前のように人々の間で使われている 」からだ。日本において同様の概念を表現するとしたら、「LGBTQ」や「トランスジェンダー」など、外国から入ってきた単語を使わざるを得ない だろう。もしかしたら、「男性でも女性でもない性」を表す日本古来の言葉も存在するのかもしれない が、しかしそうだとしても、その単語を知っている人も使っている人も今はほとんどいない はずだ。
あわせて読みたい
【家族】ゲイの男性が、拘置所を出所した20歳の男性と養子縁組し親子関係になるドキュメンタリー:映画…
「ゲイの男性が、拘置所から出所した20歳の男性と養子縁組し、親子関係になる」という現実を起点にしたドキュメンタリー映画『二十歳の息子』は、奇妙だが実に興味深い作品だ。しばらく何が描かれているのか分からない展開や、「ゲイであること」に焦点が当たらない構成など、随所で「不協和音」が鳴り響く1作
しかしパキスタンでは、ビバがトランスジェンダーだと判明するや、すぐに「ヒジュラー」という単語が出てくる 。それぐらい、当たり前の概念として認識されている ということだろう。本作を観ているだけでは正直、「ヒジュラー」が社会的にどんな風に扱われているのかちゃんとは分からなかった のだが、いずれにせよ「古くから概念として存在し、それが今でも使われている」という事実とにまずは驚かされてしまった のだ。
そしてもう1つ気になったこと がある。作中には、「ヒジュラー」に対する世間の反応がはっきり描かれる場面が一度だけある のだが、私にはそのシーンが上手く理解できなかった 。それはビバが電車に乗っている時のことで、隣に座っていた女性から、「ここは女性専用車両だから移って」と指摘されるという場面 だ。
で、私が理解できなかったのは、「どうしてビバが『女性ではない』と判断されたのか? 」である。ビバは見た目は完全に女性で、喋っていても男性だとは分からない 。だから、外見だけから「ヒジュラー」だけは判断出来ないよう に思う。にも拘らず、恐らく知り合いでも何でもないはずの女性が、ただ黙って座っていただけのビバを見て「男性だ」と判断する のである。どうしてそんな判断が出来たのか、私にはまったく理解できなかった。
あわせて読みたい
【感想】映画『窮鼠はチーズの夢を見る』を異性愛者の男性(私)はこう観た。原作も読んだ上での考察
私は「腐男子」というわけでは決してないのですが、周りにいる腐女子の方に教えを請いながら、多少BL作品に触れたことがあります。その中でもダントツに素晴らしかったのが、水城せとな『窮鼠はチーズの夢を見る』です。その映画と原作の感想、そして私なりの考察について書いていきます
もちろん、「ビバが有名人だから」と考えるのが最も理解しやすい だろう。お客を集めることが求められるダンサー であり、であればSNSもやっているはず だし、その中で「自分はヒジュラーだ」と言っていたりするのかもしれない。しかし本作での描かれ方的には、ビバが「電車に乗り合わせた人に一発で気づかれる」ほど有名な人には思えなかった 。だから、どういう理屈で「ヒジュラー」だと判断されたのか 、個人的にはとても気になる。
そしてそのような点も含めての話だが、パキスタン人ではない私には「『ヒジュラー』をどのような存在捉えるべきなのか」という認識が難しかった なと思う。ネットで調べた感じだと、「ヒジュラー=トランスジェンダー」というわけではなさそう なのだが、それ以上のことはよく分からなかった。もしかしたら、イスラム教という宗教的な観点からも何か特別な存在として扱われているのかもしれない し(ある種の「異端的存在」が宗教において特別な意味を持つことはあるように思う)、そういう「パキスタンにおける『ヒジュラー』の立ち位置」は、もう少し理解できたら(知った上で観れたら)良かった なと思う。
また、「『ヒジュラー』という単語はヌチとムムターズの会話の中で出てくる」というのは先述した通りだが、観客視点で言えば、「ビバがヒジュラーである」という事実をこの時初めて知ることになる 。だから、「『ビバはヒジュラーである』とハイダルがいつ知ったのか 」や「その事実を知ったハイダルが何か葛藤を抱いたのか 」みたいなことは全然分からないまま物語が進んでいく のだ。
あわせて読みたい
【肯定】価値観の違いは受け入れられなくていい。「普通」に馴染めないからこそ見える世界:『君はレフ…
子どもの頃、周りと馴染めない感覚がとても強くて苦労しました。ただし、「普通」から意識的に外れる決断をしたことで、自分が持っている価値観を言葉で下支えすることができたとも感じています。「普通」に馴染めず、自分がダメだと感じてしまう人へ。
こういう、「外国人であるが故に捉えきれないニュアンス」が、本作の理解を少し遠ざけていた ような感触はある。その点は少し残念 だった。ただこの事実は裏を返せば、「まさか世界中で観られる話題作になるなんて思っていなかった」みたいに捉えることも可能 だろう。制作側も予想していなかった高評価だったのかもしれない。
監督:サーイム・サーディク, クリエイター:オールキャップス, クリエイター:クーサットフィルムズ, プロデュース:アポールヴァ・チャラン, プロデュース:サルマド・クーサット, プロデュース:ローレン・マン, Writer:サーイム・サーディク, 出演:アリ・ジュネージョー, 出演:ラスティ・ファルーク, 出演:アリーナ・ハーン, 出演:サルワット・ギラーニ, 出演:ソハイル・サミール, 出演:サルマーン・ピアザダ, 出演:サニア・サイード
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
私は本当に「宗教」というものを全般的に毛嫌いしている ので、「宗教によって何らかの『制約』が生まれる状況」は耐え難い 。「信仰」というのはそもそもそういう性質を持つものなのかもしれないが、私は生涯、そんな状況を許容できない だろう。
長く続いてきた「宗教」の影響を排除することはとても難しい だろうが、新しい価値観に様々な形で触れている若い世代が、そういう困難さを吹き飛ばしてくれるんじゃないか とも思っている。「宗教だから」なんて理由で、個人の主義主張や権利が制約される世の中は間違っている と私は断言したい。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【生きる】映画『それでも私は』は、オウム真理教・麻原彰晃の三女・松本麗華の現在を追う衝撃作
映画『それでも私は Though I’m His Daughter』は、オウム真理教の教祖・麻原彰晃の三女である松本麗華に密着したドキュメンタリー映画だ。彼女は「父親が松本智津夫である」というだけの理由で排除され、そればかりか国家からも虐げられている。あまりにも酷すぎる現実だ。加害者家族が苦しむ社会は間違っていると私は思う
あわせて読みたい
【不寛容】カルトと呼ばれた「イエスの方舟」の現在は?「理解できなければ排除する社会」を斬る映画:…
映画『方舟にのって』は、1980年に社会を騒がせ、「ハーレム教団」「セックスカルト教団」と呼ばれて大問題となった「イエスの方舟」の現在を追うドキュメンタリー映画だ。そして、そんな本作が本当に映し出してるのは「大衆」の方である。「『理解できないもの』は排除する」という社会に対する違和感を改めて浮き彫りにする1作
あわせて読みたい
【狂気】映画『ミッシング』(吉田恵輔監督)は「我が子の失踪」を起点に様々な「嫌な世界」を描く(主…
映画『ミッシング』は、「娘の失踪を機に壊れてしまった母親」を石原さとみが熱演する絶望的な物語である。事件を取材する地元局の記者の葛藤を通じて「『事実』とは何か」「『事実を報じる』ことの難しさ」が突きつけられ、さらに、マスコミを頼るしかない母親の苦悩と相まって状況が混沌とする。ホントに「嫌な世界」だなと思う
あわせて読みたい
【悲劇】東京大空襲経験者の体験談。壊滅した浅草、隅田川の遺体、その後の人々の暮らし等の証言集:映…
映画『東京大空襲 CARPET BOMBING of Tokyo』は、2時間半で10万人の命が奪われたという「東京大空襲」を始め、「山手空襲」「八王子空襲」などを実際に経験した者たちの証言が収録された作品だ。そのあまりに悲惨な実態と、その記憶を具体的にはっきりと語る証言者の姿、そのどちらにも驚かされてしまった
あわせて読みたい
【人権】フランスの民主主義は死んではいないか?映画『暴力をめぐる対話』が問う「権力の行使」の是非
映画『暴力をめぐる対話』は、「『黄色いベスト運動』のデモの映像を観ながら『警察による暴力』について討論を行う者たちを映し出す映画」である。「デモの映像」と「討論の様子」だけというシンプル過ぎる作品で、その上内容はかなり高度でついていくのが難しいのだが、「民主主義とは何か?」について考えさせる、実に有意義なやり取りだなと思う
あわせて読みたい
【人生】映画『雪子 a.k.a.』は、言葉は出ないが嘘もないラップ好きの小学校教師の悩みや葛藤を描き出す
「小学校教師」と「ラップ」というなかなか異色の組み合わせの映画『雪子 a.k.a.』は、「ここが凄く良かった」と言えるようなはっきりしたポイントはないのに、ちょっと泣いてしまうぐらい良い映画だった。「口下手だけど嘘はない」という主人公・雪子の日常的な葛藤には、多くの人が共感させられるのではないかと思う
あわせて読みたい
【実話】映画『あんのこと』(入江悠)は、最低の母親に人生を壊された少女の更生と絶望を描く(主演:…
映画『あんのこと』では、クソみたいな母親の元でクソみたいな人生を歩まされた主人公・杏の絶望を河合優実が絶妙に演じている。色んな意味で実に胸糞悪い作品で、こんな社会の歪さがどうしてずっとずっと放置され続けるのか理解できないなと思う。また、河合優実だけではなく、佐藤二朗の演技にも圧倒させられてしまった
あわせて読みたい
【包容】映画『違国日記』を観て思う。「他者との接し方」が皆こうだったらもっと平和なはずだって(主…
映画『違国日記』は、人見知りの小説家・高代槙生が両親を亡くした姪・朝を引き取り一緒に暮らすところから始まる物語で、槙生と朝を中心とした様々な人間関係が絶妙に描かれている作品でした。人付き合いが苦手ながら、15歳という繊細な存在を壊さないように、でも腫れ物みたいには扱わないように慎重になる槙生のスタンスが素敵です
あわせて読みたい
【拒絶】映画『ブルータリスト』は、ホロコーストを生き延びた建築家の数奇な人生を描く壮大な物語(監…
映画『ブルータリスト』は、ホロコーストを生き延びたユダヤ人建築家の、アメリカに移り住んで以降の人生を丁寧に追いながら、「ユダヤ人を受け入れないアメリカ」を静かに描き出す物語である。離れ離れにならざるを得なかった妻とのすれ違いにも焦点を当てつつ、時代に翻弄された者たちの悲哀が浮き彫りにされていく
あわせて読みたい
【友情】映画『ノー・アザー・ランド』が映し出す酷すぎる現実。イスラエル軍が住居を壊す様は衝撃だ
イスラエルのヨルダン川西岸地区内の集落マサーフェル・ヤッタを舞台にしたドキュメンタリー映画『ノー・アザー・ランド』では、「昔からその場所に住み続けているパレスチナ人の住居をイスラエル軍が強制的に破壊する」という信じがたい暴挙が映し出される。そんな酷い現状に、立場を越えた友情で立ち向かう様を捉えた作品だ
あわせて読みたい
【尊厳】映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、安楽死をテーマに興味深い問いを突きつける(監督:ペ…
全然期待せずに観た映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、思いがけず面白い作品だった。「安楽死」をテーマにした、ティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーアのほぼ2人芝居といったシンプルな作品だが、そこに通底する「死生観」や、「死生観」の違いによるすれ違いなどが実に見事に描かれていて、強く惹きつけられた
あわせて読みたい
【異常】オンラインゲーム『DayZ』内でドキュメンタリー映画を撮るという狂気的な実験が映す人間模様:…
映画『ニッツ・アイランド』は、「『DayZ(デイジー)』というサバイバル・ゲーム内で撮られたドキュメンタリー映画」という斬新すぎる作品だ。「生き物を殺さない集団」「人殺しを楽しんで行う集団」など、ゲーム内の様々なプレイヤーから話を聞きつつ、「ゲーム内の世界は『リアル』なのか?」という問いにも焦点が当てられる
あわせて読みたい
【異様】映画『聖なるイチジクの種』は、イランで起こった実際の市民デモを背景にした驚愕の物語である
「家庭内で銃を紛失した」という設定しか知らずに観に行った映画『聖なるイチジクの種』は、「実際に起こった市民デモをベースに、イランという国家の狂気をあぶり出す作品」であり、思いがけず惹きつけられてしまった。「反政府的な作品」に関わった本作監督・役者・スタッフらが処罰されるなど、人生を賭けて生み出された映画でもある
あわせて読みたい
【感動】映画『ぼくとパパ、約束の週末』は「自閉症への理解が深まる」という点で実に興味深かった
映画『ぼくとパパ、約束の週末』は「心温まる物語」であり、一般的にはそういう作品として評価されているはずだが、個人的には「『自閉症』への解像度が高まる」という意味でも興味深かった。「ルールは厳密に守るが、ルール同士が矛盾していて袋小路に陥ってしまう」という困難さが実に分かりやすく描かれている
あわせて読みたい
【捏造】袴田事件はついに再審での無罪が決定!冤罪の元死刑囚・袴田巌の現在と姉・秀子の奮闘:映画『…
映画『拳と祈り』は、2024年に再審無罪が確定した「袴田事件」の元死刑囚・袴田巌と、そんな弟を献身的にサポートする姉・秀子の日常を中心に、事件や裁判の凄まじい遍歴を追うドキュメンタリーである。日本の司法史上恐らく初めてだろう「前代未聞の状況」にマスコミで唯一関わることになった監督が使命感を持って追い続けた姉弟の記録
あわせて読みたい
【日常】映画『大きな家』(竹林亮)は、児童養護施設で「家族」と「血縁」の違いや難しさに直面する
児童養護施設に長期密着した映画『大きな家』は、映画『14歳の栞』で中学2年生をフラットに撮り切った竹林亮が監督を務めたドキュメンタリーである。子どもたちの過去に焦点を当てるのではなく、「児童養護施設の日常風景」として彼らを捉えるスタンスで、その上でさらに「家族のあり方」に対する子どもたちの認識が掘り下げられる
あわせて読みたい
【絶望】満員続出の映画『どうすればよかったか?』が描き出す、娘の統合失調症を認めない両親の不条理
たった4館から100館以上にまで上映館が拡大した話題の映画『どうすればよかったか?』を公開2日目に観に行った私は、「ドキュメンタリー映画がどうしてこれほど注目されているのだろうか?」と不思議に感じた。統合失調症を発症した姉を中心に家族を切り取る本作は、観る者に「自分だったらどうするか?」という問いを突きつける
あわせて読みたい
【異様】映画『大いなる不在』(近浦啓)は、認知症の父を中心に「記憶」と「存在」の複雑さを描く(主…
「父親が逮捕され、どうやら認知症のようだ」という一報を受けた息子が、30年間ほぼやり取りのなかった父親と再会するところから始まる映画『大いなる不在』は、なんとも言えない「不穏さ」に満ちた物語だった。「記憶」と「存在」のややこしさを問う本作は、「物語」としては成立していないが、圧倒的な“リアリティ”に満ちている
あわせて読みたい
【記憶】映画『退屈な日々にさようならを』は「今泉力哉っぽさ」とは異なる魅力に溢れた初期作品だ(主…
今泉力哉作品のオールナイト上映に初めて参加し、『退屈な日々にさようならを』『街の上で』『サッドティー』を観ました。本作『退屈な日々にさようならを』は、時系列が複雑に入れ替わった群像劇で、私が思う「今泉力哉っぽさ」は薄い作品でしたが、構成も展開も会話も絶妙で、さすが今泉力哉という感じです
あわせて読みたい
【真相?】映画『マミー』が描く和歌山毒物カレー事件・林眞須美の冤罪の可能性。超面白い!
世間を大騒ぎさせた「和歌山毒物カレー事件」の犯人とされた林眞須美死刑囚は無実かもしれない。映画『マミー』は、そんな可能性を示唆する作品だ。「目撃証言」と「ヒ素の鑑定」が詳細に検証し直され、さらに「保険金詐欺をやっていた」という夫の証言も相まって、証拠的にも感情的にも支持したくなるような驚きの仮説である
あわせて読みたい
【感想】映画『夜明けのすべて』は、「ままならなさ」を抱えて生きるすべての人に優しく寄り添う(監督…
映画『夜明けのすべて』は、「PMS」や「パニック障害」を通じて、「自分のものなのに、心・身体が思い通りにならない」という「ままならなさ」を描き出していく。決して他人事ではないし、「私たちもいつそのような状況に置かれるか分からない」という気持ちで観るのがいいでしょう。物語の起伏がないのに惹きつけられる素敵な作品です
あわせて読みたい
【狂気】押見修造デザインの「ちーちゃん」(映画『毒娘』)は「『正しさ』によって歪む何か」の象徴だ…
映画『毒娘』は、押見修造デザインの「ちーちゃん」の存在感が圧倒的であることは確かなのだが、しかし観ていくと、「決して『ちーちゃん』がメインなわけではない」ということに気づくだろう。本作は、全体として「『正しさ』によって歪む何か」を描き出そうとする物語であり、私たちが生きる社会のリアルを抉り出す作品である
あわせて読みたい
【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…
映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です
あわせて読みたい
【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…
映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う
あわせて読みたい
【狂気】異質なホラー映画『みなに幸あれ』(古川琴音主演)は古い因習に似せた「社会の異様さ」を描く
古川琴音主演映画『みなに幸あれ』は、”シュールさ”さえ感じさせる「異質なホラー映画」だ。「村の因習」というよくあるパターンをベースに据えつつ、そこで展開される異様な状況が、実は「私たちが生きる世界」に対応しているという構成になっている。「お前の物語だからな」と終始突きつけられ続ける作品だ
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
あわせて読みたい
【家族】映画『女優は泣かない』は、蓮佛美沙子が「再起を賭ける女優」を演じる笑い泣き満載の作品(出…
蓮佛美沙子が、スキャンダルで落ちぶれ再起を賭ける女優を演じる映画『女優は泣かない』は、ミニマムかつシンプルな構成ながら、笑いあり涙ありのハートフルコメディだった。「やりたくはないが、やらねばならぬ」とお互いが感じているドキュメンタリー撮影を軸に、家族の物語を織り込む展開が素敵
あわせて読みたい
【闘争】映画『あのこと』が描く、中絶が禁止だった時代と、望まぬ妊娠における圧倒的な「男の不在」
中絶が禁止されていた1960年代のフランスを舞台にした映画『あのこと』は、「望まぬ妊娠」をしてしまった秀才の大学生が、「未来を諦めない」ために中絶を目指す姿が描かれる。さらに、誰にも言えずに孤独に奮闘する彼女の姿が「男の不在」を強調する物語でもあり、まさに男が観るべき作品だ
あわせて読みたい
【助けて】映画『生きててごめんなさい』は、「共依存カップル」視点で生きづらい世の中を抉る物語(主…
映画『生きててごめんなさい』は、「ちょっと歪な共依存関係」を描きながら、ある種現代的な「生きづらさ」を抉り出す作品。出版社の編集部で働きながら小説の新人賞を目指す園田修一は何故、バイトを9度もクビになり、一日中ベッドの上で何もせずに過ごす同棲相手・清川莉奈を”必要とする”のか?
あわせて読みたい
【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!
かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ
あわせて読みたい
【感想】是枝裕和監督映画『怪物』(坂元裕二脚本)が抉る、「『何もしないこと』が生む加害性」
坂元裕二脚本、是枝裕和監督の映画『怪物』は、3つの視点を通して描かれる「日常の何気ない光景」に、思いがけない「加害性」が潜んでいることを炙り出す物語だ。これは間違いなく、私たち自身に関わる話であり、むしろ「自分には関係ない」と考えている人こそが自覚すべき問題だと思う
あわせて読みたい
【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に
「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた
あわせて読みたい
【感想】映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)の稲垣吾郎の役に超共感。「好きとは何か」が分からない人へ
映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)は、稲垣吾郎演じる主人公・市川茂巳が素晴らしかった。一般的には、彼の葛藤はまったく共感されないし、私もそのことは理解している。ただ私は、とにかく市川茂巳にもの凄く共感してしまった。「誰かを好きになること」に迷うすべての人に観てほしい
あわせて読みたい
【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…
遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている
あわせて読みたい
【悲劇】アメリカの暗黒の歴史である奴隷制度の現実を、元奴隷の黒人女性自ら赤裸々に語る衝撃:『ある…
生まれながらに「奴隷」だった黒人女性が、多くの人の協力を得て自由を手にし、後に「奴隷制度」について書いたのが『ある奴隷少女に起こった出来事』。長らく「白人が書いた小説」と思われていたが、事実だと証明され、欧米で大ベストセラーとなった古典作品が示す「奴隷制度の残酷さ」
あわせて読みたい
【感想】殺人事件が決定打となった「GUCCI家の崩壊」の実話を描く映画『ハウス・オブ・グッチ』の衝撃
GUCCI創業家一族の1人が射殺された衝撃の実話を基にした映画『ハウス・オブ・グッチ』。既に創業家一族は誰一人関わっていないという世界的ブランドGUCCIに一体何が起こったのか? アダム・ドライバー、レディー・ガガの演技も見事なリドリー・スコット監督作
あわせて読みたい
【愛】ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の“衝撃の出世作”である映画『灼熱の魂』の凄さ。何も語りたくない
映画館で流れた予告映像だけで観ることを決め、他になんの情報も知らないまま鑑賞した映画『灼熱の魂』は、とんでもない映画だった。『DUNE/デューン 砂の惑星』『ブレードランナー 2049』など有名作を監督してきたドゥニ・ヴィルヌーヴの衝撃の出世作については、何も語りたくない
あわせて読みたい
【衝撃】卯月妙子『人間仮免中』、とんでもないコミックエッセイだわ。統合失調症との壮絶な闘いの日々
小学5年生から統合失調症を患い、社会の中でもがき苦しみながら生きる卯月妙子のコミックエッセイ『人間仮免中』はとんでもない衝撃作。周りにいる人とのぶっ飛んだ人間関係や、歩道橋から飛び降り自殺未遂を図り顔面がぐちゃぐちゃになって以降の壮絶な日々も赤裸々に描く
あわせて読みたい
【抵抗】西加奈子のおすすめ小説『円卓』。「当たり前」と折り合いをつけられない生きづらさに超共感
小学3年生のこっこは、「孤独」と「人と違うこと」を愛するちょっと変わった女の子。三つ子の美人な姉を「平凡」と呼んで馬鹿にし、「眼帯」や「クラス会の途中、不整脈で倒れること」に憧れる。西加奈子『円卓』は、そんなこっこの振る舞いを通して「当たり前」について考えさせる
あわせて読みたい
【葛藤】正論を振りかざしても、「正しさとは何か」に辿り着けない。「絶対的な正しさ」など存在しない…
「『正しさ』は人によって違う」というのは、私には「当たり前の考え」に感じられるが、この前提さえ共有できない社会に私たちは生きている。映画『由宇子の天秤』は、「誤りが含まれるならすべて間違い」という判断が当たり前になされる社会の「不寛容さ」を切り取っていく
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ
私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。
あわせて読みたい
【感想】映画『竜とそばかすの姫』が描く「あまりに批判が容易な世界」と「誰かを助けることの難しさ」
SNSの登場によって「批判が容易な社会」になったことで、批判を恐れてポジティブな言葉を口にしにくくなってしまった。そんな世の中で私は、「理想論だ」と言われても「誰かを助けたい」と発信する側の人間でいたいと、『竜とそばかすの姫』を観て改めて感じさせられた
あわせて読みたい
【中絶】望まない妊娠をした若い女性が直面する現実をリアルに描く映画。誰もが現状を知るべきだ:『17…
他の様々な要素を一切排し、「望まぬ妊娠をした少女が中絶をする」というただ1点のみに全振りした映画『17歳の瞳に映る世界』は、説明もセリフも極端に削ぎ落としたチャレンジングな作品だ。主人公2人の沈黙が、彼女たちの置かれた現実を雄弁に物語っていく。
あわせて読みたい
【生きる】しんどい人生を宿命付けられた子どもはどう生きるべき?格差社会・いじめ・恋愛を詰め込んだ…
厳しい受験戦争、壮絶な格差社会、残忍ないじめ……中国の社会問題をこれでもかと詰め込み、重苦しさもありながら「ボーイ・ミーツ・ガール」の爽やかさも融合されている映画『少年の君』。辛い境遇の中で、「すべてが最悪な選択肢」と向き合う少年少女の姿に心打たれる
あわせて読みたい
【認識】「固定観念」「思い込み」の外側に出るのは難しい。自分はどんな「へや」に囚われているのか:…
実際に起こった衝撃的な事件に着想を得て作られた映画『ルーム』は、フィクションだが、観客に「あなたも同じ状況にいるのではないか?」と突きつける力強さを持っている。「普通」「当たり前」という感覚に囚われて苦しむすべての人に、「何に気づけばいいか」を気づかせてくれる作品
あわせて読みたい
【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事
「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である
あわせて読みたい
【家族】映画『そして父になる』が問う「子どもの親である」、そして「親の子どもである」の意味とは?
「血の繋がり」だけが家族なのか?「将来の幸せ」を与えることが子育てなのか?実際に起こった「赤ちゃんの取り違え事件」に着想を得て、苦悩する家族を是枝裕和が描く映画『そして父になる』から、「家族とは何か?」「子育てや幸せとどう向き合うべきか?」を考える
あわせて読みたい
【感想】映画『若おかみは小学生!』は「子どもの感情」を「大人の世界」で素直に出す構成に号泣させられる
ネット記事を読まなければ絶対に観なかっただろう映画『若おかみは小学生!』は、基本的に子ども向け作品だと思うが、大人が観てもハマる。「大人の世界」でストレートに感情を表に出す主人公の小学生の振る舞いと成長に、否応なしに感動させられる
あわせて読みたい
【葛藤】子どもが抱く「家族を捨てたい気持ち」は、母親の「家族を守りたい気持ち」の終着点かもしれな…
家族のややこしさは、家族の数だけ存在する。そのややこしさを、「子どもを守るために母親が父親を殺す」という極限状況を設定することで包括的に描き出そうとする映画『ひとよ』。「暴力」と「殺人犯の子どもというレッテル」のどちらの方が耐え難いと感じるだろうか?
あわせて読みたい
【レッテル】コミュニケーションで大事なのは、肩書や立場を外して、相手を”その人”として見ることだ:…
私は、それがポジティブなものであれ、「レッテル」で見られることは嫌いです。主人公の1人、障害を持つ大富豪もまたそんなタイプ。傍若無人な元犯罪者デルとの出会いでフィリップが変わっていく『THE UPSIDE 最強のふたり』からコミュニケーションを学ぶ
あわせて読みたい
【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…
「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟
あわせて読みたい
【実話】「家族とうまくいかない現実」に正解はあるか?選択肢が無いと感じる時、何を”選ぶ”べきか?:…
「自分の子どもなんだから、どんな風に育てたって勝手でしょ」という親の意見が正しいはずはないが、この言葉に反論することは難しい。虐待しようが生活能力が無かろうが、親は親だからだ。映画『MOTHER マザー』から、不正解しかない人生を考える
あわせて読みたい
【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…
「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
あわせて読みたい
【葛藤】「多様性を受け入れること」は難しい。映画『アイヌモシリ』で知る、アイデンティティの実際
「アイヌの町」として知られるアイヌコタンの住人は、「アイヌ語を勉強している」という。観光客のイメージに合わせるためだ。映画『アイヌモシリ』から、「伝統」や「文化」の継承者として生きるべきか、自らのアイデンティティを意識せず生きるべきかの葛藤を知る
あわせて読みたい
【排除】「分かり合えない相手」だけが「間違い」か?想像力の欠如が生む「無理解」と「対立」:映画『…
「共感」が強すぎる世の中では、自然と「想像力」が失われてしまう。そうならないようにと意識して踏ん張らなければ、他人の価値観を正しく認めることができない人間になってしまうだろう。映画『ミセス・ノイズィ』から、多様な価値観を排除しない生き方を考える
あわせて読みたい
【救い】耐えられない辛さの中でどう生きるか。短歌で弱者の味方を志すホームレス少女の生き様:『セー…
死にゆく母を眺め、施設で暴力を振るわれ、拾った新聞で文字を覚えたという壮絶な過去を持つ鳥居。『セーラー服の歌人 鳥居』は、そんな辛い境遇を背景に、辛さに震えているだろう誰かを救うために短歌を生み出し続ける生き方を描き出す。凄い人がいるものだ
あわせて読みたい
【挑戦】自閉症のイメージを変えるおすすめ本。知的障害と”思い込む”専門家に挑む母子の闘い:『自閉症…
専門家の思い込みを覆し、自閉症のイメージを激変させた少年・イド。知的障害だと思われていた少年は、母親を通じコミュニケーションが取れるようになり、その知性を証明した。『自閉症の僕が「ありがとう」を言えるまで』が突きつける驚きの真実
あわせて読みたい
【異端】子育ては「期待しない」「普通から外れさせる」が大事。”劇薬”のような父親の教育論:『オーマ…
どんな親でも、子どもを幸せにしてあげたい、と考えるでしょう。しかしそのために、過保護になりすぎてしまっている、ということもあるかもしれません。『オーマイ・ゴッドファーザー』をベースに、子どもを豊かに、力強く生きさせるための”劇薬”を学ぶ
あわせて読みたい
【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…
好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性
あわせて読みたい
【諦め】母親の存在にモヤモヤを抱えた人生から、「生きてさえいればいい」への違和感を考える:『晴天…
生まれ育つ環境を選ぶことはできません。そして、家族との関わりや家庭環境は、その後の人生に大きな影響を及ぼします。努力するスタートラインにも立てないと感じる時、それでも前進することを諦めてはいけないのかを、『晴天の迷いクジラ』をベースに書く
あわせて読みたい
【覚悟】人生しんどい。その場の”空気”から敢えて外れる3人の中学生の処世術から生き方を学ぶ:『私を知…
空気を読んで摩擦を減らす方が、集団の中では大体穏やかにいられます。この記事では、様々な理由からそんな選択をしない/できない、『私を知らないで』に登場する中学生の生き方から、厳しい現実といかにして向き合うかというスタンスを学びます
あわせて読みたい
【呪縛】「良い子」に囚われ人生苦しい。どう見られるかを抜け出し、なりたい自分を生きるために:『わ…
「良い子でいなきゃいけない」と感じ、本来の自分を押し隠したまま生きているという方、いるんじゃないかと思います。私も昔はそうでした。「良い子」の呪縛から逃れることは難しいですが、「なりたい自分」をどう生きればいいかを、『わたしを見つけて』をベースに書いていきます
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
ジェンダー・LGBT【本・映画の感想】 | ルシルナ
私はLGBTではありません。また、ジェンダーギャップは女性が辛さを感じることの方が多いでしょうが、私は男性です。なので、私自身がジェンダーやLGBTの問題を実感すること…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…









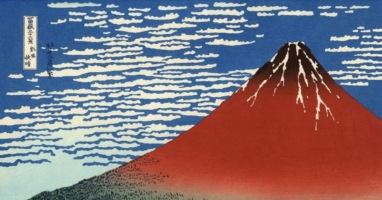

















































































コメント