目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:ユヴァル・ノア・ハラリ, 翻訳:柴田裕之
¥3,960 (2022/02/15 20:55時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 他にも様々な人類種が存在していたにも拘わらず、最終的に「サピエンス」だけが残ったのは何故か?
- 「農業」によって「未来への不安」を抱くようになった理由とは?
- 「我々は無知である」という視点の転換こそが「科学革命」の真髄
大ベストセラーになるのも納得の、圧倒的な壮大さであらゆる「知」を描き出す傑作
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
世界的大ベストセラーになるのも当然だ。『サピエンス全史』は人類史を俯瞰で捉える「知の宝庫」
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
言わずと知れた大ベストセラーであり、私が紹介する必要性などまったくないが、本作のガイドとなるような文章を書くことはできるだろうと思っている。この記事では、本書全体の大きな流れを概説していくつもりだ。
「『サピエンス』だけがなぜ我々のようになっていったのか?」が、本書の中心となる謎だ
さて、人類誕生の歴史にあまり詳しくない場合、そもそもこの「『サピエンス』だけがなぜ我々のようになっていったのか?」という問いの意味を上手く理解できないと思う。まずはその辺りの説明から進めていこう。
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ

私たち人間は、「ホモ属」と呼ばれる分類に属する生物だ。「属」というのは生物の分類の仕方で、「科」の下にある。例えば、「イヌ科」の中に「イヌ属・ホッキョクギツネ属・タヌキ属」などが、「オナガザル科」の中に「ヒヒ属・マンドリル属・オナガザル属」などがあるという具合だ。人間の場合は、「ホモ科ホモ属」となる。
普通は、「◯科◯属」の中にもさらに様々な種類がいる。例えば「イヌ科イヌ属」の中に、「秋田犬・シベリアンハスキー・ダックスフンド」など、見た目や能力の異なる様々な種類が存在するというわけだ。
あわせて読みたい
【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…
タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。
では「ホモ科ホモ属」はどうだろうか? 何故かこの「ホモ科ホモ属」には現在、我々「ホモ・サピエンス(賢いヒト)」しかいない(本書ではこの「ホモ・サピエンス」のことを「サピエンス」と表記する)。これが主たる謎なのだ。
かつては「ホモ科ホモ属」にも、様々な種類がいた。歴史の授業で習うだろうか、ネアンデルタール人やアウストラロピテクスなどだ。サピエンスが、そのような他の種類の「ホモ属」と同時期に共存していた時代もある。秋田犬がポメラニアンとすれ違うように、我々の先祖サピエンスが歩いていたらアウストラロピテクスを見かける、なんてことがあり得たわけだ。
しかし現在その可能性はない。「ホモ科ホモ属」には我々サピエンスしか存在しないからだ。これは、世界中すべての犬がゴールデンレトリバーであるような状況と言える。
あわせて読みたい
【化石】聞き馴染みのない「分子生物学」を通じて、科学という学問の本質を更科功が分かりやすく伝える…
映画『ジュラシック・パーク』を観たことがある方なら、「コハクの化石に閉じ込められた蚊の血液から恐竜の遺伝子を取り出す」という設定にワクワクしたことだろう。『化石の分子生物学』とは、まさにそのような研究を指す。科学以外の分野にも威力を発揮する知見に溢れた1冊
こう説明されると、なかなか異常な事態だと感じるだろう。まさに「ホモ科ホモ属」では、そのような不可思議な状況にあるのだ。
本書ではこの疑問、つまり「なぜ『ホモ科ホモ属』の中で『サピエンス』だけが生き残ったのか」、さらに、「なぜ『サピエンス』は高度な文明を築き、我々のようになっていったのか」を中心軸にしながら、「サピエンスの歴史」を紐解いていく作品なのである。
サピエンスが獲得した「言語」の凄さと「認知革命」
ここからは、「ホモ科ホモ属」のことを「人類」と表記することにする。
あわせて読みたい
【意外】自己免疫疾患の原因は”清潔さ”?腸内フローラの多様性の欠如があらゆる病気を引き起こす:『寄…
人類は、コレラの蔓延を機に公衆衛生に力を入れ、寄生虫を排除した。しかし、感染症が減るにつれ、免疫関連疾患が増大していく。『寄生虫なき病』では、腸内細菌の多様性が失われたことが様々な疾患の原因になっていると指摘、「現代病」の蔓延に警鐘を鳴らす
人類は他の生物と比べて脳が大きく発達し、またある時点から火を扱えるようにもなった。他の生物にはない、かなり特異な特徴と言えるだろう。しかし、
火の恩恵にあずかってはいたものの、十五万年前の人類は、依然として取るに足らない生き物だった。
そうである。地球全体で見ても、人類は特別存在感を示すような生物ではなかった、ということだろう。
その後、人類は「言語」を獲得する。サピエンス以外の人類が、我々がイメージするような「言語」を有していたのかについては議論があるようだが、とりあえず何らかの形で人類全体が言語を獲得したのだとしよう。
あわせて読みたい
【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…
小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る
そう考えても今後の議論に支障は出ない。何故なら、ある種の言語は人類以外の生物も使っているからだ。声や何らかの音によってコミュニケーションを取る生物は様々に知られており、それらを一種の「言語」とみなすことができる。

さてここで重要なのは、「サピエンス以外の人類を含め、他の生物が獲得した『言語』と、サピエンスが獲得した『言語』は何が違うのか?」という問いだ。その凄さを著者は、「架空のことについて話せる力」だと指摘する。
とはいえ、私たちの言語が持つ真に比類ない特徴は、人間やライオンについての情報を伝達する能力ではない。むしろそれは、まったく存在しないものについての情報を伝達する能力だ。見たことも、触れたことも、匂いを嗅いだこともない、ありとあらゆる種類の存在について話す能力があるのは、私たちの知る限りではサピエンスだけだ。
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
そして、「言語獲得によって架空のことについて話せる力を得たこと」によって、サピエンスにとっての第1の革命である「認知革命」がもたらされることになった。
この「認知革命」が生んだものこそ「神話」である。本書における「神話」は、「大多数と共有している想像上の存在」を指す。「神話」と聞くと、「ギリシャ神話」「北欧神話」「古事記」など具体的な何かを連想するかもしれないが、本書ではより広い概念として登場する。
もう少し詳しく説明しよう。
例えば「リンゴ」は、サピエンスが地球上からいなくなってもそこにあり続けるだろう。では、「日本という国」はどうだろうか。確かにサピエンスがいなくなっても「島」は残る。しかし「そこが『日本という国』である」という事実は、サピエンスが消えた時点で失われてしまうだろう。もう少し具体的なモノでイメージしたければ「お金」はどうだろう。確かに「硬貨」や「紙幣」というモノは残る。しかしサピエンスがいなくなれば、そこに「お金」という価値を見出す生物は地球上に存在しなくなるだろう。
このように、「サピエンスが地球上から消えれば失われてしまう概念全般」を本書では「神話」と呼んでいる。
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
サピエンスにとって「神話」の力は絶大だった。
言葉を使って想像上の現実を生み出す能力のおかげで、大勢の見知らぬ人どうしが効果的に協力できるようになった。
つまり、他の生物には成し遂げられないタイプの「協働」を生み出すことができるようになったというわけだ。ピラミッドのような巨大建設が存在し得るのも、「王様の絶対権力」という「神話」を多くの人々が共有していたからだろう(ピラミッド建設には「公共事業として雇用を創出した」という仮説もあるが)。

しかし「神話」がもたらしたものはそれだけではない。より重要なポイントについて著者はこう書いている。
あわせて読みたい
【情報】日本の社会問題を”祈り”で捉える。市場原理の外にあるべき”歩哨”たる裁き・教育・医療:『日本…
「霊性」というテーマは馴染みが薄いし、胡散臭ささえある。しかし『日本霊性論』では、「霊性とは、人間社会が集団を存続させるために生み出した機能」であると主張する。裁き・教育・医療の変化が鈍い真っ当な理由と、情報感度の薄れた現代人が引き起こす問題を語る
人間どうしの大規模な協力は神話に基づいているので、人々の協力の仕方は、その神話を変えること、つまり別の物語を語ることによって、変更可能なのだ。適切な条件下では、神話はあっという間に現実を変えることができる。例えば、1789年にフランスの人々は、ほぼ一夜にして、王権神授説の神話を信じるのをやめ、国民主権の神話を信じ始めた。このように、認知革命以降、ホモ・サピエンスは必要性の変化に応じて迅速に振る舞いを改めることが可能になった。
認知革命は「神話によって人々を協力させる」という仕組みを生み出したわけだが、このやり方はさらに、「神話を変更することで、人々の協力の仕方をすぐに変えられる」というプラス効果を生むことにもなった。最近の例でイメージしやすいのは、諸外国におけるマスク着用ではないだろうか。コロナ以前は、「海外で日本人がマスクをしたまま店に入ると強盗だと思われる」などという時代もあったようだが、世界的パンデミックによって「神話」が変わったことで、欧米人もマスクを着用するようになった。
SDGsや気候変動の危機などの訴えも、「神話を変えることで人々の行動変容を促す」目的だと言えるし、私たちも日常的に、このような「認知革命」による影響を実感していると言っていいだろう。
このようにしてサピエンスは、他の生物には不可能なレベルでの大規模な協力を生み出すことができるようになったのである。
あわせて読みたい
【意外】思わぬ資源が枯渇。文明を支えてきた”砂”の減少と、今後我々が変えねばならぬこと:『砂と人類』
「砂が枯渇している」と聞いて信じられるだろうか?そこら中にありそうな砂だが、産業用途で使えるものは限られている。そしてそのために、砂浜の砂が世界中で盗掘されているのだ。『砂と人類』から、石油やプラスチックごみ以上に重要な環境問題を学ぶ
「農業革命」がサピエンスに「不安」をもたらした
人類の中でサピエンスだけが突出したもう1つの要因として、著者は「農耕」を挙げている。これを第2の革命である「農業革命」と呼ぶ。
サピエンスが「農耕」に踏み出したこ歴史的事実は、次のような議論を巻き起こしているようだ。
農業革命は歴史上、最も物議を醸す部類の出来事だ。この革命で人類は繁栄と進歩への道を歩みだしたと主張する熱心な支持者がいる。一方、地獄行きにつながったと言い張る人もいる。
あわせて読みたい
【危機】遺伝子組み換え作物の危険性を指摘。バイオ企業「モンサント社」の実態を暴く衝撃の映画:映画…
「遺伝子組み換え作物が危険かどうか」以上に注目すべきは、「モンサント社の除草剤を摂取して大丈夫か」である。種子を独占的に販売し、農家を借金まみれにし、世界中の作物の多様性を失わせようとしている現状を、映画「モンサントの不自然な食べもの」から知る
私のおぼろげな記憶では、高校までの歴史の授業で、「人間は農耕によって安定した定住生活を手に入れた」という趣旨の説明がなされていたように思う。確かにその主張を支持する立場の人もいるそうだ。しかし一方で「地獄行き」と表現する人もいる。なかなか過激な主張だが、そこには、
私たちが小麦を栽培化したのではなく、小麦が私たちを家畜化した。
という考えがあるそうだ。

あわせて読みたい
【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:…
グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る
結果から見れば、狩猟採集から農耕に移行したことによる恩恵はないはずだ、と著者は語る。狩猟採集の方が、様々な栄養を摂取することが可能だ。また小麦の傍での定住を強いられるため自由が奪われるし、農作業によってヘルニアや関節炎などの病気も増えることになったという。
確かにそう指摘されると、狩猟採集が当然の生活を送る中で、農耕に移行しようなどと考えるものだろうかと疑問を抱かされる。私なら、「今は気が向いた時に動物や果物を採りに行って、自分が気に入る場所で生活すればいいのに、農耕なんて種まきとか収穫の作業が大変だし、生涯ずっと小麦の傍から離れられない。そんな生活したくないよ」と感じるのではないかと思う。
農耕への移行が実現した背景の1つについて著者は、その変化は非常に緩やかだったと指摘している。ある個人の一生で見れば、ひと世代前と比べて変化は僅かだったというわけだ。一斉に農業が始まったのではなく、「あ、あの一家も農耕始めるんだー」みたいな感覚だったのだろう。
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
少しずつでも農耕に移行する人が出てくるようになったのは、近視的な視点で考えると狩猟採集より農耕の方が有利に思えたからだろう、と書いている。災害などにより果物が採れない年があったり、ある一定地域に人口が密集しすぎ1人当たりの取り分が減るなど、「長期的に見れば有利でも、短期的に見れば欠点もある狩猟採集」を諦める人がポツポツ出始めたということだろう。
そんな風にして、サピエンスは少しずつ狩猟採集を手放して農耕へと移行していくのだが、著者はこれを、
農業革命は、史上最大の詐欺だったのだ。
と捉えている。
あわせて読みたい
【不満】この閉塞感は打破すべきか?自由意志が駆逐された社会と、不幸になる自由について:『巡査長 真…
自由に選択し、自由に行動し、自由に生きているつもりでも、現代社会においては既に「自由意志」は失われてしまっている。しかし、そんな世の中を生きることは果たして不幸だろうか?異色警察小説『巡査長 真行寺弘道』をベースに「不幸になる自由」について語る
その理由の1つが、「農耕によって『未来への不安』を抱くようなったこと」だ。
狩猟採集生活は「その日暮らし」のようなものであり、「きっとこれからも、今日と同じように肉や果物を食べられるだろう」という前提を元にしている。だからそもそも、「未来」という時間軸に思いを馳せる理由がない。
一方で農耕の生活は、「未来」の心配をする機会が多くなるだろう。時期ごとの決まった作業のために人の手配が必要だし、災害などによって収穫ができない恐れも出てくる。このように、「農耕」によって「未来を不安に感じる」という性質が生まれることになったのだ。
あわせて読みたい
【実話】障害者との接し方を考えさせる映画『こんな夜更けにバナナかよ』から”対等な関係”の大事さを知る
「障害者だから◯◯だ」という決まりきった捉え方をどうしてもしてしまいがちですが、『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』の主人公・鹿野靖明の生き様を知れば、少しは考え方が変わるかもしれません。筋ジストロフィーのまま病院・家族から離れて“自活”する決断をした驚異の人生
しかし農耕生活には実は、「未来への不安」への対処も内在している。がむしゃらに働くことで生産性を上げられるし、節制して食料を蓄えることで不測の事態に備えることも可能だからだ。
だったら問題ないじゃないか、とはいかない。この「がむしゃらに働く」「食料を蓄える」という行為が、逆に農耕民を苦しめることになったのだ。
なぜなら、そのような「余剰の生産」をエリートが収奪するからである。狩猟採集生活ではそもそも「余剰の生産」など存在しないわけで、だからそれを収奪する存在も現れ得ない。しかし農耕生活では、「未来への不安」が必然的に生まれてしまい、さらにそれに対処するための「余剰の生産」を行えてしまうが故に、その「余剰の生産」を収奪しようとする存在が現れることになるというわけだ。
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
争いによって、あるいは「年貢」などの税によって、「余剰の生産」は奪われていく。そして、農耕民から収奪することで富を得ている者たちは、農耕民を働かせてさらに多く奪おうとするので、農耕民は疲弊する生活から抜け出せなくなってしまうのだ。まさに「小麦による家畜化」である。
しかし、この「余剰の生産」は我々人類の歴史にとってとても重要なものだった。
こうして没収された食糧の余剰が、政治や戦争、芸術、哲学の原動力となった。

人類が高度な文明を築き上げるのに不可欠な様々な事柄は、農耕民が生み出す「余剰の生産」がベースになっていたというわけだ。そう考えると、「余剰の生産」が存在しない狩猟採集生活を続けていたら、サピエンスは現在のような社会を作り出せなかったと言えるだろう。
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
農耕は「史上最大の詐欺」であり、結果的に農耕民の生活は苦しくなってしまったが、一方、農耕のお陰で、ごく一部の人間は巨大な富を有することができるようになり、高度な社会が生まれるきっかけとなったのだ。
さらに農業革命は「書記」をも生み出した。
農耕生活においては、膨大な数理データを管理しなければならない。温度や水量など農業に必要なデータは様々にあるし、収穫した作物の量なども記録しておく必要があっただろう。
これらの記録のために開発されたのが「書記」というシステムであり、シュメール人がその先鞭をつけたそうだ。彼らはさらに、記録した文書を保管するシステムも考案し、非常に効率の良い文書管理を実現したという。
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
この「書記システム」もまた、サピエンスが大規模な協力を実現するために不可欠だったのだ。
「認知革命」による「神話の共有」、そして「農業革命」による「富の収奪」「書記システムの開発」によって、サピエンスは他の生物には真似できない協働を実現し、大規模なネットワークを生み出すことに成功するのである。
しかしこの流れは一方で、ヒエラルキーや差別を生み出すことにも繋がった。
「神話の共有」は、「想像上の秩序」を生むことになる。要するに、「白人と黒人」「男性と女性」というような区別のことだ。また「富の収奪」は当然、「富者と貧者」という区別を生んでしまう。本書では、サピエンスがこれらの区別を基にしてどのような差別を生み出してきたのかが振り返られる。人類の歴史を大枠で捉える非常に面白い流れと言えるだろう。
あわせて読みたい
【教養】美術を「感じたまま鑑賞する」のは難しい。必要な予備知識をインストールするための1冊:『武器…
芸術を「感性の赴くまま見る」のは、日本特有だそうだ。欧米では美術は「勉強するもの」と認識されており、本書ではアートを理解しようとするスタンスがビジネスにも役立つと示唆される。美術館館長を務める著者の『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』から基礎の基礎を学ぶ
その後、「巨視的な視点に立てば、サピエンスは統一の方向へと進んでいる」という話が展開される。「貨幣」「帝国」「宗教」の3要素を取り上げ、それらが社会の仕組み・価値観・文化などをどのように同一の方向へとまとめたのかが語られるが、この記事では省略しよう。
第3の革命である「科学革命」
さてこれ以降、ここまで「サピエンス」と書いていたものを「人類」という表記に変えようと思う。
話は「科学革命」に移る。私たちは「科学」が様々に世の中を変えていく様を見知っているので、これが「革命」と呼ばれることに違和感はないだろう。しかし、当時はそうではなかった。
あわせて読みたい
【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…
デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える
これが革命であるのには、理由がある。西暦1500年ごろまでは、世界中の人類は、医学や軍事、経済の分野で新たな力を獲得する能力が自らにあるとは思えなかったのだ。政府や裕福な後援者が教育や学問に資金を割り当てはしたものの、その目的は一般に、新たな能力の獲得ではなく、既存の能力の維持だった。近代以前の典型的な支配者は、自分の支配を正当化して社会秩序を維持してもらうことを願って、聖職者や哲学者、詩人にお金を与えた。そして、彼らが新しい医薬品を発見したり、新しい武器を発明したり、経済成長を促したりすることは期待していなかった。
「医学」「軍事」「経済」は、「新しいものを生み出す分野」だと思われていなかったのだ。現在の視点からすると意外に思える。
さらに当時の人々はそもそも、こんな考えを抱いていた。

あわせて読みたい
【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画
1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品
科学革命以前は、人類の文化のほとんどは進歩というものを信じていなかった。人々は、黄金時代は過去にあり、世界は仮に衰退していないまでも停滞していると考えていた。長年積み重ねてきた叡智を厳しく固守すれば、古き良き時代を取り戻せるかもしれず、人間の創意工夫は日常生活のあちこちの面を向上させられるかもしれない。だが、人類の実際的な知識を使って、この世の根本的な諸問題を克服するのは不可能だと思われていた。知るべきことをすべて知っていたムハンマドやイエス、ブッダ、孔子さえもが飢饉や疫病、貧困、戦争をこの世からなくせなかったのだから、私たちにそんなことがどうしてできるだろう?
「科学革命」以前は、宗教の力が強かった。そして宗教にはイエス・キリストやブッダなどの創始者がおり、彼らが「凄い人物」と崇められる。だから、「過去の方が偉大だった」と考えるのは自然な感覚だと言えるだろう。
つまり、「科学革命」以前は、「自分たちは世界を既に理解している。すべてを理解しているのに問題は無くならないのだから、問題は永久に無くなることはない」という理解が当たり前だったのだ。
この点を理解することで、「科学革命」がなぜ「革命」なのかを理解しやすくなるだろう。つまり、「自分たちはまだ何も知らない」というスタートラインに立ったことこそが「革命」なのである。
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
この差異は、ヨーロッパの帝国主義の違いにも関係している。
ヨーロッパの帝国主義は、それまでの歴史で行われた諸帝国のどの事業とも完全に異なっていた。それ以前の帝国における探求者は、自分はすでにこの世界を理解していると考えがちだった。征服とはたんに自分たちの世界観を利用し、それを広めることだった。一例を挙げると、アラビア人は、自分たちにとって何か未知のものを発見するためにエジプトやスペインやインドを征服したわけではなかった。ローマ人やモンゴル人やアステカ族は、知識ではなく、富や権力を求めて新天地を貪欲に征服した。それとは対照的に、ヨーロッパの帝国主義者は、新たな領土とともに新たな知識を獲得することを望み、遠く離れた土地を目指して海へ乗り出していった。

かつては「すべてを知っている自分たちの考えを広める」ために世界に飛び出していったのだが、ある時点から「新しい知識を獲得する」ことが目的になっていった、というわけだ。確かにこの変化は非常に大きいと言えるだろう。
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
この違いを理解することで、
ユーラシア大陸の寒冷な末端に暮らすヨーロッパの人々は、どのようにして世界の中心からほど遠いこの片隅から抜け出し、全世界を征服しえたのだろう?
という疑問にも答えることができるようになる。重要なのは「無知である」というスタートラインに立てたかどうかなのだ。軍事・産業・科学の複合体がインドではなくヨーロッパで発展したことも、イギリスが飛躍した際にフランス・ドイツ・アメリカはすぐに追いいたが中国は遅れを取ったことも、すべて同じ理由で説明できるという。
あわせて読みたい
【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す
タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる
つまり人類は、「自分たちはすべてを理解している」という「宗教の軛」を振り払い、「自分たちはまだ何も知らない」という前提に立つことで「科学革命」を実現し、現在に至るまで様々な知見を積み上げてきたというわけだ。
本書では「科学革命」に不可欠だった要素として「資本主義」と「産業革命」が挙げられるのだが、私は本書を読んで初めて「資本主義」の本質的な部分を理解できた気になれた。
今まで経済系の本などで「資本主義」に関する記述を何度も読んだことがある。しかしその度にずっと違和感を覚えていた。正確には覚えていないが、私がこれまで読んだ説明には大体、「資本主義では富は増え続ける」というような記述がされていたように思う。ただ、「なぜ増えるのか」については説明されていなかったのだ。
本書ではこの点について、「資本主義の根底には、『科学者が何か驚くべき発見をしてくれるはずだ』という期待がある」と書かれている。つまり、「それが何かは分からないが、『科学者が新しい何かを生み出してくれるはずという幻想』こそが資本主義を成立させている」というわけだ。
あわせて読みたい
【扇動】人生うまくいかないと感じる時に読みたい瀧本哲史の本。「未来をどう生きる?」と問われる1冊:…
瀧本哲史は非常に優れたアジテーターであり、『2020年6月30日にまたここで会おう』もまさにそんな1冊。「少数のカリスマ」ではなく「多数の『小さなリーダー』」によって社会が変革されるべきだ、誰にだってやれることはある、と若者を焚きつける、熱量満載の作品

逆に言えば、「科学が新しい何かを生み出せなくなったら、資本主義は成立しなくなる」ということでもある。そういう意味で、「科学」と「資本主義」は切っても切り離せない存在だと言っていいだろう。
また本書には、「資本主義」が与えた影響についても面白い話がある。なんと、「資本主義」が「個人」という概念を生み出したというのだ。
それまで人類は、「家族」や「コミュニティ」を通じて生活に関わる様々な事柄に関わっていた。つまり、「個人」という単位が重視されない社会生活が行われていたということだ。しかし、資本主義が「市場」に力を与えたことで、誰もが「市場」を通じて様々なサービスを享受できるようになっていく。そのような背景の元、「家族」や「コミュニティ」の力を弱体化させたいと考えていた国家が、「家族やコミュニティに依存せず、もっと自由に生きればいい」と発信するようになったのだ。
このような流れで「個人」という概念が生まれるようになっていった、という話も興味深かった。
あわせて読みたい
【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ
江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品
著:ユヴァル・ノア・ハラリ, 翻訳:柴田裕之
¥3,960 (2022/02/15 20:57時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
この記事では、あくまでも全体的な流れにざっと触れたに過ぎず、本書はもっと多岐に渡る話題に溢れている。
私はそれなりに本を読み、ノンフィクションにも結構触れているが、そんな私でも多少の難しさを感じたので、本を読み慣れない人にはちょっと読み進めるのが大変な本かもしれない。
ルシルナ
おすすめのノンフィクション本【本の感想】 | ルシルナ
このブログは、本と映画をベースに考えたことを綴っていますが、ここでは記事の中で取り上げたノンフィクション本についてまとめています。社会・国際情勢・政治・経済・哲…
しかし本書は、「サピエンスの歴史」という壮大なテーマを掲げ、それを見事に昇華させた素晴らしい作品であり、歴史に限らない様々な知見に溢れている。
チャレンジしてみる価値のある、知的興奮に満ちた一冊だ。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
あわせて読みたい
【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる
ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?
あわせて読みたい
【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか
私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう
あわせて読みたい
【映画】『街は誰のもの?』という問いは奥深い。「公共」の意味を考えさせる問題提起に満ちた作品
映画『街は誰のもの?』は、タイトルの通り「街(公共)は誰のものなのか?」を問う作品だ。そしてそのテーマの1つが、無許可で街中に絵を描く「グラフィティ」であることもまた面白い。想像もしなかった問いや価値観に直面させられる、とても興味深い作品である
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
あわせて読みたい
【挑発】「TBS史上最大の問題作」と評されるドキュメンタリー『日の丸』(構成:寺山修司)のリメイク映画
1967年に放送された、寺山修司が構成に関わったドキュメンタリー『日の丸』は、「TBS史上最大の問題作」と評されている。そのスタイルを踏襲して作られた映画『日の丸~それは今なのかもしれない~』は、予想以上に面白い作品だった。常軌を逸した街頭インタビューを起点に様々な思考に触れられる作品
あわせて読みたい
【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す
タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる
あわせて読みたい
【思考】文章の書き方が分かんない、トレーニングしたいって人はまず、古賀史健の文章講義の本を読め:…
古賀史健『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、「具体的なテクニック」ではない記述も非常に興味深い1冊だ。「なぜ文章を書く必要があるのか」という根本的な部分から丁寧に掘り下げる本書は、「書くからこそ考えられる」という、一般的なイメージとは逆だろう発想が提示される
あわせて読みたい
【革命】観る将必読。「将棋を観ること」の本質、より面白くなる見方、そして羽生善治の凄さが満載:『…
野球なら「なんで今振らないんだ!」みたいな素人の野次が成立するのに、将棋は「指せなきゃ観てもつまらない」と思われるのは何故か。この疑問を起点に、「将棋を観ること」と「羽生善治の凄さ」に肉薄する『羽生善治と現代』は、「将棋鑑賞」をより面白くしてくれる話が満載
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
あわせて読みたい
【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ
江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品
あわせて読みたい
【扇動】人生うまくいかないと感じる時に読みたい瀧本哲史の本。「未来をどう生きる?」と問われる1冊:…
瀧本哲史は非常に優れたアジテーターであり、『2020年6月30日にまたここで会おう』もまさにそんな1冊。「少数のカリスマ」ではなく「多数の『小さなリーダー』」によって社会が変革されるべきだ、誰にだってやれることはある、と若者を焚きつける、熱量満載の作品
あわせて読みたい
【奇跡】信念を貫いた男が国の制度を変えた。特別養子縁組を実現させた石巻の産婦人科医の執念:『赤ち…
遊郭で生まれ育った石巻の医師が声を上げ、あらゆる障害をなぎ倒して前進したお陰で「特別養子縁組」の制度が実現した。そんな産婦人科医・菊田昇の生涯を描き出す小説『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』には、法を犯してでも信念を貫いた男の衝撃の人生が描かれている
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
あわせて読みたい
【組織】新入社員・就活生必読。「社内コミュニケーション」でやるべきことを山田ズーニーが語る:『半…
組織内のコミュニケーションが上手くできないと悩んでいる方、多いのではないだろうか。山田ズーニー『半年で職場の星になる!働くためのコミュニケーション力』は、組織に属するあらゆる人に向けて、「コミュニケーションで重視すべき本質」をテクニックと共に伝授する
あわせて読みたい
【化石】聞き馴染みのない「分子生物学」を通じて、科学という学問の本質を更科功が分かりやすく伝える…
映画『ジュラシック・パーク』を観たことがある方なら、「コハクの化石に閉じ込められた蚊の血液から恐竜の遺伝子を取り出す」という設定にワクワクしたことだろう。『化石の分子生物学』とは、まさにそのような研究を指す。科学以外の分野にも威力を発揮する知見に溢れた1冊
あわせて読みたい
【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい
「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる
あわせて読みたい
【人生】日本人有名プロゲーマー・梅原大吾の名言満載の本。「努力そのものを楽しむ」ための生き方とは…
「eスポーツ」という呼び名が世の中に定着する遥か以前から活躍する日本人初のプロゲーマー・梅原大吾。17歳で世界一となり、今も一線を走り続けているが、そんな彼が『勝ち続ける意志力』で語る、「『努力している状態』こそを楽しむ」という考え方は、誰の人生にも参考になるはずだ
あわせて読みたい
【変革】「ビジネスより自由のために交渉力を」と語る瀧本哲史の”自己啓発”本に「交渉のコツ」を学ぶ:…
急逝してしまった瀧本哲史は、「交渉力」を伝授する『武器としての交渉思考』を通じて、「若者よ、立ち上がれ!」と促している。「同質性のタコツボ」から抜け出し、「異質な人」と「秘密結社」を作り、世の中に対する「不満」を「変革」へと向かわせる、その勇気と力を本書から感じてほしい
あわせて読みたい
【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:…
グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る
あわせて読みたい
【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…
デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ
あわせて読みたい
【真実】ホロコーストが裁判で争われた衝撃の実話が映画化。”明らかな虚偽”にどう立ち向かうべきか:『…
「ホロコーストが起こったか否か」が、なんとイギリスの裁判で争われたことがある。その衝撃の実話を元にした『否定と肯定』では、「真実とは何か?」「情報をどう信じるべきか?」が問われる。「フェイクニュース」という言葉が当たり前に使われる世界に生きているからこそ知っておくべき事実
あわせて読みたい
【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者…
世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
あわせて読みたい
【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…
「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る
あわせて読みたい
【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…
「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【教養】美術を「感じたまま鑑賞する」のは難しい。必要な予備知識をインストールするための1冊:『武器…
芸術を「感性の赴くまま見る」のは、日本特有だそうだ。欧米では美術は「勉強するもの」と認識されており、本書ではアートを理解しようとするスタンスがビジネスにも役立つと示唆される。美術館館長を務める著者の『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』から基礎の基礎を学ぶ
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
あわせて読みたい
【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…
一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する
あわせて読みたい
【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…
20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る
あわせて読みたい
【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…
「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる
あわせて読みたい
【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…
古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る
あわせて読みたい
【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ
350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る
あわせて読みたい
【異端】数学の”証明”はなぜ生まれたのか?「無理数」と「無限」に恐怖した古代ギリシャ人の奮闘:『数…
学校で数学を習うと、当然のように「証明」が登場する。しかしこの「証明」、実は古代ギリシャでしか発展しなかった、数学史においては非常に”異端”の考え方なのだ。『数学の想像力 正しさの深層に何があるのか』をベースに、ギリシャ人が恐れたものの正体を知る
あわせて読みたい
【対立】数学はなぜ”美しい”のか?数学は「発見」か「発明」かの議論から、その奥深さを知る:『神は数…
数学界には、「数学は神が作った派」と「数学は人間が作った派」が存在する。『神は数学者か?』をベースに、「数学は発見か、発明か」という議論を理解し、数学史においてそれぞれの認識がどのような転換点によって変わっていったのかを学ぶ
あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
あわせて読みたい
【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…
タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。
あわせて読みたい
【ゴミ】プラスチックによる環境問題の実態を描く衝撃の映画。我々は現実をあまりに知らない:映画『プ…
プラスチックごみによる海洋汚染は、我々の想像を遥かに超えている。そしてその現実は、「我々は日常的にマイクロプラスチックを摂取している」という問題にも繋がっている。映画『プラスチックの海』から、現代文明が引き起こしている環境破壊の現実を知る
あわせて読みたい
【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…
小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る
あわせて読みたい
【意外】思わぬ資源が枯渇。文明を支えてきた”砂”の減少と、今後我々が変えねばならぬこと:『砂と人類』
「砂が枯渇している」と聞いて信じられるだろうか?そこら中にありそうな砂だが、産業用途で使えるものは限られている。そしてそのために、砂浜の砂が世界中で盗掘されているのだ。『砂と人類』から、石油やプラスチックごみ以上に重要な環境問題を学ぶ
あわせて読みたい
【情報】日本の社会問題を”祈り”で捉える。市場原理の外にあるべき”歩哨”たる裁き・教育・医療:『日本…
「霊性」というテーマは馴染みが薄いし、胡散臭ささえある。しかし『日本霊性論』では、「霊性とは、人間社会が集団を存続させるために生み出した機能」であると主張する。裁き・教育・医療の変化が鈍い真っ当な理由と、情報感度の薄れた現代人が引き起こす問題を語る
あわせて読みたい
【希望】貧困の解決は我々を豊かにする。「朝ベッドから起きたい」と思えない社会を変える課題解決:『…
現代は、過去どの時代と比べても安全で清潔で、豊かである。しかしそんな時代に、我々は「幸せ」を実感することができない。『隷属なき道』をベースに、その理由は一体なんなのか何故そうなってしまうのかを明らかにし、さらに、より良い暮らしを思い描くための社会課題の解決に触れる
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
歴史・文明・人類【本・映画の感想】 | ルシルナ
現在、そして未来の社会について考える場合に、人類のこれまでの歴史を無視することは難しいでしょう。知的好奇心としても、人類がいかに誕生し、祖先がどのような文明を作…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…































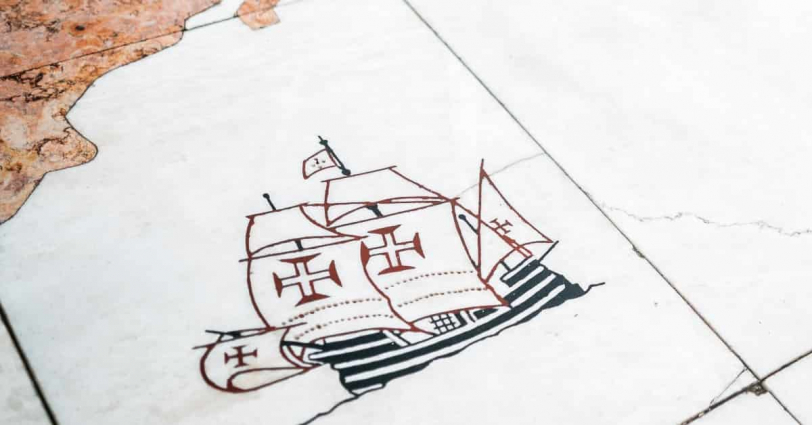














































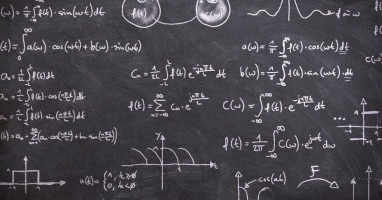

















コメント