目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:ケン・オーレッタ, 翻訳:土方 奈美
¥159 (2022/07/25 21:01時点 | Amazon調べ)
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
創業から4年経っても、収益化の目処がまったく立っていなかったグーグル 収益化に無関心だった創業者2人の、無邪気な理想主義 グーグルを軌道に乗せた2人の立役者と、グーグルの内奥に入り込んだ著者の奮闘 良い意味でも悪い意味でも”イカれている”創業者2人の生き様に私は強く惹かれる
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
世界を一変させた「グーグル」とはどんな企業なのか?『グーグル秘録』から知る、「無邪気さ」と「偶然」によってたどり着いた現在地
スマホやインターネットを使っている人間で、グーグルの恩恵を受けていない人はそういないだろう 。「Gmail」「Google Chrome」「Google Map」などは誰もが日常的に使っているだろうし、YouTubeもグーグルが買収したサービスだ。もし今この瞬間に、「グーグルという会社と、グーグルが生み出したすべての技術」が消えるとしたら、社会は大混乱に陥るのではないだろうか 。
あわせて読みたい
【恐怖】SNSの危険性と子供の守り方を、ドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』で学ぶ
実際にチェコの警察を動かした衝撃のドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』は、少女の「寂しさ」に付け込むおっさんどもの醜悪さに満ちあふれている。「WEBの利用制限」だけでは子どもを守りきれない現実を、リアルなものとして実感すべき
それぐらい、私たちの生活にグーグルが深く関係している 。
そんな「世界を一変させた企業 」について、あなたはどのぐらい知っているだろうか ? その問いに答えるのが本書である。著者のケン・オーレッタは、
ケン・オーレッタほど、今起こりつつあるメディア革命を完全にカバーしている記者はいない。
と評されるほど、その分野に精通したジャーナリストだ。本書はグーグルについての本ではあるが、同時に、グーグルが登場したことで破壊されてしまった世界についても描いている 。グーグルという一企業を中心に据えた、「世界のメディア産業の激変」を描く作品 というわけだ。
あわせて読みたい
【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….
つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る
ちなみに本書は、日本での単行本の発売が2010年、アメリカで発売されたのはそれ以前である。つまり、最新の情報に触れられている作品ではない 。ただ本書は、どちらかと言えば「歴史書」に近い と言っていいだろう。グーグルがどのように創業され、いかにして今のような地点にたどり着くことになったのかが描かれる作品 なので、最新の情報が含まれていないことは、本書の欠点にはならない。その点を理解して手に取ってほしいと思う。
創業当初は、売上を見込める予測がまったく存在しなかった
グーグルは、メディア産業のあり方を一変させた 。
あわせて読みたい
【組織】意思決定もクリエイティブも「問う力」が不可欠だ。MIT教授がCEOから学んだ秘訣とは?:『問い…
組織マネジメントにおいては「問うこと」が最も重要だと、『問いこそが答えだ!』は主張する。MIT教授が多くのCEOから直接話を聞いて学んだ、「『問う環境』を実現するための『心理的安全性の確保』の重要性」とその実践の手法について、実例満載で説明する1冊
伝統メディアでは、コンテンツのある場所に視聴者を連れていくことが大切だった。だが新たなメディアでは、コンテンツがある場所に視聴者を連れて行くのではなく、視聴者のいるところにコンテンツを届けることが重要だ。そして視聴者は、ウェブのありとあらゆる場所に存在するんだ。
生まれながらにしてインターネットが存在する世代にとっては、「自分の元に情報が届くこと」が当たり前 だろう。しかしそれまでは、新聞なりテレビなり映画なり何でもいいが、「そのコンテンツがある場所にユーザーを連れて行く」必要があった 。そんな、伝統メディアにとって常識的だった考え方を、グーグルは創業からたった10数年で打ち破ってしまった のである。
あわせて読みたい
【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…
一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う
また、グーグルがもたらした新たな価値観として、「ネットは無料であるべき」 という考えも挙げられるだろう。
グーグルは無料サービスを通じて、「ネット上の情報やコンテンツは無料であるべきだ」という意識を広めた。それこそ伝統メディアが目下、必死で抵抗しているものだ。「”グーグル世代”とも言うべき企業は、デジタルなものはすべて無料にすべき、というシンプルな前提にもとづいて成長してきた」とアンダーソンは書いている。
グーグルの革命的だった点は、「すべてが無料」という点だ 。一般的なユーザーが、グーグルに対して何か支払いを行うことはないだろう。少なくとも私は、グーグルに対して何か料金を支払ったことはないと思う。そしてそんな、何もかもを無料で打ち出すグーグルが、最終的にとんでもない額の広告収入を得ている のだ。2008年の広告収入は、5大テレビ・ネットワーク(CBS・NBC・ABC・FOX・CW)の合計に拮抗するそうだ 。恐らく2022年現在は、2008年時点よりも遥かに増えているだろう。
あわせて読みたい
【異様】ジャーナリズムの役割って何だ?日本ではまだきちんと機能しているか?報道機関自らが問う映画…
ドキュメンタリーで定評のある東海テレビが、「東海テレビ」を被写体として撮ったドキュメンタリー映画『さよならテレビ』は、「メディアはどうあるべきか?」を問いかける。2011年の信じがたいミスを遠景にしつつ、メディア内部から「メディアの存在意義」を投げかける
しかし、創業者2人を始めとして、グーグルがこのように収益を生み出せるようになるなどとは、誰も考えていなかった 。そこに、グーグルという企業の凄まじさがあると感じる。
グーグルがCPCという画期的な広告手法を発明し、「アドワーズ」と名付けて稼働させたのが2002年のこと 。既に創業から4年が経っていた 。つまり、この4年間、グーグルには「収入」が存在しなかったというわけだ。また「アドワーズ」にしても、起死回生の一手として生み出されたなんてことはない。これが収益の柱になるとは誰も考えていなかったというから驚きだ。
そもそも創業者の2人、ラリー・ペイジとサーゲイ・ブリンは、「収益化」にはほとんど関心を示さなかった という。ただ、この表現は正確ではない。正しくは、「『検索の質を高めれば、自ずと収益化の方法が見つかるはず』という信念を疑うことなく持ち続けていた 」である。
二人ともグーグルの宣伝のためには1セントたりとも使う気はなかった。
会社には収入はほとんどなかったが、ペイジもブリンも、グーグルが完成さえすればユーザーは集まってくると信じて疑わなかった。
あわせて読みたい
【驚異】『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』って書名通りの本。異端ロックバンドの”稼ぎ方”
日本ではあまり知られていないが、熱狂的なファンを持つロックバンド「グレイトフル・デッド」。彼らは50年も前から、現代では当たり前となった手法を続け、今でも年間5000万ドルを稼いでいる。『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』で「ファンからの愛され方」を学ぶ
本書には、「創業者2人が収益化にいかに無関心だったか」を示す凄まじいエピソード が記されている。
ついにひとりの記者がまっとうな質問を投げかけた。「グーグルはどうやって利益を上げるのか?」
あるクレジットカード会社(実際にはビザ)が、グーグルのホームページに自社のロゴマークを載せ、リンクを張ってくれれば五百万ドル支払うと申し出たことがあるが、ペイジとブリンはまったく相手にしなかった。
あわせて読みたい
【圧巻】150年前に気球で科学と天気予報の歴史を変えた挑戦者を描く映画『イントゥ・ザ・スカイ』
「天気予報」が「占い」と同等に扱われていた1860年代に、気球を使って気象の歴史を切り開いた者たちがいた。映画『イントゥ・ザ・スカイ』は、酸素ボンベ無しで高度1万1000m以上まで辿り着いた科学者と気球操縦士の物語であり、「常識を乗り越える冒険」の素晴らしさを教えてくれる
このスタンスこそ、まさに「グーグル」なのである 。結果としてグーグルは、CPCという手法を発明し、現在に至る「世界を一変させた企業」への道を歩んでいく。しかしCPCの開発は、あくまで偶然にすぎなかった と語っている。もしグーグルが画期的な広告手法を生み出せなかったから、グーグルは現在のような企業としては存在しなかっただろう 。
ある意味で世界を支配しているような存在でもあるグーグルの創業者が、「収益化にまったく関心がなかった」というのは驚くべき事実であるようにも感じられる 。しかしだからこそ、普通ではあり得ない企業として異端的な存在感を示すことにもなった のだとも感じた。
創業者2人の「無邪気さ」と、グーグルを大きくしたキーパーソン
それでは、創業者2人は一体何に関心を持っていたのか 。それはシンプルに、次のように表現できる。
シュミットと創業者たちの理想とは何か? それは検索をするユーザーの真意をたちどころに理解できるほどの情報を手に入れ、問いに対して唯一最高の答えのみを提示できるようになり、ユーザーにこれ以上ないというほどの満足感を与えることだ。
あわせて読みたい
【衝撃】「仕事の意味」とは?天才・野崎まどが『タイタン』で描く「仕事をしなくていい世界」の危機
「仕事が存在しない世界」は果たして人間にとって楽園なのか?万能のAIが人間の仕事をすべて肩代わりしてくれる世界を野崎まどが描く『タイタン』。その壮大な世界観を通じて、現代を照射する「仕事に関する思索」が多数登場する、エンタメ作品としてもド級に面白い傑作SF小説
なんとも理想主義的な主張 だと感じるだろう。そう、彼らは「理想主義者」だと受け取られている のだ。
ペイジとブリンを「ユートピアン(理想主義者)」と評する。「彼らは質の高い情報さえ手に入れば、誰もがより良い生活を送れると信じている。『技術さえできれば、おのずとうまくいく』と考える二人は、”技術的楽観主義”と言えるだろう」
ペイジとブリンには、別の共通点もあった。二人は共に、やや救世主めいた理想主義に燃えていた。グーグルを創業した背景には、広告は人々をだまして無駄金を使わせているという憤りや、インターネットこそ人々を開放する、民主的な精神を育むはずだという強い思いがあった。
あわせて読みたい
【不安】環境活動家グレタを追う映画。「たったひとりのストライキ」から国連スピーチまでの奮闘と激変…
環境活動家であるグレタのことを、私はずっと「怒りの人」「正義の人」だとばかり思っていた。しかしそうではない。彼女は「不安」から、いても立ってもいられずに行動を起こしただけなのだ。映画『グレタ ひとりぼっちの挑戦』から、グレタの実像とその強い想いを知る
私は基本的に、あまのじゃくや奇人変人が大好き なので、アップル製品を1つも使っていないにも拘わらず、スティーヴ・ジョブズには興味を抱いている。同じように、ラリー・ペイジとサーゲイ・ブリンにも強く惹かれてしまった。彼らのあまりに「理想主義的」な願望は、普通には実現不可能だろう 。2022年現在の話であればまだしも、彼らがそのように考えてグーグルを創業したのは1998年のことだ。Windows95が発売されてからたった3年、日本ではまだインターネットがまともには普及していなかった頃である。そんな時代に、「ストレスフリーの検索を実現すれば世の中はハッピーになる」と主張するのは、なかなかにイカれている と思う。しかしだからこそ面白いし、そんな異端的な創業者だからこそ、グーグルという特異な会社が生まれた とも言えるだろう。
理想主義的と言えば、
グーグルのスローガンは、「邪悪になってはいけない」
どうすれば邪悪なことをせずに成長できるか。
というスタンスも興味深い。しかし、ネットで調べてみると、この「Don’t Be Evil(邪悪になってはいけない)」というスローガンは、2018年に外された ようだ。そのことが何を意味するのかは分からないが、少なくともグーグルは「邪悪になってはいけない」というスタンスで創業され、そのスローガンと共に長い間歩んできたというのは確か である。
あわせて読みたい
【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…
生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る
さて、収益化にまったく興味がなかったグーグルが、創業からしばらくの間なんとか持ちこたえ、どうにか会社を軌道に乗せることができたのは、エリック・シュミットとビル・キャンベルの2人の存在のお陰だ 。エリック・シュミットはグーグルのCEOとして会社を率い、ビル・キャンベルは経営相談役として創業者2人をコーチした。どちらも、その世界では知らない者のいない超有名人である。
ラリー・ペイジとサーゲイ・ブリンは共にエンジニアだ 。グーグルは「エンジニアがキングだ」という社風を持つ会社であり、その中でエンジニアにいかに力を発揮してもらうかという点において2人は抜群の能力を発揮する 。しかし、「会社経営」という点ではどちらも覚束ない。創業当初、「事業計画書を作ってくれ」と言われた2人が「何それ?」と返したというエピソードも本書では紹介されている。2人の”世話役”なくして、グーグルの成功はあり得なかった というわけだ。
本書を読めば分かるが、グーグルという会社はかなり「運」に好かれていた と言っていい。エリック・シュミットとビル・キャンベルというプロの経営者2人が関わっていたとしても、普通は乗り越えられないだろう事態が次々に起こっていたのだ。本当に、私たちが知っているようなグーグルとして今も生き残っているのは、奇跡だと言っていいだろう 。
あわせて読みたい
【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…
メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方
良いところも悪いところもすべて描き出す
著者は本書の執筆に当たり、グーグルの協力を取り付けることに苦心した と書いている。
同社は協力を渋った。共同創業者をはじめ、同社幹部は本の電子化には熱心だが、本を読むことには大して興味がないのだ。執筆に協力するのは”時間の無駄”ではないかと懸念していた。そこで私は、本書の使命はグーグルのしていることや、メディア業界をどのように変えようとしているかを理解し、説明することであり、グーグルは私のプロジェクトを検索と同じ発想で考えるべきだと訴えた。優れた本が完成すれば、検索結果の上位に表示され、多くの人の目に触れるようになる――。何ヶ月もドアを蹴飛ばしつづけた結果、彼らはようやく私を受け入れてくれた。
こうして著者は、本書執筆に至るまでにグーグル社員に対して150回以上のインタビューを行い、その内実を探ってきた 。その過程で著者は、何度も同じような質問を受けた という。
あわせて読みたい
【感涙】衆議院議員・小川淳也の選挙戦に密着する映画から、「誠実さ」と「民主主義のあり方」を考える…
『衆議院議員・小川淳也が小選挙区で平井卓也と争う選挙戦を捉えた映画『香川1区』は、政治家とは思えない「誠実さ」を放つ”異端の議員”が、理想とする民主主義の実現のために徒手空拳で闘う様を描く。選挙のドキュメンタリー映画でこれほど号泣するとは自分でも信じられない
グーグルの社員からは、自分たちにとって好ましい本になるのか、とよく聞かれた。それに対する私の答えはいつも同じで、私がきちんとした仕事をすれば、彼らにとって好ましくない事柄も含まれるだろうというものだった。
その言葉通り、本書には良い面も悪い面も書かれている 。それは創業者2人に対しても変わらない。
著者が創業者2人を絶賛する場面ももちろん多々ある 。
創業者二人に共通するのは「常識を覆すような発想をうながす能力」だ。彼らには、”並外れた洞察力”に加えて、周囲の人々の発想を刺激する才能があることに気付いたという。
あわせて読みたい
【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ
『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?
ペイジとブリンは、どこでこうしたブレのない姿勢を身につけたのだろう?
一方で、悪い面についても触れている 。その多くは、「創業者2人の『他人の気持ちを理解する能力』の欠如 」に関するものであることが多い。
またしてもブリンとペイジは、自分たちの意図を疑われる可能性を想定したり、数字では説明できない消費者の不安に耳を傾けたりする能力のなさを見事に露呈したのである。
あわせて読みたい
【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…
映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった
一人の人間の価値を、客観的な指標のみで測れるなどという考えはばかげている。これは若い起業家の例にもれず、社会人としてペイジとブリンの視野がいかに狭いかを物語る事例といえるだろう。彼らの成功の一因は、目標から頑なに目をそらさなかったことだ。だが創業前にペイジが経営の本を何冊か読んでいたとはいえ、二人の知識やモノの見方はきわめて偏っていた。
なんとなく、「理系男子」のようなイメージ をしてもらえればいいだろう。好きなことを突き詰め、途方もない成果を生み出すことには長けているが、「共感力」は低く、他人や社会の感覚を理解することには難がある 。それらを総合して著者は、彼らをこんな風に評している。
三人の優秀さや成功ぶりは人々に感動を与えるが、彼らの言葉やイメージはこころを揺さぶるものではない。彼らはスティーブ・ジョブズではないのだ。才能あるセールスマンでも、啓蒙的なリーダーでもない。
あわせて読みたい
【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…
映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う
スティーヴ・ジョブズ についての本も何冊か読んだことがあるが、彼もまた「共感力」という点ではかなり劣っている人物 だと感じた。では、ラリー・ペイジとサーゲイ・ブリンとは一体何が違うのだろう? そう考えたとき、「技術」ではなく「物語」で世界を変えようとしたジョブズのスタンスこそが大きな違いなのかもしれない と感じた。
いずれにしても、グーグルもその創業者たちもとんでもない企業・人物 であることは間違いない。そんな企業の「創世の歴史 」に触れてみてはいかがだろうか?
あわせて読みたい
【革新】天才マルタン・マルジェラの現在。顔出しNGでデザイナーの頂点に立った男の”素声”:映画『マル…
「マルタン・マルジェラ」というデザイナーもそのブランドのことも私は知らなかったが、そんなファッション音痴でも興味深く観ることができた映画『マルジェラが語る”マルタン・マルジェラ”』は、生涯顔出しせずにトップに上り詰めた天才の来歴と現在地が語られる
著:ケン・オーレッタ, 翻訳:土方 奈美
¥159 (2022/07/25 21:03時点 | Amazon調べ)
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
本書は、巻末の訳注も含めれば650ページを超えるかなりの分量 の作品だ。私は、テック系の知識にはかなり疎い方だが、それでも面白く読める作品だった。
何かとんでもない事態でも起こらない限り、私たちは永遠にグーグルという企業と関わらざるを得ない だろう。確かにグーグルは、生活を便利にする様々なサービスを生み出してくれている。しかし、グーグルがどのようなスタンスを取るかによって、一気に「悪の存在」へと変わる危険性がある のだと意識しておく必要はあるだろう。
無料で便利だからといって、何も考えずにその有益さを享受するだけでいいのか 。本書を読んで、改めてその点について考えてみるのもいいだろう。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【現実】「食」が危ない!映画『フード・インク ポスト・コロナ』が描く、大企業が操る食べ物の罠
映画『フード・インク ポスト・コロナ』は、主にアメリカの事例を取り上げながら、「私たちが直面している『食』はかなり危険な状態にある」と警告する作品だ。「アメリカ人の摂取カロリーの58%を占める」と言われる「超加工食品」の研究はダイエット的な意味でも興味深いし、寡占企業による様々な弊害は私たちにも関係してくるだろう
あわせて読みたい
【憧憬】「フランク・ザッパ」を知らずに映画『ZAPPA』を観て、「この生き様は最高」だと感じた
「フランク・ザッパ」がミュージシャンであることさえ禄に知らない状態で私が映画『ZAPPA』を観た私は、そのあまりに特異なスタンス・生き様にある種の憧憬を抱かされた。貫きたいと思う強い欲求を真っ直ぐ突き進んだそのシンプルな人生に、とにかくグッときたのだ。さらに、こんな凄い人物を知らなかった自分にも驚かされてしまった
あわせて読みたい
【ル・マン】ゲーマーが本物のカーレース出場!映画『グランツーリスモ』が描く衝撃的すぎる軌跡(ヤン…
映画『グランツーリスモ』は、「ゲーマーをレーサーにする」という、実際に行われた無謀すぎるプロジェクトを基にした作品だ。登場人物は全員イカれていると感じたが、物語としてはシンプルかつ王道で、誰もが先の展開を予想出来るだろう。しかしそれでも、圧倒的に面白かった、ちょっと凄まじすぎる映画だった
あわせて読みたい
【天才】映画『笑いのカイブツ』のモデル「伝説のハガキ職人ツチヤタカユキ」の狂気に共感させられた
『「伝説のハガキ職人」として知られるツチヤタカユキの自伝的小説を基にした映画『笑いのカイブツ』は、凄まじい狂気に彩られた作品だった。「お笑い」にすべてを捧げ、「お笑い」以外はどうでもいいと考えているツチヤタカユキが、「コミュ力」や「人間関係」で躓かされる”理不尽”な世の中に、色々と考えさせられる
あわせて読みたい
【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…
映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う
あわせて読みたい
【真実】田原総一朗✕小泉純一郎!福島原発事故後を生きる我々が知るべき自然エネルギーの可能性:映画『…
田原総一朗が元総理・小泉純一郎にタブー無しで斬り込む映画『放送不可能。「原発、全部ウソだった」』は、「原発推進派だった自分は間違っていたし、騙されていた」と語る小泉純一郎の姿勢が印象的だった。脱原発に舵を切った小泉純一郎が、原発政策のウソに斬り込み、再生可能エネルギーの未来を語る
あわせて読みたい
【歴史】NIKEのエアジョーダン誕生秘話!映画『AIR/エア』が描くソニー・ヴァッカロの凄さ
ナイキがマイケル・ジョーダンと契約した時、ナイキは「バッシュ業界3位」であり、マイケル・ジョーダンも「ドラフト3位選手」だった。今からは信じられないだろう。映画『AIR/エア』は、「劣勢だったナイキが、いかにエアジョーダンを生み出したか」を描く、実話を基にした凄まじい物語だ
あわせて読みたい
【苦悩】「やりがいのある仕事」だから見て見ぬふり?映画『アシスタント』が抉る搾取のリアル
とある映画会社で働く女性の「とある1日」を描く映画『アシスタント』は、「働くことの理不尽さ」が前面に描かれる作品だ。「雑用」に甘んじるしかない彼女の葛藤がリアルに描かれている。しかしそれだけではない。映画の「背景」にあるのは、あまりに悪逆な行為と、大勢による「見て見ぬふり」である
あわせて読みたい
【実話】実在の人物(?)をモデルに、あの世界的超巨大自動車企業の”内実”を暴く超絶面白い小説:『小…
誰もが知るあの世界的大企業をモデルに据えた『小説・巨大自動車企業トヨトミの野望』は、マンガみたいなキャラクターたちが繰り広げるマンガみたいな物語だが、実話をベースにしているという。実在の人物がモデルとされる武田剛平のあり得ない下剋上と、社長就任後の世界戦略にはとにかく驚かされる
あわせて読みたい
【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ
『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?
あわせて読みたい
【圧巻】150年前に気球で科学と天気予報の歴史を変えた挑戦者を描く映画『イントゥ・ザ・スカイ』
「天気予報」が「占い」と同等に扱われていた1860年代に、気球を使って気象の歴史を切り開いた者たちがいた。映画『イントゥ・ザ・スカイ』は、酸素ボンベ無しで高度1万1000m以上まで辿り着いた科学者と気球操縦士の物語であり、「常識を乗り越える冒険」の素晴らしさを教えてくれる
あわせて読みたい
【組織】意思決定もクリエイティブも「問う力」が不可欠だ。MIT教授がCEOから学んだ秘訣とは?:『問い…
組織マネジメントにおいては「問うこと」が最も重要だと、『問いこそが答えだ!』は主張する。MIT教授が多くのCEOから直接話を聞いて学んだ、「『問う環境』を実現するための『心理的安全性の確保』の重要性」とその実践の手法について、実例満載で説明する1冊
あわせて読みたい
【衝撃】「仕事の意味」とは?天才・野崎まどが『タイタン』で描く「仕事をしなくていい世界」の危機
「仕事が存在しない世界」は果たして人間にとって楽園なのか?万能のAIが人間の仕事をすべて肩代わりしてくれる世界を野崎まどが描く『タイタン』。その壮大な世界観を通じて、現代を照射する「仕事に関する思索」が多数登場する、エンタメ作品としてもド級に面白い傑作SF小説
あわせて読みたい
【激変】天才・藤井聡太と将棋界について加藤一二三、渡辺明が語る。AIがもたらした変化の是非は?:『…
『天才の考え方 藤井聡太とは何者か?』は、加藤一二三・渡辺明という棋界トップランナー2人が「将棋」をテーマに縦横無尽に語り合う対談本。この記事では、「AIがもたらした変化」について触れる。「答えを教えてくれるAI」は、将棋を、そして棋士をどう変えたのか?
あわせて読みたい
【貢献】社会問題を解決する2人の「社会起業家」の生き方。「豊かさ」「生きがい」に必要なものは?:『…
「ヤクの毛」を使ったファッションブランド「SHOKAY」を立ち上げ、チベットの遊牧民と中国・崇明島に住む女性の貧困問題を解決した2人の若き社会起業家の奮闘を描く『世界を変えるオシゴト』は、「仕事の意義」や「『お金』だけではない人生の豊かさ」について考えさせてくれる
あわせて読みたい
【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい
「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる
あわせて読みたい
【誇り】福島民友新聞の記者は、東日本大震災直後海に向かった。門田隆将が「新聞人の使命」を描く本:…
自身も東日本大震災の被災者でありながら、「紙齢をつなぐ」ために取材に奔走した福島民友新聞の記者の面々。『記者たちは海に向かった』では、取材中に命を落とした若手記者を中心に据え、葛藤・後悔・使命感などを描き出す。「新聞」という”モノ”に乗っかっている重みを実感できる1冊
あわせて読みたい
【抽象】「思考力がない」と嘆く人に。研究者で小説家の森博嗣が語る「客観的に考える」ために大事なこ…
世の中にはあまりに「具体的な情報」が溢れているために、「客観的、抽象的な思考」をする機会が少ない。そんな時代に、いかに思考力を育てていくべきか。森博嗣が『人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか』を通じて伝える「情報との接し方」「頭の使い方」
あわせて読みたい
【生と死】不老不死をリアルに描く映画。「若い肉体のまま死なずに生き続けること」は本当に幸せか?:…
あなたは「不老不死」を望むだろうか?私には、「不老不死」が魅力的には感じられない。科学技術によって「不老不死」が実現するとしても、私はそこに足を踏み入れないだろう。「不老不死」が実現する世界をリアルに描く映画『Arc アーク』から、「生と死」を考える
あわせて読みたい
【驚愕】これ以上の”サバイバル映画”は存在するか?火星にたった一人残された男の生存術と救出劇:『オ…
1人で火星に取り残された男のサバイバルと救出劇を、現実的な科学技術の範囲で描き出す驚異の映画『オデッセイ』。不可能を可能にするアイデアと勇気、自分や他人を信じ抜く気持ち、そして極限の状況でより困難な道を進む決断をする者たちの、想像を絶するドラマに胸打たれる
あわせて読みたい
【評価】元総理大臣・菅義偉の来歴・政治手腕・疑惑を炙り出す映画。権力を得た「令和おじさん」の素顔…
「地盤・看板・カバン」を持たずに、総理大臣にまで上り詰めた菅義偉を追うドキュメンタリー映画『パンケーキを毒見する』では、その来歴や政治手腕、疑惑などが描かれる。学生団体「ivote」に所属する現役大学生による「若者から政治はどう見えるか」も興味深い
あわせて読みたい
【差別】才ある者の能力を正しく引き出す者こそ最も有能であり、偏見から能力を評価できない者は無能だ…
「偏見・差別ゆえに、他人の能力を活かせない人間」を、私は無能だと感じる。そういう人は、現代社会の中にも結構いるでしょう。ソ連との有人宇宙飛行競争中のNASAで働く黒人女性を描く映画『ドリーム』から、偏見・差別のない社会への道筋を考える
あわせて読みたい
【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…
Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた
あわせて読みたい
【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る
地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する
あわせて読みたい
【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死
映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る
あわせて読みたい
【考察】アニメ映画『虐殺器官』は、「便利さが無関心を生む現実」をリアルに描く”無関心ではいられない…
便利すぎる世の中に生きていると、「この便利さはどのように生み出されているのか」を想像しなくなる。そしてその「無関心」は、世界を確実に悪化させてしまう。伊藤計劃の小説を原作とするアニメ映画『虐殺器官』から、「無関心という残虐さ」と「想像することの大事さ」を知る
あわせて読みたい
【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者…
世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る
あわせて読みたい
【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統…
現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ
あわせて読みたい
【天才】読書猿のおすすめ本。「いかにアイデアを生むか」の発想法を人文書に昇華させた斬新な1冊:『ア…
「独学の達人」「博覧強記の読書家」などと評される読書猿氏が、古今東西さまざまな「発想法」を1冊にまとめた『アイデア大全』は、ただのHow To本ではない。「発想法」を学問として捉え、誕生した経緯やその背景なども深堀りする、「人文書」としての一面も持つ作品だ
あわせて読みたい
【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…
「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る
あわせて読みたい
【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…
「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる
あわせて読みたい
【真実?】佐村河内守のゴーストライター騒動に森達也が斬り込んだ『FAKE』は我々に何を問うか?
一時期メディアを騒がせた、佐村河内守の「ゴースト問題」に、森達也が斬り込む。「耳は聴こえないのか?」「作曲はできるのか?」という疑惑を様々な角度から追及しつつ、森達也らしく「事実とは何か?」を問いかける『FAKE』から、「事実の捉え方」について考える
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
あわせて読みたい
【権威】心理学の衝撃実験をテレビ番組の収録で実践。「自分は残虐ではない」と思う人ほど知るべき:『…
フランスのテレビ局が行った「現代版ミルグラム実験」の詳細が語られる『死のテレビ実験 人はそこまで服従するのか』は、「権威」を感じる対象から命じられれば誰もが残虐な行為をしてしまい得ることを示す。全人類必読の「過ちを事前に回避する」ための知見を学ぶ
あわせて読みたい
【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…
科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる
あわせて読みたい
【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…
20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る
あわせて読みたい
【絶望】権力の濫用を止めるのは我々だ。映画『新聞記者』から「ソフトな独裁国家・日本」の今を知る
私個人は、「ビジョンの達成」のためなら「ソフトな独裁」を許容する。しかし今の日本は、そもそも「ビジョン」などなく、「ソフトな独裁状態」だけが続いていると感じた。映画『新聞記者』をベースに、私たちがどれだけ絶望的な国に生きているのかを理解する
あわせて読みたい
【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…
生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る
あわせて読みたい
【研究】光の量子コンピュータの最前線。量子テレポーテーションを実現させた科学者の最先端の挑戦:『…
世界中がその開発にしのぎを削る「量子コンピューター」は、技術的制約がかなり高い。世界で初めて「量子テレポーテーション」の実験を成功させた研究者の著書『光の量子コンピューター』をベースに、量子コンピューター開発の現状を知る
あわせて読みたい
【驚異】プロジェクトマネジメントの奇跡。ハリウッドの制作費以下で火星に到達したインドの偉業:映画…
実は、「一発で火星に探査機を送り込んだ国」はインドだけだ。アメリカもロシアも何度も失敗している。しかもインドの宇宙開発予算は大国と比べて圧倒的に低い。なぜインドは偉業を成し遂げられたのか?映画『ミッション・マンガル』からプロジェクトマネジメントを学ぶ
あわせて読みたい
【能力】激変する未来で「必要とされる人」になるためのスキルや考え方を落合陽一に学ぶ:『働き方5.0』
AIが台頭する未来で生き残るのは難しい……。落合陽一『働き方5.0~これからの世界をつくる仲間たちへ~』はそう思わされる一冊で、本書は正直、未来を前向きに諦めるために読んでもいい。未来を担う若者に何を教え、どう教育すべきかの参考にもなる一冊。
あわせて読みたい
【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…
一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う
あわせて読みたい
【無知】メディアの問題の本質は?「報道の限界」と「情報の受け取り方」を独裁政治の現実から知る:『…
メディアは確かに「事実」を報じている。しかし、報道に乗らない情報まで含めなければ、本当の意味で世の中を理解することは難しいと、『こうして世界は誤解する』は教えてくれる。アラブ諸国での取材の現実から、報道の「限界」と「受け取り方」を学ぶ
あわせて読みたい
【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…
小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る
あわせて読みたい
【奇跡】ビッグデータに”直感”を組み込んで活用。メジャーリーグを変えたデータ分析家の奮闘:『アスト…
「半世紀で最悪の野球チーム」と呼ばれたアストロズは、ビッグデータの分析によって優勝を果たす。その偉業は、野球のド素人によって行われた。『アストロボール』をベースに、「ビッグデータ」に「人間の直感」を組み込むという革命について学ぶ
あわせて読みたい
【諦め】「人間が創作すること」に意味はあるか?AI社会で問われる、「創作の悩み」以前の問題:『電気…
AIが個人の好みに合わせて作曲してくれる世界に、「作曲家」の存在価値はあるだろうか?我々がもうすぐ経験するだろう近未来を描く『電気じかけのクジラは歌う』をベースに、「創作の世界に足を踏み入れるべきか」という問いに直面せざるを得ない現実を考える
あわせて読みたい
【恐怖】SNSの危険性と子供の守り方を、ドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』で学ぶ
実際にチェコの警察を動かした衝撃のドキュメンタリー映画『SNS 少女たちの10日間』は、少女の「寂しさ」に付け込むおっさんどもの醜悪さに満ちあふれている。「WEBの利用制限」だけでは子どもを守りきれない現実を、リアルなものとして実感すべき
あわせて読みたい
【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…
メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
経済・企業・マーケティング【本・映画の感想】 | ルシルナ
私自身にはビジネスセンスや起業経験などはありませんが、興味があって、経済や企業の様々な事例についての本を読むようにしています。専門的な踏み込んだ描写ができるわけ…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…





















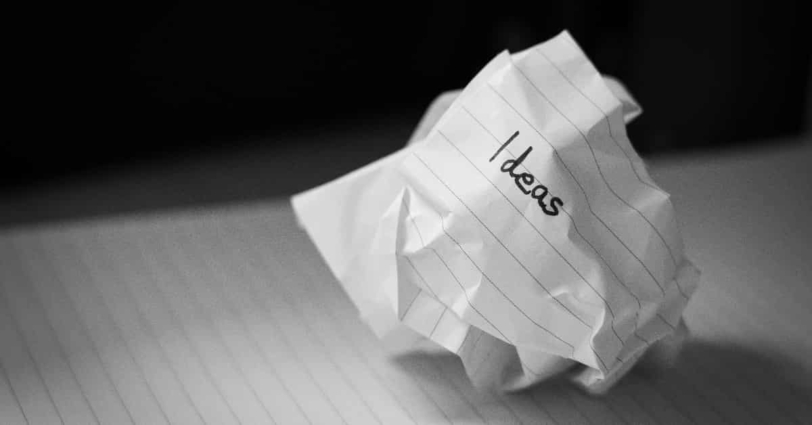












































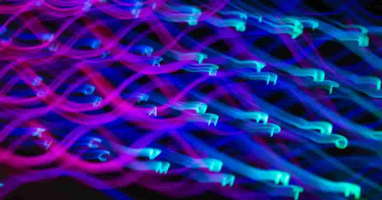
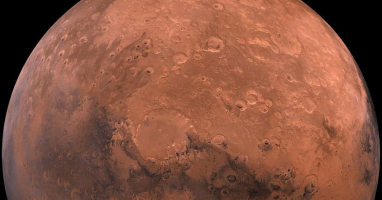

















コメント