目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
「暴力をめぐる対話」公式HP
VIDEO
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
今どこで観れるのか?
公式HPの劇場情報 をご覧ください
この記事の3つの要点
武器を持たない丸腰のデモ参加者を”過剰な暴力”で制圧する警察の振る舞いが様々な動画に収められている デモ映像に登場する人物や、社会学者・弁護士・警察関係者などが一同に介し、「暴力」や「民主主義」について深く討論を行う 日本を含めたあらゆる国で「民主主義」が危機に瀕している今、ここで議論される内容は全世界的に重要と言えるのではないかと思う 「暴力は国家のみが保持すべき」という大前提は許容するしかないと思うが、その上で、「『権力による暴力』はどの程度許容されるべきか」についての議論は必須だと改めて感じさせられた
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
民主主義を早くに根付かせたフランスでは、民主主義はもう死んでいるのではないか?映画『暴力をめぐる対話』が浮き彫りにする権力との緊張関係
本作ではとにかく、フランスという国のヤバさ が映し出される。トランプが大統領になったアメリカも相当マズい と思うが、本作『暴力をめぐる対話』が映し出すフランスの姿もまた相当にヤバい と思う。日本ではさすがにここまでの状況にはならないとは思うが、「民主主義の危機」という意味では、決して他人事ではいられない だろう。
あわせて読みたい
【称賛?】日本社会は終わっているのか?日本在住20年以上のフランス人が本国との比較で日本を評価:『…
日本に住んでいると、日本の社会や政治に不満を抱くことも多い。しかし、日本在住20年以上の『理不尽な国ニッポン』のフランス人著者は、フランスと比べて日本は上手くやっていると語る。宗教や個人ではなく、唯一「社会」だけが善悪を決められる日本の特異性について書く
映画『暴力をめぐる対話』は、「『警察による暴力』を映した映像を観ながら討論する様」をそのまま映し出すドキュメンタリー映画だ
本作『暴力をめぐる対話』は、「映像を観ながら議論する人々」をカメラに収めただけのなかなか異色のドキュメンタリー映画 である。そして彼らが観ているのは、いわゆる「黄色いベスト運動」と呼ばれる市民デモの映像 だ。「黄色いベスト運動」という名前は、本作を観る前の時点でなんとなく知っていたし、ニュース番組の中で「警察と黄色いベストを着た市民がパリの街で衝突する映像」が度々取り上げられていたな とも思う。
本作では、2018年11月から2020年2月に掛けて撮影された映像 が流される。そしてデモの映像に映っている人物を始め、社会学者、弁護士、警察関係者などが一同に介し、映像を観ながら討論している様子 を捉えたのが、本作『暴力をめぐる対話』というわけだ。討論の様子をそのままドキュメンタリーとして提示するというのは、劇場公開される映画としてはかなり珍しい ように思う。
あわせて読みたい
【絶望】安倍首相へのヤジが”排除”された衝撃の事件から、日本の民主主義の危機を考える:映画『ヤジと…
映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』が映し出すのは、「政治家にヤジを飛ばしただけで国家権力に制止させられた個人」を巡る凄まじい現実だ。「表現の自由」を威圧的に抑えつけようとする国家の横暴は、まさに「民主主義」の危機を象徴していると言えるだろう。全国民が知るべき、とんでもない事件である
さて、ではその「討論」の主題は何だろうか? それは「警察による暴力 」である。
デモの映像を見れば誰もがそう感じると思うが、フランスの警察は市民に対しかなり酷い扱いをしていた 。デモに参加しているとはいえ市民 であり、さらに、程度問題はあるものの「デモそのもの」は権利として認められているはず だ。そんな市民に対する扱いとしては、ちょっと考えられないぐらい酷かった なと思う。
さて、警察側にも当然言い分はある のだが、まずはデモの映像を素直に捉えた場合の一般的だろう印象 について書いておこう。デモ参加者は基本的に武器を所持していない 。これまで、デモ参加者による銃の所持は一度も確認されていない そうだ。確かに、デモ参加者の振る舞いは暴力的 だ。素手で警官を殴り、また集団で襲いかかって威圧もする 。さらに、「金持ちの象徴」であるブランド店を破壊 したりもしていた。それらはもちろん褒められた行為ではない し、やり過ぎ だとも思う。とはいえ、警察の振る舞いはさらに輪をかけて過剰 だというのが私の印象である。
あわせて読みたい
【不正義】正しく行使されない権力こそ真の”悪”である。我々はその現実にどう立ち向かうべきだろうか:…
権力を持つ者のタガが外れてしまえば、市民は為す術がない。そんな状況に置かれた時、私たちにはどんな選択肢があるだろうか?白人警官が黒人を脅して殺害した、50年前の実際の事件をモチーフにした映画『デトロイト』から、「権力による不正義」の恐ろしさを知る
警察は「デモによる暴動の鎮圧」と「治安維持」を大義名分に暴力を行使する のだが、武器を持たない丸腰の人間に対するものとしてはちょっとやり過ぎ だと思う。なにせ、使用が禁止されているゴム弾で怪我を負ったり、催涙弾の爆発で手を失ってしまった者もいる くらいなのだ。映画の最後には、「2018年11月から2020年2月の間だけでも、2つの命、5つの手、27個の目が失われた 」という内容の字幕が表記された。「治安維持」で片付けるには、ちょっと犠牲のバランスが合わない ように思う。
討論に参加した「被害者」や「低所得者」は、「警察はエリートしか守らない 」「自分たちは、警察が権力を行使するための実験場にいる 」みたいな表現で警察を非難していた 。また、ある学者は「フランスにおける警察による暴力は過剰さを増している 」みたいなことを言っていたし、普通に考えれば「警察の振る舞いの方がヤバい」という見方になるはず だと思う。
警察側の人間は討論の場で反論するような主張をしていた が、個人的にはあまりしっくり来るものではない と感じた。「警察がデモ参加者に襲われている映像」に対して「この時の警察の振る舞いの何が過剰な暴力なんだ?」みたいなことを言ったりするのだが、全体としてはそういう「警察がデモ参加者に襲われている状況」の方が圧倒的に少ない (少なくとも映画で扱われていた限りは)。また、「ネット上にアップされているのは警察が暴力を振るっている場面ばかりだが、その前後はどうなってるんだ? 」みたいなことも言っていた。要するに、「作為的に切り取られているだけだ」という主張 である。しかし、本作中で使われているデモの映像はかなり長回しのもの であり、これもまた的を射ていない ように感じられた。
あわせて読みたい
【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す
香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す
誤解がないように書いておくが、私は決して「デモ側に問題が無い」などと主張しているのではない 。デモ側も大いに問題だ。ただ、「デモ側と警察側の問題を比較した場合に、圧倒的に警察側の問題の方が大きい」というのが私の感触 なのである。
では、マクロン大統領はこの状況にどのような反応を示しているのだろうか 。彼はどうやら、「フランスは法治国家なのだから、警察による暴力など存在しない」と主張している ようだ。いや、さすがにそれは無理がある だろう。本作で使われているものも含め、証拠の映像が多数存在している からだ。それら個別の映像に対してマクロン大統領がどんな主張をしているのかは分からないが、いずれにせよ、政権側は「暴徒を抑え込むためには必要な措置だった」という主張をどうにか押し通そうとしている のだと思う。
デモの映像を実際に観てみないとなんとも言えないだろうが、私の感触としては「フランス、マジでヤベェな」という感じ だった。これほどまでに圧倒的な「暴力」を警察(権力)が行使しているにも拘らず、その現状を認めないばかりか、そのまま押し通そうとしている のだから。
あわせて読みたい
【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件
映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった
ちなみに、ある人物が話していたのだが、国際的な「民主主義ランキング」において、フランスの評価は格下げされてしまった のだという。元々は「完全な民主主義」だった のが、今は「欠陥のある民主主義」という評価 になっているそうだ。この討論には国連の関係者も参加していた のだが、彼は現在のフランスの状況を踏まえ、「『人権の国フランスでここまでやれるなら、自分たちももっとやっちゃっていいんじゃないか』と考えるアフリカ諸国が出てきてもおかしくない 」みたいな懸念を示していた。
本作を観るまで全然知らなかったが、フランスの民主主義は相当危険な状況に陥っている ようである。
「民主主義の根本」を問う、ある女性参加者の視点
さて、ここで少し本作の構成や討論の雰囲気 に触れておこうと思う。
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
本作で映し出される討論の内容はかなり高度 だった。ハンナ・アーレントやマックス・ヴェーバーの引用 がバンバン出てきたり、現実の問題から離れた「理論」についての話 になったりと、かなり難解なやり取りが多かった印象 だ。私は普段、映画館でメモを取りながら映画を観ている のだが、普段なら出来る「字幕の内容を理解し、同時にメモする」という作業がかなり難しかった 。それぐらい、まず「理解する」という点で躓いてしまうような高度なやり取り が展開されていたのである。
その上で本作は、さらに挑戦的な構成 になっていた。というのも、状況や討論参加者について一切何も説明しない のだ。フランス制作の映画だから、「黄色いベスト運動」についての説明がないのは当然 だろうが、恐らく一般的に広く知られてはいないだろう人物も多数討論に参加しているにも拘らず、字幕などでその肩書きが表記されたりはしない 。映画の最後で討論参加者の紹介はなされるものの、まさに討論をしている最中には、彼らが一体誰で、どのような立場の人物なのかまったく理解できない のだ。さらに討論の中身についても、「今何が議題に上がっているのか?」みたいなことを整理するような情報はまったくない 。ひたすら「参加者による発言」だけが映し出される というわけだ。
つまり本作は、とにかく徹底して「デモの映像」と「討論」のみを提示する作品 であり、そのことによって一層難解さは増している と言えるだろうが、個人的には面白い趣向 だと感じた。
あわせて読みたい
【アート】「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」(森美術館)と「美術手帖 Chim↑Pom特集」の衝撃から「…
Chim↑Pomというアーティストについてさして詳しいことを知らずに観に行った、森美術館の「Chim↑Pom展:ハッピースプリング」に、思考をドバドバと刺激されまくったので、Chim↑Pomが特集された「美術手帖」も慌てて買い、Chim↑Pomについてメッチャ考えてみた
さて、そんな討論において、私が個人的に最も納得感を抱いた主張が、高齢の白髪女性のもの である。彼女についても討論中は誰なのかさっぱり分からなかったのだが、最後の紹介では「公法 名誉教授」と記載されていた と思う。「公法」というのは、「憲法」や「刑法」など、私たちが普段「法律」と読んでいるもの全般 を指していると捉えればいいだろう。そして彼女は、大雑把に次のような主張をしていた のだ。
民主主義というのは「社会分裂」を容認する仕組みだ。だから警察は、「多様性の保証」に努めるべきである。
「意見の相違が存在する状態」こそが民主主義なのであり、全員の意見が一致していたとしたら、その民主主義には何か問題がある。何かが自由を侵害しているのです。
あわせて読みたい
【問題】映画『国葬の日』が切り取る、安倍元首相の”独裁”が生んだ「政治への関心の無さ」(監督:大島新)
安倍元首相の国葬の1日を追ったドキュメンタリー映画『国葬の日』は、「国葬」をテーマにしながら、実は我々「国民」の方が深堀りされる作品だ。「安倍元首相の国葬」に対する、全国各地の様々な人たちの反応・価値観から、「『ソフトな独裁』を維持する”共犯者”なのではないか」という、我々自身の政治との向き合い方が問われているのである
この主張は、討論全体のテーマである「警察による暴力」からは少し外れている かもしれないが、しかし、結局のところ問題の本質は「民主主義とは何か?」にある わけで、そういう包括的な意味で投げかけられた意見 だと思う。そして、私はこのシンプルな主張に強く賛同させられた 。まさにその通りという感じだ。
「黄色いベスト運動」に対するフランス政府のスタンスは、「自分たちに反対する者はすべて敵」という感じ なのだと思う。日本でも、安倍晋三が首相だった頃は特にそういう印象が強かった 気がする。そしてフランス政府は、そんな「敵」を排除しようとして警察権力を行使している のだ。このような構図であることは認めざるを得ないだろう。討論の参加者の1人も、「これは政治的な問題なのに、あらゆる声明や対処が”非政治的なもの”に置き換えられている」という言い方で政府を非難していた 。
民主主義である以上、必ず「自分に反対する者」は存在する 。そんな存在を「敵」と捉えるのであれば、民主主義など成り立つはずがない だろう。しかしそのような「民主主義の根幹」が、フランスだけではなくあらゆる国で成立しなくなっている ように感じられる。公法の専門家である白髪の女性は、「暴動は民主主義の生命線 」という表現を使っていた。民主主義が正しく成り立つためには、「暴動(の可能性)」は必要不可欠 というわけだ。だからこそ、そんな「暴動」を公権力によって押さえつけてしまうのは間違い だと私は思う。
あわせて読みたい
【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り
プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品
相手に「お前は暴力的だ」と正当に主張できるのは一体誰なのか?
さて、もちろん「治安維持を疎かにしていい」なんて話をしたいのではない 。「暴動」を野放しにすれば、「民主主義の危機」以上に社会に問題が生まれ得る だろう。だから対処する必要があるのだが、とはいえ、「武器を持たない人間をゴム弾で撃つ」ことが「治安維持」として正解だとも思えない 。なかなか難しい問題 である。
この点に関連して、ある人物がなかなか興味深い論点 を提示していた。それは、「『お前は暴力的だ』と正当に主張できるのは誰なのか? 」である。これは実に面白い問い だと言えるだろう。
「黄色いベスト運動」における問題というのは結局、「両サイドが『お前は暴力的だ』と主張している 」という点にあると言っていい。警察は「デモ側が暴力的だから、治安を維持するにはこちらも暴力を行使するしかない」と言っており 、デモ側も「警察が暴力的だから、それに対抗するにはこちらも暴力的にならざるを得ない」と主張している 。どちらかの主張が正しいのだとして、果たしてその「正しさ」はどのように判定されるのだろうか?
あわせて読みたい
【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』
2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない
確かに、この点がクリアになれば、感情的に相手を非難することなく善悪を判断出来る だろう。しかし作中では、この問いに明確な答えを出す参加者はいなかった ように思う。確かに難しい問い である。「どんな場合であれ、『権力側の暴力』のみが合法である」などとすれば権力の暴走を抑えられない し、かといって「何が『許される暴力』で何が『許されない暴力』なのか」という基準を示すのも難しい 。
マックス・ヴェーバーの言葉 だったと思うが、討論の冒頭で「国家とは、合法的に暴力を保持するものだ」というような言葉 が表示される。恐らく、討論参加者のほとんどが(そして観客の多くも)、この主張そのものには賛同出来るはず だ。ただ、「そうだとしても今のフランス警察のスタンスは許容できない」という点が問題 なのであり、それこそが討論の焦点 なのである。「『暴力の保持』を前提とする国家に対し、どのようなアプローチを取れば現状の抑制・改善に繋がるのか」が最も重要な問い であり、本作ではそれらについて多くの人が理論的に、あるいは現実サイドから様々な意見を出し合う討論が行われていた というわけだ。
「暴力」に対する「抑圧」「予防」という異なる対処の仕方
さて、討論の中でもう1つ興味深かったのが、「抑圧」と「予防」に関する話 である。これは、マクロン大統領がプーチン大統領と会談する映像を観ながら展開されていたやり取り だ。
あわせて読みたい
【弾圧】香港デモの象徴的存在デニス・ホーの奮闘の歴史。注目の女性活動家は周庭だけじゃない:映画『…
日本で香港民主化運動が報じられる際は周庭さんが取り上げられることが多いが、香港には彼女よりも前に民主化運動の象徴的存在として認められた人物がいる。映画『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』の主人公であるスター歌手の激動の人生を知る
民主主義国家であるフランスでは、当然「デモの権利」が認められており 、だからこそ「起こったデモを抑圧する」という対応 になる。まあ当然の話 だろう。しかしロシアでは違う 。「デモが起こる前に、予防的に人々を拘束・逮捕する」という対処 になるのだ。この比較で言うなら、「抑圧」のフランスの方が圧倒的に民主主義的 と言えるだろう。ただ討論の参加者から、「これからの民主主義は、『抑圧』から『予防』のスタンスに変化していくのではないか 」という意見が出た。「民主主義の形」そのものが変わっていくんじゃないか というわけだ。
そしてそうだとするなら、「警察による過剰な暴力」は、その変化の途上 と捉えることも出来るかもしれない。しかしそれはなかなかに恐ろしい想像 であり、だからこそ余計に、デモの映像に収められた警察の振る舞いを許容したくない なと感じられてしまう。
日本での本作の公開は2022年 なのだが、この文章を書いている2025年の方が一層「民主主義」は危機に瀕している ように思う。特に、ドナルド・トランプが大統領に就任して以降、その危うさが益々顕在化している と言っていいのではないだろうか。そしてそんな時代だからこそ私たちは、「『権力による暴力』をどこまで許容するか」について、改めて考えるべき なのだと思う。
あわせて読みたい
【異様】映画『聖なるイチジクの種』は、イランで起こった実際の市民デモを背景にした驚愕の物語である
「家庭内で銃を紛失した」という設定しか知らずに観に行った映画『聖なるイチジクの種』は、「実際に起こった市民デモをベースに、イランという国家の狂気をあぶり出す作品」であり、思いがけず惹きつけられてしまった。「反政府的な作品」に関わった本作監督・役者・スタッフらが処罰されるなど、人生を賭けて生み出された映画でもある
討論の参加者の1人は、ルソーの社会契約論を引き合いに出し、「私は『権力による暴力』の被害を受けることを許容する。それは安全を確保したいからだ。それが社会契約である」と主張していた 。確かに、理屈としては私もこの主張に賛同できる 。個人の視点ではなく社会的な観点から捉えれば、「国家が暴力を独占的に有し、それによって国民の安全を担保する」というやり方が最善 だろう。国家と国民がこのような「契約」を結ぶことで、民主主義国家は正常に機能する というわけだ。
ただこの主張に対して、「当事者の一方が正しく契約を履行していないのではないか?」という意見 も出て、それにも納得させられた。確かに、「国家が“正しく”暴力を独占的に有する」からこそこの契約は機能する のであり、その「正しく」の部分に疑義が生じるのであれば、そんな契約成り立つはずもない 。
日本の場合、「警察が直接的に市民に暴力を振るう」という状況はそう多くないはず なので、このような問題はまだ顕在化していないと言えるだろう。しかし、民主主義国家が様々に揺れる中で、日本もまたこの問いから逃れられはしない とも思う。深刻な状況に陥る前に、何らかの形で国民的な議論がなされればいい なと思うが、実際には難しいだろう。一筋縄ではいかない問題 だなと思う。
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
本作『暴力をめぐる対話』の最後に、監督による5分ほどのトーク映像が流れた 。日本向けに新たに撮影し追加されたもの のようだ。監督は、「大規模なデモが50年以上も行われていない日本と、デモが日常茶飯事であるフランスとでは基本的な考え方が大きく違うはずだ 」としながらも、「『あらゆる国で民主主義が後退している』という現実がある中で日本も他人事ではいられないはずだ」というような主旨の発言 をしていた。加えて、これは映画の冒頭で説明してくれても良かったんじゃないかと感じたが、日本人には馴染みの薄い「黄色いベスト運動」の基本情報についての紹介もある 。
先述した通り、かなり難しい討論でついていくのが大変だった が、討論のベースとなるデモの映像はなかなかのインパクト で、SNS時代だからこそこうして表に出てきた のだろうなと思う。そしてそんな映像がきちんと残っているからこそ、客観的な事実を基に討論を行うことも可能 なわけで、そういう意味でも有意義な討論 と言えるかもしれない。何にせよ、色々と考えさせられる映画 だった。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【不寛容】カルトと呼ばれた「イエスの方舟」の現在は?「理解できなければ排除する社会」を斬る映画:…
映画『方舟にのって』は、1980年に社会を騒がせ、「ハーレム教団」「セックスカルト教団」と呼ばれて大問題となった「イエスの方舟」の現在を追うドキュメンタリー映画だ。そして、そんな本作が本当に映し出してるのは「大衆」の方である。「『理解できないもの』は排除する」という社会に対する違和感を改めて浮き彫りにする1作
あわせて読みたい
【未来】6度目の大量絶滅時代を生きる今、映画『アニマル』を観て気候変動の現状と対策を知るべき
映画『アニマル ぼくたちと動物のこと』は、環境問題や気候変動の現状・問題を改めて突きつけるドキュメンタリーだ。16歳の若き環境活動家2人が世界中を巡り、現状を確認したり専門家に話を聞いたりする構成で、彼らはその過程で「誰も『解決策』を持っていない」と知り驚かされる。これからどう生きるべきか考えさせられる作品だ
あわせて読みたい
【評価】都知事選出馬、安芸高田市長時代の「恥を知れ」などで知られる石丸伸二を描く映画『掟』
石丸伸二をモデルに描くフィクション映画『掟』は、「地方政治に無関心な人」に現状の酷さを伝え、「自分ごと」として捉えてもらうきっかけとして機能し得る作品ではないかと感じた。首長がどれだけ変革しようと試みても、旧弊な理屈が邪魔をして何も決まらない。そんな「地方政治の絶望」が本作には詰め込まれているように思う
あわせて読みたい
【権力】コンクラーベをリアルに描く映画『教皇選挙』は、ミステリ的にも秀逸で面白い超社会派物語(監…
映画『教皇選挙』は、「カトリックの教皇を選ぶコンクラーベ」という、一般的な日本人にはまず馴染みのないテーマながら劇場が満員になるほどで、まずそのことに驚かされた。本質的には「権力争い」なのだが、そこに「神に仕える者」という宗教ならではの要素が組み込まれることによって特異で狂気的な状況が生み出されている
あわせて読みたい
【実話】不可能を成し遂げた男を描く映画『愛を耕すひと』は、愛を知るための長い旅路の物語でもある(…
映画『愛を耕すひと』は、18世紀のデンマークを舞台に、「不可能」とまで言われた「ユトランド半島の開拓」を成し遂げたルドヴィ・ケーレンを描き出す物語だ。とはいえ「偉人の伝記」のような内容ではない。嫌がらせをしてくる貴族や、迷信を信じる者たちからの不信感などと闘いながら「愛」を知っていく、実に印象的な物語である
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『ソウルの春』は、軍部が反乱を起こした衝撃の実話「粛清クーデター」の真相を描く(…
映画『ソウルの春』は、「これが実話!?」と感じるほど信じがたい史実が描かれる作品だ。韓国が軍事政権下にあったことは当然知っていたが、まさかこんな感じだったとは。「絶対的な正義 VS 絶対的な悪」みたいな展開で、「絶対にこうなるはず!」と思い込んでいたラストにならなかったことも、個人的には衝撃的すぎた
あわせて読みたい
【友情】映画『ノー・アザー・ランド』が映し出す酷すぎる現実。イスラエル軍が住居を壊す様は衝撃だ
イスラエルのヨルダン川西岸地区内の集落マサーフェル・ヤッタを舞台にしたドキュメンタリー映画『ノー・アザー・ランド』では、「昔からその場所に住み続けているパレスチナ人の住居をイスラエル軍が強制的に破壊する」という信じがたい暴挙が映し出される。そんな酷い現状に、立場を越えた友情で立ち向かう様を捉えた作品だ
あわせて読みたい
【異様】映画『聖なるイチジクの種』は、イランで起こった実際の市民デモを背景にした驚愕の物語である
「家庭内で銃を紛失した」という設定しか知らずに観に行った映画『聖なるイチジクの種』は、「実際に起こった市民デモをベースに、イランという国家の狂気をあぶり出す作品」であり、思いがけず惹きつけられてしまった。「反政府的な作品」に関わった本作監督・役者・スタッフらが処罰されるなど、人生を賭けて生み出された映画でもある
あわせて読みたい
【忌避】小児性愛者から子どもを救え!映画『サウンド・オブ・フリーダム』が描く衝撃の実話(主演:ジ…
映画『サウンド・オブ・フリーダム』は、世界的に大問題となっている「子どもの人身売買」を扱った、実話を基にした物語である。「フィクションとしか思えないようなおとり捜査」を実行に移した主人公の凄まじい奮闘と、「小児性愛者の変態的欲望」の餌食になる悲惨な子どもたちの現実をリアルに描き出していく
あわせて読みたい
【解説】映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、凄まじい臨場感で内戦を描き、我々を警告する(…
映画『シビル・ウォー』は、「アメリカで勃発した内戦が長期化し、既に日常になってしまっている」という現実を圧倒的な臨場感で描き出す作品だ。戦争を伝える報道カメラマンを主人公に据え、「戦争そのもの」よりも「誰にどう戦争を伝えるか」に焦点を当てる本作は、様々な葛藤を抱きながら最前線を目指す者たちを切り取っていく
あわせて読みたい
【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実
映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた
あわせて読みたい
【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞
映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である
あわせて読みたい
【正義?】FBIが警告した映画『HOW TO BLOW UP』は環境活動家の実力行使をリアルに描き出す
映画『HOW TO BLOW UP』は、「テロを助長する」としてFBIが警告を発したことでも話題になったが、最後まで観てみると、エンタメ作品として実に見事で、とにかく脚本が優れた作品だった。「環境アクティビストが、石油パイプラインを爆破する」というシンプルな物語が、見事な脚本・演出によって魅力的に仕上がっている
あわせて読みたい
【実話】映画『ダム・マネー ウォール街を狙え!』は「株で大儲けした」だけじゃない痛快さが面白い
ダム・マネー ウォール街を狙え!』では、株取引で莫大な利益を得た実在の人物が取り上げられる。しかし驚くべきは「大金を得たこと」ではない。というのも彼はなんと、資産5万ドルの身にも拘らず、ウォール街の超巨大資本ファンドを脅かす存在になったのである! 実話とは思えない、あまりにも痛快な物語だった
あわせて読みたい
【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件
映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
あわせて読みたい
【日本】原発再稼働が進むが、その安全性は?樋口英明の画期的判決とソーラーシェアリングを知る:映画…
映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』では、大飯原発の運転差し止め判決を下した裁判長による画期的な「樋口理論」の説明に重点が置かれる。「原発の耐震性」に関して知らないことが満載で、実に興味深かった。また、農家が発案した「ソーラーシェアリング」という新たな発電方法も注目である
あわせて読みたい
【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…
映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う
あわせて読みたい
【感想】関東大震災前後を描く映画『福田村事件』(森達也)は、社会が孕む「思考停止」と「差別問題」…
森達也監督初の劇映画である『福田村事件』は、100年前の関東大震災直後に起こった「デマを起点とする悲劇」が扱われる作品だ。しかし、そんな作品全体が伝えるメッセージは、「100年前よりも現代の方がよりヤバい」だと私は感じた。SNS時代だからこそ意識すべき問題の詰まった、挑発的な作品である
あわせて読みたい
【脅迫】原発という巨大権力と闘ったモーリーン・カーニーをイザベル・ユペールが熱演する映画『私はモ…
実話を基にした映画『私はモーリーン・カーニー』は、前半の流れからはちょっと想像もつかないような展開を見せる物語だ。原発企業で従業員の雇用を守る労働組合の代表を務める主人公が、巨大権力に立ち向かった挙げ句に自宅で襲撃されてしまうという物語から、「良き被害者」という捉え方の”狂気”が浮かび上がる
あわせて読みたい
【絶望】安倍首相へのヤジが”排除”された衝撃の事件から、日本の民主主義の危機を考える:映画『ヤジと…
映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』が映し出すのは、「政治家にヤジを飛ばしただけで国家権力に制止させられた個人」を巡る凄まじい現実だ。「表現の自由」を威圧的に抑えつけようとする国家の横暴は、まさに「民主主義」の危機を象徴していると言えるだろう。全国民が知るべき、とんでもない事件である
あわせて読みたい
【現実】我々が食べてる魚は奴隷船が獲ったもの?映画『ゴースト・フリート』が描く驚くべき漁業の問題
私たちは、「奴隷」が獲った魚を食べているのかもしれない。映画『ゴースト・フリート』が描くのは、「拉致され、数十年も遠洋船上に隔離されながら漁をさせられている奴隷」の存在だ。本作は、その信じがたい現実に挑む女性活動家を追うドキュメンタリー映画であり、まさに世界が関心を持つべき問題だと思う
あわせて読みたい
【絶望】映画『少年たちの時代革命』が描く、香港デモの最中に自殺者を救おうとした若者たちの奮闘
香港の民主化運動の陰で、自殺者を救出しようと立ち上がったボランティア捜索隊が人知れず存在していた。映画『少年たちの時代革命』はそんな実話を基にしており、若者の自殺が急増した香港に様々な葛藤を抱えながら暮らし続ける若者たちのリアルが切り取られる作品だ
あわせて読みたい
【抵抗】若者よ、映画『これは君の闘争だ』を見ろ!学校閉鎖に反対する学生運動がブラジルの闇を照らす
映画『これは君の闘争だ』で描かれるのは、厳しい状況に置かれた貧困層の学生たちによる公権力との闘いだ。「貧困層ばかりが通う」とされる公立校が大幅に再編されることを知った学生が高校を占拠して立て籠もる決断に至った背景を、ドキュメンタリー映画とは思えないナレーションで描く異色作
あわせて読みたい
【驚愕】本屋大賞受賞作『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は凄まじい。戦場は人間を”怪物”にする
デビュー作で本屋大賞を受賞した『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は、デビュー作であることを抜きにしても凄まじすぎる、規格外の小説だった。ソ連に実在した「女性狙撃兵」の視点から「独ソ戦」を描く物語は、生死の境でギリギリの葛藤や決断に直面する女性たちのとんでもない生き様を活写する
あわせて読みたい
【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…
ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?
あわせて読みたい
【信念】映画『ハマのドン』の主人公、横浜港の顔役・藤木幸夫は、91歳ながら「伝わる言葉」を操る
横浜港を取り仕切る藤木幸夫を追うドキュメンタリー映画『ハマのドン』は、盟友・菅義偉と対立してでもIR進出を防ごうとする91歳の決意が映し出される作品だ。高齢かつほとんど政治家のような立ち位置でありながら、「伝わる言葉」を発する非常に稀有な人物であり、とても興味深かった
あわせて読みたい
【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る
TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す
あわせて読みたい
【爆笑】ダースレイダー✕プチ鹿島が大暴れ!映画『センキョナンデス』流、選挙の楽しみ方と選び方
東大中退ラッパー・ダースレイダーと新聞14紙購読の時事芸人・プチ鹿島が、選挙戦を縦横無尽に駆け回る様を映し出す映画『劇場版 センキョナンデス』は、なかなか関わろうとは思えない「選挙」の捉え方が変わる作品だ。「フェスのように選挙を楽しめばいい」というスタンスが明快な爆笑作
あわせて読みたい
【驚異】映画『RRR』『バーフバリ』は「観るエナジードリンク」だ!これ程の作品にはなかなか出会えないぞ
2022年に劇場公開されるや、そのあまりの面白さから爆発的人気を博し、現在に至るまでロングラン上映が続いている『RRR』と、同監督作の『バーフバリ』は、大げさではなく「全人類にオススメ」と言える超絶的な傑作だ。まだ観ていない人がいるなら、是非観てほしい!
あわせて読みたい
【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態
ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない
あわせて読みたい
【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す
香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す
あわせて読みたい
【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ
ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ
あわせて読みたい
【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作
大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい
あわせて読みたい
【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』
2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない
あわせて読みたい
【衝撃】権力の濫用、政治腐敗を描く映画『コレクティブ』は他人事じゃない。「国家の嘘」を監視せよ
火災で一命を取り留め入院していた患者が次々に死亡した原因が「表示の10倍に薄められた消毒液」だと暴き、国家の腐敗を追及した『ガゼタ』誌の奮闘を描く映画『コレクティブ 国家の嘘』は、「権力の監視」が機能しなくなった国家の成れの果てが映し出される衝撃作だ
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【驚愕】キューバ危機の裏側を描くスパイ映画『クーリエ』。核戦争を回避させた民間人の衝撃の実話:『…
核戦争ギリギリまで進んだ「キューバ危機」。その陰で、世界を救った民間人がいたことをご存知だろうか?実話を元にした映画『クーリエ:最高機密の運び屋』は、ごく普通のセールスマンでありながら、ソ連の膨大な機密情報を盗み出した男の信じがたい奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【日常】難民問題の現状をスマホで撮る映画。タリバンから死刑宣告を受けた監督が家族と逃避行:『ミッ…
アフガニスタンを追われた家族4人が、ヨーロッパまで5600kmの逃避行を3台のスマホで撮影した映画『ミッドナイト・トラベラー』は、「『難民の厳しい現実』を切り取った作品」ではない。「家族アルバム」のような「笑顔溢れる日々」が難民にもあるのだと想像させてくれる
あわせて読みたい
【民主主義】占領下の沖縄での衝撃の実話「サンマ裁判」で、魚売りのおばぁの訴えがアメリカをひっかき…
戦後の沖縄で、魚売りのおばぁが起こした「サンマ裁判」は、様々な人が絡む大きな流れを生み出し、最終的に沖縄返還のきっかけともなった。そんな「サンマ裁判」を描く映画『サンマデモクラシー』から、民主主義のあり方と、今も沖縄に残り続ける問題について考える
あわせて読みたい
【残念】日本の「難民受け入れ」の現実に衝撃。こんな「恥ずべき国」に生きているのだと絶望させられる…
日本の「難民認定率」が他の先進国と比べて異常に低いことは知っていた。しかし、日本の「難民」を取り巻く実状がこれほど酷いものだとはまったく知らなかった。日本で育った2人のクルド人難民に焦点を当てる映画『東京クルド』から、日本に住む「難民」の現実を知る
あわせて読みたい
【真実】ホロコーストが裁判で争われた衝撃の実話が映画化。”明らかな虚偽”にどう立ち向かうべきか:『…
「ホロコーストが起こったか否か」が、なんとイギリスの裁判で争われたことがある。その衝撃の実話を元にした『否定と肯定』では、「真実とは何か?」「情報をどう信じるべきか?」が問われる。「フェイクニュース」という言葉が当たり前に使われる世界に生きているからこそ知っておくべき事実
あわせて読みたい
【驚愕】正義は、人間の尊厳を奪わずに貫かれるべきだ。独裁政権を打倒した韓国の民衆の奮闘を描く映画…
たった30年前の韓国で、これほど恐ろしい出来事が起こっていたとは。「正義の実現」のために苛烈な「スパイ狩り」を行う秘密警察の横暴をきっかけに民主化運動が激化し、独裁政権が打倒された史実を描く『1987、ある闘いの真実』から、「正義」について考える
あわせて読みたい
【勇敢】”報道”は被害者を生む。私たちも同罪だ。”批判”による”正義の実現”は正義だろうか?:『リチャ…
「爆弾事件の被害を最小限に食い止めた英雄」が、メディアの勇み足のせいで「爆弾事件の犯人」と報じられてしまった実話を元にした映画『リチャード・ジュエル』から、「他人を公然と批判する行為」の是非と、「再発防止という名の正義」のあり方について考える
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
あわせて読みたい
【絶望】権力の濫用を止めるのは我々だ。映画『新聞記者』から「ソフトな独裁国家・日本」の今を知る
私個人は、「ビジョンの達成」のためなら「ソフトな独裁」を許容する。しかし今の日本は、そもそも「ビジョン」などなく、「ソフトな独裁状態」だけが続いていると感じた。映画『新聞記者』をベースに、私たちがどれだけ絶望的な国に生きているのかを理解する
あわせて読みたい
【正義】マイノリティはどう生き、どう扱われるべきかを描く映画。「ルールを守る」だけが正解か?:映…
社会的弱者が闘争の末に権利を勝ち取ってきた歴史を知った上で私は、闘わずとも権利が認められるべきだと思っている。そして、そういう社会でない以上、「正義のためにルールを破るしかない」状況もある。映画『パブリック』から、ルールと正義のバランスを考える
あわせて読みたい
【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…
歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る
あわせて読みたい
【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像
1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ
あわせて読みたい
【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…
一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
戦争・世界情勢【本・映画の感想】 | ルシルナ
日本に生きているとなかなか実感できませんが、常に世界のどこかで戦争が起こっており、なくなることはありません。また、テロや独裁政権など、世界を取り巻く情勢は様々で…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…


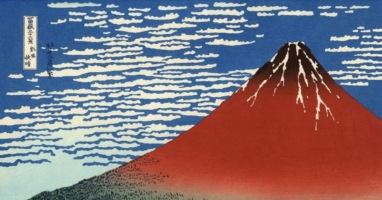














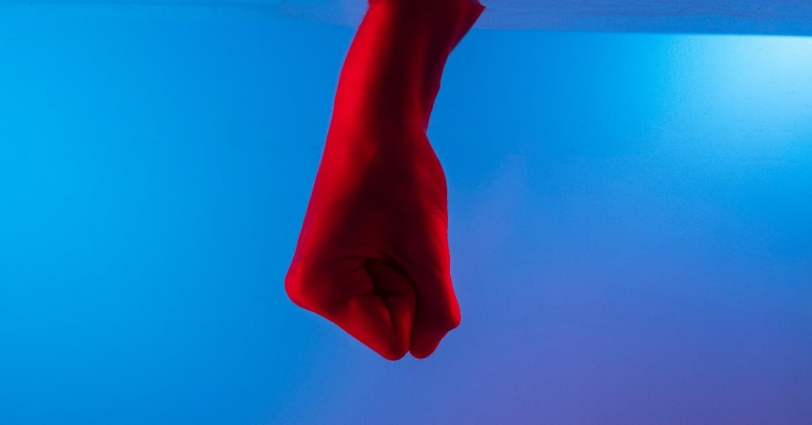































































コメント