目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
監督:コリン・ケアンズ, 監督:キャメロン・ケアンズ, Writer:コリン・ケアンズ, Writer:キャメロン・ケアンズ, 出演:デヴィッド・ダストマルチャン, 出演:ローラ・ゴードン, 出演:フェイザル・バジ, 出演:イアン・ブリス, 出演:イングリッド・トレリ, 出演:リース・アウテーリ
¥500 (2025/05/10 20:19時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 鳴り物入りで始まり、結果として視聴率競争に苦戦することになった『ナイト・オウルズ』という深夜番組についてまずは説明される
- 本作の大部分は、視聴率低迷の打開策として期待されていたハロウィンの夜の放送回「悪魔と夜ふかし」をそのまま流しているというテイで展開される
- CM中の舞台裏の様子がモノクロで挿入され、その構成によって、観客がさらに幻惑させられていく
「本当にこんな番組が存在したのではないか?」と感じさせるリアルな雰囲気があり、実に興味深かった
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
映画『悪魔の夜ふかし』は、「1970年代の生放送番組」を再現し、その中で「悪魔の召喚」が行われる、実に奇妙なモキュメンタリーである
「架空のテレビ番組」をベースにした実にリアルな設定
なかなか面白いモキュメンタリー(フェイクドキュメンタリー)だった。本作では、「1970年代に放送されていた(という設定の)生放送番組『ナイト・オウルズ(Night Owls)』という生放送番組」が物語の舞台となる。そして「1977年のハロウィンの夜の放送回「悪魔と夜ふかし」のマスターテープが最近見つかった」という設定の元、「そのマスターテープをそのまま流している」というテイで進んでいくというわけだ。「悪魔と夜ふかし」を流す前に『ナイト・オウルズ』の遍歴みたいなものがざっくり紹介され、さらにマスターテープ部分の合間合間には、「CM中の舞台裏をモノクロで流す」という演出もある。観ていればもちろん「こんな番組実在しなかっただろう」と分かるわけだが、しかし、本作がモキュメンタリーだと知らずに観に行ったら、途中までは「もしかしたら本当にこういう番組が存在したのかもしれない」なんて感じたりもするんじゃないかと思う。そういう意味で、かなりリアルな設定・展開と言っていいだろう。
あわせて読みたい
【感想】これはドキュメンタリー(実話)なのか?映画『女神の継承』が突きつける土着的恐怖
ナ・ホンジンがプロデューサーを務めた映画『女神の継承』は、フィクションなのかドキュメンタリーなのか混乱させる異様な作品だった。タイ東北部で強く信じられている「精霊(ピー)」の信仰をベースに、圧倒的なリアリティで土着的恐怖を描き出す、強烈な作品
公式HPによると、本作の制作においては「1970年代によくあった怪しげなテレビ番組の雰囲気」を再現するのに最も苦労したそうだ。そしてその点をクリアするために、本作の撮影はなんと「生放送番組を実際に収録している」かのように行われたという。なかなかのこだわりと言えるだろう。ちなみに「Owl」はフクロウのことで、「Night Owls」は英語のスラングで「夜ふかしすること」を意味するらしい。これも、実際にあってもおかしくないような番組タイトルだなと思う。

それではまず、マスターテープ部分よりも前に説明される「『ナイト・オウルズ』の遍歴」について紹介することにしよう。
1971年4月4日に始まった『ナイト・オウルズ』は、人気ラジオアナだったジャック・デルロイを司会に迎え、インタビュー・コント・音楽など様々な内容を盛り込んだ深夜番組である。観客を入れた生放送番組で、番組中の音響はすべて、スタジオにいる生バンドが担うという構成だ。番組はすぐに人気を博し、「彼は週に5夜、国民を不安にさせた」とも言われた。『ナイト・オウルズ』は毎年エミー賞の候補に上がり、同番組を放送するUBCはジャックと5年契約を結ぶ。彼はこのまま「深夜の帝王」を目指すつもりでいた。
あわせて読みたい
【現在】ウーマンラッシュアワー村本大輔がテレビから消えた理由と彼の”優しさ”を描く映画:『アイアム…
「テレビから消えた」と言われるウーマンラッシュアワー・村本大輔に密着する映画『アイアム・ア・コメディアン』は、彼に対してさほど関心を抱いていない人でも面白く観られるドキュメンタリー映画だと思う。自身の存在意義を「拡声器」のように捉え、様々な社会問題を「お笑い」で発信し続ける姿には、静かな感動さえ抱かされるだろう
そんな彼を支えたのが、妻で女優のマデリン・パイパーである。「芸能界屈指のおしどり夫婦」と呼ばれ、その仲の良さはよく知られていた。ただその一方で、彼にはもう1つ、心の支えにしていたものがある。それが「グローブ」という名の紳士クラブだ。
「グローブ」は1800年代に設立されたと言われているのだが、謎も多い。同団体には政治家や実業家などの有力者も多く参加しており、ジャックもラジオ時代から関わりが噂されていた。「金持ちのサマーキャンプ」と呼ばれる奇妙な儀式を繰り返すなど得体の知れない部分も多いのだが、影響力も大きいそうで、ジャックもそんな紳士クラブでメンバーと関わりを深めていたと考えられている。
さて、華麗にスタートダッシュを決めたかに思われた『ナイト・オウルズ』とその司会者ジャックだったが、実は大きなライバルが存在した。カーソンという司会者による裏番組である。『ナイト・オウルズ』は実は、4年経ってもその裏番組の視聴率を抜けずにいたのだ。ジャックは、「このままでは『負け組』のイメージがついてしまう」と焦っていた。しかしそんな折、彼の人生を根底から揺るがすような出来事が起こる。1976年9月、喫煙の習慣のない最愛の妻が、なんと末期の肺がんと診断されたのだ。
あわせて読みたい
【倫理】報道の自由度に関わる「放送法の解釈変更」問題をわかりやすく説明(撤回の真相についても):…
安倍政権下で突然発表された「放送法の解釈変更」が、2023年3月17日に正式に”撤回された”という事実をご存知だろうか?映画『テレビ、沈黙。 放送不可能。Ⅱ』は、その「撤回」に尽力した小西洋之議員に田原総一朗がインタビューする作品だ。多くの人が知るべき事実である
ジャックはここで、起死回生の策を打つ。なんと、病弱な妻を番組に出演させたのだ。夫の夢を叶えたい妻も喜んで同意し、その放送回は番組史上最高の視聴率を叩き出した(とはいえ、それでも裏番組に1ポイント負けてしまったのだが)。そしてこの放送の2週間後、マデリンはこの世を去ってしまう。
愛妻を喪い、さらに番組の視聴率が低迷していたことも関係しているのだろう、ジャックは1ヶ月ほど行方をくらませた。しかしその後無事に復帰、失踪前と変わらず番組作りに精を出すのだが、その奮闘も虚しくなかなか結果が付いてこない。打ち切りの噂も持ち上がるほどだった。
そしてそんな状況の中、ハロウィンの夜に放送されたのが「悪魔と夜ふかし」だったのである……。
あわせて読みたい
【異例】東映京都撮影所が全面協力!自主制作の時代劇映画『侍タイムスリッパー』は第2の『カメ止め』だ…
映画『侍タイムスリッパー』は、「自主制作映画なのに時代劇」「撮影スタッフ10人なのに東映京都撮影所全面協力」「助監督役が実際の助監督も務めている」など、中身以外でも話題に事欠かない作品ですが、何もよりも物語が実に面白い!「幕末の侍が現代にタイムスリップ」というよくある設定からこれほど面白い物語が生まれるとは
ハロウィンの夜の放送回「悪魔と夜ふかし」は、どのような内容だったのか?
では今度は、本作のメインであり、「最近発見された」という設定のマスターテープに収められたハロウィン夜の放送回「悪魔と夜ふかし」の内容に触れることにしよう。ちなみにこの記事では、ハロウィン夜の放送回を「悪魔と夜ふかし」、本作映画のタイトルを『悪魔と夜ふかし』と表記して区別している。
この日の放送は、主に3つの要素で構成されていた。最初に登場したのは、「霊聴師」「奇跡の人」などと紹介されたスピリチュアリストのクリストゥ。彼は「霊の声を聴くことが出来る」のだそうだ。登場した後で彼は、「客席に座る観客と対話しながらその人と関係する死者にチューニングを合わせ、その声を聴いて届ける」というパフォーマンスを行っていた。
そして次に出てきたのが、カーマイケル・ヘイグである。彼は元々ラスベガスなどでも人気を博していたマジシャンで、「ショービズ界の至宝」とも呼ばれており、ジャックは彼の「集団催眠」という演目を「前代未聞」と評していた。現在はショーの世界を引退し、「IFSIP(超常現象科学的調査国際連盟)」という団体に所属している。主な活動は、「超常現象を科学的に研究しつつ、超常現象を謳うエセ連中のトリックを暴き出す」というものだ。カーマイケルは、「この日スタジオ内で起こる奇妙な出来事にどのようなトリックが存在するのか見破る役割」が期待されているのである。
あわせて読みたい
【不思議】森達也が「オカルト」に挑む本。「科学では説明できない現象はある」と否定も肯定もしない姿…
肯定派でも否定派でもない森達也が、「オカルト的なもの」に挑むノンフィクション『オカルト』。「現象を解釈する」ことよりも、「現象を記録する」こと点に注力し、「そのほとんどは勘違いや見間違いだが、本当に説明のつかない現象も存在する」というスタンスで追いかける姿勢が良い
そして3つの要素の中で最も重要だったのが、「悪魔を召喚できる」という少女・リリーと、彼女の治療を担当しているジューン・ロスミッチェル博士だろう。ジャックが博士の著書『悪魔との対話』を読んで衝撃を受け、自ら企画し2人を呼んだのだという。この日の放送におけるメイン企画というわけだ。

リリーは3年前、とある場所で保護された少女である。彼女は、悪魔崇拝者であるサンダー・ディアボ率いるカルト集団「アブラクサス第一教会」に「生贄」として囚われていたのだ。このカルト集団は、「犠牲さえ払えばどんなものでも手に入る」という思想を抱いており、その「犠牲」として「子どもたちを悪魔に差し出している」と噂されていたのである。
「アブラクサス第一教会」のことはFBIも以前からマークしており、誘拐や銃犯罪への関与を疑っていたのだが、そんな中で、1974年8月に教団施設で警察との銃撃戦が始まってしまう。そのまま3日間膠着状態が続いたのだが、サンダーが信者たちに「家と身体にガソリンをかけろ」と指示し、結果としてほとんどの信者が命を落としてしまった。
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
そしてそんな凄惨な現場から救い出されたのが、当時10歳のリリーだったのである。しかし彼女の扱いには、FBIも手を焼いていた。過酷な環境にいたことが影響しているのだろう、どうにもまともなコミュニケーションが取れなかったのだ。
そのため、スタンフォード大学で超心理学の博士号を取得したジューンにリリーの件が回ってきたのである。彼女はリリーに催眠退行の治療を施す一方で、長い時間を掛けて信頼関係を築いていった。そしてその過程で彼女は、「リリーには悪魔が憑いている」ことに気づいたのである。その悪魔は「アブラクサスの下僕」という立場らしく、またリリー自身はその悪魔のことを「リグリス(もぞもぞ)」と呼んでいた。「もぞもぞとやってきては、もぞもぞと去っていく」からだそうだ。
そんなわけで今宵、その悪魔を生放送番組で召喚しようというわけである。
あわせて読みたい
【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ
江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品
そして本作は、「このような3つの要素が組み込まれた『悪魔と夜ふかし』のマスターテープをそのまま流している」というテイで物語が展開されていくというわけだ。繰り返しになるが、「こんな深夜番組が実際に放送されていたとしてもおかしくない」と感じさせるような内容であり、まずは全体の雰囲気がとても興味深かった。また、リリーを呼んでからの展開はかなりホラー的なのだが、『ナイト・オウルズ』という番組自体は「色んな要素をガチャガチャに詰め込んだ雑多なエンタメ」であり、特に前半は軽妙な感じで進んでいく。後半のホラー展開は観る人を選ぶかもしれないが、全体としては肩肘張らずに気楽に観られる作品ではないかと思う。
「CM中の様子」が挿入される構成と、一筋縄ではいかないラストの畳み掛け
本作『悪魔と夜ふかし』においては、「CM中の舞台裏の様子がモノクロ映像で流れる」という構成もまた興味深かった。「モノクロ」なのは、本作が「番組のマスターテープが見つかった」という設定になっているからだろう。そのマスターテープの中に「CM中の舞台裏」まで収録されていたら不自然なので、それで映像をモノクロにして「違い」を明確にしているのだと思う。
生放送番組であるが故に、予期せぬ出来事が度々起こる。そのためCM中は「トラブルへの対処」や「CM明けの展開の変更に関する説得」など様々なドタバタが映し出されるのだが、その際に割と”ゲスい”話が出てきたりするのも面白い。「番組で披露したデモンストレーションは実はヤラセである」ことを示唆するような会話になったり、あるいは、観覧に来ていた番組のメインスポンサーであるキャベンディッシュの会長夫妻の対応をプロデューサーと検討する際にもちょっと腹黒い話になったりしていた。
あわせて読みたい
【挑戦】杉並区長・岸本聡子を誕生させた市民運動・選挙戦と、ミュニシパリズムの可能性を描く:『映画…
映画『映画 ◯月◯日、区長になる女。』は、杉並区初の女性区長・岸本聡子を誕生させた選挙戦の裏側を中心に、日本の民主主義を問う作品だ。劇場公開されるや、チケットを取るのが困難なほど観客が殺到した作品であり、観れば日本の政治の「変化」を感じられるのではないかと思う
そしてそういう「舞台裏」を映し出すことによって、本作『悪魔と夜ふかし』を観ている観客は「何が本当で何がヤラセなのか」が分からなくなり幻惑させられていく。そもそも「悪魔と夜ふかし」は、視聴率が低迷する『ナイト・オウルズ』の起死回生の策としての側面もあり、だから「何が何でも視聴率を取りにいかなければならない状況」にある。そのため制作側はヤラセでも何でもするつもりでいるわけだが、ただ、番組中に起こっている色んなトラブルを踏まえると、ヤラセ一辺倒とも思えない。もちろん、実際には『ナイト・オウルズ』なんて番組自体が存在しないのでヤラセも何もないのだが、ただ、「『悪魔と夜ふかし』という放送回では一体何が真実なのか?」みたいな視点を持って観るのは面白いと思うし、そういう感覚を高めるために「舞台裏」が挿入されているという感じがした。なかなか面白い構成だったなと思う。

しかし、「悪魔と夜ふかし」のラストであり、本作『悪魔と夜ふかし』のラストでもあるのだが、最後の展開はかなり謎だった。私には正直、何がどうなっているのかさっぱり理解できなかったのだ。もしかしたら、考察が得意な人であれば何か捉えられるのかもしれないが。
「悪魔」とジャックのやり取りを踏まえると、「ジャックの背後にはとても大きな闇が広がっている」みたいに想像出来る。ただ本作では「マスターテープをそのまま流している」というテイで物語が進むため、放送に乗らない要素は映し出されないし、だからその辺りの謎解きもなされないままだ。それはある意味で消化不良とも言えるのだが、本作のテイストとしては凄く合っているという感じがしたし、悪くない終わらせ方だったように思う。
ただやはり、ラストの展開にはモヤモヤする人が多いだろうなぁ、きっと。
あわせて読みたい
【赦し】映画『過去負う者』が描く「元犯罪者の更生」から、社会による排除が再犯を生む現実を知る
映画『過去負う者』は、冒頭で「フィクション」だと明示されるにも拘らず、観ながら何度も「ドキュメンタリーだっけ?」と感じさせられるという、実に特異な体験をさせられた作品である。実在する「元犯罪者の更生を支援する団体」を舞台にした物語で、当然それは、私たち一般市民にも無関係ではない話なのだ
監督:コリン・ケアンズ, 監督:キャメロン・ケアンズ, Writer:コリン・ケアンズ, Writer:キャメロン・ケアンズ, 出演:デヴィッド・ダストマルチャン, 出演:ローラ・ゴードン, 出演:フェイザル・バジ, 出演:イアン・ブリス, 出演:イングリッド・トレリ, 出演:リース・アウテーリ
¥500 (2025/05/10 20:20時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
全体としては「かなりリアルに作り込まれたモキュメンタリー」であり、映画館の大画面で観ているからそんな錯覚には陥らなかったものの、例えばスマホやパソコンで本作を観ていたとしたら、「実在したテレビ番組を観ているのかもしれない」みたいな気分になったりもするかもしれない。本作ではそういう雰囲気を楽しむべきという感じがするし、そういう意味でも面白い作品と言えるのではないかと思う。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「文章の書き方が分からない」「文章力がないから鍛えたい」という方にオススメ…
「文章の書き方」についてのKindle本を出版しました。「文章が書けない」「どう書いたらいいか分からない」「文章力を向上させたい」という方の悩みを解消できるような本に仕上げたつもりです。数多くの文章を書き、さらに頼まれて文章を推敲してきた経験を踏まえ、「文章を書けるようになるにはどうしたらいいか」についての私なりの考えをまとめました。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【丁寧】筒井康隆『敵』を吉田大八が映画化!死を見定めた老紳士が囚われた狂気的日常を描く(主演:長…
映画『敵』(吉田大八監督)は、原作が筒井康隆だけのことはあり、物語はとにかく意味不明だった。しかしそれでも「面白い」と感じさせるのだから凄いものだと思う。前半では「イケオジのスローライフ」が丁寧に描かれ、そこから次第に、「元大学教授が狂気に飲み込まれていく様」が淡々と、しかし濃密に描かれていく
あわせて読みたい
【ネタバレ】フィンランド映画『ハッチング』が描くのは、抑え込んだ悪が「私の怪物」として生誕する狂気
映画『ハッチング―孵化―』は、「卵から孵った怪物を少女が育てる」という狂気的な物語なのだが、本作全体を『ジキルとハイド』的に捉えると筋の通った解釈をしやすくなる。自分の内側に溜まり続ける「悪」を表に出せずにいる主人公ティンヤの葛藤を起点に始まる物語であり、理想を追い求める母親の執念が打ち砕かれる物語でもある
あわせて読みたい
【洗脳】激しく挑発的だった映画『クラブゼロ』が描く、「食べないこと」を「健康」と言い張る狂気(主…
映画『クラブゼロ』は、「健康的な食事」として「まったく食べないこと」を推奨する女性教師と、彼女に賛同し実践する高校生を描き出す物語。実に狂気的な設定ではあるが、しかし同時に、本作で描かれているのは「日々SNS上で繰り広げられていること」でもある。そんな「現代性」をSNSを登場させずに描き出す、挑発的な作品だ
あわせて読みたい
【狂気】瀧内公美の一人語りのみで展開される映画『奇麗な、悪』の衝撃。凄まじいものを見た(監督:奥…
映画『奇麗な、悪』は、女優・瀧内公美が78分間一人語りするだけの作品で、彼女が放つ雰囲気・存在感に圧倒させられてしまった。誰もいない廃院で、目の前に医師がいるかのように話し続ける主人公の「狂気」が凄まじい。スクリーンの向こう側の出来事なのに、客席で何故か息苦しさを感じたほどの圧巻の演技に打ちのめされた
あわせて読みたい
【異次元】リアリティ皆無の怪作映画『Cloud クラウド』は、役者の演技でギリ成立している(監督:黒沢…
映画『Cloud クラウド』(黒沢清監督)は、リアリティなどまったく感じさせないかなり異様な作品だった。登場人物のほとんどが「人間っぽくない」のだが、錚々たる役者陣による見事な演技によって、「リアリティ」も「っぽさ」も欠いたまま作品としては成立している。「共感は一切出来ない」と理解した上で観るなら面白いと思う
あわせて読みたい
【天才】映画『箱男』はやはり、安部公房がSNSの無い時代に見通した「匿名性」への洞察が驚異的(監督:…
映画『箱男』は、安部公房本人から映画化権を託されるも一度は企画が頓挫、しかしその後27年の月日を経て完成させた石井岳龍の執念が宿る作品だ。SNSなど無かった時代に生み出された「匿名性」に関する洞察と、「本物とは何か?」という深淵な問いが折り重なるようにして進む物語で、その魅惑的な雰囲気に観客は幻惑される
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス)は意味不明なのに何故か超絶面白かった(主…
映画『憐れみの3章』(ヨルゴス・ランティモス監督)は、最初から最後まで「意味不明」と言っていいレベルで理解できなかったが、しかし「実に良い映画を観たなぁ」という感覚にさせてもくれる、とても素敵な作品だった。さらに、「3つの異なる物語を同じ役者の組み合わせで撮る」という斬新な構成が上手くハマっていたようにも思う
あわせて読みたい
【狂気】「こんな作品を作ろうと考えて実際世に出した川上さわ、ヤベェな」って感じた映画『地獄のSE』…
私が観た時はポレポレ東中野のみで公開されていた映画『地獄のSE』は、最初から最後までイカれ狂ったゲロヤバな作品だった。久しぶりに出会ったな、こんな狂気的な映画。面白かったけど!「こんなヤバい作品を、多くの人の協力を得て作り公開した監督」に対する興味を強く抱かされた作品で、とにかく「凄いモノを観たな」という感じだった
あわせて読みたい
【感想】B級サメ映画の傑作『温泉シャーク』は、『シン・ゴジラ』的壮大さをバカバカしく描き出す
「温泉に入っているとサメに襲われる」という荒唐無稽すぎる設定のサメ映画『温泉シャーク』は、確かにふざけ倒した作品ではあるものの、観てみる価値のある映画だと思います。サメの生態を上手く利用した設定や、「伏線回収」と表現していいだろう展開などが巧みで、細かなことを気にしなければ、そのバカバカしさを楽しめるはずです
あわせて読みたい
【解説】映画『スターフィッシュ』をネタバレ全開で考察。主人公が直面する”奇妙な世界”の正体は?
映画『スターフィッシュ』は、「親友の葬儀」とそれに続く「不法侵入」の後、唐突に「意味不明な世界観」に突入していき、その状態のまま物語が終わってしまう。解釈が非常に難しい物語だが、しかし私なりの仮説には辿り着いた。そこでこの記事では、ネタバレを一切気にせずに「私が捉えた物語」について解説していくことにする
あわせて読みたい
【狂気】押見修造デザインの「ちーちゃん」(映画『毒娘』)は「『正しさ』によって歪む何か」の象徴だ…
映画『毒娘』は、押見修造デザインの「ちーちゃん」の存在感が圧倒的であることは確かなのだが、しかし観ていくと、「決して『ちーちゃん』がメインなわけではない」ということに気づくだろう。本作は、全体として「『正しさ』によって歪む何か」を描き出そうとする物語であり、私たちが生きる社会のリアルを抉り出す作品である
あわせて読みたい
【常識】群青いろ制作『彼女はなぜ、猿を逃したか?』は、凄まじく奇妙で、実に魅力的な映画だった(主…
映画『彼女はなぜ、猿を逃したか?』(群青いろ制作)は、「絶妙に奇妙な展開」と「爽快感のあるラスト」の対比が魅力的な作品。主なテーマとして扱われている「週刊誌報道からのネットの炎上」よりも、私は「週刊誌記者が無意識に抱いている思い込み」の方に興味があったし、それを受け流す女子高生の受け答えがとても素敵だった
あわせて読みたい
【狂気】群青いろ制作『雨降って、ジ・エンド。』は、主演の古川琴音が成立させている映画だ
映画『雨降って、ジ・エンド。』は、冒頭からしばらくの間「若い女性とオジサンのちょっと変わった関係」を描く物語なのですが、後半のある時点から「共感を一切排除する」かのごとき展開になる物語です。色んな意味で「普通なら成立し得ない物語」だと思うのですが、古川琴音の演技などのお陰で、絶妙な形で素敵な作品に仕上がっています
あわせて読みたい
【衝撃】広末涼子映画デビュー作『20世紀ノスタルジア』は、「広末が異常にカワイイ」だけじゃない作品
広末涼子の映画デビュー・初主演作として知られる『20世紀ノスタルジア』は、まず何よりも「広末涼子の可愛さ」に圧倒される作品だ。しかし、決してそれだけではない。初めは「奇妙な設定」ぐらいにしか思っていなかった「宇宙人に憑依されている」という要素が、物語全体を実に上手くまとめている映画だと感じた
あわせて読みたい
【映画】ウォン・カーウァイ4Kレストア版の衝撃!『恋する惑星』『天使の涙』は特にオススメ!
『恋する惑星』『天使の涙』で一躍その名を世界に知らしめた巨匠ウォン・カーウァイ作品の4Kレストア版5作品を劇場で一気見した。そして、監督の存在さえまったく知らずに観た『恋する惑星』に圧倒され、『天使の涙』に惹きつけられ、その世界観に驚かされたのである。1990年代の映画だが、現在でも通用する凄まじい魅力を放つ作品だ
あわせて読みたい
【天才】映画『ツィゴイネルワイゼン』(鈴木清順)は意味不明だが、大楠道代のトークが面白かった
鈴木清順監督作『ツィゴイネルワイゼン』は、最初から最後まで何を描いているのかさっぱり分からない映画だった。しかし、出演者の1人で、上映後のトークイベントにも登壇した大楠道代でさえ「よく分からない」と言っていたのだから、それでいいのだろう。意味不明なのに、どこか惹きつけられてしまう、実に変な映画だった
あわせて読みたい
【怖い?】映画『アメリ』(オドレイ・トトゥ主演)はとても奇妙だが、なぜ人気かは分かる気がする
名作として知られているものの観る機会の無かった映画『アメリ』は、とても素敵な作品でした。「オシャレ映画」という印象を持っていて、それは確かにその通りなのですが、それ以上に私は「主人公・アメリの奇妙さ」に惹かれたのです。普通には成立しないだろう展開を「アメリだから」という謎の説得力でぶち抜く展開が素敵でした
あわせて読みたい
【あらすじ】声優の幾田りらとあのちゃんが超絶良い!アニメ映画『デデデデ』はビビるほど面白い!:『…
幾田りらとあのちゃんが声優を務めた映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』は、とにかく最高の物語だった。浅野いにおらしいポップさと残酷さを兼ね備えつつ、「終わってしまった世界でそれでも生きていく」という王道的展開を背景に、門出・おんたんという女子高生のぶっ飛んだ関係性が描かれる物語が見事すぎる
あわせて読みたい
【斬新】フィクション?ドキュメンタリー?驚きの手法で撮られた、現実と虚構が入り混じる映画:『最悪…
映画『最悪な子どもたち』は、最後まで観てもフィクションなのかドキュメンタリーなのか確信が持てなかった、普段なかなか抱くことのない感覚がもたらされる作品だった。「演技未経験」の少年少女を集めての撮影はかなり実験的に感じられたし、「分からないこと」に惹かれる作品と言えるいだろうと思う
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『レザボア・ドッグス』(タランティーノ監督)はとにかく驚異的に脚本が面白い!
クエンティン・タランティーノ初の長編監督作『レザボア・ドッグス』は、のけぞるほど面白い映画だった。低予算という制約を逆手に取った「会話劇」の構成・展開があまりにも絶妙で、舞台がほぼ固定されているにも拘らずストーリーが面白すぎる。天才はやはり、デビュー作から天才だったのだなと実感させられた
あわせて読みたい
【斬新】映画『王国(あるいはその家について)』(草野なつか)を観よ。未経験の鑑賞体験を保証する
映画『王国(あるいはその家について)』は、まず経験できないだろう異様な鑑賞体験をもたらす特異な作品だった。「稽古場での台本読み」を映し出すパートが上映時間150分のほとんどを占め、同じやり取りをひたすら繰り返し見せ続ける本作は、「王国」をキーワードに様々な形の「狂気」を炙り出す異常な作品である
あわせて読みたい
【痛快】精神病院の隔離室から脱した、善悪の判断基準を持たない狂気の超能力者が大暴れする映画:『モ…
モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』は、「10年以上拘束され続けた精神病院から脱走したアジア系女性が、特殊能力を使って大暴れする」というムチャクチャな設定の物語なのだが、全編に通底する「『善悪の判断基準』が歪んでいる」という要素がとても見事で、意味不明なのに最後まで惹きつけられてしまった
あわせて読みたい
【狂気】映画『ニューオーダー』の衝撃。法という秩序を混沌で駆逐する”悪”に圧倒されっ放しの86分
映画『ニューオーダー』は、理解不能でノンストップな展開に誘われる問題作だ。「貧富の差」や「法の支配」など「現実に存在する秩序」がひっくり返され、対極に振り切った「新秩序」に乗っ取られた世界をリアルに描き出すことで、私たちが今進んでいる道筋に警鐘を鳴らす作品になっている
あわせて読みたい
【不穏】大友克洋の漫画『童夢』をモデルにした映画『イノセンツ』は、「無邪気な残酷さ」が恐ろしい
映画『イノセンツ』は、何がどう展開するのかまるで分からないまま進んでいく実に奇妙な物語だった。非現実的な設定で描かれるのだが、そのことによって子どもたちの「無邪気な残酷さ」が一層リアルに浮き彫りにされる物語であり、「意図的に大人が排除された構成」もその一助となっている
あわせて読みたい
【倫理】アート体験の行き着く未来は?映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』が描く狂気の世界(…
「『痛み』を失った世界」で「自然発生的に生まれる新たな『臓器』を除去するライブパフォーマンス」を行うソール・テンサーを主人公にした映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、すぐには答えの見出しにくい「境界線上にある事柄」を挑発的に描き出す、実に興味深い物語だ
あわせて読みたい
【感想】これはドキュメンタリー(実話)なのか?映画『女神の継承』が突きつける土着的恐怖
ナ・ホンジンがプロデューサーを務めた映画『女神の継承』は、フィクションなのかドキュメンタリーなのか混乱させる異様な作品だった。タイ東北部で強く信じられている「精霊(ピー)」の信仰をベースに、圧倒的なリアリティで土着的恐怖を描き出す、強烈な作品
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『夕方のおともだち』は、「私はこう」という宣言からしか始まらない関係性の”純度”を描く
「こんな田舎にはもったいないほどのドM」と評された男が主人公の映画『夕方のおともだち』は、SM嬢と真性ドMの関わりを通じて、「宣言から始まる関係」の難しさを描き出す。「普通の世界」に息苦しさを感じ、どうしても馴染めないと思っている人に刺さるだろう作品
あわせて読みたい
【異様】西成のあいりん地区を舞台にした映画『解放区』は、リアルとフェイクの境界が歪んでいる
ドキュメンタリー映画だと思って観に行った『解放区』は、実際にはフィクションだったが、大阪市・西成区を舞台にしていることも相まって、ドキュメンタリー感がとても強い。作品から放たれる「異様さ」が凄まじく、「自分は何を観せられているんだろう」という感覚に襲われた
あわせて読みたい
【考察】ヨネダコウ『囀る鳥は羽ばたかない』は、BLの枠組みの中で「歪んだ人間」をリアルに描き出す
2巻までしか読んでいないが、ヨネダコウのマンガ『囀る鳥は羽ばたかない』は、「ヤクザ」「BL」という使い古されたフォーマットを使って、異次元の物語を紡ぎ出す作品だ。BLだが、BLという外枠を脇役にしてしまう矢代という歪んだ男の存在感が凄まじい。
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
あわせて読みたい
【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ
江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品
あわせて読みたい
【純愛】映画『ぼくのエリ』の衝撃。「生き延びるために必要なもの」を貪欲に求める狂気と悲哀、そして恋
名作と名高い映画『ぼくのエリ』は、「生き延びるために必要なもの」が「他者を滅ぼしてしまうこと」であるという絶望を抱えながら、それでも生きることを選ぶ者たちの葛藤が描かれる。「純愛」と呼んでいいのか悩んでしまう2人の関係性と、予想もつかない展開に、感動させられる
あわせて読みたい
【感想】湯浅政明監督アニメ映画『犬王』は、実在した能楽師を”異形”として描くスペクタクル平家物語
観るつもりなし、期待値ゼロ、事前情報ほぼ皆無の状態で観た映画『犬王』(湯浅政明監督)はあまりにも凄まじく、私はこんなとんでもない傑作を見逃すところだったのかと驚愕させられた。原作の古川日出男が紡ぐ狂気の世界観に、リアルな「ライブ感」が加わった、素晴らしすぎる「音楽映画」
あわせて読みたい
【おすすめ】「天才」を描くのは難しい。そんな無謀な挑戦を成し遂げた天才・野崎まどの『know』はヤバい
「物語で『天才』を描くこと」は非常に難しい。「理解できない」と「理解できる」を絶妙なバランスで成り立たせる必要があるからだ。そんな難題を高いレベルでクリアしている野崎まど『know』は、異次元の小説である。世界を一変させた天才を描き、「天才が見ている世界」を垣間見せてくれる
あわせて読みたい
【衝撃】洗脳を自ら脱した著者の『カルト脱出記』から、「社会・集団の洗脳」を避ける生き方を知る
「聖書研究に熱心な日本人証人」として「エホバの証人」で活動しながら、その聖書研究をきっかけに自ら「洗脳」を脱した著者の体験を著した『カルト脱出記』。広い意味での「洗脳」は社会のそこかしこに蔓延っているからこそ、著者の体験を「他人事」だと無視することはできない
あわせて読みたい
【矛盾】法律の”抜け穴”を衝く驚愕の小説。「ルールを通り抜けたものは善」という発想に潜む罠:『法廷…
完璧なルールは存在し得ない。だからこそ私たちは、矛盾を内包していると理解しながらルールを遵守する必要がある。「ルールを通り抜けたものは善」という”とりあえずの最善解”で社会を回している私たちに、『法廷遊戯』は「世界を支える土台の脆さ」を突きつける
あわせて読みたい
【生と死】不老不死をリアルに描く映画。「若い肉体のまま死なずに生き続けること」は本当に幸せか?:…
あなたは「不老不死」を望むだろうか?私には、「不老不死」が魅力的には感じられない。科学技術によって「不老不死」が実現するとしても、私はそこに足を踏み入れないだろう。「不老不死」が実現する世界をリアルに描く映画『Arc アーク』から、「生と死」を考える
あわせて読みたい
【世界観】映画『夜は短し歩けよ乙女』の”黒髪の乙女”は素敵だなぁ。ニヤニヤが止まらない素晴らしいアニメ
森見登美彦の原作も大好きな映画『夜は短し歩けよ乙女』は、「リアル」と「ファンタジー」の境界を絶妙に漂う世界観がとても好き。「黒髪の乙女」は、こんな人がいたら好きになっちゃうよなぁ、と感じる存在です。ずっとニヤニヤしながら観ていた、とても大好きな映画
あわせて読みたい
【考察】映画『ジョーカー』で知る。孤立無援の環境にこそ”悪”は偏在すると。個人の問題ではない
「バットマン」シリーズを観たことがない人間が、予備知識ゼロで映画『ジョーカー』を鑑賞。「悪」は「環境」に偏在し、誰もが「悪」に足を踏み入れ得ると改めて実感させられた。「個人」を断罪するだけでは社会から「悪」を減らせない現実について改めて考える
あわせて読みたい
【異様】ジャーナリズムの役割って何だ?日本ではまだきちんと機能しているか?報道機関自らが問う映画…
ドキュメンタリーで定評のある東海テレビが、「東海テレビ」を被写体として撮ったドキュメンタリー映画『さよならテレビ』は、「メディアはどうあるべきか?」を問いかける。2011年の信じがたいミスを遠景にしつつ、メディア内部から「メディアの存在意義」を投げかける
あわせて読みたい
【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…
ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ
あわせて読みたい
【権威】心理学の衝撃実験をテレビ番組の収録で実践。「自分は残虐ではない」と思う人ほど知るべき:『…
フランスのテレビ局が行った「現代版ミルグラム実験」の詳細が語られる『死のテレビ実験 人はそこまで服従するのか』は、「権威」を感じる対象から命じられれば誰もが残虐な行為をしてしまい得ることを示す。全人類必読の「過ちを事前に回避する」ための知見を学ぶ
あわせて読みたい
【驚嘆】この物語は「AIの危険性」を指摘しているのか?「完璧な予知能力」を手にした人類の過ち:『預…
完璧な未来予知を行えるロボットを開発し、地震予知のため”だけ”に使おうとしている科学者の自制を無視して、その能力が解放されてしまう世界を描くコミック『預言者ピッピ』から、「未来が分からないからこそ今を生きる価値が生まれるのではないか」などについて考える
あわせて読みたい
【逃避】つまらない世の中で生きる毎日を押し流す”何か”を求める気持ちに強烈に共感する:映画『サクリ…
子どもの頃「台風」にワクワクしたように、未だに、「自分のつまらない日常を押し流してくれる『何か』」の存在を待ちわびてしまう。立教大学の学生が撮った映画『サクリファイス』は、そんな「何か」として「東日本大震災」を描き出す、チャレンジングな作品だ
あわせて読みたい
【リアル】社会の分断の仕組みを”ゾンビ”で学ぶ。「社会派ゾンビ映画」が対立の根源を抉り出す:映画『C…
まさか「ゾンビ映画」が、私たちが生きている現実をここまで活写するとは驚きだった。映画『CURED キュアード』をベースに、「見えない事実」がもたらす恐怖と、立場ごとに正しい主張をしながらも否応なしに「分断」が生まれてしまう状況について知る
あわせて読みたい
【難しい】映画『鳩の撃退法』をネタバレ全開で考察。よくわからない物語を超詳細に徹底解説していく
とても難しくわかりにくい映画『鳩の撃退法』についての考察をまとめていたら、1万7000字を超えてしまった。「東京編で起こったことはすべて事実」「富山編はすべてフィクションかもしれない」という前提に立ち、「津田伸一がこの小説を書いた動機」まで掘り下げて、実際に何が起こっていたのかを解説する(ちなみに、「実話」ではないよ)
あわせて読みたい
【誤り】「信じたいものを信じる」のは正しい?映画『星の子』から「信じること」の難しさを考える
どんな病気も治す「奇跡の水」の存在を私は信じないが、しかし何故「信じない」と言えるのか?「奇跡の水を信じる人」を軽々に非難すべきではないと私は考えているが、それは何故か?映画『星の子』から、「何かを信じること」の難しさについて知る
あわせて読みたい
【解説】「小説のお約束」を悉く無視する『鳩の撃退法』を読む者は、「読者の椅子」を下りるしかない
佐藤正午『鳩の撃退法』は、小説家である主人公・津田が、”事実”をベースに、起こったかどうか分からない事柄を作家的想像力で埋める物語であり、「小説のお約束を逸脱しています」というアナウンスが作品内部から発せられるが故に、読者は「読者の椅子」を下りざるを得ない
あわせて読みたい
【解説】テネットの回転ドアの正体を分かりやすく考察。「時間逆行」ではなく「物質・反物質反転」装置…
クリストファー・ノーラン監督の映画『TENET/テネット』は、「陽電子」「反物質」など量子力学の知見が満載です。この記事では、映画の内容そのものではなく、時間反転装置として登場する「回転ドア」をメインにしつつ、時間逆行の仕組みなど映画全体の設定について科学的にわかりやすく解説していきます
あわせて読みたい
【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…
小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る
あわせて読みたい
【不満】この閉塞感は打破すべきか?自由意志が駆逐された社会と、不幸になる自由について:『巡査長 真…
自由に選択し、自由に行動し、自由に生きているつもりでも、現代社会においては既に「自由意志」は失われてしまっている。しかし、そんな世の中を生きることは果たして不幸だろうか?異色警察小説『巡査長 真行寺弘道』をベースに「不幸になる自由」について語る
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
メディア・マスコミ・表現の自由【本・映画の感想】 | ルシルナ
様々な現実を理解する上で、マスコミや出版などメディアの役割は非常に大きいでしょう。情報を受け取る我々が正しいリテラシーを持っていなければ、誤った情報を発信する側…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…



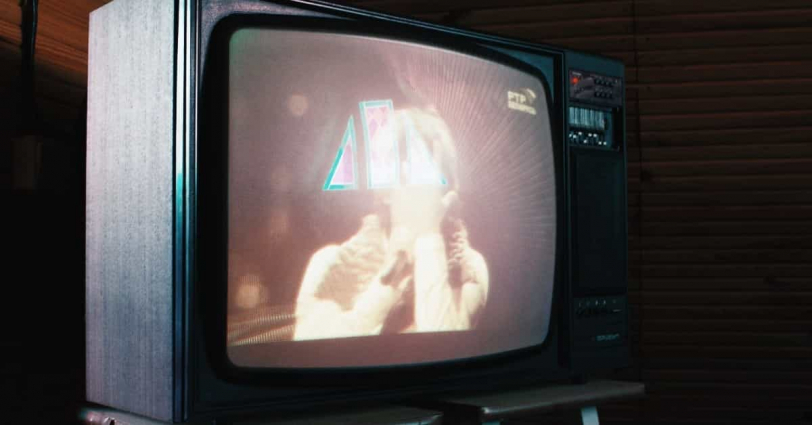






















































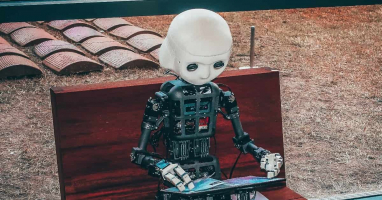


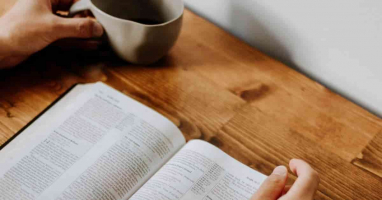








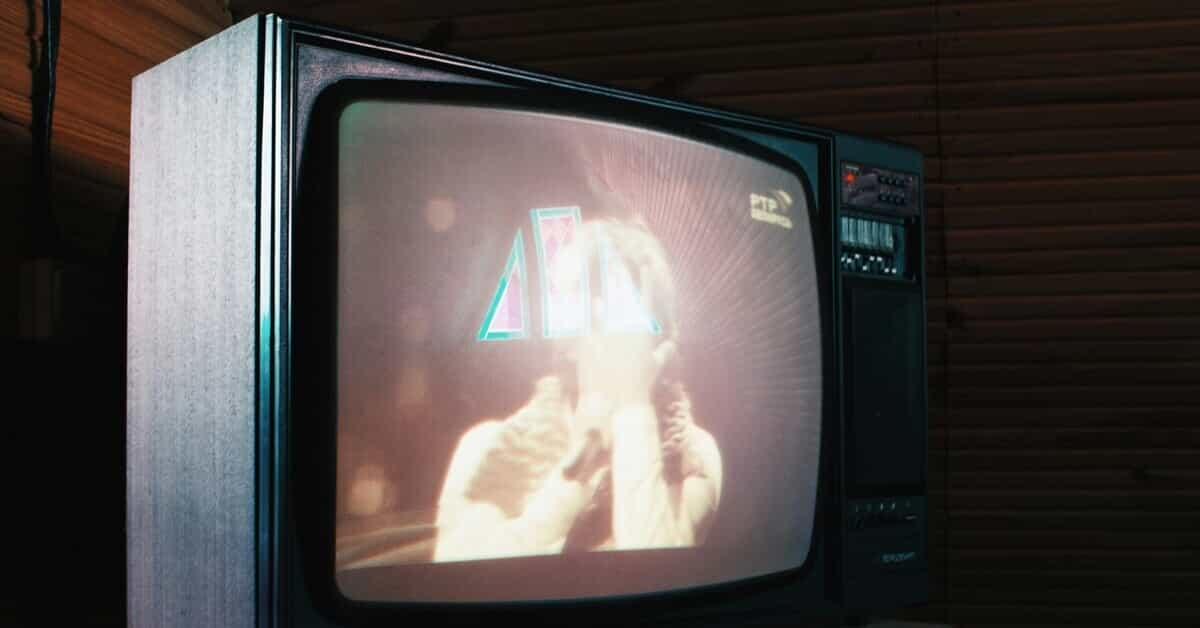





コメント