目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
¥500 (2025/12/27 07:44時点 | Amazon調べ)
ポチップ
VIDEO
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
「巣鴨プリズン以外では日記を書くことさえ許されなかった」「BC級戦犯の裁判記録は基本的にアメリカが持ち帰った」ことを踏まえると、冬至堅太郎に関する記録は非常に貴重である 戦争が起これば、誰もがBC級戦犯として裁かれる可能性があるという事実は認識しておくべきだろう 「戦勝国による裁判の記録」を再検証する意味とは? 冬至堅太郎という1人の個人の生涯を通じて、謎多きBC級戦犯の実相が明らかにされていく
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
映画『巣鴨日記 あるBC級戦犯の生涯』は、巣鴨プリズンに収監されていた冬至堅太郎に焦点を当て知られざる戦後史を描くドキュメンタリー
実に興味深い作品 だった。本作には「『BC級戦犯』についてあまりにも知られていない」という問題意識がベースにある のだが、確かに知らないことばかりだった なと思う。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『1917』は、ワンカット風の凄まじい撮影手法が「戦場の壮絶な重圧」を見事に体感させる
映画『1917 命をかけた伝令』は、「全編ワンカット風」という凄まじい撮影手法で注目されたが、私は、その撮影手法が「戦場における緊迫感」を見事に増幅させているという点に驚かされた。「物語の中身」と「撮影手法」が素晴らしく合致したとんでもない作品だ
あまりにも知られていない「BC級戦犯」の実相を、冬至堅太郎の記録から浮き彫りにしていく作品
多くの人が「A級戦犯」という言葉は聞いたことがあるだろう 。これは、東條英機ら28人の「戦争犯罪人」を指す もので、戦犯の中でも特に責任が重い者たち のことである。ちなみに、「A級戦犯」の内の7人が絞首刑に処せられた そうだ。この辺りの事実は比較的よく知られている のではないかと思う。
さて、「A級」があるならA級以外もある はずで、それが「BC級戦犯 」である。私はこの言葉にどこかしらで触れたことがあるような気もするのだが、しかしほぼ何も知らなかった と言っていい。そして本作では、「『BC級戦犯』については、世間的にはほぼまったく知られていない」と説明されていた 。私は学生時代「歴史」の授業を諦めた人間なので何とも言えないが、恐らく、学校で習う知識にも含まれていない ということなのだろう。そして本作は、そんな「BC級戦犯」に焦点を当てる作品 である。
あわせて読みたい
【あらすじ】老夫婦の”穏やかな日常”から核戦争の恐怖を描くアニメ映画『風が吹くとき』の衝撃
一軒家の中だけで展開される老夫婦の日常から「核戦争」の危機をリアルに描き出す映画『風が吹くとき』は、日本では1987年に公開された作品なのだが、今まさに観るべき作品ではないかと。世界的に「核戦争」の可能性が高まっているし、また「いつ起こるか分からない巨大地震」と読み替えても成立する作品で、実に興味深かった
BC級戦犯もA級戦犯と同様に「戦争犯罪人」を指す のだが、A級戦犯が主に「戦争主導者」 だったのに対して、BC級戦犯は「捕虜を虐殺した者」 とされていたようだ。「戦争犯罪」と呼ばれ得る対象は「捕虜虐殺」以外にも色々と存在するのだろうが、この「A級戦犯」「BC級戦犯」というのは「戦勝国アメリカが敗戦国日本を裁く上での分類」 であり、そのため「捕虜虐殺」を中心に「戦争犯罪」が認定された ということらしい。
BC級戦犯と認定されたのは、民間人を含む5700もの人たち であり、7ヶ国に設置された49の法廷で裁判が行われた 。そして最終的に920人が処刑された のだそうだ。日本では唯一、米軍に接収されていた横浜地方裁判所内でBC級戦犯を裁く「横浜軍事法廷」が開かれ 、ここでは51人に死刑判決が下った という。
そしてそんな横浜軍事法廷で死刑判決を下された1人が、本作における主人公と言っていいだろう冬至堅太郎 である。彼はBC級戦犯として32歳の時に巣鴨プリズンに収監された のだが、その獄中での生活を日記という形で残していた 。本作『巣鴨日記 あるBC級戦犯の生涯』は、そんな貴重な記録をベースに制作された作品 である。1946年から1952年に掛けての6年間分の日記 が現存しており、本作中でも何度も引用されていた 。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話
映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ
しかし、本作で冬至堅太郎に焦点が当てられるのは、日記が残っているからというだけではない 。なんと、横浜軍事法廷における冬至堅太郎の裁判記録が日本に残っている のである。
裁判はアメリカ主導で行われた ため、当然、その記録はアメリカが本国へと持ち帰った 。もちろんそれらの資料はアメリカの公文書館などで保管されているだろうし、手続きを踏めば閲覧も可能だろう が、アメリカまで行くことも含め、そこには様々な制約が存在する 。しかし冬至堅太郎の裁判記録は日本に残っているため、本作の制作においてかなり自由度高く使用することが出来た というわけだ。日記と裁判記録という資料が残っているからこそ、冬至堅太郎という人物について深く掘り下げることが出来た のである。ちなみに、何故日本に残っているかと言えば、彼の弁護を担当した横浜弁護士会の桃井銈次が、何度も提出要請を受けながらもそれを無視して保管し続けた からだそうだ。
さて、私が鑑賞した回では、上映後に監督らによる舞台挨拶が行われた 。この記事でも随時、その中で語られた話に触れる つもりだ。それで、舞台挨拶にはある大学教授も登壇した のだが、彼女は「巣鴨プリズン以外に収監された者は、日記のような形で記録を残すことも許されなかった 」と言っていた。つまり、冬至堅太郎はたまたま巣鴨プリズンに収監されたため日記を書くことが出来た のだし、さらに担当弁護士がアメリカからの要請を無視する気骨ある人物だったお陰で、非常に重要な資料が日本に残った というわけだ。作中では彼以外の人物の資料もそれなりには出てくる ものの、やはり冬至堅太郎の日記・裁判記録が無ければ何も進まなかった ように思う。そしてもしそうなら、こうして劇場公開される形で映画が作られることもなく、我々がBC級戦犯について知る機会も減ってしまった はずだ。というわけでまずは、本作のようなドキュメンタリー映画が作られたその背景みたいなものに驚かされてしまった 。
あわせて読みたい
【証言】ナチスドイツでヒトラーに次ぐナンバー2だったゲッベルス。その秘書だった女性が歴史を語る映画…
ナチスドイツナンバー2だった宣伝大臣ゲッベルス。その秘書だったブルンヒルデ・ポムゼルが103歳の時にカメラの前で当時を語った映画『ゲッベルスと私』には、「愚かなことをしたが、避け難かった」という彼女の悔恨と教訓が含まれている。私たちは彼女の言葉を真摯に受け止めなければならない
しかし、資料があっても取材が簡単だったわけではない 。というのも、これは監督が話していたことだが、「死刑を免れたBC級戦犯も、『戦争犯罪人として裁かれた過去がある』という事実を積極的には話したがらない 」からだ。まあそれは当然だろう なと思う。恐らく、家族でさえ「父親(祖父)がBC級戦犯だった」(BC級戦犯が全員男性だったかは知らないが)なんてことを知らない可能性も全然ある だろう。それ故にBC級戦犯については一般的にはまったく知られていない のだし、そしてだからこそ冬至堅太郎の資料や本作『巣鴨日記 あるBC級戦犯の生涯』はとても貴重 なのだと思う。
「『戦争』が起これば、誰もが『BC級戦犯』になり得る」と理解しておくべき
さて、この記事でも当然、冬至堅太郎について詳しく触れていくわけだが、しかしその前に書いておきたいこと がある。それは「戦争犯罪とは一体何か? 」という話だ。
舞台挨拶に登壇した大学教授は本作にも出演しており 、次のような発言をしていた。
あわせて読みたい
【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…
クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい
「戦争犯罪」と聞くとどうしても「犯罪」の方に力点を置きがちだが、実際には「戦争」の方に着目すべき。
さて、この発言は一体何を示唆しているのだろうか? それは、「BC級戦犯は決して、自らの意思で捕虜虐殺を行ったわけではない 」ということだ。BC級戦犯として裁かれた者の多くは「上官に命令されて捕虜を殺害した」 のである。そしてそんな人たちが、裁判を経て死刑判決を受けてしまった というわけだ。
令和の現代では、「上官の命令は絶対」という感覚はなかなか理解できないかもしれない が(昔は運動部などで体育会系のキツさが残っていただろうが、さすがに現代ではそれもほとんど無くなっている気がする)、「戦時下」においては上官が命じたことは必ず実行しなければならなかった 。つまり、自分の意思とは関係なく「犯罪」に加担してしまった人たちがBC級戦犯として裁かれていた というわけだ。そしてもちろんそれは、「戦争」が背景にあったから である。
あわせて読みたい
【解説】映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、凄まじい臨場感で内戦を描き、我々を警告する(…
映画『シビル・ウォー』は、「アメリカで勃発した内戦が長期化し、既に日常になってしまっている」という現実を圧倒的な臨場感で描き出す作品だ。戦争を伝える報道カメラマンを主人公に据え、「戦争そのもの」よりも「誰にどう戦争を伝えるか」に焦点を当てる本作は、様々な葛藤を抱きながら最前線を目指す者たちを切り取っていく
つまり、今後日本が戦争に巻き込まるようなことがあれば (今の世界情勢を踏まえるとあり得ないことではないだろう)、誰もがBC級戦犯になる可能性がある のだ。また前述した通り、BC級戦犯には民間人も含まれていた ので、そういう意味でも、国民全員に関係する話 と考えていいだろう。
さて、この点に関連して、舞台挨拶の中で監督が語っていた「取材の苦労」についての話 が興味深かった。
そもそもだが、BC級戦犯に関する資料が日本の公文書館で公開され始めたのが1999年頃 だったという。私の感覚では「大分遅いな 」という感じである。しかも公開されたというその資料は、人名は基本的に黒塗りのいわゆる「ノリ弁状態」 だった。これでは取材のスタートが切れない 。また、どうにかして個人の特定に成功したとしても、その本人は亡くなっていることがほとんど である。だからその子孫に連絡を取る ことになるのだが、やはり「親族がBC級戦犯だった」という事実は聞こえが悪いからだろう、取材を断られることが多かった という。
あわせて読みたい
【驚異】信念を貫く勇敢さを、「銃を持たずに戦場に立つ」という形で示した実在の兵士の凄まじさ:映画…
第二次世界大戦で最も過酷な戦場の1つと言われた「前田高地(ハクソー・リッジ)」を、銃を持たずに駆け回り信じがたい功績を残した衛生兵がいた。実在の人物をモデルにした映画『ハクソー・リッジ』から、「戦争の悲惨さ」だけでなく、「信念を貫くことの大事さ」を学ぶ
しかしそれでも、BC級戦犯だった人物の子ども(ざっくり60代~80代ぐらいだろうか)は取材をOKしてくれる、みたいなケースもあった そうだ。ただそういう場合でも、さらにその孫(40代~50代ぐらいだろうか)から取材NGが出てしまう のだという。話を聞いてみると、「戦時中のこととは言え、人を殺したから裁かれているんですよね? やはりそれは印象が悪いので取材は受けたくない」みたいな反応 なのだそうだ。
さて、先程の「『犯罪』よりも『戦争』に力点を置くべき」という主張を踏まえてこの話を捉え直してみる と、要するに「『戦時下だった』という前提条件を正確に認識出来ていない 」ということなのだろう。この点については、私も大差ない と思う。今日本に住んでいる人のほとんどは「戦争や終戦直後を経験していない」 わけで、だから「平時」の基準であらゆる物事を捉えてしまう 。そしてそれ故に「えっ、でも、人を殺したんですよね?」みたいな感覚になってしまう というわけだ。しかし実際には「戦時下だったからそうせざるを得なかった」だけの話 である。BC級戦犯とされた人たちのほとんどは、「戦時下でなければ人を殺さなかった」 はずだ。そういう人たちのことを「人を殺したんですよね?」みたいな視点でしか捉えられないのは正しくない よなと、私は本作を観て改めて実感させられた。
外国では今も戦争が行われていて 、また、世界大戦が起こってもおかしくないような不安定な情勢 でもある。台湾有事や北朝鮮のリスクもある中で、「日本が戦争に巻き込まれることはない」なんて断言出来る人はいないはずだ 。そしてだとすれば、「自分がBC級戦犯として処罰される可能性」はについても想定しておくべき だろう。BC級戦犯についての情報に触れる際には、この点を的確に理解しておくことが重要 なのだと強く感じさせられた。
あわせて読みたい
【凄絶】北朝鮮の”真実”を描くアニメ映画。強制収容所から決死の脱出を試みた者が語る驚愕の実態:『ト…
在日コリアン4世の監督が、北朝鮮脱北者への取材を元に作り上げた壮絶なアニメ映画『トゥルーノース』は、私たちがあまりに恐ろしい世界と地続きに生きていることを思い知らせてくれる。最低最悪の絶望を前に、人間はどれだけ悪虐になれてしまうのか、そしていかに優しさを発揮できるのか。
冬至堅太郎が逮捕・起訴された経緯
さて、私はここまで「BC級戦犯の多くは『上官の命令』によって捕虜を虐殺したに過ぎず、その犯罪行為は仕方ないものだった」みたいな話を長々と書いてきた のだが、実は冬至堅太郎のケースはそれには当てはまらない 。彼は自らの意思で米兵を殺した ことがはっきりしているのだ。というわけでここからはしばらくの間、彼がどのような経緯で巣鴨プリズンに囚われ死刑判決を受けるに至ったのかに触れたい と思う。
福岡の和文具店で生を享けた 堅太郎は、東京商科大学(現・一橋大学)を卒業後すぐに召集された 。中国に3年間いた 後、福岡の西部軍司令部に主計中尉として臨時召集される 。そしてそこで運命の日を迎える こととなった。1945年6月19日の福岡大空襲である 。1500トンもの焼夷弾 が降り注いだ福岡の街では、死者・行方不明者合わせて1000人以上 という多大な被害が生まれた。そしてその被害者の中に、最愛の母・ウタがいた のである。
さて、堅太郎が所属していた西部軍司令部の近くには九州中から集められた米兵の捕虜を収容する場所があり 、堅太郎はある日たまたま、そこでB29の搭乗員の処刑が行われているのを目にした 。その際、母親を米軍に殺された堅太郎は「私こそ処刑人としてふさわしい」と考え、自ら銃剣を手にして4人の米兵を殺害した のである。
あわせて読みたい
【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…
『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る
その後終戦を迎えると、冬至堅太郎は「自分は恐らく戦犯として捕えられるだろう」と考える ようになっていく。もちろん周囲の人間は「逃亡」や「嘘の証言」を勧めた のだが、彼にはそんなことをするつもりはなかった 。妻も子どももいる身でありながら、捕まることを覚悟で「真実を唯一の道として選ぶ」ことを決めていた のである。
こうして彼は1946年4月に土手町刑務所に勾留され、その後巣鴨プリズンに移された 。そして横浜軍事法廷での裁判を経て死刑判決を受けた のである。
裁判に際して冬至堅太郎は、担当してくれることになった桃井弁護士から「厳しい闘いになる」と言われていた 。やはり「自らの意思で米兵を殺したこと」が致命的 だというのだ。もちろん、堅太郎自身もそのことは理解していた が、その話とは別に、彼はある希望を抱いていた 。それは「『処刑者』としては罪を負うが、『殺人者』として追及されたくはない 」というものである。冬至堅太郎はあくまでも「最愛の母を殺した連中を処刑した」という認識だった のであり、「殺人者として裁かれることは納得できない」と考えていた というわけだ。彼のこの希望が実際の裁判でどのように扱われたのか(あるいは扱われなかったのか)は本作を観ているだけではよく分からなかったが、いずれにせよ、結果として彼は死刑判決を受けた のである。
あわせて読みたい
【驚愕】本屋大賞受賞作『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は凄まじい。戦場は人間を”怪物”にする
デビュー作で本屋大賞を受賞した『同志少女よ、敵を撃て』(逢坂冬馬)は、デビュー作であることを抜きにしても凄まじすぎる、規格外の小説だった。ソ連に実在した「女性狙撃兵」の視点から「独ソ戦」を描く物語は、生死の境でギリギリの葛藤や決断に直面する女性たちのとんでもない生き様を活写する
また彼は「裁判では証言台に立ちたい」と桃井弁護士に相談していた そうだ。しかし実際には、彼のように直接米兵に手を下した者は証言台に立たせてもらえないことの方が多かった という。彼は結局、自分の口からは何も説明できないまま判決の日を迎えた のである。
本作ではこのようにして、冬至堅太郎の来歴から死刑判決を受けるまでの詳細が、記録や証言などによって再構築されていく 。
「戦勝国による裁判の記録」を再検証することの意味
私は以前、『東京裁判』というドキュメンタリー映画を観た ことがある。A級戦犯の裁判の記録映像を基にした作品 だ。そして私はそんな作品を観て、「東京裁判が思いがけずフェアに行われていた」という事実を知って驚かされた 。民主主義の国らしく、アメリカの弁護士が「彼らには正当な裁判を受ける権利がある」と言ってA級戦犯の弁護を買って出た というのだ。しかもそれだけではなく、フェアな裁判になるように彼ら弁護士がかなり奮闘した という。私にはかなり意外 に感じられた。
あわせて読みたい
【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…
歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る
さて、だからといって、BC級戦犯の裁判もフェアに行われたのかは私には分からない 。作中では、冬至堅太郎の裁判記録を検証している横浜弁護士会のある弁護士が、「しっかりした議論がなされていなかった可能性はあるでしょう」と話していた 。しかしそれでも彼は、「この裁判には意味があった」と断言する 。「裁判が行われたからこそ記録が残っているのだし、記録があるからこそ検証できる 」からだそうだ。確かにそれはその通り だなと思う。
また舞台挨拶の中で監督が、「過去の裁判記録を検証する意味」について同弁護士が語っていた という話を紹介していた。その最大の目的は「過去の惨禍を検証すること」 だという。日本国憲法 には、「(前略)政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する 」という記述がある。しかし、「戦争の惨禍が起ることのないやうにする」ためにはまず、「戦争の惨禍」が何であるのかをはっきりさせなければならない はずだ。そしてそのためには、過去の検証が不可欠 である。そんな話だったそうだ。監督はこの話を聞いて、「これまで、『どうして戦争のことを伝えようとするのか』と聞かれても答えられずモヤモヤすることが多かったが、それがすっきりした 」みたいなことを言っていた。
さて、ここで少し冬至堅太郎から離れるが、あるBC級戦犯が裁判において「米軍による無差別空襲は国際法違反だ」という点について争った という話が出てくる。岡田資という人物 で、結局彼にも死刑判決が下った のだそうだ。ただ、「部下を庇った」と紹介されていたので、彼の部下は死刑判決を免れたのかもしれない 。
あわせて読みたい
【実話】映画『アウシュビッツ・レポート』が描き出す驚愕の史実。世界はいかにホロコーストを知ったのか?
映画『アウシュヴィッツ・レポート』は、アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした実話を基にした作品。2人が持ち出した「アウシュビッツ・レポート」こそが、ホロコーストについて世界が知るきっかけだったのであり、そんな史実をまったく知らなかったことにも驚かされた
それで、この「無差別空襲は国際法違反」という話については、『東京大空襲』というドキュメンタリー映画の中でも少し言及があった 気がする。戦争のルールを規定した国際法では確か「民間人を殺すこと」を禁じているはず で、そのような観点から考えれば、「『無差別空襲』は国際法違反である」という主張も筋が通る んじゃないだろうか。しかし、本作『巣鴨日記 あるBC級戦犯の生涯』ではこの点に関して詳しく触れられなかった ので、どういう議論が展開されたのかはよく分からない。ただやはり、「戦勝国による裁判なので、この点に関しては特に触れられずスルーされた」と考えるのが自然だろうか 。
「平和」のために、私たちは何をしなければならないのだろうか?
映画の後半では、「石垣島事件」と呼ばれる捕虜虐殺事件の話 になる。最終的には、この事件に関わった者の内7人に死刑判決が下った のだが、後半ではその1人である藤中松雄という人物に焦点が当てられる のだ。彼もまた、取り調べや裁判の記録が公文書館で発見されたり 、あるいは、冬至堅太郎の日記に「死刑台に向かう直前の様子」が記されていたり と、多くの情報が残るBC級戦犯 である。さらに、この「石垣島事件」に関わった者の死刑執行は、結果的にだが巣鴨プリズンにとっても大きな区切りとなった と言っていいだろう。詳しくは書かないが、冬至堅太郎にも関係するそれ以後の展開には正直、かなり驚かされてしまった 。そういう意味でも「石垣島事件」はとても印象的 だったなと思う。
さて、冬至堅太郎は『世紀の遺書』という本の出版にも関わっている (以下のリンクは、後に出版された簡易版である)。BC級戦犯ら701名の遺書を収録した大作 であり、そして本作ではその一部が紹介されていた 。恐らく、ほとんどが本意ではない形で死刑を言い渡された者 だろう。そしてそんな彼らの最後の言葉は、当然と言えば当然ではあるが、「戦争には絶対反対 」「恒久的な平和を望んでいる 」「平和を願っていると子々孫々に伝えてくれ 」みたいな主張で溢れていた。
¥2,750 (2025/12/05 06:48時点 | Amazon調べ)
ポチップ
「戦争反対」「恒久平和」みたいな言葉は、現代でも色んな場面で見聞きする ことがあるだろう。しかし私にはどうにも、そういう言葉に「実感」が伴っているようにはあまり感じられない 。やはりそれは、平和な日本で生まれ育った者の言葉だから だと思う。いや、別に私は「平和な国で生まれ育ったら『戦争反対』『恒久平和』みたいなことを言っちゃいけない」なんて話をしているのではない 。むしろ、そういう主張はみんなでした方がいい と考えてさえいる。ただ、そこに「重み」が生まれないのは事実としてどうしたって仕方ない と思う。
一方で、遺書に「戦争反対」などと書いた者たちは、戦争という理不尽を経験し、さらに許しがたい死を目の前にした上でそういう言葉を口にしている のだ。そりゃあ「重み」が全然違う だろう。彼らが「戦争反対」「恒久平和」と書き遺したという事実に対して、私たちはもっと「重み」を感じ、真剣に受け取らなければならない と思う。
さて最後に。冬至堅太郎がある場面で口にした言葉がとても印象的 だったので紹介しておこう。彼は「日本は、加害者としての国民全体の反省がない 」と主張していたのだ。あるいは舞台挨拶で大学教授も、「日本はアジア各国に対する加害についても考えなければならない 」と話していた。この点については私も時々考える 。ただやはり、自分の中にはどうしたって「加害者意識」はない なと思うし(ただ同時に「被害者意識」も私の中にはほぼない )、自分の中からそれが湧き上がってくることもないだろうな という気がしている。「当事者ではない」という点が状況を余計難しくしている と言えるだろう。
この「加害者意識」に関しては、『蟻の兵隊』というドキュメンタリー映画のことも連想された 。主人公である奥村和一は、上官の命令で終戦後も中国での内戦に参加させられた「中国残留部隊」の1人 であり、そんな彼には、訓練で「罪のない中国人」を殺したという過去 がある。
あわせて読みたい
【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞
映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である
帰国した奥村和一は、「自分は被害者だ」という意識で主張・発信を続けていた わけだが、ドキュメンタリー映画の撮影の過程で「自身が成した加害」について改めて直視させられ、そしてそれを受けて自身の行動や思考を変えていった という。そういうことを、上映後のトークイベントの中で監督が話していた。自身の加害を振り返り見つめ直すことはとても勇気が要る ことだと思うのだが、奥村和一は「加害者としての過去」もきちんと背負う覚悟を持って前に進んでいく決断をした というわけだ。
私自身もそういうことが出来る人間でありたい なと思うし、日本という国もやはり、「都合の悪い過去」を隠すのではなく、徹底的に向き合って振り返るべき なのだと改めて感じさせられた。
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
私にとっては、今外国で起こっている戦争も、かつて日本が関わった戦争も、どちらもとても遠い存在 に思えている。自分に関係がある出来事だとはあまり感じられない 。それは仕方ないことだと思いつつ、やはり良くないよなぁ とも思う。
あわせて読みたい
【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実
映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた
だからこうして時々、過去の歴史に触れるようなドキュメンタリーを意識的に観るようにしている 。それで何か分かった気になれるわけではないが、知らないよりは知っておいた方がいいはずだし、分からなくても分かろうとすることは大事じゃないか と思う。
それにしても、BC級戦犯については全然何も知らなかった 。ごく一般的な人であれば私と変わらない知識レベルだろう し、そういう人にとって本作は、BC級戦犯について知るのにとても良い作品 と言っていいだろうと思う。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【煽動】プロパガンダの天才ゲッベルスがいかにヒトラーやナチスを”演出”したのかを描く映画:『ゲッベ…
映画『ゲッベルス ヒトラーをプロデュースした男』では、ナチスドイツで宣伝大臣を担当したヨーゼフ・ゲッベルスに焦点が当てられる。「プロパガンダの天才」と呼ばれた彼は、いかにして国民の感情を操作したのか。「現代の扇動家」に騙されないためにも、そんな彼の数奇な人生や実像を理解しておいた方がいいのではないかと思う
あわせて読みたい
【評価】都知事選出馬、安芸高田市長時代の「恥を知れ」などで知られる石丸伸二を描く映画『掟』
石丸伸二をモデルに描くフィクション映画『掟』は、「地方政治に無関心な人」に現状の酷さを伝え、「自分ごと」として捉えてもらうきっかけとして機能し得る作品ではないかと感じた。首長がどれだけ変革しようと試みても、旧弊な理屈が邪魔をして何も決まらない。そんな「地方政治の絶望」が本作には詰め込まれているように思う
あわせて読みたい
【悲劇】東京大空襲経験者の体験談。壊滅した浅草、隅田川の遺体、その後の人々の暮らし等の証言集:映…
映画『東京大空襲 CARPET BOMBING of Tokyo』は、2時間半で10万人の命が奪われたという「東京大空襲」を始め、「山手空襲」「八王子空襲」などを実際に経験した者たちの証言が収録された作品だ。そのあまりに悲惨な実態と、その記憶を具体的にはっきりと語る証言者の姿、そのどちらにも驚かされてしまった
あわせて読みたい
【信念】アフガニスタンに中村哲あり。映画『荒野に希望の灯をともす』が描く規格外の功績、生き方
映画『荒野に希望の灯をともす』は、アフガニスタンの支援に生涯を捧げ、個人で実現するなど不可能だと思われた用水路建設によって砂漠を緑地化してしまった中村哲を追うドキュメンタリー映画だ。2019年に凶弾に倒れるまで最前線で人々を先導し続けてきたその圧倒的な存在感に、「彼なき世界で何をすべきか」と考えさせられる
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『ソウルの春』は、軍部が反乱を起こした衝撃の実話「粛清クーデター」の真相を描く(…
映画『ソウルの春』は、「これが実話!?」と感じるほど信じがたい史実が描かれる作品だ。韓国が軍事政権下にあったことは当然知っていたが、まさかこんな感じだったとは。「絶対的な正義 VS 絶対的な悪」みたいな展開で、「絶対にこうなるはず!」と思い込んでいたラストにならなかったことも、個人的には衝撃的すぎた
あわせて読みたい
【正義】名張毒ぶどう酒事件の真相解明の鍵を握る、唯一の再審請求人である妹・岡美代子を追う映画:『…
冤罪と目されている「名張毒ぶどう酒事件」を扱ったドキュメンタリー映画『いもうとの時間』は、逮捕され死刑囚として病死した奥西勝の妹・岡美代子に焦点を当てている。というのも彼女は、「再審請求権」を持つ唯一の人物なのだ。このままでは、事件の真相は闇の中だろう。まずは再審の扉が開かれるべきだと私は思う
あわせて読みたい
【友情】映画『ノー・アザー・ランド』が映し出す酷すぎる現実。イスラエル軍が住居を壊す様は衝撃だ
イスラエルのヨルダン川西岸地区内の集落マサーフェル・ヤッタを舞台にしたドキュメンタリー映画『ノー・アザー・ランド』では、「昔からその場所に住み続けているパレスチナ人の住居をイスラエル軍が強制的に破壊する」という信じがたい暴挙が映し出される。そんな酷い現状に、立場を越えた友情で立ち向かう様を捉えた作品だ
あわせて読みたい
【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実
映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた
あわせて読みたい
【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞
映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である
あわせて読みたい
【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…
映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた
あわせて読みたい
【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件
映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品
あわせて読みたい
【狂気】ISISから孫を取り戻せ!映画『”敵”の子どもたち』が描くシリアの凄絶な現実
映画『”敵”の子どもたち』では、私がまったく知らなかった凄まじい現実が描かれる。イスラム過激派「ISIS」に望んで参加した女性の子ども7人を、シリアから救出するために奮闘する祖父パトリシオの物語であり、その最大の障壁がなんと自国のスウェーデン政府なのだる。目眩がするような、イカれた現実がここにある
あわせて読みたい
【情熱】選挙のおもしろ候補者含め”全員取材”をマイルールにする畠山理仁の異常な日常を描く映画:『NO …
選挙に取り憑かれた男・畠山理仁を追うドキュメンタリー映画『NO 選挙, NO LIFE』は、「平均睡眠時間2時間」の生活を長年続ける”イカれた”ライターの「選挙愛」が滲み出る作品だ。「候補者全員を取材しなければ記事にはしない」という厳しすぎるマイルールと、彼が惹かれる「泡沫候補」たちが実に興味深い
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話
映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ
あわせて読みたい
【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー
北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった
あわせて読みたい
【衝撃】映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想外すぎる着地を見せる普通じゃないドキュメンタリー
国連事務総長だったハマーショルドが乗ったチャーター機が不審な墜落を遂げた事件を、ドキュメンタリー映画監督マッツ・ブリュガーが追う映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想もつかない衝撃の展開を見せる作品だ。全世界を揺るがしかねない驚きの”真実”とは?
あわせて読みたい
【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実
弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている
あわせて読みたい
【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…
ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?
あわせて読みたい
【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る
TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す
あわせて読みたい
【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…
稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる
あわせて読みたい
【誠実】映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』で長期密着した政治家・小川淳也の情熱と信念が凄まじい
政治家・小川淳也に17年間も長期密着した映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』は、誠実であるが故に大成できない1人の悩める政治家のありのままが描かれる。サラリーマン家庭から政治家を目指し、未来の日本を健全にするために奮闘する男の信念と情熱が詰まった1本
あわせて読みたい
【衝撃】自ら立ち上げた「大分トリニータ」を放漫経営で潰したとされる溝畑宏の「真の実像」に迫る本:…
まったく何もないところからサッカーのクラブチーム「大分トリニータ」を立ち上げ、「県リーグから出発してチャンピオンになる」というJリーグ史上初の快挙を成し遂げた天才・溝畑宏を描く『爆走社長の天国と地獄』から、「正しく評価することの難しさ」について考える
あわせて読みたい
【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態
ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない
あわせて読みたい
【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す
香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見
ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す
あわせて読みたい
【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…
『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか
あわせて読みたい
【狂気】アメリカの衝撃の実態。民営刑務所に刑務官として潜入した著者のレポートは国をも動かした:『…
アメリカには「民営刑務所」が存在する。取材のためにその1つに刑務官として潜入した著者が記した『アメリカン・プリズン』は信じがたい描写に溢れた1冊だ。あまりに非人道的な行いがまかり通る狂気の世界と、「民営刑務所」が誕生した歴史的背景を描き出すノンフィクション
あわせて読みたい
【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り
プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
あわせて読みたい
【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』
2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない
あわせて読みたい
【歴史】『大地の子』を凌駕する中国残留孤児の現実。中国から奇跡的に”帰国”した父を城戸久枝が描く:…
文化大革命の最中、国交が成立していなかった中国から自力で帰国した中国残留孤児がいた。その娘である城戸久枝が著した『あの戦争から遠く離れて』は、父の特異な体験を起点に「中国残留孤児」の問題に分け入り、歴史の大きなうねりを個人史として体感させてくれる作品だ
あわせて読みたい
【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…
映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた
あわせて読みたい
【驚愕】キューバ危機の裏側を描くスパイ映画『クーリエ』。核戦争を回避させた民間人の衝撃の実話:『…
核戦争ギリギリまで進んだ「キューバ危機」。その陰で、世界を救った民間人がいたことをご存知だろうか?実話を元にした映画『クーリエ:最高機密の運び屋』は、ごく普通のセールスマンでありながら、ソ連の膨大な機密情報を盗み出した男の信じがたい奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?
タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う
あわせて読みたい
【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…
ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ
あわせて読みたい
【衝撃】『ゆきゆきて、神軍』はとんでもないドキュメンタリー映画だ。虚実が果てしなく入り混じる傑作
奥崎謙三という元兵士のアナーキストに密着する『ゆきゆきて、神軍』。ドキュメンタリー映画の名作として名前だけは知っていたが、まさかこんなとんでもない映画だったとはと驚かされた。トークショーで監督が「自分の意向を無視した編集だった」と語っていたのも印象的
あわせて読みたい
【実話】映画『アウシュビッツ・レポート』が描き出す驚愕の史実。世界はいかにホロコーストを知ったのか?
映画『アウシュヴィッツ・レポート』は、アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした実話を基にした作品。2人が持ち出した「アウシュビッツ・レポート」こそが、ホロコーストについて世界が知るきっかけだったのであり、そんな史実をまったく知らなかったことにも驚かされた
あわせて読みたい
【勇敢】ユダヤ人を救った杉原千畝を描く映画。日本政府の方針に反しながら信念を貫いた男の生き様
日本政府の方針に逆らってまでユダヤ人のためにビザを発給し続けた外交官を描く映画『杉原千畝』。日本を良くしたいと考えてモスクワを夢見た青年は、何故キャリアを捨てる覚悟で「命のビザ」を発給したのか。困難な状況を前に、いかに決断するかを考えさせられる
あわせて読みたい
【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…
『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る
あわせて読みたい
【絶望】「人生上手くいかない」と感じる時、彼を思い出してほしい。壮絶な過去を背負って生きる彼を:…
「北九州連続監禁殺人事件」という、マスコミも報道規制するほどの残虐事件。その「主犯の息子」として生きざるを得なかった男の壮絶な人生。「ザ・ノンフィクション」のプロデューサーが『人殺しの息子と呼ばれて』で改めて取り上げた「真摯な男」の生き様と覚悟
あわせて読みたい
【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…
歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る
あわせて読みたい
【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…
金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る
あわせて読みたい
【現実】戦争のリアルを”閉じ込めた”映画。第一次世界大戦の英軍を収めたフィルムが描く衝撃:映画『彼…
第一次世界大戦でのイギリス兵を映した膨大な白黒フィルムをカラー化して編集した『彼らは生きていた』は、白黒の映像では実感しにくい「リアルさ」を強く感じられる。そして、「戦争は思ったよりも安易に起こる」「戦争はやはりどこまでも虚しい」と実感できる
あわせて読みたい
【天才】『三島由紀夫vs東大全共闘』後に「伝説の討論」と呼ばれる天才のバトルを記録した驚異の映像
1969年5月13日、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の討論が行われた。TBSだけが撮影していたフィルムを元に構成された映画「三島由紀夫vs東大全共闘」は、知的興奮に満ち溢れている。切腹の一年半前の討論から、三島由紀夫が考えていたことと、そのスタンスを学ぶ
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
戦争・世界情勢【本・映画の感想】 | ルシルナ
日本に生きているとなかなか実感できませんが、常に世界のどこかで戦争が起こっており、なくなることはありません。また、テロや独裁政権など、世界を取り巻く情勢は様々で…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…



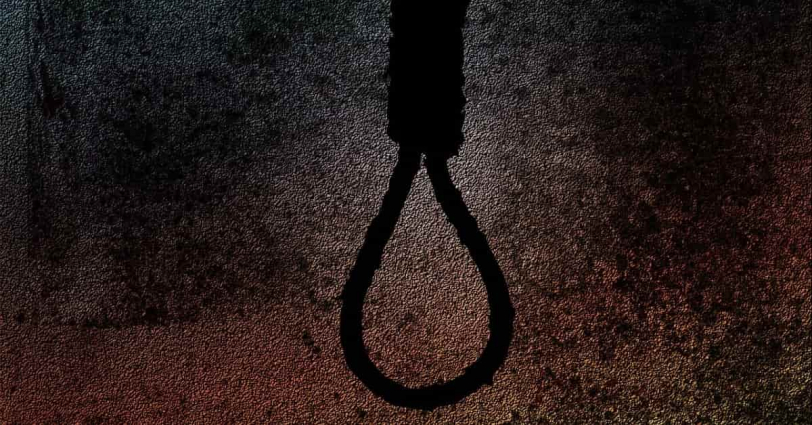










































































コメント