目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:前間孝則
¥700 (2021/12/24 06:18時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- NASAでさえ理解していなかった航空理論を、自動車メーカーのホンダが見出した奇跡
- 試作機の飛行テストが成功したからこその苦悩
- 世界的企業GE社も驚愕した「本田技研工業」の異次元の企業文化
技術的にも社風的にも、ホンダでなければ成し遂げられなかっただろう歴史的偉業
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
「ホンダジェット」はいかにして誕生したか?革命的な技術革新とホンダの英断に迫る
「航空機の歴史における革新的な案」と評価された「主翼上のエンジン」
あわせて読みたい
【実話】実在の人物(?)をモデルに、あの世界的超巨大自動車企業の”内実”を暴く超絶面白い小説:『小…
誰もが知るあの世界的大企業をモデルに据えた『小説・巨大自動車企業トヨトミの野望』は、マンガみたいなキャラクターたちが繰り広げるマンガみたいな物語だが、実話をベースにしているという。実在の人物がモデルとされる武田剛平のあり得ない下剋上と、社長就任後の世界戦略にはとにかく驚かされる
2015年から運用が開始された、ホンダ開発の小型ビジネスジェット機「ホンダジェット」。販売初日に100機が売れ、その後出荷数世界一を達成するなど、ビジネスとしても高く評価されるこの「ホンダジェット」だが、その最も革新的な点はエンジンにある。
「ホンダジェット」のエンジンはなんと、主翼の上にあるのだ。

一般的なビジネスジェット機の場合は、機体の側面にエンジンがついている。しかしホンダは、様々なチャレンジを続けた結果、主翼の上にエンジンを載せる方がより効率が良いと発見する。そして、世界初となる「主翼上のエンジン」を実用化させるに至ったのだ。
この発明は、
航空機の歴史における革新的な案
と評され、
航空先進国の欧米の研究者、技術者といえども、この三賞を合わせて同時に受賞した人物はいない。ホンダジェットの設計責任者であり開発リーダーでもある藤野が、これらの栄誉ある賞をすべて受賞したことは、間違いなく世界が彼の功績を認知して高く評価したことを意味している
と、航空機業界では並ぶもののない評価を得ている。
あわせて読みたい
【超人】NHKによる「JAXAの宇宙飛行士選抜試験」のドキュメント。門外不出の「最強の就活」:『ドキュメ…
難攻不落のJAXAと粘り強い交渉を重ね、門外不出の「最強の就活」を捉えたドキュメンタリーを書籍化した『ドキュメント宇宙飛行士選抜試験』。2021年の13年ぶりの募集も話題になったが、「欠点があってはいけない」という視点で厳しく問われる試験・面接の実情を描き出す
しかしこの設計は本当に繊細なようで、
実際のホンダジェットの機体でいえば、主翼上のエンジンの位置が、それこそわずか数十センチさらには数センチ異なるだけで、干渉抵抗がまったく違ってきます。本当に細かいところまで最適な位置を探さないと抵抗が下がらない
というほどだという。「主翼の上にエンジンを載せる」というアイデア1つで実現に至ったわけではないのだ。
そもそもこのアイデアはどれほど突飛なのか。それを実感させてくれる、こんな文章がある。
出すのはやめたほうがいい。NASAですら、いろいろな研究をしてきて、こういうことをまだわかっていないのだから、発表した後に、『こんなのダメだ』と酷評されたら、お前の航空機設計者としての生命は終わりだぞ。もちろん、ホンダジェットの未来も無くなる可能性がある
あわせて読みたい
【驚異】プロジェクトマネジメントの奇跡。ハリウッドの制作費以下で火星に到達したインドの偉業:映画…
実は、「一発で火星に探査機を送り込んだ国」はインドだけだ。アメリカもロシアも何度も失敗している。しかもインドの宇宙開発予算は大国と比べて圧倒的に低い。なぜインドは偉業を成し遂げられたのか?映画『ミッション・マンガル』からプロジェクトマネジメントを学ぶ
「こういうこと」というのは、「エンジンを主翼に対して最適な位置に配置することで、高速飛行時の造波抵抗を減少させる理論」のことだ。NASAでさえ分かっていないということは、世界の航空機メーカーのどこも知らないということでもある。そんなとんでもない理論と実用機を、ホンダは生み出してしまったのだ。

そこには当然、「航空機メーカーではない、自動車メーカーのホンダが実現した」という驚きもある。航空機メーカーからすれば信じがたい偉業だろう。
「ホンダジェット」のプロジェクトが動き始めたのはなんと1986年、プロジェクトリーダーである藤野が入社して3年目というタイミングだった。藤野は突然「航空機をやれ」と命じられ、社内でも極秘裏に開発が進められることになったのだ。その後2003年に初飛行を成功させるわけだが、開発を始めた当初は、
そもそもチームの誰ひとりとして実際に航空機を設計したこともつくったこともない
あわせて読みたい
【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…
『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る
という状態だった。そんなホンダが今では、
世界を見渡してみても、機体とジェットエンジンの両方をすべて丸ごと自前で開発・生産している主要なメーカーは見当たらない
というほど唯一無二の存在になっている。まったくの異業種でありながら、航空機というかなり参入のハードルが高い分野で、誰も真似できない存在にまで上り詰めた「技術のホンダ」の凄まじさが実感できることだろう。
あわせて読みたい
【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….
つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る
「試作機完成後」の苦難
やっと初飛行に成功したとの安堵感と同時に、これでもってホンダにおける小型機の開発プロジェクトが終わりになるのでは、との思いが頭をもたげてきて、先行きに対する不安を覚えました
これは、試作機のフライトが成功した直後の藤野の感想である。一読して意味が分かるだろうか? 私は、試作機が完成したのに先行きが不安になる理由が想像できなかった。
そこには航空機ならではの事情が関係している。
航空機は、電化製品やバイクなどと違い、売った後も整備やアフターサービスが不可欠だ。つまり、航空機を作るだけではなく、その整備やアフターサービスの態勢も整えなければならないということだ。また当然だが、量産するとなれば新たに工場の建設も必要である。しかし小型ジェット機の売上は景気変動に左右されるし、車と比べれば圧倒的に出荷台数が少ない。そのため、工場を建設して量産体制を整えてもビジネスとして成り立つのか分からないのだ。
たとえ実験機(試作機)づくりに巨額の資金がかかったとしても、そこで止めれば、それまでの出費で終わらせることができる。ところが事業化して量産・販売するとなると、そうはいかない
確かにその通りだ。初飛行の際にはマスコミに向けて、
これは実験機であり、ビジネスプランは持っていない。あくまで技術を確認するための初飛行であり、今後も飛行試験を続けていきます
と、ビジネスとしての展開を見据えているわけではないのだと釘をさすように言っている。
あわせて読みたい
【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…
メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方
この経営判断には、上層部も相当に悩んだようだ。本書には、
会社の首脳陣すら決めかねていたが、むしろ、開発プロジェクトの中止に大きく傾いていた

というような表現が随所に登場する。プロジェクトリーダーの藤野は開発に成功したのだが、その後に続く「小型ジェット機をビジネスにする」というステップに進むまでには相当時間を要することになってしまったのである。
それだけ慎重になる理由も分からないではない。ジェットエンジンの世界的な巨大企業でさえ倒産してしまう世界だからだ。
やはり1970年代、世界三大ジェットエンジンメーカーの一つ、英ロールス・ロイス社も、大型エンジンの開発が低迷して事実上倒産し、国有化されて再建を図った。
世界的な名門の巨大企業が、一つの航空機やジェットエンジンの開発あるいはビジネスに失敗したことで倒産してしまう。なにしろ、数年前に市場投入された新型機のボーイング787は開発費だけで1兆8000億円にも達しているのである。量産を前提とする工業製品において、このようにリスクが高くて巨額の開発費を要するものはほかには見当たらない。
あわせて読みたい
【挑戦】手足の指を失いながら、今なお挑戦し続ける世界的クライマー山野井泰史の”現在”を描く映画:『…
世界的クライマーとして知られる山野井泰史。手足の指を10本も失いながら、未だに世界のトップをひた走る男の「伝説的偉業」と「現在」を映し出すドキュメンタリー映画『人生クライマー』には、小学生の頃から山のことしか考えてこなかった男のヤバい人生が凝縮されている
このような厳しい世界に、まったくの異業種から参戦すべきなのか。二の足を踏むのも無理はないだろう。
他にも、こんな懸念があった。
アメリカで売り出したはいいが、もし事故などを起こして人命が失われたりすると、圧倒的な売上を占めるオートバイや自動車の信用を傷つけ、販売にダメージを与えて大きなマイナスになるのではないか。やはり試作機の段階に止めるべきではないか
確かにその通りだろう。軌道に乗るかどうか分からない小型ジェット機の事業で死者を出してしまえば、ホンダを支えるオートバイや自動車の販売にも影響が出るかもしれない。そのリスクを負ってでもビジネスに乗り出すべきなのだろうか。
あわせて読みたい
【伝説】やり投げ選手・溝口和洋は「思考力」が凄まじかった!「幻の世界記録」など数々の逸話を残した…
世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的なトレーニングと、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界記録」を叩き出した天才の伝説と実像
会社がその決断を下すまでの間、藤野は相当悩んだ。
先が見えないまま、新たなコンセプトに基づく具体的なプランをまとめ上げるまでの一年半ほどは、今までの大変さとは違う、これまでで最も辛い時期でした。サポートも得られず、いっそのこと、会社を辞めてしまおうかと迷ったこともあります。いろんなことを考え悩みました
それはそうだろうと思う。初飛行を成功させたことでプロジェクトは縮小、プロジェクトメンバーの多くは異動となり、藤野自身は実験データを取り続ける日々を過ごしていたのだ。事業化の話が進展しないまま、藤野には他社からの引き抜きの話が来て揺れる。しかし、チャンスを見つけてはアピールを続け、ついに社長が決断。事業化へと舵を切ることができたのである。
あわせて読みたい
【誤解】「意味のない科学研究」にはこんな価値がある。高校生向けの講演から”科学の本質”を知る:『す…
科学研究に対して、「それは何の役に立つんですか?」と問うことは根本的に間違っている。そのことを、「携帯電話」と「東急ハンズの棚」の例を使って著者は力説する。『すごい実験』は素粒子物理学を超易しく解説する本だが、科学への関心を抱かせてもくれる
「ホンダ」だからこそ成し得た技術開発と事業化
事業化を決断したホンダは、その後GE社と手を組むが、
「このようなやり方が許容される会社など、世界を見渡しても、ホンダをおいてほかにはないだろう」とGEからも散々いわれました
と藤野は語っている。それほどまでにホンダという会社は、普通とはまったくマインドの異なる企業文化があるということだ。
あわせて読みたい
【組織】意思決定もクリエイティブも「問う力」が不可欠だ。MIT教授がCEOから学んだ秘訣とは?:『問い…
組織マネジメントにおいては「問うこと」が最も重要だと、『問いこそが答えだ!』は主張する。MIT教授が多くのCEOから直接話を聞いて学んだ、「『問う環境』を実現するための『心理的安全性の確保』の重要性」とその実践の手法について、実例満載で説明する1冊
そこにはやはり、創業者である本田宗一郎のスピリットが関係している。
本田宗一郎は1962年の時点で既に、社内報で航空機の開発・生産に言及していた。
1962年6月、本田宗一郎は航空機の開発・生産に乗り出そうとしていることを全従業員に伝えた。
「いよいよ私どもの会社でも軽飛行機を開発しようと思っていますが、この飛行機はだれにも乗れる優しい操縦で、値段が安い飛行機でございます」
本田宗一郎自身が、航空機への夢を抱いていたのだ。藤野もまた、「本田技研工業」という社名に対して次のような想いを持っている。

歴代トップの誰もが『ホンダはパーソナルモビリティーのカンパニーである』と口にされてきました。だから、『本田自動車』とはいわないで、『本田技研工業』といってきたのだと思います。われわれ社員もまた、ホンダは自動車会社というよりは広くパーソナルモビリティーを追求する会社だと思っています
彼はこう首脳陣に主張し、事業化へのGOサインを勝ち取ったのだ。
しかし、日本で航空機の開発を行うにあたって様々な障害にぶつかった。開発費が巨額であること、あるいは、日本で自動車の需要が高まっていく時期に航空機まで手が回らなかったことなどに加えて、
また、通産省も大蔵省(現・財務省)もメーカーとともに、失敗した“YS-11”のトラウマを引きずっていて、足並みも揃わなかったのである
という事情もある。YS-11とは、日本が初めて作った国産の旅客機だ。様々な事情から上手くいかなかったYS-11の記憶が、日本での航空機開発を及び腰にさせていたのである。
あわせて読みたい
【圧巻】150年前に気球で科学と天気予報の歴史を変えた挑戦者を描く映画『イントゥ・ザ・スカイ』
「天気予報」が「占い」と同等に扱われていた1860年代に、気球を使って気象の歴史を切り開いた者たちがいた。映画『イントゥ・ザ・スカイ』は、酸素ボンベ無しで高度1万1000m以上まで辿り着いた科学者と気球操縦士の物語であり、「常識を乗り越える冒険」の素晴らしさを教えてくれる
藤野が就職活動をしていたのは、まさにYS-11の失敗の記憶が色濃かった時期であり、
たとえ日本の大手航空機メーカーに入ったとしても、米軍機のライセンス生産とか、ボーイングとの共同開発に甘んじるような仕事ばかりでは魅力が感じられない。ダイナミックな仕事はできないのではないか。そう考えて迷わず自動車会社に入ったのです
と語っている。航空機への想いを抱きつつ、日本では大きな仕事はできないだろうと考えてホンダに入社した藤野がいたからこそ、このプロジェクトは完遂したとも言えるかもしれない。
またホンダには、技術者出身の社長が多いことも大きく影響した。6代目社長の福井威夫も技術者出身である。
六代目社長に就任した福井威夫は、引き継いだホンダジェットの開発をさらに推し進めるのだが、やがて、事業化するか否かの重い決断を迫られることになる。彼もまた、無類のレース好きであった。このような資質の持ち主が歴代の社長を務めなければ、大きなリスクを伴うホンダジェットの開発から事業化に至るまでの迷いと逡巡の20年間は、耐えられなかったであろう

確かに、技術者だからこそ理解できることがあるはずだ。予算やバランスシートだけからは判断できない、技術者だからこその信念や確信がトップにも息づいているからこそ、チャレンジングなことができると言える。
また技術者出身の社長だからこそ、
研究開発に対して金をちびったらいかん
という感覚を共有することが可能なのだ。このスタンスこそが「技術のホンダ」を支えているのだろうとも感じる。
藤野道格は何故、航空業界の常識に立ち向かうようなチャレンジができたのか
ピッチングモーメントは空気中の剥離が影響するのですが、翼あるいは飛行機を設計する人の考え方は、空気流の剥離をできるだけ起こさせないというのが基本でした。しかし、深く考えてみると、剥離を起こさせないということが、果たして第一条件なのかどうか。もちろん剥離は最小限であるのが望ましいですが、剥離が起こっても実際の機体にペナルティーがほとんどなければ、逆に剥離をうまく使ってピッチングモーメントを軽減できるのではないかという点に着目したのです
今度は空力干渉を最小限にするというより、むしろ、この空力干渉を使って抵抗をさらにマイナスに(低減)できることがわかってきました
こういう技術的な内容がきちんと理解できるわけではないのだが、これらの記述から、藤野が「航空業界の『当たり前』を打ち崩したことで新たな発見が生まれた」と分かるだろう。
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
ここには当然、藤野のずば抜けたセンスと才能、そして努力が関係してくるのだが、他にもこんな要素が絡んでくる。
実はこれらの機体の基本設計思想は、60,70年代の延長線上にあって、基本的な形や全体のコンフィギュレーション(構成)も、十年、いや五十年一日のごとく相変わらず、胴体の脇にエンジンが付いている形態です。決して性能が抜群にいいとか、革新的な技術を使っているというわけでもないのです
確かに航空機は昔から形が決まっているし、そもそも本書には、
機体の形状の99%はすべて機能で決まってしまう
とさえ書かれている。しかも、参入障壁が高いが故に少数の企業でしか作られない。そういう状態にあるから、「より良いアイデアを追究しよう」という発想にならなくなってしまうのではないか、という指摘だ。
さらに、こんな問題もある。

自分が一番難しいと思ったのは、確かに、これらの専門的な勉強に10年、20年かかり、それだけでも大変なことではあるのだが、その専門分野を長く勉強していると、いつのまにか勉強すること自体が仕事になってしまう。新しい発想というよりも、今までに読んで学んだ論文や理論に従って、この設計はおかしいとか、学んだ知識を他の人に教えることが仕事になってしまうというか。たとえば、評論家のように、これはすでにNASAで試験がなされていて、こういう結果が出ているからダメだとかなって、飛行機とはこういうものだ、という固定観念にとらわれてしまう。それは怖いことです
あわせて読みたい
【問い】「学ぶとはどういうことか」が学べる1冊。勉強や研究の指針に悩む人を導いてくれる物語:『喜嶋…
学校の勉強では常に「課題」が与えられていたが、「学び」というのは本来的に「問題を見つけること」にこそ価値がある。研究者の日常を描く小説『喜嶋先生の静かな世界』から、「学びの本質」と、我々はどんな風に生きていくべきかについて考える
航空機というのは「安全に飛ぶこと」が至上命題であり、そのために学ばなければならないことが膨大に存在する。そしてそれらを学んでいく内に、「自分が学んでいること、学んできたことが『絶対的な真理』のようになってしまう」というわけだ。習得に時間が掛かる分野であるが故の問題だと言える。
そしてだからこそ、ホンダのような未経験の新規参入企業が、「技術で正面突破する」という正攻法で闘える余地が残されている、というわけだ。
その辺りのことを理解していた藤野は、「ホンダジェット」のプロジェクト初期から明確なビジョンを持っていた。しかしそれはなかなか受け入れられなかったという。
あえて未知なる技術を幾つも盛り込んだホンダジェットの狙いや意味、技術的な価値、小型ビジネスジェット機業界における位置付けなどを、直属の上司だけでなく、同僚にもなかなか理解してもらえない日々が続きました。ですから、経営会議の後の一年半から二年にわたり、チームの中では議論百出で大揉めでした
それでも藤野は、
他のメーカーがつくったものと同じようなものを、これから新規参入しようとするホンダがつくって、何か意味があるのか?
と訴えて、自分たちが進むべき道を明確に示したという。
あわせて読みたい
【奇跡】ビッグデータに”直感”を組み込んで活用。メジャーリーグを変えたデータ分析家の奮闘:『アスト…
「半世紀で最悪の野球チーム」と呼ばれたアストロズは、ビッグデータの分析によって優勝を果たす。その偉業は、野球のド素人によって行われた。『アストロボール』をベースに、「ビッグデータ」に「人間の直感」を組み込むという革命について学ぶ
また、当初から藤野は、「ホンダジェット」の事業化にこだわっていた。
「人の役に立ち、使ってもらうものを開発する」というかねてからの希望に手応えを感じられないからだ。「航空機をやるというのなら、絶対に売るところまでもっていくべきだし、やり抜くべきだ」というのが、このときに抱いた彼の決意だった
そしてだからこそ、何よりも事業化を優先した。技術的にチャレンジすべき部分はもちろん挑戦するのだが、事業化の足かせになると判断すればその挑戦を諦めもする。このようなバランス感覚があったからこそ、プロジェクトを最後まで導くことができたのだ。
そんな藤野を始めとする、プロジェクトメンバーたちの奮闘の記録を、是非読んでみてほしい。
あわせて読みたい
【情熱】選挙のおもしろ候補者含め”全員取材”をマイルールにする畠山理仁の異常な日常を描く映画:『NO …
選挙に取り憑かれた男・畠山理仁を追うドキュメンタリー映画『NO 選挙, NO LIFE』は、「平均睡眠時間2時間」の生活を長年続ける”イカれた”ライターの「選挙愛」が滲み出る作品だ。「候補者全員を取材しなければ記事にはしない」という厳しすぎるマイルールと、彼が惹かれる「泡沫候補」たちが実に興味深い
著:孝則, 前間
¥418 (2022/01/29 20:36時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…
稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる
本書を読んで改めて感じたのは、「圧倒的な技術」は1つの「物語」である、ということだ。一企業の開発物語にここまで心を打たれるのは、技術に対するリスペクトや、技術と向き合う者たちへの敬意を持ってしまうからだろう。
決して技術だけでは成し得なかった大プロジェクトではあるが、「技術のホンダ」の名に恥じない歴史的偉業であることは間違いないだろう。そんな壮大な物語を、是非体感してほしいと思う。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【情熱】選挙のおもしろ候補者含め”全員取材”をマイルールにする畠山理仁の異常な日常を描く映画:『NO …
選挙に取り憑かれた男・畠山理仁を追うドキュメンタリー映画『NO 選挙, NO LIFE』は、「平均睡眠時間2時間」の生活を長年続ける”イカれた”ライターの「選挙愛」が滲み出る作品だ。「候補者全員を取材しなければ記事にはしない」という厳しすぎるマイルールと、彼が惹かれる「泡沫候補」たちが実に興味深い
あわせて読みたい
【伝説】映画『ミスター・ムーンライト』が描くビートルズ武道館公演までの軌跡と日本音楽への影響
ザ・ビートルズの武道館公演が行われるまでの軌跡を描き出したドキュメンタリー映画『ミスター・ムーンライト』は、その登場の衝撃について語る多数の著名人が登場する豪華な作品だ。ザ・ビートルズがまったく知られていなかった頃から、伝説の武道館公演に至るまでの驚くべきエピソードが詰まった1作
あわせて読みたい
【天才】映画『Winny』(松本優作監督)で知った、金子勇の凄さと著作権法侵害事件の真相(ビットコイン…
稀代の天才プログラマー・金子勇が著作権法違反で逮捕・起訴された実話を描き出す映画『Winny』は、「警察の凄まじい横暴」「不用意な天才と、テック系知識に明るい弁護士のタッグ」「Winnyが明らかにしたとんでもない真実」など、見どころは多い。「金子勇=サトシ・ナカモト」説についても触れる
あわせて読みたい
【実話】福島智とその家族を描く映画『桜色の風が咲く』から、指点字誕生秘話と全盲ろうの絶望を知る
「目が見えず、耳も聞こえないのに大学に進学し、後に東京大学の教授になった」という、世界レベルの偉業を成し遂げた福島智。そんな彼の試練に満ちた生い立ちを描く映画『桜色の風が咲く』は、本人の葛藤や努力もさることながら、母親の凄まじい献身の物語でもある
あわせて読みたい
【苦悩】「やりがいのある仕事」だから見て見ぬふり?映画『アシスタント』が抉る搾取のリアル
とある映画会社で働く女性の「とある1日」を描く映画『アシスタント』は、「働くことの理不尽さ」が前面に描かれる作品だ。「雑用」に甘んじるしかない彼女の葛藤がリアルに描かれている。しかしそれだけではない。映画の「背景」にあるのは、あまりに悪逆な行為と、大勢による「見て見ぬふり」である
あわせて読みたい
【傑物】フランスに最も愛された政治家シモーヌ・ヴェイユの、強制収容所から国連までの凄絶な歩み:映…
「フランスに最も愛された政治家」と評されるシモーヌ・ヴェイユ。映画『シモーヌ』は、そんな彼女が強制収容所を生き延び、後に旧弊な社会を変革したその凄まじい功績を描き出す作品だ。「強制収容所からの生還が失敗に思える」とさえ感じたという戦後のフランスの中で、彼女はいかに革新的な歩みを続けたのか
あわせて読みたい
【実話】映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』(杏花主演)が描く、もの作りの絶望(と楽しさ)
実在したエロ雑誌編集部を舞台に、タブーも忖度もなく業界の内実を描き切る映画『グッドバイ、バッドマガジンズ』は、「エロ雑誌」をテーマにしながら、「もの作りに懸ける想い」や「仕事への向き合い方」などがリアルに描かれる素敵な映画だった。とにかく、主役を演じた杏花が良い
あわせて読みたい
【感動】円井わん主演映画『MONDAYS』は、タイムループものの物語を革新する衝撃的に面白い作品だった
タイムループという古びた設定と、ほぼオフィスのみという舞台設定を駆使した、想像を遥かに超えて面白かった映画『MONDAYS』は、テンポよく進むドタバタコメディでありながら、同時に、思いがけず「感動」をも呼び起こす、竹林亮のフィクション初監督作品
あわせて読みたい
【実話】実在の人物(?)をモデルに、あの世界的超巨大自動車企業の”内実”を暴く超絶面白い小説:『小…
誰もが知るあの世界的大企業をモデルに据えた『小説・巨大自動車企業トヨトミの野望』は、マンガみたいなキャラクターたちが繰り広げるマンガみたいな物語だが、実話をベースにしているという。実在の人物がモデルとされる武田剛平のあり得ない下剋上と、社長就任後の世界戦略にはとにかく驚かされる
あわせて読みたい
【衝撃】自ら立ち上げた「大分トリニータ」を放漫経営で潰したとされる溝畑宏の「真の実像」に迫る本:…
まったく何もないところからサッカーのクラブチーム「大分トリニータ」を立ち上げ、「県リーグから出発してチャンピオンになる」というJリーグ史上初の快挙を成し遂げた天才・溝畑宏を描く『爆走社長の天国と地獄』から、「正しく評価することの難しさ」について考える
あわせて読みたい
【偉業】「卓球王国・中国」実現のため、周恩来が頭を下げて請うた天才・荻村伊智朗の信じがたい努力と…
「20世紀を代表するスポーツ選手」というアンケートで、その当時大活躍していた中田英寿よりも高順位だった荻村伊智朗を知っているだろうか?選手としてだけでなく、指導者としてもとんでもない功績を残した彼の生涯を描く『ピンポンさん』から、ノーベル平和賞級の活躍を知る
あわせて読みたい
【働く】給料が上がらない、上げる方法を知りたい人は木暮太一のこの本を。『資本論』が意外と役に立つ…
「仕事で成果を出しても給料が上がるわけではない」と聞いて、あなたはどう感じるだろうか?これは、マルクスの『資本論』における「使用価値」と「価値」の違いを踏まえた主張である。木暮太一『人生格差はこれで決まる 働き方の損益分岐点』から「目指すべき働き方」を学ぶ
あわせて読みたい
【挑戦】手足の指を失いながら、今なお挑戦し続ける世界的クライマー山野井泰史の”現在”を描く映画:『…
世界的クライマーとして知られる山野井泰史。手足の指を10本も失いながら、未だに世界のトップをひた走る男の「伝説的偉業」と「現在」を映し出すドキュメンタリー映画『人生クライマー』には、小学生の頃から山のことしか考えてこなかった男のヤバい人生が凝縮されている
あわせて読みたい
【伝説】やり投げ選手・溝口和洋は「思考力」が凄まじかった!「幻の世界記録」など数々の逸話を残した…
世界レベルのやり投げ選手だった溝口和洋を知っているだろうか? 私は本書『一投に賭ける』で初めてその存在を知った。他の追随を許さないほどの圧倒的なトレーニングと、常識を疑い続けるずば抜けた思考力を武器に、体格で劣る日本人ながら「幻の世界記録」を叩き出した天才の伝説と実像
あわせて読みたい
【あらすじ】蝦夷地の歴史と英雄・阿弖流為を描く高橋克彦の超大作小説『火怨』は全人類必読の超傑作
大げさではなく、「死ぬまでに絶対に読んでほしい1冊」としてお勧めしたい高橋克彦『火怨』は凄まじい小説だ。歴史が苦手で嫌いな私でも、上下1000ページの物語を一気読みだった。人間が人間として生きていく上で大事なものが詰まった、矜持と信念に溢れた物語に酔いしれてほしい
あわせて読みたい
【圧巻】150年前に気球で科学と天気予報の歴史を変えた挑戦者を描く映画『イントゥ・ザ・スカイ』
「天気予報」が「占い」と同等に扱われていた1860年代に、気球を使って気象の歴史を切り開いた者たちがいた。映画『イントゥ・ザ・スカイ』は、酸素ボンベ無しで高度1万1000m以上まで辿り着いた科学者と気球操縦士の物語であり、「常識を乗り越える冒険」の素晴らしさを教えてくれる
あわせて読みたい
【組織】意思決定もクリエイティブも「問う力」が不可欠だ。MIT教授がCEOから学んだ秘訣とは?:『問い…
組織マネジメントにおいては「問うこと」が最も重要だと、『問いこそが答えだ!』は主張する。MIT教授が多くのCEOから直接話を聞いて学んだ、「『問う環境』を実現するための『心理的安全性の確保』の重要性」とその実践の手法について、実例満載で説明する1冊
あわせて読みたい
【衝撃】「仕事の意味」とは?天才・野崎まどが『タイタン』で描く「仕事をしなくていい世界」の危機
「仕事が存在しない世界」は果たして人間にとって楽園なのか?万能のAIが人間の仕事をすべて肩代わりしてくれる世界を野崎まどが描く『タイタン』。その壮大な世界観を通じて、現代を照射する「仕事に関する思索」が多数登場する、エンタメ作品としてもド級に面白い傑作SF小説
あわせて読みたい
【特異】「カメラの存在」というドキュメンタリーの大前提を覆す映画『GUNDA/グンダ』の斬新さ
映画『GUNDA/グンダ』は、「カメラの存在」「撮影者の意図」を介在させずにドキュメンタリーとして成立させた、非常に異端的な作品だと私は感じた。ドキュメンタリーの「デュシャンの『泉』」と呼んでもいいのではないか。「家畜」を被写体に据えたという点も非常に絶妙
あわせて読みたい
【超人】NHKによる「JAXAの宇宙飛行士選抜試験」のドキュメント。門外不出の「最強の就活」:『ドキュメ…
難攻不落のJAXAと粘り強い交渉を重ね、門外不出の「最強の就活」を捉えたドキュメンタリーを書籍化した『ドキュメント宇宙飛行士選抜試験』。2021年の13年ぶりの募集も話題になったが、「欠点があってはいけない」という視点で厳しく問われる試験・面接の実情を描き出す
あわせて読みたい
【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…
アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている
あわせて読みたい
【具体例】行動経済学のおすすめ本。経済も世界も”感情”で動くと実感できる「人間の不合理さ」:『経済…
普段どれだけ「合理的」に物事を判断しているつもりでも、私たちは非常に「不合理的」な行動を取ってしまっている。それを明らかにするのが「行動経済学」だ。『経済は感情で動く』『世界は感情で動く』の2冊をベースにして、様々な具体例と共に「人間の不思議さ」を理解する
あわせて読みたい
【驚異】信念を貫く勇敢さを、「銃を持たずに戦場に立つ」という形で示した実在の兵士の凄まじさ:映画…
第二次世界大戦で最も過酷な戦場の1つと言われた「前田高地(ハクソー・リッジ)」を、銃を持たずに駆け回り信じがたい功績を残した衛生兵がいた。実在の人物をモデルにした映画『ハクソー・リッジ』から、「戦争の悲惨さ」だけでなく、「信念を貫くことの大事さ」を学ぶ
あわせて読みたい
【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…
『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る
あわせて読みたい
【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統…
現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ
あわせて読みたい
【貢献】飛行機を「安全な乗り物」に決定づけたMr.トルネードこと天才気象学者・藤田哲也の生涯:『Mr….
つい数十年前まで、飛行機は「死の乗り物」だったが、天才気象学者・藤田哲也のお陰で世界の空は安全になった。今では、自動車よりも飛行機の方が死亡事故の少ない乗り物なのだ。『Mr.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』から、その激動の研究人生を知る
あわせて読みたい
【創作】クリエイターになりたい人は必読。ジブリに見習い入社した川上量生が語るコンテンツの本質:『…
ドワンゴの会長職に就きながら、ジブリに「見習い」として入社した川上量生が、様々なクリエイターの仕事に触れ、色んな質問をぶつけることで、「コンテンツとは何か」を考える『コンテンツの秘密』から、「創作」という営みの本質や、「クリエイター」の理屈を学ぶ
あわせて読みたい
【思考】「”考える”とはどういうことか」を”考える”のは難しい。だからこの1冊をガイドに”考えて”みよう…
私たちは普段、当たり前のように「考える」ことをしている。しかし、それがどんな行為で、どのように行っているのかを、きちんと捉えて説明することは難しい。「はじめて考えるときのように」は、横書き・イラスト付きの平易な文章で、「考えるという行為」の本質に迫り、上達のために必要な要素を伝える
あわせて読みたい
【驚愕】ロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」はどう解釈すべきか?沢木耕太郎が真相に迫る:『キャパ…
戦争写真として最も有名なロバート・キャパの「崩れ落ちる兵士」には、「本当に銃撃された瞬間を撮影したものか?」という真贋問題が長く議論されてきた。『キャパの十字架』は、そんな有名な謎に沢木耕太郎が挑み、予想だにしなかった結論を導き出すノンフィクション。「思いがけない解釈」に驚かされるだろう
あわせて読みたい
【快挙】「暗黒の天体」ブラックホールはなぜ直接観測できたのか?国際プロジェクトの舞台裏:『アイン…
「世界中に存在する電波望遠鏡を同期させてブラックホールを撮影する」という壮大なEHTプロジェクトの裏側を記した『アインシュタインの影』から、ブラックホール撮影の困難さや、「ノーベル賞」が絡む巨大プロジェクトにおける泥臭い人間ドラマを知る
あわせて読みたい
【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…
一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する
あわせて読みたい
【貢献】働く上で大切にしたいことは結局「人」。海士町(離島)で持続可能な社会を目指す若者の挑戦:…
過疎地域を「日本の未来の課題の最前線」と捉え、島根県の離島である「海士町」に移住した2人の若者の『僕たちは島で、未来を見ることにした』から、「これからの未来をどう生きたいか」で仕事を捉える思考と、「持続可能な社会」の実現のためのチャレンジを知る
あわせて読みたい
【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…
「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する
あわせて読みたい
【挑戦】社会に欠かせない「暗号」はどう発展してきたか?サイモン・シンが、古代から量子暗号まで語る…
「暗号」は、ミステリやスパイの世界だけの話ではなく、インターネットなどのセキュリティで大活躍している、我々の生活に欠かせない存在だ。サイモン・シン『暗号解読』から、言語学から数学へとシフトした暗号の変遷と、「鍵配送問題」を解決した「公開鍵暗号」の仕組みを理解する
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
あわせて読みたい
【情熱】「ルール」は守るため”だけ”に存在するのか?正義を実現するための「ルール」のあり方は?:映…
「ルールは守らなければならない」というのは大前提だが、常に例外は存在する。どれほど重度の自閉症患者でも断らない無許可の施設で、情熱を持って問題に対処する主人公を描く映画『スペシャルズ!』から、「ルールのあるべき姿」を考える
あわせて読みたい
【天才】諦めない人は何が違う?「努力を努力だと思わない」という才能こそが、未来への道を開く:映画…
どれだけ「天賦の才能」に恵まれていても「努力できる才能」が無ければどこにも辿り着けない。そして「努力できる才能」さえあれば、仮に絶望の淵に立たされることになっても、立ち上がる勇気に変えられる。映画『マイ・バッハ』で知る衝撃の実話
あわせて読みたい
【情熱】常識を疑え。人間の”狂気”こそが、想像し得ない偉業を成し遂げるための原動力だ:映画『博士と…
世界最高峰の辞書である『オックスフォード英語大辞典』は、「学位を持たない独学者」と「殺人犯」のタッグが生みだした。出会うはずのない2人の「狂人」が邂逅したことで成し遂げられた偉業と、「狂気」からしか「偉業」が生まれない現実を、映画『博士と狂人』から学ぶ
あわせて読みたい
【使命】「CRISPR-Cas9」を分かりやすく説明。ノーベル賞受賞の著者による発見物語とその使命:『CRISPR…
生物学の研究を一変させることになった遺伝子編集技術「CRISPR-Cas9」の開発者は、そんな発明をするつもりなどまったくなかった。ノーベル化学賞を受賞した著者による『CRISPR (クリスパー) 究極の遺伝子編集技術の発見』をベースに、その発見物語を知る
あわせて読みたい
【驚異】プロジェクトマネジメントの奇跡。ハリウッドの制作費以下で火星に到達したインドの偉業:映画…
実は、「一発で火星に探査機を送り込んだ国」はインドだけだ。アメリカもロシアも何度も失敗している。しかもインドの宇宙開発予算は大国と比べて圧倒的に低い。なぜインドは偉業を成し遂げられたのか?映画『ミッション・マンガル』からプロジェクトマネジメントを学ぶ
あわせて読みたい
【嫉妬?】ヒッグス粒子はいかに発見されたか?そして科学の”発見”はどう評価されるべきか?:『ヒッグ…
科学研究はもはや個人単位では行えず、大規模な「ビッグサイエンス」としてしか成立しなくなっている。そんな中で、科学研究の成果がどう評価されるべきかなどについて、「ヒッグス粒子」発見の舞台裏を追った『ヒッグス 宇宙の最果ての粒子』をベースに書く
あわせて読みたい
【課題】原子力発電の廃棄物はどこに捨てる?世界各国、全人類が直面する「核のゴミ」の現状:映画『地…
我々の日常生活は、原発が生み出す電気によって成り立っているが、核廃棄物の最終処分場は世界中で未だにどの国も決められていないのが現状だ。映画『地球で最も安全な場所を探して』をベースに、「核のゴミ」の問題の歴史と、それに立ち向かう人々の奮闘を知る
あわせて読みたい
【対話】刑務所内を撮影した衝撃の映画。「罰則」ではなく「更生」を目指す環境から罪と罰を学ぶ:映画…
2008年に開設された新たな刑務所「島根あさひ社会復帰促進センター」で行われる「TC」というプログラム。「罰則」ではなく「対話」によって「加害者であることを受け入れる」過程を、刑務所内にカメラを入れて撮影した『プリズン・サークル』で知る。
あわせて読みたい
【挑戦】東日本大震災における奇跡。日本の出版を支える日本製紙石巻工場のありえない復活劇:『紙つな…
本を読む人も書く人も作る人も、出版で使われる紙がどこで作られているのか知らない。その多くは、東日本大震災で甚大な被害を受けた日本製紙石巻工場で作られていた。『紙つなげ』をベースに、誰もが不可能だと思った早期復旧の舞台裏を知る
あわせて読みたい
【デマ】情報を”選ぶ”時代に、メディアの情報の”正しさ”はどのように判断されるのか?:『ニューヨーク…
一昔前、我々は「正しい情報を欲していた」はずだ。しかしいつの間にか世の中は変わった。「欲しい情報を正しいと思う」ようになったのだ。この激変は、トランプ元大統領の台頭で一層明確になった。『ニューヨーク・タイムズを守った男』から、情報の受け取り方を問う
あわせて読みたい
【奇跡】ビッグデータに”直感”を組み込んで活用。メジャーリーグを変えたデータ分析家の奮闘:『アスト…
「半世紀で最悪の野球チーム」と呼ばれたアストロズは、ビッグデータの分析によって優勝を果たす。その偉業は、野球のド素人によって行われた。『アストロボール』をベースに、「ビッグデータ」に「人間の直感」を組み込むという革命について学ぶ
あわせて読みたい
【勇敢】日本を救った吉田昌郎と、福島第一原発事故に死を賭して立ち向かった者たちの極限を知る:『死…
日本は、死を覚悟して福島第一原発に残った「Fukushima50」に救われた。東京を含めた東日本が壊滅してもおかしくなかった大災害において、現場の人間が何を考えどう行動したのかを、『死の淵を見た男』をベースに書く。全日本人必読の書
あわせて読みたい
【実話】仕事のやりがいは、「頑張るスタッフ」「人を大切にする経営者」「健全な商売」が生んでいる:…
メガネファストファッションブランド「オンデーズ」の社長・田中修治が経験した、波乱万丈な経営再生物語『破天荒フェニックス』をベースに、「仕事の目的」を見失わず、関わるすべての人に存在価値を感じさせる「働く現場」の作り方
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
経済・企業・マーケティング【本・映画の感想】 | ルシルナ
私自身にはビジネスセンスや起業経験などはありませんが、興味があって、経済や企業の様々な事例についての本を読むようにしています。専門的な踏み込んだ描写ができるわけ…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…





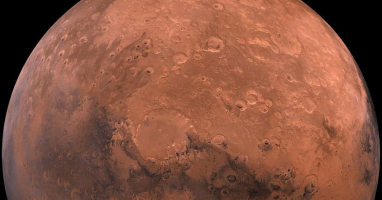


























































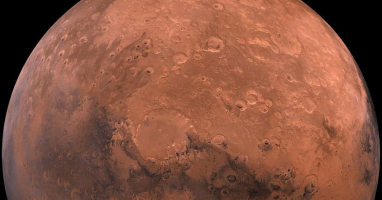


















コメント