目次
はじめに
この記事で取り上げる映画

「劇場用実写映画 秒速5センチメートル」公式HP
この映画をガイドにしながら記事を書いていくようだよ
今どこで観れるのか?
公式HPの劇場情報をご覧ください
この記事で伝えたいこと
主人公の2人、遠野貴樹と篠原明里の関係性は凄く羨ましく見えました
私も「お互いが『魂が震える人』だと認識している関係」に憧れます
この記事の3つの要点
- 「いずれ離れ離れになってしまうなら、2人は出会うべきではなかっただろうか?」とずっと考えていた
- 早くに「魂が震える人」と出会ったがために、それ以外の関係性に何も感じられなくなってしまった遠野の「残酷な人生」が描かれている
- 会話も演技もとにかく素晴らしく、また主題歌『1991』の「ジジッ」というノイズにさえ意味を感じてしまった
実写版を観た後で原作を観ましたが、実写の方が素晴らしいと感じたほど良かったです
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
実写映画『秒速5センチメートル』は本当に素晴らしかった。原作を超えてるんじゃないか。「こんな出会いが出来たら」という希望と残酷さを描き出す作品
私は基本的に「ストーリー」にしか興味がないが、本作は「雰囲気の良さ」だけで名作に仕上がっている
本当にメチャクチャ素敵な作品でした。これはホント観て良かったなぁ。
ただ正直、松村北斗が主演じゃなかったら観てない可能性あったよね
初めて予告を観た時、「松村北斗なら観るか」って感じになったもんなぁ

私は、実写映画を観た時点では原作に触れたことがなく(その後、実写映画公開記念としてテレビ放送されたものをTVerで観ました)、『秒速5センチメートル』という作品に対する思い入れは何もなかったので、単に「実写化した」というだけだったら「ふーん」という感じでスルーしていたかもしれません。ただ、主演が松村北斗であること、さらに監督が、少し前に観た映画『アット・ザ・ベンチ』の人だと知って、それで「なるほど、だったら観よう」と思いました。ホントに、映画『アット・ザ・ベンチ』はちょっと衝撃的な面白さだったので、「あの監督が撮るなら」と感じたのです。
あわせて読みたい
【天才】映画『アット・ザ・ベンチ』面白すぎる!蓮見翔の脚本に爆笑、生方美久の会話劇にうっとり(監…
役者も脚本家も監督も何も知らないまま、「有名な役者が出てこないマイナーな映画」だと思い込んで観に行った映画『アット・ザ・ベンチ』は、衝撃的に面白い作品だった。各話ごと脚本家が異なるのだが、何よりも、第2話「回らない」を担当したダウ90000・蓮見翔の脚本が超絶面白い。あまりの衝撃にぶっ飛ばされてしまった
そしてやはり素晴らしい作品でした。
さて私は、小説でも映画でも何でも、「物語」に触れる場合は基本的に「ストーリー」、つまり「話の筋」にしか興味がありません。極端に言えば、映像が美しくなくても、役者の演技が下手でも、衣装や音楽に光るものがなくても、「話の筋」さえピカイチなら全然評価できる、ぐらいに思っているというわけです。
まあ、映画の場合はさすがに、「役者の演技」があまりにも下手だと「厳しいな」って感じたりもするけど
ただ、本作『秒速5センチメートル』には正直、ストーリーらしいストーリーはありません。いや、無いわけではありませんが、少なくとも「話の筋」で惹きつけるような物語ではないでしょう。普段の私なら、さほど興味を抱けない作品と言っていいかもしれません。ただ私は、究極的には「ストーリー」さえどうでもよくて、「雰囲気さえ良ければそれでいい」みたいに感じることがあります。まさに本作もそのような作品で、「雰囲気の良さ」しかないと言ってもいいぐらいの作品でした。「シーン毎の『空気感』だけを切り取って並べました」みたいな作品で、そしてそんな本作がとにかくもの凄く素敵に感じられたというわけです。
あわせて読みたい
【衝撃】広末涼子映画デビュー作『20世紀ノスタルジア』は、「広末が異常にカワイイ」だけじゃない作品
広末涼子の映画デビュー・初主演作として知られる『20世紀ノスタルジア』は、まず何よりも「広末涼子の可愛さ」に圧倒される作品だ。しかし、決してそれだけではない。初めは「奇妙な設定」ぐらいにしか思っていなかった「宇宙人に憑依されている」という要素が、物語全体を実に上手くまとめている映画だと感じた
さて、私が本作を観る直前に放送していた『ボクらの時代』(フジテレビ系)に、主演の松村北斗、監督の奥山由之、原作の新海誠が出演していたのですが、その中で松村北斗が、「新海誠作品には『エモい』という言葉では表現しきれない何かがあるけど、その何かをピッタリ表現する言葉はないし、だから『エモい』って言うしかない」みたいな発言をしていました。そしてその感覚は、まさに本作にもそのまま当てはまるだろうと思います。「『エモい』なんて言葉で表現できている気はしないのだけど、でも他に適切な言葉はないし、だから「『エモい』って言うしかない」というわけです。そしてそれは、まさに「空気感」に対する評価という感じがするし、その見事な「空気感」を最初から最後までずっと映し出し続けているという点に、本作の凄まじさがあるのだと思います。
その上で、「アニメ版のシーンの再現」にもかなりこだわったらしいから、ホント凄いことやってるよなって思う
「大人気の原作を実写化する」ってプレッシャーもあっただろうし、大変だっただろうね
遠野貴樹は小学生の頃に「魂が震えるような人」に出会った
さて、実写映画を観た後で原作に触れた私は、実写化によって一層輪郭が濃くなった要素があるなと感じました。それが「『魂が震えるような人』と出会った」という描写です。そして私は本作を観ながら、このことばかりずっと考えていました。
あわせて読みたい
【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…
映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う
基本的に時系列通りに展開する原作と違い、実写映画では松村北斗演じる「大人になった遠野貴樹」の物語から始まります。なので、原作を観ていなかった私は、「遠野が小学生の頃に忘れられない人と出会った」みたいなことを知らないまま物語を追っていたし、さらに「その人が『魂が震えるような人』だった」という事実も少しずつ理解していったという感じです。

さて、そんな遠野は大人になった今、システムエンジニアとして働きながら、それ以外の時間をほとんど死んだように過ごしています。そもそも何かに追いまくられているかのように仕事をしているし(仕事が好きというわけでもなさそうなのに)、時折家にまで仕事を持ち帰っていました。そして仕事をしていない時は、例えば同じ会社で働く恋人と一緒にいる時でさえ、まるで心がそこに存在していないかのような雰囲気を醸し出しているのです。
こういう雰囲気を松村北斗はホント絶妙に醸し出すよね
松村北斗自身が陰キャっていうか、なかなかポジティブにはなれない人だって要素も大きいんだろうけど
そしてそんな大人の遠野とはまったく異なり、小学生の頃の彼は活き活きしています。転校生の篠原明里と仲良くなったからです。2人はお互いに惹きつけられます。小学生が出会う言葉では、それは「好き」という表現でまとめるしかなかったでしょう。しかし私は彼らの関わり方を見ながら、「お互いが『魂が震える人』と出会ったんだな」と感じました。
あわせて読みたい
【純愛】映画『ぼくのエリ』の衝撃。「生き延びるために必要なもの」を貪欲に求める狂気と悲哀、そして恋
名作と名高い映画『ぼくのエリ』は、「生き延びるために必要なもの」が「他者を滅ぼしてしまうこと」であるという絶望を抱えながら、それでも生きることを選ぶ者たちの葛藤が描かれる。「純愛」と呼んでいいのか悩んでしまう2人の関係性と、予想もつかない展開に、感動させられる
さて本作には、大人になった明里が印象的な言葉を口にする場面がありました。仕事の関係で知り合った女性と、「子どもの頃は全然友達がいなかったけど、1人だけ仲良くなれた人がいたんです」と遠野のことを思い浮かべながら話す彼女が、「彼とはもう長いこと会っていない」と口にします。それに対して相手の女性が「じゃあ、良い思い出だ」と話を受けるのですが、明里はそれにこんな風に返していました。
いや、思い出というよりは、今も日常です。
作中では、ある人物が「会えないと気持ちも離れちゃうのかな」と口にするのですが、少なくとも明里の場合はそんなことはなかったのでしょう。小学生の頃に離れ離れになって以降一度も会えていない(いや、中学生の頃に一度は会っているのか)存在を、それでも「今も日常です」と言い切れるほどに、彼女の気持ちはずっと遠野の方を向いているというわけです。
あわせて読みたい
【世界観】映画『夜は短し歩けよ乙女』の”黒髪の乙女”は素敵だなぁ。ニヤニヤが止まらない素晴らしいアニメ
森見登美彦の原作も大好きな映画『夜は短し歩けよ乙女』は、「リアル」と「ファンタジー」の境界を絶妙に漂う世界観がとても好き。「黒髪の乙女」は、こんな人がいたら好きになっちゃうよなぁ、と感じる存在です。ずっとニヤニヤしながら観ていた、とても大好きな映画
そんなの、「魂が震えている」としか言いようがないよなと思います。そして、そんな2人の関係性が、私にはとても羨ましく見えたというわけです。
「好き」「愛してる」「尊い」と「魂が震える」は何が違うのか、上手く説明は出来ませんが、私には明確な違いがあるように感じられます(「尊い」は「魂が震える」と近い感じがしますが、ただ「尊い」は私の中で「関われない、触れられない存在」に対して使うイメージがあるので、その点で少し違う印象です)。そして恐らくですが、人生の中で「魂が震える人」に出会えない人だって全然いるでしょう。明里は2人の関係を「太陽と月」に喩えていましたが、そんな風に「相手の存在が自分を成立させてくれている」みたいに思えるような関係にはなかなか出会えるものではありません。仮に自分が相手にそういう感覚を抱けたとしても、相手も同じぐらいそう思ってくれているとは限らないでしょう。そういう意味でも、2人の関係は奇跡的なものに感じられたというわけです。
私も、「好き」「愛してる」みたいなのは別にいいから「魂が震える」みたいな関係をずっと望んでるんだよなぁ
そう感じられる人に出会えて、相手も同じように思ってくれてるとしたら、それでもう人生完璧だよね
小学生の時点で「魂が震える人」と出会ってしまったことの残酷さ
しかし一方で私は、「小学生の頃にそんな存在に出会えてしまったことは、ある意味では残酷なんじゃないか」とも思っています。
あわせて読みたい
【感想】映画『ルックバック』の衝撃。創作における衝動・葛藤・苦悩が鮮やかに詰め込まれた傑作(原作…
アニメ映画『ルックバック』は、たった58分の、しかもセリフも動きも相当に抑制された「静」の映画とは思えない深い感動をもたらす作品だった。漫画を描くことに情熱を燃やす2人の小学生が出会ったことで駆動する物語は、「『創作』に限らず、何かに全力で立ち向かったことがあるすべての人」の心を突き刺していくはずだ
スマホやSNSがある現代ではまた状況は違うでしょうが、本作は「1991年に遠野と明里が出会った」という設定なので、「物理的に距離が離れた相手」のことを身近に感じるのは相当難しかったと言っていいでしょう。遠野も明里も「親の仕事の都合で転校せざるを得ない」という状況にあり、それ故に出会えたとも言えるわけですが、やはりそのせいで離れ離れにもなってしまいます。大人になってから出会った相手であれば、基本的には自らの意思で相手との関係を決められるわけですが、子どもの頃にはそうではない様々な不確定要素が絡んでくるというわけです。

だから、子どもの頃に「魂が震える人」と出会えたとしても、否応なしに離れ離れにならざるを得なくなるかもしれず、そしてそれは、スマホがなかった時代にはほとんど「悠久の別れ」だと言っていいと思います。そんなの、とても残酷ではないでしょうか? だからこそ、「どうせ離れ離れになってしまうくらいなら、最初から出会わなければ良かったのではないか」と感じずにはいられませんでした。
これって、私がよく思う「メチャクチャ美味いものを食べたくない」って話に近いんだよなぁ
「凄く美味しいものを食べると、普段食べてるものが劣ってるように感じられちゃう」みたいなことね
あわせて読みたい
【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…
好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性
さて、私がそんな風に感じたのには、遠野が口にしていたある感覚も関係しています。彼は恋人から「転勤族だったから引っ越しが好きなんだね」と言われるのですが、実はそうではありません。かつて遠野は明里に、「好きな家に住んで、そこからずっと引っ越したくない」と言っていたのです。しかし、大人になった遠野は実際のところ、定期的に引っ越しを繰り返しています。そしてどうやらそれは、「いつでも他人と離れられるようにするため」のようなのです。そのことは、ある場面でこんな独白をしていたことからも理解できるのではないかと思います。
誰かに近づきすぎないように。
1箇所に留まらないように。
誰といつ離れ離れになっても平気でいられるように。
作中でこの独白が出てくるのは、「小学生の頃に出会った明里が『魂が震える人』である」と私が理解する前のことで、だから正直私には、「遠野がどうしてこんな感覚を抱いているのか」がしばらく理解できませんでした。ただ、「『魂が震える人』との別れの残酷さを経験している」のであれば納得できるなという感じです。
あわせて読みたい
【感想】映画『窮鼠はチーズの夢を見る』を異性愛者の男性(私)はこう観た。原作も読んだ上での考察
私は「腐男子」というわけでは決してないのですが、周りにいる腐女子の方に教えを請いながら、多少BL作品に触れたことがあります。その中でもダントツに素晴らしかったのが、水城せとな『窮鼠はチーズの夢を見る』です。その映画と原作の感想、そして私なりの考察について書いていきます
遠野ほどじゃないけど、私も「誰といつ離れ離れになっても」みたいな感覚は全然理解できるなぁって思う
他人のことを絶望的に「つまらない」って感じちゃうことが多いから、余計にね
遠野は恐らく、「明里のような人と出会うことは二度とない」と考えているはずだし、それはきっとその通りでしょう。それぐらい、明里との「親和度」みたいなものが強かったというわけです。そしてそうだとすれば、「それなら、明里以外の人との関わりなんて何の意味もない」と感じるのも当然だと思います。
遠野自身はそんな風には言っていませんでしたが、恐らく彼にとっても明里は今も「日常」であり、強く意識される存在なのでしょう。だから、明里以外の誰と関わっていても、「そうじゃないんだよなぁ」みたいな気持ちが強くなってしまうのだと思います。とはいえ、別に孤独を好んでいるわけでもないだろうし、だから他者との関わりは求めてしまうわけですが、ただその代わりに「いつでも離れられるように」なんて風に考えているということなのでしょう。相手に深入りせず、「いつでも『今いる場所』を離れられる」ぐらいの身軽さを持ちつつ、今も「明里との日常」を生きているのだと思います。
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
つまり私は、「遠野は『魂が震える人』との出会いと別れを経験したが故に、それ以降の人生を死んだように生きざるを得なくなった」のだと思っているし、やはりそれは健全な状態じゃないよなとも感じました。もしも明里と出会っていなければ、日常のちょっとしたことにも心が反応したかもしれません。ただ、明里と過ごした時間があまりにも濃密で激しく彼の心を揺さぶったために、多少の揺れでは反応出来なくなったのだと思います。

映画の冒頭で、遠野のこんな独白が流れました。
いつの頃からだろう。まるで信じられなくなってしまった。
かつてあんなにも信じていたこの世界のことを。
あわせて読みたい
【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…
映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ
この時も私はまだ、どうして遠野がこんな風に感じているのかが全然理解できなかったのですが、彼のこの感覚もやはり、「明里との距離が物理的に離れてしまったことで自分の世界が次第にくすんでいき、大人になる頃には灰色になってしまった」みたいなことなのだと思います。誰も悪くないし、どこかに悪意が存在するわけでもありません。しかしそれでも、結果として遠野の世界は暗く閉ざされてしまったというわけです。やはりそれは、とても残酷なことに感じられました。
でもそうだとしても、やっぱり私は「魂が震える人」との出会いを期待しちゃう
もうそれぐらいしか、人生に期待できることがないんだよね
長く会っていなかった「魂が震える人」と、大人になってから再会したいだろうか?
さて、別の「残酷さ」として、こんな問いについて考えることも出来るでしょう。これは「小学生の時点で『魂が震える人』と出会ってしまったこと」と関係するわけですが、「その相手と大人になってから再会したいのか?」という話です。
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
人は大体、大人になる過程で考え方や価値観などが固まっていくだろうし、もちろん見た目的な意味でも変化が少なくなるでしょう。だから、大人になってから出会った人であれば、たとえ10年ぶりに再会となったとしてもさほど躊躇せずに済むんじゃないかと思います。一方で、30歳の遠野(作中で「30歳になりました」と口にする場面があります)が子ども時代のある時点から一度も会っていない明里との再会を考える際は、やはり躊躇が生まれるでしょう。確かに小学生の頃には「お互いにとって『魂が震える人』だった」かもしれません。ただ、お互いが大人になった今もそうであり続けているかは何とも言えないはずです。
あなたなら、そういう相手との再会を望むでしょうか?
観客視点では、遠野のことも明里のこともどちらも見えているので、「再び出会い直せば、2人は素敵な関係になれるはずだ」と素直に思えるはずです。ただ、当人同士は簡単にそうは思えないでしょう。十数年ぶりに再会したとして、もしも自分の心があの頃と同じようには動かなかったら。いや、それどころか、「なんか違うぞ」みたいに感じてしまったら。その恐怖は計り知れないように私には思えます。完璧な再会になるかもしれないけれど、同時に、残酷なまでに「無」あるいは「幻滅」に至る可能性もあるわけです。
あわせて読みたい
【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…
誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます
「だったら、再会なんて望まずに、自分の中の完璧なイメージを保ったまま壊さない」みたいな判断もかなり妥当だと言えるように思います。私も、そんな風に判断してしまうかもしれません。
実際には、大人になってから出会った人でもそういうことって起こり得るしね
だから、遠野の立場でも明里の立場でも、「再会」はちょっと恐ろしいよねって思う
2人とも、ある例外を除けば、「相手と積極的に再会しようとする行動」を取っていないように見えます。恐らくですが、本気で再会を望めば、連絡を取り付けるぐらいのところまでは辿り着けたでしょう。ただそうはしなかったわけで、つまり少なくとも遠野の方は、やはり「恐れ」を抱いていたのではないかと思います。

さて、「少なくとも遠野の方は」と書いたのには理由があって、明里の方はどうやら「恐れ」ではない感覚を抱いていたようだと示唆されるからです。ある状況で遠野は、人づてに「明里の真意」を聞く機会があったのですが、そこに込められた「想い」にはかなりグッときてしまいました。しかも、このシーンは原作にはなく、実写化において新たに加えられた要素です。ホントによくもまあ、原作の雰囲気を壊さないまま、こんな素敵なシーンを挿入できたものだなと感じました。
あわせて読みたい
【あらすじ】驚きの設定で「死と生」、そして「未練」を描く映画『片思い世界』は実に素敵だった(監督…
広瀬すず・杉咲花・清原果耶という超豪華俳優が主演を務める映画『片思い世界』は、是非、何も知らないまま観て下さい。この記事ではネタバレをせずに作品について語っていますが、それすらも読まずにまっさらな状態で鑑賞することをオススメします。「そうであってほしい」と感じてしまうような世界が“リアル”に描かれていました
「遠野との再会」について明里が本心ではどう思っているのかは何とも言えません。会えるなら会いたいのか、あるいは「絶対に会わない」と決めているのか、はっきりとは分からないでしょう。ただ、「今も日常です」と口にするくらいには気になる存在なことは確かなわけで、だからこそああいう彼女の判断に至っているわけです。実に素敵だったなと思います。
明里のこのセリフを聞いてしまったからこそ余計に、観客としては「再会してほしい!」ってなるよね
こんな風に観客の気持ちを動かしていく感じも上手いよなぁって思う
「遠野くんは私のことなんか見ていない」と分かってしまった花苗
さて本作では、さらに別の種類の「残酷さ」も描かれています。原作では「コスモナウト」という中盤のストーリーに当たるパートで、種子島で展開される物語内での描写です。
あわせて読みたい
【切実】映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』は河合優実目当てだったが伊東蒼が超最高!(…
映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』は、伊東蒼演じるさっちゃんがひたすらに独白し続けるシーンがとにかく圧巻で、恋しさとせつなさと心強さが無限に伝わる最高すぎるシーンだった!「想いを伝えたい気持ち」と「伝えることの暴力性」の間で葛藤しながら、それでも喋らずにはいられない想いの強さが素敵すぎる
高校生になっても転勤族だった遠野は、ある時点から種子島に住むことになりました。そしてそんな遠野に惹かれたのが、同じクラスの花苗です。他の人とは明らかに違う雰囲気を醸し出す彼のことが気になり、どうにか接触の機会を増やしたいと、下校時間が偶然被ったように装って一緒にスクーターで帰るみたいな日々を過ごしています。
ただ花苗は、「遠野くんには、東京に彼女がいるんじゃないか?」と疑っていました。というのも、ふとしたタイミングで誰かにメールを送信している感じがするからです。でももちろん「彼女いるの?」なんて聞けないし、一方で遠野への想いは溢れていきます。友人からも「気持ちを伝えるしかないよ」みたいに言われていました。そんなわけで、花苗も少しずつ勇気を溜め込んで「気持ちを伝えよう」みたいなモードになっていくのです。
ホント、花苗を演じた森七菜が絶妙に素晴らしかったよね
高校時代の遠野を演じた青木柚も元々好きな俳優だから、この種子島パートも凄く良かった
さてそんなある日のこと。花苗のスクーターが故障したので商店に置かせてもらい、2人は歩いて帰ることにします。遠野は別にスクーターで帰れるのに、「ちょっと歩きたいからさ」なんて言って短くもない距離を一緒に歩いて帰ってくれるのでした。そしてそんな風にして2人で歩いている時、彼女は思わずといった感じで涙を流します。この涙の意味は正直正確には理解できていないのですが、私は「『ちょっと歩きたいからさ』が優しい嘘すぎるから」みたいに感じました。つまり「嬉し涙」という解釈なんだけど、どうなんだろう?
あわせて読みたい
【失恋】ひたすらカオスに展開する映画『エターナル・サンシャイン』は、最後まで観ると面白い!(主演…
映画『エターナル・サンシャイン』は、冒頭からしばらくの間、とにかくまったく意味不明で、「何がどうなっているのか全然分からない!」と思いながら観ていました。しかし、映像がカオスになるにつれて状況の理解は進み始め、最終的には「よくもまあこんな素っ頓狂なストーリーを理解できる物語に落とし込んだな」と感心させられました
ただその後いろいろあって、家に帰った花苗は再び大粒の涙を流します。これははっきりと「悲しみの涙」でした。そして泣きながら彼女はこんな独白をしていたのです。
遠野くんは私のことなんか見てないんだと、同時にはっきり気がついた。
まあ、あの場面ではそう感じてもおかしくはないかもね
ただ、別に遠野が悪いわけでもないだろうし、これもホント「やるせない」って感じのシーンだよなぁ

「遠野くんは凄く優しいけど、でもそれは私だからそうしてくれているわけじゃなくて、ただ遠野くんがそういう人ってだけ」みたいに感じてしまったのでしょう。花苗が遠野を好きになったことを含め、この状況も別に誰も悪くないのですが、しかしそれでもはっきりと「残酷さ」が存在するなという感じでした。そして私は、「もし遠野が『魂が震える人』と出会っていなかったら、また全然違っていただろうな」という気がしているのです。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』を観てくれ!現代の人間関係の教科書的作品を考…
映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』は、私にグサグサ突き刺さるとても素晴らしい映画だった。「ぬいぐるみに話しかける」という活動内容の大学サークルを舞台にした物語であり、「マイノリティ的マインド」を持つ人たちの辛さや葛藤を、「マジョリティ視点」を絶妙に織り交ぜて描き出す傑作について考察する
遠野の恋人・水野との「距離のある関係性」
そして同じことは、会社の同僚でもある恋人・水野に対しても言えるでしょう。水野は職場ではほぼ誰とも話さずコミュニケーションを絶っているのですが、遠野の前では違った雰囲気を見せています。「水野から遠野に向けられた気持ちのベクトルは割とはっきり見える」みたいな感じです。一方で、その逆はよく分からず、遠野は常に「心ここにあらず」みたいな雰囲気を醸し出しています。ただ水野はどうも、そんな彼の気持ちを自分寄りに動かそうと強く思っているわけでもないようで(本心は分かりませんが)、そのままの遠野のことを受け入れているように見えました。「恋人同士」というイメージからはかなり距離を感じるような関係性というわけです。
これはこれで1つの形として全然アリだと思うから、最初は別に違和感を抱かなかったんだけど
こういう関係性で成立している恋人とか夫婦も全然いるだろうしね
彼女にとって遠野との関係がどうだったら理想的なのかははっきりとは分かりませんでした。ただ1つ明確に言えるのは、「『自分に特段の関心が向けられていない』とある程度理解した上で、それでも一緒にいたいと思っている」ということです。そしてそうであればやはり、彼女は遠野に対して強い想いを抱いていると考えていいのだと思います。
あわせて読みたい
【狂気】「当たり前の日常」は全然当たり前じゃない。記憶が喪われる中で”日常”を生きることのリアル:…
私たちは普段、「記憶が当たり前に継続していること」に疑問も驚きも感じないが、「短期記憶を継続できない」という記憶障害を抱える登場人物の日常を描き出す『静かな雨』は、「記憶こそが日常を生み出している」と突きつけ、「当たり前の日常は当たり前じゃない」と示唆する
ただそんな彼女が遠野に、ちょっと釘を刺すみたいな言い方をしていたシーンがあって、それが凄く印象的でした。彼女は面と向かって、「私と一緒にいるの、ラクだけど楽しくないでしょ?」みたいに口にしていたのです。遠野は理解出来なかったようで「どういう意味?」と返すのですが、それに対して水野は自身の話をします。
彼女が会社で喋らないのは、「あの子はそういう人だから」という印象を植え付けることで「コミュニケーションコスト」を出来るだけ下げたいと思っているからだと話していました。彼女は職場を「ラクだけど楽しくない」と感じていて、それで最小限の労力でやり過ごそうとしているのです。そんな自分のことを「まあまあズルいよね」と評していました。
私も職場ではまったく同じ理屈でほぼ喋らないからメチャクチャ理解できるわ
「不機嫌だから黙ってるんだ」みたいに見られるとめんどくさいから、「元々喋らない人なんだね」って思われるようにしてるんだよね
そしてやはり、彼女が遠野に向けた言葉には「あなたもズルいよ」という言外の意味が含まれていると捉えるべきでしょう。水野は「働き続けるため」に「コミュニケーションコスト」を下げる行動を取っているわけですが、同じことを遠野は「誰かと一緒にいるため(というか、せめて孤独にはならないため)」に行っている(と彼女は感じている)わけで、そのズルさを指摘している場面だと私は受け取りました。
あわせて読みたい
【感想】映画『先生、私の隣に座っていただけませんか?』は、「リアル」と「漫画」の境界の消失が絶妙
映画『先生、私の隣に座っていただけませんか?』は、「マンガ家夫婦の不倫」という設定を非常に上手く活かしながら、「何がホントで何かウソなのかはっきりしないドキドキ感」を味わわせてくれる作品だ。黒木華・柄本佑の演技も絶妙で、良い映画を観たなぁと感じました
とはいえ、遠野の気持ちも分からないではありません。彼は人生の早い段階で「魂が震える人」と出会い、否応なしに離れ離れになったことで、それ以外の人に興味を抱けなくなってしまったわけです(あくまでも私の仮説ですが)。そしてそんな自身の性質は、「遠野に惹きつけられる人」を傷つけてしまいもします。つまり遠野の中には、「相手のためを思って距離を取っている」みたいな気持ちもあるんじゃないかとも想像出来るのです。
もちろん、そんな気持ちは相手には絶対に伝わらないけどね
それが遠野なりの「優しさ」だとして、ホント意味のない優しさだよなぁ

会話の絶妙さ、そして役者の素晴らしい存在感
鑑賞後に見たネット記事には、監督の奥山由之が脚本家に対して、「原作ではモノローグが多いけど、実写化に際してはなるべくモノローグを減らしたい」みたいにオーダーした、というようなことが書かれていました。そんなわけで本作では原作と違って会話によるやり取りが多いのですが、本当にその会話が素晴らしかったです。先述した映画『アット・ザ・ベンチ』も「会話の圧倒的な素晴らしさ」が印象的な作品で、この監督は「会話の雰囲気」を撮るのが上手いんだろうなと思います。
Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
松村北斗、高畑充希、森七菜などは「役者の技量」なのかもしれないけど、例えば小学生時代の遠野を演じた上田悠斗は初演技だったらしいし、明里を演じた白山乃愛もそこまで場数を踏んでいるわけではないでしょう。それでも、「演技をしている」なんて雰囲気を感じさせないやり取りをしていて、凄く良かったなと思います。とにかく、まずは何よりも本作の「会話」全般に惹かれたという感じです。
映画『アット・ザ・ベンチ』を観て改めて、「会話が面白かったら成立しちゃうよね」って思った
さて、私は割と以前から松村北斗を推しているのですが、本作では「松村北斗が松村北斗的に存在している感じ」があって、それも凄く良かったなと思います。「役者が、役としてではなく役者のまま存在している」みたいな捉え方は、一般的には「悪い評価」と受け取られるだろうし、私も大体そういう意味で使いますが、今回はそうではありません。本作の主人公・遠野貴樹があまりにも松村北斗感の強い存在だったので、「松村北斗そのものの佇まい」は大正解だったと思っています。松村北斗は、映画『夜明けのすべて』でも割と「何かしらのマイナスを抱えた暗い人物」を演じていたし、そういう雰囲気が凄く似合う役者です。そしてそれはやはり、「彼自身がそういう人物である」という事実とは無関係ではないはずだし、だからこの配役は素晴らしかったなと思います。
あわせて読みたい
【感想】映画『夜明けのすべて』は、「ままならなさ」を抱えて生きるすべての人に優しく寄り添う(監督…
映画『夜明けのすべて』は、「PMS」や「パニック障害」を通じて、「自分のものなのに、心・身体が思い通りにならない」という「ままならなさ」を描き出していく。決して他人事ではないし、「私たちもいつそのような状況に置かれるか分からない」という気持ちで観るのがいいでしょう。物語の起伏がないのに惹きつけられる素敵な作品です
また先述した通り、青木柚のことは昔から好きで、本作でも良い存在感を発揮しているなと感じました。映画『うみべの女の子』『サクリファイス』では「何を考えているのかよく分からない雰囲気」を醸し出す役を演じていて、本作でもそういう感じをナチュラルに出していたなという印象です。
あわせて読みたい
【考察】『うみべの女の子』が伝えたいことを全力で解説。「関係性の名前」を手放し、”裸”で対峙する勇敢さ
ともすれば「エロ本」としか思えない浅野いにおの原作マンガを、その空気感も含めて忠実に映像化した映画『うみべの女の子』。本作が一体何を伝えたかったのかを、必死に考察し全力で解説する。中学生がセックスから関係性をスタートさせることで、友達でも恋人でもない「名前の付かない関係性」となり、行き止まってしまう感じがリアル
あわせて読みたい
【逃避】つまらない世の中で生きる毎日を押し流す”何か”を求める気持ちに強烈に共感する:映画『サクリ…
子どもの頃「台風」にワクワクしたように、未だに、「自分のつまらない日常を押し流してくれる『何か』」の存在を待ちわびてしまう。立教大学の学生が撮った映画『サクリファイス』は、そんな「何か」として「東日本大震災」を描き出す、チャレンジングな作品だ
さらにこれも既に触れましたが、森七菜がホントに最高でした。青木柚が演じた遠野とは違い、彼女が演じた花苗はメチャクチャ分かりやすく感情を表に出す役柄で、でも「遠野くんの前ではちゃんと抑えなくちゃ」みたいにも考えているわけです。しかしそれでも抑えきれない想いが溢れ出てしまうわけで、森七菜はそういうグチャグチャっとした心の動きを絶妙に表現していたなと思います。映画『国宝』でも良い存在感を放っていましたけど、ホント良い役者だよなぁ。
あと、水野を演じた木竜麻生も凄く素敵でした。遠野との恋人関係は、その在り方を考えればシンプルに「よそよそしい印象」になってもおかしくないはずですが、そんな違和感を抱かされることはありません。そしてそれは、木竜麻生の演技によるものだと感じました。

さらに、ラスト付近で改めて遠野と関わるシーンも凄く印象的だったなと思います。この場面で彼女が発した「遅くはないのか」というセリフには、「決定的に壊れちゃったから元通りになることはないけど、でもちょっとは印象変わったよ」みたいなニュアンスが含まれている感じがありました。まあ、「だから何だよ」って話ではあるのですが、ただこの2人の関係値的には意味のあるやり取りだったなという感じがして、凄く良かったです。
あわせて読みたい
【恋心】映画『サッドティー』は、「『好き』を巡ってウロウロする人々」を描く今泉力哉節全開の作品だった
映画『サッドティー』は、今泉力哉らしい「恋愛の周辺でグルグルする人たち」を描き出す物語。関係性が微妙に重なる複数の人間を映し出す群像劇の中で、「『好き』のややこしさ」に焦点を当てていく構成はさすがです。実に奇妙な展開で終わる物語ですが、それでもなお「リアルだ」と感じさせる雰囲気は、まるで魔法のようでした
木竜麻生は、本作の直後に観た映画『見はらし世代』でも凄く良かったんだよなぁ
全然違う雰囲気だったけど、絶妙な存在感って感じだったよね
あと個人的には、中田青渚はいつ見ても気になっちゃう存在で、出番こそ少なかったけどとても素敵でした。映画『街の上で』を観てメチャクチャ惹かれた役者で、まだ大作映画で大きな役をもらう感じではないですが、ちょいちょ見かける度に「おっ、いた」みたいになる存在です。また、宮﨑あおいも何とも言えない絶妙な雰囲気を放っていたし、白山乃愛も素敵な存在感で、とにかく役者がメチャクチャ良かったなと思います。あと、書店の店長役として又吉直樹が、システムエンジニアの同僚としてダウ90000の蓮見翔が出てきたりして、そういうところも楽しかったです。
あわせて読みたい
【面白い】映画『ラストマイル』は、物流問題をベースに「起こり得るリアル」をポップに突きつける(監…
映画『ラストマイル』は、「物流」という「ネット社会では誰にでも関係し得る社会問題」に斬り込みながら、実に軽妙でポップな雰囲気で展開されるエンタメ作品である。『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界で展開される「シェアード・ユニバース」も話題で、様々な人の関心を広く喚起する作品と言えるだろう
米津玄師による主題歌『1991』に含まれる「雑音」にはどんな意味があるのか?
本作の主題歌は米津玄師が担当していて、そのタイトルは『1991』。これは、小学生の遠野と明里が出会った年ですが、同時に、米津玄師が生まれた年でもあるそうです。米津玄師はインタビューで本作『秒速5センチメートル』について、「1991年という時代設定のこともあり、余計自分ごととして捉えられた」みたいなことを言っていました。
Billboard JAPAN
<インタビュー>米津玄師 「1991」へ“自分”が滲んだ理由――実写版『秒速5センチメートル』と“抗えない”ほ…
米国で最も権威のある音楽チャート・Billboard(ビルボード)の日本公式サイト。洋楽チャート、邦楽チャート、音楽ニュース、プレゼント情報などを提供。
しかしホント、米津玄師はこういう「作品をまとめて締めくくる主題歌」を作らせても天才だよね
「作品に対する解像度が高い」って色んな作品で言われているみたいだし
さて私は、音楽を聴く際に「歌詞」がまったく頭に入ってこない人間です。基本的には「言葉」に強く興味を持っているので、自分でも凄く不思議なんですが、歌詞の言葉を「音」としてしか捉えていない感覚があって、だから「歌詞の意味」みたいなものが全然意識されません。なので歌詞の話ではないのですが、『1991』には曲中の随所に「ジジッ」みたいな雑音のような音が入っています。予告編を観ていた時から気になっていたのですが、本編を観て、この「ジジッ」が作品全体に凄く合っているように感じられました。
あわせて読みたい
【革新】映画音楽における唯一のルールは「ルールなど無い」だ。”異次元の音”を生み出す天才を追う:映…
「無声映画」から始まった映画業界で、音楽の重要性はいかに認識されたのか?『JAWS』の印象的な音楽を生み出した天才は、映画音楽に何をもたらしたのか?様々な映画の実際の映像を組み込みながら、「映画音楽」の世界を深堀りする映画『すばらしき映画音楽たち』で、異才たちの「創作」に触れる
本作『秒速5センチメートル』では、実写化にあたりかなり新たな要素を付け加えたようで(後で原作を観てそのことに気づきました)、その1つが「宇宙的な話」です。重要な舞台としてプラネタリウムを併設する科学館が登場するし、「ある約束」を思い出すきっかけに隕石が使われたりもします。そして作中に度々登場するのが「探査機ボイジャーに載せたゴールデンレコード」で、これは「いつかどこかで遭遇するかもしれない地球外生命体に向けたメッセージ」を収録したものです。
なんやかんやあって、遠野がボイジャーの話をするシーンがあるんだけど、これも良いんだよねぇ
実写版では、こういう「交錯」が随所で描かれているところも上手いなって思う

さて、「ジジッ」という異音に米津玄師がどんな意味を込めたのか、その正確なところは知りませんが、分かりやすいところで言えば「ゴールデンレコードを物理的に再生している時の振動」みたいにも捉えられるでしょう。とすればそれはそのまま「遠くにいる誰かに思いを届けようとしている」みたいにも受け取れるはずです。あるいは、決して「美しい」とは言えない「ジジッ」という音は、「あまりにも綺麗すぎる形で再生されている遠野の記憶」をグチャっと塗り潰そうとしているようにも感じられるし、そうだとすればそれは、「遠野が過去の美しい記憶から決別しようとしている意思の表れ」みたいにも捉えられるかもしれません。あるいは、「ジジッ」というのは「地球外生命体からの返信の電波信号(ノイズ)」を表現していて、つまり「仮に遠くの存在から返信があったとしても、それを受け取った側は解読出来ない」みたいな悲哀を表現していたりするなんて可能性もあるでしょう。
あわせて読みたい
【驚愕】これ以上の”サバイバル映画”は存在するか?火星にたった一人残された男の生存術と救出劇:『オ…
1人で火星に取り残された男のサバイバルと救出劇を、現実的な科学技術の範囲で描き出す驚異の映画『オデッセイ』。不可能を可能にするアイデアと勇気、自分や他人を信じ抜く気持ち、そして極限の状況でより困難な道を進む決断をする者たちの、想像を絶するドラマに胸打たれる
この中に正解があるのか、あるいはまったく的外れなのか、それはどっちでも構いません。ただ少なくとも、米津玄師が何らかの意図を込めてこの「ジジッ」を組み込んだことは確かだろうし、だからこそ考察の余地があるなと思うし、私も先のような可能性について考えられたわけです。表面的に捉えるなら、「美しい映像で彩られた作品には『ジジッ』は似合わない」という判断になりそうですが、敢えて組み込んだことで作品の読み取り方に深みが増しているような感じがしました。こういう要素も凄く良かったなと思います。
曲が作れて歌えるだけじゃなくて、「解釈の解像度」も高いって、才能ありすぎだよなぁ
絵もメチャクチャ上手いし、才能分けてほしいよねって思う
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきた映画(フィクション)を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきた映画(フィクション)を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【感想】映画『すずめの戸締まり』(新海誠)は、東日本大震災後を生きる私達に「逃げ道」をくれる(松…
新海誠監督の『すずめの戸締まり』は、古代神話的な設定を現代のラブコメに組み込みながら、あまりに辛い現実を生きる人々に微かな「逃げ道」を指し示してくれる作品だと思う。テーマ自体は重いが、恋愛やコメディ要素とのバランスがとても良く、ロードムービー的な展開もとても魅力的
長々と色々書いてきましたが、とにかく素晴らしい作品でした。本当に観て良かったなと思います。
映画『アット・ザ・ベンチ』では、あまりにも会話が素敵すぎて「映像はなくてもいいから、せめて音声だけ繰り返し聴きたい」と感じましたが、本作『秒速5センチメートル』では、会話も良かったのだけどそれ以上に作品全体の雰囲気が素敵すぎて、「音声はなくてもいいから、せめて映像だけ繰り返し観たい」と感じさせられました。実に良いものを観たなという感じです。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!「それってホントに『コミュ力』が高いって言えるの?」と疑問を感じている方に…
私は、「コミュ力が高い人」に関するよくある主張に、どうも違和感を覚えてしまうことが多くあります。そしてその一番大きな理由が、「『コミュ力が高い人』って、ただ『想像力がない』だけではないか?」と感じてしまう点にあると言っていいでしょう。出版したKindle本は、「ネガティブには見えないネガティブな人」(隠れネガティブ)を取り上げながら、「『コミュ力』って何だっけ?」と考え直してもらえる内容に仕上げたつもりです。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『国宝』は圧巻だった!吉沢亮の女形のリアル、圧倒的な映像美、歌舞伎の芸道の狂気(…
映画『国宝』は、ちょっと圧倒的すぎる作品だった。原作・監督・役者すべての布陣が最強で、「そりゃ良い作品になるよね」という感じではあったが、そんな期待をあっさりと超えていくえげつない完成度は圧巻だ。あらゆる意味で「血」に翻弄される主人公・喜久雄の「狂気の生涯」を、常軌を逸したレベルで描き出す快作である
あわせて読みたい
【感想】映画『ファーストキス 1ST KISS』は、「過去に戻り未来を変える物語」として脚本が秀逸(監督…
映画『ファーストキス 1ST KISS』は、稀代の脚本家である坂元裕二の手腕が存分に発揮された作品。「過去にタイムスリップして未来を変える」というありがちな設定をベースにしながら、様々な「特異さ」を潜ませた物語は、とにかく絶妙に上手かったし面白かった。設定も展開も役者の演技もすべて秀逸な、実に面白いエンタメ作品
あわせて読みたい
【感想】実写映画『からかい上手の高木さん』(今泉力哉)は「あり得ない関係」を絶妙に描く(主演:永…
私は実写映画『からかい上手の高木さん』を「今泉力哉の最新作」として観に行った。常に「普通には成立しないだろう関係性」を描き出す今泉力哉作品らしく、本作でもそんな「絶妙にややこしい関係」が映し出されている。「正解がない」からこそ「すべてが正解になる」はずの「恋愛」をベースに、魅力的な関わりを描き出す物語
あわせて読みたい
【あらすじ】驚きの設定で「死と生」、そして「未練」を描く映画『片思い世界』は実に素敵だった(監督…
広瀬すず・杉咲花・清原果耶という超豪華俳優が主演を務める映画『片思い世界』は、是非、何も知らないまま観て下さい。この記事ではネタバレをせずに作品について語っていますが、それすらも読まずにまっさらな状態で鑑賞することをオススメします。「そうであってほしい」と感じてしまうような世界が“リアル”に描かれていました
あわせて読みたい
【あらすじ】「夢を追い求めた先」を辛辣に描く映画『ネムルバカ』は「ダルっとした会話」が超良い(監…
映画『ネムルバカ』は、まず何よりも「ダルっとした会話・日常」が素晴らしい作品です。そしてその上で、「夢を追い求めること」についてのかなり現代的な感覚を描き出していて、非常に印象的でした。「コスパが悪い」という言い方で「努力」を否定したくなる気持ちも全然理解できるし、若い人たちは特に大変だろうなと思います
あわせて読みたい
【人生】映画『雪子 a.k.a.』は、言葉は出ないが嘘もないラップ好きの小学校教師の悩みや葛藤を描き出す
「小学校教師」と「ラップ」というなかなか異色の組み合わせの映画『雪子 a.k.a.』は、「ここが凄く良かった」と言えるようなはっきりしたポイントはないのに、ちょっと泣いてしまうぐらい良い映画だった。「口下手だけど嘘はない」という主人公・雪子の日常的な葛藤には、多くの人が共感させられるのではないかと思う
あわせて読みたい
【実話】映画『あんのこと』(入江悠)は、最低の母親に人生を壊された少女の更生と絶望を描く(主演:…
映画『あんのこと』では、クソみたいな母親の元でクソみたいな人生を歩まされた主人公・杏の絶望を河合優実が絶妙に演じている。色んな意味で実に胸糞悪い作品で、こんな社会の歪さがどうしてずっとずっと放置され続けるのか理解できないなと思う。また、河合優実だけではなく、佐藤二朗の演技にも圧倒させられてしまった
あわせて読みたい
【包容】映画『違国日記』を観て思う。「他者との接し方」が皆こうだったらもっと平和なはずだって(主…
映画『違国日記』は、人見知りの小説家・高代槙生が両親を亡くした姪・朝を引き取り一緒に暮らすところから始まる物語で、槙生と朝を中心とした様々な人間関係が絶妙に描かれている作品でした。人付き合いが苦手ながら、15歳という繊細な存在を壊さないように、でも腫れ物みたいには扱わないように慎重になる槙生のスタンスが素敵です
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『夏目アラタの結婚』は黒島結菜が演じた品川真珠の歯並びが凄い(でもかわいい)(監…
映画『夏目アラタの結婚』は、まずとにかく、黒島結菜が演じた主人公・品川真珠のビジュアルが凄まじかった。原作者が「譲れない」と言ったという「ガタガタの汚い歯」の再現が凄まじく、これだけで制作陣の本気度が伝わるくらい。ストーリー展開も見事で、もう1人の主人公が最終的に思いがけない実感に行き着く流れも興味深い
あわせて読みたい
【尊厳】映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、安楽死をテーマに興味深い問いを突きつける(監督:ペ…
全然期待せずに観た映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、思いがけず面白い作品だった。「安楽死」をテーマにした、ティルダ・スウィントンとジュリアン・ムーアのほぼ2人芝居といったシンプルな作品だが、そこに通底する「死生観」や、「死生観」の違いによるすれ違いなどが実に見事に描かれていて、強く惹きつけられた
あわせて読みたい
【煌めき】映画『HAPPYEND』が描く、”監視への嫌悪”と”地震への恐怖”の中で躍動する若者の刹那(監督:…
映画『HAPPYEND』は、「監視システム」と「地震」という「外的な制約条件」を設定し、その窮屈な世界の中で屈せずに躍動しようとする若者たちをリアルに描き出す物語である。特に、幼稚園からの仲であるコウとユウタの関係性が絶妙で、演技未経験だという2人の存在感と映像の雰囲気が相まって、実に素敵に感じられた
あわせて読みたい
【天才】映画『アット・ザ・ベンチ』面白すぎる!蓮見翔の脚本に爆笑、生方美久の会話劇にうっとり(監…
役者も脚本家も監督も何も知らないまま、「有名な役者が出てこないマイナーな映画」だと思い込んで観に行った映画『アット・ザ・ベンチ』は、衝撃的に面白い作品だった。各話ごと脚本家が異なるのだが、何よりも、第2話「回らない」を担当したダウ90000・蓮見翔の脚本が超絶面白い。あまりの衝撃にぶっ飛ばされてしまった
あわせて読みたい
【豪快】これまで観た中でもトップクラスに衝撃的だった映画『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』(…
私は、シリーズ最新作『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』と、そのメイキングが中心のドキュメンタリー映画しか観ていませんが、あらゆる要素に圧倒される素晴らしい鑑賞体験でした。アクションシーンの凄まじさはもちろん、個人的には、杉本ちさとと深川まひろのダルダルな会話がとても好きで、混ざりたいなとさえ思います
あわせて読みたい
【実話】映画『ディア・ファミリー』は超良い話だし、大泉洋が演じた人物のモデル・筒井宣政は凄すぎる…
実話を基にした映画『ディア・ファミリー』では、個人が成したとは信じがたい偉業が描き出される。大泉洋が演じたのは、娘の病を治そうと全力で突き進んだ人物であり、そのモデルとなった筒井宣政は、17万人以上を救ったとされるIABPバルーンカテーテルの開発者なのだ。まったくホントに、凄まじい人物がいたものだと思う
あわせて読みたい
【評価】高山一実の小説かつアニメ映画である『トラペジウム』は、アイドル作とは思えない傑作(声優:…
原作小説、そしてアニメ映画共に非常に面白かった『トラペジウム』は、高山一実が乃木坂46に在籍中、つまり「現役アイドル」として出版した作品であり、そのクオリティに驚かされました。「現役アイドル」が「アイドル」をテーマにするというド直球さを武器にしつつ、「アイドルらしからぬ感覚」をぶち込んでくる非常に面白い作品である
あわせて読みたい
【記憶】映画『退屈な日々にさようならを』は「今泉力哉っぽさ」とは異なる魅力に溢れた初期作品だ(主…
今泉力哉作品のオールナイト上映に初めて参加し、『退屈な日々にさようならを』『街の上で』『サッドティー』を観ました。本作『退屈な日々にさようならを』は、時系列が複雑に入れ替わった群像劇で、私が思う「今泉力哉っぽさ」は薄い作品でしたが、構成も展開も会話も絶妙で、さすが今泉力哉という感じです
あわせて読みたい
【感想】映画『ルックバック』の衝撃。創作における衝動・葛藤・苦悩が鮮やかに詰め込まれた傑作(原作…
アニメ映画『ルックバック』は、たった58分の、しかもセリフも動きも相当に抑制された「静」の映画とは思えない深い感動をもたらす作品だった。漫画を描くことに情熱を燃やす2人の小学生が出会ったことで駆動する物語は、「『創作』に限らず、何かに全力で立ち向かったことがあるすべての人」の心を突き刺していくはずだ
あわせて読みたい
【絶妙】映画『水深ゼロメートルから』(山下敦弘)は、何気ない会話から「女性性の葛藤」を描く(主演…
高校演劇を舞台化する企画第2弾に選ばれた映画『水深ゼロメートルから』は、「水のないプール」にほぼ舞台が固定された状態で、非常に秀逸な会話劇として展開される作品だ。退屈な時間を埋めるようにして始まった「ダルい会話」から思いがけない展開が生まれ、「女として生きること」についての様々な葛藤が描き出される点が面白い
あわせて読みたい
【実話】さかなクンの若い頃を描く映画『さかなのこ』(沖田修一)は子育ての悩みを吹き飛ばす快作(主…
映画『さかなのこ』は、兎にも角にものん(能年玲奈)を主演に据えたことが圧倒的に正解すぎる作品でした。性別が違うのに、「さかなクンを演じられるのはのんしかいない!」と感じさせるほどのハマり役で、この配役を考えた人は天才だと思います。「母親からの全肯定」を濃密に描き出す、子どもと関わるすべての人に観てほしい作品です
あわせて読みたい
【怖い?】映画『アメリ』(オドレイ・トトゥ主演)はとても奇妙だが、なぜ人気かは分かる気がする
名作として知られているものの観る機会の無かった映画『アメリ』は、とても素敵な作品でした。「オシャレ映画」という印象を持っていて、それは確かにその通りなのですが、それ以上に私は「主人公・アメリの奇妙さ」に惹かれたのです。普通には成立しないだろう展開を「アメリだから」という謎の説得力でぶち抜く展開が素敵でした
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『悪は存在しない』(濱口竜介)の衝撃のラストの解釈と、タイトルが示唆する現実(主…
映画『悪は存在しない』(濱口竜介監督)は、観る者すべてを困惑に叩き落とす衝撃のラストに、鑑賞直後は迷子のような状態になってしまうだろう。しかし、作中で提示される様々な要素を紐解き、私なりの解釈に辿り着いた。全編に渡り『悪は存在しない』というタイトルを強く意識させられる、脚本・映像も見事な作品だ
あわせて読みたい
【絶望】杉咲花主演映画『市子』の衝撃。毎日がしんどい「どん底の人生」を生き延びるための壮絶な決断…
映画『市子』はまず何よりも主演を務めた杉咲花に圧倒させられる作品だ。そしてその上で、主人公・川辺市子を巡る物語にあれこれと考えさせられてしまった。「川辺市子」は決してフィクショナルな存在ではなく、現実に存在し得る。本作は、そのような存在をリアルに想像するきっかけにもなるだろう
あわせて読みたい
【感想】映画『キリエのうた』(岩井俊二)はアイナ・ジ・エンドに圧倒されっ放しの3時間だった(出演:…
映画『キリエのうた』(岩井俊二監督)では、とにかくアイナ・ジ・エンドに圧倒されてしまった。歌声はもちろんのことながら、ただそこにいるだけで場を支配するような存在感も凄まじい。全編に渡り「『仕方ないこと』はどうしようもなく起こるんだ」というメッセージに溢れた、とても力強い作品だ
あわせて読みたい
【考察】映画『街の上で』(今泉力哉)が描く「男女の友情は成立する」的会話が超絶妙で素晴らしい(出…
映画『街の上で』(今泉力哉監督)は、「映画・ドラマ的会話」ではない「自然な会話」を可能な限り目指すスタンスが見事だった。「会話の無駄」がとにかく随所に散りばめられていて、そのことが作品のリアリティを圧倒的に押し上げていると言える。ある男女の”恋愛未満”の会話もとても素晴らしかった
あわせて読みたい
【感想】映画『正欲』に超共感。多様性の時代でさえどこに行っても馴染めない者たちの業苦を抉る(出演…
映画『正欲』は、私には共感しかない作品だ。特に、新垣結衣演じる桐生夏月と磯村勇斗演じる佐々木佳道が抱える葛藤や息苦しさは私の内側にあるものと同じで、その描かれ方に圧倒されてしまった。「『多様性』には『理解』も『受け入れ』も不要で、単に否定しなければ十分」なのだと改めて思う
あわせて読みたい
【助けて】映画『生きててごめんなさい』は、「共依存カップル」視点で生きづらい世の中を抉る物語(主…
映画『生きててごめんなさい』は、「ちょっと歪な共依存関係」を描きながら、ある種現代的な「生きづらさ」を抉り出す作品。出版社の編集部で働きながら小説の新人賞を目指す園田修一は何故、バイトを9度もクビになり、一日中ベッドの上で何もせずに過ごす同棲相手・清川莉奈を”必要とする”のか?
あわせて読みたい
【共感】斎藤工主演映画『零落』(浅野いにお原作)が、「創作の評価」を抉る。あと、趣里が良い!
かつてヒット作を生み出しながらも、今では「オワコン」みたいな扱いをされている漫画家を中心に描く映画『零落』は、「バズったものは正義」という世の中に斬り込んでいく。私自身は創作者ではないが、「売れる」「売れない」に支配されてしまう主人公の葛藤はよく理解できるつもりだ
あわせて読みたい
【映画】ストップモーションアニメ『マルセル 靴をはいた小さな貝』はシンプルでコミカルで面白い!
靴を履いた体長2.5センチの貝をコマ撮りで撮影したストップモーション映画『マルセル 靴をはいた小さな貝』は、フェイクドキュメンタリーの手法で描き出すリアリティ満載の作品だ。謎の生き物が人間用の住居で工夫を凝らしながら生活する日常を舞台にした、感情揺さぶる展開が素晴らしい
あわせて読みたい
【違和感】三浦透子主演映画『そばかす』はアセクシャルの生きづらさを描く。セクシャリティ理解の入り口に
「他者に対して恋愛感情・性的欲求を抱かないセクシャリティ」である「アセクシャル」をテーマにした映画『そばかす』は、「マイノリティのリアル」をかなり解像度高く映し出す作品だと思う。また、主人公・蘇畑佳純に共感できてしまう私には、「普通の人の怖さ」が描かれている映画にも感じられた
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』を観てくれ!現代の人間関係の教科書的作品を考…
映画『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』は、私にグサグサ突き刺さるとても素晴らしい映画だった。「ぬいぐるみに話しかける」という活動内容の大学サークルを舞台にした物語であり、「マイノリティ的マインド」を持つ人たちの辛さや葛藤を、「マジョリティ視点」を絶妙に織り交ぜて描き出す傑作について考察する
あわせて読みたい
【感想】映画『すずめの戸締まり』(新海誠)は、東日本大震災後を生きる私達に「逃げ道」をくれる(松…
新海誠監督の『すずめの戸締まり』は、古代神話的な設定を現代のラブコメに組み込みながら、あまりに辛い現実を生きる人々に微かな「逃げ道」を指し示してくれる作品だと思う。テーマ自体は重いが、恋愛やコメディ要素とのバランスがとても良く、ロードムービー的な展開もとても魅力的
あわせて読みたい
【感想】映画『朝が来る』が描く、「我が子を返して欲しい気持ち」を消せない特別養子縁組のリアル
「特別養子縁組」を軸に人々の葛藤を描く映画『朝が来る』は、決して「特別養子縁組」の話ではない。「『起こるだろうが、起こるはずがない』と思っていた状況」に直面せざるを得ない人々が、「すべての選択肢が不正解」という中でどんな決断を下すのかが問われる、非常に示唆に富む作品だ
あわせて読みたい
【感想】映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)の稲垣吾郎の役に超共感。「好きとは何か」が分からない人へ
映画『窓辺にて』(今泉力哉監督)は、稲垣吾郎演じる主人公・市川茂巳が素晴らしかった。一般的には、彼の葛藤はまったく共感されないし、私もそのことは理解している。ただ私は、とにかく市川茂巳にもの凄く共感してしまった。「誰かを好きになること」に迷うすべての人に観てほしい
あわせて読みたい
【愛】ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の“衝撃の出世作”である映画『灼熱の魂』の凄さ。何も語りたくない
映画館で流れた予告映像だけで観ることを決め、他になんの情報も知らないまま鑑賞した映画『灼熱の魂』は、とんでもない映画だった。『DUNE/デューン 砂の惑星』『ブレードランナー 2049』など有名作を監督してきたドゥニ・ヴィルヌーヴの衝撃の出世作については、何も語りたくない
あわせて読みたい
【感想】映画『先生、私の隣に座っていただけませんか?』は、「リアル」と「漫画」の境界の消失が絶妙
映画『先生、私の隣に座っていただけませんか?』は、「マンガ家夫婦の不倫」という設定を非常に上手く活かしながら、「何がホントで何かウソなのかはっきりしないドキドキ感」を味わわせてくれる作品だ。黒木華・柄本佑の演技も絶妙で、良い映画を観たなぁと感じました
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『流浪の月』を観て感じた、「『見て分かること』にしか反応できない世界」への気持ち悪さ
私は「見て分かること」に”しか”反応できない世界に日々苛立ちを覚えている。そういう社会だからこそ、映画『流浪の月』で描かれる文と更紗の関係も「気持ち悪い」と断罪されるのだ。私はむしろ、どうしようもなく文と更紗の関係を「羨ましい」と感じてしまう。
あわせて読みたい
【感想】映画『竜とそばかすの姫』が描く「あまりに批判が容易な世界」と「誰かを助けることの難しさ」
SNSの登場によって「批判が容易な社会」になったことで、批判を恐れてポジティブな言葉を口にしにくくなってしまった。そんな世の中で私は、「理想論だ」と言われても「誰かを助けたい」と発信する側の人間でいたいと、『竜とそばかすの姫』を観て改めて感じさせられた
あわせて読みたい
【考察】『うみべの女の子』が伝えたいことを全力で解説。「関係性の名前」を手放し、”裸”で対峙する勇敢さ
ともすれば「エロ本」としか思えない浅野いにおの原作マンガを、その空気感も含めて忠実に映像化した映画『うみべの女の子』。本作が一体何を伝えたかったのかを、必死に考察し全力で解説する。中学生がセックスから関係性をスタートさせることで、友達でも恋人でもない「名前の付かない関係性」となり、行き止まってしまう感じがリアル
あわせて読みたい
【生きる】しんどい人生を宿命付けられた子どもはどう生きるべき?格差社会・いじめ・恋愛を詰め込んだ…
厳しい受験戦争、壮絶な格差社会、残忍ないじめ……中国の社会問題をこれでもかと詰め込み、重苦しさもありながら「ボーイ・ミーツ・ガール」の爽やかさも融合されている映画『少年の君』。辛い境遇の中で、「すべてが最悪な選択肢」と向き合う少年少女の姿に心打たれる
あわせて読みたい
【死】映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に号泣。「家族とは?」を問う物語と、タイトル通りのラストが見事
「死は特別なもの」と捉えてしまうが故に「日常感」が失われ、普段の生活から「排除」されているように感じてしまうのは私だけではないはずだ。『湯を沸かすほどの熱い愛』は、「死を日常に組み込む」ことを当たり前に許容する「家族」が、「家族」の枠組みを問い直す映画である
あわせて読みたい
【矛盾】その”誹謗中傷”は真っ当か?映画『万引き家族』から、日本社会の「善悪の判断基準」を考える
どんな理由があれ、法を犯した者は罰せられるべきだと思っている。しかしそれは、善悪の判断とは関係ない。映画『万引き家族』(是枝裕和監督)から、「国民の気分」によって「善悪」が決まる社会の是非と、「善悪の判断を保留する勇気」を持つ生き方について考える
あわせて読みたい
【助けて】息苦しい世の中に生きていて、人知れず「傷」を抱えていることを誰か知ってほしいのです:『…
元気で明るくて楽しそうな人ほど「傷」を抱えている。そんな人をたくさん見てきた。様々な理由から「傷」を表に出せない人がいる世の中で、『包帯クラブ』が提示する「見えない傷に包帯を巻く」という具体的な行動は、気休め以上の効果をもたらすかもしれない
あわせて読みたい
【映画】『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』で号泣し続けた私はTVアニメを観ていない
TVアニメは観ていない、というかその存在さえ知らず、物語や登場人物の設定も何も知らないまま観に行った映画『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 劇場版』に、私は大号泣した。「悪意のない物語」は基本的に好きではないが、この作品は驚くほど私に突き刺さった
あわせて読みたい
【感想】映画『窮鼠はチーズの夢を見る』を異性愛者の男性(私)はこう観た。原作も読んだ上での考察
私は「腐男子」というわけでは決してないのですが、周りにいる腐女子の方に教えを請いながら、多少BL作品に触れたことがあります。その中でもダントツに素晴らしかったのが、水城せとな『窮鼠はチーズの夢を見る』です。その映画と原作の感想、そして私なりの考察について書いていきます
あわせて読みたい
【あらすじ】「愛されたい」「必要とされたい」はこんなに難しい。藤崎彩織が描く「ままならない関係性…
好きな人の隣にいたい。そんなシンプルな願いこそ、一番難しい。誰かの特別になるために「異性」であることを諦め、でも「異性」として見られないことに苦しさを覚えてしまう。藤崎彩織『ふたご』が描き出す、名前がつかない切実な関係性
あわせて読みたい
【覚悟】人生しんどい。その場の”空気”から敢えて外れる3人の中学生の処世術から生き方を学ぶ:『私を知…
空気を読んで摩擦を減らす方が、集団の中では大体穏やかにいられます。この記事では、様々な理由からそんな選択をしない/できない、『私を知らないで』に登場する中学生の生き方から、厳しい現実といかにして向き合うかというスタンスを学びます
あわせて読みたい
【呪縛】「良い子」に囚われ人生苦しい。どう見られるかを抜け出し、なりたい自分を生きるために:『わ…
「良い子でいなきゃいけない」と感じ、本来の自分を押し隠したまま生きているという方、いるんじゃないかと思います。私も昔はそうでした。「良い子」の呪縛から逃れることは難しいですが、「なりたい自分」をどう生きればいいかを、『わたしを見つけて』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【感想】人間関係って難しい。友達・恋人・家族になるよりも「あなた」のまま関わることに価値がある:…
誰かとの関係性には大抵、「友達」「恋人」「家族」のような名前がついてしまうし、そうなればその名前に縛られてしまいます。「名前がつかない関係性の奇跡」と「誰かを想う強い気持ちの表し方」について、『君の膵臓をたべたい』をベースに書いていきます
あわせて読みたい
【肯定】価値観の違いは受け入れられなくていい。「普通」に馴染めないからこそ見える世界:『君はレフ…
子どもの頃、周りと馴染めない感覚がとても強くて苦労しました。ただし、「普通」から意識的に外れる決断をしたことで、自分が持っている価値観を言葉で下支えすることができたとも感じています。「普通」に馴染めず、自分がダメだと感じてしまう人へ。
ルシルナ
孤独・寂しい・友達【本・映画の感想】 | ルシルナ
孤独と向き合うのは難しいものです。友達がいないから学校に行きたくない、社会人になって出会いがない、世の中的に他人と会いにくい。そんな風に居場所がないと思わされて…
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…















































































































































































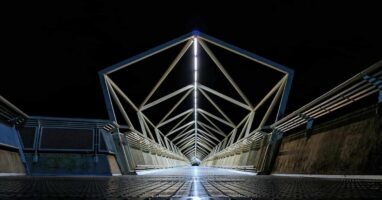
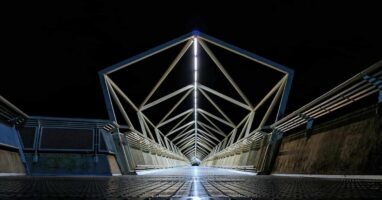



























































































コメント