目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:野矢茂樹
¥715 (2022/11/23 18:55時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 「無限」には「実無限」と「可能無限」という2種類の捉え方が存在するなんて本書で初めて知った
- 私が数学の証明の中で最も好きな「カントールの対角線論法」を、「可能無限」派が認めていないという事実に驚かされた
- 「可能無限」派は、「√2」のことを「数」ではないと考えている
「可能無限」派の主張はかなり異端的に感じられるが、本書は「『数学』にも『価値観』が入り込む余地がある」と感じさせてくれる興味深い1冊だ
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
本書『無限論の教室』で初めて「無限」に種類があることを知ったし、「実無限」と「可能無限」の話には驚かされた

あわせて読みたい
【刺激】結城浩「数学ガール」で、ゲーデルの不完全性定理(不可能性の証明として有名)を学ぶ
『結城浩「数学ガール」シリーズは、数学の面白さを伝えながら、かなり高難度の話題へと展開していく一般向けの数学書です。その第3弾のテーマは、「ゲーデルの不完全性定理」。ヒルベルトという数学者の野望を打ち砕いた若き天才の理論を学びます
皆さんは「無限」というものについて考えたことがあるだろうか? 「『無限』って言ったら、あの『無限』のことだろ」と思った方、それでは、「『無限』には種類がある」と聞いて何を言っているのか理解できるだろうか? 私は本書を読んで初めてその事実を知った。まさか「無限」に複数の異なる捉え方が存在するとはまったく想像もしていなかったのだ。
本書には、「『カントールの対角線論法』を否定する」という主張が登場する。本書を読む以前から私は「カントールの対角線論法」の存在を知っており、数学の証明の中で一番好きなのだが、まさかそれを「認めない」なんて状況が存在し得るとは驚きでしかなかった。
本書で扱われる「無限」は、確かに「数学」の領域に属する話なのだが、語られている内容は「哲学」のように感じられるかもしれない。数学でも物理でも、分野によっては、まさに「哲学」としか受け取れないような主張がたくさん登場するものだ。本書には、恐らく理解不能に感じられる話も多々出てくるだろうが、そういう点も含めて楽しんでもらえたらいいと思う。
本書の構成をざっと説明しておこう。基本的に、物語のように展開される作品だ。大学生の「僕」が、タカムラさんという女の子と2人で、タジマという講師による無限論の講義を聞いているという設定になっている。一般向けの数学書として非常に読みやすい「数学ガール」シリーズのように、本書も会話を中心にして「無限」の話が展開されるので、かなりとっつきやすい作品だと言っていいだろう。
あわせて読みたい
【興奮】結城浩「数学ガール」で、決闘で命を落とした若き天才数学者・ガロアの理論を学ぶ
高校生を中心に、数学を通じて関わり合う者たちを描く「数学ガール」シリーズ第5弾のテーマは「ガロア理論」。独力で「群論」という新たな領域を切り開きながら、先駆的すぎて同時代の数学者には理解されず、その後決闘で死亡した天才の遺した思考を追う
それでは以下、私が興味深いと感じた話について書いていきたいと思う。
「実無限」「可能無限」とは一体何か?

あわせて読みたい
【幻想】超ひも理論って何?一般相対性理論と量子力学を繋ぐかもしれないぶっ飛んだ仮説:『大栗先生の…
『大栗先生の超弦理論入門』は最先端科学である「超弦理論」を説明する1冊だが、この記事では著者の主張の1つである「空間は幻想かもしれない」という発想を主に取り上げる。「人類史上初の『適用する次元が限定される理論』」が描像する不可思議な世界とは?
本書の内容でとにかく驚かされたのは、「無限論には2つの立場がある」という主張だ。それまでまったくそんな話を聞いたことがなかったので、メチャクチャ驚かされた。その2つというのが「実無限」と「可能無限」である。タジマ先生は基本的に「可能無限」の立場に立っており(恐らくそれが、著者自身の立場でもあるのだと思う)、本書は全体として「『実無限』は幻想に過ぎない」と主張する内容になっている。
では、「実無限」と「可能無限」は何がどう違うのだろうか。この説明のために、まずは横に長い1本の線を思い浮かべてほしい。そしてその線上のどこかに点を1つ打ち、「0」と記入する。0より右側がプラスの数、0より左側がマイナスの数という、いわゆる数直線である。
さて、この数直線上に適切に目盛りを刻むと、そこには「無数の数字が存在する」と捉えられるだろう。例えば、「-10~+10」まで目盛りを刻んだとする。この場合、「1」「7」のような整数はもちろん、「2.56」「1/3」といった有理数や、「√2」「π(パイ)」のような実数も、この数直線上のどこかに「存在する」と考えるのが自然であるように思う。というか、私はそんな風に考えていた。
このような捉え方のことを「実無限」と呼ぶ。「この数直線上には、ある範囲内に収まるべき数が『点』として『存在する』」と考えるのが、「実無限」の立場というわけだ。
あわせて読みたい
【興奮】素数の謎に迫った天才数学者たちの奮闘と、数学の”聖杯”である「リーマン予想」について:『素…
古今東西の数学者を惹きつけて止まない「素数」。その規則性を見つけ出すことは非常に困難だったが、「リーマン予想」として初めてそれが示された。『素数の音楽』『リーマン博士の大予想』から、天才数学者たちが挑んできた「リーマン予想」をざっくり理解する
しかし「可能無限」派はそのようには考えない。そのようには考えないということはつまり、「数直線上に数が『点』として『存在する』わけではない」ということだ。では、「可能無限」の立場ではどのように考えるのだろうか。
それを短く説明すると、「数直線をどこかで切断した場合に、数としての『点』を取り出すことが可能であり、その『可能性』が『無限』に『存在する』」となる。

意味が分かるだろうか? ざっくり説明してみよう。
例えば、数直線を「3」のところで切断すると、「3という点(数)」を取り出すことができる。しかし「可能無限」派は、「その『3という点(数)』が数直線上に元から存在していた」とは考えない。「3」のところで切断すれば「3という点(数)」を取り出すことはできる。しかし最初から「3」という点(数)が数直線上に存在しているわけではない、というわけだ。
あわせて読みたい
【天才】数学の捉え方を一変させた「シンメトリー(対称性)」と、その発見から発展に至る歴史:『シン…
「5次方程式の解の公式は存在しない」というアーベルの証明や、天才・ガロアが発展させた「群論」は、「シンメトリー(対称性)」という領域に新たな光を当てた。『シンメトリーの地図帳』をベースに、「シンメトリー」の発展と「モンスター」の発見の物語を知る
この違いを、トランプを例にして捉え直してみよう。52枚のトランプをシャッフルした後で、裏向きのままテーブルにダーッと綺麗に広げ、その中から1枚引くことを考える。引いたカードは「ハートの3」だとしよう。この場合、「実無限」的に考えれば、「マーク4種類、1~13の計52枚のカードが元から存在し、その中から『ハートの3』を選びだした」という説明になるだろう。しかし「可能無限」派の場合は、こんな捉え方になるんじゃないかと思う。「裏返しになったトランプは、マークも数字もまったく決まっていない。そして、トランプを1枚選んだ時に、初めてそのカードが『ハートの3』であることが確定した」と。
トランプを用いたこの説明は私が考えたものであり、恐らく「実無限」と「可能無限」の違いを適切に説明できてはいないだろう。しかし、意識したことはなかったものの「実無限」派だった私には、「可能無限」派の主張は、先のトランプの喩えと同じぐらいの不可思議さを感じさせられた。「そんな捉え方も存在するのか」と驚かされたのである。
しかし、「可能無限」派のように考えることにメリットも存在すると知り、受け取り方が変わった。例えば、有名な「アキレスと亀のパラドックス」も、「可能無限」の立場で考えればパラドックスでもなんでもなくなるのである。
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
「アキレスと亀のパラドックス」とは、足の速いアキレスと足の遅い亀がハンデ戦の徒競走を行うという話だ。亀がアキレスより前の位置からスタートし、アキレスが亀を追い抜けばアキレスの勝利となる。時間制限もゴールもなく、単に「アキレスが亀を追い抜けば終了」という条件なのだが、アキレスはいつまでたっても亀に追いつけないというのがこのパラドックスのポイントだ。なぜなら、アキレスが亀のスタート地点に辿り着いた時には、亀はその少し先を走っているし、アキレスがさらに亀がいた地点に辿り着いた時には、亀はやはりもう少し先に行っているからである。アキレスは必ず「亀が少し前にいた地点」を後から通過しなければならず、そのためアキレスは亀に永遠に追いつけない、ということになるわけだ。
もちろん、実際には亀を追い抜けないはずがないので、この考え方はどこかおかしいことになる。しかし、その矛盾を指摘するのはなかなか難しい。これが、有名なパラドックスとして知られる「アキレスと亀」である。
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
このパラドックス、「実無限」派にとってはなかなか難問だ。「実無限」派は、数直線上に無限の数が存在すると捉えるのと同様に、「空間を無限に分割することができる」と考えるため、上述のような矛盾が起こってしまうことになる。しかし「可能無限」派は、「空間を無限に分割することができる」とは考えない。「なんらかのものが『無限』に存在する」と考えるのではなく、あくまでも「可能性が無限に存在する」と捉えるに過ぎないからだ。

その違いは、こんなふうにも説明できる。アキレスが、先述した数直線上を走っているとしよう。この状況を「実無限」的に考えると、アキレスの行為は、「有限の時間で無限個の数を数える」ことに相当すると言える。「実無限」派は、数直線上に無数の数が存在すると考えるのだから、「-10~+10」の数直線を走る間でさえ、アキレスは無限個の数を通過することになるはずだ。しかし、やはりそれは奇妙な話だろう。一方、「可能無限」的に考えると話は変わってくる。「数直線上に無限個の数があるわけではない」のだから、そもそも矛盾は生まれないのだ。なかなかイメージは難しいが、「『可能無限』的に考えると、そもそも『アキレスと亀』のパラドックス自体が成立しない」という発想は、実に興味深いと感じた。
あわせて読みたい
【対立】数学はなぜ”美しい”のか?数学は「発見」か「発明」かの議論から、その奥深さを知る:『神は数…
数学界には、「数学は神が作った派」と「数学は人間が作った派」が存在する。『神は数学者か?』をベースに、「数学は発見か、発明か」という議論を理解し、数学史においてそれぞれの認識がどのような転換点によって変わっていったのかを学ぶ
「可能無限」派は「カントールの対角線論法」を許容しない
本書の記述で一番衝撃だったのは、「『可能無限』的に考えると『カントールの対角線論法』は認められない」という主張だ。これには本当に驚いた。「カントールの対角線論法」は、文系の人でも頑張れば理解できるレベルの話なのだが、「よくもまあこんなことを思いついたものだ」と感心させられるような証明であり、数学の中で私が一番好きな証明だ。それが「可能無限」の立場からは否定されるというのだから驚いてしまった。
「カントールの対角線論法」は、「無限の濃度」に関する証明だ。というわけでまずは「無限の濃度」の話をしよう。
突然だが、「整数」と「偶数」とではどちらの方が多い(正確には「濃度が濃い」)か考えてみてほしい。例えば、「100までの整数」と「100までの偶数」であれば、「整数」の方が「偶数」の2倍存在する。当たり前だ。だったら、「無限の整数」と「無限の偶数」を比較した場合も、「無限の整数」の方が2倍多い(2倍濃い)と考えるのが自然だろう。
あわせて読みたい
【異端】数学の”証明”はなぜ生まれたのか?「無理数」と「無限」に恐怖した古代ギリシャ人の奮闘:『数…
学校で数学を習うと、当然のように「証明」が登場する。しかしこの「証明」、実は古代ギリシャでしか発展しなかった、数学史においては非常に”異端”の考え方なのだ。『数学の想像力 正しさの深層に何があるのか』をベースに、ギリシャ人が恐れたものの正体を知る
しかし、カントールという数学者はそうは考えなかった。彼は「一対一対応」という考え方を用いて、「整数」と「偶数」の濃度が同じであることを示したのだ(この話はまだ「カントールの対角線論法」とは関係ないので注意してほしい)。

「一対一対応」とは、その名の通り、「一対一の対応を付けられる」という意味である。そして、一対一の対応を付けられる場合は「濃度が同じ」だとカントールは考えた。
例えば、以下のように「整数」と「偶数」を並べてみよう(どちらも正の数とする)。
整数:1 2 3 4 5 6 7 ……
偶数:2 4 6 8 10 12 14 ……
この場合、「整数」と「偶数」をどこまで並べても必ず「一対一の対応」を付けることができるだろう。どこかで「一対一の対応」が付かなくなるような区切りが現れることは絶対にない。だから「整数」と「偶数」の濃度は同じだというのがカントールの結論である。納得しにくい話かもしれないが、ここではとにかく「カントールはそのように定義した」と考えてほしい。
あわせて読みたい
【変人】結城浩「数学ガール」から、1億円も名誉ある賞も断った天才が証明したポアンカレ予想を学ぶ
1億円の賞金が懸けられた「ポアンカレ予想」は、ペレルマンという天才数学者が解き明かしたが、1億円もフィールズ賞も断った。そんな逸話のある「ポアンカレ予想」とは一体どんな主張であり、どのように証明されたのかを結城浩『数学ガール』から学ぶ
そしてカントールは同じようにして、今度は「整数」と「実数」の濃度を比較してみることにした。そして、その際に生み出した手法こそが「カントールの対角線論法」なのである。
基本的な考え方は、先程と同じだ。「整数」と「実数」に「一対一の対応」が付けば同じ濃度、付かなければどちらかの濃度が濃い(普通に考えれば「実数」の濃度の方が濃い)ということになる。
では、どんな風に比較すればいいだろうか?
カントールはまず、「『整数』と『実数』の濃度が仮に『同じ』だとしたらどうなるか」と考えてみることにした。濃度が同じなら、「整数」と「偶数」の議論と同じように、「『すべての整数』が『すべての実数』と対応する表」を作れるはずである。例えば、以下のように対応がつけられたとしよう。
整数 実数
1 1.0056897……
2 8.6987881……
3 0.0300144……
4 9.9915586……
5 2.0006547……
︙ ︙
︙ ︙
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
6以降のすべての整数についても、このような対応がすべて付いていると仮定してみるのである。

さてここから、実数の「対角線」に並ぶ数字を拾うことにしよう。これこそが「対角線論法」の真骨頂である。「1.0056897……」の「1」、「8.6987881……」の「6」、「0.0300144……」の「3」、「9.9915586……」の「1」、「2.0006547……」の「6」……という風に、斜めに並ぶ数字だけを拾い、さらにそれらを順番に並べて新たな小数を作ると、「1.6316……」となるのだが、理解できるだろうか? さらに、この新たに作った小数の各桁に「1」を加えると、「2.7427……」という小数が出来上がる。これで準備は完成だ。
整数 実数
1 1.0056897……
2 8.6987881……
3 0.0300144……
4 9.9915586……
5 2.0006547……
︙ ︙
︙ ︙
それでは、この「2.7427……」という小数が、先程の対応表の中に存在するか考えてみてほしい。元々、「『整数』と『実数』の濃度が『同じ』」であり、「すべての実数がこの対応表に載っている」と仮定したので、「2.7427……」という小数もこの表に存在していなければならないはずだ。しかし、実際には存在しないことが分かる。
あわせて読みたい
【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ
350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る
何故そう言い切れるのか。では、「2.7427……」という小数を、表の上から順に比較してみよう。「整数1と対応する小数(1.0056897……)」とは「左から1番目の数字」が、「整数2と対応する小数」とは「左から2番めの数字」が、「整数3と対応する小数」とは「左から3番めの数字」が必ず違っているだろう。「2.7427……」という小数はそのようにして作り出した数なのだから当然だ。つまり、この「2.7427……」という小数は、「整数nと対応する小数」と「左からn番めの数字」が必ず異なるのである。
なので、新たに作り出した「2.7427……」という小数は、先程の対応表の中には絶対に存在しないことが分かるのだ。「すべての実数が載っていること」を前提にして作った表に存在しない実数を生み出せてしまったのだから、「『整数』と『実数』の濃度が『同じ』」という最初に設定した前提が誤っていることになる。つまり、実際には「『整数』と『実数』の濃度が『違う』」のであり、「整数」よりも「実数」の濃度の方が濃いというわけだ。
あわせて読みたい
【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…
「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる
これが「カントールの対角線論法」である。なんとなくでも理解していただけただろうか?
では、「可能無限」派は何故「カントールの対角線論法」を受け入れないのか。その理由はシンプルで、「可能無限」派はそもそも、「1.0056897……」のような「……」で表される小数を「数」として認めていないからだ。

「実無限」派は、「すべての数が数直線上の点として存在している」という立場なので、「1.0056897……」のようなどこまでも続く小数でも、「『……』の部分がどうなっているか分からないが、『……付きの小数』も数直線上のどこかにあるはずだし、当然『数』として認める」と考える。しかし「可能無限」派は、「数直線を切断した時に『数』を取り出せる『可能性』が無限に存在する」とという立場だ。そして、「……付きの小数」は、数直線の切り方が指定されていないという判断になり、だから「そんな『数』は存在しない」という結論になるのである。「カントールの対角線論法」では、「……付きの小数」を「数」として扱っているため、「可能無限」派としては許容できない、というわけだ。
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
なかなか面白い考え方だと感じた。
「可能無限」派は、当然「√2」も「数」とは捉えない。小数に直すと「1.41421356……」となるからだ。では「数」ではないならなんだというのか。「√2」の各桁の数字は、ある規則(「開平法」と呼ばれている)によって導くことができる。だから「可能無限」派にとって「√2」は、「開平法に付けられた名前」ということになるのだ。例えば、「√2>1」(ルート2大なり1)という式があるとして、「実無限」派はこれを「√2は1よりも大きい」と読む。私もそう読むし、普通はそうだろう。しかし「可能無限」派は、「√2という開平の仕方によって、1よりも大きな数を作ることができる」と読むのだそうだ。ほえ~という感じである。
また、このように思考することで、「可能無限」派は「『実数』という集合は存在しない」とも考えるのだそうだ。「実無限」派が「実数」と捉える√2を「数ではない」と考えるのだから、「実数」という集合も認めるはずがないだろう。なかなか異端的な発想だと思う。とはいえ、「答えが必ず定まる」と思っていた数学という分野において、「価値観の違いによって見解が異なる状況」が存在するなどと想像したことがなかったので非常に驚かされた。とても面白い主張である。
あわせて読みたい
【奇人】天才数学者で、自宅を持たずに世界中を放浪した変人エルデシュは、迷惑な存在でも愛され続けた…
数学史上ガウスに次いで生涯発表論文数が多い天才エルデシュをご存知だろうか?数学者としてずば抜けた才能を発揮したが、それ以上に「奇人変人」としても知られる人物だ。『放浪の天才数学者エルデシュ』で、世界中の数学者の家を泊まり歩いた異端数学者の生涯を描き出す
著:野矢茂樹
¥715 (2022/11/23 18:58時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
当然と言うべきか、「可能無限」の立場を取る者はかなり少数派なのだそうだ。実際、「数直線上には無限に『数』が存在する」「√2は『数』である」と考えて特に支障はないのだから、「可能無限」という特殊な考え方をする必要はないように思えてしまう。しかし、「実無限」的な世界の捉え方が唯一のものという考えも決めつけでしかないし、「可能無限」的な解釈の余地もあるのだと本書を読んで実感できた。
「数学」という学問分野に対して新たな視点をもたらしてくれた、非常に興味深い作品である。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
あわせて読みたい
【人類学】少数民族・ムラブリ族に潜入した映画『森のムラブリ』は、私たちの「当たり前」を鮮やかに壊す
タイとラオスにまたがって存在する少数民族・ムラブリ族に密着したドキュメンタリー映画『森のムラブリ』。「ムラブリ族の居住地でたまたま出会った日本人人類学者」と意気投合し生まれたこの映画は、私たちがいかに「常識」「当たり前」という感覚に囚われているのかを炙り出してくれる
あわせて読みたい
【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…
数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊
あわせて読みたい
【幸福】「死の克服」は「生の充実」となり得るか?映画『HUMAN LOST 人間失格』が描く超管理社会
アニメ映画『HUMAN LOST 人間失格』では、「死の克服」と「管理社会」が分かちがたく結びついた世界が描かれる。私たちは既に「緩やかな管理社会」を生きているが、この映画ほどの管理社会を果たして許容できるだろうか?そしてあなたは、「死」を克服したいと願うだろうか?
あわせて読みたい
【おすすめ】江戸川乱歩賞受賞作、佐藤究『QJKJQ』は、新人のデビュー作とは思えない超ド級の小説だ
江戸川乱歩賞を受賞した佐藤究デビュー作『QJKJQ』はとんでもない衝撃作だ。とても新人作家の作品とは思えない超ド級の物語に、とにかく圧倒されてしまう。「社会は『幻想』を共有することで成り立っている」という、普段なかなか意識しない事実を巧みにちらつかせた、魔術のような作品
あわせて読みたい
【奇人】天才数学者で、自宅を持たずに世界中を放浪した変人エルデシュは、迷惑な存在でも愛され続けた…
数学史上ガウスに次いで生涯発表論文数が多い天才エルデシュをご存知だろうか?数学者としてずば抜けた才能を発揮したが、それ以上に「奇人変人」としても知られる人物だ。『放浪の天才数学者エルデシュ』で、世界中の数学者の家を泊まり歩いた異端数学者の生涯を描き出す
あわせて読みたい
【要約】福岡伸一『生物と無生物のあいだ』は、「生命とは何か」を「動的平衡」によって定義する入門書…
「生命とは何か?」という、あまりに基本的だと感じられる問いは、実はなかなか難しい。20世紀生物学は「DNAの自己複製」が本質と考えたが、「ウイルス」の発見により再考を迫られた。福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』の2著作から、「生命の本質」を知る
あわせて読みたい
【思考】『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、中学生と猫の対話から「自分の頭で考える」を学べる良書
「中学生の翔太」と「猫のインサイト」が「答えの出ない問い」について対話する『翔太と猫のインサイトの夏休み』は、「哲学」の違う側面を見せてくれる。過去の哲学者・思想家の考えを知ることが「哲学」なのではなく、「自分の頭で考えること」こそ「哲学」の本質だと理解する
あわせて読みたい
【考察】アニメ映画『虐殺器官』は、「便利さが無関心を生む現実」をリアルに描く”無関心ではいられない…
便利すぎる世の中に生きていると、「この便利さはどのように生み出されているのか」を想像しなくなる。そしてその「無関心」は、世界を確実に悪化させてしまう。伊藤計劃の小説を原作とするアニメ映画『虐殺器官』から、「無関心という残虐さ」と「想像することの大事さ」を知る
あわせて読みたい
【本質】子どもの頃には読めない哲学書。「他人の哲学はつまらない」と語る著者が説く「問うこと」の大…
『<子ども>のための哲学』は決して、「子どもでも易しく理解できる哲学の入門書」ではない。むしろかなり難易度が高いと言っていい。著者の永井均が、子どもの頃から囚われ続けている2つの大きな疑問をベースに、「『哲学する』とはどういうことか?」を深堀りする作品
あわせて読みたい
【博覧強記】「紙の本はなくなる」説に「文化は忘却されるからこそ価値がある」と反論する世界的文学者…
世界的文学者であり、「紙の本」を偏愛するウンベルト・エーコが語る、「忘却という機能があるから書物に価値がある」という主張は実にスリリングだ。『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』での対談から、「忘却しない電子データ」のデメリットと「本」の可能性を知る
あわせて読みたい
【異端】「仏教とは?」を簡単に知りたい方へ。ブッダは「異性と目も合わせないニートになれ」と主張し…
我々が馴染み深い「仏教」は「大乗仏教」であり、創始者ゴータマ・ブッダの主張が詰まった「小乗仏教」とは似て非なるものだそうだ。『講義ライブ だから仏教は面白い!』では、そんな「小乗仏教」の主張を「異性と目も合わせないニートになれ」とシンプルに要約して説明する
あわせて読みたい
【感想】池田晶子『14歳からの哲学』で思考・自由・孤独の大事さを知る。孤独を感じることって大事だ
「元々持ってた価値観とは違う考えに触れ、それを理解したいと思う場面」でしか「考える」という行為は発動しないと著者は言う。つまり我々は普段、まったく考えていないのだ。『14歳からの哲学』をベースに、「考えること」と自由・孤独・人生との関係を知る
あわせて読みたい
【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…
『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏の超面白い哲学小説。「正義とは?」の意味を問う”3人の女子高生”の主張とは?:『正義の…
なんて面白いんだろうか。哲学・科学を初心者にも分かりやすく伝える飲茶氏による『正義の教室』は、哲学書でありながら、3人の女子高生が登場する小説でもある。「直観主義」「功利主義」「自由主義」という「正義論」の主張を、「高校の問題について議論する生徒会の話し合い」から学ぶ
あわせて読みたい
【知】内田樹が教育・政治を語る。「未来の自分」を「別人」と捉える「サル化した思考」が生む現実:『…
「朝三暮四」の故事成語を意識した「サル化」というキーワードは、現代性を映し出す「愚かさ」を象徴していると思う。内田樹『サル化する世界』から、日本の教育・政治の現状及び問題点をシンプルに把握し、現代社会を捉えるための新しい視点や価値観を学ぶ
あわせて読みたい
【人生】「資本主義の限界を埋める存在としての『贈与論』」から「不合理」に気づくための生き方を知る…
「贈与論」は簡単には理解できないが、一方で、「何かを受け取ったら、与えてくれた人に返す」という「交換」の論理では対処できない現実に対峙する力ともなる。『世界は贈与でできている』から「贈与」的な見方を理解し、「受取人の想像力」を立ち上げる
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
あわせて読みたい
【ドラマ】「フェルマーの最終定理」のドラマティックな証明物語を、飲茶氏が平易に描き出す:『哲学的…
「フェルマーの最終定理」は、問題の提示から350年以上経ってようやく証明された超難問であり、その証明の過程では様々な人間ドラマが知られている。『哲学的な何か、あと数学とか』をベースに、数学的な記述を一切せず、ドラマティックなエピソードだけに触れる
あわせて読みたい
【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…
古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る
あわせて読みたい
【挑戦】社会に欠かせない「暗号」はどう発展してきたか?サイモン・シンが、古代から量子暗号まで語る…
「暗号」は、ミステリやスパイの世界だけの話ではなく、インターネットなどのセキュリティで大活躍している、我々の生活に欠かせない存在だ。サイモン・シン『暗号解読』から、言語学から数学へとシフトした暗号の変遷と、「鍵配送問題」を解決した「公開鍵暗号」の仕組みを理解する
あわせて読みたい
【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ
350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
あわせて読みたい
【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…
私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する
あわせて読みたい
【変人】結城浩「数学ガール」から、1億円も名誉ある賞も断った天才が証明したポアンカレ予想を学ぶ
1億円の賞金が懸けられた「ポアンカレ予想」は、ペレルマンという天才数学者が解き明かしたが、1億円もフィールズ賞も断った。そんな逸話のある「ポアンカレ予想」とは一体どんな主張であり、どのように証明されたのかを結城浩『数学ガール』から学ぶ
あわせて読みたい
【興奮】結城浩「数学ガール」で、決闘で命を落とした若き天才数学者・ガロアの理論を学ぶ
高校生を中心に、数学を通じて関わり合う者たちを描く「数学ガール」シリーズ第5弾のテーマは「ガロア理論」。独力で「群論」という新たな領域を切り開きながら、先駆的すぎて同時代の数学者には理解されず、その後決闘で死亡した天才の遺した思考を追う
あわせて読みたい
【刺激】結城浩「数学ガール」で、ゲーデルの不完全性定理(不可能性の証明として有名)を学ぶ
『結城浩「数学ガール」シリーズは、数学の面白さを伝えながら、かなり高難度の話題へと展開していく一般向けの数学書です。その第3弾のテーマは、「ゲーデルの不完全性定理」。ヒルベルトという数学者の野望を打ち砕いた若き天才の理論を学びます
あわせて読みたい
【異端】数学の”証明”はなぜ生まれたのか?「無理数」と「無限」に恐怖した古代ギリシャ人の奮闘:『数…
学校で数学を習うと、当然のように「証明」が登場する。しかしこの「証明」、実は古代ギリシャでしか発展しなかった、数学史においては非常に”異端”の考え方なのだ。『数学の想像力 正しさの深層に何があるのか』をベースに、ギリシャ人が恐れたものの正体を知る
あわせて読みたい
【対立】数学はなぜ”美しい”のか?数学は「発見」か「発明」かの議論から、その奥深さを知る:『神は数…
数学界には、「数学は神が作った派」と「数学は人間が作った派」が存在する。『神は数学者か?』をベースに、「数学は発見か、発明か」という議論を理解し、数学史においてそれぞれの認識がどのような転換点によって変わっていったのかを学ぶ
あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
あわせて読みたい
【興奮】素数の謎に迫った天才数学者たちの奮闘と、数学の”聖杯”である「リーマン予想」について:『素…
古今東西の数学者を惹きつけて止まない「素数」。その規則性を見つけ出すことは非常に困難だったが、「リーマン予想」として初めてそれが示された。『素数の音楽』『リーマン博士の大予想』から、天才数学者たちが挑んできた「リーマン予想」をざっくり理解する
あわせて読みたい
【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…
小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る
あわせて読みたい
【情報】日本の社会問題を”祈り”で捉える。市場原理の外にあるべき”歩哨”たる裁き・教育・医療:『日本…
「霊性」というテーマは馴染みが薄いし、胡散臭ささえある。しかし『日本霊性論』では、「霊性とは、人間社会が集団を存続させるために生み出した機能」であると主張する。裁き・教育・医療の変化が鈍い真っ当な理由と、情報感度の薄れた現代人が引き起こす問題を語る
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
哲学・思想【本・映画の感想】 | ルシルナ
私の知識欲は多方面に渡りますが、その中でも哲学や思想は知的好奇心を強く刺激してくれます。ニーチェやカントなどの西洋哲学も、禅や仏教などの東洋哲学もとても奥深いも…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…







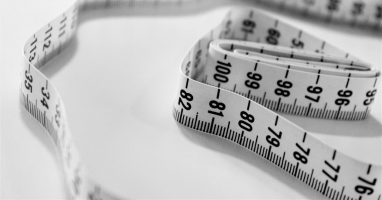






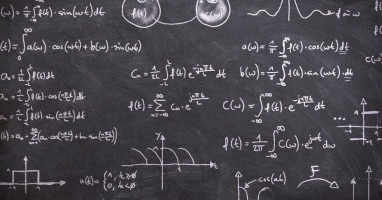









































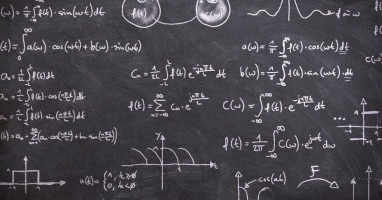


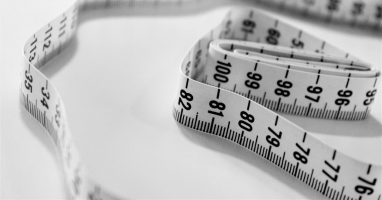











コメント