目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:サイモン・シン, 翻訳:青木薫
¥663 (2021/09/28 06:17時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 「宇宙の始まり」は科学では扱えないと考えられていた
- アインシュタインの「相対性理論」が宇宙観を大きく変化させた
- 「ビッグバンモデル」は批判され続けながらも生き残った”異端”の仮説だった
「宇宙」をテーマに、これほどまでに広範な知識を盛り込んだ作品は、そうそう無いでしょう
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
サイモン・シン『宇宙創成』は、数十世紀に及ぶ「宇宙の捉えられ方」を描き出す一冊
これほどのスケールで「宇宙論」を描く作品は読んだことがない
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
本書は「宇宙」をテーマにした作品だ。そして「宇宙」というのは、あまりにも広すぎるテーマである。

例えば本書では最終的に、「ビッグバン」という現在正しいと信じられている「宇宙の始まり」の理論に行き着く。そしてこの「ビッグバン」だけを取り上げても、様々な科学者による様々な議論があり、驚くような発見があり、反対派が多かったところから少しずつ支持を集めていったというなかなかにドラマティックな話だ。
また古代から人類は、「宇宙」を様々な形で捉えてきた。古くは「亀の上に地球が載っている」と思われていたこともある。「それでも地球は回っている」というガリレオの言葉もある。「宇宙には始まりも終わりもない、永遠に変わらない存在だ」と考えられていた時代もある。
あわせて読みたい
【研究】光の量子コンピュータの最前線。量子テレポーテーションを実現させた科学者の最先端の挑戦:『…
世界中がその開発にしのぎを削る「量子コンピューター」は、技術的制約がかなり高い。世界で初めて「量子テレポーテーション」の実験を成功させた研究者の著書『光の量子コンピューター』をベースに、量子コンピューター開発の現状を知る
このように、どの時代を切り取るかによって「宇宙の捉えられ方」はまったく変わってくるし、人類が思い描いてきた「宇宙像」は多岐に渡る。普通は、それぞれの時代ごとの宇宙観だけを切り取って1冊にまとめるか、あるいは全体を網羅するにしても、雑学本のような個々の記述が薄い内容になってしまうだろう。
しかし本書でサイモン・シンは、古代から現代に至るまでの人類の宇宙観の変遷を可能な限り濃密に描くという、かなりチャレンジングなことを行っている。そしてその点が、本書の凄まじさだと思う。
あわせて読みたい
【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ
350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る
あわせて読みたい
【挑戦】社会に欠かせない「暗号」はどう発展してきたか?サイモン・シンが、古代から量子暗号まで語る…
「暗号」は、ミステリやスパイの世界だけの話ではなく、インターネットなどのセキュリティで大活躍している、我々の生活に欠かせない存在だ。サイモン・シン『暗号解読』から、言語学から数学へとシフトした暗号の変遷と、「鍵配送問題」を解決した「公開鍵暗号」の仕組みを理解する
「人類が宇宙をどんな風に捉えてきたのか」について、基本となる知識をあまり持っていないという方は、まずこの1冊を読んでみるといいだろう。本書の記述だけでも十分満足できるくらいに深く描かれているし、さらに関心を深めたい領域が見つかれば、それに特化した作品を読めばいい。
本書は、科学書でもあり歴史書でもあり、そして「宇宙」という鏡に映し出された人類の物語でもあるというわけだ。
「宇宙の始まりは科学の領域ではない」と考えられていた
現在科学者は、「宇宙がどう始まったのか」を科学の力で解き明かせると考えている。実際に、量子力学の知見を駆使して、「まったく何もないところから、こんな風に宇宙が始まったのだろう」という仮説と、その仮説に至るまでの科学者の奮闘を読んだことがあり、研究の最前線に驚かされた。
あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
しかしかつて科学者は、「宇宙の始まりは科学の領域ではない」と考えていた。恐らく中には、キリスト教の創世記など宗教的なものと結びつけることで「科学の領域ではない」と考える科学者もいただろう(特に、時代を遡れば遡るほどそういう科学者は増えるはずだ)。しかし、そういう宗教的なものと結びつけなくとも、「科学では辿り着けない」と感じてしまう気持ちは、なんとなく理解できる気がする。
一方で科学の歴史というのは、不可能を覆してきた歴史でもある。
例えば、「宇宙」について知ろうとする過程で、科学者がこんな風に考えていた時代もある。
人間は、星の成分やその性質を知ることはできない
あわせて読みたい
【刺激】結城浩「数学ガール」で、ゲーデルの不完全性定理(不可能性の証明として有名)を学ぶ
『結城浩「数学ガール」シリーズは、数学の面白さを伝えながら、かなり高難度の話題へと展開していく一般向けの数学書です。その第3弾のテーマは、「ゲーデルの不完全性定理」。ヒルベルトという数学者の野望を打ち砕いた若き天才の理論を学びます
これも、普通に考えれば「そうだよな」と感じてしまう事柄だろう。星や天体について理解しようと思えば、実際にそこまで行って物質を採取し観察しなければならない、と考えるのは当たり前だと思う。しかし我々は、「ブラックホール」という、そもそも近くまでたどり着くことさえ不可能な天体についてさえ、それがどんなものであるのか理解している。人類は、「光」について研究を積み重ねることで、自分ではたどり着けない領域の事柄でも理解できるようになったのだ。

さらに、こんな風に考えられていた時代もある。地上と天上(要するに「宇宙」のこと)は、違う物理法則で成り立っているのだ、と。地上には地上の、天上には天上のルールがあり、我々は天上のルールを知ることができないのだ、と考えられている時代さえあったのだ。
あわせて読みたい
【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…
「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る
しかしその考えを、ニュートンが打ち砕いた。「万有引力」という考え方を提示し、地上と天上の物理法則が同じであることを示して見せたのだ。
このように、科学は常に不可能を乗り越えてきた。だから「宇宙の始まり」についても、現在の仮説が「正しい」と証明される日が来るだろうと思っている。
しかしそうだとしても、「宇宙が始まる前」を科学で扱うのはやはり困難かもしれない、とも考えられている。
あわせて読みたい
【奇人】天才数学者で、自宅を持たずに世界中を放浪した変人エルデシュは、迷惑な存在でも愛され続けた…
数学史上ガウスに次いで生涯発表論文数が多い天才エルデシュをご存知だろうか?数学者としてずば抜けた才能を発揮したが、それ以上に「奇人変人」としても知られる人物だ。『放浪の天才数学者エルデシュ』で、世界中の数学者の家を泊まり歩いた異端数学者の生涯を描き出す
たとえ特異点を物理学的に扱えたとしても、「ビッグバン以前はどうなっていたのか?」という問題は、論理的に矛盾しているがゆえに答えることは不可能だと考える宇宙論研究者は多い。なにしろビッグバン・モデルによれば、ビッグバンのときには物質と放射が生じただけでなく、空間と時間も生じたはずだからだ。もしも時間がビッグバンで創造されたのなら、ビッグバン以前には時間は存在しなかったことになり、「ビッグバン以前」という言葉は意味を失う。これを理解するために、「北」という言葉を考えてみよう。北という言葉は、「ロンドンの北はどうなっているか?」とか、「エディンバラの北はどうなっているか?」という問いには使えるが、「北極の北はどうなっているか?」という文脈では意味を失うのである。
確かに、「ビッグバン」によって時間(と空間)が生まれたのだから、「ビッグバン以前はどうなっていたのか?」という問いは論理矛盾だろう。「ビッグバン以前」には時間(も空間)も存在しないのだから。しかし、もしかしたら未来の科学は、この論理矛盾さえも乗り越えて、何か驚くべき仮説を生み出してくれるのではないか、と期待している。
古代から人々は「宇宙」をどう捉えてきたのか
あわせて読みたい
【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…
「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る
本書では、人類の宇宙観の変遷が時系列で捉えられている。古代からの宇宙の捉えられ方がぎゅっとまとまっており、時代ごとの考え方に触れることができる。また、「古代の人々が地球の大きさをどう推定したか」や「ケプラーの三原則」など、科学的な側面からも宇宙に対してどのようなアプローチがなされてきたのかも描かれる。
本書を読むと、古代ギリシャの時代には既に、「地球が太陽の周りを回っている」という、現在と同様の認識をしていた哲学者がいたことが分かる。普通に宇宙を見ているだけでは、「自分(地球)は止まっていて、天体が動いている」と考えてしまうのが当たり前だと思うが、古代ギリシャ時代に「地球の方が動いているのだ」と考えていた人物が既にいたというのは凄いことだと思う。
しかしその後、キリスト教の力が大きくなり、科学も飲み込まれていく。ガリレオが「それでも地球は回っている」と言ったとするエピソードはあまりに有名だが、キリスト教は、「自分たちが宇宙の中心である」という信仰を貫くために、「地球が太陽の周りを回っている」という考え方を認めなかった。そして、いわゆる「天動説」と呼ばれる考え方が主流になっていく。
あわせて読みたい
【要約】福岡伸一『生物と無生物のあいだ』は、「生命とは何か」を「動的平衡」によって定義する入門書…
「生命とは何か?」という、あまりに基本的だと感じられる問いは、実はなかなか難しい。20世紀生物学は「DNAの自己複製」が本質と考えたが、「ウイルス」の発見により再考を迫られた。福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』の2著作から、「生命の本質」を知る

ただ、この天動説の広がりの背景には、当時まだ高度な観測技術が存在しなかったことも大きく影響しているだろう。そしてガリレオは、自ら望遠鏡を自作し、宇宙を観測した結果を元に、「地球が太陽の周りを回っている」という「地動説」を主張することになる。しかしその時には既に「天動説」の力が強くなりすぎていて、ガリレオは最終的に自説を曲げざるを得なかった、というわけだ。
しかし次第に、科学は宗教から距離を取るようになる。そして、観測データを元に事実が捉えられるようになり、ようやく「地動説」が認められるようになっていくというわけである。
宇宙観という意味で、この「天動説」と「地動説」の闘いは大きな事件だったといえるだろう。本書では、その変遷が丁寧に描かれていく。
あわせて読みたい
【逸話】天才数学者ガロアが20歳で決闘で命を落とすまでの波乱万丈。時代を先駆けた男がもし生きていた…
現代数学に不可欠な「群論」をたった1人で生み出し、20歳という若さで決闘で亡くなったガロアは、その短い生涯をどう生きたのか?『ガロア 天才数学者の生涯』から、数学に関心を抱くようになったきっかけや信じられないほどの不運が彼の人生をどう変えてしまったのか、そして「もし生きていたらどうなっていたのか」を知る
宇宙論を一変させることになった、アインシュタインの「相対性理論」
次に宇宙観が揺さぶられたきっかけには、アインシュタインが大きく関係している。しかし、アインシュタインがどう関係しているのかを説明するためには、彼が生み出した「相対性理論」の説明をしなければならないので、まずその話から始めよう。
アインシュタインが「相対性理論」を発表する以前、科学界には大きな難問が横たわっていた。それは「光は何を伝わってきているのか?」だ
当時、「光」は「波」だと考えられていた(この辺りの詳細はこの記事では踏み込まないが、「光」には「波」と「粒子」の性質があるとされている。この点には科学の歴史の中でかなりの激論が交わされ、アインシュタインはそれにも絡んでいる。興味のある方は以下の記事を)。
あわせて読みたい
【敗北】「もつれ」から量子論の基礎を学ぶ。それまでの科学では説明不能な「異次元の現象」とは?:『…
アインシュタインは量子力学を生涯受け入れなかったのだが、アインシュタインが批判し続けたことによって明らかになったこともある。「もつれ」の重要性もその一つだ。『宇宙は「もつれ」でできている』から量子力学の基礎を成す現象を知る。
さて、当たり前だが、「波」という物質が存在するわけではない。「波」は「現象」の名前であり、「何かが揺れ動くこと」で発生する。例えば「海の波」は「水」が動くことで、そして「音(波)」は「空気」が動くことで伝わる。このように「波」を伝える物質を「媒質」と呼ぶ。
そして、「光の媒質は一体なんなのだろう?」というのが大きな問題だった。よく知られていることだろうが、仮に宇宙空間(宇宙船の中ではなく外)で音楽を流しても、聞こえない。「音」を伝える「空気」が存在しないからだ。しかしそんな宇宙空間も、「光」は通ってくることができる。「光」は「波」なのだから何か媒質が存在するはずだが、科学者はその正体を見極めることが出来ずにいたのだ。
あわせて読みたい
【限界】有名な「錯覚映像」で心理学界をザワつかせた著者らが語る「人間はいかに間違えるか」:『錯覚…
私たちは、知覚や記憶を頼りに社会を生きている。しかしその「知覚」「記憶」は、本当に信頼できるのだろうか?心理学の世界に衝撃を与えた実験を考案した著者らの『錯覚の科学』から、「避けられない失敗のクセ」を理解する
そこで科学者は、「光」の媒質として「エーテル」という物質を想定した。宇宙空間(これは「宇宙船の外」というだけではなく、地球上も含む)には「エーテル」という物質が存在しており、「光」はそのエーテルを媒質として伝わるのだ、と。科学者は誰も「エーテル」を観測できずにいたが、「光が伝わるためには媒質は必要」というのは絶対条件と考えられていたので、「まだ見つかっていないが、いずれエーテルは観測されるだろう」と考えていた。
しかし、「マイケルソン・モーリーの実験」として知られる有名な実験によって、「エーテルなど存在しない」ことが明らかになった。この結果は科学者を驚愕させたという。そして、その実験結果を知ってか知らずか(本によって「知っていた」「知らなかった」と記述が分かれる)、アインシュタインが「特殊相対性理論」を発表し、エーテル問題に終止符を打ったのだ。
あわせて読みたい
【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…
数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊
アインシュタインが主張したことは、「光が伝わるのにエーテルは不要」「光は『観測者に対して』秒速30万キロメートルで進む」というものだった。

エーテル問題と関連して、当時の科学者にはもう1つ理解できないことがあった。マクスウェル方程式と呼ばれる非常に有名な方程式があるのだが、この方程式から、「光の速度は秒速約30万キロメートル」と導かれる。しかし「何に対しての速度なのか」が分からなかったのだ。
「何に対しての速度なのか」という疑問の説明をしよう。
あわせて読みたい
【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…
現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する
片側2車線の真っ直ぐな道路を、2台の車がまったく同じ時速100キロで並走しているとする。この2台の車を「歩道に立っている人」が見ると、「車は時速100キロで走っている」となる。しかし、一方の車からもう一方の車を見る場合は、「車は時速0キロで走っている(つまり止まっている)」となるだろう。
このように、「速度」を考える時には、「どの立場から見ているのか(何に対してなのか)」を併せて考える必要があるのだ。
しかし、マクスウェル方程式を解いて導き出される「光速は時速約30万キロメートル」という解に関しては、「何に対してなのか」が分からなかった。そこで科学者は、「これはエーテルに対する速度だ」と考えることにしたのである。
あわせて読みたい
【嫉妬?】ヒッグス粒子はいかに発見されたか?そして科学の”発見”はどう評価されるべきか?:『ヒッグ…
科学研究はもはや個人単位では行えず、大規模な「ビッグサイエンス」としてしか成立しなくなっている。そんな中で、科学研究の成果がどう評価されるべきかなどについて、「ヒッグス粒子」発見の舞台裏を追った『ヒッグス 宇宙の最果ての粒子』をベースに書く
しかしアインシュタインは、非常に有名な思考実験を元に考えを深めた結果、「エーテルに対する速度」という捉え方が誤りであることを見抜いた。その思考実験というのが、
目の前に鏡を置いたまま自分自身が光速で移動している時、鏡に自分の顔は映るだろうか?
というものである。この思考実験の説明をしていこう。
ここで、「鏡に何かが映る」という現象についてちょっとイメージをしてほしい。例えば、「顔の前に持ってきた手鏡に自分の顔が映る」という現象は、細かく考えると以下のようなステップで成り立っている。
- 自分の顔に光が当たる
- 「自分の顔に当たった光」が光速で鏡に向かってぶつかる
- 「鏡にぶつかった光」が光速で自分の目に戻ってくる
- 鏡に自分の顔が映っているのが見える
あわせて読みたい
【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…
日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊
要するに、「光の反射を目が捉える」のが「見える」という現象であり、その光は光速で移動している、ということがイメージできていればよい。
さてここで、手鏡を顔の前に固定した状態で、手鏡と自分が共に光速で前進することを考えよう(このように、現実的には行えない実験を頭の中で考えてみることを「思考実験」と呼ぶ。アインシュタインはこの「思考実験」の天才だったと言われている)。

この場合、先のステップ①が終わった後、ステップ②が実行されるかどうかが問題となる。手鏡も自分も光速で動いているのだから、「自分の顔に当たった光」が光速で鏡に向かったとしても、その光は鏡まで届かないかもしれない、と理解できるだろうか?
あわせて読みたい
【歴史】ベイズ推定は現代社会を豊かにするのに必須だが、実は誕生から200年間嫌われ続けた:『異端の統…
現在では、人工知能を始め、我々の生活を便利にする様々なものに使われている「ベイズ推定」だが、その基本となるアイデアが生まれてから200年近く、科学の世界では毛嫌いされてきた。『異端の統計学ベイズ』は、そんな「ベイズ推定」の歴史を紐解く大興奮の1冊だ
イメージが難しければ、こう考えてみよう。2台の車が前後に1メートルの車間距離を空けて、共に時速100キロで走っているとする。この状態で、後ろの車からボールを時速100キロで投げた場合、前の車にそのボールは届くだろうか? どちらの車も時速100キロで進んでいるのだから、時速100キロで打ち出したボールは前の車まで届かないはずだ。
同じように、手鏡も自分も光速で動いている時に、「自分の顔に当たった光」は鏡まで届かないかもしれない。そうなれば、鏡に自分の顔は映らない、ということになる。
アインシュタインは、「それはおかしい」と感じた。仮に手鏡と自分が光速で動いていたとしても、鏡に自分の顔は映るはずだ、と考えたのである。
あわせて読みたい
【快挙】「暗黒の天体」ブラックホールはなぜ直接観測できたのか?国際プロジェクトの舞台裏:『アイン…
「世界中に存在する電波望遠鏡を同期させてブラックホールを撮影する」という壮大なEHTプロジェクトの裏側を記した『アインシュタインの影』から、ブラックホール撮影の困難さや、「ノーベル賞」が絡む巨大プロジェクトにおける泥臭い人間ドラマを知る
そしてアインシュタインは、この思考実験について考えを突き詰めた結果、「光は『観測者』に対して時速約30万キロメートルで進む」という結論に達した。しかしこれは実に奇妙な結論だ。その奇妙さを、先程の並走している2台の車で改めて説明してみよう。
時速100キロで並走している車の場合、「歩道から見れば時速100キロ」「一方の車から見れば時速0キロ」に見えた。ではこれを、2台の車が光速(秒速約30万キロメートル)で並走している、と条件を変えてみよう。この場合、「歩道から見ても秒速約30万キロ」「一方の車から見ても時速30万キロ」に見える、ということだ。
これが、「光は『観測者』に対して時速約30万キロメートルで進む」という意味なのだが、ちょっと信じがたい結論だろう。
あわせて読みたい
【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…
一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する
アインシュタインは、「どんな観測者から見ても、光の速度は常に秒速約30万キロメートルだ」と主張した。そして、こんな奇妙な現象が実現するためには、エーテルなんてものが存在してはむしろ困る。もし「光が何らかの媒質を通ってくる」なら、「光は媒質に対して秒速30万キロメートル」ということになり、アインシュタインが主張する「光は『観測者』に対して時速約30万キロメートル」が実現されないからだ。
このようにしてアインシュタインは、「エーテルが存在する」という幻想をも打ち砕いたのである。
「相対性理論」の方程式が導き出した「宇宙の姿」
さて、「相対性理論」について長々と説明してしまったが、「宇宙」の話に戻そう。
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ
アインシュタインは、「光はどんな場合でも秒速約30万キロメートルで観測される」という「光速度不変の原理」をベースにして「特殊相対性理論」を導き出したが、その後、「特殊相対性理論」に「重力」を組み込んだ「一般相対性理論」を発表する。そしてこの「一般相対性理論」が、宇宙像を一変させることになるのだ。
なんと一般相対性理論は、アインシュタインが理想とする「宇宙の姿」を否定するのである。
アインシュタインが「一般相対性理論」の方程式を解いてみたところ、「宇宙は膨張している」という解が導き出された。この事実に、アインシュタインは驚愕する。
アインシュタインが何故驚いたのかを理解するために、当時広く信じられていた宇宙観の説明をしよう。
あわせて読みたい
【平易】一般相対性理論を簡単に知りたい方へ。ブラックホール・膨張宇宙・重力波と盛りだくさんの1冊:…
現役の研究者が執筆した『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』は、アインシュタインが導き出した一般相対性理論が関わる3つのテーマについて、初心者にも分かりやすく伝える内容になっている。歴史的背景も含めて科学的知見を知りたい方にオススメの1冊
アインシュタインを含め、当時の科学者の多くは、「宇宙は過去から未来において変化せず、常に同じ状態で存在し続けてきた」という、「変化のない宇宙」を信じていた。これは、観測などによって裏付けられたものではなく、科学者たちの「願望」や「妄想」の類と言っていいものなのだが、当時の科学者にとってこの認識は「当然」「当たり前」のものだった。
だからこそアインシュタインは、自分が生み出した方程式から「宇宙が膨張している」という解が出てきたことに驚かされてしまったのだ。その解は「変化する宇宙」を示唆するため、アインシュタインは受け入れられなかった。
そこで彼は、後に様々な意味で有名になる「宇宙項」と呼ばれる項目を方程式に付け足し、「一般相対性理論の方程式を解いたら、『宇宙は静止している』という解が導かれる」ように微調整を施したのだ。正直この微調整は、科学的な態度ではまったくなく、アインシュタインが自分の願望を実現するための小細工だと言っていい。しかしこの事実から、アインシュタインがどれだけ強く「変化のない宇宙」を望んでいたかということが理解できるだろう。
あわせて読みたい
【謎】恐竜を絶滅させた隕石はどこから来た?暗黒物質が絡む、リサ・ランドールの驚愕の仮説:『ダーク…
「生物の絶滅」には、以前から知られていたある謎があった。そしてその謎を、未だに観測されておらず、「科学者の妄想の産物」でしかない「ダークマター(暗黒物質)」が解決するかもしれない。現役の科学者が『ダークマターと恐竜絶滅』で語る驚きの仮説。

しかしアインシュタインがそんな小細工をしてからしばらくして、ハッブルという天文学者が科学者を驚愕させる観測を行うことになる。ハッブルは、「宇宙が膨張している」ことを天体望遠鏡の観測によって明らかにしたのだ。
アインシュタインはハッブルの発見を受け、その観測データを精査し、やがて「宇宙は膨張している」という事実を認めた。そして「宇宙項」という、方程式に施した小細工を撤回したのである。アインシュタインが「宇宙項」という小細工を施さず、方程式の解をそのまま受け止めていれば、「宇宙膨張を予言した人物」としても記憶されることになっただろう。
アインシュタインはこの「宇宙項」について「我が人生最大の過ち」と語った、という非常に有名なエピソードがある。しかし後の研究によって、おそらくこのエピソードはガモフという科学者の創作だろうと考えられているそうだ。
さてこの「宇宙項」、実はアインシュタインの死後復活することになる。この記事ではその詳細には触れないので、先程も紹介した以下の記事を読んでみてほしい。
あわせて読みたい
【驚嘆】「現在は森でキノコ狩り」と噂の天才”変人”数学者グリゴリー・ペレルマンの「ポアンカレ予想証…
数学界の超難問ポアンカレ予想を解決したが、100万ドルの賞金を断り、フィールズ賞(ノーベル賞級の栄誉)も辞退、現在は「森できのこ採取」と噂の天才数学者グリゴリー・ペレルマンの生涯を描く評伝『完全なる証明』。数学に関する記述はほぼなく、ソ連で生まれ育った1人の「ギフテッド」の苦悩に満ちた人生を丁寧に描き出す1冊
「ビッグバンモデル」の誕生
アインシュタインとハッブルによって「宇宙が膨張している」という事実が明らかになったわけだが、ここからある仮説が容易に生まれる。「時間と共に宇宙が膨張している」とするならば、時間を巻き戻すと宇宙はどんどん小さくなっていくということだ。では、そのまま時間をどんどん巻き戻していけば、最終的に宇宙は「ある一点」に収束するのではないだろうか。
このようにして、「宇宙に『始まり』があった」と考えられるようになっていくのだ。そして、そのアイデアには「ビッグバン」という名前がつけられることになる。
私たちは既に、「宇宙はビッグバンから始まった」ということを知っているし、そのことに違和感や拒否反応を抱くことはないだろうが、当初は違った。
あわせて読みたい
【平易】ブラックホールを分かりやすく知りたい。難しいことは抜きにふわっと理解するための1冊:『ブラ…
2019年に初めて直接観測されるも、未だに謎多き天体である「ブラックホール」について現役研究者が分かりやすく語る『ブラックホールをのぞいてみたら』をベースに、科学者がその存在を認めてこなかった歴史や、どんな性質を持つ天体なのかを理解する
「ビッグバンモデル」は、最終的にそれが正しいと証明されるまでは常に「異端」であり続け、ほとんどずっと賛同者が少数派であるような考え方だったのだ。
「ビッグバンモデル」に対抗していたのが「定常宇宙論」と呼ばれるアイデアだった。これは、アインシュタインが信じていた「始まりも終わりもない、ずっと変わらない宇宙」という考え方に理論的な肉付けを行ったものだと思えばいい。「宇宙は膨張している」という発見がなされた後も、「宇宙はずっと状態が変わらない」という考えが存在し、むしろこちらの方が長く主流派だったのである。
宇宙論は、「ビッグバンモデル」VS「定常宇宙論」という最後の大きな闘いを迎えることになったのだ。

あわせて読みたい
【興奮】素数の謎に迫った天才数学者たちの奮闘と、数学の”聖杯”である「リーマン予想」について:『素…
古今東西の数学者を惹きつけて止まない「素数」。その規則性を見つけ出すことは非常に困難だったが、「リーマン予想」として初めてそれが示された。『素数の音楽』『リーマン博士の大予想』から、天才数学者たちが挑んできた「リーマン予想」をざっくり理解する
「ビッグバンモデル」が不人気だったのには理由がある。当時の常識からはあまりにも逸脱していると思われるような主張ばかりしていたからだ。この記事ではその詳細には触れないが、科学者が「そんなことが起こったはずがない」と感じてしまうような理論だったのである。
しかしそれでも一定の支持者が存在していたのは、「ビッグバンモデルでなければ説明不可能な状況」があったからだ。つまり、「ビッグバンモデルはムチャクチャな主張をするが、それが起こったことを示唆する証拠も若干存在する理論」だったのである。
一方の「定常宇宙論」は、科学者をビックリさせるようなムチャクチャな主張はしなかったが、証拠も一切無いという理論だった。
あわせて読みたい
【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ
『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?
いずれにせよ、「ビッグバンモデル」と「定常宇宙論」の議論が盛んに行われていた当時の観測技術には様々な限界があったため、分からないことも多かった。そしてどちらのモデルも、その時点で判明している事実とは大きく矛盾しないという意味では五十歩百歩だったのである。
しかしようやく観測技術が追いついた。そして、「ビッグバンモデル」だけが予測した現象が捉えられ、これが決定的な証拠となって、現在では「ビッグバンモデル」が正しいと認められるようになった、という流れである。
「ビッグバンモデル」と「定常宇宙論」のバトルには、「人間の醜い争い」から「偶然の発見でノーベル賞受賞」まで刺激的なドラマが詰まっている。理論の中身があまり上手く理解できなかったとしても、その人間ドラマには興奮させられるはずだ。本書ではそれらが余すところなく描かれているので、是非読んでほしいと思う。
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
著:サイモン シン, 原著:Singh,Simon, 翻訳:薫, 青木
¥781 (2022/01/29 21:30時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
サイモン・シンの著作についてはこれまで、『フェルマーの最終定理』と『暗号解読』を紹介してきた。
あわせて読みたい
【証明】結城浩「数学ガール」とサイモン・シンから「フェルマーの最終定理」とそのドラマを学ぶ
350年以上前に一人の数学者が遺した予想であり「フェルマーの最終定理」には、1995年にワイルズによって証明されるまでの間に、これでもかというほどのドラマが詰め込まれている。サイモン・シンの著作と「数学ガール」シリーズから、その人間ドラマと数学的側面を知る
あわせて読みたい
【挑戦】社会に欠かせない「暗号」はどう発展してきたか?サイモン・シンが、古代から量子暗号まで語る…
「暗号」は、ミステリやスパイの世界だけの話ではなく、インターネットなどのセキュリティで大活躍している、我々の生活に欠かせない存在だ。サイモン・シン『暗号解読』から、言語学から数学へとシフトした暗号の変遷と、「鍵配送問題」を解決した「公開鍵暗号」の仕組みを理解する
どれでもいいが、読んでみたら、サイモン・シンという作家の「分かりやすく記述する能力」が実感できることだろう。いずれも、科学・数学に関心を持っているが苦手意識もあるという方にオススメできる作品だ。
本書もまた、「宇宙」という壮大なテーマに臆することなく立ち向かい、執筆時点で理解されていた事柄をこれでもかと詰め込んだ、贅沢な一冊である。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【宣伝】アポロ計画での月面着陸映像は本当か?映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』のリアル
「月面着陸映像はニセモノだ」という陰謀論を逆手にとってリアリティのある物語を生み出した映画『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』は、「ベトナム戦争で疲弊し、事故続きのNASAが不人気だった」という現実を背景に「歴史のif」を描き出す。「確かにそれぐらいのことはするかもしれない」というリアリティをコメディタッチで展開させる
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
あわせて読みたい
【知的】「BLって何?」という初心者に魅力を伝える「腐男子」の「BLの想像力と創造力」講座:『ボクた…
「BLは知的遊戯である」という主張には「は?」と感じてしまうでしょうが、本書『ボクたちのBL論』を読めばその印象は変わるかもしれません。「余白の発見と補完」を通じて、「ありとあらゆる2者の間の関係性を解釈する」という創造性は、現実世界にどのような影響を与えているのか
あわせて読みたい
【驚異】数学の「無限」は面白い。アキレスと亀の矛盾、実無限と可能無限の違い、カントールの対角線論…
日常の中で「無限」について考える機会などなかなか無いだろうが、野矢茂樹『無限論の教室』は、「無限には種類がある」と示すメチャクチャ興味深い作品だった。「実無限」と「可能無限」の違い、「可能無限」派が「カントールの対角線論法」を拒絶する理由など、面白い話題が満載の1冊
あわせて読みたい
【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ
『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?
あわせて読みたい
【要約】福岡伸一『生物と無生物のあいだ』は、「生命とは何か」を「動的平衡」によって定義する入門書…
「生命とは何か?」という、あまりに基本的だと感じられる問いは、実はなかなか難しい。20世紀生物学は「DNAの自己複製」が本質と考えたが、「ウイルス」の発見により再考を迫られた。福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』の2著作から、「生命の本質」を知る
あわせて読みたい
【新視点】世界の歴史を「化学」で語る?デンプン・砂糖・ニコチンなどの「炭素化合物」が人類を動かし…
デンプン・砂糖・ニコチンなどは、地球上で非常に稀少な元素である「炭素」から作られる「炭素化合物」だ。そんな「炭素化合物」がどんな影響を与えたかという観点から世界の歴史を描く『「元素の王者」が歴史を動かす』は、学校の授業とはまったく違う視点で「歴史」を捉える
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ
あわせて読みたい
【飛躍】有名哲学者は”中二病”だった?飲茶氏が易しく語る「古い常識を乗り越えるための哲学の力」:『1…
『14歳からの哲学入門』というタイトルは、「14歳向けの本」という意味ではなく、「14歳は哲学することに向いている」という示唆である。飲茶氏は「偉大な哲学者は皆”中二病”だ」と説き、特に若い人に向けて、「新しい価値観を生み出すためには哲学が重要だ」と語る
あわせて読みたい
【興奮】世界的大ベストセラー『サピエンス全史』要約。人類が文明を築き上げるに至った3つの革命とは?
言わずと知れた大ベストセラー『サピエンス全史』は、「何故サピエンスだけが人類の中で生き残り、他の生物が成し得なかった歴史を歩んだのか」を、「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つを主軸としながら解き明かす、知的興奮に満ち溢れた1冊
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【感想】飲茶の超面白い東洋哲学入門書。「本書を読んでも東洋哲学は分からない」と言う著者は何を語る…
東洋哲学というのは、「最終回しか存在しない連続ドラマ」のようなものだそうだ。西洋哲学と比較にならないほど異質さと、インド哲学・中国哲学など個別の思想を恐ろしく分かりやすく描く『史上最強の哲学入門 東洋の哲人たち』は、ページをめくる手が止まらないくらい、史上最強レベルに面白かった
あわせて読みたい
【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…
「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【問い】「学ぶとはどういうことか」が学べる1冊。勉強や研究の指針に悩む人を導いてくれる物語:『喜嶋…
学校の勉強では常に「課題」が与えられていたが、「学び」というのは本来的に「問題を見つけること」にこそ価値がある。研究者の日常を描く小説『喜嶋先生の静かな世界』から、「学びの本質」と、我々はどんな風に生きていくべきかについて考える
あわせて読みたい
【平易】ブラックホールを分かりやすく知りたい。難しいことは抜きにふわっと理解するための1冊:『ブラ…
2019年に初めて直接観測されるも、未だに謎多き天体である「ブラックホール」について現役研究者が分かりやすく語る『ブラックホールをのぞいてみたら』をベースに、科学者がその存在を認めてこなかった歴史や、どんな性質を持つ天体なのかを理解する
あわせて読みたい
【限界】「科学とは何か?」を知るためのおすすめ本。科学が苦手な人こそ読んでほしい易しい1冊:『哲学…
「科学的に正しい」という言葉は、一体何を意味しているのだろう?科学者が「絶対に正しい」とか「100%間違っている」という言い方をしないのは何故だろう?飲茶『哲学的な何か、あと科学とか』から、「科学とはどんな営みなのか?」について考える
あわせて読みたい
【快挙】「暗黒の天体」ブラックホールはなぜ直接観測できたのか?国際プロジェクトの舞台裏:『アイン…
「世界中に存在する電波望遠鏡を同期させてブラックホールを撮影する」という壮大なEHTプロジェクトの裏側を記した『アインシュタインの影』から、ブラックホール撮影の困難さや、「ノーベル賞」が絡む巨大プロジェクトにおける泥臭い人間ドラマを知る
あわせて読みたい
【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…
どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る
あわせて読みたい
【到達】「ヒッグス粒子の発見」はなぜ大ニュースなのか?素粒子物理学の「標準模型」を易しく説明する…
「ヒッグス粒子の発見」はメディアでも大きく取り上げられたが、これが何故重要なのかを説明できる人はそう多くはないだろう。『強い力と弱い力 ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く』をベースに、謎めいた「弱い力」を説明する「自発的対称性の破れ」を学ぶ
あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
あわせて読みたい
【平易】一般相対性理論を簡単に知りたい方へ。ブラックホール・膨張宇宙・重力波と盛りだくさんの1冊:…
現役の研究者が執筆した『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』は、アインシュタインが導き出した一般相対性理論が関わる3つのテーマについて、初心者にも分かりやすく伝える内容になっている。歴史的背景も含めて科学的知見を知りたい方にオススメの1冊
あわせて読みたい
【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…
現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
宇宙・ビッグバン・ブラック ホール・相対性理論【本・映画の感想】 | ルシルナ
科学全般に関心を持っていますが、その中でも宇宙に関する本はたくさん読んできました。ビッグバンがいかに起こったか、ブラックホールはどうやって直接観測されたか、宇宙…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…





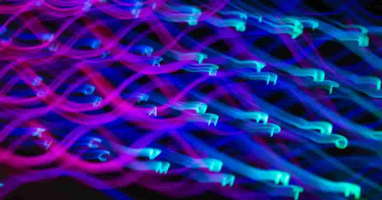











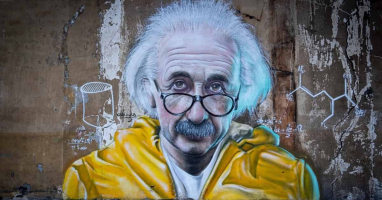












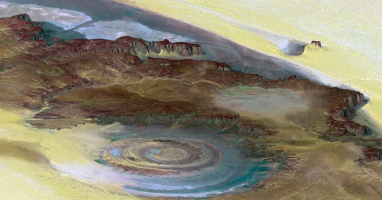


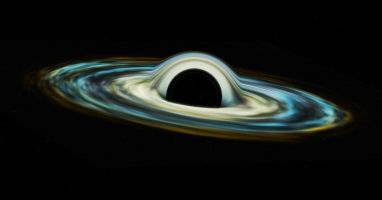

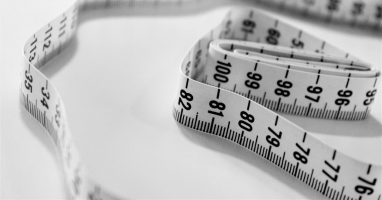





















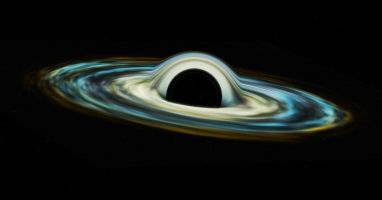



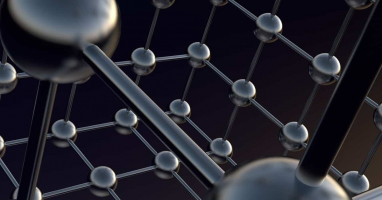













コメント