目次
はじめに
この記事で取り上げる本
著:リサ・ランドール, 監修:向山信治, 翻訳:向山 信治, 翻訳:塩原 通緒
¥1,376 (2021/08/27 06:22時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
この本をガイドにしながら記事を書いていきます
この記事の3つの要点
- 「隕石によって恐竜が絶滅したこと」は、ごく最近正式に認められた
- 「ダークマター」は、見えないし触れられもしない物質
- 恐竜を絶滅させた隕石がどこからやってきたのか明らかにする仮説「DDDM理論」
非常に高度な内容の本で、すべてを理解することはできなかったが、物凄く刺激的で面白い
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
恐竜を絶滅させた隕石は、一体どこからやってきたのか?現役科学者リサ・ランドールが『ダークマターと恐竜絶滅』でその謎を説明する
本書『ダークマターと恐竜絶滅』の構成と、著者リサ・ランドールについて
あわせて読みたい
【化石】聞き馴染みのない「分子生物学」を通じて、科学という学問の本質を更科功が分かりやすく伝える…
映画『ジュラシック・パーク』を観たことがある方なら、「コハクの化石に閉じ込められた蚊の血液から恐竜の遺伝子を取り出す」という設定にワクワクしたことだろう。『化石の分子生物学』とは、まさにそのような研究を指す。科学以外の分野にも威力を発揮する知見に溢れた1冊
本書はタイトルの通り、「恐竜絶滅」と「ダークマター」に関する仮説の話だ。「ダークマター」については後で触れるが、「まだ存在するかどうか分かっていない未知の物質」ぐらいに今は理解しておいてほしい。そんな物質と「恐竜絶滅」を結びつけるというのだから、なかなかアクロバティックな話だ。

著者のリサ・ランドールは、基本的には「恐竜絶滅」とはまったく関係がない。第一線で活躍する素粒子物理学者であり、デビュー作である『ワープする宇宙』は、20世紀物理学を概説しながら宇宙に関するある仮説を提示するという野心的な作品だった。
あわせて読みたい
【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…
現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する
そして本書では一転、宇宙の話と恐竜の絶滅を結びつける。本書では、著者らが「ダブルディスク・ダークマター(DDDM)理論」と名付けた理論が提示され、これが「恐竜絶滅」と関係しているのではないか、と示唆される。物理学の話だけではなく、古生物学に関する知見もふんだんに盛り込まれており、相変わらず知的好奇心が刺激される作品だ。
しかしなかなか難しい作品で、ついていけない箇所も多々あった。この記事では、あくまでも私が理解できた範囲内のことにしか触れられないのでご容赦いただきたい。
「隕石によって恐竜が絶滅した」と認められたのはごく最近のこと
あわせて読みたい
【快挙】「暗黒の天体」ブラックホールはなぜ直接観測できたのか?国際プロジェクトの舞台裏:『アイン…
「世界中に存在する電波望遠鏡を同期させてブラックホールを撮影する」という壮大なEHTプロジェクトの裏側を記した『アインシュタインの影』から、ブラックホール撮影の困難さや、「ノーベル賞」が絡む巨大プロジェクトにおける泥臭い人間ドラマを知る
本書を読んで最も驚いたのが、以下の記述だ。
2010年3月に、古生物学、地球化学、気候モデル研究、地球物理学、堆積学の各分野の専門家41名が集まって、この20年以上のあいだに積み重ねられていた衝突―大量絶滅仮説のさまざまな証拠を検討した。その結論として、チクシュルーブ・クレーターをつくったのもK-Pg絶滅を生じさせたのも、確実に6600万年前の流星物質の衝突であり、そしてその最大の被害者が、かの偉大なる恐竜だったという見解に落ち着いた
恐竜を含めた多数の生物が絶滅した出来事には「K-Pg絶滅」という名前が付けられているのだが、要するに「恐竜が隕石によって絶滅したと確定した」と言っているわけだ。そしてそれが確定したのが2010年3月だったことに驚かされた。ついこの間じゃないか、と感じたのだ。
あわせて読みたい
【神秘】脳研究者・池谷裕二が中高生向けに行った講義の書籍化。とても分かりやすく面白い:『進化しす…
「宇宙」「深海」「脳」が、人類最後のフロンティアと呼ばれている。それほど「脳」というのは、未だに分からないことだらけの不思議な器官だ。池谷裕二による中高生向けの講義を元にした『進化しすぎた脳』『単純な脳、複雑な「私」』をベースに、脳の謎を知る
子どもの頃から、「恐竜は隕石の衝突で絶滅した」と理解していたと思う。図鑑などには、必ずそう書かれていたはずだ。しかし学問的にはあくまでそれは仮説に過ぎず、2010年にようやく、科学の統一見解として「恐竜は隕石で絶滅した」と確定したということなのだ。この点にはまず驚かされた。
さらに本書には、こんな記述もある。

あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
1973年には地球化学者のハロルド・ユーリーが、溶けた岩石からできるガラス質のテクタイトを根拠に、流星物質の衝突がK-Pg絶滅の原因だったと提唱したが、その時点でもまだ大半の科学者はユーリーの考えを無視した
しかしながら、そうした先見の明のある鋭い考えも、アルヴァレズの説が発表されるまでは基本的に無視されていた。宇宙からの飛来物の衝突が絶滅を引き起こすという考えは、1980年代になってもなお過激と見なされ、ちょっと頭がおかしいのではないかという第一印象さえ持たれかねなかった
私は1983年生まれだが、私が生まれた頃でさえまだ、「恐竜が隕石によって絶滅したと考えるのはおかしいんじゃない?」という考えが科学者の間では支配的だった、ということだ。一般的には非常に有名で馴染みのある見解だと思うが、科学的には長いこと疑問符の付く考え方だった、と知ることができた。
あわせて読みたい
【快挙】「チバニアン」は何が凄い?「地球の磁場が逆転する」驚異の現象がこの地層を有名にした:『地…
一躍その名が知れ渡ることになった「チバニアン」だが、なぜ話題になり、どう重要なのかを知っている人は多くないだろう。「チバニアン」の申請に深く関わった著者の『地磁気逆転と「チバニアン」』から、地球で起こった過去の不可思議な現象の正体を理解する
そもそも科学において、「隕石」という存在がなかなか厄介なものだったらしい。写真や映像などが存在せず、機械による科学分析もまだまだ難しかった時代には、「空から何か落ちてきた」という一般民衆の証言のみが頼りだったからだ。本書には、「隕石」の捉えられ方についてもこんな風に書かれている。
宇宙から飛来した物体が地球にぶつかるなんていう奇妙な現象は、とても信じがたいことのように思えるものだ。実際、かつての科学界はそんな主張をまったく真実だとは思わなかった
隕石が宇宙由来であるという考えがようやく正式に認められるにいたったきっかけは、1794年6月、シエナのアカデミーに不意にたくさんの石が落ちてきたことだった
あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
科学の歴史は、その時代その時代における「常識」との闘いなのだが、「宇宙から石が飛んでくるはずがない」という考え方もまた、覆されるまでに時間が掛かった、ということだ。
「ダークマター」とは何か?
本書のもう一つの主役が「ダークマター」だが、一体これはなんだろうか?
これは、「目には見えない(ダーク)だが、存在すると仮定しないと説明がつかない物質(マター)」のことである。
ダークマターは、こんな風に”発見”された(この”発見”は”存在を仮定するに至った”という意味)。
あわせて読みたい
【嫉妬?】ヒッグス粒子はいかに発見されたか?そして科学の”発見”はどう評価されるべきか?:『ヒッグ…
科学研究はもはや個人単位では行えず、大規模な「ビッグサイエンス」としてしか成立しなくなっている。そんな中で、科学研究の成果がどう評価されるべきかなどについて、「ヒッグス粒子」発見の舞台裏を追った『ヒッグス 宇宙の最果ての粒子』をベースに書く
科学者はある時、奇妙なことに気づいた。銀河の周縁部に存在している天体は、なぜ銀河から振り落とされないのだろうかという疑問を抱いたのだ。

例えばこんな想像をしてみてほしい。あなたはクルクル回る円盤の上に乗っている。円盤が回転すると、フィギュアスケーターのようにその場で回転し続けるのだ。さてその円盤の上にボウリングの球を抱えた状態で乗り、円盤を回転させよう。ボウリングを持ったあなた自身もクルクル回ることになる。
あわせて読みたい
【天才】『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、科学者のイメージが変わる逸話満載の非・科学エッセイ
「天才科学者」と言えばアインシュタインやニュートン、ホーキングが思い浮かぶだろうが、「科学者らしくないエピソード満載の天才科学者」という意味ではファインマンがずば抜けている。世界的大ベストセラー『ご冗談でしょう、ファインマンさん』は、「科学」をほぼ扱わないエッセイです
さてこの状態で、ボウリングの球を持った腕を少しずつ前に伸ばそう。ボウリングの球が身体からさほど離れていない時であれば、腕に掛かる力はそう大きくないが、腕をピンと伸ばし、自分の身体から遠く離れた場合にある時には、自分の腕にもの凄く大きな力が掛かることがイメージできるだろうか? 回転スピードが早くなればなるほど腕に掛かる力は大きくなり、ついには支えきれずにボウリングの球を離してしまうかもしれない。
銀河も実はこれと同じ状態にある。銀河の中心に近い天体はさほど大きな力を受けないのだが、銀河の周縁部に存在する天体はもの凄く大きな力を受ける。科学者の計算によると、銀河の周縁部にある天体は、あまりに大きな力を受けるため、普通に考えれば銀河に留まっていられずに飛び出してしまうはずという。
しかし実際にはそうならず、銀河の周縁部にある天体は銀河内に留まっている。不思議だ。どうしてそんなことが可能なのだろうか?
あわせて読みたい
【平易】ブラックホールを分かりやすく知りたい。難しいことは抜きにふわっと理解するための1冊:『ブラ…
2019年に初めて直接観測されるも、未だに謎多き天体である「ブラックホール」について現役研究者が分かりやすく語る『ブラックホールをのぞいてみたら』をベースに、科学者がその存在を認めてこなかった歴史や、どんな性質を持つ天体なのかを理解する
そこで科学者が考えたのが、目には見えない「ダークマター」である。
ここでもう一度、先程の回転する円盤の例に戻ろう。ここで、この円盤に乗るのがお相撲さんだとしよう(この例では、体重が重い=ボウリングの球を支える力が強い、とする)。普通の人では支えられない回転速度であっても、お相撲さんなら耐えられるかもしれない。
銀河についてもこれと同じように考えることができる。「計算上、銀河を飛び出してしまう」というのは、「目に見える物質(の質量)」だけのことを考えている。もし、我々の目には見えない(つまり、光と相互作用しない)物質が存在していれば、計算が変わるのだ。
あわせて読みたい
【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…
どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る
目に見える物質だけでは「ヒョロヒョロの男がボウリングの球を支えている」ようにしか考えられないが、実は「透明人間のお相撲さんも一緒にボウリングの球を支えている」とするなら理屈は合う。
そのような理由から、「宇宙には『透明人間のお相撲さん(ダークマター)』が存在するはずだ」と考えられるようになったのである。
さて先程、「ダークマターは光とは相互作用しない」と書いた。これは、我々の目には見えないということだ。さらに、仮に私たちの近くにダークマターが存在していても触れられないという。我々凡人には、どんなものか想像もつかない。
まだ「ダークマター」は発見されていない(つまり、科学者の妄想上の産物である)が、「ダークマターが存在するに違いない」という間接的な証拠は得られており、それらの証拠から、「ダークマターは重力としか相互作用しない」とも考えられている。
あわせて読みたい
【論争】サイモン・シンが宇宙を語る。古代ギリシャからビッグバンモデルの誕生までの歴史を網羅:『宇…
古代から現代に至るまで、「宇宙」は様々な捉えられ方をしてきた。そして、新たな発見がなされる度に、「宇宙」は常識から外れた不可思議な姿を垣間見せることになる。サイモン・シン『宇宙創成』をベースに、「ビッグバンモデル」に至るまでの「宇宙観」の変遷を知る
やはりイメージしにくいが、「目には見えないし、触ることもできないが、重力が存在すれば重力の影響を受ける物質」ということだ。
「ダークマター」は「暗黒物質」とも表記されるので注意しよう。また、「ダークマター」に似たものとして「ダークエネルギー」と呼ばれるものもあるが、両者はまったく別物である。ここでは詳しく説明しないが、この「ダークエネルギー」も、「まだ発見されていないが、存在を仮定しないとおかしなことになってしまうエネルギー」につけられた名前だ。
あわせて読みたい
【バトル】量子力学の歴史はこの1冊で。先駆者プランクから批判者アインシュタインまですべて描く:『量…
20世紀に生まれた量子論は、時代を彩る天才科学者たちの侃々諤々の議論から生み出された。アインシュタインは生涯量子論に反対し続けたことで知られているが、しかし彼の批判によって新たな知見も生まれた。『量子革命』から、量子論誕生の歴史を知る

現在の科学では、宇宙は「ダークマター」「ダークエネルギー」「通常の物質(我々が知っている原子など)」で構成されていると考えられている。そしてその比率がなかなか衝撃的だ。「ダークマター」と「ダークエネルギー」を合わせて宇宙の96%を占め、「通常の物質」はたったの4%しかないと考えられている。つまり、これまでの科学では、宇宙全体の4%についてしか理解できていなかった、というわけだ。
「ダークマター」も「ダークエネルギー」もまだ発見すらされていない存在だが、本書では、「ダークマター」が存在すると仮定して、それがどんな性質を持つのかを研究した結果について様々に触れられている、ということである。
「DDDM理論」への道筋と、「恐竜絶滅」との関係性
あわせて読みたい
【敗北】「もつれ」から量子論の基礎を学ぶ。それまでの科学では説明不能な「異次元の現象」とは?:『…
アインシュタインは量子力学を生涯受け入れなかったのだが、アインシュタインが批判し続けたことによって明らかになったこともある。「もつれ」の重要性もその一つだ。『宇宙は「もつれ」でできている』から量子力学の基礎を成す現象を知る。
さて、準備が整ったところで、本書のメインとなる主張についてざっくり触れていこう。
冒頭でも書いたが、本書は非常に高度な内容なので、すべてをきちんと理解できているわけではない。あくまでも、ざっくりとしか書けないが、それでも流れがなんとなく理解できるようには説明したいと思う。
著者と共同研究者は、別の研究者が提示したある数値に注目した。後に誤りだったと判明するのだが、その数値がまだ正しいと考えられている時期に著者らは、この数値が実現可能な何らかのモデル(仮説)を構築できないだろうか、と考えた。というのも、著者らが注目したその数値は、「ダークマターは対消滅によって生じたかもしれない」と示唆するものであり、仮にそれが正しいとすれば、ダークマターに関する新しい見方が可能だと考えられたからだ。
「ダークマター」に関しては、その存在の可能性が指摘されてから、「もし存在するとしたらどんなものなのか?」という研究が続けられてきた。なにせ、「目には見えず、触れられもせず、重力としか相互作用しない物質」である。かなり特異な性質だと言えるし、その候補に関しては様々な説が提案されていた。
あわせて読みたい
【研究】光の量子コンピュータの最前線。量子テレポーテーションを実現させた科学者の最先端の挑戦:『…
世界中がその開発にしのぎを削る「量子コンピューター」は、技術的制約がかなり高い。世界で初めて「量子テレポーテーション」の実験を成功させた研究者の著書『光の量子コンピューター』をベースに、量子コンピューター開発の現状を知る
しかし著者らは、「ダークマター」の候補探しに関して、研究者が無意識に排除している可能性に気づいた。それは、「ダークマターは1種類ではないかもしれない」という可能性だ。「ダークマター」の候補としては、「WIMP」「アクシオン」「ニュートリノ」などが示唆されていたが、著者らは、「これらのどれか1つを選ぶのではなく、複数のものがダークマターと関係していると考えてもいいのではないか」と発想したのだ。
これは、「通常の物質」に関する知見と照らし合わせても合理的な判断だと言える。「通常の物質」に関しては「標準モデル」と呼ばれる非常に精緻な理論が存在する。「ヒッグス粒子」の発見で最後のピースが埋まったことで完成したこの「標準モデル」では、様々な性質を持つ「素粒子」が関係して「通常の物質」が構成されている、ということが示されている。
だとすれば、「ダークマター」についても、複数の「ダークマター素粒子」が存在していると考えるのは自然な発想だろう。

あわせて読みたい
【未知】タコに「高度な脳」があるなんて初耳だ。人類とは違う進化を遂げた頭足類の「意識」とは?:『…
タコなどの頭足類は、無脊椎動物で唯一「脳」を進化させた。まったく違う進化を辿りながら「タコに心を感じる」という著者は、「タコは地球外生命体に最も近い存在」と書く。『タコの心身問題』から、腕にも脳があるタコの進化の歴史と、「意識のあり方」を知る。
そして著者らは、「ダークマター素粒子が複数存在するとしたらどうなるか?」という発想を突き詰めることで、これまで誰も想定したことのない構造物が銀河系に存在する可能性に気づき、それを「ダークディスク」と名付けた。
これが本書で詳しく説明される「DDDM理論」の骨子である。
「ダークディスク」が存在するかは検証可能であり、観測によって見つかる(あるいは、想定した場所に見つからない)かもしれない。いずれその真偽が明らかになる日が来るだろう。
では、この「DDDM理論」はどのように「恐竜絶滅」と関係するのだろうか?
あわせて読みたい
【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ
『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?
著者のリサ・ランドールは、この研究の過程において、「恐竜絶滅」との関連性など考えたことはなかった。しかしある日、「DDDM理論」の原型となるアイデアを話すためにとあるディスカッションに参加した際、その主催者から、「もしかしたらあなたの考えが、恐竜絶滅のきっかけになったかもしれない」という話を聞いた。ここで初めて「DDDM理論」と「恐竜絶滅」が結びつくのだ。
実は古生物学の世界には、まったく解決不可能だと思われていた疑問があった。それは、「生物の絶滅には一定の周期があるように観察される」というものだ。もし生物の絶滅に周期が存在するとすれば、それは彗星や小惑星の動きと関連付けるしかないと考えられてはいたのだが、しかし既存のどんなモデルと照らし合わせてみても、生物の絶滅の周期を上手く説明するものは見つからなかったという。
この疑問に関して、進むべき方向性は2つある。1つは「生物の絶滅に周期が存在するという見方が間違っており、その考え方を捨てる」であり、もう1つが、「まだ知られていない何らかの現象によって、生物の絶滅の周期が説明できる」というものだ。
あわせて読みたい
【変人】結城浩「数学ガール」から、1億円も名誉ある賞も断った天才が証明したポアンカレ予想を学ぶ
1億円の賞金が懸けられた「ポアンカレ予想」は、ペレルマンという天才数学者が解き明かしたが、1億円もフィールズ賞も断った。そんな逸話のある「ポアンカレ予想」とは一体どんな主張であり、どのように証明されたのかを結城浩『数学ガール』から学ぶ
そこに、リサ・ランドールの「DDDM理論」が登場した。著者は「絶滅」に関するこの疑問を知った上で、再度「DDDM理論」を検討し、「DDDM理論は、絶滅の周期を説明できる可能性がある」と結論づけることになる。
これが、「ダークマター」と「恐竜絶滅」を結びつける、本書の主張のざっくりした説明だ。
「絶滅」に関する意外な話
ここまでの記述で、この記事本来の趣旨は終了だが、最後に、本書で触れられていた「絶滅」に関する興味深い話を取り上げて終わろうと思う。
あわせて読みたい
【刺激】結城浩「数学ガール」で、ゲーデルの不完全性定理(不可能性の証明として有名)を学ぶ
『結城浩「数学ガール」シリーズは、数学の面白さを伝えながら、かなり高難度の話題へと展開していく一般向けの数学書です。その第3弾のテーマは、「ゲーデルの不完全性定理」。ヒルベルトという数学者の野望を打ち砕いた若き天才の理論を学びます
まずはこんな引用から。
絶滅という概念は比較的新しい。フランスの博物学者で、のちに貴族にもなったジョルジュ・キュヴィエが、完全にこの惑星から消えてしまっている種があるという証拠に気づいたのが、ようやく1800年代初めのことだ。キュヴィエ以前にも、過去の動物の骨が発見されてはいたが、発見者は決まってそれらを現存する種と結びつけようとした。もちろん当時としては、まずそう考えるのが常識だったのだろう。たしかにマンモスとマストドンとゾウは別のものだが、それほど大きく違っているわけでもないのだから、最初はそれらを混同してもおかしくないし、少なくともそれらの化石を結びつけたくなるに違いない。これを解きほぐしたのがキュヴィエであって、彼の研究により、マストドンとマンモスは現在生きているどんな動物の直系祖先でもないことが実証された。キュヴィエは引き続き、ほかの多くの絶滅種も特定した。
だが、絶滅の概念はいまでこそしっかり確立しているが、種全体が消滅して二度と戻ってこないという考えは、最初は多くの抵抗にあった。
先程、「科学の歴史は、その時代その時代における『常識』との闘い」と書いたが、「絶滅」という概念についても認められるまでに時間が掛かったのである。我々が当たり前だと感じている考え方も、長い論争を経て「常識」となったということだ。
あわせて読みたい
【驚嘆】人類はいかにして言語を獲得したか?この未解明の謎に真正面から挑む異色小説:『Ank: a mirror…
小説家の想像力は無限だ。まさか、「人類はいかに言語を獲得したか?」という仮説を小説で読めるとは。『Ank: a mirroring ape』をベースに、コミュニケーションに拠らない言語獲得の過程と、「ヒト」が「ホモ・サピエンス」しか存在しない理由を知る
そしてこのような歴史を知ることによって、さらにこのような気づきを得ることができる。それは、「現在多数の賛同を得られていない考え方であっても、未来には当たり前の常識になるかもしれない」ということだ。自分が生きている時代だけを見ていると、なかなかこのことに気づきにくい。歴史を知るということの大事さを改めて実感させられる。
またもう1つ、「絶滅」に関して興味深い記述があった。
現在、多くの科学者は、現在まさに第六の大量絶滅が進行しつつあると考えている。しかも今回の絶滅は、もともと人間が引き起こしたものなのだ。(中略)推定は確定ではないが、現在のペースではことによると平均の何百倍も速い
あわせて読みたい
【衝撃】ABC予想の証明のために生まれたIUT理論を、提唱者・望月新一の盟友が分かりやすく語る:『宇宙…
8年のチェック期間を経て雑誌に掲載された「IUT理論(宇宙際タイヒミュラー理論)」は、数学の最重要未解決問題である「ABC予想」を証明するものとして大いに話題になった。『宇宙と宇宙をつなぐ数学』『abc予想入門』をベースに、「IUT理論」「ABC予想」について学ぶ

「絶滅」という言葉は、あまり身近なものには感じられないし、自分とは関係がないものに感じられる。確かに、「メダカは絶滅危惧種だ」みたいな話を聞くこともあるが、あくまでもそれらは「一部の生物の話」だと考えてしまうし、我々がまさに今生きているこの瞬間に「絶滅」を意識することはあまりないだろう。
しかし実は、過去のどの「絶滅」と比べても、今進行中の「絶滅」は驚異的なスピードで起こっているのだそうだ。そしてそれは間違いなく我々「人類」のせいだという。
この問題について、個人にできることはなかなか多くはないかもしれないが、自分の存在が他の生物種の絶滅に大きく関わっているというのは、罪悪感を抱かせる事実だなと感じさせられる。
あわせて読みたい
【意外】思わぬ資源が枯渇。文明を支えてきた”砂”の減少と、今後我々が変えねばならぬこと:『砂と人類』
「砂が枯渇している」と聞いて信じられるだろうか?そこら中にありそうな砂だが、産業用途で使えるものは限られている。そしてそのために、砂浜の砂が世界中で盗掘されているのだ。『砂と人類』から、石油やプラスチックごみ以上に重要な環境問題を学ぶ
著:リサ・ランドール, 監修:向山信治, 翻訳:向山 信治, 翻訳:塩原 通緒
¥2,178 (2022/01/29 21:49時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
あわせて読みたい
【全作品読了済】私が読んできたノンフィクション・教養書を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が読んできたノンフィクションを様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本選びの参考にして下さい。
最後に
あわせて読みたい
【要約】福岡伸一『生物と無生物のあいだ』は、「生命とは何か」を「動的平衡」によって定義する入門書…
「生命とは何か?」という、あまりに基本的だと感じられる問いは、実はなかなか難しい。20世紀生物学は「DNAの自己複製」が本質と考えたが、「ウイルス」の発見により再考を迫られた。福岡伸一の『生物と無生物のあいだ』『動的平衡』の2著作から、「生命の本質」を知る
本書は、元々理系の人間で科学的な知識に関心がある私でもかなり高度な内容だと考えたので、「ちょっと面白そうだから読んでみよう」という感じで手を出せる作品ではないかもしれない。しかし、リサ・ランドールは難解な概念でもかなり噛み砕いて説明してくれるし(現役の科学者でこれだけ分かりやすく描写できるというのは凄い能力だと思う)、知的好奇心をバリバリと刺激してくれるのでチャレンジしてみる価値はあるだろう。
「まだ科学者の妄想の産物でしかないダークマターという物質」が、「ようやく隕石によるものと確定した恐竜絶滅」と関わっているというのも興味深い構図で、科学の奥深さを改めて実感させられる作品だった。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
次にオススメの記事
あわせて読みたい
【奇妙】大栗博司『重力とはなにか』は、相対性理論や量子力学の説明も秀逸だが、超弦理論の話が一番面白い
『重力とはなにか』(大栗博司)は、科学に馴染みの薄い人でもチャレンジできる易しい入門書だ。相対性理論や量子力学、あるいは超弦理論など、非常に難解な分野を基本的なところから平易に説明してくれるので、「科学に興味はあるけど難しいのはちょっと……」という方にこそ読んでほしい1冊
あわせて読みたい
【挑戦】相対性理論の光速度不変の原理を無視した主張『光速より速い光』は、青木薫訳だから安心だぞ
『光速より速い光』というタイトルを見て「トンデモ本」だと感じた方、安心してほしい。「光速変動理論(VSL理論)」が正しいかどうかはともかくとして、本書は実に真っ当な作品だ。「ビッグバン理論」の欠陥を「インフレーション理論」以外の理屈で補う挑戦的な仮説とは?
あわせて読みたい
【化石】聞き馴染みのない「分子生物学」を通じて、科学という学問の本質を更科功が分かりやすく伝える…
映画『ジュラシック・パーク』を観たことがある方なら、「コハクの化石に閉じ込められた蚊の血液から恐竜の遺伝子を取り出す」という設定にワクワクしたことだろう。『化石の分子生物学』とは、まさにそのような研究を指す。科学以外の分野にも威力を発揮する知見に溢れた1冊
あわせて読みたい
【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死
映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る
あわせて読みたい
【最新】「コロンブス到達以前のアメリカ大陸」をリアルに描く歴史書。我々も米国人も大いに誤解してい…
サイエンスライターである著者は、「コロンブス到着以前のアメリカはどんな世界だったか?」という問いに触れ、その答えが書かれた本がいつまで経っても出版されないので自分で執筆した。『1491 先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』には、アメリカ人も知らない歴史が満載だ
あわせて読みたい
【知的】文系にオススメの、科学・数学・哲学の入門書。高橋昌一郎の「限界シリーズ」は超絶面白い:『…
例えば「科学」だけに限ってみても、「なんでもできる」わけでは決してない。「科学」に限らず、私たちが対峙する様々な事柄には「これ以上は不可能・無理」という「限界」が必ず存在する。高橋昌一郎の「限界シリーズ」から、我々が認識しておくべき「限界」を易しく学ぶ
あわせて読みたい
【驚異】ガイア理論の提唱者が未来の地球を語る。100歳の主張とは思えない超絶刺激に満ちた内容:『ノヴ…
「地球は一種の生命体だ」という主張はかなり胡散臭い。しかし、そんな「ガイア理論」を提唱する著者は、数々の賞や学位を授与される、非常に良く知られた科学者だ。『ノヴァセン <超知能>が地球を更新する』から、AIと人類の共存に関する斬新な知見を知る
あわせて読みたい
【興奮】飲茶氏が西洋哲学を語る。難解な思想が「グラップラー刃牙成分」の追加で驚異的な面白さに:『…
名前は聞いたことはあるがカントやニーチェがどんな主張をしたのかは分からないという方は多いだろう。私も無知なまったくの初心者だが、そんな人でも超絶分かりやすく超絶面白く西洋哲学を”分かった気になれる”飲茶『史上最強の哲学入門』は、入門書として最強
あわせて読みたい
【幻想】超ひも理論って何?一般相対性理論と量子力学を繋ぐかもしれないぶっ飛んだ仮説:『大栗先生の…
『大栗先生の超弦理論入門』は最先端科学である「超弦理論」を説明する1冊だが、この記事では著者の主張の1つである「空間は幻想かもしれない」という発想を主に取り上げる。「人類史上初の『適用する次元が限定される理論』」が描像する不可思議な世界とは?
あわせて読みたい
【快挙】「暗黒の天体」ブラックホールはなぜ直接観測できたのか?国際プロジェクトの舞台裏:『アイン…
「世界中に存在する電波望遠鏡を同期させてブラックホールを撮影する」という壮大なEHTプロジェクトの裏側を記した『アインシュタインの影』から、ブラックホール撮影の困難さや、「ノーベル賞」が絡む巨大プロジェクトにおける泥臭い人間ドラマを知る
あわせて読みたい
【貢献】有名な科学者は、どんな派手な失敗をしてきたか?失敗が失敗でなかったアインシュタインも登場…
どれほど偉大な科学者であっても失敗を避けることはできないが、「単なる失敗」で終わることはない。誤った考え方や主張が、プラスの効果をもたらすこともあるのだ。『偉大なる失敗』から、天才科学者の「失敗」と、その意外な「貢献」を知る
あわせて読みたい
【平易】一般相対性理論を簡単に知りたい方へ。ブラックホール・膨張宇宙・重力波と盛りだくさんの1冊:…
現役の研究者が執筆した『ブラックホール・膨張宇宙・重力波』は、アインシュタインが導き出した一般相対性理論が関わる3つのテーマについて、初心者にも分かりやすく伝える内容になっている。歴史的背景も含めて科学的知見を知りたい方にオススメの1冊
あわせて読みたい
【到達】「ヒッグス粒子の発見」はなぜ大ニュースなのか?素粒子物理学の「標準模型」を易しく説明する…
「ヒッグス粒子の発見」はメディアでも大きく取り上げられたが、これが何故重要なのかを説明できる人はそう多くはないだろう。『強い力と弱い力 ヒッグス粒子が宇宙にかけた魔法を解く』をベースに、謎めいた「弱い力」を説明する「自発的対称性の破れ」を学ぶ
あわせて読みたい
【始まり】宇宙ができる前が「無」なら何故「世界」が生まれた?「ビッグバンの前」は何が有った?:『…
「宇宙がビッグバンから生まれた」ことはよく知られているだろうが、では、「宇宙ができる前はどうなっていたのか」を知っているだろうか? 実は「宇宙は”無”から誕生した」と考えられているのだ。『宇宙が始まる前には何があったのか?』をベースに、ビッグバンが起こる前の「空間も時間も物理法則も存在しない無」について学ぶ
あわせて読みたい
【嫉妬?】ヒッグス粒子はいかに発見されたか?そして科学の”発見”はどう評価されるべきか?:『ヒッグ…
科学研究はもはや個人単位では行えず、大規模な「ビッグサイエンス」としてしか成立しなくなっている。そんな中で、科学研究の成果がどう評価されるべきかなどについて、「ヒッグス粒子」発見の舞台裏を追った『ヒッグス 宇宙の最果ての粒子』をベースに書く
あわせて読みたい
【究極】リサ・ランドールが「重力が超弱い理由」を解説する、超刺激的なひも理論の仮説:『ワープする…
現役の研究者であるリサ・ランドールが、自身の仮説を一般向けに分かりやすく説明する『ワープする宇宙』。一般相対性理論・量子力学の知識を深く記述しつつ「重力が超弱い理由」を説明する、ひも理論から導かれる「ワープする余剰次元」について解説する
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
宇宙・ビッグバン・ブラック ホール・相対性理論【本・映画の感想】 | ルシルナ
科学全般に関心を持っていますが、その中でも宇宙に関する本はたくさん読んできました。ビッグバンがいかに起こったか、ブラックホールはどうやって直接観測されたか、宇宙…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…















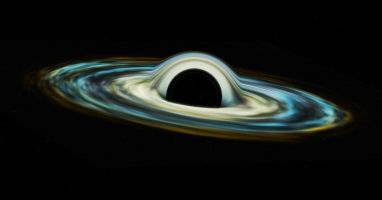




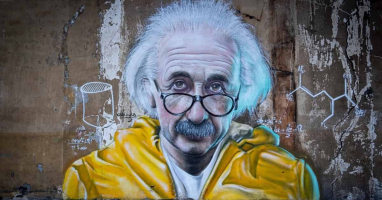
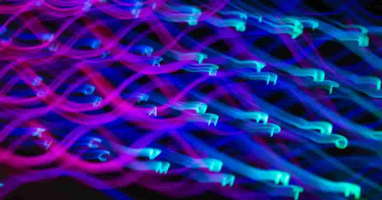
























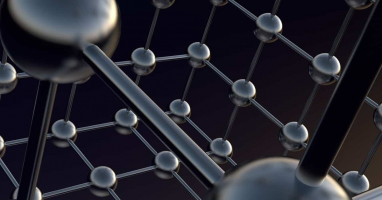












コメント