目次
はじめに
この記事で取り上げる映画
「東京大空襲 CARPET BOMBING of Tokyo」公式HP
VIDEO
この映画をガイドにしながら記事を書いていきます
今どこで観れるのか?
公式HPの劇場情報 をご覧ください
この記事の3つの要点
実際に空襲に遭い、命からがら逃げ延びた者たちの証言は、あまりにも具体的で生々しく、圧倒されてしまう 「戦闘機から直接機銃掃射を受けた」「戦争孤児として辛酸を嘗めた」など、「空襲」だけではない様々な話についても語られる 「アメリカを憎んでいますか?」という問いに対する多様な返答もまた印象的だった 原爆投下と比べ日本でもあまり知られていない空襲の話を、まずは日本人の私たちが知って伝えていくべきなのだろうと思う
自己紹介記事
あわせて読みたい
ルシルナの入り口的記事をまとめました(プロフィールやオススメの記事)
当ブログ「ルシルナ」では、本と映画の感想を書いています。そしてこの記事では、「管理者・犀川後藤のプロフィール」や「オススメの本・映画のまとめ記事」、あるいは「オススメ記事の紹介」などについてまとめました。ブログ内を周遊する参考にして下さい。
あわせて読みたい
【全作品読了・視聴済】私が「読んできた本」「観てきた映画」を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が『読んできた本』『観てきた映画』を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非本・映画選びの参考にして下さい。
どんな人間がこの記事を書いているのかは、上の自己紹介記事をご覧ください
記事中の引用は、映画館で取ったメモを参考にしているので、正確なものではありません
映画『東京大空襲 CARPET BOMBING of Tokyo』は、悲惨な大空襲を体験した者たちへのインタビュー集であり、そのあまりに壮絶な状況に驚かされる
これは実に興味深いドキュメンタリー映画 だった。
あわせて読みたい
【勇敢】ユダヤ人を救った杉原千畝を描く映画。日本政府の方針に反しながら信念を貫いた男の生き様
日本政府の方針に逆らってまでユダヤ人のためにビザを発給し続けた外交官を描く映画『杉原千畝』。日本を良くしたいと考えてモスクワを夢見た青年は、何故キャリアを捨てる覚悟で「命のビザ」を発給したのか。困難な状況を前に、いかに決断するかを考えさせられる
本作『東京大空襲 CARPET BOMBING of Tokyo』は基本的に、「第二次世界大戦中に行われた東京への大空襲を経験した者たちへのインタビュー 」で構成されている。その合間合間に昔の映像が挿入されたり、証言者たちによる「証言する」以外の行動が映し出されたりもする のだが、私の体感では8割以上がインタビューで構成されていた ように思う。
そしてそのインタビューで私がまず驚かされたのが、話をする人たちが実に明晰に語っていた ことだ。東京大空襲から既に80年が経っている 。また、証言者たちの「空襲当時の年齢」は様々 だったが、大体15歳以下 だった(1人だけ、当時20歳という方がいたが)。と考えると、本作に出演している人たちの現在の(映画公開時の)年齢は概ね、85歳から95歳ぐらい だろう(ただし、インタビューを行ったのは少し前だと思うので、撮影時の年齢はもう少し若かっただろう とは思う)。かなり高齢なので、昔のことを覚えていなかったり、あるいは覚えていてもはっきりとは喋れなかったりしてもおかしくない はずだ。
しかし本作に登場するほとんどの人が、とにかく明晰に、そしてはっきりと当時のことを語っていた のである。これにはかなり驚かされた 。観ながら、「今の若い人の方が要領を得ない説明をしちゃうんじゃないか」とさえ感じた ほどである。必要な情報を過不足なく織り込みながら当時の状況を具体的に詳細に語る姿 にとにかくビックリさせられたし、そのことがまずとても印象的 だった。
あわせて読みたい
【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞
映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である
空襲を体験、あるいは見聞きした者たちによる証言がとにかく凄まじい
本作では主に、「東京大空襲」「山手空襲」「八王子空襲」の3つに焦点が当てられている 。そしてこの記事では、この3つを特に区別せずにあれこれ書いていこう と思う(映画を観ながら取ったメモを元にして感想を書いており、どの証言がどの空襲のものなのかまではなかなかメモし切れなかった)。本作では、これらの空襲を直接的に経験した人(つまり、実際に避難をし、その過程で多くの死体を目にするなどした人)や、空襲の炎や様子を遠くから見ていた人たちの話がまとめられている 。
中でも私は、浅草周辺が壊滅的な被害を受けたという「東京大空襲」の話が特に印象に残った 。というのも、まさに私が今住んでいるのが浅草 なのである。証言の中にはいくつか小学校の名前も出てくる のだが、その内の1つは、私が普段国政選挙などの投票の際に行く場所 だ。超近所の話 である。証言者たちの話も、何となくではあるがどの辺りのことを言っているのか分かる 感じがあり(浅草生まれというわけではないのでざっくりとしか分からないが)、そういう意味でも実に興味深く感じられた 。
またこの「東京大空襲」に関しては、「雷門の前で外国人観光客に『東京大空襲を知っているか?』と質問する様子」も映し出される 。そして多くの人が、「広島や長崎のことは知っているけど、浅草がそんな状況だったなんて知らなかった 」と答えていた。「東京大空襲」では、2時間半で10万人もの人が亡くなった とされている。そして当時撮られた被害写真を目にした外国人は、「こんなことが起こっていたなんて」とその驚きを口にしていた 。
あわせて読みたい
【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…
原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す
さて当然ではあるが、証言者の話の中ではやはり、実際に空襲に直面し何とか逃げ延びた人たちの話が興味深い 。ちょっとびっくりしたのが、当時出されていたある「お触れ」の話 である。なんと、「もしも自宅に火がついたら、それを消すまで家族は避難するな」と厳命されていた というのだ。火事の延焼を防ぐため ということなのだろうが、平時では考えられない指示 だろう。また、戦争が始まって以降、多くの家庭では「防空壕」を作った そうなのだが、「実際にはまるで役に立たなかった」と語る人が多かった のも印象的だった。ただ地面に穴を堀っただけの代物 であり、そりゃあまともに機能するはずもない だろう。というか、空襲の際にそうした簡易の防空壕に逃げ込み、窒息死、あるいは高温による熱死などで命を落とす人も多かった という。あまりにも悲惨すぎる話 だなと思う。
そしてさらに印象的だったのが浅草周辺を流れる「隅田川」の話 である。多くの人が「隅田川は死体でいっぱいだった 」と話していたのだ。以前何かで広島の原爆の話を見聞きした際、「熱さから逃れるために川に飛び込んだ人たちが折り重なるように亡くなっていた」みたいな証言に触れた気がする のだが、それと同じような状況だったそうである。ある証言者は確か、「綺麗な身体の死体が川に整列するように並んでいた 」みたいなことを言っていたように思う。
空襲では多くの人が命を落とし、当然、その最期も様々だった わけだが、ある証言者は自分が見た光景として、「マンホールの中に入ろうとしたら、マネキンのような死体があった 」みたいな話をしていた。要するに、髪も服も燃えてしまった ということだ。どういう状況でマンホールまで辿り着いたのかは推して知るべしだが、その凄まじさが理解できる だろう。
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
さて、当然と言えば当然の話ではあるが、空襲が収まった後はおびただしい数の死体をどうにかしなければならない 。そしてこの点に関しても様々な証言 があった。空襲から半年ほど経ってから出現した死体を見に行った という証言者は、「とんでもない臭いで、それから3日間ぐらいご飯が食べられなかった 」と話す。また、「トラックに死体を詰め込んでトタンを載せ、それを別の場所に積み上げていた 」のを目撃したという人物は、「川の死体は、底にあったものほど凄まじい臭いだった 」と語っていた。
そんな中、個人的に最も衝撃的だったのが「警察官が死体の内蔵を切り取っていた」という証言 だ。もちろん、腐敗を避けるため である。「東京大空襲」だけで10万人も亡くなったのだから、火葬場も埋葬場所も当然足りない 。「東京大空襲」が起こったのは3月10日 。当時の気候がどんな感じだったのかは分からないものの、徐々に暖かくなっていく頃合い であることは確かだろう。だから仕方ない処置だったことはもちろん理解できる のだが、それにしても凄まじい状況 だなと思う。
その凄まじさについては、こんな字幕も表示されていた 気がする(「気がする」については後で説明しよう)。
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『1917』は、ワンカット風の凄まじい撮影手法が「戦場の壮絶な重圧」を見事に体感させる
映画『1917 命をかけた伝令』は、「全編ワンカット風」という凄まじい撮影手法で注目されたが、私は、その撮影手法が「戦場における緊迫感」を見事に増幅させているという点に驚かされた。「物語の中身」と「撮影手法」が素晴らしく合致したとんでもない作品だ
「広島・長崎の原爆投下」と「東京大空襲」は、過去の戦争の事象においても最も酷いものに数えられる。
本作では時々、書籍や報告書などからの「長文の引用」が表示された 。上述の文章は、その内の1つである。ただ本作では、表示される文字があまりにも小さく、まだそこまで目が悪いわけではない私でも全然見えなかった 。客席にはお年寄りも多かったので、かなりの人がほとんど表示内容を理解できなかったんじゃないか と思う。配信で観るならあのサイズでも問題ないだろうが、劇場で観るにはちょっと無理がある大きさ だった気がする。
まあそんなわけで、先の引用もどこまで正確か分からない が、私の記憶では確か、アメリカかどこかの報告書の文章 として紹介されていたものだったように思う。表示された文章以上に詳しい説明はなかった はずだが、恐らく「過去の戦争の(民間人が多数亡くなった)事象」という意味ではないか と私は受け取った。もちろんホロコーストのように、さらに多くの民間人の命が失われた事例 もある。しかし、「原爆」と「空襲」は「無差別」 であり、そういう要素も含めて考えれば、その「悲惨さ」は突出している と言えるのかもしれない。
我々が生きている日本はまさにそのような「世界レベルの『悲惨さ』」を体験した のだと、現代を生きる私たちも改めて認識する必要がある だろうと思う。
あわせて読みたい
【驚異】信念を貫く勇敢さを、「銃を持たずに戦場に立つ」という形で示した実在の兵士の凄まじさ:映画…
第二次世界大戦で最も過酷な戦場の1つと言われた「前田高地(ハクソー・リッジ)」を、銃を持たずに駆け回り信じがたい功績を残した衛生兵がいた。実在の人物をモデルにした映画『ハクソー・リッジ』から、「戦争の悲惨さ」だけでなく、「信念を貫くことの大事さ」を学ぶ
空襲と絡めて語られていた「機銃掃射」「戦争孤児」などの話
証言者が語る話には、何となく知っていたこともそれなりにはあった が、もちろん知らないことの方が多かった 。そしてその中でも「えっ?」と感じたのが「機銃掃射を経験した」という話 である。驚くべきことに、「戦闘機から直接狙い撃ちされた 」というのだ。
さて、その話をする前に、そもそも「空襲」がどのように行われたか について触れておこう。夜間に行われたのだろう(そういう基本的な知識も私にはなかったりする)、まずは照明弾を落とす飛行機が来る のだそうだ。そしてそれから、焼夷弾を落とすB29が飛んでくる 。B29はとにかく爆音が凄まじく、「それ以外の音が一切存在しない」みたいな状況になる のだそうだ。しかしそんな爆音を響かせるB29は、かなりの上空から焼夷弾を落とす 。もちろん、地上での爆発の余波を食らわないため だろう。ある人物は、「B29が焼夷弾を落としたのを目にしてから、それが実際に地上に落ちてくるまで、かなり時間が掛かった 」みたいなことを言っていた。ちなみにだがその人物は、焼夷弾が落ちてくる様子を見た母親が「花火みたい」と口にしたのを聞いて、「なるほど、あれが花火なのかと思った」という話 もしていた。戦争が始まってからは、花火を打ち上げる機会もなくなっていたので知らなかった のだそうだ。
で、機銃掃射 である。機銃掃射の場合は空襲の時とは全然違い、グラマンという飛行機が地上近くまで降下してきて、そこから銃をぶっ放す のだそうだ。ある人物は友人から「グラマンに乗った兵士の顔を見た」という話を聞いた という。また別の人物は、「(機銃掃射による)空の薬莢がトタン屋根のニワトリ小屋に落ちてもの凄い音がしたし、そのせいでしばらくニワトリが卵を産まなくなってしまった 」みたいな話をしていた。どちらも、その状況が容易に浮かぶ、リアリティのある光景 ではないかと思う。
あわせて読みたい
【感想】映画『野火』は、戦争の”虚しさ”をリアルに映し出す、後世に受け継がれるべき作品だ
「戦争の悲惨さ」は様々な形で描かれ、受け継がれてきたが、「戦争の虚しさ」を知る機会はなかなかない。映画『野火』は、第二次世界大戦中のフィリピンを舞台に、「敵が存在しない戦場で”人間の形”を保つ困難さ」を描き出す、「虚しさ」だけで構成された作品だ
空襲だってもちろん最悪だが、しかし、「低空飛行する飛行機から銃で直接狙われる」というのはまた全然違った恐ろしさがある だろう。米軍は当然、銃を向けている相手が民間人だと理解していたはず だし、そう考えると余計に怖い なと思う。現代では「戦争のルール」がある程度明文化されているはず で、だから「民間人が直接的に攻撃対象にされる」という状況は”理論上は”あり得ない 。もちろん、実際には「民間人が命を落とすことが分かっていて行われる攻撃」も当然ある とは思うが、しかしそれでも、「民間人が機銃掃射で狙われる」なんて状況はさすがに起こらない のではないだろうか。そういう意味でも、かなり特異的な状況 だったと言っていいように思う。
また本作では他にも、「空襲」ではなく「戦争」全般に関係する話として「戦争孤児」についても取り上げられていた 。
とその前に、本作『東京大空襲 CARPET BOMBING of Tokyo』の制作に関する話 を少し書いておこうと思う(その辺りのことが作中で少し触れられていた)。そもそもだが、「空襲を経験した人」を探し出すだけでも相当苦労した ようだ。序盤の方で、「探し始めてから2ヶ月は、誰も見つけ出せなかった」みたいな字幕が表示された ぐらいである。制作陣はまず、かつて出版された「空襲についての証言集」みたいな本に載っている名前・住所などから手当たり次第に辿っていった のだが、既に亡くなっている方が多かった という。「空襲について証言してくれる人を探す」という点がまずかなりの困難だった ようだ。
あわせて読みたい
【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…
『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る
そしてその上で、さらに困難を極めたのが「戦争孤児の捜索」 だったという。本作では結局空襲については15~20人ぐらいの人が証言していた と思うが、戦争孤児として登場したのは2人だけ だった。もしかしたら「見つけたが映画出演は断られた」みたいなパターンもあったかもしれない が、そうだとしてもかなり少ない人数だったことは確かなんじゃないか と思う。
制作陣は「東京養育院」という、戦後に戦争孤児を受け入れていた施設から捜索を始めた のだが、まったくダメ だったそうだ。結局どうやって見つけたのかはよく分からなかったが、本作には「母親が戦争孤児を受け入れる施設を運営していた」という空襲経験者も出演していた ので、そういう方面から辿っていったのかもしれない 。
戦争孤児になってしまった背景 には色々な状況があったと思うが、空襲の証言者の方からは「子どもだけ疎開させる」という話が出てきた (本作に登場した2人の戦争孤児は恐らく違う状況だった と思うのだが)。本作には「空襲の前日に疎開先から戻ってきた」という凄まじくタイミングの悪い女性 が出演していたのだが、彼女は「子どもだけ疎開させたって、親が死んじゃったらどうするの?」みたいに言っていた と思う。まあ確かにその通り である。親の「せめて子どもだけは生きていてほしい」みたいな気持ちも当然理解できる が、現実問題として「戦中戦後に子どもだけで生き延びる」というのは相当な困難 だと何となく想像できるだろう。
あわせて読みたい
【歴史】『大地の子』を凌駕する中国残留孤児の現実。中国から奇跡的に”帰国”した父を城戸久枝が描く:…
文化大革命の最中、国交が成立していなかった中国から自力で帰国した中国残留孤児がいた。その娘である城戸久枝が著した『あの戦争から遠く離れて』は、父の特異な体験を起点に「中国残留孤児」の問題に分け入り、歴史の大きなうねりを個人史として体感させてくれる作品だ
本作に登場した2人の戦争孤児は、「最初は縁戚に引き取られた」と話していた 。しかしどちらも、虐待されたり「死んだ方がマシ」だと感じられたりするような環境だった らしく、そのまま浮浪者にならざるを得なかった そうだ。
さて本作には、そんな「浮浪者」に関する証言 も存在した。ある空襲経験者が戦後、高校までの通学路で経験したエピソード である。彼は通学の際、上野駅の地下通路(恐らく現在の、銀座線から地上に出る坂道の通路のことだと思う)を通っていた という。地上よりも暖かかったからだろう、そこには多くの浮浪者がいた そうだ。そして彼は、特に寒くなる時期に、その通路の両脇の壁に白墨で「◯」が書かれているのをよく目にした という。誰に向けてのサインだったのかは分からないと言っていたと思うが、この「◯」はどうやら「そこにあった死体を回収した」という意味だった のだそうだ。だから彼は寒くなると、「通路に『◯』が書かれているかもしれないなぁ」と思い憂鬱に感じていた と話していた。実に生々しい証言 だなと思う。
また当時は、「狩込」と呼ばれる「浮浪者を施設に無理やり収容する」みたいな対策がよく取られていた という。私は最初、「路上生活よりも施設の方がいいんじゃないか?」と思っていたので「狩込」の問題点が理解できなかった のだが、実態はなかなか酷いもの だったそうだ。先に紹介した「母親が戦争孤児を引き取る活動をしていた女性」は「友人が東水園に連れて行かれた」みたいな話をしていた のだが、戦争孤児を収容していたこの東水園はかなり酷い施設だった という。
あわせて読みたい
【現実】生きる気力が持てない世の中で”働く”だけが人生か?「踊るホームレスたち」の物語:映画『ダン…
「ホームレスは怠けている」という見方は誤りだと思うし、「働かないことが悪」だとも私には思えない。振付師・アオキ裕キ主催のホームレスのダンスチームを追う映画『ダンシングホームレス』から、社会のレールを外れても許容される社会の在り方を希求する
東水園は「人工島に作られた収容施設 」であり、「戦争孤児を島に隔離すれば逃げないだろう」みたいな発想で作られた ようである。しかし、東水園は子どもたちに対してかなり酷い扱いをしていた らしく、その環境に耐えかねて泳いで逃亡を図る者もいた のだそうだ。そのまま水死してしまう人もいた ようだが、先述の「友人」はどうにか泳いで逃げ切れた という。女性は、「当時は東水園の酷さを知らなかった 」みたいなことを言っていたので、友人が逃げ出してきたことでようやく状況を理解したのだろう 。本当に酷い話 だなと思う。
というわけで、証言者たちが語る話を色々と紹介してきたが、もちろんまだまだ興味深い話は色々と出てきた 。一部箇条書きにしてみようと思う。
警視庁でカメラマンとして働いていた父親が東京大空襲の被害の様子を写真に撮り 、その後、GHQに接収されないようにフィルムを庭に埋めた (作中では、そのフィルムを印刷した実際の写真も映し出される)別の場所で空襲があったという話を聞いてはいたが、まさか自分のところも狙われるなんて想像もしていなかった それまで日本は戦争に負けたことがなく、それゆえ「戦争で死ぬこと」は「名誉」だった 。だから「死ぬこと」を怖いと感じたことはない 兄が特攻隊に入れられた のだが、結局飛行機が足りなくて生きて帰って来られた 。しかし、恐怖心を取り除くために渡されていたモルヒネの中毒になってしまい、戦後相当苦しんだ このように様々な話が語られる のだ。
あわせて読みたい
【解説】映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、凄まじい臨場感で内戦を描き、我々を警告する(…
映画『シビル・ウォー』は、「アメリカで勃発した内戦が長期化し、既に日常になってしまっている」という現実を圧倒的な臨場感で描き出す作品だ。戦争を伝える報道カメラマンを主人公に据え、「戦争そのもの」よりも「誰にどう戦争を伝えるか」に焦点を当てる本作は、様々な葛藤を抱きながら最前線を目指す者たちを切り取っていく
また本作には、恐らく証言者全員に同じことを聞いたのだろう、「アメリカを憎んでいますか?」という質問に対する返答がまとめられている箇所 もあった。この返答もまた、実に興味深い 。
「意外」という感想で間違っていないと思う のだが、ほとんどの証言者が「アメリカを憎んではいない」と言っていた 。もちろんここには様々なグラデーション があり、簡単にはまとめられないので、いくつか具体的な証言 を紹介しておくことにしよう。
「アメリカ」という国家のことはともかく、「アメリカ人」のことは嫌いになれない 「アメリカ」のことは別に嫌いではないが、ただ「アメリカに行く」というのはどうにも抵抗がある 「アメリカ」のことはまったく憎んでいません。「戦争」は悪いと思っていますけどね
あわせて読みたい
【衝撃】ウクライナでのホロコーストを描く映画『バビ・ヤール』は、集めた素材映像が凄まじすぎる
ソ連生まれウクライナ育ちの映画監督セルゲイ・ロズニツァが、「過去映像」を繋ぎ合わせる形で作り上げた映画『バビ・ヤール』は、「単一のホロコーストで最大の犠牲者を出した」として知られる「バビ・ヤール大虐殺」を描き出す。ウクライナ市民も加担した、そのあまりに悲惨な歴史の真実とは?
どれも「なるほど」と感じる返答 だし、このような感想はきっと、戦後の長い時間の中でも色々変遷があったのではないか とも思う。今後変わることだってあるだろう 。それで全然いいし、他人がとやかく評価するようなことでもない と思う。
さてその一方で、戦争孤児の女性はまったく違う感覚を持っていて、その際に話していたエピソードも実にインパクトがあった 。彼女は「アメリカは嫌い」とはっきり口にする のだが、自分のその気持ちの強さを伝えるために「戦後にアメリカ兵が配ったチョコレート」の話をしていた のだ。
戦争孤児だった彼女は当然常に空腹で、アメリカ兵がばら撒いて地面に落ちていたチョコレートを拾って口に入れたことがある という。しかしやはり、どうしても「悔しい」という気持ちを抑えることが出来ず、口からチョコレートを吐き出してそのまま踏んづけた というのである。絶望的な空腹を抱えていたはずなのに、そんな生理的な欲求を押さえつけるほどにアメリカへの憎しみの方が強かった というわけだ。それぐらい苦労させられた ということなのだろう。個人的には「憎しみは何も生まない」と思っている が、しかしそれは、「平和な人生だったからこそ言えること 」だとも理解している。どうしたって捨てきれない憎しみを抱えながら生きていくことはかなり大変だと思う のだが、しかしそういう生き方もまた許容されるべき だろう。
そんなことを色々と考えさせられる作品 だった。
あわせて読みたい
【狂気】ISISから孫を取り戻せ!映画『”敵”の子どもたち』が描くシリアの凄絶な現実
映画『”敵”の子どもたち』では、私がまったく知らなかった凄まじい現実が描かれる。イスラム過激派「ISIS」に望んで参加した女性の子ども7人を、シリアから救出するために奮闘する祖父パトリシオの物語であり、その最大の障壁がなんと自国のスウェーデン政府なのだる。目眩がするような、イカれた現実がここにある
あわせて読みたい
【全作品視聴済】私が観てきたドキュメンタリー映画を色んな切り口で分類しました
この記事では、「今まで私が観てきたドキュメンタリー映画を様々に分類した記事」を一覧にしてまとめました。私が面白いと感じた作品だけをリストアップしていますので、是非映画選びの参考にして下さい。
最後に
前述した通り、インタビューを行ったのがいつなのかは分からない が、証言者たちの年齢を考えると、本作『東京大空襲 CARPET BOMBING of Tokyo』に収録されたものが「実際に体験した人の最後の証言」になる可能性も十分にある だろう。そもそも貴重な証言 なのだが、そういう観点からもその希少さが理解できる のではないかと思う。
また本作は、「国境なき医師団」の人が登場 したり、ウクライナ侵攻の映像が使われたり と、「現代の戦争」との繋がりを感じさせる構成 にもなっていた。私たちは戦争を経験していないからこそ、再び戦争を起こさないようにその歴史を知るべきだと思うし、本作の証言はまさにその一助となる だろう。
あわせて読みたい
【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る
TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す
原爆投下と比べると、世界にもそして日本でもあまり知られていない「東京大空襲」の実態 。まずは私たち日本人が知り、そして伝え、残していかなければならない だろう。色々と考えさせられる作品 だった。
あわせて読みたい
Kindle本出版しました!『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を…
Kindleで本を出版しました。タイトルは、『天才・アインシュタインの生涯・功績をベースに、簡単過ぎない面白科学雑学を分かりやすく書いた本:相対性理論も宇宙論も量子論も』です。科学や科学者に関する、文系の人でも読んでもらえる作品に仕上げました。そんな自著について紹介をしています。
次におすすめの記事
あわせて読みたい
【煽動】プロパガンダの天才ゲッベルスがいかにヒトラーやナチスを”演出”したのかを描く映画:『ゲッベ…
映画『ゲッベルス ヒトラーをプロデュースした男』では、ナチスドイツで宣伝大臣を担当したヨーゼフ・ゲッベルスに焦点が当てられる。「プロパガンダの天才」と呼ばれた彼は、いかにして国民の感情を操作したのか。「現代の扇動家」に騙されないためにも、そんな彼の数奇な人生や実像を理解しておいた方がいいのではないかと思う
あわせて読みたい
【平和】巣鴨プリズン収監のBC級戦犯だった冬至堅太郎の貴重な記録から知られざる歴史を紐解く映画:『…
映画『巣鴨日記 あるBC級戦犯の生涯』は、一般的にはまったく詳しいことが知られていないという「BC級戦犯」に関するドキュメンタリー映画である。巣鴨プリズンに収監された冬至堅太郎がつけていた日記、そして横浜軍事法廷で行われた彼の裁判の記録。これらを基に知られざる戦後史が明らかにされていく
あわせて読みたい
【信念】映画『太陽の運命』は、2人の知事、大田昌秀・翁長雄志から沖縄の基地問題の歴史を追う(監督:…
映画『太陽(ティダ)の運命』は、米軍基地問題に翻弄され続けた沖縄の歴史を、大田昌秀・翁長雄志という2人の知事に焦点を当てることで浮き彫りにしていくドキュメンタリー映画である。「日本一難しい問題を背負わされている」という沖縄県知事の苦悩と、「2人の間にあった様々な因縁」がないまぜになった数奇な“運命”の物語
あわせて読みたい
【信念】アフガニスタンに中村哲あり。映画『荒野に希望の灯をともす』が描く規格外の功績、生き方
映画『荒野に希望の灯をともす』は、アフガニスタンの支援に生涯を捧げ、個人で実現するなど不可能だと思われた用水路建設によって砂漠を緑地化してしまった中村哲を追うドキュメンタリー映画だ。2019年に凶弾に倒れるまで最前線で人々を先導し続けてきたその圧倒的な存在感に、「彼なき世界で何をすべきか」と考えさせられる
あわせて読みたい
【人権】チリ女性の怒り爆発!家父長制と腐敗政治への大規模な市民デモを映し出すドキュメンタリー:映…
「第2のチリ革命」とも呼ばれる2019年の市民デモを映し出すドキュメンタリー映画『私の想う国』は、家父長制と腐敗政治を背景にかなり厳しい状況に置かれている女性たちの怒りに焦点が当てられる。そのデモがきっかけとなったチリの変化も興味深いが、やはり「楽しそうにデモをやるなぁ」という部分にも惹きつけられた
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『ソウルの春』は、軍部が反乱を起こした衝撃の実話「粛清クーデター」の真相を描く(…
映画『ソウルの春』は、「これが実話!?」と感じるほど信じがたい史実が描かれる作品だ。韓国が軍事政権下にあったことは当然知っていたが、まさかこんな感じだったとは。「絶対的な正義 VS 絶対的な悪」みたいな展開で、「絶対にこうなるはず!」と思い込んでいたラストにならなかったことも、個人的には衝撃的すぎた
あわせて読みたい
【友情】映画『ノー・アザー・ランド』が映し出す酷すぎる現実。イスラエル軍が住居を壊す様は衝撃だ
イスラエルのヨルダン川西岸地区内の集落マサーフェル・ヤッタを舞台にしたドキュメンタリー映画『ノー・アザー・ランド』では、「昔からその場所に住み続けているパレスチナ人の住居をイスラエル軍が強制的に破壊する」という信じがたい暴挙が映し出される。そんな酷い現状に、立場を越えた友情で立ち向かう様を捉えた作品だ
あわせて読みたい
【父親】パキスタン本国では上映禁止の映画『ジョイランド』は、古い価値観に翻弄される家族を描く
映画『ジョイランド』は、本国パキスタンで一時上映禁止とされた作品だが、私たち日本人からすれば「どうして?」と感じるような内容だと思う。「(旧弊な)家族観を否定している」と受け取られたからだろうが、それにしたってやはり理不尽だ。そしてそんな「家族のややこしさ」には、現代日本を生きる我々も共感できるに違いない
あわせて読みたい
【現実】「食」が危ない!映画『フード・インク ポスト・コロナ』が描く、大企業が操る食べ物の罠
映画『フード・インク ポスト・コロナ』は、主にアメリカの事例を取り上げながら、「私たちが直面している『食』はかなり危険な状態にある」と警告する作品だ。「アメリカ人の摂取カロリーの58%を占める」と言われる「超加工食品」の研究はダイエット的な意味でも興味深いし、寡占企業による様々な弊害は私たちにも関係してくるだろう
あわせて読みたい
【解説】映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、凄まじい臨場感で内戦を描き、我々を警告する(…
映画『シビル・ウォー』は、「アメリカで勃発した内戦が長期化し、既に日常になってしまっている」という現実を圧倒的な臨場感で描き出す作品だ。戦争を伝える報道カメラマンを主人公に据え、「戦争そのもの」よりも「誰にどう戦争を伝えるか」に焦点を当てる本作は、様々な葛藤を抱きながら最前線を目指す者たちを切り取っていく
あわせて読みたい
【思想】川口大三郎は何故、早稲田を牛耳る革マル派に殺された?映画『ゲバルトの杜』が映す真実
映画『ゲバルトの杜』は、「『革マル派』という左翼の集団に牛耳られた早稲田大学内で、何の罪もない大学生・川口大三郎がリンチの末に殺された」という衝撃的な事件を、当時を知る様々な証言者の話と、鴻上尚史演出による劇映画パートによって炙り出すドキュメンタリー映画だ。同じ国で起こった出来事とは思えないほど狂気的で驚かされた
あわせて読みたい
【絶望】知られざる「国による嘘」!映画『蟻の兵隊』(池谷薫)が映し出す終戦直後の日本の欺瞞
映画『蟻の兵隊』は、「1945年8月15日の終戦以降も上官の命令で中国に残らされ、中国の内戦を闘った残留日本軍部隊」の1人である奥村和一を追うドキュメンタリー映画だ。「自らの意思で残った」と判断された彼らは、国からの戦後補償を受けられていない。そんな凄まじい現実と、奥村和一の驚くべき「誠実さ」が描かれる作品である
あわせて読みたい
【正義?】FBIが警告した映画『HOW TO BLOW UP』は環境活動家の実力行使をリアルに描き出す
映画『HOW TO BLOW UP』は、「テロを助長する」としてFBIが警告を発したことでも話題になったが、最後まで観てみると、エンタメ作品として実に見事で、とにかく脚本が優れた作品だった。「環境アクティビストが、石油パイプラインを爆破する」というシンプルな物語が、見事な脚本・演出によって魅力的に仕上がっている
あわせて読みたい
【SDGs】パリコレデザイナー中里唯馬がファッション界の大量生産・大量消費マインド脱却に挑む映画:『…
映画『燃えるドレスを紡いで』は、世界的ファッションデザイナーである中里唯馬が、「服の墓場」と言うべきナイロビの現状を踏まえ、「もう服を作るのは止めましょう」というメッセージをパリコレの場から発信するまでを映し出すドキュメンタリー映画である。個人レベルで社会を変革しようとする凄まじい行動力と才能に圧倒させられた
あわせて読みたい
【正義】ナン・ゴールディンの”覚悟”を映し出す映画『美と殺戮のすべて』が描く衝撃の薬害事件
映画『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの凄まじい闘いが映し出されるドキュメンタリー映画である。ターゲットとなるのは、美術界にその名を轟かすサックラー家。なんと、彼らが創業した製薬会社で製造された処方薬によって、アメリカでは既に50万人が死亡しているのだ。そんな異次元の薬害事件が扱われる驚くべき作品
あわせて読みたい
【実話】映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』が描く、白人警官による黒人射殺事件
映画『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』は、2011年に起こった実際の事件を元にした作品である。何の罪もない黒人男性が、白人警官に射殺されてしまったのだ。5時22分から始まる状況をほぼリアルタイムで描き切る83分間の物語には、役者の凄まじい演技も含め、圧倒されてしまった
あわせて読みたい
【挑戦】映画『燃えあがる女性記者たち』が描く、インドカースト最下位・ダリットの女性による報道
映画『燃えあがる女性記者たち』は、インドで「カースト外の不可触民」として扱われるダリットの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」を取り上げる。自身の境遇に抗って、辛い状況にいる人の声を届けたり権力者を糾弾したりする彼女たちの奮闘ぶりが、インドの民主主義を変革させるかもしれない
あわせて読みたい
【狂気】ISISから孫を取り戻せ!映画『”敵”の子どもたち』が描くシリアの凄絶な現実
映画『”敵”の子どもたち』では、私がまったく知らなかった凄まじい現実が描かれる。イスラム過激派「ISIS」に望んで参加した女性の子ども7人を、シリアから救出するために奮闘する祖父パトリシオの物語であり、その最大の障壁がなんと自国のスウェーデン政府なのだる。目眩がするような、イカれた現実がここにある
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『戦場のピアニスト』(ロマン・ポランスキー)が描く、ユダヤ人迫害の衝撃の実話
映画『戦場のピアニスト』の4Kリマスター版を観に行ったところ、上映後のトークイベントに主人公の息子が登壇したので驚いた。何せ私は、本作が「実話を基にしている」ことさえ知らなかったのである。だからその驚きもひとしおだった。ホロコーストの生存者である主人公の壮絶な人生を描き出す、不朽の名作だ
あわせて読みたい
【壮絶】アウシュヴィッツで”人体実験の神メンゲレ”から生き残り、ホロコーストから生還した男の人生:…
映画『メンゲレと私』は、タイトルと内容がそぐわないものの、とても興味深い作品だった。44ヶ月間の収容所生活を生き延び、ホロコーストから生還したダニエル・ハノッホが、少年とは思えない「思考力」を武器に、最低最悪な状況を生き延びた経験をカメラの前で語る。あまりにも壮絶な、信じがたい現実である
あわせて読みたい
【あらすじ】原爆を作った人の後悔・葛藤を描く映画『オッペンハイマー』のための予習と評価(クリスト…
クリストファー・ノーラン監督作品『オッペンハイマー』は、原爆開発を主導した人物の葛藤・苦悩を複雑に描き出す作品だ。人間が持つ「多面性」を様々な方向から捉えようとする作品であり、受け取り方は人それぞれ異なるだろう。鑑賞前に知っておいた方がいい知識についてまとめたので、参考にしてほしい
あわせて読みたい
【無謀】映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、脱北ルートに撮影隊が同行する衝撃のドキュメンタリー
北朝鮮からの脱北者に同行し撮影を行う衝撃のドキュメンタリー映画『ビヨンド・ユートピア 脱北』は、再現映像を一切使用していない衝撃的な作品だ。危険と隣り合わせの脱北の道程にカメラもついて回り、北朝鮮の厳しい現状と共に、脱北者が置かれた凄まじい状況を映し出す内容に驚かされてしまった
あわせて読みたい
【抵抗】映画『熊は、いない』は、映画製作を禁じられた映画監督ジャファル・パナヒの執念の結晶だ
映画『熊は、いない』は、「イラン当局から映画製作を20年間も禁じられながら、その後も作品を生み出し続けるジャファル・パナヒ監督」の手によるもので、彼は本作公開後に収監させられてしまった。パナヒ監督が「本人役」として出演する、「ドキュメンタリーとフィクションのあわい」を縫うような異様な作品だ
あわせて読みたい
【衝撃】映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想外すぎる着地を見せる普通じゃないドキュメンタリー
国連事務総長だったハマーショルドが乗ったチャーター機が不審な墜落を遂げた事件を、ドキュメンタリー映画監督マッツ・ブリュガーが追う映画『誰がハマーショルドを殺したか』は、予想もつかない衝撃の展開を見せる作品だ。全世界を揺るがしかねない驚きの”真実”とは?
あわせて読みたい
【現実】映画『私のはなし 部落のはなし』で初めて同和・部落問題を考えた。差別はいかに生まれ、続くのか
私はずっと、「部落差別なんてものが存在する意味が分からない」と感じてきたが、映画『私のはなし 部落のはなし』を観てようやく、「どうしてそんな差別が存在し得るのか」という歴史が何となく理解できた。非常に複雑で解決の難しい問題だが、まずは多くの人が正しく理解することが必要だと言えるだろう
あわせて読みたい
【狂気】ホロコーストはなぜ起きた?映画『ヒトラーのための虐殺会議』が描くヴァンゼー会議の真実
映画『ヒトラーのための虐殺会議』は、ホロコーストの計画について話し合われた「ヴァンゼー会議」を描き出す作品だ。唯一1部だけ残った議事録を基に作られた本作は、「ユダヤ人虐殺」をイベントの準備でもしているかのように「理性的」に計画する様を映し出す。その「狂気」に驚かされてしまった。
あわせて読みたい
【驚愕】ベリングキャットの調査報道がプーチンを追い詰める。映画『ナワリヌイ』が示す暗殺未遂の真実
弁護士であり、登録者数640万人を超えるYouTuberでもあるアレクセイ・ナワリヌイは、プーチンに対抗して大統領選挙に出馬しようとしたせいで暗殺されかかった。その実行犯を特定する調査をベリングキャットと共に行った記録映画『ナワリヌイ』は、現実とは思えないあまりの衝撃に満ちている
あわせて読みたい
【抵抗】若者よ、映画『これは君の闘争だ』を見ろ!学校閉鎖に反対する学生運動がブラジルの闇を照らす
映画『これは君の闘争だ』で描かれるのは、厳しい状況に置かれた貧困層の学生たちによる公権力との闘いだ。「貧困層ばかりが通う」とされる公立校が大幅に再編されることを知った学生が高校を占拠して立て籠もる決断に至った背景を、ドキュメンタリー映画とは思えないナレーションで描く異色作
あわせて読みたい
【デモ】クーデター後の軍事政権下のミャンマー。ドキュメンタリーさえ撮れない治安の中での映画制作:…
ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー賞を受賞したミャンマー映画『ミャンマー・ダイアリーズ』はしかし、後半になればなるほどフィクショナルな映像が多くなる。クーデター後、映画制作が禁じられたミャンマーで、10人の”匿名”監督が死を賭して撮影した映像に込められた凄まじいリアルとは?
あわせて読みたい
【悲劇】大川小学校はなぜ津波被害に遭ったのか?映画『生きる』が抉る現実と国家賠償請求の虚しさ
東日本大震災において、児童74人、教職員10人死亡という甚大な津波被害を生んだ大川小学校。その被害者遺族が真相究明のために奮闘する姿を追うドキュメンタリー映画『生きる』では、学校の酷い対応、出来れば避けたかった訴訟、下された画期的判決などが描かれ、様々な問題が提起される
あわせて読みたい
【映画】『戦場記者』須賀川拓が、ニュースに乗らない中東・ウクライナの現実と報道の限界を切り取る
TBS所属の特派員・須賀川拓は、ロンドンを拠点に各国の取材を行っている。映画『戦場記者』は、そんな彼が中東を取材した映像をまとめたドキュメンタリーだ。ハマスを巡って食い違うガザ地区とイスラエル、ウクライナ侵攻直後に現地入りした際の様子、アフガニスタンの壮絶な薬物中毒の現実を映し出す
あわせて読みたい
【狂気?】オウム真理教を内部から映す映画『A』(森達也監督)は、ドキュメンタリー映画史に残る衝撃作だ
ドキュメンタリー映画の傑作『A』(森達也)をようやく観られた。「オウム真理教は絶対悪だ」というメディアの報道が凄まじい中、オウム真理教をその内部からフラットに映し出した特異な作品は、公開当時は特に凄まじい衝撃をもたらしただろう。私たちの「当たり前」が解体されていく斬新な一作
あわせて読みたい
【衝撃】これが実話とは。映画『ウーマン・トーキング』が描く、性被害を受けた女性たちの凄まじい決断
映画『ウーマン・トーキング』の驚くべき点は、実話を基にしているという点だ。しかもその事件が起こったのは2000年代に入ってから。とある宗教コミュニティ内で起こった連続レイプ事件を機に村の女性たちがある決断を下す物語であり、そこに至るまでの「ある種異様な話し合い」が丁寧に描かれていく
あわせて読みたい
【実話】映画『グリーンブック』は我々に問う。当たり前の行動に「差別意識」が含まれていないか、と
黒人差別が遥かに苛烈だった時代のアメリカにおいて、黒人ピアニストと彼に雇われた白人ドライバーを描く映画『グリーンブック』は、観客に「あなたも同じような振る舞いをしていないか?」と突きつける作品だ。「差別」に限らず、「同時代の『当たり前』に従った行動」について考え直させる1作
あわせて読みたい
【異常】韓国衝撃の実話を映画化。『空気殺人』が描く、加湿器の恐怖と解決に至るまでの超ウルトラC
2011年に韓国で実際に起こった「加湿器殺菌剤による殺人事件」をモデルにした映画『空気殺人』は、金儲け主義の醜悪さが詰まった作品だ。国がその安全を保証し、17年間も販売され続けた国民的ブランドは、「水俣病」にも匹敵する凄まじい健康被害をもたらした
あわせて読みたい
【性加害】映画『SHE SAID その名を暴け』を観てくれ。#MeToo運動を生んだ報道の舞台裏(出演:キャリ…
「#MeToo」運動のきっかけとなった、ハリウッドの絶対権力者ハーヴェイ・ワインスタインを告発するニューヨーク・タイムズの記事。その取材を担った2人の女性記者の奮闘を描く映画『SHE SAID その名を暴け』は、ジャニー喜多川の性加害問題で揺れる今、絶対に観るべき映画だと思う
あわせて読みたい
【生還】内戦下のシリアでISISに拘束された男の実話を基にした映画『ある人質』が描く壮絶すぎる現実
実話を基にした映画『ある人質 生還までの398日』は、内戦下のシリアでISISに拘束された男の壮絶な日々が描かれる。「テロリストとは交渉しない」という方針を徹底して貫くデンマーク政府のスタンスに翻弄されつつも、救出のために家族が懸命に奮闘する物語に圧倒される
あわせて読みたい
【実話】ソ連の衝撃の事実を隠蔽する記者と暴く記者。映画『赤い闇』が描くジャーナリズムの役割と実態
ソ連の「闇」を暴いた名もなき記者の実話を描いた映画『赤い闇』は、「メディアの存在意義」と「メディアとの接し方」を問いかける作品だ。「真実」を届ける「社会の公器」であるべきメディアは、容易に腐敗し得る。情報の受け手である私たちの意識も改めなければならない
あわせて読みたい
【衝撃】匿名監督によるドキュメンタリー映画『理大囲城』は、香港デモ最大の衝撃である籠城戦の内部を映す
香港民主化デモにおける最大の衝撃を内側から描く映画『理大囲城』は、とんでもないドキュメンタリー映画だった。香港理工大学での13日間に渡る籠城戦のリアルを、デモ隊と共に残って撮影し続けた匿名監督たちによる映像は、ギリギリの判断を迫られる若者たちの壮絶な現実を映し出す
あわせて読みたい
【解説】実話を基にした映画『シカゴ7裁判』で知る、「権力の暴走」と、それに正面から立ち向かう爽快さ
ベトナム戦争に反対する若者たちによるデモと、その後開かれた裁判の実話を描く『シカゴ7裁判』はメチャクチャ面白い映画だった。無理筋の起訴を押し付けられる主席検事、常軌を逸した言動を繰り返す不適格な判事、そして一枚岩にはなれない被告人たち。魅力満載の1本だ
あわせて読みたい
【あらすじ】映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』で描かれる、グアンタナモ”刑務所”の衝撃の実話は必見
ベネディクト・カンバーバッチが制作を熱望した衝撃の映画『モーリタニアン 黒塗りの記録』は、アメリカの信じがたい実話を基にしている。「9.11の首謀者」として不当に拘束され続けた男を「救おうとする者」と「追い詰めようとする者」の奮闘が、「アメリカの闇」を暴き出す
あわせて読みたい
【執念】「桶川ストーカー事件」で警察とマスコミの怠慢を暴き、社会を動かした清水潔の凄まじい取材:…
『殺人犯はそこにいる』(文庫X)で凄まじい巨悪を暴いた清水潔は、それよりずっと以前、週刊誌記者時代にも「桶川ストーカー殺人事件」で壮絶な取材を行っていた。著者の奮闘を契機に「ストーカー規制法」が制定されたほどの事件は、何故起こり、どんな問題を喚起したのか
あわせて読みたい
【狂気】アメリカの衝撃の実態。民営刑務所に刑務官として潜入した著者のレポートは国をも動かした:『…
アメリカには「民営刑務所」が存在する。取材のためにその1つに刑務官として潜入した著者が記した『アメリカン・プリズン』は信じがたい描写に溢れた1冊だ。あまりに非人道的な行いがまかり通る狂気の世界と、「民営刑務所」が誕生した歴史的背景を描き出すノンフィクション
あわせて読みたい
【驚愕】一般人スパイが北朝鮮に潜入する映画『THE MOLE』はとてつもないドキュメンタリー映画
映画『THE MOLE』は、「ホントにドキュメンタリーなのか?」と疑いたくなるような衝撃映像満載の作品だ。「『元料理人のデンマーク人』が勝手に北朝鮮に潜入する」というスタートも謎なら、諜報経験も軍属経験もない男が北朝鮮の秘密をバンバン解き明かす展開も謎すぎる。ヤバい
あわせて読みたい
【差別】映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』の衝撃。プーチンが支持する国の蛮行・LGBT狩り
プーチン大統領の後ろ盾を得て独裁を維持しているチェチェン共和国。その国で「ゲイ狩り」と呼ぶしかない異常事態が継続している。映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』は、そんな現実を命がけで映し出し、「現代版ホロコースト」に立ち向かう支援団体の奮闘も描く作品
あわせて読みたい
【あらすじ】死刑囚を救い出す実話を基にした映画『黒い司法』が指摘する、死刑制度の問題と黒人差別の現実
アメリカで死刑囚の支援を行う団体を立ち上げた若者の実話を基にした映画『黒い司法 0%からの奇跡』は、「死刑制度」の存在価値について考えさせる。上映後のトークイベントで、アメリカにおける「死刑制度」と「黒人差別」の結びつきを知り、一層驚かされた
あわせて読みたい
【事件】デュポン社のテフロン加工が有害だと示した男の執念の実話を描く映画『ダーク・ウォーターズ』
世界的大企業デュポン社が、自社製品「テフロン」の危険性を40年以上前に把握しながら公表せず、莫大な利益を上げてきた事件の真相を暴き出した1人の弁護士がいる。映画『ダーク・ウォーターズ』は、大企業相手に闘いを挑み、住民と正義のために走り続けた実在の人物の勇敢さを描き出す
あわせて読みたい
【現実】権力を乱用する中国ナチスへの抵抗の最前線・香港の民主化デモを映す衝撃の映画『時代革命』
2019年に起こった、逃亡犯条例改正案への反対運動として始まった香港の民主化デモ。その最初期からデモ参加者たちの姿をカメラに収め続けた。映画『時代革命』は、最初から最後まで「衝撃映像」しかない凄まじい作品だ。この現実は決して、「対岸の火事」ではない
あわせて読みたい
【憤り】世界最強米海軍4人VS数百人のタリバン兵。死線を脱しただ1人生還を果たした奇跡の実話:『アフ…
アフガニスタンの山中で遭遇した羊飼いを見逃したことで、数百人のタリバン兵と死闘を繰り広げる羽目に陥った米軍最強部隊に所属する4人。奇跡的に生き残り生還を果たした著者が記す『アフガン、たった一人の生還』は、とても実話とは信じられない凄まじさに満ちている
あわせて読みたい
【歴史】『大地の子』を凌駕する中国残留孤児の現実。中国から奇跡的に”帰国”した父を城戸久枝が描く:…
文化大革命の最中、国交が成立していなかった中国から自力で帰国した中国残留孤児がいた。その娘である城戸久枝が著した『あの戦争から遠く離れて』は、父の特異な体験を起点に「中国残留孤児」の問題に分け入り、歴史の大きなうねりを個人史として体感させてくれる作品だ
あわせて読みたい
【アメリカ】長崎の「原爆ドーム」はなぜ残らなかった?爆心地にあった「浦上天主堂」の数奇な歴史:『…
原爆投下で半壊し、廃墟と化したキリスト教の大聖堂「浦上天主堂」。しかし何故か、「長崎の原爆ドーム」としては残されず、解体されてしまった。そのため長崎には原爆ドームがないのである。『ナガサキ 消えたもう一つの「原爆ドーム」』は、「浦上天主堂」を巡る知られざる歴史を掘り下げ、アメリカの強かさを描き出す
あわせて読みたい
【理解】小野田寛郎を描く映画。「戦争終結という現実を受け入れない(=認知的不協和)」は他人事じゃ…
映画『ONODA 一万夜を越えて』を観るまで、小野田寛郎という人間に対して違和感を覚えていた。「戦争は終わっていない」という現実を生き続けたことが不自然に思えたのだ。しかし映画を観て、彼の生き方・決断は、私たちと大きく変わりはしないと実感できた
あわせて読みたい
【信念】水俣病の真実を世界に伝えた写真家ユージン・スミスを描く映画。真実とは「痛みへの共感」だ:…
私はその存在をまったく知らなかったが、「水俣病」を「世界中が知る公害」にした報道写真家がいる。映画『MINAMATA―ミナマタ―』は、水俣病の真実を世界に伝えたユージン・スミスの知られざる生涯と、理不尽に立ち向かう多くの人々の奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【驚愕】キューバ危機の裏側を描くスパイ映画『クーリエ』。核戦争を回避させた民間人の衝撃の実話:『…
核戦争ギリギリまで進んだ「キューバ危機」。その陰で、世界を救った民間人がいたことをご存知だろうか?実話を元にした映画『クーリエ:最高機密の運び屋』は、ごく普通のセールスマンでありながら、ソ連の膨大な機密情報を盗み出した男の信じがたい奮闘を描き出す
あわせて読みたい
【衝撃】『殺人犯はそこにいる』が実話だとは。真犯人・ルパンを野放しにした警察・司法を信じられるか?
タイトルを伏せられた覆面本「文庫X」としても話題になった『殺人犯はそこにいる』。「北関東で起こったある事件の取材」が、「私たちが生きる社会の根底を揺るがす信じがたい事実」を焙り出すことになった衝撃の展開。まさか「司法が真犯人を野放しにする」なんてことが実際に起こるとは。大げさではなく、全国民必読の1冊だと思う
あわせて読みたい
【実話】「ホロコーストの映画」を観て改めて、「有事だから仕方ない」と言い訳しない人間でありたいと…
ノルウェーの警察が、自国在住のユダヤ人をまとめて船に乗せアウシュビッツへと送った衝撃の実話を元にした映画『ホロコーストの罪人』では、「自分はそんな愚かではない」と楽観してはいられない現実が映し出される。このような悲劇は、現在に至るまで幾度も起こっているのだ
あわせて読みたい
【実話】映画『アウシュビッツ・レポート』が描き出す驚愕の史実。世界はいかにホロコーストを知ったのか?
映画『アウシュヴィッツ・レポート』は、アウシュビッツ強制収容所から抜け出し、詳細な記録と共にホロコーストの実態を世界に明らかにした実話を基にした作品。2人が持ち出した「アウシュビッツ・レポート」こそが、ホロコーストについて世界が知るきっかけだったのであり、そんな史実をまったく知らなかったことにも驚かされた
あわせて読みたい
【弾圧】香港デモの象徴的存在デニス・ホーの奮闘の歴史。注目の女性活動家は周庭だけじゃない:映画『…
日本で香港民主化運動が報じられる際は周庭さんが取り上げられることが多いが、香港には彼女よりも前に民主化運動の象徴的存在として認められた人物がいる。映画『デニス・ホー ビカミング・ザ・ソング』の主人公であるスター歌手の激動の人生を知る
あわせて読みたい
【勇敢】ユダヤ人を救った杉原千畝を描く映画。日本政府の方針に反しながら信念を貫いた男の生き様
日本政府の方針に逆らってまでユダヤ人のためにビザを発給し続けた外交官を描く映画『杉原千畝』。日本を良くしたいと考えてモスクワを夢見た青年は、何故キャリアを捨てる覚悟で「命のビザ」を発給したのか。困難な状況を前に、いかに決断するかを考えさせられる
あわせて読みたい
【驚異】信念を貫く勇敢さを、「銃を持たずに戦場に立つ」という形で示した実在の兵士の凄まじさ:映画…
第二次世界大戦で最も過酷な戦場の1つと言われた「前田高地(ハクソー・リッジ)」を、銃を持たずに駆け回り信じがたい功績を残した衛生兵がいた。実在の人物をモデルにした映画『ハクソー・リッジ』から、「戦争の悲惨さ」だけでなく、「信念を貫くことの大事さ」を学ぶ
あわせて読みたい
【危機】シードバンクを設立し世界の農業を変革した伝説の植物学者・スコウマンの生涯と作物の多様性:…
グローバル化した世界で「農業」がどんなリスクを負うのかを正しく予測し、その対策として「ジーンバンク」を設立した伝説の植物学者スコウマンの生涯を描く『地球最後の日のための種子』から、我々がいかに脆弱な世界に生きているのか、そして「世界の食」がどう守られているのかを知る
あわせて読みたい
【実話】権力の濫用を監視するマスコミが「教会の暗部」を暴く映画『スポットライト』が現代社会を斬る
地方紙である「ボストン・グローブ紙」は、数多くの神父が長年に渡り子どもに対して性的虐待を行い、その事実を教会全体で隠蔽していたという衝撃の事実を明らかにした。彼らの奮闘の実話を映画化した『スポットライト』から、「権力の監視」の重要性を改めて理解する
あわせて読みたい
【実話】映画『イミテーションゲーム』が描くエニグマ解読のドラマと悲劇、天才チューリングの不遇の死
映画『イミテーションゲーム』が描く衝撃の実話。「解読不可能」とまで言われた最強の暗号機エニグマを打ち破ったのはなんと、コンピューターの基本原理を生み出した天才数学者アラン・チューリングだった。暗号解読を実現させた驚きのプロセスと、1400万人以上を救ったとされながら偏見により自殺した不遇の人生を知る
あわせて読みたい
【驚愕】正義は、人間の尊厳を奪わずに貫かれるべきだ。独裁政権を打倒した韓国の民衆の奮闘を描く映画…
たった30年前の韓国で、これほど恐ろしい出来事が起こっていたとは。「正義の実現」のために苛烈な「スパイ狩り」を行う秘密警察の横暴をきっかけに民主化運動が激化し、独裁政権が打倒された史実を描く『1987、ある闘いの真実』から、「正義」について考える
あわせて読みたい
【告発】アメリカに”監視”される社会を暴露したスノーデンの苦悩と決断を映し出す映画:『スノーデン』…
NSA(アメリカ国家安全保障局)の最高機密にまでアクセスできたエドワード・スノーデンは、その機密情報を持ち出し内部告発を行った。「アメリカは世界中の通信を傍受している」と。『シチズンフォー』と『スノーデン』の2作品から、彼の告発内容とその葛藤を知る
あわせて読みたい
【史実】太平洋戦争末期に原爆を落としたアメリカは、なぜ終戦後比較的穏やかな占領政策を取ったか?:…
『八月十五日に吹く風』は小説だが、史実を基にした作品だ。本作では、「終戦直前に原爆を落としながら、なぜ比較的平穏な占領政策を行ったか?」の疑問が解き明かされる。『源氏物語』との出会いで日本を愛するようになった「ロナルド・リーン(仮名)」の知られざる奮闘を知る
あわせて読みたい
【意外】東京裁判の真実を記録した映画。敗戦国での裁判が実に”フェア”に行われたことに驚いた:『東京…
歴史に詳しくない私は、「東京裁判では、戦勝国が理不尽な裁きを行ったのだろう」という漠然としたイメージを抱いていた。しかし、その印象はまったくの誤りだった。映画『東京裁判 4Kリマスター版』から東京裁判が、いかに公正に行われたのかを知る
あわせて読みたい
【驚愕】「金正男の殺人犯」は”あなた”だったかも。「人気者になりたい女性」が陥った巧妙な罠:映画『…
金正男が暗殺された事件は、世界中で驚きをもって報じられた。その実行犯である2人の女性は、「有名にならないか?」と声を掛けられて暗殺者に仕立て上げられてしまった普通の人だ。映画『わたしは金正男を殺していない』から、危険と隣り合わせの現状を知る
あわせて読みたい
【課題】原子力発電の廃棄物はどこに捨てる?世界各国、全人類が直面する「核のゴミ」の現状:映画『地…
我々の日常生活は、原発が生み出す電気によって成り立っているが、核廃棄物の最終処分場は世界中で未だにどの国も決められていないのが現状だ。映画『地球で最も安全な場所を探して』をベースに、「核のゴミ」の問題の歴史と、それに立ち向かう人々の奮闘を知る
あわせて読みたい
【危機】遺伝子組み換え作物の危険性を指摘。バイオ企業「モンサント社」の実態を暴く衝撃の映画:映画…
「遺伝子組み換え作物が危険かどうか」以上に注目すべきは、「モンサント社の除草剤を摂取して大丈夫か」である。種子を独占的に販売し、農家を借金まみれにし、世界中の作物の多様性を失わせようとしている現状を、映画「モンサントの不自然な食べもの」から知る
あわせて読みたい
【無知】メディアの問題の本質は?「報道の限界」と「情報の受け取り方」を独裁政治の現実から知る:『…
メディアは確かに「事実」を報じている。しかし、報道に乗らない情報まで含めなければ、本当の意味で世の中を理解することは難しいと、『こうして世界は誤解する』は教えてくれる。アラブ諸国での取材の現実から、報道の「限界」と「受け取り方」を学ぶ
あわせて読みたい
【意外】思わぬ資源が枯渇。文明を支えてきた”砂”の減少と、今後我々が変えねばならぬこと:『砂と人類』
「砂が枯渇している」と聞いて信じられるだろうか?そこら中にありそうな砂だが、産業用途で使えるものは限られている。そしてそのために、砂浜の砂が世界中で盗掘されているのだ。『砂と人類』から、石油やプラスチックごみ以上に重要な環境問題を学ぶ
あわせて読みたい
【衝撃】壮絶な戦争映画。最愛の娘を「産んで後悔している」と呟く母らは、正義のために戦場に留まる:…
こんな映画、二度と存在し得ないのではないかと感じるほど衝撃を受けた『娘は戦場で生まれた』。母であり革命家でもあるジャーナリストは、爆撃の続くシリアの街を記録し続け、同じ街で娘を産み育てた。「知らなかった」で済ませていい現実じゃない。
この記事を読んでくれた方にオススメのタグページ
ルシルナ
戦争・世界情勢【本・映画の感想】 | ルシルナ
日本に生きているとなかなか実感できませんが、常に世界のどこかで戦争が起こっており、なくなることはありません。また、テロや独裁政権など、世界を取り巻く情勢は様々で…
タグ一覧ページへのリンクも貼っておきます
ルシルナ
記事検索(カテゴリー・タグ一覧) | ルシルナ
ルシルナは、4000冊以上の本と500本以上の映画をベースに、生き方や教養について書いていきます。ルシルナでは36個のタグを用意しており、興味・関心から記事を選びやすく…





















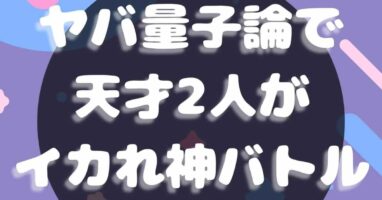


















































































コメント