
3冊目のKindle本を出版しました!
以下のリンクから冒頭の一部をお読みいただけます。

他の2作については以下の記事を読んで下さい。
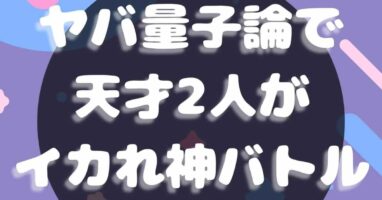

今回出版した『なぜ「想像力の無さ」が「コミュ力」と呼ばれるのか? 「隠れネガティブ」的コミュニケーション能力』は、タイトルの通り「コミュ力」についての本です。私は、世間的な意味での「コミュ力が高い」に、どうも違和感を覚えてしまいます。「ホントにそれを『コミュ力が高い』と呼んでいいのか?」と感じてしまうのです。本書は、長年抱き続けてきたそんな疑問をまとめた1冊になっています。
「コミュ力」について語る1つの軸として、本書では「隠れネガティブ」について取り上げました。これは、「一見ネガティブには全然見えないんだけど、実際にはもの凄くネガティブな人」ぐらいの意味です。私の周りには、このような「隠れネガティブ」がたくさんいるのですが(私自身も「隠れネガティブ」的な性質を持っています)、そういう人に話を聞くと、多くの人が私と同じように「よく言われる『コミュ力』にはなんか違うなって感じる」と口にします。
なので本書では、「『隠れネガティブ』とどう関わるか」を核にしつつ、「本当の意味で『コミュ力が高い』ってどういうことだろう?」と考え直してもらえるような内容に仕上げたつもりです。
以下に、本書の「内容紹介文」「まえがき」「目次」を載せておきました。気になるという方は是非お読みいただければ嬉しいです。Kindle Unlimitedに登録されている方は無料で、あるいは250円で購入していただけます。
内容紹介
「コミュ力が高い」と聞くと、どんな人を思い浮かべるでしょうか? 「誰とでも仲良くなれる」「どんな時にも会話の中心にいる」「いつも明るくポジティブに振る舞っている」みたいなイメージを持つ方が多いんじゃないかと思います。
ただ、そういう振る舞いは、本当に「コミュ力が高い」と言えるのでしょうか?
「コミュ力」に関する本やネット記事などは色々あるし、そこには様々なことが書かれています。しかし私はどうしても、そのような主張に違和感を覚えてしまうことが多いです。「コミュ力」についてのよくあるアドバイスは、「○○の時には△△しましょう」みたいな感じだと思います。しかし、そういう類のアドバイスは、全部無意味に思えるのです。
コミュニケーションにおいて最も大事なものは「想像力」だと私は考えています。そして、「○○の時には△△しましょう」みたいな主張は、むしろ「想像力が欠如している」ように感じられてしまうのです。とにかく私には、「『想像力の無い人』が『コミュ力が高い』と呼ばれているだけ」であるようにしか思えません。
一般的に、「笑顔で接する」「相手の名前を覚える」「良いところを褒める」みたいな行動は、コミュニケーションにおいて良いとされているはずです。しかし私の周りには、こういう振る舞いを「嫌だ」と感じる人がかなりいます。「いつも笑ってる人って何考えてるかわからない」「店員さんに存在を記憶されたらその店にはもう行けない」「どうして私なんかのことを褒めてくれるんだろう」みたいに考えてしまうからです。この話だけでも既に、「一般的に良いとされているコミュニケーション」は、決して万能ではないと理解してもらえるでしょう。
私の周りには、「凄くネガティブだけど、周りからネガティブであるようには見られていない人」がとても多いです。私はそういう人のことを「隠れネガティブ」と呼んでいます。そして本書では、「『隠れネガティブ』には、『一般的に良いとされているコミュニケーション』はむしろ逆効果でしかない」という話を中心に書きました。「隠れネガティブ」がどのように他人の振る舞いを受け取るのかを知ることで、「『隠れネガティブ』とどう接するか」が理解できる内容になっていると思います。
しかし単にそれだけの内容ではありません。私は、「『隠れネガティブ』とどう接するか」について理解を深めてもらうことで、「『コミュ力』について考え直すきっかけ」を作りたいと思って本書を書きました。「一般的に良いとされているコミュニケーション」では上手くいかない例を色々知って、「コミュニケーションで大事なことは、『行為の良し悪し』ではなく『いかに想像力を発揮するか』である」という、本書のメインとなる主張が正しく伝わってくれたらいいなと思っています。
本書の内容は、「一般的に『コミュ力が高い』と言われるタイプの人」には、なかなか意味不明かもしれません。「隠れネガティブ」の価値観や行動原理を理解するのはなかなか難しいはずだからです。中には、「こんな『隠れネガティブ』みたいな人ってホントにいるの?」みたいに感じてしまう人もいるでしょう。
しかし、実際に「隠れネガティブ」はいますし、私自身も「隠れネガティブ」的な性質を持っています。もちろん、あなたの近くにもいるはずです。「隠れネガティブ」は、「自分の『ネガティブさ』を表に出してはいけない」と考えているので、表向き「明るく楽しくポジティブな人」に擬態しています。だから、その存在に気づくのはかなり難しいでしょう。私の周りには「隠れネガティブ」がたくさんいるのですが、普段の感じを見ていると、「むしろ『リア充』にしか見えない」ぐらいの人さえいるのです。
もしあなたが、自分の周りの「隠れネガティブ」に気づいていないとすれば、間違いなく、あなたの普段の振る舞いが、「隠れネガティブ」に何らかの負担を与えていると思います。また、「一般的に良いとされているコミュニケーション」がそうさせてしまうので、自分の振る舞いのどこに問題があるのか、気づくのはなかなか難しいはずです。
なので本書を読んで、「『隠れネガティブ』とどう接するか」についてイメージしてみてほしいと思います。そしてさらに、「コミュニケーションで大事なのは『想像力』である」という、どんな人間関係にも欠かせない「原則」みたいなものを改めて理解し直してもらえたら嬉しいです。 また、「自分も『隠れネガティブ』です」という方、もし読んで共感していただけたら、「『隠れネガティブ』的にかなり共感できる内容です」みたいなコメントを書いたりしてくれるととても嬉しいです。本書出版前に、自分の周りの「隠れネガティブ」何人かに【まえがき】だけ読んでもらったところ、「凄く共感できる」と言ってもらえました。ただやはり、色んな「隠れネガティブ」の方から賛同してもらえると、本書に書かれている内容の信憑性が上がると思っています。もちろん、共感できなければ「共感できなかった」と書いていただいて構いません。どんな内容でもいいので、何か意見や感想などいただけたら嬉しいです。
まえがき
「ルシルナ」というブログを運営している犀川後藤と申します。そして本書では「コミュ力」について書きました。ただ、一般的な「コミュ力本」とは内容も対象とする読者もかなり違うので、少し長くはなりますが、【はじめに】でその辺りのことについて詳しく触れておきたいと思います。
さてまずは、「犀川後藤という男は、『コミュ力』を語るのに相応しい人物なのか?」について触れておく必要があるでしょう。
率直に言って私は、「一般的に『コミュ力が高い』と言われるタイプ」ではありません。友達が多いわけではないし(というか、はっきり言って少ないです)、ワイワイ盛り上がっているところにはなるべく近づきたくないし、いわゆる「コミュ力が高い人(例えばYouTuberの「フワちゃん」みたいな人)」は苦手です。喋る時と喋らない時の差が激しいので、私を「コミュ障」側の人間だと思っている人もいるかもしれません。
しかし一方で、親しくしている人からは「コミュ力が異常」と言われることもあります。そしてそう感じてくれる人は大体、「一般的に『コミュ力が高い』と言われるタイプ」が苦手だったりするのです。
「コミュ力」に関する本よくあるアドバイスとしては、「笑顔で接しましょう」「相手の名前を覚えましょう」「良いところを褒めましょう」みたいなことが挙げられると思います。もちろん、そのような振る舞いを「好意的」に受け取ってくれる人もいるでしょう。しかし、私の周りにいる人たちはよく、「いつも笑ってる人って何考えてるかわかんない」「店員さんに存在を記憶されたらその店にはもう行きたくない」「どうして私なんかのことを褒めてくれるんだろう」みたいに感じていたりします。先程挙げたような行為が、全然プラスに働いていないというわけです。こういうことは全然普通に起こり得ます。
そして私は、「そういう『一般的に良いとされている振る舞い』を苦手だと感じる人」から、「コミュ力が異常」と言ってもらえることが多いのです。この話だけでも、「『一般的に推奨されるコミュ力』は決して万能ではない」のだと理解してもらえるかと思います。
もちろん私自身も、「一般的に良いとされる振る舞い」をあまりポジティブには受け取れません。だから私は、「同じタイプの人が何を嫌だと感じるのか」が分かるつもりだし、「そのような振る舞いをしない形で他者と関われているはず」だと思ってもいます。そしてこのような理由から私は、「『コミュ力』を語るのにそれなりに適している」と言っていいのではないかと考えているのです。
さて私はこれまで、「ネガティブな人」とばかり関わってきました(「ネガティブ」の程度は様々ですが)。つまり、ネガティブだからこそ、「笑顔で接しましょう」「相手の名前を覚えましょう」「良いところを褒めましょう」みたいな「一般的に良いとされている振る舞い」に強く違和感を覚えてしまうというわけです。中には、「そのような振る舞いが『上っ面』に感じられ、相手に対する関心を抱けなくなってしまう」と口にする人さえいました。
しかしその一方で、私の周りの「ネガティブな人」には「『ネガティブ』には見られていない」という特徴もあります。私はほとんど「女友達」しかおらず、しかも10歳以上年下であることが多いのですが、彼女たちはホントに、「見た感じまったくネガティブっぽくないのに、話してみるとネガティブでしかない」という人ばかりなのです。
このような人のことを本書では「隠れネガティブ」と呼ぼうと思います。そして、「皆さんが想像する以上に『隠れネガティブ』はたくさんいる」と断言しておきましょう。特に若い世代には「隠れネガティブ」が多い印象です。
私の周りの「隠れネガティブ」は大体、見た目や接し方なども含め、「リア充の生き方で無双できそう」と感じるような雰囲気を持っています。もちろん、普段の振る舞いも明るく楽しそうに見えるのですが、しかし色々話してみると「根っからのネガティブ」であることが分かってくるという感じです。
「自分もそうだ」という方には分かってもらえるでしょうが、「隠れネガティブ」は「『ネガティブさ』を表に出すこと」を、「周りの空気を悪くする『良くない行為』」だと認識しています。なので普段から、「ネガティブ」だと悟られないように頑張っているのです。当然、「ポジティブな人」と認識した相手に自身の「ネガティブさ」を見せることはないし、「明るく元気な雰囲気」を崩すことも恐らくないでしょう。同じような「ネガティブさ」を内に秘めている人でなければ、その本性を見通せないのです。
そのため、「一般的に『コミュ力が高い』と言われるタイプ」は特に、そもそも「隠れネガティブ」の存在に気づけないと思います。もし「自分の周りには『隠れネガティブ』なんていない」と考えているなら、その認識は大いに間違っていると言っていいでしょう。あなたの周りにも「隠れネガティブ」はいると思います。そして、あなたが「隠れネガティブ」の存在に気づいていないのであれば、あなたの「言動」が「隠れネガティブ」に負担を与えたり傷つけたりしていると考える方が自然なのです。
それで私は、「『隠れネガティブと接するためのコミュ力』がかなり高い」という自覚を持っています。ここ20年ぐらい、「隠れネガティブ」とばかり関わってきたので(「面白いなと感じる人」は大体「隠れネガティブ」でした)、その経験値はかなり高いと思っているのです。
というわけで、そんな経験を踏まえつつ、本書では「隠れネガティブ的コミュ力」について書いてみました。
「隠れネガティブ的コミュ力」という言葉には2つの意味があります。1つは恐らくイメージ通りでしょうが、「『隠れネガティブ』と接するためのコミュ力」です。そしてもう1つ、「『隠れネガティブ』との関わり方から『コミュ力』を考え直す」という意味も込めています。
私はどうしても、よく見聞きする「コミュ力に関するアドバイス」に違和感を覚えてしまいがちです。ただ、それは決して「『隠れネガティブ』には通用しないから」みたいな理由ではありません。私には「『想像力』が欠如している」と感じられてしまうからです。
「コミュ力の本質」は「想像力」だと私は考えています。相手が「何をしてほしい/何をしてほしくない」と思っているのか、あるいは「何に嬉しい/辛い」と感じるのかなど、「相手の受け取り方を想像すること」こそが「コミュ力」の最も重要なポイントだというのが私の理解です(「当たり前だろ」と感じる人も多いでしょうが)。
さて、よく見聞きする「コミュ力に関するアドバイス」を雑に要約するなら、「○○の時には△△しましょう」みたいな感じになるんじゃないかと思います。そして私は、このような認識に対して「『想像力』を放棄している」と感じてしまうのです。同じ人間でも、「いつ」「どこで」「どんな状態にあるのか」によって受け取り方・感じ方は異なるはずだし、別の人なら当然もっと違いは大きくなるでしょう。それなのに、相手の振る舞いや性格を「大雑把な括り」で捉えて、「こういう時はこんな風にすれば大丈夫」などとアドバイスするのは、「あまりに『想像力』が欠如している」と感じられてしまうのです。
そんなわけで、私は本書に「『隠れネガティブ』にはこういう振る舞いを”しない”方がいい」みたいな話を多く書きました。もちろんこれは、「アドバイス」としては不十分だと理解しています。「じゃあどうすればいいんだよ」に答えていないからです。しかしここまで書いてきた通り、コミュニケーションに関しては「想像力」が何よりも大事だと私は考えています。つまり、「『どう振る舞うべきか』は、その時のあらゆる状況を踏まえた上で、『想像力』を発揮して自分で決めるしかない」というのが私の基本的なスタンスなのです。
このように私は、「『隠れネガティブ』との関わり方」について言及することで、「そもそも『コミュ力』って何なんだっけ?」みたいに問いかけたいと考えています。そしてそのことによって、「コミュ力」について多くの人に再考を迫れたらなお素晴らしいでしょう。つまり、「『隠れネガティブ』との接し方講座」と「『コミュ力』そのものの議論」を同時に行おうというのが本書の目的というわけです。
さらに言えば、「『ネガティブな人』の方がコミュ力が高い」という私の認識も共有したいと考えています。というのも、「『ネガティブな人』の方が明らかに『想像力が高い』」からです。というか、「『想像力が高い』からこそ『ネガティブ』になってしまう」と表現すべきでしょうか。
「ネガティブな人」ほど、「こんなことを言ったら相手を傷つけてしまうかもしれない」「誰か1人にこういう振る舞いをしたら、贔屓してるみたいに思われるかもしれない」「良かれと思っての行動でも、相手は悪く受け取るかもしれない」など、様々な「可能性」を思い浮かべてしまいます。それらは、「ポジティブな人」からしたら「考え過ぎ!」と一笑したくなるようなものかもしれません。ただ、「考え過ぎてしまう」というのは裏を返せば、「想像力が高い」ことの現れでもあると私は思っています。そして、「様々な可能性を思い浮かべられる能力」は、そのまま「コミュ力」に直結するはずです。
私は逆に、「考え過ぎ!」と笑って受け流すような人に対して「想像力の無さ」を感じてしまいます。そしてそういう人の言動には、やはり「違和感」を覚えてしまうことが多いのです。
さて、誤解されるかもしれないので書いておきますが、私は別に「ネガティブになれ」などと言いたいのではありません。そうではなく、「ポジティブな自分は、対人関係における『想像力』が少し低いのかもしれない」と”想像”してみてほしいと考えているだけなのです。
本書の主張は、「一般的に『コミュ力が高い』と言われるタイプ」の人にはもしかしたら理解不能かもしれません。ただ、私の周りの「隠れネガティブ」はきっと本書の内容に共感してくれるだろうし、世の中にも同じように感じる人は恐らくたくさんいるはずだと思っています。実際、この【はじめに】の文章を何人かの「隠れネガティブ」に読んでもらったのですが、「凄く共感できる」という反応をもらえました。本文の内容にも結構賛同してもらえるはずです。
なので、本書の内容が意味不明だった場合は、「こんな世界線も存在するんだなぁ」ぐらいに受け取ってもらえればよいかと思います。そして本書の内容に触発される形で、「コミュニケーションにおける『想像力』」について多くの人が考えを巡らせてくれたら嬉しい限りです。
目次
はじめに
第1章 「隠れネガティブ」と「コミュ力」について
・「隠れネガティブ」ってどんな人?
・「コミュ力」とは「想像力」のことである
それって「コミュ力が高い」ですか?
「コミュ障」の方が「コミュ力が高い」のではないか
・「行為」ではなく「記号」こそが重要である
コミュニケーションにおける「記号」という考え方
「隠れネガティブ」は「『記号』に合わせた振る舞い」をしてしまいがち
第2章 「隠れネガティブ」とどう接するか
・「嫌だったら『嫌』って言うはず」だって思ってますか?
・「優しさ」が辛く感じられることもあるんです
・その「共感」、私には「分かってない」に感じられます
・興味を持ってくれたら嬉しい……わけがない!
・そんなこと褒められても嬉しくないです……
・褒めてくれるなら、もう少し上手くやってほしい……
・「過剰に感じられるプラス評価」はちょっと苦手です……
・そのイメージに合わせるの、しんどいなぁ……
・「期待に応えなきゃ」って思っちゃうんです
・顔も名前も覚えてくれなくて大丈夫です
・もっと適当な反応でいいんですけど……
・出来れば謝らないでほしいです
・「明日ヒマ?」だけじゃ返信できません……
・あなたには「異性」だと見られたくないんです……
・いつも喋ってる人が黙ってると怖いんだよなぁ……
・それが「普通」って誰が決めたわけ?
・理解できなきゃ、歩み寄れませんか?
・「困ったら相談して」って言われても……
・相談したいけど、あなたとは話が通じる気がしません
・「面白い話」はちょっと苦手です……
・「共通の話題」なんて必要ですか?
あとがき






